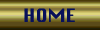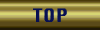【最新更新日 : 2002年05月07日 火曜日 】
『国民の道徳』
西部 邁 著 産経新聞社 刊
一章……
歴史――道徳の歴史と日本の国柄
2 「明治」以降の道徳
神儒仏習合に分裂が生じた
- 明治維新は、それまでの経緯のなかに、すでに二つの大きな矛盾を抱え込んでいた。よく知られているように、・ ・ ・ 攘夷か開国かという論点は、思想的にみて日本の近代史における葛藤の根本因となったのである。もう一つの矛盾は、倒幕運動が下級武士によって指導されたということもあって、平等化の要求にたいする肯定と否定が相剋を起こしていたということである。つまり一方では、民衆の世論を政治に反映させようという、のちに自由民権といわれることになる、思想の傾きがあった。そうであるにもかかわらず、他方では、明治維新はいわゆる薩長を中心とする藩閥政治になり、それがのちに国権派とよばれることになる。つまり、権力の集中なのか分散なのかという幕末の矛盾を、それ以後の国内政治も引き継ぐことになったのである。
・ ・ ・ それゆえ明治政府は、発足に当たって、国家の価値観として日本に独特の歴史的産物をおのずと持ち出そうとした。それが神道を中心とする価値観である。もう少しく特定すれば、平田神学の影響を受けた道徳観である。明治初年に、いわゆる制度がおかれた。・ ・ ・ そうした神儒習合の方向で国家の共有価値を見いだそうとする動きが始められたのである。
そうした背景には、いわゆるの運動があった。天皇の存在を価値論的に正当化する際の最も便利なやり方が神道に頼ることであり、そして徳川政治に組み込まれていた仏教体制を壊すことであった。それが廃仏毀釈、つまり仏教を排して神道に就けという運動であった。
教育勅語の意味
- 教育勅語は天皇を政治的に利用したといわれて致し方ない。しかし、そこに明治の絶対君主制をみようとするような左翼主義は誇張にすぎない。それは、天皇を政治的に逆利用して、自分たちのイデオロギーをふりまく振る舞いといってよい。
見逃しにできないのは、戦後の教育基本法もまた、文化的権威の政治的利用だということである。教育勅語の表現における「朕」(天子)が「アメリカ」に変わったとすれば、教育基本法はまさにアメリカの臣民を創るための教育となっているのである。
近代日本の自我探し
・ ・ ・ 。つまり封建の世であれば、その人の存在の場所も役割もあらかじめ制度的に決められている。自分は何ものであるかという自我探しは、ことさらに大きな問題にはなりえなかった。しかし、そういう身分が急速に取り払われたとき、自分を支える精神の基盤は何であるかを問う自我探しが起こらざるをえない。
近代日本の特徴の二つめは、オポチュニズム(状況適応主義)ということである。近代日本の思想遍歴は実にめまぐるしい。欧米の新思想が次々と紹介される。しかも日本の内外情勢が狂おしく変化する。そうした状況の変化に合わせて、日本人の表現活動が、そこに含まれる価値観とともに、万華鏡のように変わっていく。その意味で、きわめて状況適応主義的な道徳の変遷があったといえる。
二章……
戦後――敗戦日本人の道徳に何がおこったのか
4 天皇は「聖と俗」の境界に立っている
- 言葉がそうであるように、どんな象徴も善用されたり悪用されたりする。要するに、天皇・日の丸・君が代の存在に反対するものは、それらを善用する能力もしくは事の善悪を区別する能力に欠けているのだ。
天皇と国旗・国家は別次元の国家象徴
- 平成十一年に国旗・国家法ができた。戦後、とくに教育の現場において、いわゆる日教組教育が日の丸・君が代を戦前の軍国主義・天皇主義の象徴であるとして、排斥してきた。国旗掲揚と国歌斉唱を拒否する教育が子供を健全な国民にするためのものである公教育の場に広がっていった。・ ・ ・ そのせいで、日の丸・君が代の衰運は、戦後日本人における国家意識の衰弱の象徴となってしまった。
この日の丸・君が代にたいする反対論がいわば二枚舌で吐かれていることについても指摘しておくべきであろう。たとえばオリンピック・ゲームで日の丸が掲げられ君が代が歌われることに、ほとんどすべての日本人が興奮している。だが戦後知識人はそういう日本人の振る舞いを批判したことはほとんどない。それは、天皇制に反対しておきながら、天皇条項を含んでいる日本国憲法を礼賛するのと同じ二枚舌だというほかない。つまり、日の丸・君が代は、こうした否定・肯定の同時存在によって、いわば無に帰していったのである。
こうした国家意識の低さが日本人の活力の低下となって具体化するという昨今の事情のなかで、日の丸を国旗とし、君が代を国家とするという法律が定められたわけである。それはとくに初等・中等の教育段階にある日本の次の世代に健全な国家意識の発育を促すことを狙いとしているとみてよい。
5 戦争責任をめぐる道徳論の歪み
- 他人の不徳とおぼしき動機を追求することそれ自体、えてして不徳に陥りやすい所業である。なぜなら、一つにそれが憶測にすぎないため、二つに完全な徳者がいない以上、その不徳追求が無際限になりがちだからである。たとえば、汚職行為で既に罰せられた役人が、その道徳的責任を追及されて、“終生”、社会から抹殺されるというようなことである。
結果責任論の危険
- 歴史上の出来事についての責任は、おおよそつねに、あとの世代のものたちによって問われる ・ ・ ・ 。後世にとっては当時の歴史的事情のことをいくら追体験してみても、想像の域を出ない。それにもかかわらず、あの悪しき結果は当事者の努力が足りなかったことによる間違った予測のせいだ、だからその当事者の責任を問えというのは、後世のであり、歴史にたいする軽蔑だといわざるをえない。その点で、戦争責任論において結果責任を振り回すのは要注意なのである。したがって、最初に問われるべきは動機責任のほうだということになる。
東京裁判を「みせしめ」と認定できない戦後日本人
- 東京裁判というのは、太古の昔から戦争につきまとう「みせしめ」の儀式であった。だから、東京裁判を不当とるのは適切ではない。詰られるべきなのは、東京裁判を「みせしめ裁判」とまだ認定できていない戦後日本人のほうである。
・戦争で死んだものたちを「犬死」とみなすのが不道徳への第一歩だといってよい。それがらの死であるかどうかは、後生がその死者たちの意志を活かすかどうかにかかっている。わかりやすい例でいえば、「国のために」との意志で特攻隊員がみずから選びとった死は、「国のために」と思うのを罪とみなしてきた戦後教育にあっては、犬死とみえるであろう。しかし、「公」の意思が過剰に及ぶなら、「私」のという無理を犯すことになるであろうが、同時に、私の欲望が過剰に及べば公のとなる。そして、健全な「自分」の姿はどんなものかと考えてみれば、公の気持ちと私の気持ちにおいてバランスをとっていることだとわかる。そうならば、戦争に責任をとるということの真髄は、公と私のバランスのための知恵を先人たちの戦争の経験から学ぶ点にあるということになる。そうした良識を打ち壊してきたのが戦後の戦争責任論であったのだから、道徳を回復するためには、まずこの責任論から脱却しなければならないのである。
6 祖国のために戦うということ
- 「国のために戦うか」という質問にたいして世界各国の青年たちのおおむね八十%以上が「戦う」と答えているのに、日本の青年たちにあってはそれがたったの十五%ということになっている。
おそらく、我らの世代は我々の子孫にたいして道徳的な「不戦争責任」を負うことになるであろう。
死をめぐる私徳と公徳
- 国のために死ぬのは嫌だ、と日本の青年たちはいう。そういう青年たちを育てたのは、その親たちの世代が作った家庭、学校、地域社会、議会である、つまりその青年たちを取り囲む社会環境である。その環境のうちには、「社会が悪い」とすることによって自分の責任を回避する、といった態度を青年たちに許すような不道徳のことも含まれている。
戦争についての思考停止が平和主義
- 戦後日本では、平和主義という言葉の意味はもちろん肯定的なものである。しかし外国ではパシフィズム(平和主義)あるいはパシフィスト(平和主義者)といえば、否定的な意味合いで用いられることが多い。あっさりいうと、卑劣漢、臆病者ということである。だから、「お前はパシフィストだね」といわれたら、常識を持った外国人なら、「俺はでも臆病でもない。いざとなったら家族のため、祖国のために戦うことをわぬ人間である」と抗議するに違いない。
- 戦後日本人は、結局のところ、平和つまり「戦争のない状態」をアメリカに守ってもらうという前提のもとで、自分たちは平和の維持や回復のために戦うことを不徳と見なしてきた。
- 経済大国としての日本にとって、マラッカ海峡をはじめとするシーレーンの安全をいかに確保するか、また広くいって、経済にかかわる技術・情報の国際的システムをいかに守るか、それがの課題になりつつある。それが日本に影響を及ぼさないなどと考えるのは本当の痴愚のみである。加えて、湾岸戦争においてそれがり出されたのであるが、世界秩序の防衛のために物的貢献による後方支援は行うが、人的支援による前方支援はしないという日本のやり方がもう通用しなくなっている。というより、そういう見下げ果てた国民からは金銭・物資を絞りとれるだけとれ、それが国際世論になってきている。
憲法第九条の第一項と第二項の解釈をめぐって
- 国際関係が友好のみによって貫かれていたことは、人類の歴史において、一度もなかった。その事実に戦後日本人は、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」(日本国憲法前文)という文句に素直に従うようにして、眼をつむってきた。しかし、そのこと自体が「人間は誤りを犯す」ということの歴然たる証拠なのである。平和というのは、あくまで消極的な概念である。つまり「戦争のない状態」にすぎない。そういう状態を創るために何が必要かと積極的に考えると、戦争に対する備えとして武装する必要があると認めるほかない。さらに防衛のための武力の保有ということだけではなくて、積極的にみずから武力を発動しなければならないときもありうる。
- 日本国憲法の第九条第一項に書かれている「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」という条文をどう受け止めるかということである。日本では、どんな戦争も放棄することだと誤解されてきたが、この「国際紛争を解決する手段としての戦争」というのはいうまでもなく1928年のパリ不戦条約における用語法である。そこでは、インターナショナル・ディスピュート(国際紛争)を解決するための手段としての戦争は侵略戦争であり、他方、「自国の安全を守る手段としての戦争」が自衛戦争だというふうに区別されていた。
- 現憲法の第九条第二項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」
・ ・ ・ 。
第一項で侵略戦争はしないと決めたのであるから、その第二項の意味は「侵略戦争を しないという目的のための戦力不保持と交戦権否認」ということになってしまう。自衛のための戦力も自衛のための交戦もありうるのであるから、「日本人には自衛と侵略の区別がつかない」もしくは「日本人は自衛を口実にして侵略をやる」というようにしか解釈できない。・ ・ ・ この限定は逆の形に、つまり「前項の目的に反するような」となるべきである。侵略戦争のための戦力や交戦を禁止するということだ。
8 米ソの歴史軽視に擦り寄った戦後知識人
欧米的な価値基準でみた日本の成功
- 進歩的文化人とは何か。それは、あきらかに社会主義とその基礎をなす進歩主義とに強い共感を寄せる知識人たちのことであった。その文化人ということの意味合も、文化を歴史・伝統のなかにまれるものとしてみるのではなく、文化もまた新しい知識の上に構築されるべきものだと判断する人々のことであった。
- 社会主義に典型をみる社会主義的実験主義、つまり社会を大がかりな実験として構築しようとする設計主義の影響力は、六十年代いっぱいで退潮に向かったといってよい。つまり、それらの青年運動には、破壊のエネルギーはあったものの、建設への展望はなかったということである。
三章……
政治――道徳を傷つけた「アメリカ的なるもの」
10 自由が道徳を破壊する
- 自由は選択肢が複数あるときに生じる。AをとるかBをとるか、それが自由の意識である。
自由と道徳は表裏一体
- 人間の行為にたいして規制をし規範を指し示すもの、それが道徳である。そしてその規制や規範に違反した人間は何らかの制裁を受ける。それが道徳的制裁である。また、道徳の基礎の上に法律の体系が作られる場合には、法律に違反した行為にたいして法律的制裁(刑罰や罰金)が科せられる。徳律と法律のいずれにせよ、それに逆らったなら制裁をする、という責任の態度が社会のなかで生きる人間には要請される。
11 道徳を砕く進歩の歯車
「進歩とは良きこと」は根拠薄弱
- 四半世紀間、社会主義を中心として、左翼主義的な反体制の気分と行動が持続していたのはなぜか。それは、現状を批判し攻撃し変革すると、そこから新しき変化が生まれ、それは良きものとしての進歩をもたらすものだ、と人々が強く思っていたからだ。つまり、ドグマ(独断)の原義は「良いように思われること」という意味であるが、新しい変化を良いことのように思うという意味で、進歩主義は戦後のドグマであったのだ。
進歩主義が世界を動揺させている
- 守旧を排し改革を好むのは、新旧それぞれの良否についてまともな検討がされていないかぎり、まさしく紋切り型の進歩主義なのだ。
本当の進歩は「革命」ではなく「温故知新」から
- 維新と復古との統一は、よくつかわれる熟語でいえば、「温故知新」にほかならない。つまり古きをねて新しきを知る、という精神が近代日本の出発点には、ながらも、あったのである。
歴史の英知を忘れた自由民主主義
- 全体主義もまた、自由民主主義の産物であることが今に至るも理解されていない。自由がに流れて無秩序状態が出現すれば、「民」は拍手・喝采の熱狂のなかから独裁者を選び出すことによって、秩序を取り戻そうとする。つまり民主主義の「自己否定」が全体主義なのである。自由と民主をそれぞれ健全なものにとどめる条件は何か、それは歴史の英知ではないのか。自由は、価値判断なしには、単なる放埒である。・ ・ ・ 自由を真っ当な価値判断に立脚させるのは、根本的には歴史の英知である。民主にしても、社会の多数派が健全な価値判断を抱いていなければ、多数派による少数派の排除にすぎないものになる。
12 自由の虚妄、平等の欺瞞、博愛の偽善
理想の標語だけが流通しつづける
- 近代主義のスタートラインを引いたのはフランス大革命であり、そこで「自由・平等・博愛」という、それ以後二百余年に渡って不動の価値の柱とみなされるものが打ち出された。しかし、その革命の実態は、「革命がその子らをむ」というアクトン卿(1834〜1902 イギリスの歴史家)の言い方に示されているように、しいとみえた革命の理想がたちどころに醜い現実に転落するということであった。・ ・ ・ 自由はにち、放埒は抑圧に転回した。平等は悪平等(もしくは画一化)に変わり、悪平等は差別に逆転した。博愛は偽善に堕ち、偽善は酷薄に反転した。フランス大革命にかぎらず、ロシア大革命であろうが中国大革命であろうが、「革命はその子らを食む」というのが革命の現実なのである。それにもかかわらず、・ ・ ・ 革命のなかでわれた理想の標語だけが流通しつづけることになる。
自由と規制、平等と格差そして博愛と競合
- 「自由・平等・博愛」を常識・良識に照らしてみれば、次のようなことがすぐ明らかとなる。・ ・ ・ レギュレーション(規制)とフリーダム(自由)は、互いに対立の可能性をみつつも、両者がうまく平衡され、さらには総合されるならば、そのとき、良き時代が実現されるということができる。なぜなら、規制にもとづく自由とあるべき自由のための規制がそこでは現実のものとなっているからである。
エクオリティ(平等)についてもである。・ ・ ・ 「人間というのは生まれながらにして平等である」という世界人県宣言の規定は単なる誇張である。人間には知性と徳性の両面でまぎれもなく能力差がある。そうである以上、能力の違うものを同列に扱うことに弊害が生じないわけがない。・ ・ ・
博愛についても、フラタニティ(博愛)はエミュレーション(競合)と対立の関係にある。・ ・ ・ つまり自由・平等・博愛という価値体系に並んで、規制・格差・競合の価値体系もなければならないのである。
ただし両体系はかならずしも同次元にはない。つまり、自由・平等・博愛がおおむね人間の目的意識にかんするものであるのにたいし、規制・格差・競合はおおよそ手段意識にかかわる。目的が理想に引きずられがちであり、手段が現実に縛られがちであるという意味では、前者の価値は理想次元に、そして後者の価値は現実次元にあるといえよう。
・ ・ ・ 規制なき自由は放埒に陥り、格差なき平等は画一化をもたらし、競合なき博愛は偽善に落ちる。
13 マスメディアが第一権力を掌握した
多数派の欲望がいじめに、少数者の欲望が反逆に
- 多数派の欲望が主権者の主張となることの結果は恐るべきものであって、たとえばそれが子供たちの世界における「いじめ」の温床ともなる。戦後民主主義つまり多数派の欲望が少数派の欲望を排除するという方式がストレートに応用されると、多数派とは違った性格なり態度なりを示す子供たちが、いじめによって排除されることになる。・ ・ ・ 加えて、多数者にあっても、彼らにとてまったくないというわけではない繊細な精神が多数決という画一主義によって圧殺されているという欲求不満があるので、「いじめ」における残酷さが度外れになりがちなのだ。
他方、少数派にしても、自分たちがいずれ多数者になりうると見込む場合には、あるいは自分らだけの集団を作ろうと企てる場合には、その欲望表現が「人間の権利」と美化されているのであってみれば、多数者への反抗を隠そうとしない。その結果、子供たちの世界でいえば、非行少年たちの暴力が、家庭や学校や地域社会を破壊するまでに野放図に荒れ狂うということになりうる。
そして、多数派による抑圧にせよ少数派による反抗にせよ、子供にのみ特有のことではない。・ ・ ・ 世論そのものが、人々の思考を封殺すると同時に、人々の行為を反逆へと駆り立てているのである。つまり、まず自由が民衆の基本権として認められているので、規制は多数者の自由によって少数者の自由を排除するということ以外ではありえなくなっている。しかし多数性に価値が宿ると信じるのは困難であり、だから、排除するがわもされるがわも、その価値をめぐる虚無感を補填しようとして、それぞれの自由をあえて熱狂的に表現しようとするのである。それが多数者による抑圧と少数者による反逆をもたらす。
14 権威を足蹴にする大衆人
- 「大衆は大衆でないものを徹底的に嫌う」(オルテガ)
大衆とは「多くの普通の人々」のことではない
- マスメディアが第一権力となるような民衆政治は、一般に、マスデモクラシーつまり大衆民主主義とよばれている。しかし、より厳密にいうと、マス(大衆)が、さまざまな形で社会の意思決定に参加してくれることをさして大衆民主主義とよぶのである。
四章……
文化――道徳の本質を考える
17 「公と私」のドラマが国家意識を産み出す
公務は国民性に奉じるもの
- 軍人が、高額の報酬が与えられるわけでもないのに死の危険を引き受けるのは、国家を守るという名誉が、国民から与えられると期待するからである。しかしその第九条において、軍隊の存在を非合法としているのが日本国憲法である。軍人にかぎらず、国家を守ることにたいする評価は、戦後において、うかぎりにおいて低められている。死の危険を引き受ける公務についてすら名誉が与えられないのなら、そのほかの公務については推して知るべしである。だから、公務員が国の歴史・文化を守るべく努力するというようなことをしなくなるのは、「戦後」の枠組のなかでは当然のことである。また、国家の危機に際しても戦わないと青年たちが構えるのも無理はないともいえる。
19 徳育のための知育――国語・歴史・古典的な道徳を学ぶ
徳育なければ知育なし
- 戦後、学校の教科にかかわる制度としては、道徳教育は廃止された。そのかわりに、とくに国公立の教育機関においては、ホームルームなる制度が普及させられた。・ ・ ・
歴史感覚が子供たちの自主性の根源であるのだということすら確認されないままのホームルームであるから、まず、に自分の意見を言い合う場となり、次に、民主主義の名において教室の異端派や少数派を抑圧する場となった。つまり、教室の全体的な雰囲気から逸脱する子供を、ホームルームを通じて排除し、それをきっかけにしていじめをすら加える、ということになった。つまり多数派に属するということが人間の尊厳の証拠となり、民主主義の多数決によって少数派を排除するのが自主的な営みとなった。そのように振る舞うのが戦後の道徳となったわけだ。そのようにして排除されるものは、尊厳に値するのが人間であるという大前提があるからには、人間ではないとみなすほかない。そういう理路が、子供を含めて、人々のあいだに無自覚にせよ形成される。そうであればこそ、戦後の「いじめ」はかつてない残酷味を帯びる。
- 少数者を異常の部外者であると認定することで、それが多数決による排除ということなのである。戦後の人間主義は、どんな人間も排除されてるべき不徳と不知を持っているという前提に立っていないため、排除されたものを人間にずとみなすほかなくなったわけである。その意味で、人間主義は残忍なイデオロギーであるといってよい。
五章……
経済――道徳なきグローバリズム
23 技術が環境に襲いかかる
文明が文化を駆逐する
- 文化によって支えられなくなった文明が没落に至るのは知識の技術化によるのだが、それは今に始まったことでも西洋に限られることでもない。いくつもの文明が衰退する過程を追ってみると、文明が文化から離脱して衰弱していくというのは、ほとんど歴史的法則といいたくなるくらいの根強い傾向である。その傾向線に近代の西洋文明がもののみごとに乗っている、とシュペングラーは指摘したのであった。
- 技術は、それが「主義」となることによって、異常なばかりに発展してきたのだが、その「主義」は同時に現代人の精神を狭く浅いものにしているのだ。その結果として、道徳の荒廃も起こっている。したがって、技術の成果を存分に享受しながら道徳的に生きよう、というのは虫のいい話といわざるをえない。むしろ、現代における道徳は、技術とどうするか、技術への解釈をどう生活のなかに組み込むか、ということをおいては成り立たないのである。
六章……
社会――我々は道徳を取り戻せるのか
25 「物神」に憑かれた欲望
- メソポタミアの昔から、年寄りたちは「最近の若者ときたひには」と文句をいってきた。人類はずっとそうしてきたのだから、文句の言い方には気をつけねばなるまいが、今後ともそうすべきだと私は思う。なぜといって、人間の欲望はかならずしも順調に発達しないことを、年寄りたちは、自分らの失敗多き人生を通じて、よく知っているからである。
フリーターからは勤労者の道徳がみえてこない
- 我が国で、今、百五十万人を超えるフリーターがいるといわれている。万やむをえず時間契約で勤労をしているものもいるのであろうが、半分以上は、人生設計上のいわゆるモラトリアム期間として、フリーター生活をしているようである。モラトリアムとして歪んだ生活を選ぶというのはいかにも奇妙である。それは、たぶん、フリーターにおける就職・離職の「自由」が物神のようにめられているせいなのであろう。また、採用するがわに、こうした歪んだモラトリアム人間を利用しようという態度があるが、それは、長期的には、当該の産業の在り方を不安定なものにせざるにはいないであろう。なぜなら、それは産業の組織をひよわなものにするに決まっているからである。
マズローにもとづけば欲望には五つの側面があるはずなのに、フリーターの自由労働は、そのうちの「生存」の側面にしかかかわらない。それは、その人の道徳にもかかわる問題である。なぜなら、道徳とは人間の精神的な力強さということであった。そしてその力強さは、この場合でいえば、欲望の諸側面にバランスをもたらす能力である。生存、安全、帰属、愛情そして自己実現のあいだの矛盾を調整し、それらを総合していく知恵、それが勤労者(つまり消費者)の道徳である。そういう道徳なしに半日を過ごすなら、それはその人の道徳的な力利用をかならずや阻害する。そういう道徳的な空虚感は、その人たちの生活態度を乱れさせ、そういう人が増えるにつれ都市環境が壊されていく。
アメリカに典型的にみられてきた人間を物化および商品化する傾向は、かれ早かれ、 社会を混乱のなかに引きずり込む。その意味でも、日本のアメリカ化には重大な警告を発するべきである。
26 の道徳、の不道徳
「無党派」を肯定することの愚かしさ
- 政党政治の時代にあって、総選挙に臨んでなおも無党派であることは、政党間選択にかんして無関心もしくは無能力であるというのとほぼ同義である。しかしマスメディアにあって無党派という言葉は、既成政党にたいする不信感、という肯定的な意味を与えられている。その不信感それ自体はけるとしても、総選挙にあってなおも無党派であるものに可能なのは、本来は、投票棄権か白票投票だけだといってよい。
・ ・ ・
この例にみられるのは、無党派という政治意識の低い存在に強い政治的影響力を発揮させよう、とするマスメディアの策略であり、それが世論の大勢となるこしによって、無党派への迎合としての雰囲気を旨とする選挙戦がポリティカリー・コレクト(政治的に正しい)とみなされるようになってしまう。これと類似の現象が社会の全域に広がっていればこそ、現代社会の最大特徴は大衆民主主義だといわれるのである。
差別語を過剰に禁止すると、博愛が偽善に陥る
- 公の場から差別的表現を一切すると、どんな人間にあっても完全にはされえない差別意識が私の場に封じ込められ、その結果、かえって差別意識が隠微な形で増殖す るということが懸念されるのである。
27 「恥の文化」を壊す大衆社会
ヨーロッパは大衆化にたいする防波堤を築こうとしていた
- 公共の場で「人が善を為す」ように仕向けるのが公共心なのである。
28 春を売るなかれ、人を殺すなかれ
他人に迷惑をかけないかぎり何をやってもいいのか
- 大人の世界における道徳にかんする観念の崩壊が、子供たちの行為における乱脈として現れているのだ。
- かつて福澤諭吉が喝破したことなのだが、他人に迷惑をかけなければ何をやっても自由だ、というのは劣等な自由論にすぎない。「自分」が歴史という精神的土壌において形成されたと認識し、さらに「自分」のうちに、私心や個人だけでなく、公心や集(団)心もあると認識するなら、人はかならず、過去からいかなる道徳を受け継ぎ、未来にいかなる道徳を引き継がせるかについて、無関心ではおれなくなる。あっさりいえば、自分たちの孫子の世代にたいしても何ほどか責任を持たなければならない、ということである。そうならば、それが残されたら将来の世代が迷惑に思うような制度や風習を、現在において禁じるべきだ、という徳律が成立する。つまり、「他人」は現在の他人に限られないし、ましてや目の前にいる他人ということではないのである。そういう空間的および時間的な他人一般にたいして迷惑になるようなことをしてはならない、そう考えなければ、まともなパブリック・ソサイアティ(公共社会)をつくることができない、これが福沢諭吉のいわんとしたことである。
29 家庭は社交場である――親が子に伝えるべきこと
家族制度にたいする攻撃
- 確認さるべきは、家族制度にたいするな攻撃をし煽動してきたのは、主として知識人だということである。しかも大方の知識人は、自分らが家族制度に多大な損傷を与えてきたにもかかわらず、こうまで家族制度のがゆるんでしまったら、もう後戻りはできないのだから、この家族解体という新しい状況を受け入れざるをえない、などと世間に勧告するときている。
しかし、家族制度がいかに強い粘着力を持っているかが、実は、その崩壊過程においてすら示されている。つまり、離婚率が五〇%を超えようとも、離婚の前には結婚があったのである。また同性結婚にせよシングル・ライフにせよ、それが意味を持つのは、スタンダードとして男女の婚姻があるからである。早い話が、そうした新式の生活が社会の一標準となれば、人口の減少によって、人類は滅びに向かうこと必然とみなければならない。シングル・マザーにしても、まず間違いなく、養育や教育における困難のために、二人以上の子供を持つというわけにはいかなくなるであろう。要するに、それらの新式生活は、「暗黙の長期契約」としての婚姻にたいするカウンター・カルチャー(対抗文化)にすぎない。
家族の四つの機能
- 家族の重みは、人間の性格形成における家族の影響力という点にある。家族は、大きく分けて、四つの機能を果たしている。
一つは文化的機能である。・ ・ ・ 主として母親を通じて言葉の感情生を身につけ、主として父親を通じて言葉の論理性を学ぶ。三つ子の魂百までというが、深い潜在意識のレベルに、両親を経由して形作られた言語能力がその人の人格の礎石として横たわっているのである。
二つ目の機能は政治的機能である。人間は、言葉を用いて、未来への計画を立てる。そのために目的を定め、そのための手段を探す。そういう未来への活動の土台もまた家族において作られる。・ ・ ・ 家族はつねに何ほどか不確実な未来に挑戦しており、そこにおける決断と(家族およびその周辺への)説得は本質において政治的な機能である。
第三の機能は経済的機能である。この場合の経済というのは、目的と手段の関係を実際に遂行することをさす。・ ・ ・ 経済的といって狭ければ、それは技術的な過程だといってもよく、そこで子供は生活の合理性にかんする訓練を受けるのである。
・ ・ ・ 社会は一個の巨大な「舞台」なのであり、それゆえ家族にもロール・プレイ(役割演技)が要求される。
最後は社会的機能である。・ ・ ・ これら文化、政治、経済、社会の四方面にわたる機能は、家族のみに特有なことではなく、まさに国家を含めてあらゆる集団が担わなければならないものである。集団のみならず、一個の人間の生活においてもそれら四機能の平衡が必須なのだが、それは成人に衝いて言えることであって、子供は家族のなかで初めてそうした生活の多面性を学習することになる。
家族は社会の縮図である
夫婦における死の共感
- 人間は、死にゆく自分を我が事のように感じとってくれる他人がいる、と思うことによって、死の不安や恐怖を克服しようと願う。夫婦というものの真の複雑さは、連れ合いの死をほかの誰よりも深く思いやるという予見のうちに夫婦が生きているという点にある。
- 男女関係において責任をとれないような人間は、おそらく職業上の危機にたいしても責任をとれないであろうし、ましてや国家の危機に際して責任をとれるはずがない。
家庭は社会からの逃避先ではない
- やはり日本の国・家(つまり国民とその政府)には何ほどか特有の形式的な枠組みがあって、それが日本の徳律や法律に表されているということである。その意味でも家族は、国家をはじめとする諸集団をいかに引き受けるかということの原点となるのである。
30 地域社会は道徳の訓練場である
- 権理というのは福澤諭吉の時代の言葉で、今、それは権利といういささか卑しい言葉に変わってしまった。人間は地域共同体のなかで社会的動物になり常識を身につけることができるのだから、そのお返しに地域共同体に貢献しなければならないのではないか、というように自分の公心をめぐって「」をった上で、自分に許されていると判断される行為がある。その行為の可能性がである。
それにたいし権利は、正しい理のことなどはそっちのけで、地域共同体からどれだけの利益を得ることができるかを、私心の上で権ったものである。そういう権利のぶつけ合いをやりつづけた結果、そこを訪れる他者たちに自信を持って展示できる共同体がなくなった。それが現代日本人の都市であり田園である。いいかえれば、自分らの公心を具体的に示す最大の手だてを自分らで壊したわけだ。日本の大人たちは、自分たちの公心がいかに貧しいかを社会に平然とさらした挙げ句に、自分らの子供たちに公心がいかに乏しいと嘆いている。
以上