| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2015年12月28日 月曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
120 |
15/12 |
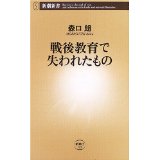 |
戦後教育で失われたもの |
森口 朗 |
新潮新書 |
〇 |
第一章 「己」を知る謙虚さ 第二章 「縮命」を受け入れる潔さ 親は子どもにとって宿命である ・自分の力ではどうにもならない各人の所与条件を、我々は「宿命」と呼んでいます。そして、どの親のもとに生まれるかは、宿命中の宿命と言えるでしょう。親の年収や社会的地位、生まれた地域や家庭の文化レベルは所与条件です。 「仰げば尊し」の二番を歌えますか ・立身出世主義がけしからんと攻撃されて戦後歌われることのなくなった二番を堂々と歌える日が来ないかぎり、子どもが学校に行って「勉強しなきゃ」と思う日は来ないでしょう。 第三章 「不条理」を生きぬく図太さ 戦後教育は誰を不幸にしたのか ・教育勅語が廃止され、学校で人生の先輩を敬えと教えなくなりました。目上の方への敬意は順送りで行われるはずです。自分が行ってきたことを後輩からされるという意味で、年金と同じシステムです。それが価値観の転換によって「尊敬年金」を掛け捨てにされたのです。 ・戦後教育の基本テーゼ ●戦後教育は個人の幸福に最高の価値を置く。個人の幸せを最大にするために、学校教育を通じて「平和」「自由」「民主主義」の素晴らしさを教えなければならない。 ●逆に個人を抑圧する存在(戦争で個人を死に追いやった国家、封建的な因習から脱却できない地域社会、個人の自由を奪おうとする古い家族意識など)は学校教育を通じて廃止していく。そうすれば社会の全員が幸せになれる。 中高年の離婚は必然だが・・・・・・ ・幼い頃に面倒を見てもらった実の親ならともかく、義理の親のために何故自分が犠牲にならなければならないのか。この素朴な疑問に対する明確な反論を、戦後教育は持ちえません。 ・今でも「実家」という言葉は使われていますが、この概念は家制度があって初めて成り立つものです。 ・家制度がある限り夫婦は「実家」として存在する意義がありました。 しかし、家制度は法的には戦後すぐの民法改正により、実態的には戦後教育により、数十年かけて解体されました。 不登校の末の「ニート」「フリーター」 ・中学校は確かに義務教育ですが、一日も出席しない者を卒業させてよい理屈はありません。今でも、家庭の事情で中学を卒業できなかった人のための夜間中学は存在します。一日も出席しない不登校児を卒業させるなど、働きながら夜間中学で学ぶ人々への冒瀆ではありませんか。 通過儀礼としての学校 ・現実に反抗するかどうかではなく、「反抗してはいけない」という規範が、現在の高校生には存在しないのです。 ・先生は社会の正会員です。対して生徒は未熟者の準会員に過ぎません。だから、個々の是非や能力を問うことなく、とにかく先生に反抗することはいけないことなのです。 ・戦後教育の価値観では、先生と生徒は平等ですから自分が正しければ反抗してよいに決まっています。しかし、他の国の高校生は同じ状況でも、「反抗してはいけない」という規範と「相手が誰であれ正しいことは正しい」という良心・理念の板ばさみに会います。この板ばさみが、人を大人に育てるのです。 ・気に入らないことがあればブーブー文句をたれてもよい空間で、人は大人になることはできません。いまや日本の学校はそういう空間になってしまいました。 「正しくない」親が子どもを救う ・どういうタイプの親の子どもが優秀かというと、学校(特に公立学校)の主張は主張として聞き流し、戦後教育的価値観からは「正しくない」家庭の教育方針をしっかりと持っている親の子です。その上で、学校は学校、家は家と使い分けることのできる親の子です。 ・こういう親のもとで育つと、子どもは親の価値観と戦後教育の価値観を相対化することができます。この価値を相対化できる思考が、不条理な社会を生きぬく力へと育っていくのです。 第四章 「日本人」であることの誇り 誰も知らない「教育の民主化」 ・戦争直後に行われた学校改革が「教育の民主化」ですから、教育基本法を始めとした改革の産物を批判し、時代に合わなくなったから変更しようという主張は、単純な頭脳には「非民主的」「反動」と映ります。 今でも本気でそう思っている人が、教育界には大勢います。 若手教師の内面は知識で変わる ・日中戦争には多分に侵略戦争的側面があると思っています。しかし、日中戦争があったから、中国が「半植民地状態」から抜け出せたことを知る人は多くありません。 ・「アヘン戦争に敗れて以後、列強の清国に対する要求は激しくなり、いたるところ租界(清国の統治権が及ばない地域)だらけとなった。清国は半植民地状態だった」とは習うのに、いつ、どのような経緯で中国が半植民地状態から抜け出たかという知識は封印されているのです。 ・清国が中華民国になって以降、租界の回収は積極的に行われていましたが、租界返還の仕上げをしたのは日本です。しかも、それは第二次世界大戦中の出来事です。 ・日本は英米に宣戦布告すると、直ちにイギリス租界を占領し、フランスのビジー政権(親ナチス政権)が有する租界も事実上支配下におきました。一九四三年にこれら租界をすべて中華民国(汪兆銘政権)に返還します。さらにイタリアが連合国に降伏すると、天津にあったイタリア租界も日本の軍事力により汪兆銘政権のものになりました。かくして中国は百年間の半植民地状態から脱却したのです。 ・日中戦争によって(しかも日本の手によって)、中国は正真正銘の独立国になれたのです。 だから日中戦争は正しかったというつもりは毛頭ありません。汪兆銘政権が日本の 悪政の中にも人士あり ・軍国主義を否定することと軍人を侮辱することは同じではありません。戦争末期に行われた「特攻」は「作戦の これを区分せずに軍人の自衛官を軽蔑し、特効を犬死と侮辱することが民主的であると教えたのは、戦後教育のもっとも醜い部分です。 第五章 「大人」を取り戻すために 三十人学級は学校を滅ぼす ・戦後教育の諸問題を解決しないままに三十人学級を実現しても、決して学校は良くならない。 学力と生徒数は無関係 ・東京都での調査では、 「一人の教員が受け持つ生徒数が増えても学力は低下しないし、減っても学力は向上しない」 「小中学校とも教職員の数と生徒の学力に何の関係もない」 ことが分かった。 誰が子どもを大人にするのか ・幼稚なまま社会に放り出される子ども達をこれ以上増やせばどうなるか。フリーターやニートはますます増えていくでしょう。子ども達に必要なのは、さらなる保護ではなく、成長過程に応じた自律です。 ・親には親の役割があり、学校には学校の役割がある。小学校低学年ならいざ知らず、中学生になっても「ウチの子をちゃんと見てください」と公的機関である学校に要求する親は、そもそも親として失格なのではないでしょうか。 親と学校ができるほんの小さなこと ・戦後教育は子どもから「『己』を知る謙虚さ」「『宿命』を受け入れる潔さ」「『不条理』を生きぬく図太さ」「『日本人』であることの誇り」を奪いました。 ・何よりも大切なのは謙虚さ、潔さ、図太さ、誇りを獲得する中で「大人になる」ことです。 凡人による凡人のための教育論 ・学校という枠に納まらない天才は、放っておいても自分でやりたいことを見つけて成就します。天才に教育論は不要なのです。それが天才の天才たる ・学校という枠に納まらない悪党ににも、教育論は不要です。彼らに必要なのは教育ではなく矯正だからです。 |