| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年02月09日 火曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 |
著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
80 |
1508 |
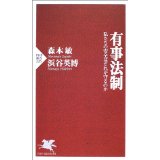 |
有事法制 |
森本 敏 浜谷英博 |
PHP新書 |
☆ |
・幸運なことに日本は戦後の半世紀、侵略や攻撃というもっとも深刻な事態には遭遇していない。 これは日本の平和憲法のおかげだと思う人がいるかもしれないが、そうではない。憲法に頼ってきたから平和が維持できたと考えるのはまったくの誤りである。 ・それは日本が戦後、米国と同盟関係を結び、米国の力を借りて国家の安全を確保してきたからであり、また、憲法の下でみずから防衛力を構築し、その抑止力が全体として機能したからである。そのことを忘れてはならない。 ・現在、日本にとってもっとも深刻な事態、外国の侵略や攻撃を受けるという事態を「有事」と呼び、それに備える体制を整備しようとしているのである。 ・日本は法治国家だから、法律にないことはできないし、根拠のない行動もとれない。したがって、まず最初に法律を整備しようということになる。ところが驚くなかれ、日本には有事の場合に国家がどのようにして国民を守るのかとう法律がないのである。 ・歴代政府が政治的リスク、つまり反対勢力の批判を恐れてその努力を怠ってきたからである。 ・しかしいまや日本は、そんなことを言ってはいられない状況になりつつある。有事とは、そのような事態になるかならないかではなくて、なったときのことを考えて、どのような体制と準備を整えておくか、ということなのである。 ・国家にとって重大な事態に際しては、国家や政府の取り組み方、行使しうる権限および国民の義務などの基本事項について、本来、その国の憲法に明文で規定されていることが望ましい。 ・国家としての包括的な有事法制も未整備のままであることが、わが国の危機管理政策を遅れたものにしてきたといえる。 ・そもそも日本は、歴史的に他国から重大かつ深刻な侵略を受けたという経験をあまりしてこなかった。島国という特殊な地理的環境もあって対外的な危機感に乏しい国家・国民である。 ・日本人が、どちらかというと予想される事態に備えるというより、何かが起こって初めて対処するという性格の持ち主なのは、こうした日本人の置かれた客観的な環境条件と深く関連している。 ・危機に見舞われるたびに新しい国内法を制定し、また国家の体制を改善して対処してきた。だが、それはあくまでも「発生してしまった事態」への対処に限られてきた。日本人は、かなりの被害にあってからでないと、法的措置をとることができない。だから何も起きていないのに、起こるかもしれないからという理由だけで法的整備を行うには、相当な事情が必要になるのである。 ・日本の法整備は、日本という国家としての体制と政策はいかにあるべきかという観点から整備されてきたのではなく、原則として「憲法上、何ができるか」という観点から法的解釈を行い、政策を実行してきたといってよい。 ・米国や英国では、緊急事態に直面して大統領や首相が、国家として何をすべきかという観点から意思決定を行い、それが法律上どのようなことになるかについては、法律家や議会が判断を下せばよいという仕組みになっている。 ・ところが戦後の日本では、緊急事態に直面すると、現行法体系のなかで何ができるかという議論を行い、法体系がないということになると、憲法の枠のなかでどのような法律を整備することが可能かについて議論し、それがすなわち政策論議であるとされてきた。 ・そこには国益に照らして日本は何をすべきかという議論はなく、憲法解釈と立法措置という法的解釈のなかに政治が存在するという世界なのである。政治主導どころか、これは法律家たちの仕事であり、けっしてリーダーの決断などといえるものではない。 ・有事という事態は到来してしまってからでは遅いのであって、国家と国民を救うためには、事前に法整備を進め、国家の体制を整えておくことが不可欠だ。そうしないと結局は超法規的措置をとらざるをえない。つまり、憲法に何と書いてあろうとも、国家・国民を救うことが優先されると言うことで、憲法上あるいは現行法令上の欠陥は無視されてしまうのである。これでは法治国家とはいえない。 ・有事法制とは、こうした超法規的な措置をとることなく、緊急時に対応できるようにするための法体系であるといってよい。 ・日本の法律に従う意思がないテロリストや武装工作員、あるいはその義務もない外国の軍隊などが、集団で協力に武装して日本国民を襲ってきた場合は、一般国民はもちろん警察も、個の強い暴力の前には無力である。自衛隊の存在意義はそこにある。 ・有事法制とは、 「国家に対する武力攻撃の事態に際して、国民の人権を保護し国家の主権と独立を守るため、侵略者に対抗し得る武力を備えた自衛隊と非武装の一般国民が、ともに侵略者と直接・間接に戦うシステムを作るための合理的ルールである」 といってよい。 ・「有事法制がいま、なぜ必要なのか」という問いは、マスコミでもさんざん取り上げられた。しかし、この問いかけは正しいとはいえない。有事法制は、主権国家として当然備えるべき法制であり、むしろ「いままでなぜ整備されなかったのか」こそが問われるべきなのである。 ・世界中の主要先進国を見渡したとき、国家の緊急事態、とりわけ侵略に備えての法制を整備していない国はない。日本がこれらの法制をきちんと整備することは、結果として日本に対する侵略や武力行使への抑止につながる。 ・二十一世紀に入ってなお国民の安全に対する脅威は確実に高まっており、これらに国家として有効に対処するための法制はできるだけ早く整備すべきである。 それも、まだ何も起きていないうちに整備することが必要だ。 ・国を守る自衛隊がいざというときにその能力を十分に発揮できるよう、また国民が戦争の被害から保護されるためにも、平時、まだ国民生活や社会が正常に機能しているときに、冷静な立場で有事・緊急時の対応について検討し、法制を整備するのは、きわめて重要であり、当然のことである。 ・有事法制が緊急時になってから整備すればよいという意見があるが、これは無責任な、国家・国民のことを真剣に考えていない意見だといわざるをえない。国家の緊急時には、まず外交交渉などによって平和的に危機を回避する努力をすべきであるが、その段階で有事法制を整備すれば、かえって緊張状態を悪化させてしまうことにもなりかねない。 ・いうまでもなく日本は立憲国家である。近代立憲主義とは、国家の専制を排除し、あらゆる状況下において国民の人権を保障しようとする憲法原理である。したがって、国家のすべての権力行使には法的根拠を必要とし、その法は立憲主義に基づく憲法の理念に合致していなければならないとされる。この意味で国家は、国民の人権を保障する装置だといえるわけである。 ・ところが、この装置は、内外の物理的力によって破壊されることがある。それを防御する手段として、歴史上さまざまな方策が講じられ、その法的根拠として自衛隊や国家緊急権が主張されてきた。 ・有事とは、国家および所属する国民に対する物理的侵害およびおそれをいい、そのまま放置すれば近代立憲主義を保障する装置としての国家が崩壊し、ひいては国民の各種人権の蹂躙を許すような緊急事態をいう。したがって有事法制は、国家緊急権とのかかわりのなかで発想されたものであり、国民の人権保障を究極の目的とする。 ・本来、軍隊には任務遂行のための国内法的規制はない。任務の目的が、国家の独立と国民の安全確保にあるからである。唯一の制約は、国際法上の禁止事項だけである。そのため昨今、国際法上認められている諸原則や基準が、自衛隊にはストレートに適用されないなど、多くの矛盾が指摘されている。日本を取り巻く国際環境の激変にともない、自衛隊の法的性格にも国際基準に照らした位置づけが必要となってくるだろう。 【国会の事前承認にこだわるのは危険】 ・国会承認については、政府の判断による具体的行動の事前か事後かにばかり議論が集中し、国会みずからの特性を発揮するための制度的配慮が欠如している ・本来の緊急事態が一刻を争う対応措置を必要とするものであれば、限られた情報と刻々と推移する現状の中で事前承認行為自体が政府案の丸呑み状態と大差なく、かかる承認行為が国会関与のすべてだとすれば、シビリアン・コントロール自体が形骸化してしまう。 ・この意味で「原則は事前承認、状況によっては事後承認」(実質的には事後承認)という点は必然的な結論なのである。 ・事前承認制を法律中に入れることによって、政府独走の歯止め措置としてシビリアン・コントロールの実効性が向上すると考えるのは、国会の自己満足にすぎない。 ・一度国会が承認を与えた場合、法律上の無効手続をとらない限りそれを取り消す方法がないとすれば、安易な承認行為自体が危険であり、国会は事前承認にこだわるべきではない。 ・政府と国会が各々の特性を発揮して、国家の存亡にかかわる政策判断をいかに迅速かつ効果的に遂行できるのかの一点につきる。 ・国会の真の出番は、政府判断を承認して具体的行動が行われたあとであって、それを継続的にフォローし、チェックしつづける体制をいかに確立しておくかが重要なのである。 ・そもそも国会の合議体としての特性は、多くの情報や資料に基づいて十分な審議時間をとり検討・抑制する点にあり、国民の直接代表たる存在価値は、その特性によってこそ示されるべきであろう。 ・加えて緊急事態対処に関する政策はつねに不法な主権侵害や人権侵害などの一刻も早い排除を目的とし、そのための軍事的合理性の追求と国民一般の人権制約との調和をいかに求めるかが問われつづけることになる。したがって、国会によるシビリアン・コントロールをいかに効果的に行うかは、軍事に関する性格かつ豊富な知識を有する政治家によって、プロフェッショナルな視点からの的確な判断こそが期待されているといえよう。 【期限付き国会承認制という方法】 ・現行法制のなかで、一度国会が承認した案件について、その後の国会が再評価して少なくとも先の承認を取り消す手段は制度的にない。「国権の最高機関」としての判断に対する尊厳性の維持からは当然ともいえる。しかし他方から見れば、現行法制上の国会承認は、政府の行動に対する将来的な白紙委任的効果を有することにもなる。 ・そこで国会承認効果に有効期限を設け、必要な場合にはそれを更新する手続きを条文中に明記しておく「期限付き国会承認制」は有効で検討に値しよう。 ・すなわち事前であれ事後であれ、初回の承認から特定の有効期限を設け、承認された活動を期間満了後も継続するには、有効期限満了前の特定期日までに、政府に対して活動継続に対する事前承認手続きを義務づけるのである。 【国会のチェック機能を高める「国会拒否権」】 ・わが国の制度内に国会拒否権を導入しうる余地は大きいといえる。つまり内閣が国会に対して連帯責任を負い、国会の信任を内閣存立の要件としていることは、つねに国会のチェック機能を作用させ、ときに強制的に政策拒否を明らかにすることの法的根拠であるともいえる。 ・つまり国会(衆議院)が最終的に内閣全体に対する不信任さえ突きつけることができるということは、内閣に対する全面的拒否権の行使にほかならない。しかしながら平時における対立ならば、衆議院の解散による総選挙の施行など長期の政治空白も民主制の原理から首肯されようが、有事とはそれ自体が許されない状況である。政府部門である両府の意思の合致を国民に示しながら、有効かつ迅速な対処措置をとりつづけなければならず、内閣全体に対する不信任ではあまりに影響力が大きすぎる。 ・したがって特定の有事関連法にのみ国会拒否権の行使によるシビリアン・コントロールを規定し、つねに政府と国会の共同判断を求める方法が肝要となろう。 【国会承認は取消しできたほうがよい】 ・自衛隊法七六条(防衛出動) 国連平和維持活動(PKO)協力法(実施計画) 周辺事態安全確保法五条(国会の承認) テロ対策特別措置法五条(国会の承認) ・以上の現行法の共通点は、PKO協力法の二年を超えた活動継続に対する事前承認の制度を除き、いずれの条項も、一度承認を与えたあとのフォローについて国会の関与に関する規定がないことである。 ・従来の国会論議が、自衛隊の活動の初動時に限定した事前承認か事後承認かという点にのみ集中し、問題の本質をついていない点、また緊急事態の突発性から実態的には事後承認にならざるをえず、仮に事前承認を求められても少ない情報や判断材料のなかでは結果的に政府の意向を丸呑みせざるをえない点、国会の特性から本来の出番は最初の承認後の継続的検証にある。 ・この前提で考える限り、シビリアン・コントロールの実効性を確保するため、承認効果を左右する手段を法律中に明記して、その効果を担保しておくことには大きな意味がある。先の条文で見る限り、ことごとくこの手段が欠如していることがわかる。 【地域の防災組織は民間防衛組織に改編できる】 ・現在市町村の各地域に設けられている自主防災組織の民間防衛組織への転換も、急ぎ検討されるべきである。 ・地域住民にとって、突然みずからの生命や生活を脅かし危険に陥れるものは、人為的と自然的とを問わず、すべてある種の緊急事態である。そこでは大規模テロもミサイル攻撃も緊急事態の一類型にすぎない。 ・アメリカのFEMA(アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁)の創設理念にも、「自然災害に役立つものは、当然、民間防衛にも役立つものでなければならない」との発想がある。 ・自衛隊と警察は法的にも、機能上も、責任・権限の範囲・内容が明確に区分されている。しかし、有事に際して、国家の防衛、治安および国民の避難ならびに、これにともなって生起する緊急事態・混乱に対し自衛隊と警察が一体となって有機的に活動しなければならないことはいうまでもない。国民の保護のための法制は自衛隊と警察の権限と責任をどこまで法的に調整できるかという問題を抱えているのである。 ・ただし大規模侵略などの有事では、内閣総理大臣の直接指揮がふさわしい場合もあろう。重要なのは内閣総理大臣の代理として、つねに現場で指揮を行う担当官の存在である。これら一連の判断を補佐する機関として、日本版FEMAの創設が望ましい。各省庁は個別に有する緊急事態対処機能をあらかじめマトリックス化し、縦割りを排除した機能別の協力態勢を確立し、当該機関にその役割を調整する権限を与えるのである。 【戦争がはじまったら自衛隊だけでは国防は難しい】 ・諸外国の防衛法制を比較検討してみると、ほとんどの国で国民の保護法制に相当の力点が置かれていることがわかる。とりわけ各国が民間防衛を重要視するのは、航空戦中心の近代戦においては、戦闘地域が大幅に拡大されるとともに、同地域に軍隊を迅速に派遣すること自体が距離的にも時間的にも不可能になり、おのずと多くの地域住民が被災することが増加した現実による。 ・戦時における軍人と一般国民の死亡者数の史的推移がある。第一次大戦時には軍人の犠牲者一〇〇〇万人に対し、一般国民の犠牲者五〇万人の二〇対一だったのが、第二次大戦時には二六〇〇万人対二四〇〇万人とほぼ拮抗、朝鮮戦争では一対五に逆転して一般国民の犠牲者が軍人の五倍を記録し、ベトナム戦争では、一般国民の犠牲者が軍人の二〇倍にまで増加したのである。 ・ところが戦後の日本では、有事法制の論議自体が先送りされてきたと同時に、戦時中の「隣組」や国家総動員法の復活をイメージさせるとの反対論も根強く、民間防衛の議論自体が行われてこなかったのである。 ・しかし民間防衛の法制化は国民の生命・財産の保護という観点からは不可避的に重要である。 ・とりわけ、わが国が「専守防衛」を自国防衛の基本指針としている以上、武力行使の現場となるほとんどすべてはわが国領土内であり、狭い国土に人口密度の高い地域を多く抱える実態に配慮すれば、その重要性はおのずと理解されよう。民間防衛組織の整備は最優先課題ともいえるのである。 ・有事には、特定の公的任務を遂行する自衛隊を除き、守る役割と守られる立場とが判然としない場合が多い。われわれ国民は自助努力を基本としながら、互いの立場を理解し相互に助け合うことが必要なのであり、直接的な戦闘行為には参加しないにしろ各々の国民の役割は決して小さくはない。 ・国家存亡の危機にあたって、国民が一協力しなければならないことは当然であり、諸外国が憲法で「国防は国民の神聖な義務である」と明記している理由もここにある。わが国憲法にこうした明文規定がないからといって、国防義務は自衛隊だけが負っているという考え方があるとすれば、これは根本的な誤解であり勘違いである。自衛隊だけで国防がまっとうできるはずはない。 ・有事には、自衛隊はあくまで不法にわが国領土に侵入してきた武装集団やテロ集団と対峙し、それらとの戦闘に専念し、それを撃破することで間接的に一般国民を守る以外にないはずである。防衛出動時の目的はまさにこの点にある。 ・非戦闘員たる国民は、種々の支援は受けるにせよ、みずからが主体となってみずからを擁護し、避難・誘導や避難所の運営、各種の連絡、相互の救援・救助、治安の維持などにあたらなければならない。 ・また政府が国家防衛の役割を担っている一方、国民生活に対する直接的支援は地方自治体が担当せざるをえない。国はそれらへの有効かつ適切な支援体制を確立し、国民の安全確保に万全を期することが求められる。 ・いずれにせよ、国・地方自治体など行政サイドの支援と国民サイドの自助・共助の組織が確立してこそ、国民の保護体制が具体的に機能することになる。その意味で民間防衛組織が整備されなければ、有事法制は完結しないといっても過言ではない。 【国民を守るのは結局、国民自身】 ・戦時における非軍事的な側面として、一般に「民間防衛」や「市民防衛」といわれる概念がある。これには国民生活の安全を確保する活動全般が含まれ、究極的な目的は被害の局限化である。 ・具体的には人命の危険からの防御と救助を第一に掲げることから、純粋な人道主義的組織ともいうことができる。加えて住民の避難・誘導や被害の復旧、医療・治療・被災者介護、捜索・救援・救助、食糧の配給や生活物資の支援、消防、警察や情報・通信・輸送・工事、危険物の処理や取り扱い、公共秩序の維持等々、幅広い非軍事的活動が含まれている。 ・当然のことながら、これら活動のすべてに自主組織だけで対応することは不可能であり、行政サイドからの各種支援は不可欠であるが、国民各自が具体的活動の当事者として自覚すべき基本的な自助・共助の姿勢は重要である。 ・そもそも民間防衛は、有事や戦時において、国民の被災を局限化し保護することを目的にして定められた「戦時における文民の保護に関するジュネーブ条約」(一九五〇年発効)で認められた権利である。 ・わが国は一九五三(昭和二八年)に批准したが、それに関する国内法制は未整備のままである。先進国で民間防衛に関する法制や具体的な組織を持たないのは日本ぐらいともいわている。 【韓国の民間防衛隊は年一〇日の訓練が義務】 ・韓国は七五年、外的の侵攻や国土の全部または一部の安寧秩序を脅かす国家緊急事態からの住民の生命・財産を保護するため「民間防衛基本法」を制定した。 ・同法は、国家緊急事態における国民保護のため、政府の指導下で各地域住民が行うべき応急の防災・救助・復旧の活動および軍事作戦上必要な民間の支援など、あらゆる自衛活動を規定している。 ・民間防衛隊は、軍人や学生などを除く二〇~四五歳の男子および志願した女子で構成され、一年に一〇日、五〇時間以内の教育・訓練を受ける。 ・こうした組織は、戦時における被災のみならず、平時における地震や洪水などの自然災害時にも十分機能し、住民保護全般、とりわけ人命救助や各種支援活動を行っている。 ・つまり枠組みや組織行政サイド主導であったとしても、その実効性を確保するのは国民一人ひとりの自覚と責任であり、これが民間防衛にとって不可欠な基盤的視点といえる。 【緊急事態に私権はどの程度制限されるのか】 ・有事発生の段階では、もはや国民の人権制限の是非を論ずるのではなく、国民の人権のうち、どれを、どの程度制約するかの問題なのである。その際、人権は天賦のものであるとか、財産権は憲法で保障されていると息巻いてみても、ほとんど意味がない。 ・国家が蹂躙され、人権保障装置が破壊されてしまえば、生命・財産をはじめすべてが終焉を迎えることになるからである。私権の制限は、平和の回復と人権保障制度の復活のため、やむをえない最小限の措置なのである。 ・日本国憲法も、人権の保障については公共の福祉の原理を用いてその濫用を禁じている。すなわち、国民には永久不可侵の権利として基本的人権が賦与される(一一条)としながら、これを濫用してはならず、「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」(一二条)とし、さらに生命・自由および幸福追求権についても、「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」(一三条)と定めた。 ・つまり有事は「公共の福祉」の維持がもっとも危機にさらされている状態であり、その回復・実現のためには必要最小限の一時的な人権制限は、国民として甘受せざるを得ないところであろう。 ・とりわけ財産権についての規定は、その不可侵性(二九条一項)とともに、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共の福祉のために用いることができる(二九条三項)と規定され、災害対策基本法の具体的条文にもこの発想が生かされている。 ・いずれにせよ、まず国家として速やかに取り組むべき重要問題を整理して最優先に取り組むことが求められているのである。同時に、こうした一連の有事法制を国民にとってわかりやすいものにするよう努力する必要がある。国民の理解と支持がない法案は、結局のところ国民に定着しないし機能しない。 ・自衛隊の本質は、国家の独立と安全を確保し、国民の生命と財産を擁護することにある。つまり自衛権が、憲法への明記など必要としない国家の属性といわれる所以である。だし自衛権が画餅に帰すことのないよう、正当な法的根拠によって実効性のある自衛作用が保障されていなければならない。これが有事法制整備の究極的目的である。すなわち立憲主義を標榜する法治国家にあって、その整備は国家としての当然の責務である。 ・加盟国の増加によるNATO地域の拡大や各種の安全保障環境の整備は、集団的自衛権の発想さえ転換させようとしている。つまり、イデオロギーの相違に端を発する国家群の対立を前提とした自国防衛の発想から、平和的国際協調を攪乱する不法な集団や国家を排除する発想へと変革しつつあるのだ。 ・有事法制はもはや整備するか否かではなく、いかに整備するかの段階に着実に移行しているといえよう。 ・また有事法制の未整備は、周辺国の疑心や懸念を増幅させることにもなる。ためにする政治的牽制を除けば、一朝有事の折には日本は何をやるのか、どこまでやるのかわからない状態は、緊急時に乗じた行動の不明確性や不安定性を逆に拡大させている。 ・周辺国の信頼醸成によって平和外交を積極的に促進させるためにも、また同盟国との連携や国際協力の強化による自国の安全保障の確保のためにも、有事法制整備は不可欠な政治課題として緊急に推進されるべきであろう。 ・国際社会における日本の立場と役割を自覚し、成熟した独立国として独自の貢献をいかに果たすか、新世紀初頭における国際情勢の変化を敏感に察した政策の具体化が望まれている。 |
78 |
15.08 |
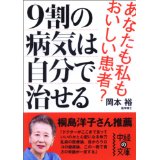 |
9割の病気は自分で治せる |
岡本 裕 |
中経の文庫 |
☆ |
・私の周りでは、高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満症、痛風、便秘症、頭痛、腰痛症、不眠症、自律神経失調症などは総称して「喜劇の病気」と呼ばれています。 理由は簡単です。なぜなら、それらの疾患は悲劇のヒロインの病気にはなりえないからなのです。 ・「喜劇の病気」は原則として自らの力で治すことができますし、仮に医者の力が必要な場合でも、ほんのわずかなアドバイスで事足ります。 ・日本には「おいしい患者」が実に多くいます。 「おいしい患者」とは、言うまでもなく、医者にとって非常にありがたい患者さんだという意味です。 文句も言わずに定期的にずっと通院してくれること。 その上、黙って薬をのみ続け、検査を受け続けてくれます。そうなれば、儲けも確実に見込めて、とてもありがたいはずです。 さらに、これが非常に重要なポイントになるのですが、命にかかわることもなく、さりとて完全に治らないことが、重宝するのです。 ・命にかかわらない患者さんを診る場合は、やりがいという点でははなはだ疑問がありますが、なんと言っても気楽に対応できますので、非常にありがたいのです。しかも完全には治らないというのもおいしい点です。いくら気楽な病気でも、すぐに治ってしまってはリピーター(顧客)になることがありませんので、まったくおいしくありません。 ・みなさんが自ら強くなって意味のない通院をやめることは、長期的にみれば、薬と検査漬けのマニュアル化された医療の現状を是正することにもなります。 ・日本の医者一人が、年間に診察する患者数はおよそ8500人、それに対してOECD平均は2421人です。 ・外来患者一人当たりの診察料の平均が、日本が7000円なのに対して、米国は6万2000円、スウェーデンはなんと8万9000円で、日本は極端に低いのです。 ・日本の医者は、日本の医療システムが薄利多売構造になっているために、多数の患者さんを診なければやっていけないのです。 ・日本の医者も欧米の医者も報酬はほぼ同じですから、結局は日本の医者は非常に忙しい思いをしているということになります。 ・50~60人くらいは診ないと経営が成り立たないのも、日本の医療現場の厳しい一面です。 ・私がいなくても治る人は治っていた ・私がいても治らない人は治らなかった ・病気の状態(病態、疾患)をおおまかに分類してみると、次の3つのカテゴリーに分けることができます。 カテゴリー1 医者がかかわってもかかわらなくても治癒する病気 カテゴリー2 医者がかかわることによってはじめて治癒にいたる病気 言い換えると、医者がいないと治癒に至らない病気 カテゴリー3 医者がかかわってもかかわらなくても治癒に至らない病気 ・開業医や市中病院の医者が日常診療で遭遇する疾病のほとんどは、カテゴリー1にあたります。その比率は、少なくとも70%以上、多ければ90%以上だと思います。 ・医者にかからなくてもい人をかからなくていいと断定することも大切な仕事ですが、そのことは今はあまり重要視されていません。 ・今の社会風潮は、高血圧、高脂血症、糖尿病、肥満などは「しっかりと治療を受けなくてはいけませんよ」という空気です。これは、医療機関の経営者にとっては、とてもありがたい追い風です。その風は自然にふいたのではなく、政府が吹かし、メディアがあおっているような気がします。 ・定期的な検査も、患者さんをつなぎとめる非常に有効な手段です。簡単な血液検査も項目を適当に増やせば、大抵はなんらかの異常値が見つかるものです。脅す材料にはこと欠きません。 ・政府の論理は、病人が増えれば医療費支出が増加し国の財政を圧迫することから、予防措置として、合併症を併発する糖尿病や高血圧の基準値を下げることで警告を鳴らしているのだと思います。しかし、医療の世界が経営の安定化を重視するあまり、その警告を逆に利用して、安易な方向に走っているのではないか。 ・米国では昨今、あまりにも医療訴訟が多すぎて、医師への希望者そのものが減る傾向にあるようです。 命がけで命を救うことは、まさに命がけなのです。 ・命にかかわる疾患と向き合う医者が、もう少し快適に、第一線に長くいられるような、そんな環境を整えなければいけないはずです。 ・がんをはじめとする慢性疾患、免疫疾患は西洋医学の考えだけではなかなか治りません。西洋医学、東洋医学、補完代替療法の枠にこだわらずに、それぞれのいい部分を取り入れ、病気の根本原因を解消し、もともと備わっている自己治癒力を増進させることによって治癒を目指すのが、最も理にかなう。 【高血圧】 ・日本人の5人に1人が高血圧症患者というのは、いくらなんでも、高血圧の定義そのものがおかしいと考える方が自然でしょう。 ・薬で血圧を下げるというのは根本的な治療ではなく、あくまでも対症療法なので、薬の服用は限られた期間に限定すること。そしてその限られた期間に生活習慣を是正して、体重を減らしたり、ストレス負荷を和らげる工夫をしたりという努力を優先して行うこと。 ・血圧が低くても脳出血は起きます。また、血圧が高くても脳出血が起こらないこともあります。 ・血圧の上の値(収縮期血圧)が常時200mmHgを超えるほどの極端な場合は別として、血圧の値と脳出血が直接相関しているという印象はありません。 ・むしろ、血圧の値の急激な変動、生活習慣の乱れ、栄養の偏り、肥満、考え方、過度なストレス負荷などの方が、脳出血とより密接に相関しているのではないか。 ・降圧剤をのみはじめて、かえって調子が悪くなる方は少なくありません。特に高齢者の場合、上の血圧(収縮期血圧)を150~160mmHg以下に急激に下げてしまうと、何かしら不定愁訴(元気がなくなった、もの覚えが悪くなった、頭がぼうっとする、集中力がなくなる、寝起きがすっきりしない、手足が冷たくなった……)を訴える人が多くなります。 ・老人ホームなどでは、降圧剤を服用している人の方が、服用をやめた人に比べて、認知症の進行が早いという報告もあります。 ・「NIPPON研究」によりますと自立度が著名に低下するとされています。 ・血圧が高くなるのは、それなりにちゃんとした理由があるからです。つまり、身体の適応であることを理解しなくてはなりません。血圧を高く保つことによって、生体の機能をうまく維持しているわけです。だから、何の脈絡もなく薬で血圧を無理やり下げてしまっては、体にいいわけはありません。 ・上の血圧値が180mmHgくらいまでは、脳卒中になる可能性が高くなるという明確な根拠もありません。 ・「ヨーロッパ高齢者高血圧研究会」が行った調査によると、高齢者にとっては、むしろ血圧が高ければ高いほど、総死亡率が低くなるという結果も出ています。 ・血圧が高いことと白血球数が多いことは、元気なご老人の共通点なのでした。 ・自律神経の1つである交感神経は、運動をしたり精神的に緊張したりしてドキドキしたときに活動する神経で、心拍数や血圧を上げるなど、全身の活動力(エネルギー)を高める方向に働きます。 ・体重が増えたりストレス負荷が強くなったりすると血圧が上がりますが、これは身体のエネルギー需要を確保するために必要なのです。より血圧を高めることが、心身に有利なために高くなっているのです。 ・“根本的な解決”とは、血圧が高くなった原因そのものを是正することです。血圧の値だけを無理やり薬で下げてみても、なんら解決にはならないということなのです。多くの方は“根本的な解決”をなおざりにするせいで、かえって薬をのみ続けなくてはいけない破目に陥るのです。それこそ本末転倒です。立ち直りを不可能にするために降圧剤をのんでいるようなものだと思います。 ・生活習慣をそれなりに是正し、ストレス負荷を軽減する工夫をして、それでも家で測った血圧値が、上が200mmHGを超え、下が100mmHGを超えるほどでなければ、さほど心配することはない。 【糖尿病】 ・空腹時血糖値が140mg/㎗くらいであれば、すぐに合併症が起きるほどの血糖値ではありませんので、あわてて服用する理由もないはずです。まずは生活習慣の改善を優先すべきです。 ・血糖降下剤の服用が問題なのは、対症療法にすぎないからなのです。 ・血糖降下剤を服用することによって、見かけ上は、血糖値やHbA1c(ヘモグロビンA1C)の値は改善されます。 しかし、それは治ったということではありません。逆に、生体の自律(自己治癒力)を損なう危険性を多分にはらんでいます。血糖降下剤のために生体の調整機能、すなわち自己治癒力はいよいよ衰退していきます。 ・ついには、自律機能がまったく機能しなくなり、インスリンを補うよりほか、手立てがなくなってしまいます。そうなればまさしく、一生薬漬けになってしまうでしょう。 ・さらに本人も、薬さえ服用すればこと足りると変に安心して、いよいよ薬に依存するようになります。そうすればますます生活習慣を改める努力もおろそかになり、自律能はいよいよ低下するばかりです。 ・日本糖尿病学会は1999年に、糖尿病の基準値を140mg/㎗から126mg/㎗にいきなり改定しました。そのおかげで、新たに数百万人もの方が、はれて血糖降下剤を服用する資格を得ることになりました。 ・ある老人ホームでは、入所して2カ月もたつと、糖尿病と診断されたお年寄りのほとんどが治ってしまうことでも有名です。ホームの“食”へのこだわりが功を奏しているのか、玄米菜食と日本の伝統食を給食の基本にしていることがキーポイントではないか。 【コレステロール】 ・日本動脈硬化学会は、治療が必要なコレステロールの値を220mg/㎗以上としています。 ・実は、コレステロールが220~280mg/㎗の範囲の人が一番長生きしています。 ・「NIPPON研究」でも、コレステロールの値が低いほど、がん死亡率が高くなり、自立度が低下するという結果が出ているのです。 ・コレステロールが高くなればなるほど、心筋梗塞だけは、ごくわずかですが発症しやすくなるのは確かです。しかし、すべてにおける死亡率や、あるいはがんの死亡率は、圧倒的にコレステロールが低いほど、高くなるのも事実なのです。 ・したがって、常識的に考えてみてどちらが得かという話になれば、スタチン剤はやめるべきでしょう。 ・コレステロールは細胞の膜の材料になったり、ホルモンの材料になったりと、非常に大切なものです。悪者呼ばわりなど、お門違いもいいところだと思います。 ・スタチン剤をのめば、もちろん大切なコレステロールが不足してしまいます。また、コレステロールが作られるときに一緒にできるはずのコエンザイムQ10もできにくくなります。 ・コエンザイムQ10は、生体活動のエネルギー源を作るために必要な物質で、非常に重要な働きを担っています。 ・コレステロールが不足しますと、細胞そのものが弱体化しますので、当然、生体の自己治癒力(防衛力)は著名に低下します。つまりスタチン剤によって、生体の維持が危うくなるということなのです。 ・したがって、あえて悪玉と言うのであれば、コレステロールよりもむしろスタチン剤を悪玉と言うのが、正しい言葉の使い方になるかと思います。 ・スタチン剤をのむということは、小さく得して、大きな損をする典型とも言えます。 ・スタチン剤には、重篤な副作用として、がんや横紋筋融解症の誘発が挙げられる。 ・コレステロール低下剤をのむ人は、今や1000万人近くに上るといわれています。 【肥満】 ・○○ダイエットのように、同じものばかりを食べると、当然のことながら栄養が偏ってしまい、自己治癒力が低下します。 ・また栄養が偏ってしまうことで、体重は減少します。何も画期的な方法ではありません。極めて当たり前の話です。 ・さて、炭水化物を極端に減らすとどなるのでしょうか。 炭水化物はもちろんエネルギーの源ですので、当然の結果としてエネルギー不足に陥ります。そのため、炭水化物のかわりにタンパク質にエネルギー源としての動員がかかります。つまり炭水化物(糖類)がエネルギー源として利用できないので、たんぱく質(アミノ酸)からわざわざ糖(炭水化物)を作ってエネルギー源を確保しようとするのです。 ・もちろん生体は、タンパク質をほとんど筋肉として備蓄しているわけですから、タンパク質がエネルギー源として必要となれば、筋肉が解けていき、もちろん自己治癒力も著名に低下していきます。 ・いずれの手法も体調を損ね、その結果として体重が減っているのです。言い換えれば、命がけのダイエットなのです。早い話が、病気になって痩せてくるという当たり前の原理なのです。 ・健康を維持しながら減量(ダイエット)する方法は、結局は栄養素を減らさないで、カロリーを減らすしか方法はありません。つまり食べる量と運動のバランスを調整するしか方法はないのです。 ・太りやすいという体質は、生物学的にはより進化しているということなのです。いつも飢餓にさらされていた人類にとっては、太りやすいということは究極の進化体、つまり超好燃費体なのです。 ・少し太り気味の方が本当は長生きなのです。 ・体重を減らすのに必要なアイテムは体重計です。ただそれに尽きると思います。 ・体重計に乗るくせをつけることです。あとはその値とにらめっこしながら、向こう1日や2日、間食を減らすか、アルコールの量を減らすか、あるいは脂っこい物、甘い物を減らすか、はたまた、エレベーターやエスカレーターに乗らないか、自問してみることに尽きます。 ・5キロを超えると少し努力が要りますが、1~2キロであれば、ほんのちょっとした心がけだけで、誰でも容易に減量できます。 少し面倒なことを1カ月もやれば、ほぼ間違いなく、少なくとも2~3キロは減量できるはずです。2~3カ月続けることができれば、数キロはダイエットできます。そのコツを掴めば、自信もつくかと思います。 ・よくある質問が、食べる量は減らさないで、運動するだけで減量するという手法があるのでは? というものです。 確かに理論的には可能です。しかしそれは現実的ではありません。なぜなら、運動だけで減量できるほど立派な自制心の持ち主であれば、きっとはじめから肥満にはなりません。 ・果物はダイエットの敵とされる向きもあるようですが、むしろダイエットに適した食物といえるかと思います。 【メタボリックシンドローム】 ・メタボリックシンドロームは、カテゴリー1の「医者がかかわってもかかわらなくても治癒する病気」の代表選手です。 ・メタボリックシンドロームを一言で言うと、ただの食べ過ぎ、運動不足で、それ以上でもそれ以下でもありません。 ・本来はそれほど大騒ぎするものではないことを、社会゛教える必要があるのですが、政府もメディアも、こぞってメタボをあおるばかりです。その風潮に乗じて、儲けてやろうという ・1つだけ、メタボブームをよしとする点を挙げるとすれば、健康への意識が低い人たちに、生活習慣の見直しを喚起したことだと思います。 ・このメタボブームで、国民が未病に関心を持つきっかけになれば、それは好ましいことでしょう。未病は自分で治す! という社会的なムーブメントを巻き起こすことができれば、メタボブームも、うまく軟着陸できるかもしれません。 【便秘】 ・便秘の人は野菜や果物、発酵食品の摂取量が極めて少ない。 ・便秘によって腸内環境が非常に劣悪になっていて、ひいては免疫力(自己治癒力)を低下させることにもつながり、場合によってはさまざまな病気の元になったり、そしてなによりも肌の老化が早まったりします。 ・また、安易に薬剤に頼りすぎると、次第に薬も効きにくくなってしまいます。 ・腸は脳からの指令ではなく、原則として、自分で考えて機能しています。 ・腸にある神経細胞(ニューロン)の数は1億以上で、この数は脊髄全体に存在する神経細胞の数より勝っています。つまり腸は立派な神経器官とて言ってもいいくらいなのです。 ・腸が自立して機能しているということは実にすごいことなのです。なぜなら、外界から入ってくる(侵入してくる)すべての物質を体内に取り入れるべきか、排除すべきか瞬時に判断して機能しているわけなのですから。 ・全身のリンパ球の約60%は腸で働いています。そして抗体の60%は腸で作られています。つまり、腸は私たちの免疫を ・実は花粉症、気管支ぜん息、アトピーなどのアレルギー疾患のなりやすさは、腸の環境に大きく左右されることが明らかになっています。 ・がんをはじめとする慢性疾患のほとんども、おそらくは腸の環境のいかんが、その発病率や治癒率に大きく影響するものと思われます。 ・腸では数多くの神経細胞や、免疫細胞が機能しています。その上、腸管内には100種類以上もの微生物が ・したがって安易に抗生物質などで腸管をきれいにしてはいけないのです。抗生物質によってはほとんどの腸内細菌は死滅してしまいますので、心身へ及ぼす悪影響は少なくないはずです。 ・脂肪の摂りすぎ、動物性たんぱく質の摂りすぎ、野菜・果物の摂取不足、薬ののみすぎ、発酵食品の摂取低下が、腸の機能を低下させている主な要因となっています。 ・それは、アレルギー、がんをはじめとして、多くの慢性疾患が増えている現状ともみごとに符合します。 ・このスゴい腸の機能を適正に保つためにはもちろん食習慣を是正することが最優先なのですが、安易に薬剤に頼るよりは、プロバイオティクス(※1)やプレバイオティクス(※2)をうまく活用することも、非常に賢明な考えだと思います。 (※1)プロバイオティクス 消化管内の最近叢を改善し、宿主に有益な作用をもたらしうる有用な微生物など(ex. 乳酸菌など)。 (※2)プレバイオティクス 有用な微生物の増殖促進物質など(ex. オリゴ糖、繊維質など)。 ・微生物は昔からよくBRM(生体応答調整物質)(※3)の宝庫だと言われています。しかも微生物や発酵の分野は、日本がもっとも得意とする研究分野の1つでもあり、今までに私たちの先輩が築き上げてきてくれた膨大な英知が蓄積されています。このすばらしい英知を利用しない手はありません。 (※3)BRM ⇒ 最適な健康状態を推進する有機化合物のこと。 【腰痛】 ・一般的には腰痛は腰の筋力の低下や、交感神経の過緊張で起こる。したがって、血流を止めてしまうように働く湿布薬や消炎鎮痛剤、そしてコルセットは、一時的には症状を軽快させるかもしれないけれども、根本的な治療にはならない。 ・腰の血流を改善させること、腰の筋力を高めること。 ・具体的には、まずは前かがみの姿勢を意識して是正すること、同じ姿勢を長時間続けないこと、ストレッチ運動をすること、ときどき腰を反ること、できれば腹筋を鍛えること。 ・薬を処方するということは、すなわち毒を盛るということです。 ・薬剤すべてに言えることですが、薬剤の連用で、一番に懸念されるのは自己治癒力を低下させることです。 ・具体的に述べますと、リンパ球の機能低下をもたらすということです。そうなればがんが発生しやすくなります。 【対症療法ではなく、根本治療を】 ・具体的な方法がどうであれ、根本治療(自己治癒力を高め、根本的に治すことを主眼におく)にこだわることが、慢性疾患の治療の必須条件です。しかも実際、ほとんどのケースは自己治癒力を高める手立てを個々に考えることによって、十分に治りうるのです。 ・根本治療を優先させたうえで、それでも、その効果が現れるまでの時間稼ぎが必要な場合には、薬をはじめとする対症療法が本領を発揮するのではないでしょうか。 ・外来受診する約9割の人たちは、根本治療を優先させれば、それだけで治る。 ・もちろん薬を用いることが必要な方もいらっしゃると思いますが、それはほとんどの場合が、期間を限定したものであるはずです。 【健康と病気の境】 ・みなさんの体の中では、毎日がん細胞が発生しているといわれています。しかしみなさんは、がん患者ではありません。それはなぜでしょうか。それは発生したがん細胞が、うまく成長することができないからです。つまりがん抑制遺伝子が働いて、正常な細胞にひき戻されるか、そうでなければリンパ球やマクロファージ(※)によって、ことごとく処理されてしまうからなのです。 (※)マクロファージ ≒ 単球・・・・・・白血球の一種。 免疫システムの一部をになう細胞で、生体内に侵入した細菌、ウイルス、はたまたごみや細胞の死骸まで、なんでも食べることを生業とする奇特な奴。 ・みなさんの1年前の細胞は、神経細胞などごく一部を除き、すべて入れ替わっています。原子や分子レベルの話になれば、完璧にすべてが入れ替わっています。 ・1年前のあなたを形作っていた細胞、原子、分子は、今はまったく存在しないのです。常に古い細胞が死んで、新しい細胞が生まれながら、全体としては何も変化していないように見えるだけなのです。 ・これを“恒常性(ホメオスターシス)”が保たれていると言います。 ・この恒常性、あるいは健全性を保とうとする力を「自己治癒力」と呼んでいるのです。 【「未病」を直せば「病気」にならない】 ・「未病」とは、恒常性が崩れかけていて、そのままほうっておけば完全に崩れてしまうような危うい状態を指します。 ・「未病」を軸に、体の状態を要約すると、 状態1 恒常性が健全に保たれている状態・・・・・・健康 状態2 恒常性が崩れかけている状態・・・・・・未病 状態3 恒常性が崩れ、そのままでは元に戻らなくなっていて、悪化している状態・・・・・・病気 ・中国医療で「未病」と診断されるのは、検査で明らかな異常がなく、明らかな症状もないが、少し調子の悪い状態で、病気になる前段階の心身の微妙な変化を指します。この大事な変わり目を早急にとらえ、速やかに改善を図れば未然に発病を阻止することができるのです。 ・西洋医学では、未病を見過ごし、発病してはじめて治療に取り掛かります。すなわち、検査で異常が発見されるか、明らかな症状が出るようになるまでは病気とみなしません。 ・例えば、がんの場合、いったん発病してしまいますと、治療に多大なエネルギーを要するようになります。したがって、西洋医学のように発病するまで待っていて、発病したら対処しようという考えはあまり得策とは言えません。中医のように、未病の段階で、微細な異常を的確に察知し、自己治癒力を高めて早く対処しておこうという考えが重要です。 ・“待つ”のが西洋医学とすれば、重篤な病には悠長すぎる考えと言えます。それに対し、事前に対処する中医は“攻め”の考え方と言えるのではないでしょうか。 ・「中医」の考えは自己治癒力を高めることで、病気や「未病」を治そうというもので、非常に理にかなった考えです。 ・漢方とは日本の伝統医学を、「中医」とは中国の伝統医学を意味するのです。 ・最近中国では、西洋医学と中医のいいところをうまく組み合わせた手法を中医結合医療と呼び、がん治療など慢性疾患の治療の主流になってきています。西洋医学で初期治療を行ない、そのあとを中医を用いて養生していくという非常に賢明な考え方なのです。 ・がん治療の場合、西洋医学が主流の日本では、手術や抗がん剤治療などの初期治療のあとは、基本的に放置するのみです。生活指導ももちろん、中医をすすめることもありません。ただただ再発・転移を待つのみです。 そのためでしょうか、実際に半数の人が再発・転移で亡くなります。積極的に再発・転移を抑えていれば、結果は大きく異なるはずだと思うのですが、いまだに西洋医学一辺倒なのが、日本の悲しいがん医療の現状です。 ・薬をのむと最初のうちは容易に血糖値が下がりますので、みなさんは治ったのではないかと錯覚してしまいます。ついつい油断して、食生活の是正や運動習慣の取り入れなどの話は、完全に忘却のかなたにいってしまいます。つまれ薬さえのんでいれば、節制などくそ食らえという、大きな気もちにとらわれてしまうのです。 ・本来ならば運動や食習慣の是正、ストレス対処などをうまくやりこなすことで自己治癒力を高め、インスリンの分泌能、もしくはインスリンの感受性を改善させなければいけないところを、まったく逆のことをやっているわけです。いくら薬をのみ続けても、治るどころかどんどん悪くなるのが道理です。 【自己治癒力を高めよう】 ・自己治癒力とは恒常性を保つ力であって、自己修復脳力、元に戻る力と言ってもいいでしょう。 この自己治癒力は、人が潜在的に持っているすばらしい能力です。 ・医者は病気を治せないのです。 どんな名医でも無のなものは無理なのです。 医者ができることは、ただ、患者さんが治るきっかけを作るだけです。 適切なきっかけを作ってあげ、あとは患者さんの自己治癒力が病気を治すのです。したがって、適切なきっかけを作ることができるのが名医だということになるでしょう。 ・風邪をひいて、不要な解熱剤を用いたり、抗生物質をのんだりすると、自分で治す力が著名に妨げられます。そのあげくが、治りが遅くなったり、治りが悪くなったりしてしまうのです。医者が余計なことをしないほうが、風邪はずっと治りがいいのです。 ・一般的に、西洋医学(現代医学)は対症療法の医学・医療ととらえていい。今ある症状をすみやかに解消させることを主な目的とします。 ・西洋医学は救急救命、再建手術、そして画像診断などにおいてはすばらしい力を発揮しますし、他の手法の追随をゆるさないところです。 ・糖尿病で使用する約85%を占める治療薬は、いずれも糖尿病を根本的に治す薬ではありません。単に対症治療として血糖値を下げるだけで、インスリンの分泌を担う膵臓β細胞の機能を戻す働きはありません。 ・特にSU剤などは、無理やり膵臓β細胞をむち打ってインスリンを絞り出しているのですから、非常に手荒な治療法と言えなくもありません。そのせいか、いずれはβ細胞も疲弊してしまいついにはインスリンを分泌しなくなってしまいます。そうなるといよいよインスリンで治療をしなくてはならなくなってしまうのです。 ・がんでも同じことが言えます。がん組織そのものが免疫力を抑えますので、がん組織を手術や放射線で取り除くことは確かに意味のあることです。ただしこれは根本治療ではなくて、対症療法です。なぜなら、がん組織はがんの結果であって原因ではないからです。 ・したがって慢性疾患の場合には根本治療を優先させなくてはいけません。 考え方、栄養、血行、自律神経バランス・リズムの是正をまずは行ない、もしそれで不十分な場合には、やむを得ない選択肢として薬剤や手術、あるいは放射線などの攻撃的治療(侵襲的治療)を、期間を限定して用います。 ・糖尿病や高血圧の場合も、まずは食事をはじめとした生活習慣を是正することを奨め、多くはそれだけで大きく改善し、治癒します。仮にそれでも改善が見られない場合にはやむを得ず短期間に限定して、並行して薬剤の投与を行なう場合もあるかもしれません。薬剤の使用とはそれくらいのものなのです。 ・薬剤は基本的には異物です。薬剤は言い換えれば毒物ですので、ずっと処方しつづけるのは避けるべきです。どうしても必要な場合に、必要な期間に限り、用いるべきです。 ・現在の診療報酬制度では、生活習慣の指導や、見極める技量はほとんど点数査定されません。 ・現在の診療報酬システムでは、できるだけ薬を少なくして治癒へ導こうという医師の努力は報われることがなく、何も考えないでただただ毒をたくさん投与した医師が報われるという非常におかしなシステムなのです。しかも毒性のある薬の処方が多いほど、多く点数加算されるのです。 ・薬は自分で病気を治すというすばらしい力を、時には壊してしまうことがわかりました。 ・日本は少なくとも世界でダントツ薬が多い国であることに間違いありません。現に外国からは、日本人は異様に薬を好む民族だとみられています。 ・しかし、これほど膨大な数の薬剤の中で、自己治癒力を高めることが証明されている薬剤は、残念ながらいまだかつて聞いたことがありません。 ・薬剤は基本的には復元力のじゃまはすれども、貢献することがないということになります。 ・しかもどんな薬にも100%もれなく副作用は付いてきます。副作用のない薬はこの世に存在しません。 ・薬剤というのは「毒を以て毒を制する」という考えで用いるのが基本ですので、よほどメリットが見込まれなければ安易に用いるべきものではないはずです。薬剤を用いるのは他の選択がなくなった際の最終手段と言ってもいいと思います。 ・薬を用いる場合というのは、症状がどうしても我慢できなくて、リスクを勘案してみてもメリットが大きいと判断される場合、あるいはこの薬でないと命を救う可能性がないという場合の、2つに限られると思います。 ・「薬」と「検査」は、患者さんをつなぎとめておく最強のアイテムです。 ・薬処方もなく、定期的な検査の予定もなければ、おそく人はなかなか真面目に通院しないのが現実ではないでしょうか。 ・検査は顧客を囲い込むにとても有効な手段です。検査のため、結果を教えるためと、最低2回は来院が見込めます。 ・CTもMRIも薬剤と同じく、検査件数も機器の台数も世界中で断トツ1位です。それもけた外れの多さ(世界中の3分の1)なのです。 ・これほどまでにCTやMRIが日本で稼働していれば、確かに医療費も被曝も大きくなるはずです。 ・たとえば60歳も過ぎれば、CTやMRI検査で多くの方に、ごくごく微細な脳梗塞が見つかります。 ・そうして微細な脳梗塞は、実はほとんどが何の問題もなく、薬で治療する必要もありませんし、治療効果もありません。 ・薬を短期間に限ってのむ分にはそれほど心配する津要はありませんが、数カ月以上、あるいは年単位にわたって薬をのみ続ければ、確実に自己治癒力を損ないます。しかものみ続けるほどに薬への依存が強くなり、ついには薬からの離脱が不可能になってしまいます。 ・医者への依存心そのものが自分で治す力を低下させます。 ・依存が自立を凌駕すると、とたんに病気は治りにくくなってしまいます。 ・40歳を超えると、自己治癒力は急速に低下していきます。したがって、40歳を超えたら、自己治癒力を意識した考え方、生き方をするかどうかで、病気になるかどうか、ひいては健康寿命が大きく左右されます。 ・責任感の強い人、義務感の強い人、我慢強い人、遠慮深い人、周りを気にしすぎる人は、自身のストレス負荷を過小評価する傾向にあります。 また、ストレス負荷そのものについても、大きな誤解があります。それは「我慢できるストレス負荷は、それほど大したことはない」というとらえ方です。これはまったくの正反対です。 ・がん患者さんにおけるデータですが、いわゆる「いい人」は長生きできない傾向があります。 ・ストレス負荷ががん発症の大きな要因になっていると思われるケースがとても多いのが現状です。おそらく、生きる姿勢が受け身で、考え方が消極的だという側面が、かなり影響しているのではないかと推測されます。 ・あまり「NO」と言わない人は、実はストレス負荷が大きく、心身への負担は思ったよりも大きいのです。 ・衰えを感じる年になってからの我慢、忍耐、根性、がんばり、競争などはすべて身体には悪く作用します。また、義理、約束、責任感、義務なども同じく、自己治癒力を低下させます。 ・嫌な感覚を大切にすることの裏返しが、WANT(したい)の気持ちを大切にすることです。どうしてもMUST(ねばならない)の考えを重視する人が、がん患者さんには多いのです。 ・このMUSTの発想を、WANTの発想に変えることが、自己治癒力を高め、がんを治療に導くには必要な作業なのです。 ・嫌なことは極力避ける、そしてやりたいことを優先してやる、その姿勢に自分が慣れ、相手にも認めることが、自己治癒力を高める重要なポイントです。そうすれば、お互いにストレスがすくなくなり、お互いの自己治癒力が高まるのではないでしょう。 ・自己治癒力を高める、もう1つの大切な感覚が“いい加減さ”です。 ・「嫌(NO)」「したい(WANT)」「いい加減(SOSO)」、この3つのかんかくをうまく取り入れた方は、治りが明らかにいいようです。 ・がんになる方の性向を見てみますと、ほとんどが、何事も生真面目に取り組み、完璧にそして徹底的に、とことんやらないと気がすまないタイプの人たちです。つまりいい加減さを知らない人たちです。そのような姿勢は立派には違いありませんが、往々にしてがんになりやすく、そして治りにくいのです。 【自己治癒力を高める14の方法】 1.前かがみの姿勢をやめる 2.ときどきゆっくりと深呼吸 3.食にこだわる 4.便秘にはくれぐれも気をつけよう 5.ベースサプリメントを上手に用いる 6.気がついたら、ときどき爪モミ 7.ついでにツボ刺激! 8.温冷浴を習慣にしよう 9.血流をよくする「ふくらはぎマッサージ」 10.「 11.1日に6000歩、歩こう! 12.屋時間睡眠のすすめ 13.自己治癒力を高める『海外旅行」と『読書』 人がカルチャーショックを受け、それがその人の考え方や生き方に変容を与えるほどのものであればあるほど、リンパ球数は増加します。すなわち、自己治癒力が有意に高まります。 このような事実を踏まえて、がん患者さんにはもちろん、慢性疾患の方、あるいはストレス負荷の多い方には、読書や海外旅行をお勧めしています。 14.薬は控えめにする 【賢い医者の活用法】 ・“患者”の立場にまで、自分の身を ・みなさんが素直に“患者”になりきってしまいますと、それはまさに医者の思うツボです。 ・医者と患者の立場がはっきりしている限り、医者としての建前が前面に立ちはだかり、まさに医者主導の、建前通りの治療が展開されることになってしまいます。 ・相手の土俵で相撲を取るのはやはり不利です。 ・医者に接するときに、“患者”という立場はすこぶる不利になります。 ・理想は“友人”、そうでなくても最低限“クライアント”という立場を崩してはなりません。 ・そもそも、自分の命のあるじは自分自身なのですから、自分の命の責任は自分自身が持つべきです。 ・最終決定は自分でするべきだということです。なんでもかんでもすべて医者任せというのは、いただけないことです。 【みなさんが日本の医療を変える】 ・おいしい患者さんをそのままにしておきながら医療費を抑制しようとしても、かえって日本の医療がますます荒廃するばかりです。 ・それはどういうことかと言いますと、医療費を抑えようと、診療報酬を削減すればどうなるでしょうか? ・そうすると新たに病人をつくったりして、さらにおいしい患者さんを確保するように動くでしょう。そして、7確保したおいしい患者さんを目いっぱい活用する手立てを模索するはずです。 ・結局は医療費の無駄遣いを助長することになるだけでなく、本来、治してあげなければいけない患者さんたちが、ますますなおざりにされてしまいます。 ・先進国と比較してみても、日本の医療費は非常に少ないことは世界的にはよく知られている事実です。 ・医療費そのものは国の安心度を測るいい物差しだと思います。医療費にこそお金をかけなければ、どこにお金をかけるのでしょうか。不必要な公共事業、無能な公務員や政治家にお金をかける方が、よほど無駄というべきではないでしょうか。 ・ちなみに日本の公共事業費は、先進各国と比べても異常なほど巨額で、このことは世界的にも有名です。 ・政治の世界でもそうです。国会の動き、社保庁問題など、常識では起こりえないことが実際に起こるのは、「おいしい選挙民」が数多くいるからだと思います。衆愚政治とまでは言いませんが、それに近いのが今の日本の現状ではないでしょうか。うまい言葉につい乗せられて選んでしまう、ムードで選んでしまう、ちょっとした便宜に義理を感じてしまう、握手されたから選んでしまう、つき合いで選んでしまう、見た目だけで選んでしまう、有名だからというだけで選んでしまう・・・・・・など、でたらめな理由ででたらめな代議士を選んでいるから、でたらめな議会、政府が出来上がってしまうのです。そしてでたらめな政策によって、結局は無垢で「おいしい選挙民」は、自分の首をしめることになってしまうのです。 ・結局は、「おいしい選挙民」が数多くいる限り、社会は変わらないということになるかと思います。 ・医療費を削減する必要はないというのが私の意見ですが、「おいしい患者」がいなくなれば、少なくとも現在の33兆円の半分以上は不要になります。 ・自己治癒力で十分治る喜劇の病気に医者がかかわるのは、非常に無駄だと思います。まさに社会的共通資本の無駄遣いです。 ・喜劇の病気に対して医療費が無駄遣いされているために、本当に必要な医療費が ・治さなくてはいけない疾患にお金を使うべきであり、容易に治る疾患にお金を費やすこともないと思います。どうしても治したい疾患にお金を使うことが、生きたお金の使い方ではないでしょうか。 ・私たち一人ひとりが自立した考えを持つことが、今こそ必要です。まさに私たち一人ひとりの自立が、社会の動向を決定付けるキャスティング・ボートなのです。 ・私たち一人ひとりが「おいしい人」にならないという自覚から、社会が変わる風潮は芽生えると思います。もちろん医療、医学も例外ではないと思います。 |
77 |
15.07 |
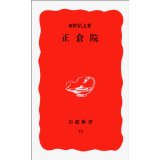 |
正倉院 |
東野治之 |
岩波新書 |
◎ |
・日本では唐の君主を皇帝と呼ばず「大唐皇」とし、それに賜うという形をとっているのに、中国ではこれを「朝貢」とみていた。中国には、文化の遅れた周辺の国や民族が、中国皇帝の徳や高い文化を慕って朝貢するという観念が、古くから形成されていたからである。 ・正倉院宝物中にある、いかにも精緻なつくりの品々は、やはり輸入品と考えなければならない。 ・正倉院宝物を見ると、天平の文化が、いかに多くの唐の文物を前提として成立していたかを示しているといえよう。 ・古代の日本は、長らく金銀を朝鮮半島からの輸入に仰いでおり、『日本書紀』にも、新羅は「金銀の国」(神功皇后紀)として描かれている。国内でも、対馬には銀山があったが、対馬からはじめて銀が出たのは、やっと六七四(天武天皇三)年のことであった。金に至っては、七四九(天平感宝元)年に、陸奥から砂金の献上されたのが、本格的な産出の最初である。この砂金が、当時完成間際だった東大寺大仏のメッキに使われたことは、あまりにも有名である。 ・「 ・六六三(天智天皇二)年に、日本は朝鮮に派兵して、百済とともに唐・新羅の連合軍と戦っている。この戦いは、日本側の大敗北に終わり、新羅との関係も一時途絶した。しかし朝鮮半島から、唐軍が引上げることを願った新羅は、日本と連携を深めようとし、六六九年以降、頻繁に朝貢の使を派遣してくるようになる。 ・光明皇后の『楽毅論』は、確かに力強い。しかし少なくとも皇族の間では、当時はまだ男子と女子の教養が分離されておらず、女性も男性と同じことを学んで身につけた。 ・平安時代ならば、考えられないことであろう。したがって、女性らしい字というものも、まだなかったと考えてよい。皇后の書と天皇の書は確かに違うが、皇后の書を後世の基準で男性的と評するのは、当たらないだろう。 ・正倉院宝物の大多数は、もともと東大寺の寺宝だった。正倉院宝物というと、聖武天皇の遺愛品とか光明皇后や孝謙天皇ゆかりの品が脚光を浴びるが、量的には、それらの占める割合は限られている。 ・宝物のすべてを皇室のものとしたのは、明治以後である。 ・正倉院宝物は「御物」であり、国宝でも重要文化財でもないのである。 |
76 |
15.07 |
 |
官邸から見た原発事故の真実 |
田坂広志 |
光文社新書 |
◎ |
・政府は、事故を起こした原発の冷温停止状態が達成できたということで、周辺住民と国民に安心してもらおうと考えています。原発の事故が収束に向かっているという前向きな情報を積極的に周辺住民や国民に伝え、できるかぎり不安を取り除き、安心してもらおうという意図そのものはも決して間違っていないのですが、そこに政界や財界、官界のリーダーの方々が陥る落し穴があります。 ・「冷温停止状態」を達成し、「最悪の事態」を脱しただけで、もう「事故は収束に向かっている」という空気が生まれてくるのは、リスク・マネジメントの原則から見ても、極めて危険なことなのです。 ・落し穴とは、「自己催眠」に陥ることです。 ・今回の福島原発事故の遠因となった「原発の絶対安全の神話」は、そうした「自己催眠」の心理から生まれてきたからです。 ・「根拠のない楽観的空気」が広がっていった時、起こる問題は「信頼」の喪失です。国民から政府への「信頼」が、決定的に失われること。それが最悪の問題です。なぜなら、「信頼」が無ければ、すべてが意味を失うからです。しばしば、原子力の問題を語るとき、「安全」と「安心」が重要だと語られますが、実は、原子力の問題において最も大切なのは、「信頼」なのです。 ・一九八六年に起こったチェルノブイリ原発事故の最大の教訓の一つは、「政府が国民からの信頼を失ったときは、最悪の状態になる」ということと言われていますが、まさに、日本は、その教訓に学ぶべきでしょう。 ・「安全な原発」を開発する努力は重要ですが、では、「絶対に安全な原発」が開発されれば、原子力の問題は解決するのか。 答えはノーです。 なぜなら、いかに「安全な原発」が開発されても、必ず、放射性廃棄物は発生します。従って、放射性廃棄物の「安全な最終処分方法」が確立されなければ、その原発もまた、「トイレ無きマンション」の状態となり、操業を続けることができなくなってしまうからです。 ・放射性廃棄物問題の本質は、究極、「高レベル放射性廃棄物の最終処分」の問題です。 なぜならば、放射性廃棄物のなかで、高レベル放射性廃棄物と呼ばれるものが、安全に最終処分することが最も困難な廃棄物だからです。 その理由も明確です。 高レベル放射性廃棄物は、極めて長期(十万年)にわたって人間環境から隔離し、その安全を確保しなければならないからです。 ・「十万年後の安全」を保証することは、極めて難しい。 ・この問題は、究極、「技術」(テクノロジー)の問題ではないのです。この問題は、究極、「社会的受容」(パブリック・アクセプタンス)の問題なのです。分かり易く言えば、「国民がそれを受け入れるか否か」「国民がそれを納得するか否か」という問題なのです。 ・高レベル放射性廃棄物の最終処分は、「技術」を超えた問題です。 ・第一の理由は、この問題には【未来予測の限界」という問題があるからです。 極端に言えば、「十問年後の安全」を科学と技術で実証することはできないからです。 どれほど精密な数学モデルを作って予測計算をしても、厳しい言い方をすれば、「その計算結果が正しいと、どうやって実証できるのか」という問いには答えようが無いのです。 ・第二の理由は、この問題は「世代間の倫理」の問題だからです。 最終処分するという行為は、明らかに「現在の世代」の責任を超え、「未来の世代」に負担とリスクを残すことを意味しています。これは、本質的に「世代間倫理」の問題であり、最後は「現在の世代」である国民の選択と意思決定の問題になってくるのです。その意味において、この問題は、明らかに「技術的問題」の領域を超えているのです。 ちなみに、三月十一日以前には、原子力エネルギーは、地球温暖化問題を解決するための切り札とまで言われていました。そして、この地球温暖化問題は、まさに「世代間倫理」の問題でもあるわけです。 ・実は、「信頼回復」ということは、「原発推進派」であっても「原発反対派」であっても、今後、共通に問われる根本的な問題なのです。 なぜなら、仮に明日、「原発反対派」の政権が成立し、原子力からの完全撤退を決め、現在国内にある五四基の原発のすべてを停止したとしても、それらの原発を完全に廃炉にするのに、少なくとも三〇年はかかるからです。そして、たとえ「原発反対派」の政権であったとしても、この原発の廃炉と放射性廃棄物の処分の問題は、必ず対処しなければならない課題であり、その課題の遂行のためには、やはりそれを遂行する政府に対する「国民からの信頼」が不可欠なのです。 ・信頼回復のために政府がすべきことは、「身を正すこと」と「先を読むこと」です。 すなわち、「原子力行政の徹底的な改革」を行うことと、「原発事故対策と原子力政策の長期的な展望」を国民に対して示すことです。 ・政府は、福島原発事故がこれから引き起こす諸問題の「全体像」を明らかにし、我々が、これからどのような問題に直面するのかの「見通し」を語らなければならないのです。 ・もし、それを行なわなければ、政府の姿勢は国民から見るならば、「問題が表ざたになったとき、その解決に取り組む」という「当面主義」の姿勢に見えてしまうからです。言葉を換えれば、「もぐら叩き」の姿勢に見えてしまうのです。 ・そして、そうした姿勢こそが、国民から政府への信頼を大きく損ねてしまうのです。 従って、政府は、福島原発事故の後の日本がこれから直面する深刻かつ困難な諸問題について、いち早く、その全体像を明らかにし、それらの諸問題についての国民の疑問に、率先して答える努力をしなければならないのです。 【政府が答えるべき【国民の七つの疑問】 第一の疑問 原子力発電所の安全性への疑問 ・実は、これまで世界で起こった原子力事故の大半が、「技術的要因」ではなく、「人的、組織的、制度的、文化的要因」によって起こっているのです。 ・原子力の「安全思想の落し穴」 それは「想定外」という落し穴です。「技術的」に、どれほど安全な対策を施していても、「人的、組織的、制度的、文化的」な要因から、技術者が「想定」していなかったことが起こるという落し穴です。 ・この「想定」という落し穴には、さらに恐ろしい「確率論」という落し穴があります。 例えば、技術者や専門家が、ある極めて危険な事態が起こることを「想像」する。しかし、直後に「いや、そうした事態は、極めて低い確率でしか起こらない」と判断し、その事態を安全設計においては「想定」しないという結論にしてしまうことです。 ・その背後には、さらに恐ろしい「経済性」という落し穴があります。 「そうした事態は、極めて低い確率でしか起こらない」という判断をする、そのプロセスに「経済性」への配慮が混入するという落し穴です。 「そうした危険な事態は起こるかもしれないが、起こる確率は極めて低い事態であり、まともに対策をするとかなりコストがかかるから、想定しないでもよい」という判断をしてしまうことです。 最悪の場合には、「そうした危険な事態は起こるかもしれないが、まともに対策をするとかなりコストがかかるから、起こる確率は極めて低い事態であるということを理由にして、想定しないようにしよう」という「経済優先主義」の判断が混入してしまうのです。 このことは極めて重要なことです。 なぜなら、今回の福島原発事故においては、まさに、その事故原因が、「想定外の津波」「想定外の電源喪失」であるという議論がなされているからです。 ・現在の行政機構の持つ問題 「一つの部署、一人の職員としては、責任を全うしている。しかし、行政全体と手は、極めて無責任な状態になっている」 ・こうした「行政機構の組織的無責任」という問題が生じる背景には、「縦割り行政の硬直化」の問題があります。 ・「この仕事は、自分の部署の仕事」[あの仕事は、あの部署の仕事」と縦割り行政を前提に硬直的に考える習慣が染みついているため、二つ以上の部署に関わる「横断的な仕事」が発生した場合、国民の立場に立ち、互いの仕事を調整することも、相手の領域に踏み込んで仕事をすることもできないという問題です。 ・原発の安全性が十分に確認され、国民がその安全性について十分に納得したならば、原発の再稼働はあってもよいと思っています。 ・また、「原発の再稼働をしないと、電力需給が逼迫する」「再稼働しないと、エネルギー・コストが上がって、経済にも影響が及ぶ」との懸念を語られる財界の方々の気持ちも、よく理解できるのです。 ・しかし、今回の原発事故の後、我々原発を推進してきた人間が、そして、この国の経済に責任を持つ人間が、一度、深く問うてみるべき大切な問いがあるのです。 ・その「経済優先の思想」こそが、今回の原発事故を引き起こしたのではないか? その問いです。 ・なぜなら、福島原発事故の後、財界のリーダーの方々が責任を負っているのは、もはや「国民の経済的豊かさ」だけではないからです。 「国民の生命と健康、そして安全と安心」 そのかけがえのないものに責任を負っているのです。 ・今回の原発事故で痛感したことは、行政組織には「危機対応型の人材」が極めて不足しているということです。例えば、緊急時における決断力という高度な能力を持った人材を育成していく必要があります。 ・組織的な問題としては、「過酷事故への対応マニュアル」が整備されていなかったことは、深刻な問題です。これを「想定外の事故」という一言で解決することなく、そうした問題を軽視してきた組織の「危機意識の欠如」についても、光を当てるべきでしょう。 ・さらに制度的な問題としては、現在の行政機構の「縦割り組織」の問題を解決するべきですが、この問題は、原子力行政だけでなく、日本の行政組織全体に共通の問題でもあります。 ・そして、文化的問題という意味では、かねて指摘されてきた「原子力村」の特殊な文化を根本から改めていく必要があるでしょう。この文化は、原子力産業と原子力行政が融合した形で形成されている文化であり、「推進」と「規制」の渾然一体の問題を始め、この事故を機に、大きな変革が求められているでしょう。 第二の疑問 使用済み核燃料の長期保管への疑問 ・冷却機能の長期喪失という最悪の状態が起こった場合、福島原発で「最も危険」であったものは、「原子炉」ではなく、「使用済み燃料プール」だったのです。具体的には、福島原発四号機の使用済み燃料プールが、最も危険な状態に陥る可能性があったのです。 ・使用済み燃料プールとは、状況によっては、「むき出しの炉心」になってしまうからです。 ・テロ対策ということについては、永く平和が続いた日本という国では「何も、そこまで考える必要はないのではないか」という空気があります。しかし、世界の原子力分野では、昔から「フィジカル・プロテクション」(物理的防御)という言葉があり、原子力発電所や原子力施設を外部攻撃から守るという対策は、ごく当然のものとして実行されているのです。そのことは、福島原発事故の後、欧米諸国の政府が国内の原発のテロ対策を強化したことに象徴されています。 ・「プールの貯蔵量」の問題、すなわち、全国の原発の使用済み燃料プールが、近い将来、満杯になってしまうという問題があります。 第三の疑問 放射性廃棄物の最終処分への疑問 ・廃棄物の「地中処分」も「地層処分」、実現するには大きな問題が二つあります。 一つは、「安全審査」の問題です。 もう一つは、「処分場選定」の問題です。 ・「放射性廃棄物の処分場を受け入れてくれる地域が見つからない」という問題です。そして、この問題は、一つの言葉とともに、昔から世界全体の原子力施設が、宿命的に背負っている問題でもあるのです。 ・「NIMBY」です。 すなわち、これは「Not in My Backyard」、「私の裏庭には捨てないでくれ」という社会心理を表現したものですが、放射性廃棄物の処分場を探すということは、究極、この問題にどう処するかという問題に他ならないのです。 第四の疑問 核燃料サイクルの実現性への疑問 第五の疑問 環境中放射能の長期的影響への疑問 第六の疑問 社会心理的な影響への疑問 第七の疑問 原子力発電コストへの疑問 ・原子力推進派の方も、原子力反対派の方も、しばしば、相手の語る政策や論理を極端に単純化して解釈し、批判するという傾向がありますが、こうした議論は生産的ではありません。 ・政治や政策というものは、「一か八かの賭け」ではありません。将来に起こるであろう状況を、「こうなるに違いない」と主観的に決めつけて政策を立案することや、「こうであったら良いのだが」と希望的観測に流されて政策を準備することは、厳に避けなければなりません。 ・総理と官邸に提言した「四つの挑戦」 今後のエネルギー政策を考えるとき、「原子力エネルギー」「自然エネルギー」「化石エネルギー」「省エネルギー」という「四つのエネルギー源」について、それぞれ、「四つの挑戦」をするべきという提言です。 ①原子力エネルギーの「安全性」への挑戦 ②自然エネルギーの「基幹性」への挑戦 現実は、現在の自然エネルギーの比率は一パーセント程度。この割合を度の程度まで高められるか。 ③化石エネルギーの「環境性」への挑戦 ④省エネルギーの「可能性」への挑戦 ・政府はこの「四つの挑戦」を進めていくことによって、エネルギー源についての「現実的な選択肢」を広げていかなければなりません。 ・まだ日本における民主主義は、本当の成熟の段階を迎えていないと思っています。そのことを象徴するのが、過去一〇年以上語られてきた「劇場型政治」や「観客型民主主義」という言葉です。これは、近年、我々国民一人ひとりの中に巣食ってきた危うい心理を、鋭く指摘している言葉です。 ・すなわち、誰か面白い「変革ドラマ」を見せてくれるリーダーはいないかと考え、人気のある政治家がいると、期待し、投票し、リーダーにする。しかし、まもなく、そのリーダーに飽き、幻滅し、また、次のリーダーを探す。 ・真の原因は、「リーダーの不在」ではなく、我々の中に巣食っている「自分以外の誰かが、この国を変えてくれる」という「依存の病」であり、この病こそを克服しなければならないのでしょう。 ・社会心理学者エーリッヒ・フロムが『自由からの逃走』の中で語った指摘 「第二次世界大戦前において、ファシズムが抬頭した本当の原因は、彼らの政治宣伝の巧みさにあったのではない。この時代の人々の心の中に『自由に伴う責任の重さから逃れたい』との無意識があり、その責任を肩代わりしてくれる強力なリーダーを求める社会心理が生まれた事こそが、本当の原因であった」 ・我々は、我々自身の中にある「誰か強力なリーダーが現れて、この国を変えてくれないか」という「英雄願望」を克服していかなければならないのでしょう。 ・民主主義とは、単に「選挙の時に投票に行く」ことではありません。真の民主主義とは、「国民一人ひとりが、この国の運営と変革に主体的に参加する」ことに他ならないのです。 |
75 |
15.07 |
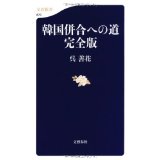 |
韓国併合への道 |
呉 善花 |
文春新書 |
☆ |
・李朝の大院君がとった政策は、あらためて徹底的な鎖国攘夷の貫徹であった。 ・日本ではすでに、「黒船ショック」を契機に「夷をもって夷を制す」、つまり西洋の文物を積極的にとり入れて産業を興し、国家の近代化を推進し、欧米列強に対抗し得るだけの力を早急につけるべきだとする考えが主流になりつつあった。 ・大院君がとった「衛生斥邪」 「衛生斥邪」とは「正を ・一八六八年(明治一)一二月一九日、日本の使節が朝鮮へ行き、明治新政府の樹立を通告するが、しかし大院君政権下の李朝は、日本使節が持参した国史をの受け取りを拒否した。 その理由は第一に、文面に「皇上」「奉勅」の文字が使われていたこと、第二に、署名・印章ともにこれまでのものと異なっていること、であった。 ・李朝からすれば「皇」は中国皇帝のみ許される称号であり、「勅」は中国皇帝の詔勅を意味した。朝鮮王は中国皇帝の臣下ではあるが、日本王の臣下ではない、このように傲慢かつ無礼な文書を受け取ることはできない、というのが李朝側の考えだった。 ・李朝の態度は変わらず、こうした情勢を受けて、日本政府内に「征韓論」が起こるのである。 ・征韓論とはいっても、朝鮮侵略それ自体が目的ではなく、真の狙いが中華主義に基づいた華夷秩序の破壊にあったことは明らかだろう。 ・<自らが世界の中心にあり、その中心から同心円状に遠ざかれば遠ざかるほど、野蛮で侵略的な者たちが これが中華主義である。 ・この世界観に基づいて、中華帝国を尊崇し朝貢などの礼式をもって臣下の意を表す周辺の夷族たちは藩属国とみなされ、それらについては中華帝国は大いに酬いて文化・道徳を与え、ときには軍事・経済などの援助も与える――こうして成立する世界秩序を ・建国以来、中華帝国に臣従する一藩属国だった李朝は、依然としてこうした古代的な世界秩序の内部での眠りから覚めようとはしなかったのである。こうした李朝にとって日本は、中華帝国への礼をつくさない周辺の野蛮なる夷族に過ぎなかった。 ・すでに日本は、欧米列強に対抗するためには、国家社会の近代化と富国強兵を早急に進める以外にない、との自覚をもっていた、そのときから日本にとって、あくまで華夷秩序を頑迷に守ろうとする隣国の李朝は、日本の安全を根本から揺るがしかねない存在となってしまったのである。 ・李朝もまた、日本のように早急に開国して近代化と富国強兵を推し進めなくては、またたくまに西欧列強の支配下におかれることになってしまうだろう。そうなれば隣国日本は窮地に立たされることになる。そのためには、武力をもってしても強引に李朝を開国させるべきだ、という考えが出て来たのである。それが明治初期の征韓論なのであって、前近代までの征韓論(古代神功皇后以来の支配権の復活)とは、まったくレベルの異なるものであることが強調されなくてはならない。 ・当時の日本にとって華夷秩序の破壊は、皇国史観やウルトラ・ナショナリズムとは別次元で、近代国家が当面する現実的な緊急課題だった。李朝が華夷秩序の従属下にある限り、日本が望むような近代化による国力増強は困難だと考えられたからである。そこで、李朝の華夷秩序からの離脱、つまり、朝鮮独立が、近代日本の外交上最重要事項として浮上することになったのである。 ・李朝側は、日本が「皇上」と書いたことは、日本の国主が単に王ではなく皇帝であることを示すもので、「奉勅」は皇帝の命を受けたことを意味する、と理解して傲慢とみなした。皇帝の称号を用いる者は、中華秩序に君臨する中国皇帝以外にはあるはずもなかったのである。 ・しかし日本側からすれば、それはなんら傲慢と言われる筋合いのものではなかった。皇帝とは臣従先をもたない独立した国主の称号として用いられ、臣従先をもつ者は単に王と称するのが世界の通例だったからである。 ・李朝の国主は中国皇帝に臣従する朝鮮王であるのに対して、日本の天皇はどこにも臣従先をもたない皇帝であった。この皇帝(エンペラー)と王(キング)の区別は世界的に行われていたものである。 ・日本の国書に対する李朝の受け取り拒否という「事件」の実態は、明らかに日朝両国の伝統的な世界観が、初めて正面から衝突した「歴史的事件」なのである。 ・李朝にとっては、中華帝国を盟主として周辺の諸国が臣従する朝貢体制こそが世界にほかならず、この世界の外にあるものはいまだ順化をとげない蔑視すべき夷族であった。李朝が日本の国書を傲慢として受け取りを拒絶したのは、夷族である日本が盟主である中国と並ぶ皇帝の格を標榜したからであり、それはこの世界秩序を正統とするものには許しがたいことだったのである。しかも日本は「仮洋夷」と化していたから、なおさらのことだった。 ・しかし日本は、李朝が従う世界秩序の内部にいるわけではなかった。また「攘夷」を乗り超えて明治維新をなしとげた日本からすれば、こうした李朝の態度は時代錯誤もはなはだしいもので、日本にとってもまた許しがたいものであった。 ・一八七六年(明治九)二月に日朝修好条約が締結されて開国となる。李朝は日本と清国へ使節・留学生・視察団などを活発に派遣しはじめる。 ・金弘集が持ち帰った『朝鮮策略』は、李朝にとっての脅威は南下政策をとるロシアであり、李朝のとるべき政策は「親中国、結日本、連米国」だと説いている。そのためには、欧米諸国と修好を結び、通商を行い、技術を導入し、産業と貿易の振興をはかり、富国強兵策を推し進めていくべきだと述べ、日清両国への留学生派遣、外国人教師の招聘などの必要性を主張している。 ・もはや専制君主を頂点にいただき、外戚である両班一族が政権を担当するという、李朝政治のあり方そのものが問われなくてはならなかった。このシステムはすでに、この国に目を覆うばかりの腐敗と堕落を蔓延させる装置以外何ものでもなかったのである。 ・欧米は日本とは比較にならないほどの文明を進展させていたが、諸国はロシアの強大な軍事力に大きな脅威を感じていた。ロシアの陸軍力・海軍力を前にしては、清国や日本はもはや敵ではないと誰もが感じただろう。そして、ロシアの南下は、時間の問題とみられた。 ・一八八四年当時の欧米列強は、東アジアではストレートに植民地化を目指すのではなく、通商の自由を通して経済的な利益を獲得しよう、という政策をとっていた。そうやって、東アジアをしだいに経済的な従属下に陥れていこうというのが、当時の欧米列強の戦略であった。だから彼らは、清国や日本と争ってまで李朝への支配を拡張しようとは考えず、適宜両国の動きを抑制したり、牽制したりすることにとどめていた。 ・ただ、英・米・独・仏などイギリスを中心とする列国と日本・清は、国際戦略上の利益で大きな一致点をもっていた。いうまでもなく、ツァーリズム・ロシアの南下政策への警戒であり、具体的には朝鮮半島のロシアからの防衛である。 そこで、清国と日本が朝鮮半島における対ロシア防波堤の役割を担い、それをイギリスを中心とする列国が支援する、という構図が自ずと形づくられていったのだ。 ・一八九〇年(明治二十三)、日本の初代総理大臣山形有朋は、第一回帝国議会の施政方針演説のなかで次のように述べた。 「国家独立自営の道に二途あり。第一に主権線を守護すること、第二には利益線を保護することである。其の主権線とは国の疆域を謂い、利益線とは其の主権線の安危に、密着関係ある区域を申したのである。」 日本にとっての利益線とはもちろん朝鮮半島を意味している。 ・清国は朝鮮への干渉強化と対日軍備拡充を同時並行的に推し進め、ロシアは一八九一年にシベリア鉄道建設に着手して、東アジアへの本格的な進出を固めようとしている。事態がこのまま推移すれば、遠からず日本の勢力が朝鮮半島から駆逐される日がやってくることはあきらかだった。 日本は表面的には清国と李朝を刺激しないようにしながら、しだいに対清戦争を準備して兵力増強へと向かっていった。 ・一八九四年(明治二七)五月、甲午農民武装蜂起(東学党の乱)が起こり、それをきっかけに、日清両国が朝鮮半島に出兵して日清戦争が勃発する。 ・東学は一八六〇年に ・日清戦争の最中の八月一七日、陸奥外相は日清戦争後の対朝鮮基本構想に四つの案を示して閣議にはかっている。 [甲案] 朝鮮の自主独立放任 [乙案] 日本による保護国化 [丙案] 日清両国による朝鮮の共同担保 [丁案] 永世中立国化 会議では結論を得られず、「乙案の大意を目的とする」にとどまっている。 ・日清戦争は、九月の平壌の戦い・黄海海戦で清国軍が敗退し、一一月に日本軍による旅順攻略、翌一八九五年(明治二八)二月に清国北洋艦隊の降伏と続いて、日本の勝利が決定的となる。 ・下関条約の第一条で、中国と朝鮮の宗属関係を破棄して朝鮮を「独立自主の国」とし、それに伴って旧来の「貢献典礼」を廃止すると宣言されたことは、まさしく朝鮮半島の歴史にとって一大画期をなす出来事であった。 ・一八九四年(明治二七)七月の甲午政変後の甲午改革は、朝鮮近代史の上できわめて大きな意義があった。甲午改革によって推進されたのは、政治・経済・社会全般にわたる制度の大幅な近代化であり、農民軍から提議されていた幣制改革にも応えうるものであった。基本的には金玉均らが甲午政変の最中に示した「甲申政綱」を引き継いだものであった。 ・主なものをあげると次のようになる。 ①王府と政府との分離 ②清国との宗属関係の廃止 ③近代的政治制度・官僚制度の導入と科挙制度の廃止 ④地方税制度の導入 ⑤租税の金納化・幣制改革をはじめとする財政改革 ⑥軍隊・警察制度の改革 ⑦近代的学校制度の導入 ⑧司法権の独立と近代的裁判制度の導入 ⑨諸身分の廃止と嫡子・庶子差別の撤廃 ⑩女子の再婚の自由と早婚の禁止 ・しかしながら、これらの改革推進には国王・閔妃・大院君各派の反発が強く、結局は実を結ぶことはなかった。 ・その第一の理由は、国王がそもそも法的に制限を受けない最高権威として伝統化されていたため、制度が改まっても政策決定は依然として国王と取り巻きの重臣貴族によって行われたことにあった。つまり改革は王府から政治権力を奪う形をとらないまま進められ、そのために改革の内容を有効に実現することができなかったのである。 ・とくに李朝側が党派対立に終始して改革推進能力を欠いていたことが大きかった。 ・また改革推進の過程で、日本は李朝政府各部門に政治顧問官を派遣し、日本の朝鮮保護国化の意図がしだいに鮮明となっていったため、朴泳孝ら旧改革派すら改革の遂行を阻害するようになり、朝鮮独自の改革案を意図するようになっていった。そのことも、改革を実現できなかった要因の一つだったろう。 ・もし挙国一致で改革が進められていたとしたら、まちがいなく王朝国家李朝は崩壊し、日本もロシアも容易に進出することのできない近代民族国家へと大きく変身を遂げていたはずである。 ・一九〇四年(明治三七)一月二一日、韓国は戦時局外中立を宣言したが、日本とロシアはもちろんのこと、韓国が恃みとするアメリカにまで無視されたため、国際的な効力を得るまでには至らなかった。 ・韓国の中立が多くの国に承認されなかったのは、それが戦時における中立の主張だったことによる。諸国とさまざまな利害関係にかかわる条約を結びながら、戦時となったら中立だというのでは、やはり大方の賛成を得ることはできなかったのである。 ・二月二三日に日韓議定書が調印された。その主な内容は次の三点である。 ①韓国は外国の侵略・皇帝の危機に対する日本の行動への便宜を与える。 ②日本は韓国の独立・領土保全を保証する。 ③韓国政府は日本の承認なしに第三国と自由に条約を締結することができない。 ・翌一九〇五年(明治三八)一月に旅順が陥落し、三月に奉天会戦、五月に日本海海戦と続き、日本が日露戦争の勝利を確定し、九月にアメリカの斡旋で日露講和条約(ポーツマス条約)が調印される。 ・ポーツマス条約の中で、日本はロシアから韓国における政治・軍事・経済上の特権を受け継ぐことを認められた。 ・その間、日本は、韓国保護国化についての列強諸国の承認取り付けに動いている。 ・日本はまず七月にアメリカとの間に桂・タフト協定を結ぶ。この協定は、アメリカがフィリピンを支配すること、日本が韓国を支配することの実質的な相互承認であった。 ・続いて八月、日英の間で日本の韓国に対する指導・監理・保護の権利が確認される(第二次日英同盟)。日本はその見返りとして、イギリスのインド支配への暗黙の承認を与えたといってよいだろう。 ・一一月、第二次日韓条約(乙巳保護条約)が結ばれる。これは日露のポーツマス条約に基づいての協約だった。 ①日本政府は日本の外務省を通じて韓国の外交関係とその事務を監督・指導し、外国在留の韓国人の利害を保護する。 ②韓国と外国との条約は日本政府の仲介を経なければならない。 ③日本政府の代表者として一名の統監を置き、統監は韓国の外交に関する事務を管理する。 こうして一二月、日本統監に伊藤博文が任命され、韓国総督府が設置されて韓国は完璧に日本の保護国となったのだ。 ・この時期の韓国の政治・社会運動は、義兵闘争と愛国啓蒙運動だけではなかった。それらとは正反対に、積極的に日本との同盟関係を強化し、さらには日韓合邦を推進していこうとする大衆運動が存在した。 ・ ・グレゴリー・ヘンダーソンは、著書『朝鮮の政治社会』で、一進会の日韓合邦運動について次のように述べている。 「日本および朝鮮内部におけるその同盟者が、一九〇五年から一九一〇年に至る期間に、日本の朝鮮併合に対する大衆の政治的支持を獲得することに成功した方法は、その方法のよしあしは別としても、列国の政治的大衆動員の歴史の中でも、もっとも興味あるものの一つであったといえる。事実それは、政治史上、自分の民族に対して行なわれた反民族主義的大衆運動として、今までになかった唯一の例である。朝鮮の民族主義者たちがこれを快しとしないことは無理からぬことで、だれもそれを口にしない」 ・日清戦争を経て日露が決定的に対立するまでに、政府、官僚、東学、独立クラブなどは、いずれも、韓国が自立・独立国家への道を歩むための指導原理を指し示すことができなかった。さらには、彼らがそれぞれの立場や枠を超えて大同団結し、挙国一致の民族的な結果を目指そうとする、連帯運動への動きも起きることがなかった。 ・開国以来、およそ李朝―韓国で改革を志した者たちの主流は、基本的に日本との提携を軸に発送する者たちだった、ということである。 ・一八八四年から一九〇四年に至る外国勢力によるシーソーゲームのなかで、改革を志す朝鮮人は、清朝中国はもっとも反動的であり、帝政ロシアの反動ぶりも似たりよったりで、米国は韓国に無関心で、韓国政府は無能であると感じていた。ひとり日本のみが、積極的に明治の改革を推進しており、彼らにおおいに訴えるところがあった。 ・この時代の大部分の改革者は日本をあてにしたのであり、日本もまた全般的に彼らを支援したのであった。 ・こうした見方は、韓国人史家からはもちろんのこと、日本人史家からも表立って主張されることは少ない。しかしながらヘンダーソンの見方は、当時の客観情勢からいっても、きわめて説得力をもつものと言えるだろう。 ・日本は、上からの近代化によって社会にもたらされる混乱を自力で乗り越えることができた。しかしだれが考えても、当時の韓国では、近代化がもたらすであろう社会的な混乱を、自力で乗り越えることなどできるはずもなかった。 ・当時の世界情勢下では、韓国が近代化をなしとげる以外に独立への道はなかった。にもかかわらず、韓国が独自に上からの行政改革をもって近代化をなしとげ、かつ自力をもって社会秩序を維持していくことはほとんど不可能だった。当時の韓国はそういう状況下におかれていたのである。 ・当時の韓国はいったん外国の保護下に入り、そこで近代化を進めて力をつけ、独立へと向かうしか現実的にはとるべき道はなかったのである。 【大アジア主義と日韓合邦論】 ・中国にしろ韓国にしろ、改革派はみな外国の力をあてにしたのである。いや、あてにするしかなかったのである。欧米・日本・ロシアなどの列強の勢力バランスとどう関係すればよいか、それを考え、そこを巧みに乗り切っていくところにしか民族の自立・独立への可能性はなく、そこへ向けた努力なしには他国の植民地と化すしかなかった。 ・そこから、アジア諸国の同盟を考える大アジア主義の思想が生まれる。しかしながら、それは日中韓の国家意志として表明されたものではなく、あくまで民意・民情を恃むものであった。 ・それはとくに、日本の言論界やジャーナリズムに顕著に現れていたと言えるだろう。 日本のジャーナリズムや民間知識人たちの多くが、終始金玉均を擁護し、彼を排斥しようとする日本政府を非難し続けたことにも、そうした民意・民情はよくあらわされていたと思う。 ・金玉均が描いた「日中朝の連帯をもって西欧列強の侵出に対抗する」という理想は、明らかに樽井藤吉の『大東合邦論』に重なるものであり、吏容九の日韓合邦もまたその理想に連なる発想だったはずである。 ・李容九らが当面の独立よりも合邦を目指したのは、第一に排日による民族の自律性確保はすでに不可能であり、朝鮮民族の命運は中国民族や日本民族の命運と、さらには諸民族の命運と軌を一にするものと理解されていたからである。 ・日本の保護国のままでは、韓国の側には反日・抗日を軸にした民族自立の動きしか生み出すことはできない。しかし日本の保護を失えば、民族の自律は一層脅かされることになる。 ・西欧列強の力をあてにする者たちもいたが、たとえそれで日本を排除できたとしても、西欧諸国がこぞって韓国の中立維持のために力を尽くす理由はどこにもなかった。かえって中国のように、列強諸国による利権切り取り合戦がさらにすさまじく展開される可能性のほうが大きかった。 ・いずれにしても、当時の状況でもし韓国が独立できたとしても、再び王室派、守旧派、親露派、親日派、親米派などの内部抗争が再開されることは目に見えていた。挙国一致体制を生み出す条件がまったく欠けていたからである。 ・日韓合邦論は、以上述べたような理念と実際的な国内・国際情勢から出てきたものである。 ・民族の自立を保ちながら、なおかつ国家的な権力をもってその自立を保障していこうとする限り、互いに自立した民族がその自立を維持しつつ一つの国家を形成するという合邦が、唯一描くことのできる構想ではなかっただろうか。 【親日派韓国人を売国奴とする韓国】 ・自らの側に外国による統治を招来させてしまった要因を探り当て、そこに深い反省を寄せて現在から未来への展望をもとうとする気持が、解放直後の韓国知識人の間に生まれることもなく、いまなお欠落したままなのである。 ・李朝――韓国の積極的な改革を推進しようとしなかった政治指導者たちは、一貫して日本の統治下に入らざるを得ない道を自ら大きく開いていったのである。彼らは国内の自主独立の動きを自ら摘み取り、独自に独立国家への道を切り開こうとする理念もなければ指導力もなかった。 ・韓国独立への道が開かれる可能性は、金玉均らによる甲申政変の時点と、彼らを引き継いだ開化派の残党が甲午改革を自主的・積極的に推進していこうとした時点にあった。 ・李朝はいずれの場合も自らの手をもって、それらの国内改革の動きを潰したのである。前者は清国を恃みとし、後者はロシアを恃みとして行われたものである。 ・以後の李朝――韓国に独立への可能性はまったくなかった。そこで登場したのが、李容九率いる一進会だった。彼らは国家への絶望から出発し、民族の尊厳の確保を目指して日韓合邦運動に挺身した。その結果は日本による韓国の併合だった。 ・しかしながら、少なくとも民族の尊厳の確保に賭けて大アジア主義を掲げ、国内で最大限の努力を傾けた李容九らを売国奴と決めつけ、国内では表だった活動をすることなく外国で抗日活動を展開した安昌浩や李承晩らを愛国者・抗日の闘士と高く評価するといったバランスシートは、まったく不当なものと思える。 ・いまだ併合をもたらした自らの側の要因への徹底的な解明への動きがはじまってはいない。それは韓国がいまなお、「李朝の亡霊の呪縛」から完全に脱することができていないことを物語っている。 ・韓国が自らの側の問題解明に着手し、さらに反日思想を乗り越え、小中華主義の残存を切り捨てたうえで、日本統治時代についての徹底的な分析に着手したとき、韓国にようやく「李朝の亡霊の呪縛」から脱したといえる状況が生まれるだろう。 ・日本はそうした方向へと韓国が歩むことを期待すべきであり、その方向にしか正しい意味での日韓の和解はないことを知るべきだろう。 【農民の疲弊から遊離した知識人たちの責任】 ・李朝は次のような政治的伝統をもっていた。 ①世界に類例をみない硬直した文治官僚国家体制。 ②中華主義に基づく華夷秩序の世界観。 ③大国に頼ろうとする事大主義。 ④儒教国家を保守する衛正斥邪の思想。 ・こうした李朝正統の流れに対して、唯一改革への可能性を示し続けたのが実学の流れだった。実学の流れは金玉均らの急進改革派と金弘集らの穏健開化派の流れに分かれ、両派壊滅以後は、東学の流れと愛国啓蒙運動の流れに命脈を保った。 それらに対して李朝正統は、儒生らの衛星斥邪派が義兵の中心勢力として最後まで力をもち続けた。 併合を前にして、この三つの流れはついに大同団結することがなかった。 ・それは李朝の統一が、「横のつながりを失った無数の極小集団がそれぞれ自己の利益をめざし、中心へ向かって猛然と突き進む力学の統一性」によって維持されていた伝統と、けっして無縁ではなかった。 ・またヘンダーソンが言ったように、「すべての非正統的活動を執拗に排除しようとする嫉妬深い中央権威主義」の伝統とも無縁ではなかった。 ・李朝――韓国は最初から最後まで、この二つの伝統を乗り越えることができなかった。上からの改革の芽を自ら摘み取り、なおかつ下からの改革の条件である挙国一致体制を生み出すことができなかった。 ・韓国併合ではなく韓国独立への道を自らの手で開くことができなかったのは、何よりもそのためである。 ・下からの改革を巻き起こす第一の条件は、当時の大衆である農民の幅広い団結を生み出すところにあったのは言うまでもない。この条件もまた、ついに達成することはできなかった。 ・守旧派から改革派に至るまで、農民たちの命を賭けた蜂起を全国的に組織することができない知識人たちがいた。 ・抗日闘争をした、独立運動をしたということで愛国者とされてきた人々については、そうした意味からの責任が強く問われなくてはならないだろう。なぜなら、それもまた日本に併合される事態を招いた李朝――韓国側の大きな要因だからである。 【日韓併合関連年表】 ・一八九八(明治31) 西・ローゼン協定。日露両国は韓国の独立を認め、直接の内政干渉を行なわないこと、軍事教官・財政顧問を送るときは両国で事前に協議すること、ロシアは朝鮮における日本の商工業の活動を認め、その発展を阻害しないこと。この協定によってロシアは日本の朝鮮における経済発展の自由を認めたが、一方で日本がロシアの旅順・大連租借を黙認する結果となった。 ・一九〇三(明治36) 日露協商会議のさい、日本は満州からの撤兵をロシアに要求。ロシアは拒否。ロシアは日本に対して、北緯三九度線で韓国を分割しそれぞれの勢力下に置くことを提案。日本は拒否。ロシア、満州を占領。 ・一九〇四(明治37) 二月、日露国交断絶。日本が旅順港を攻撃し日露戦争勃発。韓国は中立宣言をするが、日本軍が仁川に上陸しソウルへ入城、日本に協力するよう要求し日韓議定書調印(攻守同盟の性格をもつ。韓国は侵略・内乱・皇帝の危機に対する日本の行動への便宜を与える。韓国政府は日本の承認なしに第三国と自由に条約を締結することができない)。事実上、日本の保護国となる。 八月、第一次日韓条約(日本政府の推薦する日本人一名を財政顧問とし顧問の意見に従って財政事務を施行する。日本政府の推薦する西洋人一名を外交顧問とし顧問の意見に従って外務事務を施行する)。 ・一九〇五(明治38) 日本海海戦。日本、日露戦争に勝利。日本、樺太占領。 日米の間で、アメリカがフィリピンを支配すること、日本が韓国を支配することの相互承認が行われた(桂・タフト協定)。日英の間で日本の韓国に対する指導・監理・保護の権利が承認された(第二次日英同盟)。見返りとしてイギリスはインドへの支配権確保を狙う。 九月、アメリカの斡旋で日露間にポーツマス条約が締結。そのなかで、日本はロシアから韓国における政治・軍事・経済上の特権を認められた。 一一月、第二次日韓協約(乙巳保護条約)。日露のポーツマス条約に基づいての協約。日本政府は日本の外務省を通じて韓国の外交関係とその事務を監督・指導し、外国在留の韓国人の利害を保護する。韓国と外国との条約は日本政府の仲介を経なければならない。日本政府の代表者として一名の統監を置く。統監は韓国の外交に関する事務を管理する。一二月、日本統監に伊藤博文を任命。韓国統監府を設置。 ・一九一〇(明治43) 八月二二日、日韓併合条約調印。李完用内閣の議決。八月二九日、併合発布。韓国皇帝は韓国王となり大韓帝国の称号が再び朝鮮となる。一〇月、朝鮮総督府設置。寺内正毅総督に就任。 |
| 」 74 |
15.07 |
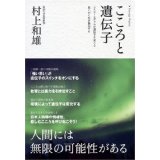 |
こころと遺伝子 |
村上和雄 |
実業之日本社 |
☆ |
・こころの持ち方は、遺伝子の在り方に大きく影響を与えているはずです。 人は、「思い」によってその気分や体調、または成績や技術が大きく変わります。楽しい、うれしい、わくわくする、感動する、こうしたポジティブなこころの動きが、いい遺伝子を目覚めさせるスイッチを入れる。 ・この数年、人体をコントロールしているのは、人体の外からの刺激である「環境」によって大きく左右される、という考え方が台頭してきました。 ・遺伝子情報そのものは、自ら書き換えられたりするのではなく、外からの刺激によって、必要な遺伝子のスイッチをオンにしたり、不必要な遺伝子をオフにしたりして、生体がコントロールされているという考え方です。 ・こうした考え方は、「エピジェネティクス」と呼ばれ、ヒトゲノム解読が完了したあとの、もっとも新しい理論であり、遺伝学の革命と考えられています。 ・コントロールするものとは、これまでの化学的薬品や特定の食べ物を指さず、「環境」と呼んでいるのには、わけがあります。 それは必ずしも、物質分子シグナルだけではなく、エナジーシグナルのすべてのものが、遺伝子をオンにするものに入るからです。磁気や光、周波数、強い思いや、情熱、愛、歓喜、笑い、ことばなどがすべて含まれるのです。 【いのちに敬意を払い、謙虚に生きる】 ◎これでいいのか日本の教育 ・魂を目覚めさせることこそ、真の教育である。 ・教育については、江戸時代の寺子屋が、そのルーツでありました。当時の日本には、二七〇〇ヵ所の寺子屋があり、広く庶民にまで世界最高水準の教育が行われていました。 寺子屋発祥の原点には、「この国を何とかしなくては」という問題意識があり、そう考える有志たちが、国のためにその場所を開いていったのです。 ・しかし時代が移るにつれ、教育は個人の出世のため、将来の経済的生活のアドバンテージのためといった、狭小な概念に変わっていってしまいました。個の利己的な目的が、公を救うことはできません。 ・日本においても、今日に至るまで、あらゆる時代において、そういう「憂国」の志を持った指導者は存在しました。 ・エデュケーション(教育)の語源は、人の能力を引き出すことです。誰かが、一方的に教え込むことではありません。 ・やがて必ず世界の教育は、ただ目の前の点数で評価するような、粗末なことはやらないようなるだろうと思います。 ・人という存在の内容がこころであり、こころが幼い頃、育てられるとすれば、とりわけ、義務教育が大切であるということはいうまでもない。教える人は、大自然の子である人の子に対して謙虚でなければならない。 ・こころの教育をないがしろにする能力テストはやめて欲しい。 ◎ヒトの差は、遺伝子レベルではわずか〇・五% ・私たちは、一人ひとりが無事にこの世に誕生したこと、そして元気に生きていること、そのことだけで、人というのは、まさに尊敬に値することであり偉大な奇跡なのでありま。 その奇跡的な出来事に比べれば、学校の成績が二十点の人と一〇〇点の人を比べて、できる人、できない人、を分けることがそもそもナンセンスであると思います。 ・天才と凡人の違いは、全遺伝情報(ゲノム)のレベルでは、わずか〇・五%でしかありせん。 ・とくに、就学前の子どもや小学生には、無限の可能性が詰まっているのです。それなのに、その可能性を狭めているのは、大人の都合だけでつけてしまう、点数で評価する制度であり、学校の規則、社会の制度そのものではないかと改めて思うのです。 ・社会も政治も官僚も、人間を支配、管理するためにあるわけではありません。 ・人はその国で誰もが快適に住まう環境を得る権利を持っています。とくに子供たちには、のびのびと大きく羽ばたくことのできる時間や場所、環境こそが、最も大事なことです。 ・立派で優秀であるかもしれませんが、昔から誰が決めたか分からないたった一つの教科書を同じように与えられ、それを覚え込まされて、その通りに答えなくては正しくないと、バツにされるのはおかしなことなのです。 ◎人生には失敗もバツもない ・この貴重な生命を授かっている私たちの人生には、失敗もバツもありません。 ・日本の教育がいかに鈍感であるかの一つの例を言いますと、数十年前から、ケンブリッジやオックスフォード大学の入学試験における合否のキーポイントは、「その人がいかに多くのことを知っているか?」ではな、「その人が、いかに多くのことを考えられるか?」にあります。 教授の話をそのまま認めて同意する人よりも、自分はこう考える、という意見をきちんと話すことのできる学生のほうを、優れていると考えているのです。 先生に反対意見を言う人がもちろん悪い学生ではなく、先生の言うことをすんなり聞く人をいい学生とも常識的に決めていなかったのです。 ・社会が必要とするのは、知識の量ではなく知恵なのです。 ・無限であるはずの人の可能性は、イージーな点数制からは、引き出されるはずがありません。子供たちの能力を三六〇度の方向へ、自由に飛んでいけるように仕向けてやるのが指導者ではないでしょうか? ・それでも私たち人類は、月に立つことができ、宇宙を自由に行き来するような技術を積み上げることができました。それは、月に行きたいと強く願い続けた、はみ出した人がいたからです。 決して、学校の成績が優秀な人だけではなかったのです。 ・疑問を抱かない限り、新しいことは生まれていきません。問題を自分で見つけ、その方向に自分で道をつけていく能力こそ磨かれなければなりません。 ・一つの興味のためには他の勉強への時間を捨ててしまうことになるかもしれません。しかしこの社会は、興味のある世界に強い思いを持ち、それを貫いた人々によって、新しい創造の芽が形作られ、開かれてきました。 ・それぞれがそれぞれの興味のあることにいて、夢中になれればいいのです。 ・オール5は必要ないのです。たった一つであれ、人それぞれの個性を生かしてこそ人間です。だからこそ、人間に生まれてよかったと思えるのではないでしょうか? ・人は強い思いさえあれば、どんなことをも成し遂げることができるのです。点数評価性を廃棄し、のびのびと勉強ができる、自由に夢を見させる余裕を与えることこそ、社会制度としての教育のあり方ではないでしょうか。 ◎子供の喜びを育もう ・とくに親には、気がついて欲しいのです。 どんなことを考える子どもであっても、どんな問題を起こし、失敗を繰り返す子供であっても、誰もが敬うべき無限の可能性を秘めた宝物であるという見方を、根本から持って接して欲しいと思うのです。それが道を探しながら育っていく子供に対する真の愛情であり、愛こそが子供のこころを、大きく温かく育む原点になるのです。 ・子どもたちが一個の無限の可能性を持った存在として、大きな夢を持てること、大きな想像をめぐらすことができること、個人のやりたいことを引き出し、その喜びを育んでることこそ、大きな意味で真の国を作る教育だと思います。 ・子どもは活きているだけで、素晴らしいのです。 ・誰もが同じように無限の可能性を持つまっさらな赤ちゃんとして誕生するというのに、元気な子とそうでない子に分れてしまうのは、思いを素直に表して、のびのび生きられるかどうかの環境によります。つねに、目の前に、夢中になってやりたいことを持っているかどうかにかかってきます。たった今からでも遅くはありません。いくつになっても今が大事なのです。 ・こうなりたい、ああしたいと強く思う願うことは、本来持っている遺伝子の中から、その可能性を引っ張り出すエネルギーになります。 それはそのまま人間の生きる力になります。 自らが自らの道を作ることになります。 ・人間の体を構成している細胞には、外からのシグナルを受けるレセプターと呼ばれるものがあります。このレセプターを活性化することが、遺伝子情報をオンにすることであると、世界的に有名なアメリカの細胞生物学者であるブルース・リプトンは言っています。 人間には、このレセプターをオンにするものが絶えず必要とされています。レセプターを活性化するものは、化学的薬品や食品だけではなく、思いや愛、音楽、ことばなどといった非物質的なエナジーシグナルが、それ以上に大きな影響を与えていることが分かりました。 ・限界への挑戦とは、かつてなかった記録を、「人間の思い」が超えてしまうことです。「人間の思い」が、眠っている遺伝子のスイッチをオンにして、新しい力を得るということがいえるのです。 ・子供にやる気を起こさせることが真の教育です。 ・人にはすべて、「脳力」という無限の可能性があります。この無限の可能性を阻んでいるのは、あれをしてはいけない、こうしなければいけないといった、社会や学校や家庭の規則です。 ・こうしなければならないと教え込むのは、本当は教育ではありません。この本を覚えなければならない、何点をとらなければならない、教えたとおりに記憶しなければならないなどは、その子の自発的な好奇心が、弾けていく機会を喪失させてしまうことになります。 ・教育(エデュケーション)とは、教え込むことではなく、その能力を引き出してやることです。 ・私たちの細胞は、一日に二%も入れ替わります。二%というと少ないように思えますが、一日に約一兆個もの細胞です。一年で私たちのからだは、ほぼまったく新しい細胞を持った生きものに代わります。 ・しかしながら、私たちの顔かたち、性格は、見た目はまったく変わりません。それは、細胞が持つ複製昨日によるものですが、私たちのこころは刻々、環境によって変わることが出来ます。 ・ウィスコンシン大学のショーン・キャロル氏曰く、 「形態の進化を引き起こす最大の推進力は、遺伝子の基本的設計図の変異ではなく、オンとオフをつかさどる遺伝子スイッチの変化である」 ・環境による影響、たとえば栄養分やストレスなどの感情が、DNAの基本設計図(塩基配列)に変異を加えることなく、DNAの働きを変えることができると分かったのです。 ◎私たちのからだは小宇宙である ・一つの細胞の核の中にあるDNA(遺伝子)は、二重に絡み合った、超微小なテープからできています。それをまっすぐにのばして実測したとしたら、約一・八メートルにもおよぶ長さであろうといわれています。ということは、一人の人間が約六十兆個の細胞を持っていますから、そのDNAのテープの総延長は、ざっと一千億キロメートル。 ・人間の成人の血管をつなげてみると、これもまた、十万キロメートル。 ・一個の動物細胞の中には、数万種類のたんぱく質が、約八〇億個も存在しているといわれています。しかも、こうしている間も、壊しては作り、作っては壊すことが繰り返されています。活発に働く細胞は、一秒間になんと数万個のたんぱく質が作られ入れ替わります。 ・たんぱく質とは、アミノ酸がつながったものです。一個のたんぱく質は、平均すると、数百個のアミノ酸からできていますが、このつながり方が遺伝子の中に書き込まれているのです。 ・遺伝子が、たんぱく質の設計図であるといわれるゆえんです。この働き、この動きを絶えず管理するために細胞は生きています。 ・私たちのからだはなんと、一日に約二%の細胞が入れ替わっていると言われています。神経細胞だけは変わらないといわれていますが、一年もすると、私たちのからだはまったく違う細胞からなる別の人のようになります。 しかし、顔や姿など、表面的にはなんら変わらないし、性格も感情も変化することはありません。これは入れ替わる細胞が、以前と同様に働いているからです。 ・DNAの二重らせん構造こそ、この遺伝子の複製機能をつかさどる構造だったのです。人の生命とは、絶えず自分の細胞を複製されることでいのちをリレーしているのです。 ・細胞の核の中にある一つのゲノムの中には、約三二億個の化学の文字(塩基)が記されています。 ・成人のからだには、その膨大な量の情報を持つ細胞が約六十兆個もあり、整然と生き続けています。 生命が誕生するということは、この文字の書き込みが、すごい勢いで十カ月の間にコピーされて完成するということになります。また細胞が入れ替わるということは、コピー機能によって、新しい細胞に転写され続けているということです。 ・DNAの二重の構造は、それぞれ陽と陰、凹凸のように、合わせるとぴったり合致するように一対の構造を成していて、この構造が、複製を進めていることが分かりました。 ・テープそのものは、糖とリン酸から成っていますが、細胞の核の中にある遺伝子の本体が、DNAという物質です。 ・外からのよからぬ侵入者に対して、抗体の生産を促して、抗原を排除する働きを「免疫」といいます。 ・私たちのからだには、二〇〇〇万種類もの抗体を、巧妙、かつ厳密に生産できる機能が、おのずと備わっています。日常的に病原体の生体への侵入を防いでくれます。 ・人類が本来持っているこの免疫の仕組みを大切にすることなく、人工的な操作による、ワクチンにだけ頼るようになると、人間に本来備わっている免疫力が退化していかないでしょうか? ・まずは一人ひとりが自分のからだを敬い、自分のからだの営みに感謝し、きちんと働いてもらう生き方を意識すること、考えることが一番大事なことです。 ・抗体はたんぱく質からできていますから、その抗体生産のたんぱく質に関わる暗号は、最新遺伝子工学によって、すぐに解読されました。 しかし、全たんぱく質生産にかかわる遺伝子は、全体で二万数千個しかなかったのです。二〇〇〇万個のウイルスに対応するとなると、どう考えても遺伝子の数が足りないではありませんか? ・これが免疫上大きな謎だったのですが、この謎が、利根川進博士らによって、解かれています。つまり、人のからだの中で、抗体を作る遺伝情報は、部品に分けて貯えられていたのです。抗原の侵入に対して、その部品が次々に巧妙に組み立てられて働くことになります。その組み合わせから、二〇〇〇万種類に対応していることが判明したのです。 ・この本来持っている人間のからだの機能を、まずはきちんと知ること、そして敬うことが必要です。日頃から免疫力を高めること、体力をつけること、気分を快適にしておくことが、最も自分自身を拝する上で大事なことになります。 ・私たちは、「病気になったら医者が治してくれる」と考えるよりも、自分の治癒力を高めるための日常的な「心の在りよう」が何よりも重要であることが分かると思います。自分のからだが必要とする遺伝子情報をいつでもオンにしてやるような、積極的でポジティブな生き方こそ大切なことです。 ・医学の祖、ヒポクラテス曰く、 「病は自然が治し、神は傷を癒し、我はただ包帯をするのみ。人間には偉大なる自然治癒力があり、その力を引き出すのが治療の鍵である」 ・私たちは、何もかも医者に頼る前に、私たちが本来持っている治癒力(免疫力)を、普段からもっといたわり、愛し、信頼し、大切にすることが大事なのです。 【日本人のすごい力を信じよう】 ・人は、「帰るところがあるから」旅に出るのです。旅や冒険は、帰る喜びがあるから出かけていくのです。その国に必要とされて、たとえ、その地に根を生やしたとしても、いつの場合も精神的に帰るところは必要です。 世界のどんな人にとっても、それは、自分が生まれたところ、つまり生まれた国であります。またはふるさとであり、両親であります。愛国心ということばが、戦争や軍国主義を連想させるということだけで国歌斉唱を反対する人がいるのは、日本だけではないでしょうか。 ・自分を、人を、自然を、宇宙の摂理を、そして、自分が大切にしているものを、敬うことこそすべての始まりである。 ・「自分が ・日本人も、日本国に誇りを持って、もっと敬意を払い、大事にする習慣を子供の頃からつけるべきだと考えます。 ・真の魂は人から人に、伝達していきます。 日本人なら誰もが、こころと一緒に、深いところに大和魂を持って生きているように思います。 ・吉田松陰の言う大和魂とは、「義や理性、魂の声、天の声に従うやむにやまれぬ強大なこころ」をいい、不正があれば断じて許さず、不義が起これば、断固として戦うことをいいます。 ・松陰語録にはある、「永遠に残る、よき心と魂を持て」……一八五八年、ここから始まった、日本人としての素晴らしい教育の意味を、もう少し考え直してみようではありませんか。 ・西暦五世紀頃の中国の 「上医は国を医し、中医は人を医し、下医は病を医す」 これは志の高い優れた医師ほど、国の悩みや戦乱などを救い、国のことを考えていることをいっています。 ・どんな環境でも、いい国を作ろうと、同時代の人々がこころを一つにすることが大事なことだと思います。 ・人はたとえ平凡であれ、人間として生きることを意識すること、私たちの住みよい環境を作る、いい国作りにコミットする視点をつねに忘れないことが、とても大事なことであると思います。 ・自分たちの国を考えるという一つの大きな共通の目的の上で、協力し合うことこそ、大事なことなのです。ひいては、その姿勢が、世界や地球を護ることにつなかっていくはずです。 ・日本の素晴らしさの一つに、日本食があります。 欧米の栄養学者によって、日本型の食生活が今、世界的に注目されています。人の日常の食事は、脂肪、たんぱく質、糖質のカロリーバランスがとれた食事が理想的であると認められたからであります。 ・日本食の特徴の一つは、米を主食にしていることです。 米は糖質が多いので、エネルギー源と考えられていますが、実に優れたたんぱく源にもなっています。私たちは、米を単品でとることがなく、ふつうは習慣的に、味噌汁や豆腐、納豆などの、大豆たんぱくと一緒にとります。この米と大豆たんぱくとの組み合わせが、とてもいいのです。米と大豆は、お互いに不足している必須アミノ酸を補い合うことで、理想的な栄養価となるのです。 ・そして日本食は、米以外に野菜や海草、魚介類を多食します。 通常、土と海から採れたものが八五%、動物は一五%というバランスが、私たちのからだにいいバランスと言われています。 ・食品を食べるとき、できればあるがままの状態が望ましい。たとえば米は、白米ではなく玄米のまま食べるほうが、栄養と生命力を同時にとることができます。 ・発芽玄米は母乳の免疫成分を増やし、母親のストレスを、明らかに抑制することが分かりました。 ・玄米菜食を世界に広めた、 ・ 「食養は一人一家族一個人の利益のみでなく、健康や経済や、美容や聡明さを支配し、延いては一国の運命をも支配する」 「低脳力、無気力は、食の乱れから起こる病弱がもたらすものである」 「職を正すことは、健康と幸福、平和への道である」 ・本来人間は、情緒的なこころが優先する生きものであるはずが、肉食過多になると、動物性が優先して、戦闘的、疑惑的、暴力的なこころや行動が、知らぬ知らぬうちに多くなってしまいます。 ・日常的に実践すること ①志を高く持つこと ②毎日感謝して生きること ③明るく、どんなときもプラス思考をつねとすること ・今までの生物化学や分子生物学は、物質そのもの、個の追求をあまりにも重大に考えすぎたために、生物にとって本当はとても重要なことですが、全体からものを見るということを見落としてきたようです。 ・アミノ酸がいくつかつながってできるたんぱく質は、それを構成する個別のアミノ酸とはまったく違う物質になり、まったく違う働きをします。さらにそのたんぱく質が脂質と一緒になり、細胞を形成したら、これは完全に一つの生物になって働きます。 ・私たちのからだの中では、そうしてできた細胞といういのちの集まりが、それぞれ個別の役割を担っています。それらは、すべていのちの一つひとつであります。私たちの組織や臓器を絶えず、おのおのの段階で、まるで質的に異なった高度な生物として誕生させているのです。 ・細胞は一日も休むことなく、作り変えているわけですから、そのメカニズムは簡単であるはずがありません。 【エピジェネティクス】 ・私たちの遺伝子情報は、それ自体が生体をコントロールしているのではなく、必要な遺伝子情報のスイッチがオンになったり、オフになったりすることで、生体がコントロールされているというものです。 ・細胞には、外からの信号を受け取るレセプターというアンテナがあります。これまではこのアンテナが受け取る信号の大部分は、ビタミン、ホルモン、たんぱく質などの分子や、化学的な薬品などと思われていました。しかし、そのスイッチを入れるシグナルは、物質だけではなかったということです。 ・これまでの考え方と大きく違うことは、量子物理学の理論が細胞生物学に加わったことです。 これまで両者は、まるで相容れない学問であったのです。 ・遺伝子のスイッチを入れるものは、からだを取り巻く、大自然の空気、磁気、波動、音楽やことば、そして思い、思考なども、大きく影響していることが、証明され始めたのです。 ・つまり、からだの中の情報からだけではなく、「環境」こそが、遺伝子情報のスイッチをコントロールする大きな要因であるというのです。 ・ブルース・リプトンは、細胞は独自の生き物であり、細胞の脳機能である細胞膜の働きを発見しました。それにより、これまでの遺伝子が生命をコントロールするとされてきた考え方が大きく変わりました。遺伝子の基本設計図はそのままで書き換えられず、外部の環境シグナルが遺伝子のスイッチをオンにしているという理論をのべています。 ・地球は、量子的な宇宙の中にある一つの大きな生命体であると言うのです。目に見えない無数の分子イオンが飛び交う波動(振動)の中に私たちは暮らしています。私たちの日常の中では、恋や愛、好意などの思いは、確かに相手に伝わります。相手からも伝わってきます。 ・私たちは地球という生命体の一員であり、植物や動物、微生物などと、ともに生きている生物の仲間なのです。 そう考えたとき、私たちのコミュニケーションの手段の一つである、思いを傳えあうということを無視して生きていくことはできません。すべて、生きものたちは相関し、支えあって生きているのです。 ・そこで、人間にとってこころや魂の働きが大切です。 癒しだったり、感謝だったり、祈りだったり、喜びだったり、悲しみだったり・・・・・。 リプトンは、「人間とは、魂が形を変えたものである」と言っています。 このことは、私たち人間は、何かを誰かを思ったり、考えたり望んだりしながら生きていることを意味しています。 ・人間とは、環境からエネルギーや情報を得て生きている「地球探査機である」と、リプトンは言います。ですから、たえず細胞のレセプターを活性化しておく必要があります。 ・こころと遺伝子は、相互作用する。 ・何を思い、どういうこころで一日一日を過ごすかがとても大事なことになるのです。その思いの質が、生きる質であり、または生きる量と関係していくのではないでしょうか? 思い、すなわち、信念が人生をコントロールするといっても過言ではありません。 私たちは、思いを正し、明確にすることで、運命の支配者になれるのです。 ・たとえば、人間の細胞のレセプターが受けるシグナルが、二つに分かれたとします。一つは、ホルモンのような情報伝達のための物質や薬のような化学物質シグナル、もう一つが、祈りや思いなどのエナジーシグナルとします。 からだの中で、エナジーシグナルは、なんと化学物質の一〇〇万倍のスピードで効果を発揮します。このことは、その人の受信機にふさわしい信号が送られた場合は、具合が悪いときなど、薬を飲むよりも早く具合が良くなることを意味します。 環境で変わる人間のすごさ、不思議さはここにあります。 ・リプトンは、遺伝子のオン、オフのスイッチに関係しているのが、限られた一点のレセプターだけでなく、細胞膜全体であることを発見しました。 細胞膜が、細胞の脳機能を果たしているという新説を、発表しているのです。 ・ですからこれまでは、効果が医学的に認められていなかった、鍼灸や、気功、音楽療法などが、みな広い意味で影響していることが証明されつつあります。 オン、オフのスイッチが、直接治癒に関係しているのではなく、免疫力をアップするのに関係しているようです。 ・悪いところを部分でとらえ、個別に直そうとする西洋医学、病気を全体で捉えようとする東洋医学、しかし今や、すべてを駆使して病気を治すという統合医学、ホリスティック・メディスンというジャンルの確立が急がれています。そこには、ころや魂のバランス、祈りや心理学も含めたスピリチュアルなケアも入って行かなければなりません。 毎日の食のとり方も立派な医学のジャンルとなります。 ・新しい目標を見つけることこそ、自分を取り巻く環境を、新しく変えていく、大きなきっかけにつながっていくものと思います。 |
73 |
15.07 |
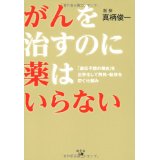 |
がんを治すのに薬はいらない |
真柄俊一 |
幻冬舎 |
☆ |
・生活習慣病といわれる病気のほとんどは、実は食べ物が大きく影響しています。日本の場合、そもそ医師が何も知っていないのです。 ・がん治療にあたっては、「食べ物」と「心の持ち方」が大きな柱になります。 ・ライフスタイルによって人は病気にもなりますし、要因となったライフスタイルを変えることによって回復にもつながるのです。 ・食生活や心の持ち方に対し、西洋医学はほとんど配慮していません。「栄養」と「意識」に関する正しい知識を持たないと自然治癒力をうまく引き出すことはできません。 ・「あなた、病院に行くと病気になりますよ!」 ・東大病院の医学生や若い医師たちは、自分たちの身内は絶対に入院させたくないと言うのです。 ・慶應大学を卒業したビジネスマンは、「家内はもちろん、私自身ががんになっても慶応病院に入院するつもりはありません。」と言われた。 ・権威主義にこり固まった医療は、伝統や先例にかたよりがちです。がん治療でいえば「手術・放射線・抗がん剤」の3大療法、言い換えれば標準治療をかたくなに守ります。 ・これ以上はない環境のもとで、最高レベルの医師たちがそろっている」という意識のもとで治療が行われます。その治療がうまくいかなかった場合、「がんとはそういう病気、われれには何の落ち度もない」と決めつけてしまうことになるのです。 ・がん治療にかぎっていえば、現代西洋医学の問題点は抗がん剤治療にあります。ごく一部のがんを別にして抗がん剤は、ガン治療に効果がないどころか、むしろ「増がん剤」です。 ・「がんがステージⅣになると、絶対に治らない」と、日本のがんの専門医のほとんどがそう信じ込んでいるのです。 ・ステージⅣのがんがすべて治るとまでは言いませんが、決してあきらめることはないのです。 ・日本は、「物言えば唇寒し」の伝統があって、改革とは名ばかりで、社会にはどんよりして沈うつな諦めモードが漂う。医療政策を決定する政府の会議でも、最初から最後まで沈黙している委員が席を占めている。役人の決めた筋道に強く異議を唱えれば、必ず「パージ」される。 改革していくダイナミズムがまったくない。 ・私の治療の基本的な考え方 ① がんは自然治癒力で治る。 ② その「治る仕組み」は遺伝子に書き込まれている。 ③ ヒトが進化の過程で経験したことが遺伝子に書き込まれている。 ④ 進化の過程で経験していないことをすると、危険なことが起こる可能性がある。 ・西洋医学の危険性は、地球上に存在しない新しい物質を化学合成によって開発し、それを薬剤としているからである。 ・健康とは何かを一番わかっていないのが医者だ。現在の医療の9割がそもそも不要だ。 ・治った患者は、西洋医学の「医者」に頼らず、自らがんと向き合って心の持ち方・考え方を変え、病気になる前の自分の食生活をみつめ直し、それを根本的に改めているからである。 ・「ナチュラル・ハイジーン」とは 「『自然の法則』に基づいた生命科学の理論」 健康維持や病気改善の秘訣は、自然と調和して生きることである。 健康および健康維持のための科学。健康を保ち、病気を予防するための原則の理論 「健康のために必要な条件を体に与え、体を傷つけるようなものを体に与えないことによって、体の内外環境を清潔に保つ」ということです。 必要な条件とは、「新鮮な空気や水」「体の生理機能構造上ふさわしい食事」「十分な睡眠や休養」「適度な運動」「日光」「ストレスマネージメント」など、生き物にとって生きていくための基本的な要素のことです。 人間に備わっている内なる力を邪魔しない限り、悪いところは治され、病気は速やかに恢復し、健康を維持できるようになる、というのがナチュラル・ハイジーンの教えです。 ・アンチエイジングの基本は「食事」、「運動」、「生きがい」が3つの柱である。 ・食材に含まれるファイトケミカル(植物に含まれる有効成分)の量とカロリー相対比が高い食材をなるべくたくさん摂取して、低い食材は避けるべきである。 ・自然の植物は、生物活性化合物の複雑な組み合わせで成り立っています。「植物の化合物」を意味する「ファイトケミカル」という用語は、動物組織に働きかけ、ヒトの健康と免疫力に微妙かつ重大な影響をもたらす、何千という植物由来の成分を指します。 ・「スーパー免疫力」とは 体の免疫機能が最大限に発揮されている状態。 自然治癒力が最も高まっている状態。 特定の食材や栄養要因によって、免疫システムの防御力が2倍にも3倍にも高まることが、現代科学の進歩により、はっきり裏付けられています。 ・スーパー免疫力をつける5つの基本ルール ① 大盛りサラダを毎日食べる。 ② 毎日少なくとも半カップの豆類を、スープかサラダ、その他の料理で食べる。 ③ 毎日少なくとも3個の生の果物を食べる。特に、ベリー類、ザクロ、サクランボ、プラム、オレンジがよい。 ④ 毎日少なくとも28グラムの生のナッツ類か種子類を食べる。 ⑤ 毎日少なくとも大盛りサラダボール1杯の緑色野菜を、生、ゆで、またはシチューで食べる。 ・人は本来だれもが持つ自然治癒力が弱まることにより病気になります。だとすれば、弱った自然治癒力を高めることこそが医療のはずです。 ・なぜ、プラス思考で治癒することがあるのでしょうか。強い思いが内なる自然治癒力をめざめさせるからです。このタイプは何か自分だけの目標を持っている人や、強固な信念、あるいは信仰を持っている人などによく見られます。 ・涙にもいろいろありますが、感動して流す涙は脳をリセットしてストレスの原因を消すのに非常に効果があるんです。感動の涙を流している時、脳の中でも前頭前野の限られた部位の血流がもの凄く増えます。 ・笑うことが健康に良いということは、だいぶ昔から知られています。笑うことが健康に良い極端な例をあげると、笑いによってがんが治ったという例もあったと言われているほどです。 ・笑うにせよ泣くにせよ、心が共鳴し、感動していることです。これをくり返していくことで自然治癒力が高まるわけですが、言い換えれば、それは、眠っていた遺伝子のスイッチが「オン」になることなのです。 ・アメリカの細胞生物学者、ブルース・リプトンいわく、 「遺伝子は単なる生物の設計図にすぎず、意識や環境が細胞をコントロールし、遺伝子の振る舞いを変える」のです。 ・結論だけ先にいえば、物理的刺激、栄養、意識などが遺伝子の働きをコントロールするというのです。つまり、食生活や心の持ち方、環境によって人間の遺伝子が左右され、それによって病気になったり、逆に病気が治ったりするわけです。 ・これまでの研究でがんを進行させる方向に働く遺伝子(がん促進遺伝子)と、逆にがんを治す方向に働く遺伝子(がん抑制遺伝子)の2種類があることはすでにわかっています。そして、それをコントロールしているのは物理的刺激や栄養、意識、環境といった、細胞の外からやってくるシグナルであることを解明したのがエピジェネティクスです。 ・ブルース・リプトン博士は、身のまわりのすべての環境、心のエネルギーである思いや考えなどが遺伝子のスイッチを入れ、病気を治すばかりか、人生をも変えると説いています。 ・「エピジェネティクス」とは」 ①遺伝子やDNAが、私たちの生体機能をコントロールしているのではないこと ②細胞の外側からやってくるシグナル、つまり物理的刺激、科学的刺激、それに私たちが抱く思考などが強力なメッセージを発していること ③それらのシグナルが細胞膜によってキャッチされていること ④その結果として、遺伝子群の働きに変化が起こる ・エピジェネティクスで言う「環境」は、「人体の外から与えられる環境因子、すべてのエネルギーシグナル」という意味になります。つまり②の「細胞の外側からやってくるシグナル」です。これが遺伝子群の働きを左右し、病気を発生させたり、逆に治したりします。がんでいえば、がん促進遺伝子を強めて病状を進行させたり、逆にがん抑制遺伝子の働きを高めて治癒に向かわせたりします。 ・言い換えれば、そのコントロール方法が、がん治療の決め手になるわけです。 ・シグナルとは ①物理的要因:電磁波、圧力、熱、音、光、運動、鍼刺激など ②化学的要因:食べ物、薬物、アルコール、喫煙、環境ホルモンなど ③精神的要因:興奮、感動、喜び、笑い、愛情、希望、不安、怒り、祈りなど ・これらの要因がプラスのシグナル、あるいはマイナスのシグナルとして体に働きかけ、遺伝子のオン・オフのスイッチを切り替えるわけです。 ・薬理作用のない偽薬ならどんな効き目もないはずですが、本物の薬と信じて服用する被験者のなかには、実際に効果が表れる場合があり、これを「プラシーボ効果」と呼びます。 ・リプトン博士は、これを「信念効果」として評価しています。 「『信念効果』はすばらしいものだ。これこそ、身体/心には治癒能力が備わっていることを示す、驚くべき証拠である」 ・心の持ち方次第でがんは進行したり、逆に抑制されたりします。意識という「環境」が、遺伝子のスイッチの働きを切り替えるにほかなりません。 ・ストレスには「他者や外部から与えられる不快な刺激」と「渇望ストレス」の2種類がある。前者は通常いわれるストレスですが、これを“マイナスストレス”とすれば、後者は“プラスストレス”とも言い換えられます。 ・人間の脳というのは自分の心の持ちようで同じ出来事がポジティブにもネガティブにもなる。人間の脳ってそういう意味では簡単に切り替わってしまい、すばらしいと思う。 ・がんを恐れるばかりでは、ストレスがどんどん溜まり、それがマイナス信号を脳細胞に伝え、病状は悪化します。逆に、がんになったのは自分が変わるきっかけを与えられたのだと思えるようになれば、そのプラスシグナルががん抑制遺伝子のスイッチをオンにし、回復に向かっていくのです。 ・「マイナスストレス」を捨て、「プラスストレス」を活かせる人は、自分の力でがんを治せるのです。 ・現代西洋医学や薬剤への批判は、医師以外の学者や研究者に多い。彼らは例外なく、医学界と製薬業界の癒着構造を指摘しています。 ・巨大製薬会社は莫大な資金を投じて新薬を開発し続け、投資の回収や利益確保のため、医学界や政界、マスコミまでを巻き込んでしまいます。 ・がんという病気は、一般的に思われているよりは、恐ろしい病気ではありません。ただし、ある一線を超えると途端に、きわめて困難な状況になります。 ・肺にだけ転移しているとか、肝臓にだけ転移している人は、条件次第では助かります。助かるための条件をあげますと、十分に食べることができて、自分の力で普通に運動ができるくらいの元気さがあることです。 ・がん以外の余病を持っていないことも、助かるための大切な一つの条件になります。病気を持っているということは、その病気の種類や状況にもよりますが、何らかの薬剤を多種類服用している人が多いからです。薬剤はまず毒物ですから、それ自体遺伝子群のネットワークを狂わせ、がん抑制遺伝子の働きにも悪影響が及ぶのです。 ・手術のあとに抗がん剤を服用することで、肝転移などの再発を予防することは事実上不可能です。同様に末期がんに対する抗がん剤による治療はほとんど効果がありません。 ・それでもエピジェネティクスの理論に則った治療で、何の苦痛も副作用もないまま治ってしまうケースがあるのです。 ・自分の病気に対して覚悟を決めると、意識が変わっていきます。 ・意識の劇的な変化は遺伝子群の働きを劇的に変えることがあるのです。 ・いつの時代にも、真実を説く者は、それによって利益を失う側からの強大な圧力を受けます。しかし、いくら圧力をかけられようと、決して消えてしまうことはありません。 ・がんが見つかったら、まずは手術をして放射線治療をして、それからベルトコンベアで流されていくように抗がん剤を次から次へと順番に投与して、という機械的な医療が、今なお多くの病院で行われているのが現実です。 ・末期まで進行していないかぎり、がんはそれほど恐れる必要のない生活習慣病のひとつです。恐れるべきは、標準治療の名の下に行われている現代医療です。 |
| 72 | 15.07 | 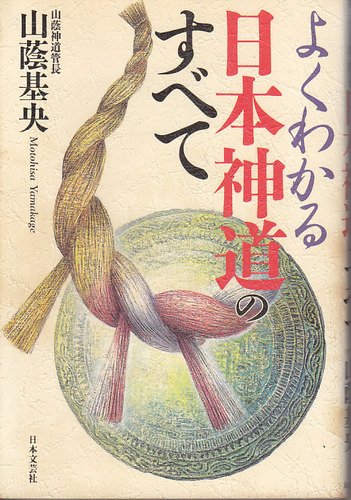 |
よくわかる日本神道のすべて | 山蔭基央 | 日本文芸社 | ◎ | ・日本での植林計画が文献に見えるのは三世紀からである。以来この方、日本は国土の危機管理を治山治水においてきた。その“気の長い”未来への贈り物が植林と育樹である。 ・とにかく「日本神道」には何もない。 「教祖がない、教義がない、戒律がない、 というのが神道である。 ・『魏志倭人伝』には、古代日本人の生活態度が立派だと讃美し、“東海の君子国”だと紹介している。これは、教祖がいなくても人倫の道が立つことを証明している。 ・しかし、当時の大文明国(中国)の文化思想に抗することはできず、社殿を それが奈良時代以降の神道である。 ・太古の日本では刑罰を行なっても、それを ・儒教や仏教の洗礼を受けた人々は“見直し、聞き直し、言い直して、水に流す”ということができなくなっていたのである。 これはまさに、全日本人の悲劇である。 ・神社は斎場であって“神霊の住居”ではない。 【水こそ神の ・近代科学の結論によると、生物は海の中から発生したとされているが、古代日本語の「ウミ」は、漢字を借りると「生み、 ・日本語の海についての認識が明らかになれば、 ・大自然の神霊が姿を現わすときは「水」が最初であるとして、水源を ・すべてのものがことごとく差別ある姿をしていることを正当なことだと観ることを“妙観察智”というが、まことにそれは、古神道において八百万神として崇める思想と同じである。 ・神は最初に「水」として顕われ、後に、万物の姿をとったのである。“万物は神の化身”なのである。その化身の筆頭がと出るという神話は正しい。 ・由緒ある古大社では、正月の元旦祭では「井戸の水神祭」がすべての祭祀に先行する。つまり、水神は、その神社の「 【氏神と鎮守と産土の違い】 ・中国宋代になると周代の郷が「鎮(小都市))」となった。元来そうした地域守護の神が「鎮守社」であったのが、日本では、城・寺院・小村落の守護神として祀られ、それを鎮守と呼ぶようになった。 ・もともと産土神とは、その土地に鎮まっている元来の神であって、ある場合は“水神”であり、ある場合は“火神”であった。そうした土地の宗主(地主)を産土といい、別名を「 ・氏神とは、その土地に入植した一族の大元祖(氏の祖先)のことをいう。藤原氏は春日大社を氏神とし、源氏は八幡宮を氏神とした。だから、それぞれの家系の大元祖が氏神である。だから郷邑の鎮守に祀って氏神とした場合もある。 ・その昔、神社には建造物(ヤシロ)はなかった。だから、祭礼の度に“神迎への儀”を行なってお祭りし、それが終わると“神送りの儀”を行なった。ある場合、臨時祭場の建物を造る神社もあったが、それは祭儀が終われば だから巨岩のことを「 ・古代の人々は、この神聖な岩を扉として、神々は ・「鳥居から中は正中を通ってはならない。右か左かどちらかを通ること」と、よくいわれるのは、真ん中は“神の道”となっているからだ。 拝殿に到着しても、やはりどちらかに寄って礼拝すべきものである。神主が中央で拝むのは“神の憑代”であるから。 ・神社は斎場であって、“神霊の住居”ではない。 【なぜ土俵で塩を撒くのか】 ・もともと相撲とは、神事に伴う“占”であったのだから、その“占の 【なぜ神様へのお供物に塩が必要なのか】 ・日本人の心には、“塩は海神(祓戸大神)の化身”として、一切を浄めてくださる 【「水に流す」とは何を流すのか】 ・ ・古来、日本には「水はすべてを浄めてくれる」という信仰がある。まさに“ ・「 【水商売の“水”の意味】 ・古代日本語では、蛇のことを「ミズチ」という。又、霊のことを「ヒ」、「ミ」、「チ」、「タマ」、「モノ」というが、その中の「チ」がついた「ミズチ」とは「水の霊」ということになる。 そこに蛇信仰が生まれる理由がある。 水商売の人は「ミーさん」と称して蛇を祀る。その心は“ミイリ=収入”がよくなるという意味につながっている。だから、水商売の水は、“ 【死水とはどういう水なのか】 ・「死に水」とは「末期の水」のことである。 末期とは、死の寸前のことで、この最後のとき唇をしめらせてあげる水のことを「死水」という。 そのことを「死水を取る」というが、転じて、「死の最後まで世話をする」意になっている。 【祝いに使う「水引」の意味】 ・「麻などを水に浸しておいて皮をはぐ」ことを水引というとあり、進物用の品を飾るためにしばる紙紐を「水引」というが、案外それは、その贈り物を浄めるための ・西洋にも贈り物にリボンを飾るという風習があるが、その感覚は「水引」とは異なる。 なぜなら、「水引」は、包装紙の上にさらに白紙をかけて、それに紅白や金銀の水引をかけるのだから、やはりそれは“浄める”の意がある。 【相撲の「水入り」とは】 ・相撲は神事の一つで「 疲れた者は“気が枯れて”いる、そうした衰えを“汚れ”と見た。そうした“気枯れ”を復活させるために“水入り”という休憩を与え、気力を整えさせてから、再び「塩祓」の上で相撲の取り直しをさせたのである。 つまり、“水入り”の原意は「汚れを浄める」ためであった。 【祝儀事は神社、不幸はお寺 この分担の意味は?】 ・おそらく仏教が人間救済の教えであると宣布した一方で“地獄の恐怖”を流布したので、それを解除する“呪術”を考案しなければならなくなったからではないか。 ・そうしたとき、唐の善導が唱えた「浄土教」なるものが渡来し、「いかなる罪人でも阿弥陀如来の御名を唱える者には極楽往生を保証する」との呪術を法然が紹介し、親鸞がそれを継承して、仏教地獄の救世主になった。 ・仏教は全国に広まり、鎌倉時代には庶民の世界にまで普及していたから、法然・親鸞の救いが必要になったわけで、それにより死者の「安心立命」は、念仏往生として確立し、「葬儀は仏教へ」となった。 ・さらに江戸時代における「キリシタン禁制」のために設けた檀家制度を活用して、仏教僧にキリシタンを監視させ、“葬儀、追善供養”はことごとく仏教に一任されることになった。 【なぜ天照大御神に絵や像がないのか】 ・それは、天照大御神は ・日本の神道には神々の偶像は作られておらず、あるのは「神楽仮面」だけである。 ・神々を造形しなかった英知は、偉大であったというしかない。 なぜならば、神霊のお姿を人間の考える低次元の容相に固定することは、自由にして偉大なる神霊を限定した枠に閉じ込めることになるからだ。 【 ・祝詞は、一般的には神様に奏上する詞であるが、経文とは、教祖から信者に対する教諭の言葉である。 【元気を出せの“元気”とは何?】 ・これは中国語で、道教の用語である。 ・辞書には、「万物の根本精気、天地生成の気、人の精気」などとあり、ひいては活動力の源泉となるわけで、人が生まれながらに持つ生命力のことである。 ・その元気の吸引は、なんとしても呼吸法にある。 ・元気は呼吸法によって吸引され、人びとの体内にある元気(風空の気)と合体して偉大な活力を増幅する。 ・だから呼吸すること自体が元気を出すことになるわけで、簡単な方法は“吐く”ことから始まる。 ・空気は吸えば入るというものではなく、まず吐かねばならない。要するに出せば入るのである。とにかく出すしかないのである。腹の底からしぼり出すように吐き出すことである。そうすれば、その反動で空気は吸引され、感情的に停滞している気は吐き出されて、新しい気が入ってくる。 ・また「笑え! 笑えば新しい気が入ってくる」と言う。まったく、その通りである。 また、高笑いする声には、 【天地神明に誓うのと聖書に誓うことの違い】 ・「神明」という語は、天照大神のことをいう。 ・「天地神明」という日本の神々は、宇宙普遍の神を中心とするあまたの神々のことなのだが、日本人にとっては正義の根源になる神々のことでもある。 ・これらの神々は人類普遍の創造主を中心にする組織的な神である。したがって、キリストをも含み、儒教の天はもとより、道教の天皇大帝をも包含する神である。もちろん、仏教で説く諸仏も包括する神である。 ・しかし日本神道の神々には、微に入り細にわたった「教誡・戒律」がない。だから真理とされ、正義とされる言語を持っていない。 そのために、いままでは幼稚で未開で原始的な宗教だと軽蔑されてきた。 ・しかし だから教義の神に誓うことは普遍性がない。 ・一人の神を信じることは、他の神に反する誓いを立てたことになるわけである。キリスト教とイスラム教の神では永遠の対決となる。 ・だから「天地神明」という“無教義の神”にこそ“普遍の誓い”があるといえる。 |
| 71 | 15.07 | 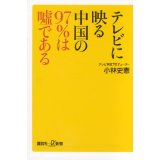 |
テレビに映る中国の97%は嘘である | 小林史憲 | 講談社+α新書 | ◎ | ・中国人の口癖は、「上有政策、下有対策(上に政策あれば、下に対策あり)」。共産党が掲げるスローガンや、表向きのルールは、現場に行けばひっくり返る。そこに、「嘘」がある。 ①「ワイロ」と「ニセモノ」 ・中国で「富裕層」と言えば、主に共産党関係者、役人、国営企業の幹部たちのことだ。 二〇一二年三月には、温家宝首相が、役人が公費を使って高級酒(マオタイ)を購入することを取り締まる方針を掲げた。 要は役人たちが公費をバンバン使ってマオタイを買っていたために、値段が高騰していたというわけだ。 ・役人や国営企業の幹部が、他人からもらったマオタイを回収店(酒やタバコを持ち込むと現金に換えてくれる店)に持ち込み、換金しているというのである。 マオタイを贈る側も、最初からそれを想定しているという。つまり、「ワイロ」である。現金だと問題になるが、酒ならば目立たない。しかも、贈る側も領収書を経費で処理できるというメリットもある。 ・いま市場に流通しているマオタイのうち、九割はニセモノと言われている。マオタイの直営店以外で購入したものは、ほとんどが本物かどうか怪しい。 いずれ換金されるものなので、本物かどうかはあまり関係ない。 ・「ワイロ」に「ニセモノ」 ―― マオタイには中国社会を象徴する二大要素が詰まっているのだ。 ②チベット族と漢族 ・日本のODA、政府開発援助について 仏教芸術などを学ぶための職業訓練校建設のために、外務省は、約一〇〇〇万円の無償援助を地元政府にしていた。二〇一〇年一〇月に建物が完成。外務省の職員も立ち会って、竣工式が行われた。 ・しかし、そこは県の共産党学校となっていた。 ・中国では、貧困対策の予算が別の用途に使われるケースがよくある。どうやら、ここでも役人が金を流用し、さらには建設費用まで未払いになっているようだった。 ・県に確認すると、職業訓練校と共産党学校が半々とのこと。無償援助は無駄にしていないとの回答だった。 ・援助を受ける側の中国もひどいが、これが日本のODAの実態でもある。 ・校舎の壁の隅の方に、日本の無償援助で建てられた旨が描かれているが、いずれペンキで塗られてしまうしろものだ。 ③毒入りギョーザ事件 ・中国では、司法は政府から独立していない。いつ裁判を開くのか、罪名をどうするのか、そして、場合によっては判決をどうするかまで、政治的に決められてしまうのだ。 |