
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年02月21日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
106 |
16/12 |
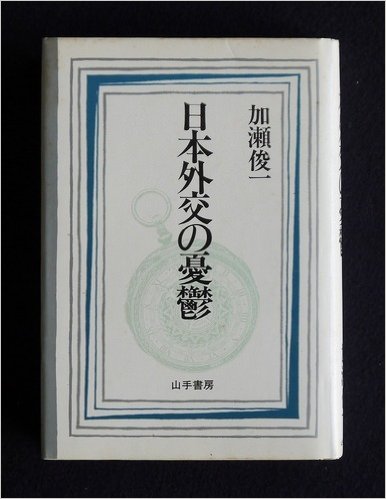 |
日本外交の憂鬱 |
加瀬俊一 |
山出書房 |
◎ |
第一部 日本外交を憂える 世界危機は切迫する 二 クレムリンの対日意図 ・第七艦隊が中東に出動すれば、北東アジアの対ソ防衛は著しく劣勢になる。 ・日ソは両国関係から衝突する公算は少なくても、ソ連が有利な軍事情勢において、中東や朝鮮半島――北朝鮮の軍備増強は顕著であってその公算は少ないとみられるが、韓国を奇襲圧倒する能力を持っているという――における紛争の余波を受けて、アジアの局面が紛糾したら、米国は日本に対して、宗谷、津軽、対馬三海峡の封鎖に協力を要請するだろう。封鎖すれば、ソ連艦隊の外洋出撃を妨碍できるからである。 ・もし、日本が協力を拒否すれば、安保条約は死文に等しくなる。 ・だが、ソ連も黙視せず、三海峡の自由航行を日本に要求するにちがいない。これを拒否すれば軍事行動に出る可能性もある。 ・自由陣営に属する日本としては、米国に協力すべきだが、このような極限状態に効果的に対応する用意が日本政府にあるか、また、国民は冷静に難局に対処できるか。日本の真価は、まさに、このような危機に際し、いかに行動するかによって定まるのである。 ・クレムリンの対日意図は明白である。ソ連はその軍事システムのなかに日本を吸収したいのである。 ・ソ連が欲しいのは、第一に日本の戦略的地位であって、これを掌握すれば米・中に対して極めて有利になる。 ・第二には日本が世界第二位の経済大国になった原動力、つまり優秀な工業施設と、これを駆使する有能な人材が欲しいのであって、破壊殺傷せずに温存して、ゴッソリ入手したいのである。 ・日本は現在のような微力な防衛態勢を放置すれば、侵攻を招く恐れがある。 ・日本はソ連に二の足を踏んで自制させるだけの防衛態勢を至急整備せねばならぬ。 ・ソ連はそれをさせまいとして、時として鬼の面をはずしてオカメの面をかぶる。善隣友好条約なるものがそれであるが、これは日米安保条約と両立しない。 ・要するに、日本を米国から引き離してソ連の勢力圏に編入したいのである。 ・ソ連は毎年わが領海領空をおびやかすので、自衛隊機は年間三百回も緊急発進するのである。八〇年八月には、ソ連原潜は警告を無視して公然と日本領海を通航した。明らかに、善隣友好に反する不法行為である。 ・しかし、わがマスコミは黙過した。それなのに、ミッドウェイの横須賀寄港(八一年六月)に対してはかまびすしく反米論陣を張った。米国民が日本は果たして同盟国かと疑うのはムリもあるまい。 ・ソ連はアフガニスタンに侵攻し、国際世論の糾弾を受けている・ ・不可解なのは、このような侵略を行いつつ、日ソ関係が冷却した責任を日本に転嫁する態度であ。 ・日ソ関係修復に、まず誠意を示すべきはソ連であって、日本ではない。それも、速やかに行動をもって立証すべきである。 ・ソ連に残された起死回生の一途はシベリア開発しかないが、それには日本の協力が絶対に必要である。だから、クレムリンは微笑外交を恐喝外交と併用して、「どうぞシベリアへ」と呼びかける。 ・日本としては合理的条件なら協力してもよいのであって、それはソ連の暴発を防止する効用もあろうというものだが、それには北方領土からの撤兵を前提条件とするのがスジである。ソ連に対しては、そのくらいの強固な基本姿勢で臨むべきである。 日米関係の乱気流 一 レーガン政権の本音 ・米国政治の恒例として、初めの百日は議会もマスコミも大統領非難は差し控えるので、蜜月期間と呼ばれる。いわば、御手並み拝見であって、この期間が経過すると批判が始まるのが常である。 三 日本の課題 ・日本国内の非核三原則論争について 米国の核抑止力に自国の安全をゆだねているのに、有事の際でも、核を積載する米艦の寄港・領海通過を絶対拒否するという日本の態度は、米国民には奇怪至極な非論理としかうつらない。この点、日米の心理的落差は大きいが、米国紙は日本のヒステリックな三原則論議などバカらしくて話にならぬ、という態度で黙殺している。だから、マスコミも国会も一人相撲をとっている観があった。 ・結局は日米の世界情勢に対する現状認識が一致せぬのである。日本は平和時の防衛を考えているのに、米国は非常時、むしろ、臨戦時の防衛を進めようとしている。だから、問題は、現在は平和常態か非常事態かという一点に帰着する。 ・それ次第で、専守防衛も、軍事費をGNPの一%以内に収めるという閣議決定も、また現行憲法をも修正せねばなるまい。このような根本認識を検討するのが首脳会談の本来の課題のはずである。 ・「ヘリテージ財団」は最近「日本の防衛政策」と題する報告書を公表したが、日本の防衛力が自国を守るのに質量ともに夥しく不足しており、ソ連の軍事力増強、第七艦隊のインド洋展開に対応するため、早急に対潜能力、海上偵察能力、防空能力を強化する必要があると力説している。 ・さらに、防衛費をGNPの一%以下に抑える政策には意味がないと批判し、非核三原則、武器禁輸政策の検討、緊急時の自衛隊の海外派遣なども含めて、この際、新たな安全保障政策を確立することを勧告している。 ・報告書は末尾において、「日本は現在の防衛態勢の基礎を成す哲学の大部分について、真剣に再検討すべきだ」と述べているが、これが米国政府の偽らぬ本心と了解すべきである。 あえて亡国外交と呼ぶ 一 外交小国・日本 ・近年の日本外交にはヴィジョンが欠けている。将来を展望して日本の進路を大きく策定する意欲も能力も少ないように見受ける。その結果、経済大国としてのポジションは持っていながら、これにふさわしいホリシィがないので、諸外国から積極的外交姿勢の欠如が指摘される状況である。 ・これは日米安保条約によって、日本が米国の庇護に多年馴れているので、また、それがわが経済発展に多大の寄与をしたために、「これでよいのだ」という安逸な思考パターンが定着したからだと思われる。 ・安保の選択は適切だった。サンフランシスコ体制が我が国益に合致するのは歴史が証明する。それなのに、社会党などの野党は今なお安保解消を唱えているが、時代錯誤も甚だしく、厳に、鄧小平副主席に「安保条約をオカしいというのがオカしい」と嘲笑されて当惑している。 ・一九七二年秋、当時の田中首相が北京に赴いて周恩来首相とサシで懇談した時、周首相は安保条約に理解を示したうえ、こんな 「お国の社会党代表が私に対して、日本は非武装中立を厳守すべきだ、と説くので私は、それは白昼夢に等しい幻想だ、と答えた。彼は深く失望したようだったが、辞去する際私にこの応答を日本人には絶対に漏らさないで頂きたい、と懇願した」 野党第一党がこのように辱められるのは、日本にとって名誉ではない。 ・周首相は、「日本にとっては日米関係が第一義的に重要であって、日中関係には第二義的考慮を払ってくれればよい。中国はそれで満足する」と語ったが、鄧副首相も同趣旨を述べている。 ・これを裏返せば、中国が日本を尊重するのは日米関係が緊密だからであって、もし日本が米国から遊離すれば、中国の日本評価は急激に低下するにつがいない。中国だけではない。ソ連・西欧・東欧も、アジア。アフリカも、全世界が日本を軽視しよう。 二 米中接近の歴史的必然 ・アジアの安定は米ソ日中四国のパワー・バランスに立脚する。 ・ソ連の前進に対抗するために、中米両国が接近するのは自然の成行きである。 三 日本と中国の優先順位 ・日本が相も変わらず観念的平和主義に溺れて、全方位外交などという空疎なスローガンをかかげれば事足りると考えるのは、極めて非現実的である。 四 米ソ共存は過大評価できぬ ・軍事的には、世界は米ソ両極体制に支配されているが、この両国の戦争観は全くちがう。 ・米国は核兵器の出現により、相互自殺を招く全面戦争は、もはや起らず、米ソの核戦力が相互に抑止効果を発揮すれば平和は保たれる、と考える。従って、対ソ優位は必要なく、抑止に足りる戦力で十分という考えになりやすい。 ・ソ連は核兵器の登場は旧来の戦略原則を、いささかも変えず、戦争は起り得るし、とくに民族解放を支援するのは正義の戦争であるとの観点から、米国を抑止するための核戦力の優位を確保せねばならぬ、と信じている。 ・つまり、米国は相互抑止で満足するが、ソ連は米国を一方的に抑止したいのであり、米国は核戦争を否定するが、ソ連は肯定する。 ・核兵器によって戦争は追放されたと思いこむのは危険である。 五 鬼の面、オカメの面 ・ソ連の妄動を抑止できるのは米国だけであるが、軽武装の日本が安全を守るには、さし当り米国の軍事力の庇護に期待するほかない。 六 ズレた感覚 ・ラムズフェルド国防長官は「日本は執拗に安保条約下の米国の対日義務について確認を求めるが、日本政府は自国民の祖国防衛義務を確認したことがあるか」と反問した。痛烈な皮肉である。この辺に、米側の心証が露呈している。 ・日本のマスコミは情緒過多で、とかく、ムードに流されやすい。みずからつくったムードに溺れてセンセーショナリズムに走ることも多い。 最も自戒すべきはムード外交である。 ・一九七二年秋、田中首相が北京に赴いて日中国交を樹立したのは、就任後わずかに五十日の時点であるが、この前後のマスコミは「北京へ北京へと草木もなびく」過熱状態にあった。 ・元来、早期復交を強く望んでいたのは中国側なのに、中国は静かなること林の如く、日本は狂風に浪さわぐ海の俑だった。これでは交渉に不利なのは明白である。 ・七八年夏の平和友好条約交渉に際しても、わがマスコミは早期妥結を要望する大合唱を日夜くり返した。妥結を急ぐ必要は多く中国側にあり、従って、日本が交渉の ・しかも、与野党の政治家や財界人が盛んに訪中して、それぞれの思惑をもって、中国要路と接触しては、中国側の主張を日本に紹介したので、結果的には北京の拡声器になった観がある。 ・野党代表が共同声明を出す「野党外交」なるものは日本以外にはないのであって、その意図は善であっても、日本の足なみをくずし正規交渉を混乱させる。 七 外交戦略なき外務省 ・日本の外交官僚は事務能力は抜群で、世界の一流に属する。だが、視野が狭くヴィジョンに欠ける。年功序列で出世するから、与えられた職責を大過なくはたせば、それでよいという安易な気風に染まりやすい。 ・だから、守備範囲以外には眼を配らず、問題提起をする意欲が足りない。この結果、外交戦術はあっても外交戦略は生まれない。 ・本省勤務でも在外勤務でも、当面の末端事務を処理するのに勢力を消尽するので、長期的政策を考察する余力がない。 ・それに、在外大使も請訓して行動するクセがついているから――本省にゲタを預ければ安全である――一種の思考停止症にかかりかねない。 ・かつては、幣原、吉田、重光、東郷などの先輩は、任地から意見を進言して本省(すなわち政府)の啓発誘導に努めたのであって、しばしば本国政府と勇敢に抗争したものである。 ・いまや、外交官とは名称だけで、実質は外交事務官であり、大使を僭称しながら実態は小使になってしまった、と酷評する声もきく。小使をコヅカイと読む人もいようというものである。 ・優秀な人材は少なくないのだが、政治家の国際感覚が極めて粗雑で、かつ、マスコミの偏向が顕著なので、一般に積極的意欲が乏しくなりがちである。 八 外交立国こそが生きる道 ・結局、外交の運用は政治の責任である。外交は内政の延長であって政局が安定し経済が繁栄しなくては、堅実な外交は望むべくもない。 ・日本外交の使命は経済力を活用して、世界の福祉に奉仕するにある。 ・現状は日本が米国を必要とする度合が、米国が日本を必要とする度合よりも遥かに大きく、顕著なアンバランスがある。これを是正し、米国が絶対に日本から遊離せぬように、速きに及んで工夫せぬと安保の前途も危うかろう。 ・例えば、日米貿易マサツが間断なく起るようではいけない。これについては、米側の無理解な態度も指摘すべきだが、日本自身が有り余る経済力を活用して、新しい国造りに邁進する必要がある。 ・マスコミは日本が袋だたきにされるといって、弱者のような被害妄想的報道を好むが、それよりも強者らしく――米国の圧力によるのでなく日本の自主的立場で――産業構造の再編革新に速やかに取り組むべきだと思う。 第二部 日本外交の軌跡 日露戦争と小村外交 一 日露協商か日英同盟か ・日本の安全を脅威する外国勢力は、古来、朝鮮半島または千島列島を経由するのが常だった。 ・一八九四―九五年の日清戦争は、シナ(中国)が朝鮮を支配しようとしたのを、日本が阻止したために起った。 ・「眠れる獅子」と呼ばれたシナが敗戦によって、意外にも弱体を露呈すると、欧州列強は死体にむらがるコンドルのように、清国領土を侵略した。 ・その結果、義和団の排外運動が起り、清国政府(西太后)がこれを利用して列強に対抗したので、北清事変(一九〇〇年夏)となった。 ・日・英・米・仏・露・独・墺(オーストリア)・伊の八国連合軍の北京占領によって、事変は終結したが、ロシアは事変に乗じて満州全域に勢力を拡大し、朝鮮をも窺うに至った。 ・放置すれば、満州・朝鮮を支配したうえ、揚子江北部のシナ本土を大きく制圧し、北京政府を意のままに操縦する形勢となりそうだった。 ・日本は日清戦争の戦果を、露仏独の三国干渉によって奪われ、遺恨十年一剣を磨いていたが、三国干渉の元凶はロシアだから、その侵略的な満鮮経営に対しては、国民感情も強く反発した。 ・とはいえ、盛強を誇るロシアに挑戦するのは大きな冒険だった。 ・日露協商か日英同盟かの選択は、日本の国運にとって重大な意味を持っていた。 ・ロシアに満州撤兵を要求する日露交渉は、日本側が極度の忍耐を続けたのにかかわらず、ロシア側は誠意を示さず満州軍備を着々増強した。 ・一九〇二年(明治三十五年)一月三十日、日英同盟が調印され、一九〇四年二月四日、御前会議が開かれて、日本はついに国運を賭してロシアの満韓侵略を排除する決意を固めた。 ・伊藤はかねての考案に従って、貴族院議員・金子堅太郎を招致し、開戦の廟議を内報し、「君は直ちに渡米して、米国世論を日本支持に誘導し、他日有利な講和を結べるよう伏線をひいてもらいたい」と要請した。 ・だが、彼は南北戦争以来の因縁で、米国民は親露的であるから、これを親日に転換させるのは至難であり、微力ではとても出来かねる、といって固辞した。 ・伊藤は色をなして、 「この戦争自体に成算があるわけではない。しかも、あえて一戦するのは、祖国の安全を確保するため真にやむを得ぬからだ。もし、戦い利あらずして敵軍が日本に来攻したら、私は一兵卒となり最前線に出動して討死する決心でいる。君も同じ精神で奮起せねばいかん」 と訓戒した。 ・金子は雷に打たれたように感動し、「成敗を度外視して最善をつくします」と誓って、早々に出発した。 ・伊藤の面目が躍如としている。太平洋戦争の時の重臣とは全く器量がちがう。開戦に臨んで、早くも講和準備に着手したのは、さすがに伊藤である。 ・開戦に当っては、(一)戦争目的 (二)進軍限界 (三)降倭準備 が必要である。日露戦争の時には、わが戦争目的は明確であって、世界も同情し、国民は勇戦奮闘して、士気において露軍(なんのために満州くんだりで血を流すのか理解しなかった)を圧倒した。進軍限界は奉天だった。 ・児玉参謀次長は奉天会戦で勝利を収めると、極秘に直ちに帰国して早期講和を要請している。 ・太平洋戦争の際は「自衛」というだけで、国民は日清・日露両戦役の時のように明確な目的意識を必ずしも自覚せず、軍部の作ったスローガンに踊らされて、夢中で戦争に突入した。しかも、独伊のほか全世界を敵にまわしながら、どこで進軍をやめるのか定見がなかった。 ・さらに重要なのは敵状を知ることである。日露開戦に先だつこと数年も前から、日本の陸海外各当局は満州におけるロシアの動静を詳細に偵察していた。 ・参謀本部は在露陸軍武官・明石元二郎大佐(のちの大将・台湾総督)に百万円の機密費を送金して、軍事情報の入手・革命運動の支持・ロシアの対日動員の妨害・シベリア鉄道の爆破・敵艦隊の反乱煽動などを手びろく行わせて業績をあげた。 ・明石は苦心の末に、レーニンと接触し、革命派に多量の武器弾薬を供給したのである。また、謀略ばかりでなく、ロシアの政治・経済・社会情勢についても、日本政府はよく研究していた。 二 ポーツマス会議 ・旅順開城の報に接すると、ルーズヴェルト大統領は「何国といえども日本の戦果を奪うことを許さぬ」と声明した。三国干渉の再演を封じたのである。彼は日本国民の勇気に感激していた。 ・日本はアメリカに代って、帝政ロシアの反動的で侵略的な暗黒政治が満州・シナに拡大されるのを阻止している。すなわち、重大な犠牲を払って米国の戦争を戦っているのだ、と考えて、陰に陽に日本を声援した。 ・日露戦争の直接的原因はロシアの満漢支配の野望だったが、その背後には、欧州列強の抗争があった。ある意味では、欧州不安が日露戦争を誘発した原因なのである。 ・欧州列強がアジア(とくにシナ)を侵略支配し、国際分割を行うのを、ルーズヴェルト大統領は不快に感じていた。 ・もっとも、アメリカの関心はフィリピン(一九〇〇年に獲得)に集中していた。 ・ロシアが満州併合の企図を進めていた時、イギリスは南阿戦争の渦中にあってアジアを顧みる余裕がなく、従って、アメリカが海洋国家代表として、大陸国群(ロシア・フランス・ドイツ)の代表格ロシアと拮抗したのは当然の成行きでもあった。 ・ロシアは陸境を越えれば、ひとまたぎでシナに侵入できるが、英米は遠くから膿を越えねばシナ市場に到達できない。 ・日本がロシアと戦ったのは、英米の利益のために、彼等のマイナスハンディキャップをゼロにしようとしたものである。日英同盟にはそういう狙いが秘められていた。 ・ロシアでは明石工作が功を奏し、旅順開城の三週後(一月二十二日)には、史上に悪名高い「血の日曜日」の惨事が起こった。 ・一九〇五年八月十日ポーツマス会議は開かれた。ロシアはウイッテ、ローゼン(新駐米大使)、日本は小村外相、高平が全権だった。 ・ウイッテのほうが小村よりも敏腕だった。米国世論は当初は日本に傾斜していたが、やがて反日親露にと変った。日本の世論工作は劣弱だった。 ・ルーズヴェルトはこの和平仲介によって、ノーベル平和賞を授けられた。 ・要するに、日露戦争の時は国家意思が統一されて軍政両略が調和していたのに、日米戦争の際は国家意思が分裂し、軍部が暴走して外交不在になったのである。 吉田茂の経綸外交 一 外交は可能性を追及する技術 ・外交は、可能性を追及する技術だといわれる。出来ることだけを目標に設定し、出来るはずのないことは目標から除外せねばならぬ、つまり、現実的な思考と行動が要請される。 ・優秀な民族であるのにかかわらず、日本国民には島国的習性があって、国際感覚が十分に発達せず、井底の蛙のように大海を知らぬきらいがある。 ・外交は国内政治の延長だから、政局が安定しなくては、強力な外交を運用しがたい。可能性が少なくなるからである。もっと、端的にいえば、国力が可能性を限定するのである。 ・日本人は情緒過多であって、政治・外交の分野にまで、おびただしく感情を移入する。つまり、感傷的に過ぎるのである。それだから、理によって動かずに情に従って揺れる。 三 戦争には負けたが外交では勝ってみせる ・日本人は主体性に乏しく、とかく権威に迎合する。 四 吉田茂の涙 ・朝鮮動乱(一九五〇年六月)が起ると、米国は占領政策を懲罰から再建へと、大きく転換した。日本は旧敵国から新友邦に変らねばならなかった。 ・米国は中ソが合作して、全アジアに共産勢力を伸張するために、北朝鮮をそそのかして、朝鮮半島の支配権を獲得しようと企図したと解釈したのである。 ・この動乱の結果、警察予備隊が組織され、やがて自衛隊に発展した。 暗号の世界と運命 三 読まれていた暗号 【私見 : 当時の日米外交の現場にいた外交官本人の発言を初めて見た。日本の暗号がすべて解読されていたことは本当だったのだ!】 第四部 外交、いまも昔も サミットの幻覚 テヘラン巨頭会談 ・ルーズヴェルトはチャーチルと会談して、欧州戦争に参加する決意を固めた。それだけに、当面、日米戦争は避けたかった。これはチャーチルにしても同じだった。だから英米共同で日本に強硬な警告を発したのである。 ・チャーチルは良識ある(と思った)日本海軍が同時に英米海軍に挑戦するはずはないと信じていた。ところが、ルーズヴェルトが焦慮するのに、アメリカの世論は依然として参戦に強く抵抗するので、彼は故意に日本を挑発し日本に攻撃させ、太平洋を入口にして大西洋(対独)戦争に参戦した。 ・アメリカが正式に参戦すると、米英ソは同盟国となり、ルーズヴェルト、チャーチル、スターリンが集まって戦争指導会議を開いた。 ・第一回は一九四三年十一月のテヘラン会談である。ソ連軍は既にスターリングラードを奪回(二月)してドイツ軍を追撃しており、米英軍はローマに進撃しイタリアは降伏(九月)していた。 ・第二回の三頭会談は一九四五年二月(ドイツ降伏の三ヵ月前)にヤルタで開かれた。 ・争点はポーランド問題だったが、ルーズヴェルトはソ連の対日参戦の代償として、千島、樺太ばかりでなく満州、旅順、大連をも提供した。戦友の中国には協議も通報もしなかった。これが悪名高いヤルタ密約であって、ルーズヴェルトの死後ホワイト・ハウスの金庫のななから発見された。 ・明らかにルーズヴェルトはスターリンにしてやられたのである。 ヨレヨレの夏服と旧式機で ・首脳会談は戦後も頻りに行われた。 ・一九五五年七月のジュネーブ会議には、アイゼンハウアー(米)大統領、イーデン(英)首相、フォール(仏)首相、ブルガーニン(ソ)首相が参集した。ブルガーニンがソ連の正式代表であるが、実権はフルシチョフ党第一書記が握っていた。 ・五三年三月スターリンが死に、六月に朝鮮休戦が成立し、五五年五月には難交渉がまとまってオーストリア講和条約が調印されて、俄かに平和共存ムードが盛りあがった。従って、四国首脳会談に対する期待は極めて大きく、「ジュネーブ精神」なるものが世界にみなぎった。 ・会談の焦点はドイツ問題だった。もとより妥協できるはずもなく、首脳会談は四日ののち空しく解散して実務を外相会議に委ねたが、これは忽ち決裂した。 ・こうして、「ジュネーブ精神」は雲散霧消してしまった。 ・同様に、一九五九年秋の「キャンプ・デイヴィッド精神」も幻想に過ぎなかった。 ・翌六〇年六月にパリで四国首脳会談――アイゼンハウアー、ドゴール両大統領、イーデン、フルシチョフ両首相――が行なわれることになったが、フルシチョフは首脳会談をボイコットした。西欧側がドイツ問題について譲歩する気配がないのに業をにやしたのである。 平和共存病 日本のマスコミほど「ジュネーブ精神」に感銘し「キャンプ・デイヴィッド精神」に共鳴したものは世界にないという事実である。日本の記者諸君は常に国際情勢の認識が甘過ぎるが、いささか平和共存病にかかっている。平和共存の美句に酔い、平和共存の標語に溺れて、冷静に現実を分析しない嫌いがある。 日本はサミットにはむかない? ・それにしても、田中訪中前のわがマスコミの中国フィーバーは凄まじいばかりで、北京へ北京へと草木もなびく状況だった。 ・国交正常化を急がねばならぬのは日本よりも中国だったのに、日本のほうが燃えに燃えて加熱していた。ライシャワー教授は「日本は昔から中国に片想いを続けている」と評したが、これでは外交的に不利である。ムード外交は国益を害する。 歴史のなかの名言 二 血と苦しみと涙と汗と ・英国の女性首相マーガレット・サッチャーは保守党が総選挙に快勝したとき、喜び躍る群衆に対して、「このように多数の議席をいただいたのだから、皆さんの好まぬことでも、国家のためなら断固として行う決意です」と語った。これが真の政治家なのです。 終戦秘話 舞台裏の四人 加瀬 ・米国の沖縄上陸が始まって鈴木内閣になり、東郷さんが外務大臣として登場して、構成員だけで火の出るような議論をしました。 ・外相になるとすぐ終戦を促進できた。信念の人ですから、がんばりとおして終戦に持っていった。その意味では東郷は大変な功労者です。 ・しかし同時に、それまでの道程に一つ一つレンガを敷いて基礎を作ったのは重光さんです。木戸さんは「終戦で一番仕事をしたのは重光だね」と言いました。 ・東郷さんは最後の場面で、本当に余人のなしがたいような勇気を発揮してやりました。しかしそこまでの縁の下の力持ちを、重光さんはやった。 東郷外相の決意 加瀬 ・ポツダム宣言が発表されたのが七月二十六日。これをどう扱うかで随分もめたんですが、こんなものは発表しちゃいかんというのが軍の主張だったのです。 ・すでに天皇陛下は東郷外務大臣に「受諾せよ」と言われていたんです。ただ受諾できるような舞台を作っていかなきゃいかんということだった。 ・ところが軍は反対する。しようがないもんですから、これは黙殺しようと打ち合わせた。打合せた。ノーコメントですね。ところが鈴木さんは新聞記者が集まったときに「日本政府は宣伝を黙殺する」と言った。黙殺すると言ってしまえば黙殺したことにならないんです。 ・果してこの言葉を使って、ソ連は「日本はポツダム宣言を拒否した」と非難した。 ・あの当時、日本がソ連に和平のあっせんをたのんだでしょう。ソ連はその和平あっせんの依頼は「基礎がなくなった。連合国から要求があるから一日も早く平和を促進するために戦争に加わる」と声明した。つまり対日参戦の口実に、日本がポツダム宣言を拒否したという建前を利用した。 ・米国の陸軍長官だったスチムソンも「こうなっちゃしようがないじゃないか。日本はポツダム宣言を拒否したじゃないか、原爆でいこう」といった。 これは不幸なことでしたね。黙殺ということは黙っているということなんでしょう。 ・不要心にそういうことを口走ってしまった。 大東亜宣言の意義 加瀬 ・四十三年の十一月五日に大東亜会議というのがあったでしょう。これはビルマ、フィリピン、インド、タイ、満州国、中国(南京政府)の首脳が集まってやったわけです。 ・いまでも歴史の本を見ますと、あれはつまらんものだ、日本の占領地域にあるそれぞれの ・いったい日本はなんのために戦争したかというとABCD包囲陣に対する自衛のために戦うということで立ったわけです。ところが自衛というのは、戦争目的としては消極的なんですね。 ・それではだめだから、なにか戦争目的を作ろうということになって、それはアジアの諸民族、従属民族を開放して、彼らに独立を与える、そういう戦争目的を一つ掲げようということになった。それが大東亜会議の目的なんです。 ・戦争は負けそうだということは判っている。負けたときに、自衛のために戦って負けたら完全な負けということになるが、しかし民族解放が目的なら、民族解放ができたというこでわれわれは戦争目的を成就したんだ、それで旗をまくことにしたらいいじゃないかという、戦争をやめるための戦争目的を作ろうというハラですね。 ・そういう点では重光はなかなか深く考えている。そういう含みがあった。それを世人は理解してくれない。 ・結局、外交と内政は一枚の銀貨の裏表ですよ。そこに含みがもう一つある。日本が占領している大東亜諸国やシナに対して非常に明るい進歩的政策をしながら、日本国内においては暗黒政治を続けるのは矛盾でしょう。どっちかがウソになる。 ・スカルノを見ても、インドのボースを見ても、あるいはフィリピンのラウレルを見てもお判りのとおり、来たものはみんな、日本の大東亜宣言に共鳴したのですよ。 広田弘毅とソ連工作 加瀬 ・大東亜宣言に民族解放をうたったならば、他国を開放して、自分の国を開放しないのはおかしてじゃないかということになる。私どもはそれをねらったわけです。それが終戦工作の大きな底流をなしている。 ・私はこのごろ日本の歴史、特に終戦後の歴史を読みますと「大東亜宣言とか大東亜会議とかはインチキだ」と書いてありますが、これは間違いです。 ・少なくとも私たちが目ざしたところは、戦争目的を大きく掲げて、それによって戦争を早めにやめるように持っていく。同時に国内的に憲兵政治、暗黒政治というものを変えてゆくための、伏線にしたつもりなんです。 ・大東亜宣言は英語で書いた。だって、あれは外国人に読ませるものです。われわれはイギリス人、アメリカ人に読ませるつもりだった。 ・あれは敵国に読ませ、あるいは世界中に読ませたなら、「これならば日本もいいじゃないか」と思う人も出てくるだろう。あるいはもっと頭のいい人なら「これが日本の戦争目的か。お前さんうまいことをやったじゃないか。その辺で戦争をやめても恥ずかしくないよ」というようなことになってくるかも知れない。そういうコミュニケーションをねらっていた次第です。 ・サンフランシスコ講和会議を経て、日本が独立を回復して最初に出た会議がバンドン会議です。アジア・アフリカ会議ですね。私はあのときの日本代表です。 ・みんなから大歓迎された。集まってきた二十数ヵ国代表がみんな私に寄ってきた。 「あの大東亜宣言はよかった」と言う。「日本のおかげで独立できたんだ。さあどうぞこちらへ、こちらへ」というわけです。そのときに「やはりあれは効果があったのだ」と思いました。 ・それから私が初代国連大使で国連に行くと、アジア・アフリカグループというのはなにをやるにしても日本が行動の規範です。みんな、大東亜共同宣言を覚えている。「あれはよかった」と言う。 ・日本では「あんなバカのものはない」と言っているが、外国ではよかったと言ってくれる。その間の落差というか、何かちぐはぐがあります。日本のマスコミというのは、政府のやることには反対で、同情がない。 マッカーサーの釈明 加瀬 ・原子爆弾が広島へ落ちたのは八月六日でしょう。ソ連は八日に参戦しているのですよ。そのときに、黙殺事件があるわけです。日本はポツダム宣言を拒否したからという理屈ではいってきたわけです。 ――広田弘毅は結局A級戦犯で死刑になったのですね。 加瀬 ・私はこれほどの人道無視はないと思います。 ・重光も東郷も戦犯、こんなことは考えられないでしょう。 ・ともかくマッカーサーが一番偉くてあの裁判をやったわけでしょう。 ・後日、マッカーサーは重光に「あなたを戦犯にしたことは間違っていた。私がしたんじゃない」という。「あれはソ連なんで、私は反対したんだ」という。釈明これ努めていましたよ。 ――日本国民に対する戦争責任の問題は別に考えなきゃならない。あの当時の政治家、軍人、官僚が国民に対してなんの責任もないとは言えませんで、これは重大な責任を負ってもらわなければならない。 加瀬 ・それならばもっと他にそういう人がいる。あの人たちがそういう犠牲になる必要があったかどうか。 |