
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2018年04月04日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
28 |
18/03 |
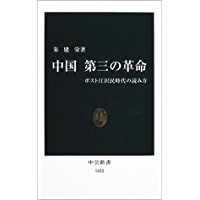 |
中国 第三の革命 |
朱建栄 |
中公新書 |
◎ |
第一章 社会構造の巨大な変化 中国の中産階級の概念 ・中国の中産階級は現在、約一億人と推定される。その職種は主に、行政管理に携わっている人、専門技術者、サービス業関係者・店員、ホワイトカラー、教師などが含まれている。 ・二〇〇一年七月、中国国家情報センターの研究者は、「これからの五年間で、中国では約二億の人口が中産階級に属する消費グループに入るだろう」と予想した。 ・そしてWTOへの加盟交渉を担当した中国側代表は二〇〇一年十二月、「WTO加盟後の中国は、十年以内に中産階級が四億~五億人になることだ」と述べた。 ・二〇〇一年末の時点で北京市民の平均年収は三五〇〇米ドル(約四五万円)に達し、上海はさらに高い四五〇〇ドル(約五八万円)になる。広東省全体では二〇〇〇ドル台だが、広州、深圳などでは平均四五〇〇ドル以上に上っている。 ・ここでいう「中産階級」の生活水準の定義は、中国の諸研究によると、安定した収入があり、自力で家と車を購入する能力を持ち、収入の一部を旅行や教育の消費に充て、大半の家庭は携帯電話、CDプレイヤー、ビデオCDプレイヤー(VCD)、テレビゲーム機、カメラを所有するグループを指すものである。 ・本書が使う「中産階級」「中流意識」「中間層」の定義 「中産階級」は経済条件によって、その社会的な地位が裏付けられた階層を指し、「中流意識」は実際の経済・生活条件が「中産階級」のレベルに至っていないが、過去や周りとの比較で生まれた一種の自己評価を指す。 「中産階級」と「中間層」は英語では「ミドルクラス」という同じ表現だが、ここでは日本語と中国語の漢字表現における両者の違いにもとづいて、「中産階級」と「中流意識の持ち主」の両者を合わせて、「中間層」としている。 新しい「中間層」の特徴 ・中産階級が増大し、貧困人口が中間層に収斂され、そして彼らが中国の政治と社会の変革を主導するという趨勢は、市民社会の形成を強力に促進していくに違いない。 ・中国は今、市民社会の入口にさしかかっている。 ・今日の先進国の市民社会のベースになる三要素 ①私的所有権が絶対的に保護され、 ②市民が互いに自由で法的に平等という原則を守り、 ③社会全体に民主主義的なルールがある、 ・ただ、中国の現状を見るにあたり、欧米の近代市民社会より、第二次世界大戦後の東アジアで形成された市民社会がもっと参考になると思う。 第四章 政治改革と「中華連邦」の可能性 WTO加盟による法治・行革の促進 ・二〇〇二年二月の時点で、最高人民法院(最高裁判所)はのべ一二二六件の司法解釈の修正を公表し、最高人民検察院も七八一件の司法解釈と規範的文書を点検し、一四〇件の廃止を決定した。 ・これほど大量の法律改正は歴史上の改革運動(一八九八年の ・中国には、法律を作っても政府の指導者や役人が勝手にそれを解釈するという「人治」社会の特徴があり、中国はWTO加盟を機に、金融、保険、電信、対外貿易など十の分野で完全な法律体系を作る一方、遵法意識を普及させ、最終的には「法治国家」を目指していくべきだ。 ・中国は西側の「三権分立」と異なる「議行合一」の態勢をとっており、国務院は憲法の枠組みの中で一定の行政法規制定権を持っている。 ・しかし行政立方は議員など民意の了承を必要とせず、国民や法人の利益を損なう可能性がある。 ・政府の各部門はルールの制定者であると同時にその執行者となるので、政府部門が職権を乱用して国民と法人の利益を侵害する可能性をどう防ぐか、この問題を解決していない。 ・今後、WTOの他のメンバー国は法律の独立と公正を主張して、過大な立法権を有する中国政府を提訴する可能性がある。 ・WTO加盟は、共産党と行政による経済と企業への介入を制限し、政府部門の役割転換、人員削減を含む行政改革、行政効率の向上なども要求している。 ・従来、共産党がすべての分野に対する指導を行うことは社会主義の原則であった。 ・「政(府)企(業)分離」と「党政分離」が中国の行政改革の中心課題として浮上してくるだろう。 ・これまで中国の政策は「朝令暮改」で、ルールが不明瞭、手続きも複雑で、管理はいいかげんといった問題点がよく指摘されてきた。 ・だが、WTO加盟後、政府の政策決定の透明度を向上させ、行政の効率と公共サービスの質を高め、官僚主義を克服し公務員自身の素質と能力を向上させるなどの努力を払わなければ、地域間の競争および諸外国との競争に負けるのは必至である。 戸籍制度の改革 ・一九五四年に制定された中国最初の憲法では「公民は居住と移住の権利がある」と明記されたが、五八年、工業化を加速するため都市部と農村部を分断し、農村人口の都市部への流入を厳しく制限する政策が採られ、「都市戸籍」と「農村戸籍」とに人為的に分けられた。 ・そして一九七五年の憲法改正で、公民が自由に移住する権利に関する条項が削除された。 ・二〇〇二年二月、国家公安部は、戸籍制度そのものを廃止することはないが、「固定の住居、仕事、生活資金の保障さえあれば国民は届出によりどこにでも戸籍を置くことができるようにするのが目標だ」と説明した。 ・都市部と農村部を分割した二元的な戸籍構造を打破し、統一的な戸籍制度を樹立することは、中国が近代国家に向かう重要な一歩になる。 深刻化する腐敗問題 ・腐敗防止対策で最も重要なのは権力に対する制限と監督である。 ・そのためには、役所に対する報道の自由を保障して、マスコミと監督機関のチェックが行われるようにし、司法を完全に独立させるなどの改革が必要だろう。 中長期的課題――社会的バランスの樹立と法治・民主化 ・「法治」は、法律の制定とともに法律の有効的で公正的な執行および国民の「遵法意識」という三つの側面から構成される。 ・今の中国では法律は次々と整備されているが、それにもとづいて腐敗と不正をチェックし摘発する検察、裁判、税務などの体制は確立されていない。 ・さらに、一般の民衆にすべて法律やルールにもとづいて行動する意識が根づいておらず、それがコピー商品の氾濫、コネの横行、腐敗の容認を助長する温床になっている。 第六章 模索される世界との協調 米中関係は安定するか ・中国は自国の歴史的経験により、カウボーイの風土から出発したアメリカには、自国の利益を守る決意と実力をはっきりと示すことがかえって妥協を図り尊敬し合う関係を可能にする、と受け止めている。 ・朝鮮戦争への中国人民義勇軍派遣、一九六五年後のベトナム戦争へののべ三十二万人の後方支援部隊の派遣、それがアメリカに中国の存在を見直させた原因だと中国国内で理解されている。 ・中国の対米強硬姿勢は主に駆け引きをするための手段である。 ・アメリカに「司法取引」をする文化があると見て、強い姿勢と決意を示してそれが妥協にこぎつけるカードにもなる、という読みがあるようだ。 ―― 完 ―― |