
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2018年08月12日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク | |
59 |
18/07 |
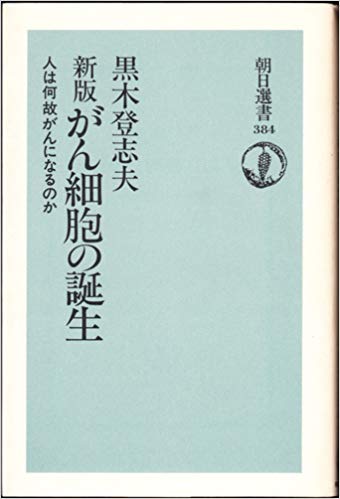 |
新版 がん細胞の誕生 |
黒木登志夫 |
朝日選書 |
◎ |
第四章 人を取り巻く発がん物質 恐れることのむずかしさ ・発がん物質というと、色素や食品添加物のように、合成されたもの、不自然なものと思う人が多いようだ。 ・そして、自然食品や有機農業に安全性を求めようとする。 ・しかし、発がん物質の大部分は自然の産物なのである。 第七章 DNAに割り込む発がん物質 代謝で化学物質が活性化 ・化学発がんのプロセス 代謝活性化された発がん物質はDNAと結合し、突然変異によりがん遺伝子を活性化させる。さらに発がんプロモーションの時期を経てがん細胞になる。 ・体はもともと自分を守るようにできている。体によって毒となるような化学物質が入り込んだ場合、それを排除するように働くのが一群の薬物代謝酵素の本来の役目である。 ・ところが、その解毒反応の途中で、あるいはそれとは別な経路の代謝で、体に有害な物質ができてしまうことがある。 ・がん細胞が生まれるか否かは、まず最初に、発がん物質の活性化と解毒化のバランスにかかっているといってもよい。 K領域から湾領域へ ・妊娠中にタバコを吸っていると、胎盤のベンツピレン代謝酵素が高くなる。これは、入ってきた発がん物質を除こうとする一種の防衛反応とも考えられるが、一方では、その酵素によって発がん物質が活性化される危険性が増すかもしれない。要は、そのバランスにかかっている。 第十章 狂った司令塔、がん遺伝子 シグナル伝達の要所要所を押さえているがん遺伝子 ・がん遺伝子の働き 細胞が増殖したり分化したりするときには、外から増殖せよ、分化せよといったシグナルがくる。 ・がん遺伝子のうちのあるものはこのシグナルそのもの、例えば増殖因子を作り出す。 ・がん遺伝子はシグナルを受け取るのに必要なアンテナ役のレセプターも作る。 ・レセプターが受けたシグナルは、Gタンパクを仲介して細胞内に伝えられる。 ・シグナルはタンパクのリン酸化の形で伝えられることもある。 ・このときのGタンパク、リン酸化酵素にもがん遺伝子が関係している。 ・シグナルは最後に核に伝えられ、情報に見あった遺伝子のスイッチが入る。 ・このスイッチを入れたり切ったりするのもがん遺伝子の役割である。 ・一言でいえば、細胞に伝えられたシグナルが遺伝子の発現となるまでのプロセスの要所要所を守っているのががん遺伝子の役割である。 第一二章 たった一個の反乱 幹部、大幹部を狙う発がん物質 ・がんになりやすい細胞となりにくい細胞がある。 ・発がんにとって、最も重要な細胞は、活発に増殖している細胞、特に組織の要となっている細胞である。 第一三章 育ての親はプロモーター 姿を現すのは最後の一時期 ・がん細胞の一生はふつう考えられているよりもはるかに長い。 ・がん細胞が一人前になるのには、一〇年、二〇年、時にはそれ以上の長い年月が必要である。 ・がん細胞の一生の四〇世代の細胞分裂のうち、最初の四分の三はひそかに進行する。そして残りの四分の一の期間に、がん細胞はその姿を現し、われわれを苦しめることになる。 ・平均していうと、人間のがんは、一カ月から三カ月で倍の大きさになる。 がん細胞の一生は約二〇年 ・がん細胞の一生は約二〇年と考えられている。 第一五章 防止の機構は幾重にも 不思議なくらいに少ないがん ・がんを研究している側からみると、どうしてこんなにがんが少ないのか、不思議なほどである。 ・食べあわせで胃のなかにできてしまうニトロソアミン、わかっていてもやめられないタバコ、間断なく降り注ぐ宇宙線、肌に焼けつく紫外線。われわれの身の回りはがんの原因で取り囲まれている。 ・突然変異の確立から考えても、がんは少なすぎる。 ・卵子と精子が一緒になり、生まれ、死ぬまでの人間の一生の間には、1016回の細胞分裂が起こるという。一兆の一万倍、一京回である。 ・細胞の世代に計算しなおすと、五〇世代(250)に相当する。 ・自然に起こる突然変異が一〇〇万~一〇〇〇万回の細胞分裂に一回程度の頻度であるとすると、一生の間には一〇億~一〇〇億回の突然変異が起こることになる。 ・もし、この計算通りだとすると、人はすべて若くしてがんで死んでしまうことになる。 ・なぜ、こんなにがんが少ないのか。何かがわれわれをがんから守ってくれているとしか考えられない。 ・免疫もその一つであろう。しかし、免疫はでき上がったがん細胞に働くだけである。 ・がん細胞が生まれる前、発がん物質が働きはじめたときから、がんから免れるような何段構えかの安全装置が隠されている。 ・体に入った大部分の発がん物質は、代謝によって解毒され、体の外に出されてしまう。 ・しかし、運悪く活性化され、細胞内のDNA、RNA、タンパク質と結合したとしても、その結合が遺伝的に何の意味もない結合であったり、あるいはあまりに多く結合して、その結果、細胞が死んでしまったりするようなときは、がんになりようがない。 ・分化し、やがて死ぬようにプログラムされている細胞が狙われたときも、同じように安全である。 ・問題は組織の ・しかし、それでもまだ大丈夫である。DNAの傷にも修正の道が残されている。 修復可能なDNAの傷 ・体にできた傷が治癒するように、心の傷がいつか癒されるように、DNAの長い鎖の上にできた傷も修復される。 ・紫外線は体の発育に欠かすことができない。子供のとき紫外線に十分にあたらないとビタミンDが不足し、くる病になってしまう。 ・しかし、紫外線を大量に浴びると皮膚がんになる。 ・紫外線には殺菌作用がある。 ・布団や洗濯物を日光で干すのは、乾燥のほかに消毒という重要な意味がある。 ・紫外線ががんを作ったり細菌を殺したりするのは、DNAに傷を作るからである。 ・紫外線は、DNAの長い鎖の上でチミン(T)が二つ並んでいるところを狙う。 ・隣り合ったチミン同士が紫外線のエネルギーによってくっつき合い、遺伝暗号としての役を果たすことができなくなってしまう。 ・このため、その遺伝子が作るはずであったタンパクができなくなり、細胞は死ぬか、あるいはがん細胞となって生き延びることになる。 ・もし紫外線によってできた傷がそのまま残るようであれば、ほとんどの人は二〇歳になる前に皮膚がんになってしまうであろう。 ・太陽光線にさらされている場所から最近は姿を消してしまうであろう。 ・しかし、人はそれほど皮膚がんにならないし、細菌はあらゆるところにはびこっている。 ・それは、細胞や細菌が紫外線によって生じたDNAの傷を修復することができるからである。 ・つまり、紫外線によってチミン同士がくっついても、それは次々に元通りの形に直されてしまう。 ・その修復のメカニズム 紫外線によって傷ができると、まずその傷の手前のところで、酵素によってハサミが入れられる。 次いで、別のハサミ(酵素)が傷のところを向かい合ったDNA鎖から切り外していく。 この切り外しは、傷からかなり隔たったところまで行われる。 切り外された部分のDNAは、本来、二本の鎖であるべきところが一本鎖になっている。 しかし、DNAは、向かい合った部分さえあれば正確にコピーを作れるような仕組みになっているので、すぐに元のDNAが作られる。 このような修復を「除去修復」と呼んでいる。 ・除去修復は、紫外線によって生じた傷にだけ働くのではない。発がん物質のような化学物質によってできた傷を治すこともできる。最も基本的な修復法といえよう。 がんは基本的には遺伝子ない病気 ・体を構成している細胞は大きく二つに分けられる。精子とか卵子を作る生殖細胞と、それ以外の体の部分を構成している体細胞である。 ・ほとんどすべてのがんは体細胞にできる。 ・体細胞のもっている遺伝子に突然変異が起こり、その細胞が分裂して次の細胞に突然変異が伝えられていく。 ・そのためにがんになったとしても、がん細胞はその人の一生とともに終わってしまう。次の世代には何の影響も及ぼさない。 ・ところが生殖細胞に突然変異のような遺伝子の変化が起こると、次の世代に遺伝する可能性がある。 ・しかし大部分の変異は致死的に働くため、受精が不可能であったり、受精したとしても胎児は育つことなく流産してしまう。一種の自衛策であろう。 ・なかには子孫に受けつがれるような遺伝子の変化もある。生物はそのような突然変異の積み重ねによって長い時間をかけて進化してきた。 ・しかし、同時に都合の悪い遺伝子の変化ももちこんだ。いわゆる遺伝病である。 ・本当に胃がんの家系といったものがあるだろうか。 ・胃がんそのものは遺伝しないが、胃がんになりやすい体質はある程度遺伝するのかもしれない。 ・胃がんになりやすい生活習慣、例えば塩からい味を好むといった習慣が「おふくろの味」として受けつがれ。「遺伝」していくこともあろう。 ・がんに限らずどんな病気にも、遺伝的な面が多かれ少なかれ存在する。 ・病気になりやすい体質とか素因とかは、親と子で似ていることが多い。 第一六章 厳しい監視網を突破した内乱 免疫力の落ちたスキに多発 ・細菌やウイルスのような敵が入り込むと、白血球やリンパ球などの免疫細胞が素早く出動してたちまち取り押さえてしまう。 ・一度入り込んだ敵の顔は決して忘れることがなく、二度目にやってきたときには、その場でつかまえ、侵入させることはない。免疫が成立しているからである。 ・がん細胞も体にとっては敵のはずである。しかし細菌やウイルスと違って、外から攻め込んできた敵ではない。 ・腎臓や心臓の移植手術をした後にがんができてくることもある。 ・移植をするときには、あらかじめ、いろいろな薬を注射して免疫力を抑えておく。そうしないと、せっかく移植した臓器が拒否反応によって脱落してしまうからだ。 ・われわれの体の中では、いつもがん細胞が生まれているのかもしれない。しかし、生まれてきたがん細胞の多くは、すぐに免疫細胞に見つかって殺されてしまう。免疫細胞は立派に役目を果たしているに違いない。 ・それなのに、成長して姿を現したがん細胞は、もはや免疫細胞のいうことなどには耳もかさない。自分勝手な道を歩きはじめる。 ・正体を現したがん細胞は、いわば免疫細胞との戦いに勝ち残ったがん細胞である。 負け戦のいいわけ ・がん細胞は協力強力である。リンパ球とがん細胞が一対一で戦ったのでは絶対に勝ち目がない。 ・一個のがん細胞に対して一〇〇個のリンパ球が束になってかかって、やっと勝つといわれている。 ・われわれの体の中にあるリンパ球の数は全部合わせて一兆(1012)個、重さにして一キログラムぐらいはある。 ・そのなかでがん細胞と戦うように訓練されたリンパ球はごく一部にすぎない。大きくなったがん組織に対して量的にもとても追いつかない。 第一七章 細胞社会の異端者、がん細胞 試験管のなかの寿命にも限界が ・ヒトが永遠に生きつづけることができないのと同じように、細胞にも寿命がある。 ・個体としてのヒトは、およそ百歳が寿命の限界であるが、細胞としての寿命は一〇カ月しかない。 ・だれも死から逃れることはできない。不老長寿の薬は、錬金術と同じように、永遠の夢でしかない。しかし。細胞は寿命を免れることができる。がん細胞になればよいのだ。 礼儀知らずのあばれん坊 ・正常の細胞は、隣の細胞がどんな細胞であるかを見分けて行動するのに、がん細胞はそんなことにはお構いなしである。 ・体のなかでがん細胞はだれにも邪魔されずに動きまわり、隣の組織に入り込み、あげくの果て、遠く離れた臓器にまで飛び火する。 ・正常細胞は、細胞同士が接触したとき、お互いの行動を阻止するような信号を出しあい、それによって、秩序ある細胞社会を作っている。しかし、がん細胞にはそれがない。接触してもわれ関せずと、行動をつづける。 第一八章 がんにならないための暮らしの知恵 がん研究者は多いか ・不安は、よく知っているらではなく、不確かな知識から生ずる。 普通のおじさん、おばさんのがんの原因 ・消費者運動に関心をもっている主婦は、食品添加物と農薬ががんの主な原因と考えている。 ・しかし、がんの疫学の研究者によると、人間のがんの最も大きな原因は食事とタバコである。それぞれ原因の三五パーセント、三〇パーセントを占めているという。 ・食品添加物や農薬ががんの原因と無関係というわけではないが、その比重は小さく、一パーセント以下にすぎない。 ・主婦たちが食品添加物・農薬を原因と考えているのは、一九七〇年代からはじまった反公害運動の一つの流れであろう。 ・毎日の何気ない生活習慣が積もり積もってがんとなって現われてくるのであろう。 生命線かえる一箱のタバコ ・がんを予防する決め手は禁煙である。ヒトのがんの三〇パーセントはタバコによる。 ・タバコが原因となるがんは肺がんだけではない。咽頭がんは肺がん以上にタバコの影響を受ける。胃がん、食道がんも喫煙者に多い。 ・タバコから直接出る煙には、いったん吸いこまれてから出てくる煙よりもはるかに多い量の発がん物質が含まれている。 ・家庭でいつも夫のタバコの煙に悩まされ、慣らされている妻は、タバコを吸わない人の妻に比べて二倍も肺がんが多い。 ・タバコによる税収は多い。 ・しかし、病気、火災などのタバコによる被害は、タバコによる収入を大きく上回ることである。 ビタミンCで防ぐニトロソアミン ・発がん物質は、その量はごく少なく、また非常に弱いものかもしれないが、あらゆる食物のなかに含まれている。 ・熱を通して調理すれば多かれ少なかれ発がん物質ができてくる。 ・植物の成分のなかにも発がん性のあるものがみつかってい。 健康問題は結局常識問題 ・がんの予防に必要なビタミンの量はそれほど多くない。 ・新鮮な野菜と果物を毎日たっぷりと食べれば十分である。 ・それに野菜、果物には消化しにくい繊維分がたくさんある。食物繊維が大腸がんの予防によい。 ・がんを予防するための生活の知恵はあまりにも常識的である。 ・タバコをやめる。野菜と果物をたくさん食べる。塩分は少なく、太らないように気をつける。何の秘密も秘訣もない。 ・健康とは、結局、常識を基礎としているものだろう。 ―― 完 ―― |