
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2019年10月27日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き&コメント |
38 |
19/09 |
昭和天皇の終戦史 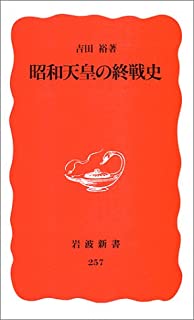 |
吉田 裕 |
岩波新書 |
◎ |
Ⅰ 太平洋戦争時の宮中グループ 1 開戦をめぐる宮中グループの動向 近衛の「転向」 ・四〇年七月に第二次内閣を、翌四一年七月には第三次内閣を組織した近衛文麿は、軍事的な勝算が立たないことから、対英米開戦には一貫して消極的な姿勢をとった。 ・このため近衛は、四〇年九月の北部仏印進駐にみられるような日本の冒険主義的な南進政策の結果、英米との間に軍事的緊張がたかまると、アメリカとの妥協の道をさぐる外交交渉=日米交渉にのり出すが、そのなかで近衛は、アメリカ側の主張する中国大陸からの日本軍の撤兵という要求を基本的にはうけ入れることで対米戦を回避しようとする。 ・しかし、陸軍を代表する東条英機陸相が撤兵に強硬に反対したため、第三次近衛内閣は四一年一〇月に総辞職し、かわって主戦派の東条英機陸軍大将が内閣を組織することになった。 ・近衛は、軍の日米開戦論と対立して内閣を投げ出して以来、「革新」派から離脱し、「現状維持」派=「親英米」派に転向した。 ・事実、近衛は、実際に戦争が開始され、初期作戦の成功に国中がかわいていた段階でも、選挙区に対する悲観的見通しを変えようとはしなかった。 天皇の開戦決意 ・天皇がある段階までは、対米開戦と、それを強硬に主張する陸海軍の主戦派の動向に大きな不安をいだき続けていたことは事実である。 ・しかしその天皇も、最終的には対英米開戦をやむなしとする方向に大きく傾いていった。 天皇の東条への信任 ・天皇が東条英機を信任し、その内閣を強く支持したことも、大きな政治的意味をもった。 2 戦局の悪化と近衛グループの台頭 近衛の上奏 ・四五年に入って、近衛は本格的な戦争終結工作に着手する。 ・ちょうどこの頃、行きづまった戦局を打開するための方策について、天皇が重臣層から意見を聴取することが決まった。 ・だが、明確な政治的方向性をもって天皇に上奏したのは、やはり近衛だけだった。 ・上奏文のなかで近衛は、「敗戦は遺憾ながら最早必至なりと存じ候」として敗戦をはっきりと予言し、敗戦にともなって「共産革命」が発生し、天皇制が崩壊するという最悪の事態を回避するために、ただちに戦争の終結に踏みきることを主張したのである。 ・近衛のこの上奏に対し天皇は、「もう一度戦果を挙げてからでないとなかなか話はむずかしいと思う」と述べて、近衛の提案に消極的な姿勢を示した。 ・天皇はまだ、戦局の挽回に期待をつないでいたのである。 ポツダム宣言の発表 ・ポツダム宣言受諾の動きの中心となったのは東郷茂徳外相、米内光政海相、鈴木貫太郎首相などであり、彼らは天皇の同意を得た木戸内大臣と連携しながら軍の強硬派を押えこもうとした。 ・しかし、八月九日に開催された最高戦争指導会議では、「国体護持」だけを条件にして直ちにポツダム宣言を受諾すべきだとする首相・外相・海相などと、「国体護持」にくわえて、軍隊の武装解除は日本側で自主的に行なう、戦争犯罪人の処罰も日本側で行なう、保障占領は行なわない、という四条件付き受諾を主張する ・ここにいたって木戸内大臣たちは、決定を御前会議にもちこみ、天皇の「聖断」によってポツダム宣言の受諾を決定することを決意して、周到な裏面工作を開始した。 ・この結果、八月九日の深夜から翌一〇日にかけての御前会議において、天皇の「聖断」によってポツダム宣言の一条件付き受諾が決定されたのである。 「聖断」による戦争の終結 ・アメリカ政府が世論の反発をひどく気にしながらも、天皇制に対して宥和的な態度に出たのは、降伏後の日本の占領統治の上で天皇を利用するのが有利であるとする判断が部内でしだいに有力になってきたからである。 ・同時に、そこには、できる限り早期に日本に降伏をうけ入れさせることによって、対日戦に参戦してきたソ連の極東における影響力の拡大を阻止したいという思惑がからんでいた。 「国体護持」のための「終戦」 ・ポツダム宣言の受諾の方向で動いた人々のなかには、これ以上戦争を継続すれば「国体」がいわば内側から崩壊するという危機感が強かったことである。 ・敗戦時の指導者のなかに、「国家の運命以上に皇室の安泰を考え」る傾向があった。 宣言受諾をリードした人々 ・「国体護持」だけを条件にしたポツダム宣言の即時受諾という方向に踏みきらせたのは、近衛であり、近衛と密接な協力関係にあった重光葵や高松宮 ・また、トップ・レベルの指導者を直接補佐する立場にあった、より若い世代の官僚グループのなかに、ポツダム宣言の即時受諾を主張して一貫した活動を展開した人々がいた。 ・宮中では内大臣秘書官長の松平康昌、政府部内では鈴木首相を補佐した内閣書記官長の ・彼らは相互に密接な連絡をとりあいながら、ポツダム宣言の受諾に向けて事実上全体の状況をリードしたのである。 ・それだけではなく、彼らは、松平・迫水・加瀬のように、敗戦後における天皇の免責工作でも、水面下で大きな役割を果たすことになる。 近衛の戦争責任論 ・戦争終結に至る政治過程をみてみると、近衛文麿が重要な役割を果たしていたことが理解できる。 ・近衛文麿は、かなり明確な戦後構想をもって行動した数少ない保守政治家の一人だった。 ・近衛は敗戦によって戦争責任の問題が政治的にも大きな争点になることを早くから見通しており、連合国による天皇の戦争責任の追求が天皇制の廃止要求にまで発展するのを阻止するため、戦争責任のすべてを軍部、とくに陸軍に意図的に押しつけることを決意していたのである。 近衛の「国体」観 ・近衛の戦後構想をみる上で重要なポイントとなるのは、彼が「国体」(天皇制)と天皇個人を区別する思考方法を身につけていたことである。 ・天皇の絶対化・神聖化が極限にまでおしすすめられることによって、トップ・レベルの指導者までもがそうした硬直した天皇観によって自縄自縛におちいっていた十五年戦争期にあって、近衛の戦後構想は、他の指導者たちのそれがもちえなかったリアリティを確保することができた。 Ⅱ 近衛の戦後構想 2 保守勢力の敗戦への対応 閣議決定の限界 ・この時期の日本の保守勢力は、戦争責任の問題をめぐって常に受動的な対応に終始しており、情勢に対する的確な見通しを欠いたまま、むしろ状況にふりまわされている感が強い。 ・そうしたなかにあって、はっきりとした見通しをもって行動していたのはやはりここでも近衛文麿であった。 3 占領期の近衛 逮捕、そして自殺 ・アメリカ戦略爆撃調査団の尋問のなかでアメリカ側は、近衛の予期に反して、首相としての近衛の日中戦争に対する政治責任を厳しく追及した。 ・他方、GHQの内部では、日本のファシズム化の過程で近衛が果たした重要な役割を強調した覚書を、GHQの政治顧問G・アチソンに提出していた。 ・この覚書はアチソンによって採用され、近衛は戦犯容疑者のリストに加えられる。 ・その結果、一二月六日にはついに近衛に対する逮捕命令が発せられるが、近衛は巣鴨拘置所への出頭予定日の一六日未明、自宅で服毒自殺した。 ・日本の侵略戦争に対して厳しい態度をとる国際世論に押されるかたちでGHQの側も近衛の対アジア責任を問題にした。 ・保守勢力のなかで最もリアルな政治感覚をもっていた近衛でさえ、アジアに対する戦争責任の問題に関してはまったく無自覚であった事実は記憶されてよい。 ・その意味でも近衛の最大の「つまづきの石」は、アジアの問題だったといえるだろう。 Ⅳ 「天皇独白録」の成立事情 5 松平康昌の役割 松平と加瀬俊一 ・「独白録」は、東京裁判対策を強く意識しながら、直接的にはGHQに対して、天皇に戦争責任がないことを「論証」するために作成された政治的文書である。 国内の天皇退位論 ・東大の南原繁総長 「国をあげての戦争に際して、一億総懺悔ということでは、結局だれも責任をとらない、責任回避です。責任にはおのずから順序がある。小学校の先生は先生で、大学の教師は大学の教師として、ことに国を代表した天皇には、おのずから道徳的・精神的な責任がある」 Ⅴ 天皇は何を語ったか 5 「独白録」をめぐる人脈 フェラーズの反共主義 ・キーナン首席検察官 「私は日本の天皇を裁判にかけないこと、また証人として法廷に出廷させないことに努力するのが第一の目的だ。今一つは、日本の再軍備を勧めることだ。アメリカは戦いに勝った。しかし勝ちに乗じて日本の軍備を全廃すれば、アジアの赤化は日を見るより明らかである」 ・反ソ反共主義は、アメリカにおける「親日派」「知日派」の思想的特質の一つであって、彼らは占領政策を効果的・効率的に実施するために天皇制を利用しようとしただけでなく、共産主義の浸透に対する防壁という点でも、天皇制を温存しようとしたのである。 Ⅵ 東京裁判尋問調書を読む 2 尋問への協力 尋問への対応の特徴 ・第一には、相互に見解や思惑のちがいをはらみながらも、ほとんどの供述が、天皇を擁護し、戦争責任を東条や武藤などを中心にした少数の陸軍軍人とその協力者にになわせるという方向性をもっていたことである。 ・第二には、ほとんど全部の日本人関係者が太平洋戦争の正統性を否定した上で、自分はその戦争に反対だったと供述していることである。 ・このことは戦争責任者を名指しすることと、いわば表裏の関係にある。 ・具体的にいえば、太平洋戦争そのものを「自存自衛」のための戦争あるいは「大東亜共栄圏」建設のための戦争として正面から日本の立場を擁護しているのは、管見の限りでは、みずから責任を負う覚悟を決めていた東条英機と嶋田繁太郎の二人だけである。 ・同様に東京裁判の公判廷の場でも、ほとんどの被告が自分はあの戦争に反対だったと陳述している。 ・右翼の指導者で被告の一人でもあった大川周明は、日記に、「いずれにもせよ、戦争は東条一人で始めたような具合になってしまった。誰もかれも反対したが戦争が始まったというのだから、こんな馬鹿げた話はない」と書きつけている。 Ⅶ 行動原理としての「国体護持」 2 英米との協調の重視 協調と侵略 ・天皇や宮中グループが、英米との協調を重視する立場に立っていたことは、疑問の余地のない事実である。 ・しかし、その一方で天皇は、中国大陸における日本の権益の維持・拡大を日本の当然の国是とみなしていた。 ・ここからは、「独白録」のなかの、「満州は田舎であるから事件が起っても大した事はないが」という印象的な発言が示しているように、対英米関係を悪化させない範囲での中国に対する軍事力の発動は容認するという姿勢が生まれる。 ・牧野伸顕は、戦争の拡大や長期化にはきわめて慎重な姿勢を示す半面、対中国戦争を、過剰な人口と食糧不足に悩む日本の生存のための戦争として、あるいは中国側の組織的な反日運動に対する反撃として、正当化する傾向をもっていた。 3 国体至上主義 「穏健派」とは ・「穏健派」全体にほぼ共通する性格 十五年戦争の時期に「親英米派」「現状維持派」などと呼ばれたこのグループは、本来、軍部、とくに陸軍の推進する対内・対外政策に対して批判的な集団であり、対外的には英米との協調を重視し、体内的には「高度国防国家」の構築という軍部の要求に慎重な姿勢をとった。 彼らは、対英米関係を悪化させる可能性のある軍事冒険政策に対しては、たしかに抑止的な態度をとったが、日本をアジアにおける「盟主」の位置に置き、「大日本帝国」のアジアにおける権益の維持・拡大のためには軍事力の行使も辞さないと考える点では、軍部の強硬派とも共通する面をもつ、「帝国意識」の持ち主である。 同時に、彼らは、思想的には強烈な反共主義に裏打ちされた国体至上主義者のグループであり、その社会的出自も概して高い。 ・この「穏健派」の評価いかんによって、日本の近代史はまったく異なった像をむすぶが、私見によれば、当初、対米英協調路線と政党内閣制を支持していたこのグループは、十五年戦争の経過のなかで次第にそのスタンスを変化させ、軍部の路線との間の距離を縮めていった。 ・そして、そのなかのかなりの部分は、天皇=木戸を中心にした宮中グループも含めて、最終的には軍部との間にゆるやかな政治ブロックを形成したと考えられる。 ・十五年戦争の時期は、「軍部独裁」が成立してゆく時期と考えられているが、軍部とてオールマイティの権力を握っていたわけではなく、「穏健派」の黙認や追認、あるいは支持や協力がなければ、軍部の推進する路線は国策とはなりえなかったのである。 ・さらに、敗戦という危機的状況の中で、「穏健派」は、東京裁判への積極的協力にみられるように、すべての戦争責任を軍部を中心にした勢力に押しつけ、彼らを切り捨てることによって生き残りをはかろうとした。 ・その意味では東京裁判は、日本の保守勢力の再編成の一環として位置づけることができる。 ・そして、この「穏健派」のなかから、アメリカの対日政策の転換に呼応するかたちで、占領政策の「受け皿」となる勢力が成長してくるのである。 ・四八年一〇月の第二次吉田茂内閣の成立は、そうした「受け皿」の形成を意味していた。 結 再び戦争責任を考える 封印された天皇の戦争責任 ・天皇・宮中グループが、四六年初頭の危機的状況を乗り切ることができたのは、冷戦という国際環境によるところが大きい。 ・彼らは、冷戦的状況を促進し、東西対立を固定化しようとする勢力と結びつき、これと一体化することによって、かろうじて危機を乗り切ることができたのである。 ・しかし、このような形での「戦後処理」のあり方は、戦後日本の戦争責任論に深刻な影響を与えることになる。 ・一つには、天皇の戦争責任が完全に免責され、天皇の側からの自己の責任に対する積極的な言及がまったくなかったことは、国民の間に「何か割り切れぬ空気を残す」結果となった。 ・さらに、天皇の戦争責任の問題が封印され、マスコミや学校教育のレベルで事実上タブー視されたことは、この国の戦争責任論の展開をきわめて窮屈なものにした。 ・本来、戦争責任論とは、政策決定の当事者であった権力者の責任を追及するという次元だけにとどまらない、裾野の広がりをもった議論である。 ・それは、戦争の最大の犠牲者であった民衆にも、戦争協力や加害行為への加担の責任を問い直すものだ。 ・侵略戦争と天皇制に一貫して反対したという点からいえば戦争責任とは最も遠い位置にあるコミュニストとその党=日本共産党に対しても、なぜ、より有効な反戦闘争を組織することができなかったのかという点で、戦時下における自己の思想と運動に関する真摯な自己点検を強いるのである。 ・また、右翼に関しても、それが戦後、思想運動として生き残ろうとするかぎり、敗戦の原因や天皇制のあり方についての本質的な議論が必要だったはずだ。 ・しかし、国家元首であった天皇の責任がタブー視され、戦争責任論の中に最初から大きな例外規定が設けられることによって、戦後の戦争責任論は国民的広がりを欠く結果となったのである。 ・もう一つの問題は、すべての戦争責任を軍部に押しつけることによって政治的なサバイバルに成功した「穏健派」のなかから、戦後の保守政治をになう主体が成長してきたことである。 ・この結果、パワー・エリートの人的構成という面では、戦前―戦後の「断絶」より、「連続」が主たる側面となった。 ・同時にこのことは、「穏健派」の政治的スタンスをある意味ではもっともよく代表していると考えられる天皇の戦争責任が封印されタブー視されたこともあいまって、「穏健派」全体の戦争責任、とくにアジアに対する戦争責任が曖昧にされたことを意味していた。 ・以上のことを歴史認識の問題としてとらえ直してみると、わたしたち日本人は、あまりにも安易に次のような歴史認識に寄りかかりながら、戦後史を生きてきたといえるだろう。 ・すなわち、一方の極に常に軍刀をガチャつかせながら威圧をくわえる粗野で粗暴な軍人を置き、他方の曲には国家の前途を憂慮して苦悩するリベラルで合理主義的んなシビリアンを置くような歴史認識、そして、良心的ではあるが政治的には非力である後者の人々が、軍人グループに力でもってねじ伏せられていくなかで、戦争への道が準備されていったとするような歴史認識である。 ・そして、その際、多くの人々は、後者のグループに自己の心情を仮託することによって、戦争責任や加害責任と言う苦い現実を飲みくだす、いわば「糖衣」としてきた。 ・しかしそのような、「穏健派」の立場に身を置いた歴史認識自体が、国際的にも大きく問い直される時代をわたしたちはむかえている。 ・すなわち、社会主義諸国の崩壊に起因した冷戦体制の解体によってそもそも冷戦期の産物である「穏健派」史観そのものの見直しが不可避となった。 ・また、アジア諸国との関係も、東京裁判の段階とは大きく変った。 ・東京裁判の段階では、日本の侵略の主たる対象となったアジア諸国は、いまだ独立か建国の途上にあって、その国際的発言力もきわめて小さなものでしかなかった。 ・東京裁判は、これらの諸国の意向をほとんど無視することによって初めて成立することができたのである。 ・しかし、そのアジア諸国もそののちしだいに国際的な発言権を強め、アジア諸国との関係の安定化を求める日本政府としても、これらの国々の対日要求にある程度の考慮を払わざるをえない状況になってきている。 ・そうしたなかで、これらの国々の間から、日本の「戦後処理」に対する批判の声が急速に高まりつつあるのが現状である。 ・こうした声に誠実に対応しようとするかぎり、わたしたちは、日本の戦後処理を支えた歴史認識そのものを、みずからの手で問い直さなければならないのだと思う。 ―― 完 ―― |