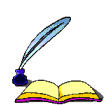
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2022年03月14日 月曜日 】
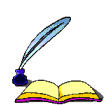
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書き |
1 |
22.01 |
臨床の知とは何か 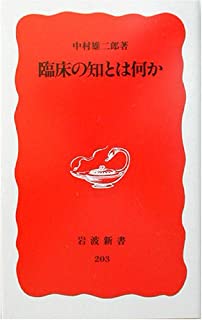 |
中村雄二郎 |
岩波新書 |
◎ |
序文――なぜ‹臨床の知›なのか ・一般的にいって、近代科学が無視し、果ては見えなくしてしまった‹現実›あるいはリアリティとは、いったいなんであろうか。 ・その一つは‹生命現象›そのものであり、もう一つは対象との‹関係の相互性›(あるいは相手との交流)である。 ・あるいはひとは、生命現象だったら近代科学は充分扱ってきたではないか、というかもしれない。たとえば、分子生物学やそれにもとづいた‹ヒト・ゲノム›(人間の遺伝子)研究のような輝かしい成果があるのだから、と。 ・けれども、操作主義の極致としての分子生物学が捉えているのは、原子論的に分子のレヴェルに還元された生命体の要素とその機械論的な組合わせであって、生命現象そのものでも、生命現象の固有の、あるいは少なくとも特徴的な働きでもない。 ・したがってそこでは、生命現象のもたらす意味の発生、自律的な振る舞い、自己創造などが真っ向から扱われることがないのである。 Ⅰ ‹科学›とはなんだったのか 1 学問の危機・地球の危機 ・今後、持続つまり生き残りということが究極の基準になるので、‹生命(生活)の質›の意味するところが問いなおされざるをえない。 Ⅳ 臨床の知の発見 2 臨床の知の仕組み ・‹臨床の知›とは、狭い意味での医学的な臨床の知ではなく、近代科学への反省のもとに、それが見落とし排除してきた諸側面を活かした知のあり方であり、学問の方法である。 ・‹臨床の知›は、科学の知の三つの構成原理を、 (1)普遍主義、 (2)論理主義、 (3)客観主義、 と呼ぶとき、そのそれぞれに対して、 (1)コスモロジー、 (2)シンボリズム、 (3)パフォーマンス、 と私が呼ぶものを構成原理としている。 Ⅴ 医療と臨床の知 2 医療の現在を考える ・健康とは、人間が生命有機体かつ精神=身体的存在として、日常生活に支障のない或るレヴェル以上で、外界や他者に対して、‹リズムとバランスを保っている状態›、より正確にいえば、‹相対的に安定した自己調節機能(ホメオスターシス)を保っている状態›である。 Ⅵ 生命倫理と臨床の知 1 脳死と臓器移植の問題 ・アメリカで発達したバイオエシックス(生命倫理)理論は、アメリカの社会事情、医療事情のもとに権利思想と功利主義と人道主義の顕在化された鍔ぜり合いによって形成され、明確化されたものである。 ・アメリカではバイオエシックスが、多発した医事紛争を契機に、一九七〇年頃になって、患者による人権の主張と医者側の責任限定との兼ね合いとして形成され成立したことは、忘れられてはならない。 ・そしてその背景には、五〇 ― 六〇年代以降の医学や生物学の新技術の開発・実現によってもたらされた一連の出来事、すなわち、遺伝子操作の実験の倫理綱領作成、バーナード博士による心臓移植、カレン・クインランの尊厳死判決、試験管ベビーの誕生、生命維持装置の発達、などがあったのである。 ・一九六八年に、「ハーバード大学脳死判定基準」がつくられた。 ・これまでの三徴候(脈拍・自発的呼吸・瞳孔反射の停止)に代えて、 ‹不可逆的な昏睡› を死の新しい定義として採用し、実質上、 ‹脳死› を以て人間の死としたのである。 ・その内容は、 (1)刺激に対する無反応 (2)自発的呼吸の停止 (3)反射の消失 (4)脳波の平坦化 から成っていた。 ・しかも、この定義が必要である実際的理由として、なんと、不可逆的な昏睡が永続する重荷から患者・家族・ベッド待ちの患者を救うこと、移植用の臓器入手をめぐる論争を終わらせること、の二つがはっきり挙げられている。 ・いずれも、無意味な延命をやめる権利を医者に与えるために言われているわけであるが、 ‹ベッド待ちの患者› といい、 ‹臓器入手› といい、なんとも即物的な表現である。 ・そして、この ‹不可逆的な昏睡› という規定がなにを意味するかをめぐって、その後の議論がおこなわれることになる。つまり、脳死と見なす上でもっとも適切なのは、脳幹死なのか、全脳死なのか、それとも大脳死なのか、というかたちである。 ・八一年の「アメリカ大統領倫理問題検討委員会」が次のような「死の判定基準」を提出した。 ・それによると、基準は二本立てになっており、伝統的な心臓死による死の判定をA、脳死による死の判定をBとしている。 A 循環および呼吸機能が不可逆的に停止した個人は死亡したとする B 脳幹を含む脳全体のすべての機能が不可逆的に停止した個人は死亡したとする。 ・アメリカ大統領委員会の基準では、死の判定は、一方では暫定的に伝統的な心臓死の考え方を許容しつつ、他方で全脳死によって脳死説を確立しようというやり方をとっている。 ・そして、アメリカでの脳死をめぐる議論を見ていると、そこには、ある顕著な傾向が見られる。それは、脳死の内容として、根本的には ‹人格の消失› を重要視し、そのために、 ‹大脳› の不可逆的な機能の喪失を問題にするつよい傾向である。 ・このような傾向のうちに潜む考え方こそ、日本において多くの人々が脳死説に対して違和感を抱く大きな原因になっていると思われる。 ・「ハーバード大学脳死判定基準」に触れて述べた ‹ベッド待ちの患者› や ‹臓器入手› ということばで代表される実用主義あるいは功利主義と、進んで自分の臓器を他人の生命を救うために役立てるというキリスト教的人道主義、およびそれと表裏をなす道徳的主体としての人格的同一性の重視とが結びついていること、そこに、アメリカでの脳死論の基本型あるいは支配的考え方が成り立っている。 ・日本の場合を考えてみると、一方では、科学的医学と医療技術の急速な進歩によって、技術的実用主義がひとり歩きをしている半面、他方では、それと対極に位置する伝統的な死の観念が習俗のなかにもち続けられ、その両者が併存してきた。 ・ここで、伝統的な死の観念について一言しておくと、とくに重要な意味をもつのは、外地で戦死した肉親の遺骨収集や飛行機事故の際の遺体・遺品の重視に見られる、遺族の執着の強さである。 ・そこにあるのは、むしろ、霊肉二元論ならぬ霊肉一元論あるいは鈴木大拙のいう ‹日本的霊性› の立場であろう。 ・またわが国では、人格性の原理にもとづく権利・義務関係が、建前として存在すると同時に、共同性の原理にもとづく実感的な相互性が、本音として根強く生きてきたという事情がある。 ・日本ではようやく七四年になって、日本脳波学会の「脳死と脳波に関する委員会」が脳死判定基準をうち出した。 ・さらに八五年になって、それへの再調査のかたちで厚生省「脳死に関する研究班」によって脳死の判定基準がまとめられた。 ・両者とも全脳死の立場を採り、慎重な基準を設けてはいるが、アメリカの場合とちがって、脳死を以て人の死とするかどうかについては触れられていない。 ・厚生省基準では、 (1)深い昏睡 (2)自発的呼吸の消失 (3)瞳孔の固定 (4)脳幹反射の消失 (5)脳波の平坦化 (6)以上の条件を充たした上で六時間経過すること が挙げられている。 ・自分の意見 一、≪脳死と臓器移植、とくに脳死の問題がわれわれ現代人にとってかぎりなく重いのは、人類史上、人間の死とはなにかがここにはじめて厳密に問われることになったからである。≫ ・一般には、伝統的に脳死の判定というのは、俗には、‹息をひきとる›‹脈がふれない›‹冷たくなる›ということを目安に、かつては家庭医によって、いわば大らかな死の判定がおこなわれてきた。 ・だから、そのときには、生と死の境界は、さほど明確ではなく、また、特別な場合を除いて、厳格に決める必要もなかった。 ・したがって、よく言われる脳死を選ぶか、それとも心臓死を選ぶかというのは、正確にいえば、二つの対立する基準の間の選択ではない。 ・それは、否応なしに人類が迎えた新たな文明的条件のなかで、はっきりと死と向かい合うか、それを回避するか、ということなのである。 ・脳死そのものは、全死亡者数の一パーセント弱に見られるにすぎないにもかかわらず、われわれが脳死を決して希少例あるいは例外として片付けることができないのは、脳死が、あとに述べる終末医療や臓器移植との関連を含めて、このように現代において人間の置かれた位置をきわめて凝縮的にあらわした問題だからである。 二、«脳死の判定はあくまで医療行為の一環であって、厳密科学(精密化学)の対象ではなく、したがって、脳死の判定に百パーセントの正しさを求めるのは、むしろ一つの逸脱である。» ・脳死の判定が医療行為の一環であるというのは、脳死の判定は、一般に終末医療においていつレスピレーター(人工呼吸器)をはずすかということの決定と密接にかかわり、また、とくに臓器移植の際に、生きているドナー(臓器提供者)を誤って死者と見なさないための判定である。 ・脳死の判定に百パーセントの正しさを求めることは、少なくとも次の三つの点から不都合である。 ・第一には、現代の医療行為のなかで否応なくバランスの求められるか科学性と臨床性との一方を切り捨てることになるからである。 ・第二には、判定に科学的知のもつ普遍性・論理的一義性・客観性を要求すること自体が、個々のケースについて医者の決断を不要にして、その責任を解除することになるからである。 ・第三には、そのような要求や硬直した批判が、問題の根底にある医者への不信を克服しうる、開かれた場所に、医者を誘い出さないどころか、逆に医者をいたずらに自己防衛的にしてしまうからである。 三、«脳死の問題がわが国において、実質的な進展をほとんど見せず、いかにも不毛に終わっているのは、この問題を総合的に考えて、その医療上、社会上の緊急性から、事態を少しでも前進させようとする方向で、論議が進められていないからである。» ・最初私は、対立は先端医学を推し進めようとする医者と患者の人権を最優先させる法律家の間で起こるものと思っていた。 ・ところが事実は、そうではなくて、概して、同じ医学の領域でも、病理学者と臨床医学者との間で、また同じ法律学者の領域でも、刑法学者と民法学者との間で、それぞれ慎重論と積極論とが対立することになった。 ・病理学的思考と刑法学的思考が結びつくのは、両者が不変性や客観性を重んじ、したがって、間違いの起こらないように、厳密な基準の決定を要求するから、当然といえば当然である。 ・また、臨床医学的思考と民法学的思考が結びつくのは、両者が個別性や主体性を重んじ、したがって、自己決定と自他相互の間の不都合のなさが優先されるから、当然ではある。 ・しかし問題は、病理学的・刑法学的思考と臨床医学的・民法学的思考との間に対話が閉ざされてきたことである。 ・本来この二つの型の思考が対立するのはやむをえないけれど、今の場合に、問題を硬直状態にしていることの責任は、普遍性や客観性を過度に主張する前者の側にある。 ・というのは、前者の型の思考は、たしかに精緻で首尾一貫した論理をつくりやすいし、そのゆえに批判者としては重要な役割は果たしうるが、それが一方的に過度に働くとき、後者の型の思考がもたらす脳死の判定や臓器移植の具体的な個々のケース(症例、事例)から、もっといえばそれらの誤りからさえも、学ぶ道を閉ざしてしまうからである。 ・しかも、臓器移植とくに心臓移植については、国内で打開の道が開けないままに、外国へ行き外国人の臓器を買って、移植手術を受けてくる患者が増えてきたということまである。これは、日本人のエゴイズムでなくてなんであろうか。 四、«一般にしばしば、宗教の立場、とくに日本人の宗教観と、脳死を医学的に人間の死とみなすのは、相容れないと考えられているが、そこには多くの固定観念があり、また、曖昧で惰性的な気分への反省の欠如がある。» ・スウェーデン保健社会省の「死の定義委員会」が八四年に出した報告『死の概念』のなかに、「宗教における死の概念」という一章がある。 ・さまざまな宗教における ‹死の概念› や ‹死の判定基準の選択› について単刀直入に答を出すことは容易ではない。 ・一般にどの宗教でも、古い時代には、死を判定する方法についての関心は小さく、主要な関心事は、むしろ、死にいかに対処するかとか、死後になにが起こるかといったことであった。«死の判定基準の選択は、どの宗教においても教義にかかわる問題ではないといっても差し支えないように思われる。» ・おそらく、死を判定する方法は宗教本来の範疇を超えているのである。 ・ユダヤ教では、死体の扱い方は厳格であり、火葬・死体解剖・臓器移植は原則的には反対されている。 ・カトリックでは、死ねば魂は身体を去ると考えられ、死の瞬間の決定は教会の権限の範囲外にある、と見なされている。多くのカトリック教国で脳による死の判定基準が抵抗感なしに採用されているのは、そのためである。 ・プロテスタントでも、死の決定の方法は神学の問題ではないと考えられている。少なくとも、脳による死の判定基準の受け容れには、なんらの反対がない。そのことは多くのプロテスタント国に見られるところである。 ・その上、プロテスタントの人々に特徴的なのは、他人を助けるために自分の臓器を提供するということに、積極的な意味を認めていることである。 ・ギリシア正教の場合には、死の判定にはあまり注意を払わないが、死体解剖と臓器移植には宗教的な反対がある。 ・ただしギリシアでは、七八年に脳による死の判定基準が公式に採用されたし、移植も若者の生命を救う場合にかぎって許されている。 ・また、イスラム教の場合も、生と死の境界についてほとんど注意を払わないが、脳による死の判定がイスラム教に反するとは見なされていない。もっとも、イスラム教では、臓器移植は認められても、死体解剖と火葬は認められていない。 ・一般的に、世界の主要な諸宗教が ‹死の判定› についてさほど問題にしていないということは、言えそうである。 ・よく考えてみると、宗教の観点では、重要なのは ‹死の意味› であり、また ‹死者の身体の保全› ではあっても、科学や技術の進歩とともに変わりうる ‹死の判定› ではなかったのである。 ・日本人の場合でも、広い意味での宗教意識と深く関わるのは、実は ‹死の判定› の基準そのものではなくて、死者あるいは死に行く者の、肉体への特別な感情であろう。 ・ここで、特に重要な意味をもつのは、外地で戦死した肉親の遺骨収集や飛行機事故の際の遺体・遺品の重視に見られる、遺族の執着の強さである。 ・そして、そこにあるのは、仏教渡来以前から存在した基層的な霊肉一元論の宗教意識であろう。つまり、鈴木大拙がその積極面を ‹日本的霊性› として主張した宗教意識である。 ・この立場に立つとき、霊と肉、精神と身体とは、それぞれ別個なものではなく、心身は合一している、と見なされる。しかもその霊は、祖霊として追慕の対象であると同時に、怨霊としておそれの対象でもあった。 ・日本人の基層的な宗教意識は、たしかに、霊肉一元論的な傾向がつよい。 ・けれども、この霊肉一元論たるや、心身合一であるとは言っても、極度の精神主義と物質主義とを合わせて含み、しかも、前者の極から後者の極に逆転することが稀ではないのである。 ・でなくて、どうして、たとえば、遺骨に執着する日本人が、 ‹人工妊娠中絶› における胎児の生命に無感覚になりえたのであろうか。水子地蔵という後ろめたさの表現はあるにしても。 ・したがって、死者あるいは死に行く者の肉体への特別な感情を顧慮すると言っても、そのような逆転まで視野に入れておかなくてはならないのである。 ・また、これから日本人が、自分の立場を世界中の人々に向かって根拠づけていくためには、それと同時に、心身合一という人間の在り様のなかにも、権利と責任の主体である自己、つまり人格的同一性を成り立たせないわけにはいかないし、そうすることがどうしても必要なのである。 ―― 完 ―― |