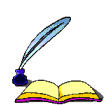
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2022年02月21日 月曜日 】
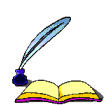
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
2 |
22.01 |
女帝誕生 危機に立つ皇位継承 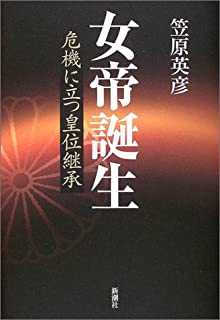 |
笠原英彦 |
新潮社 |
◎ |
はじめに 井上毅の強硬な反対 ・井上は女帝容認論に立つ「皇室制規」を批判するために、嚶鳴社の論客、島田三郎、沼間守一ら女帝否認論者の主張を引用した。 ・嚶鳴社なる自由民権結社は、明治六年に沼間らにより結成された法律講義会の後進で、社員も千人に及び、その後同社の幹部らの多くは立憲改進党の創設に参加した。 ・島田の女帝否認論の論拠は、過去の女帝が、唯一明正帝を例外として「中継ぎ」であることや男尊女卑の風潮が強いわが国では、人臣たる女帝の夫があたかも上位に位して女帝の尊厳を傷つけかねないこと、そして女帝の夫がその立場を利用して政治に干渉する畏れがあること、などである。 第一章 先例か例外か――八人十代の女帝 明治まで存在しなかった皇位継承の成文法 ・わが国には皇位継承に関する成文法が存在しなかった。明治になってにわかに皇位継承法制定が政治日程にのぼったのである。 ・それまでは、慣習法、すなわち旧来の慣習にしたがいつつ、そのときどきの事情によって天皇の即位が決定されてきた。 ・皇室典範の最初の原案が検討されたのは、明治九年のことである。 ・最初の公式のものは元老院の国憲案であるが、そこでは女帝の即位が容認されていた。 ・つまり旧皇室典範の制定過程においても、当初は柔軟な考え方が許されていた。 ・ただし、明らかに男系主義は生きていたし、男子優先の考え方が存在したことはまちがいない。 ・女帝の即位に就いては、皇統断絶の危機に直面するといったきわめて稀な状況が想定されていたといっていい。 女帝は本当に「中継ぎ」か ・井上毅の「謹具意見」の提出を境に、政府首脳部の考え方は急速に変化した。皇男子孫による皇位継承、女帝否認へと大きく舵がきられる。 ・つぎに提起された「帝室典則」からは女帝即位の可能性はすっかり姿を消した。 ・皇位継承には、子から孫へといった世代間継承と、兄から弟や妹へといった同一世代内継承がある。 ・大化以前において、わが国ではまず世代内で皇位を継承するのが一般的であった。 ・同一世代内における継承は、比較的相互の年齢差が小さいために成年間の皇位継承により皇位の安定性が確保されることが期待されたのである。 ・ここで注目しておきたいのは、推古の即位(五九二年)が東アジア世界においても史上初の女帝誕生であったという事実である。 ・古代の東アジアにあって、女帝の存在が認められるのは、日本、新羅、唐の三国である。 ・新羅では、善徳女王(在位六三二 ― 六四七)、真徳女王(在位六四七 ― 六五四)、真聖女王(在位八八七 ― 八九七)の三人が、そして唐では則天大聖皇帝(在位六九〇 ― 七〇五)、すなわち則天武后が帝位についた。 諸説入り乱れる推古の即位 ・五九二年史上初の女帝推古の即位が実現した。推古女帝の在任期間は三十六年の長期に及んだ。推古朝の課題は東アジア情勢への対応と王権の回復にあった。 ・聖徳太子信仰と呼ばれる後世の修飾によって、推古朝の政治は太子がすべて主導したかのように伝えられているが、実際には推古女帝の意向に従い、太子と馬子の共治体制が敷かれたとみてよいのではないだろうか。 ・太子らは隋との対等外交というおもいきった手法に打って出た。小野妹子ら遣隋使を派遣して、わが国が隋の冊封を受けない方針を国書ではっきり伝えた。 ・冊封とは中華思想を基礎として東アジアの国際関係を秩序づけた中国の対外政策をさす。中国皇帝は周辺諸国の国王に官号や爵位を与え、宗主国として属国から朝貢を受けた。 ・わが国は古くは中国の冊封を受けたが、七世紀頃よりその外に立ち中国を隣国として対等な関係を構築し、朝鮮半島諸国を蕃国視して一種の華夷体系を模索するようになった。 ・当初、不快感を味わった隋も、着実に対高句麗外交を展開する日本を警戒して、結局日本との外交関係維持を選択した。 ・国内政治の面でも太子を押し立て、王権回復策として官僚制の整備に腐心した。 ・冠位十二階により官僚制を外面的に、十七条憲法によって官僚制を内面的に統制した。 ・君、臣、民の政治秩序の確立による王権の安定策が積極的に進められた。 ・新羅への遠征を取りやめて、高句麗、隋との新たな外交関係を模索したのも、その究極的目標は国内秩序の安定、そのための王権回復に向けられていたことはまちがいない。 ・古来の氏姓制度を廃棄し、王権の権威を強化し、天皇を中心とする中央集権国家を志向したことは、この後の政治方針を方向づける意味で大きな意義をもった。 ・その具体的施策として、遣隋使の派遣とともに、留学生、学問僧を大陸に送り込み、大陸の進んだ文化を積極的に導入することがめざされた。 ・後の律令制導入の基盤としてこの時代に人材の育成に力を注いだことは大いに注目されていい。 推古天皇崩御 ・それにしても三十六年に及ぶ在位は長かった。 ・推古は、六二八年春、七十五年の生涯を閉じた。 犠牲を生んだ推古の遺詔 ・女帝の長期在位は王位にふさわしい次世代の王位継承資格者を次々と失うことになった。 ・こうした後悔の念が六四五年の譲位の慣行創出の背景にあるのかもしれない。 ・よく「なぜ聖徳太子は即位しなかったのか」という疑問が呈されるが、それはそれまでの王権継承史に終身制の慣行は存在しても、譲位の慣行は存在しなかったためである。 ・推古は本命の皇位継承者の成長を待つといった「中継ぎ」としての役割を負わされた中天皇ではなく、あくまでいったん失墜した王権の回復を至上命題として、蘇我氏と上宮王家を両天秤とした、いわば「暫定王」ともいうべき性格が濃厚であった。 ・聖徳太子が亡くなって後も推古が皇子を立てなかったため、田村皇子と山背大兄王の間で王位継承をめぐり確執を生じたが、群臣らの意向を反映して田村皇子が即位し、舒明天皇となった。 ・推古と同様に皇極も「中継ぎ」の天皇ではない。 司祭者、皇極女帝 ・朝廷内ではしだいに蝦夷が後退し、代わって入鹿が覇権を握ろうとしていた。 ・蝦夷と異なり権勢を求める息、入鹿は政治の専制化を進めた。 ・激動する東アジア情勢を背景に新体制の樹立をめざす中大兄や中臣鎌足らは、皇極女帝や軽皇子らの側に立ち、蘇我本宗家を除くべく大化改新の幕を切って落す一大クーデターを敢行した。 ・乙巳の変として名高いこのクーデターは本宗家討滅から新政権樹立までわずか一週間と周到な準備の下に断行された。 ・現実の権力闘争が表面化した以上、司祭者としての皇極女帝の役割は終わりをつげた。二日後、女帝は軽皇子に譲位する。わが国史上初の生前譲位が断行されたのである。 ・乙巳の変を経て成立した政権では、孝徳天皇が即位し中大兄皇子が皇太子となり、これを支えるべく中臣鎌足が内臣、阿部内麻呂が左大臣、蘇我倉山田石川麻呂が右大臣に就任した。 ・翌六四六年正月、改新の詔が出され、公地公民制が志向されるなど、天皇中心主義にたった国家構想が描き出された。 ・しかし、そもそも改新政権は思惑の異なる諸勢力の寄せ集めであり、世代間対立もみられ、孝徳天皇の権威も十分に確立したとはいえなかった。 ・白雉四年(六五三)には、天皇の反対を振り切って、皇太子中大兄は多くの人々を率いて難波をあとにし、大和に帰還した。先帝皇極はもちろんのこと、間人皇后までもがこれに随行し、幸徳のみがさびしく難波に残された。そして翌年、天皇は従容として死についた。 幕府の風下に立たされた江戸時代の天皇 ・八人十代の女帝を一括して「中継ぎ」の天皇と捉えることはできない。 ・明治以降いわれる「摂位」あるいは「中天皇」を、本来即位すべき皇子が成長するまでの「中継ぎ」と解するならば、明らかに該当するのは持統、元明、元正、後桜町の四天皇であり、推古、皇極(斉明)、孝謙(称徳)、明正の四天皇にはあてはまらないことになろう。 ・八人の天皇の共通項は、いずれも即位の際、そして在位中、独身であったことである。この八人は寡婦か、独身の内親王であり、退位後婚姻した者もいなかった。そのため、皇位を継承する子孫はなく、結果として女系の天皇は誕生しなかった。皇統が男系主義より受け継がれてきた所以である。 第二章 旧皇室典範制定への道のり 「典範の原典」だった「皇室制規」 ・明治政府がはじめての本格的な皇室法規として立案した「皇室制規」において、女帝のみならず女系をも容認していたこと、同時に生前譲位を認めない条文を立てていたことはとりわけ重要である。 ・同時に、旧皇室典範の起草に多大の影響力を行使した井上毅が女帝否認論者にして譲位容認論者であったことも注目に値しよう。 一転して女帝制を否認 ・その後、宮内省はほどなく井上の意見を大幅に採り入れ「帝室規則」を提出した。 ・構成は一見「皇室制規」に似ているが、内容はかなり異なり、一転して女帝制を否認し、男系のみに継承を限定している。また皇族の庶子にも皇族として同等の待遇が与えられるべきとした。 第四章 皇室典範の改正に向けて 憲法見直しの可能性 ・現行の皇室典範にしたがえば、一般国民のうち男子は皇族となることはできず、女子との間には明らかに差別が存在する。 【私見 : なるほど! 差別は女性ばかりが問題とされているが、こんな見方もあるのだ】 天皇の象徴性と皇位の世襲制 ・皇族とは一般国民とは異なる特別の身分であり、これを規定する皇室典範もある種特殊な法律ということができる。したがって、女性天皇をめぐって、近年さかんに唱えられる男女同権、男女共同参画社会と同じ次元で議論することはできない。 ・多くの憲法学者は天皇の象徴性と皇位の世襲制から皇族の特別な地位を説明する。 ・ある憲法学者は、 「国法は、皇位の世襲ということから、天皇その人の配偶者と、ある範囲における天皇その人の血族とその血族の配偶者を皇族とし、これらの者について、多かれ少なかれ、一般国民とはちがった身分を認め、国法上特別の地位をしつらえることにした」 「その結果として、国民のうちには、一般国民のほかに、皇位にある特定の人天皇と、そしてその縁辺の人皇族という種別が生じることになる。このことは、国民は『法の下に平等』だと定めた日本国憲法の原則と相いれない」 「しかし、皇位を認め、皇位の世襲を定めたのが日本国憲法自身であるから、天皇の一身における象徴性の顧慮と、皇位の世襲に必要な限度で、天皇その人と皇族たる人につき、法律で、一般国民についてとはちがって、あるいは特典を与え、あるいは制約を加えるなど特別に取り扱うことにしても、それは、もとより、日本国憲法の容認するところといわなければならない」 と論じた。 ・日本国憲法の基本理念は国民主権にあり、憲法第一条は「この(天皇)地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」と規定する。この前帝の上に、天皇の象徴性と皇位の世襲制とが定められている。 ・皇室典範はこうした憲法の規定に基き、皇族なる特別な身分を認めているのであるから、「国民は『法の下に平等』だと定めた日本国憲法の原則と相いれない」のは当然である。 ・皇族制度はそもそも憲法の定める皇位の世襲制を維持するために設けられている。 ・すなわち皇族という特別の身分は、皇位継承資格者を確保するべく制度化されたのであり、象徴という地位にふさわしい人材の輩出が期待されている。 ・皇族については、もちろん皇位が世襲であることから求められる規範は制度化されているが、象徴にふさわしい行為規範が法制化されているわけではない。 「側室制度」あっての「男系の男子」 ・現行の皇室典範はとりわけ皇位継承の部分で多く戦前の旧皇室典範を踏襲しており、旧典範は、庶子にも皇位継承権を認めていた。 ・戦後、庶子の皇位継承権は法的にも否認され、側室制度などはもはや論外と言うのが世間の一般的な受けとめ方となっている。 ・しかし、旧典範から現典範に受け継がれた「男系の男子」にのみ皇位継承権を限定する原則は、本来側室制度を認め庶子の皇位継承権を容認してはじめて維持可能なものであった。 ・したがって、事実上側室制度を廃止した時点でこの原則の維持はきわめて困難になったことを改めて認識しておく必要があるだろう。 ・現行法制のままでは、いつまでも皇太子妃など一部の女性皇族に男子の出産を求める無言の圧力がかかり、周囲の者を含め無用の負担を強いることになりかねない。 ・民間から皇室に入った女性が、宮中祭祀をはじめ多くの慣れない公務をこなさなければならないことにも十分な配慮が払われてしかるべきであろう。 ・そのためにも、女性天皇容認にむけた皇室典範の改正は不可避である。 ・憲法に定められた象徴としての天皇の地位に鑑み、時代の要請に適い、かつ国民の広範な支持を得られる法改正がめざされねばならないであろう。 ・旧典範の成立以前に誕生した女帝はいずれも独身であり、寡婦か未婚であった。そして終生独身を通すことを半ば強制されたとみることもできる。 ・それは、ひとえに皇位継承の可能性のある子孫が存在しないことにより、女系天皇の即位を回避し、男系主義を守り通すためであった。 ・女系天皇が母である女帝の皇婿方の姓をつぐことにでもなれば、まさに易姓革命により万世一系は崩れ去るからである。 ・現代において女性天皇を容認する場合に果たして男系主義が貫けるかどうかははなはだ疑問である。国民の間で、単に女性天皇を認めるだけでなく、女系天皇もともに容認するべきか否かを同時に問わなくてはならない。 ・女性天皇が容認されると、次に女性天皇の婚姻問題がもちあがってくる。当節、女性天皇に独身を強要することを世論が是認することはありえないであろうから、女系天皇の可否は直ちに問題化する。 ・国民は皇室をいわばファミリーとして据えているから、在位中の天皇に親王や内親王がいるのに、他へ皇統をつなぐことに納得するとは考えにくい。 ・仮に愛子内親王が即位した場合、婚姻によりもうけられた親王、あるいは内親王は即位すると女系天皇ということになる。つまり、いったん女性天皇を認めれば女系天皇も容認せざるを得なくなる可能性が高いということである。 ・現実的には、女性天皇を認めることは女系天皇の誕生を容認することにつながると考えてほぼまちがいないであろう。 ・過去に八人の女性天皇が在位したが、女系天皇の例はない。 改正点の具体的論議 ・皇室典範の改正点としては、女性天皇の容認と皇族女子の結婚後における宮家創設の二点が重要となってこよう。 ・女性天皇を認める場合には、明治の女帝論争でも焦点となった男女皇族間の継承順位が問題となる。 ・皇位継承順位については、男子優先型と第一子優先型が考えられる。 ・イギリスは男子優先型であり、オランダやスウェーデンは第一子優先型である。 ・一九九〇年代以降、ノルウェーやベルギーでも第一子優先型へと改正されるなど、世界的趨勢としては男女平等の第一子優先型を選択する傾向にある。 ・日本の場合、可能性としては、歴史的経緯や宮中祭祀との関係からいって、前者の男子優先型がまず選択されるのではなかろうか。 ・現在の皇位継承順位は、第一位、皇太子(皇長子)、第二位、秋篠宮(皇次子)、第三位、常陸宮(皇弟)、第四位、三笠宮(皇叔父)、第五位、三笠宮寛仁(皇叔父の長子)、第六位、桂宮(皇叔父の次子)、の順である。 ・直系が傍系に優先し、長幼の序が考慮されていることになる。ここに男女の優先順位が加味されることになる。 ・仮に直系が傍系にあくまで優先するのであれば、直系の女性皇族は第二位の秋篠宮の後に挿入するのが妥当かもしれない。 ・そうすると第三位、愛子内親王、第四位、眞子内親王、第五位、佳子内親王、第六位、紀宮が新たに加えられることになる。 ・皇族女子に皇位継承権を認めるとすれば、現典範の第十二条を速やかに改正して、天皇および皇族以外の者と婚姻した皇族女子が皇族の身分にとどまりうるよう、女性宮家の新設を認めなくてはならない。 ・そこで問題となるのは如何にして女性宮家を新設しうる皇族女子の範囲を定めるかである。 ・異論はあるであろうが、今上天皇の直径子孫に限定するというのが妥当ではなかろうか。 ・宮家の増設は莫大な皇族費を要することを考えれば、皇族男子とのバランスをも踏まえて、かかる範囲に限定するのが現実的であろう。 ・そうした原則に従えば、現在のところ、愛子内親王、眞子内親王、佳子内親王に紀宮清子内親王が女性宮家を創設できることになる。 女性天皇の結婚相手――皇婿問題 ・華族制度がなくなっているから、皇婿を供給する皇配族が現代の日本には存在しない。もはや一般の男性のなかから皇婿にふさわしい人材を見出すほかはない。 ・戦後まもなく臣籍降下した十一宮家など旧宮家の関係者がまず対象となる可能性もある。 ・「男系の男子」とする典範の第一条ではなく、一般男子の皇室入りを禁じた典範の第十五条が憲法十四条の「法の下の平等」に反しているのである。 ・皇婿の選定は、いわゆるお妃選び以上に至難である。 ・まず何よりも配偶者として天皇の政治的中立性を侵さないことが求められる。 ・むしろ極力民間社会での立場を捨て、戸籍から皇籍に移る際に姓を放棄することが求められよう。 ・戸籍を抹消し、皇籍に入る際に姓を失うことが許容されるとすれば、万世一系には適うことになる。 ・日本国憲法第二乗と第十四条の関係については、「皇位の世襲」を「法の下の平等」の例外と解するのが憲法解釈上の通説である。 ・皇族は「例外」的存在であって、皇位継承や摂政となる資格がある半面、職業選択の自由などが認められておらず、一般国民に認められている基本的人権が制限されている。 「女系継承」は荊の道の始まりか ・女性天皇を容認することは容易に女系天皇の誕生に帰結するということである。 ・神武天皇以来これまでわが国の皇統は男系により連綿と継承されてきた。女系天皇は一人として誕生していない。 ・女性天皇を容認した結果、女系天皇が即位することになれば、これまでの皇位継承の原則、すなわち万世一系の原理に変化が生じることになる。 ・わが国史上に在位した八人十代の女帝はいずれも男系の天皇であった。それは、女帝が寡婦、あるいは独身の内親王の即位であり、男系主義が守り通されたからである。 ・憲法第二条の「世襲」とは万世一系をさしており、万世一系とは確かに男系主義のことである。 ・皇統は男系をもって伝えるのがわが国における皇位継承の伝統であると考えられたのである。 ・われわれはいま、女性天皇を認めることによって、これまでにかった女系継承という新たな道へ一歩踏み出そうとしている。 ・女性天皇を容認するか否かを議論する前提としてまずかかる重大な認識が不可欠である。そしてそれは皇統断絶と引き換えにわれわれが選択する荊の道の始まりかもしれない。 あとがき ・われわれはまず「万世一系」が事実上男系による皇位継承であったという事実を確認しておかねばならない。 ・女性天皇を認めるということは、男女平等などの観点からではなく、これまで連綿と続いてきた皇統が女系に移る可能性が高いということがより重要である。 ・それは、まぎれもなく皇位継承ルールの一大変革といわねばならない。 ・このことは二千年以上にも及ぶ天皇史上、はじめての経験である。 ・これまでわが国史上にあっても、皇統断絶の危機が絶えず念頭におかれてきた。 ・江戸時代の光格天皇以降、仁孝、孝明、明治、大正と、いずれの天皇も側室の子、すなわち庶子であったことも、嫡男子の継承が如何に難しいかを物語っていよう。 ・われわれは、とりあえず現状を打開するといった安易な発想ではなく、永く皇統の存続をはかるべく知恵をしぼらねばならない。 ・将来にわたって皇統の存続を可能とし、人々の心の支えであり、日本の文化そのものである天皇制の維持に向けて、いまこそ冷静にして熱心な議論が必要である。 ・戦後まもなく降下した旧宮家の子孫を復活させて「男系の男子」を墨守するよりも、女性天皇を認めるべく皇室典範の改正に踏み切ることがより自然であろう。 ・ただし、いったん女性天皇を容認すべく皇族女子に皇位継承権を認めれば、いずれ女系天皇の即位に帰結することを覚悟しつつ、熟慮する必要がある。 ・女性天皇容認には皇婿の選定と処遇という難解な問題がともなうが、皇婿となる男性に姓を放棄させ、まがりなりにも「万世一系」を維持することが一つの打開策ではなかろうか。 ―― 完 ―― |