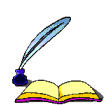
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2023年11月17日 金曜日 】
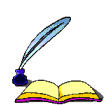
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
3 |
22.02 |
アメリカの鏡・日本  |
ヘレン・ ミアーズ |
角川one テーマ21 |
☆☆☆ | 抄訳版刊行にあたって ・「占領が終わらなければ、日本人は、この本を日本語で読むことはできない」 ――ダグラス・マッカーサー ・この本の原著『Mirror for Americans : JAPAN』がアメリカで出版されたのは、日本の敗戦後三年目、一九四八年(昭和二十三年)であった。 ・その年、翻訳家・原百代氏はヘレン・ミアーズより原著の寄贈を受け日本での翻訳出版の許可を得た。 ・原氏は、連合国総司令部(GHQ)に嘆願書を添えて日本に於ける翻訳出版の許可を求めた。しかし、その望みは断たれた。翻訳出版不許可の決定が下されたのだ。 ・マッカーサーは、 「私はいかなる形の検閲や表現の自由の制限も憎んでいるから、自分でこの本を精読したが、本書はプロパガンダであり、公共の安全を脅かすものであって占領国日本における同著の出版は、絶対に正当化しえない」 と述べている。 ・GHQによる検閲の影響が続いていたとは言え、出版不許可は当然の決定であったと推測できる。 ・そして占領が終了した翌年の一九五三年(昭和二十八年)、原氏の翻訳は『アメリカの反省』と題してやっと出版されたのであった。 ・この本の著者、ヘレン・ミアーズは一九〇〇年にニューヨークで生れた。 ・二・二六事件がおきる前年の約一年間、日本に於ける庶民の生活習慣や神道に至るまでを実際にフィールドワークし、危機迫る騒然とした日本を体験した。 ・戦争中ヘレン・ミアーズは日本専門家としてミシガン大学やノースウエスタン大学で陸軍省の占領地民政講座で講義し、日本占領に供える要員の養成に携わり、日本研究を深めた。これらの活動によって、彼女の人生は、日本及びアジア研究に決定づけられた。 ・戦争が終わった翌年、一九四六年(昭和二十一年)二月、彼女は東京のGHQに設置された労働諮問委員会の十一人のメンバーの一人として三度目の来日を果たし、日本の労働組合法等、労働法の策定に参加した。 ・同委員会のメンバーとしての立場で、GHQ内部の情報に直接ふれた彼女が、アメリカに帰国後、この本を書き上げたのは、極東国際軍事裁判の判決が下された一九四八年(昭和二十三年)であった。 ・発売当初ヘレン・ミアーズは再度全米の注目の的となったが、彼女の主張はアメリカ人にとって不愉快なものであり、アメリカ人は次第に彼女を無視するようになった。それ故、この本と共に彼女は世に出ることなくいつしか忘れ去られていった。 ・日本人にとってもアメリカ人にとっても、この本の出現は少し早すぎたようだ。 ・ヘレン・ミアーズはこの本の中で、一八五三年(嘉永六年)ペリーが四隻の軍艦を率いて日本の門戸をこじ開け、一九四五年マッカーサーが未曾有の軍艦を率いて日本の門戸を閉じた、その九十二年間の日本をグローバルな観点で説き明かし、我々が忘れていたこと、或いは忘れさせられていたことを思い出させ、或いは気付かせてくれたのだ。 ・彼女の論拠には、私たちの認識をはるかに超える鋭さと、公平さがあり、真実を静かに語りかける文章の迫力に圧倒される。 ・ヘレン・ミアーズが気付かせてくれたものとは何であるのか。それは日本の「生きざま」である。 ・一八五三年の開国まで、鎖国の中で平和を享受していた日本が、国際社会の荒波の中でどのように行動してきたのか、そして何故に日本は墜落していったのか。 ・われわれ日本人は日本の「生きざま」と正面から向き合い、日本中心の観点からではなくグローバルな視点をもって、日本はなぜそういう行動に出たのか、何が悪かったのか、何が間違っていたのか、何が正しかったのかをしっかりと理解し、悪かったことを心から反省し、同時に間違っていなかったことは正々堂々と主張し、国際社会から理解されるよう努力しなければならない。 白子英城 第一章 懲罰と拘束 1 なぜ日本を占領するか ・占領は博愛主義的行為からは、はるかに遠いものである。 ・私たちは、日本国民が指導者たち同様拘束されている事実を直視しなければならない。日本の行政、産業、資源、労働を握っているのは、法律をつくり、ときには武力をつかってでも法を執行しようとするアメリカ人である。 ・教育制度、宗教、葬式、婚姻の習慣、伝統芸能、礼儀作法からキスの仕方まで、日本の文明がアメリカの規制を受けている。 ・私たちは、日本文明の中で「戦争願望」の基になっていると判断したものはすべて打ち壊すつもりなのだ。 ・占領政策は日本国民と文明の抑圧である。 ・この計画は戦争の合法的行為、すなわち賠償行為の常識をはるかに超えた、圧倒的スケールの「懲罰」と「拘束」である。 ・日本占領は妥当で、人道的で、正当であるかのようにみえるが、多くの問題がある。 ・国は男、女、子供、何千万人の個人から成り立っている。だから、一国を「罰する」ことはむずかしい。その意図がどんなに正しくても、国民を罰しないで国だけを罰することなどできるはずがないのだ。 ・アメリカ社会でも、人一人を罰するには、間違いなく有罪かどうかの証拠探しに大変な努力が払われている。 ・しかし、日本に対しては、戦争中の感情的宣伝を証拠にして、全国民を一括処理しようというのだ。日本国民全体を罰する私たちの権利の基盤は非常に脆弱である。 ・私たちは日本側のいい分を聞いてみたことがない。日本の歴史については、戦争プロパガンダが好んでつかう史実しか教えられなかった。 ・私たちは日本とアジアの考え方をまったく無視してきた。日本人は起訴状にあるように、本当に世界征服の野望を抱く野蛮で侵略的な民族なのか、考えてみたこともない。 ・私たちは、指導者、一般庶民を問わず、全日本民族をひとくくりにしてきた。 ・国民と文明に関しては、釈明も聞かずに、いきなり有罪と断定しているのだ。 ・アメリカ文明は個人の権利と尊厳の尊重を基盤にしているはずだった。そうであるなら、審問抜きの大量懲罰は、私たちの法と正義の哲学に著しく反しているというほかない。 2 攻撃と反攻 ・私たちが罰する日本の犯罪とは何か。簡単にいえば、私たちの告発理由は「殺人」である。 ・「世界征服」の一段階として、アメリカに対し「一方的かつ計画的攻撃」をかけたというパールハーバーの定義が告発の基礎なのだ。 ・日本はこの起訴事実に対して「無罪」を主張する。世界を征服することも、あるいはアメリカ合衆国を征服することも、まったく企図していなかったし、望んだこともない。満州あるいは中国の征服さえ考えたことはない、と罪状を否認する。 ・そして検察側の私たちが「一方的かつ計画的攻撃」と呼ぶ行動は、あくまで「自国の安全保障」のためであったと主張する。 ・アメリカは経済封鎖によってパールハーバーを「挑発」したという日本側の主張には、それなりの根拠があるのだ。 ・私たちがイギリス、オランダと共同して行なった対日経済封鎖は、アメリカの「防衛」とヨーロッパで戦うイギリスを支援するためだった。 ・東京裁判で日本側は「封じ込め」を逆非難し、「正当防衛」を主張した。 ・公的立場のアメリカ人はすべて、日本の指導部は終始「国家の存亡にかかわる利益」のために戦っていると考えていた。 ・グルー大使は、一九三二年九月三日の日記に書く。 「日本は……(満州における)全行動を国の存亡にかかわる至上命令、あるいは自衛手段の一つ、と考えている。彼らはこの考えに立って、戦争も辞さない覚悟を固めている」 ・米戦略爆撃調査団が一九四六年七月、大統領に提出した報告 「日本の指導部が国家の存亡にかかわる利益のために戦っていると固く信じて、戦争を始めたことは明らかである。これに対して、アメリカは単に自分たちの経済的優位と主義主張を押しつけようとしているのであって、国家の存亡にかかわる安全保障のために戦ったのではない、と彼らは信じていた」 ・アメリカの「存亡にかかわる利益が脅かされた」と判断したら、大統領は世界のどこであれ、その国あるいは国々を攻撃する権利をもつというのだ。日本にとっては、その点が肝心なのだ。 ・米大統領は、アメリカの存亡にかかわる利益とその侵犯者を決める権利をもっているというが、自国の国益を定義し、それを誰が脅かしているかを決める権利がアメリカにあるなら、日本にも同じ権利があるはずだ。もしないなら、なぜないのか。 ・しかもアメリカは「敵が自国の海岸に上陸してくるまで」待つつもりはないといっている。それなら、日本が「国家の存立」を守るために、どこで、いつ、誰と戦うかを決める権利も許されると、日本が考えてもおかしくないだろう。 ・私たちが「国家の存亡にかかわる利益を守るために戦う」のは、私たちの権利であると主張する以上、同じように主張してきた日本を何で罰することができるのか。 ・「世界征服」を企てたという理由で、日本を公正に罰することができるというのも理解できない。 ・パールハーバーはアメリカ合衆国の制服を企んで仕掛けられた「一方的攻撃」であるというが、この論理では日本を公正に罰することはできない。 ・なぜなら、私たちの公式記録が、パールハーバーはアメリカが日本に仕掛けた経済戦争への反撃だったという事実を明らかにしているからだ。 ・パールハーバーは青天の霹靂ではなく、然るべき原因があって起きたのだ。原因は、一九四一年七月二十五日にアメリカ、イギリス、オランダが打ちだした「凍結」令である。 ・三国は自国領内にある日本の全資産を凍結し、貿易、金融関係をすべて断絶した。日本は輸入必需品の八十パーセントを「凍結」地域に頼っていたから、三国の行動は日中戦争の泥沼化だけでなく、国内経済の窒息を意味するものだった。 ・日本の立場でいえば、こうである。イギリスとオランダが禁輸したインドネシアとマレーの物資を力で奪いにいく決意を固めた。そこで、アメリカが両国の陣営に加わらないよう、奇襲によって出鼻をくじく必要があった。パールハーバーはのるか反るかの賭けだった。 ・いずれにせよ、パールハーバーを攻撃した日本の罪状は、私たちが告発し懲罰の根拠にしようとしている犯罪とは違うものなのだ。 ・「満州事変」以来企んでいた「世界征服」の「陰謀」という告発もいささか乱暴である。 ・アメリカの世論は満洲における日本の行動を何の疑いも抱かずに非難している。日本の満州進出は誰が見ても明らかな侵略行為だからだ。 ・しかし、満州「事変」に対するアメリカの態度は、世論とはまったく違う観点に立っていた。 ・政府の対日批判は一般世論のように人道的立場から中国のことを懸念していたのではない。米国政府は「国際間合意」と満洲、中国におけるアメリカの権益に懸念を抱いていたのである。 ・中国と日本が争っている。われわれはどちらが正しいか知らない。わかっているのは、両国の争いが「国際平和条約」と「門戸開放政策」の妨げになるかもしれないということだ。これがアメリカの公式見解である。 ・そうであるなら、「国際条約」とは何か、「門戸開放」とは具体的にどういう行動をとることなのか、がわからなければ、満州事変について公正な判断を下すことはできないだろう。 ・私たちは十年間、満州国の正当性を認めなかった。しかし、認めなかったというだけで、日本の計画を阻止しようとはしなかった。 ・日本人を「世界で最も好戦的な民族」と呼んだ戦争中のプロパガンダは、私たちにとって確かな事実だ。 ・そして、私たちが罰しようとしているのは、まさにこの「罪」なのだから、もし国際関係の背後に迫ろうと思うなら、日本人を「世界で最も好戦的」民族とする証拠の検討から始めなければならないのである。 第二章 世界的脅威の正体 2 日本はいつ敗れたか ・沖縄作戦は、本土上陸か原子爆弾がなければ日本は占領を受け入れない、という論理で正当化された。しかし、占領後に公表されたアメリカの公式報告は、この論理が間違っていたことを明らかにしている。 ・私たちの政策決定者たちは、なぜ、本土に上陸しなければ日本は無条件降伏しないと信じていたのだろうか。 ・この疑問に対して、スチムソン元陸軍長官は、日本人との戦いは「死ぬまで戦う能力を存分に見せつけてきた人種」との戦いだったとしか答えることができないのだ。 ・スチムソンは、戦争中に非常に多くの日本人が死んだことをいっているようだが、日本人が死んだのは、彼らがファナティック(狂信的)に戦争が好きだったからではなく、圧倒的に優勢な敵と戦っていたからだ。 ・日本人を軍国主義的人種として告発することで、私たちは論理を逆転させている。 ・私たちは、日本人のファナティックな行動を立証するために、私たちの力の優位を証拠としてつかっている。 ・私たちはさらなる証拠として原子爆弾までもちだした。私たちは日本人を完全に屈服させるために強力な新兵器をつかったが、そのためには根拠のない告発をつくり出す必要があった。そして原爆をつかった私たちの行為は、告発実を裏づけるさらなる証拠であるというのだ。 3 サムライ神話 ・「世界で最も軍国主義的な国民」という日本人像は、事実の歪曲と日本人の行動様式の曲解をもとにして描かれている。 ・私たちの事実認識の中でも、「無敵のサムライ」神話はほとんどマンガである。 ・アメリカの新聞論説委員、コラムニスト、ラジオ解説者たちは執拗に日本兵を東洋の邪悪なスーパーマンに仕立てあげた。日本兵は、神道の神々の命を受けて、現人神の天皇を「世界の王座」に就けるために戦う「戦士信仰」の野蛮な信者なのだ。 ・私たちは「文字どおり死ぬまで戦う力を示した人種」という日本人観を政策の基盤にしている。そして、それは「狂信的軍国主義者」という意味で解釈されてきた。この認識は果たして正しいかどうか、戦場からの記事を読んでみる必要がある。 ・私たちが事実として認めたこれらの記事は、「無敵のサムライ」とはまったく違う姿を伝えているのだ。 ・国の父であり、伝統文明の象徴である天皇は日本国民統合の強大な力だった。しかし、天皇はさまざまな国民感情を統合する象徴にすぎない。 ・この感情を煮詰めれば、国家存亡のときにはどこの国の国民もつき動かされる感情である。 ・日本の兵士たちは「日本は侵略の危機にさらされている。君たちは祖国の防衛とアジア・太平洋の同胞を「解放」するために戦っているのだ」と教えられてきた。 ・日本兵がほかの国の兵士より強くこういうプロパガンダに洗脳されたのは、日本が列強諸国とくらべてとくに弱かったからだ。 ・彼らは任務を果たした。しかし、日本兵が「戦うのが好きだから」、あるいは「戦死は崇高な運命」と思っているから、あるいは「天皇のために死にたいというファナティックな願望」から、あるいは勝利を確信して、圧倒的に優勢な敵に立ち向かったことを裏づけるものは何も見いだせないだろう。 ・もちろん、ファナティックな蛮勇の表われと思えるような「撃ちてしやまん」型の先頭はあった。しかし、それはほとんどの場合、カミカゼ特攻隊員、人間魚雷に単独で乗りこむ乗員、選り抜きの攻撃隊員だった。 ・カミカゼのパイロットはほとんどが大学生だった。彼らは熱烈な愛国主義者であり西洋嫌いであった。なぜなら、昔から白人は亜細亜人を劣等人種と考え、人が見ていないところでは、実際に劣等人種として扱っていると彼らは思っていたからだ。 ・集団自決の動機は、多くの場合、降伏したらどのような扱いを受けるかわからないという恐怖だった。 ・戦争が始まったころは、日本のパイロットは最も有能で遺志堅固な戦闘員だった。しかし、一九四四年までに、訓練された兵士は死んでしまい、質の低い無気力な兵士に代わっていった。 4 銃もバターも ・私たちは日本人の「ファナティックな好戦的」性格を強調しすぎてきた。だから、私たちとの戦争にも勝てるはずはなかったという事実がぼかされているのだ。 ・私たちは日本の「軍国主義的性格」にこだわりすぎたために、近代戦の勝利はほとんど、狂信的兵士にではなく工場労働者に負っているという事実がみえなくなっている。 ・軍事力が高度に機械化された今日の世界では、工業生産力を無視して「世界の脅威」を正しく議論することはできないのだ。 ・総じて私たちは、日本をドイツと同じぐらい豊かな工業国だと思ってきたが、これはまったく違う。 ・大戦中、ドイツとドイツ統治領は枢軸国の軍事物資の九〇パーセントを生産していた。イタリアと日本は残りの一〇パーセントを分担していたにすぎない。 ・日米の軍事費の差は圧倒的だ。 ・満州事変に関する公式報告が正しければ、この年日本は一億五千二百万ドルに満たない軍事予算で世界征服を開始し、一方、私たちは国内の軍隊を満足させるだけで六億六千七百万ドルを必要としていた。 ・もし日本が本気で世界征服に乗り出したというのなら、これでいったいどうするつもりだったのか。 ・日本が近代的軍事力をもつには、飛行機部品、屑鉄、石油、工作機械、ゴム、スズ、銅、綿など必要な物資や基本原料をアメリカ、イギリス、オランダから買い入れなければならなかったし、まして米ドルと英ポンドで支払わなければならなかったことを考えると、日本のいわゆる世界征服初めから本物ではなかったといえるのだ。 ・私たちは、日本が重大なパールハーバーの年の一年間に認められた軍事費をほとんど一ヵ月でつかっていた。 ・日本の軍事予算は一九四四 ― 一九四五年に三百八十億円を追加計恕してピークに達した。 ・これはほぼ九十億ドルに相当するが、すでに日本の工業生産は成長が止まっていたし、基本物資不足のために減少し始めていたのだから、これは単なる期待値にすぎない。 ・これに対して、同じ時期、私たちは九百七十億ドルにのぼる「国防」費を認められて、戦闘態勢に入ったのだ。 ・対日戦略を策定した人たちが、日本の狂信的神道崇拝なるものでなく、厳しい経済状態を事実に即して見ていたら、貴重な人命と財産をこれほど犠牲にしなくても日本の軍部は敗北していただろう。 ・国家は人間によって統治されているのだから、人間と同じように自分の立場で他人を見ようとする。 ・あまりにも豊かで強大な国に住む私たちは、戦争が始まったとたん、日本の軍事力を過大評価するようになった。同じように、逼迫した経済状態の国に住む日本人は、とかくアメリカを過小評価していたのだ。 ・日本の輸送船は底をついていた。 ・日本が保有していた輸送船総数の八八パーセントが戦争中に撃沈された。 ・鉄鋼生産だけをとってみても、十分状況がわかる。鉄はいかなる軍事計画にとっても筋肉であり骨である。 ・一九三九年、アメリカは五二五〇万トンの鉄を生産していた。一九四二年には八八〇〇万トンに達した。 ・日本の生産量は「世界征服」に乗り出した年の一九三四年で三三三万四〇〇〇トンである。 ・大戦中の一九四三年に、七八〇万トンまでもっていくが、戦争終結時の鉄鋼生産量は一五〇万トンになっていた。 ・アメリカと諸外国の生産能力を比較するにつけ、なぜ私たちが日本を怖れてきたか、わからなくなるのだ。アメリカは精神鑑定が必要かもしれない。 ・日本が経済的に窮乏していたという事実は、一つひとつが重要な意味をもっている。 ・アメリカ、イギリス、オランダ三国は、日本の軍需必需品の八五パーセントを供給していた。一九三八年には、アメリカだけで五七パーセントを供給しているのだ。 ・日本が日華事変を継続させることができたのは、アメリカとイギリス、オランダ両帝国から買っていた綿、工作機械、石油、屑鉄など戦略物資のおかげなのだ。 ・私たちは経済封鎖によって日本の補給路を遮断したから、戦争に勝てたのである。日本の本土を爆撃することで勝ったのではない。 ・日本が戦争機関(艦船、銃砲、戦車、飛行機、弾薬)を動かすには、鉄、ニッケル、ゴム、スズ、銅、鉛、コバルトなど、自国の領土からは得られない無数の物資が必要だった。 ・最寄りの補給源はオランダ領東インド諸島、マレー、フィリピンだったが、日本はこれらの地域を占領してからも、原材料を日本あるいは満州の工場に運び加工しなければならなかった。 ・私たちが輸送船舶を沈めれば、船舶、その他のものをつくるために必要な物資を輸送できなくなる。 ・封鎖は日本を破る武器だったのだから、それがたとえ日本に奪われたフィリピンであっても、島を奪還するという作戦は、戦術論からいって擁護できない。 ・日本の占領部隊は、本国からの補給を断ちさえすれば、たちまち機能不全に陥ったろう。そして本国は補給源を断たれたら、平時の通常生産さえ維持できないのだから、日本を破るのに本土爆撃など必要ではなかった。したがって、本土爆撃のための発信基地を奪う必要もなかった。 5 降伏受諾 ・スチムソンは原子爆弾の投下を正当化して、「日本の独裁体制に確実なショック」を与え「われわれが望んでいたように、和平支持勢力を強化し、軍部の力を弱める」ためには「優れて適切な武器」だったと説明する。 ・しかし、米戦略爆撃調査の公式報告は、 「広島と長崎の原子爆弾が日本を敗北させたのではない。戦争を終結させた敵指導部が証言するように、原爆は日本に無条件降伏の受諾を強いるものでもなかった」 ・原爆はポツダム宣言の受諾を「早める」よう「さらにせかせた」だけだった。 ・同報告は「原子爆弾が投下されなくても、あるいはソ連が参戦しなくても、また上陸作戦が計画ないし検討されなくても、日本は一九四五年十二月三十一日以前、「あらゆる可能性を考えに入れても一九四五年十一月一日までにまでに」無条件降伏をしていただろうという意見を付けている。 ・スチムソンは、日本が降伏しない場合は十一月一日に本土上陸することを決定していたと述べている。そしてこの作戦では「米軍だけで百万の死傷者」を覚悟していたというが、これは恐ろしい決定である。 ・これだけの命が懸かっているのに、私たちは、降伏するつもりの日本のスポークスマンを受け入れて、降伏の用意があるかないかを確かめようともしなかった。私たちは勝手に、日本は降伏しないと決めつけていた。 ・米戦略爆撃調査の報告を読むと、もし私たちがポツダム会議で日本の意向を聴取しいたら、ポツダム宣言も、原子爆弾も、本土上陸作戦も必要なく、降伏を準備で来たように思われる。 6 リーダーの資格 ・私たちの戦争・平和政策と計画が日本の将来にとって重要であるなら、アメリカの将来にとっても、計り知れないほど重要である。 ・私たちは計画立案の指導者を自任してきた。しかし、緊張に押し潰されて事実を読み違えるようでは、指導者の地位は非常に危ない。 ・私たちはまた道義の指導者を自任してきた。しかし、緊張に押し潰されて犯した罪を、それだけでなく、危機が去ったあとに重ねた罪を認めて償うことができなかったために、私たちの道義は厳しく問われているのだ。 ・日本政府の頑迷派に圧力をかけるためなら、女子供の命を蒸発させることも「優れて適切な」手段であるというスチムソン元陸軍長官の言明が、戦争の熱いさなかだけでなく、日本の降伏から一年半も経ったというのに、いまだ紀事になり、広く容認されている。 ・この事実は、私たちの選んだ社会理念が、私たちが思っていたほどには明確でなかったことを物語っている。 ・ナチスは自分たちの死の収容所を、望ましくない過剰人口を整理するための「優れて適切な」方法であると信じていた。そのことは誰も疑わない。だからといって、私たちはこの問題をナチの都合のいいようには解釈しない。私たちは収容所を犯罪と呼び、その存在を許したものを犯罪人と呼ぶ。 ・私たちは他国民の罪だけを告発し、自分たちが民主主義の名のもとに犯した罪は自動的に免責されると思っているのだろうか。 ・社会「改革」の任務を背負う国民にとっては、これは重大な問題である。 ・昔から権力は自ずと腐敗するといわれてきた。ここにいたってもなお、原爆使用の正統性に固執するのは、私たち自身の価値観を否定するものだ。 ・私たちがいつまでも論理の二重基準にしがみついているならば、私たちより力の弱い、私たちのように安全が保障されていない国の人々に向かって、私たち以上に良心的になれとはいえないのである。 7 日本は戦略地域か ・私たちは最後の最後になぜあれほど焦ったのか。日本が少なくとも三ヵ月間にわたって、降伏への道を模索してきたことを知りながら、なぜ決断までに十一日しか待ってやれなかったのか。 ・この疑問に対する答えは、アメリカと日本の関係ではなく、アメリカとソ連のやりとりにある。 ・一九四五年二月七日のヤルタ会談における「最高秘密」合意で、ソ連は中国領内の一定領土および財産を確保することを条件に、対日戦への参戦を約束した。ソ連としては、彼らが参戦して「合法的」に戦利品を要求できるまでは、日本に降伏してほしくはなかったのだろう。 ・一方、私たちはもし日本が即時無条件で降伏してしまったら、ソ連は参戦しようがすまいが、日本に侵入してくるとみていたから、日本がソ連に和平条約を提示することを望んでいなかった。そして、日本が無条件降伏をしない場合は、満洲と朝鮮に駐留する関東軍をソ連に抑えさせようとし、同時に、ソ連が来る前に日本本土を占領しようとしていたのだ。 ・もし、この分析が正しく、これ以外に事実を説明できる分析がなければ、私たちは日本の一般市民十数万人を大量虐殺してでも、早急に結論を出そうとしていたということができる。 ・もしこれに失敗したら、数十万の米兵を犠牲にしてでも、計画どおりに日本上陸作戦を敢行しようとしていた。 ・私たちが日本人に対してつかった原子爆弾は、日本に対してつかったのではない。なぜなら、日本はすでに完全に敗北していたからだ。 ・原爆はソ連との政治戦争に使用されたといえる。 ・占領は私たち自身の政治・経済目的を達成するための装置だ。この目的に日本人が関係してくるのは、たまたま日本人がチャモロ族と同じように戦略的に重要な島に住んでいるからにすぎないのだ。 8 飢餓民主主義 ・私たちの占領は、どう見ても日本の軍事力に対する防衛的軍事行動とはいえない。 ・もし対日戦争の目的が日本の戦争機関、軍事生産、軍事生産能力を破壊し、その台頭を許した国民を罰することであったなら、占領の必要はなかった。 ・なぜなら、私たちが日本に上陸する前に、その目的は達成されていたからだ。戦争それ自体の結果として、日本は「二度と侵略戦争ができない状態に置かれていた」。 ・軍事的にいえば、占領は単に警察官の役割を果たしているにすぎない。日本軍の武装解除と残存する軍事装備、貯蔵物資の解体を監視するだけのことなのだ。この仕事は二ヵ月で終った。 ・日本は完全に無防備であり、文字どおり一隻の軍艦、一機の戦闘機、いかなる種類の飛行機ももっていないのだ。武装解除され、非武装化され、産業は戦前のほぼ三分の一にまで縮小され、国民は日常の食べ物に事欠き飢餓状態にあるというのに、どうしてこの国を軍事占領しつづける必要があるのか? ・占領は日本が「再びそれを試みる」ことがなくなる保証として必要であったし、これからも必要である、というのが公式説明だ。 ・「……戦争願望を形成してきた現在の経済・社会制度が変えられ、戦争願望が存続しなくなるまで・・・・・」占領は継続しなければならないという。 ・ここで表明されているのは、一方でマッカーサー将軍がのちに「経済的扼殺」と呼ぶ管理体制であり、一方では国民を「民主化」する政策である。 ・おとなしくいえば、相矛盾する二つの原則を基盤にする政策。歯に衣を着せずにいえば、こちらを目指すといいながら、あちらに向かうがごとき政策である。 第三章 改革と再教育 1 リーダーシップ ・ペリー以後の近代日本が、侵略的であり、拡張主義的であったことは確かだ。 ・しかし、近代以前の日本が平和主義であり、非拡張主義的であったことも確かだ。 ・だから、近代日本の侵略行為は一八五三年以後の出来事に原因があると考えるべきである。 ・これらの出来事を見直すと、アメリカ人と日本人の解釈には、どうしても大きな違いが出てくる。 ・アメリカ人は将来の平和のために、日本人を罰し、再教育し、改革しようとしているというが、近代日本の行為を許さないアジアの人々でも、日本人と同じ視点で日本の近代史を見ているのだ。だから、日本人の考え方を知ることがとくに必要になってくる。 2 歴史の証言 ・私たちが日本にきた目的は、軍国主義的侵略性をもって生まれた日本人を「改革」することである。この「生まれつきの」軍国主義なるものを、日本人の過去に求めるとすれば、十六世紀、朝鮮に攻め入った孤独な将軍の失敗の記録ぐらいのものだ。 ・しかし、この遠征をとらえて日本民族を生まれつき軍国主義者と決めつけるなら、スペイン、ポルトガル、イギリス、オランダ、フランス、ロシア、そして私たち自身のことはどう性格付けしたらいいのだろう。 ・これら諸国の将軍、提督、艦長、民間人は十五世紀から、まさしく「世界征服」を目指して続々と海を渡ったではないか。 ・日本とアジアの目で見ると、日本に歴史的侵略の罪を着せる私たちの姿は、自分のガラスの家を粉々にしている(自分の罪を棚に上げて他人を非難している)立派な紳士だ。 ・私たちの非難は、むしろ、明治までの日本がいかに拡張主義でなかったか、これに対してヨーロッパ諸国がいかに拡張主義であったか、をきわだたせる。 ・秀吉の軍隊が朝鮮から追い払われた同じ時期、スペインはペルーとメキシコを征服し終え、フィリピンに地歩を固めていた。 ・ポルトガルは世界を駆け巡り、ジャワ、インド、マレーの沿岸地帯、マカオ、中国沿岸部に及ぶ広大な帝国を築きつつあった。 ・イギリス、オランダはスペイン、ポルトガルと競いながら、徐々にポルトガル領の大部分とスペイン領の一部を収め、中国、日本を目指していた。 ・十七世紀初め日本が孤立主義にこもったのは、ヨーロッパ諸国の「歴史的拡張主義」のせいなのだ。 ・十七、十八、十九世紀日本が世界から身を退いて独自の社会を発展させている間、ヨーロッパ人たちは爆発的拡張をつづけていた。 ・日本人は、私たちの非難は、西洋の猛烈な対アジア拡張政策から注意をそらすための策謀と考えるだろう。実は、西洋の拡張政策のほうが日本人の本性や伝統社会より、近代極東の混迷にずっと大きな役割を果たしているのだ。 3 初めの占領 ・日本の歴史を日本の立場から説明すれば、日本人は世界を征服する野望にとらわれていたのではない。世界のどこの国にも征服されたくないという気持ちに動かされてきたのだ。 ・日本人が小さい島の限られた中で独自の文明を育んでいたときも、世界支配を目指すヨーロッパ人同士の争いはつづいていた。十六、十七世紀のヨーロッパ人は拡張主義者だった。そして十八、十九世紀、産業革命が彼らをスーパーマンに変えた。 ・世界の未開発地域は、ヨーロッパのいずれかの国に次々と踏査され、占領され、支配されていった。 ・ヨーロッパ人はアメリカ大陸に侵入し、アフリカを分割支配し、東南アジアを吞み込み、極東に進出した。目的地は中国だった。 ・略奪が主な目的であり、極東より近いところに収奪できる土地があるうちは、西洋人にとって日本列島は無用の地だった。 ・しかし、十九世紀に入って、貿易と投資が目的となり、広大で豊かな中国の潜在的市場性がみえてくると、日本は戦略的重要性を帯びてきた。 ・そのころ中国に最も大きな関心をもっていたのはイギリス、フランス、ロシアである。 4 中途半端な力は引き合わない ・今日、私たちが日本を罰しているのは、彼らが自国でも国際社会でも狂暴になったからだという。 ・日本人は内では全体主義者に、外では「凶暴で貪欲」になった。なぜなら、彼らはもともと侵略的であり、彼らの伝統文明が「戦争願望」をあおったからだ、と説明するのである。 ・しかし、史実を子細にみると、答えはかなり違ってくる。近代日本が仲間入りした当時の国際社会は、政治・経済を中央管理しなければ生き残れない状況にあった。だから日本は中央集権国家になった。 ・日本人は暴力と貪欲が基準であり、正当である国際社会に入ったから「凶暴で貪欲」になった。 ・日本人に暴力と貪欲を組織する国際的技術を教えたのは外国の専門家たちなのだ。 5 理論と実践 ・日本人は勤勉で真面目な民族だった。八世紀に行動的な朝廷貴族と高級官僚、工匠とその弟子たちが、唐の首都を模して奈良の都をつくったように、十九世紀の日本人は東京を西洋型の都市に変えようとした。 ・日本人には大きな目的があった。近代化を達成して、抑圧的で屈辱的な「不平等条約」大勢から抜け出し、主権を取りもどしたかった。 ・科学と機械力で自信をつけた欧米人は、自分たちはアジア人やその他の「後れた」人種より本質的に優れていると確信して植民地に対していた。 ・欧米の行動様式は欧米人が「正しい」と認めたものであり、それ以外の行動様式は「間違い」だった。欧米に順応すれば「進歩」であり、順応できなければ「反動」とされた。 ・私たちが戦中戦後を通じて、日本を非難する理由は、中央集権的経済体制の発展が「全体主義」的であり、「戦争願望」をつくり出したというものである。 ・しかし、当時の欧米列強はこの発展を歓迎していたのだ。文明の遅れた韓国と中国に西洋文明の恩恵をもたらす国、近代的秩序と規律をもつ国家が必要だった。だから日本の近代化が求められていたのだ。 ・私たちは、日本が西洋文明の理想に反したことを非難している。しかし、日本が欧米社会に仲間入りさせられた歴史の事実をみるなら、日本が西洋の理想を学ばなかったなどとはとてもいえない。 ・欧米列強こそ国際社会において自分たちの原則を守らなかったし、自分の国の中でさえ原則を実践していなかったのだから、そういう非難がどこから出てくるのか、理解に苦しむのだ。 ・いかなる国をもって西洋文明の正しい規範とするか、列強の間に何の合意もないことに日本はすぐ気づいた。 第四章 最初の教科「合法的に行動すること」 ・「韓国の独立は、その戦略的位置に鑑み、日本の死命を制する大事であった。したがって、日本は韓国が名実ともに独立することを心から願っていたのである。しかしながら、独立は悪政につぶされた韓国国民の能力を超えるものであった。韓国が中国またはロシアの手に落ちるのを防ぐため、日本は二度の戦争を経て韓国を保護下におくことを宣言した。この実験は失敗した。そこで一九一〇年に締結した併合条約によって、日本は廃墟の上に新しい韓国を建設する責任を担ったのである」 ――水野錬太郎「現代の日本」1933年9月 ・「私たちはアメリカから多くのこと、とくに、隣接地域の不安定政権にどう対処するかを学んできた。そして、学んだことを実行すると、先生から激しく叱られるのである」 ――新渡戸稲造(マサチューセッツ州での講演。1933年) 1 歴史の復活 ・今日、日本を裁く判事席に着いている三大国の中で、当時日本の対韓国政策に反対していたのはロシアだけだが、そのロシアも日本の韓国での行為が許せなかったのではなく、自分が日本の地位を占めたかったにすぎない。その当時の米英両国政府にとっては、ロシアが韓国にいるより日本にいてもらったほうがよかったのだ。 ・十九世紀半ばの韓国と中国は、日本と同じように、西洋文明から遠ざかっていたかったのだ。しかし、欧米の本当の狙いである中国が最初に開かれ、ついで中国を狙ううえで戦略的に重要な日本が開かれた。欧米列強にとって韓国は直接的な意味をもっていなかった。だから、韓国は一八七〇年代半ばまで、「隠者の国」でいることができたのだが、日本は痛い思いをしながら、西洋の先生から教わった礼儀正しい国際慣行なるものを実践に移そうとしていた。 ・日本にしてみれば、すでにアジア沿岸部の大部分と日本の南北にある主要な島を収めた列強が、中国と韓国を切り取って影響圏内に入れ、独占的支配領域にすることは絶対に認められなかったのだ。 ・十九世紀の日本はヨーロッパ列強に命令できる立場にはなかった。日本にできることといえば、何とか西洋と同等の地位にのぼり、仲間に入れてもらうことだった。そういう日本を助けたのは、国際的対立関係、具体的には大英帝国とロシアの伝統的対立だった。 ・歴史は繰り返さないという人たちは、日本という立場から、歴史に近づいてみるべきだ。「共産主義」という言葉が聞かれるようになる以前から、イギリスは自分たちの合法的領分とみなす地域に、拡張主義のロシアが入ってくるのを防ぐために、同盟相手を変えながらさまざまな手段を駆使して戦っていた。 ・一八五四年、アメリカが他に先駆けて日本を国際潮流に引き入れることができたのは、イギリスとフランスがロシアの地中海進出を阻止するために、クリミア戦争でトルコ帝国を支援するのに忙殺されていたからだ。 ・英仏両国にしてみれば、ロシアの地中海進出は、極東に展開する自分たちの帝国と勢力圏にいたる独占ルートを脅かすものだった。 ・地中海で阻止されたロシアは、太平洋への出口となる不凍港を求めて、北東アジアへの進出を図った。 ・ロシアは英仏が中国から力で引き出した譲歩を利用して、日本と朝鮮北部に隣接する沿海州とウラジオストクを確保した。そして、日本本土の北に位置し、地理的には日本列島の一部である樺太と千島列島に入り込んだ。 ・樺太が日本本土のすぐ北にあり、狭い日本海をはさんですぐそこがロシア本土という状態は、日本にとって愉快ではなかった。 ・イギリスもまた面白くなかった。彼らはよその国が極東で支配的地位を占めることを望まなかった。 ・日本も韓国も中国との関係において、戦略的に「架け橋ないし防御壁」の役割を果たす位置にあったが、半植民地の日本では、いかなる力の均衡ゲームにも役立たない。かといって、相争う列強が満足いく形で分割するには、日本は小さすぎた。 ・日本政府は不平等条約によってすべての大国に縛りつけられていたから、一国に与えられる特権は自動的に他の国にも与えられる。日本がこの制約からぬけ出さないかぎり、一つの大国とだけ条約を結ぶことはできなかった。そこでイギリスは日本に「独立」を急がせた。 ・ロシアに対抗するため、一八九三年、「日英通商航海条約」で始まる日英同盟は、一九一二年にアメリカの圧力で解消されるまで、イギリスの極東政策の基盤となった。日本を小「大国」として台頭させた大きな力はこの同盟だった。 2 韓国の奴隷化 ・日本の統治グループは、国内情勢を安定させるとただちに、教わったばかりの国際関係のテクニックを韓国で実践し始めた。 ・しかし、韓国は欧米列強だけでなく、日本と交渉を始めることにも抵抗していた韓国は古くから中国の属国だった。国を統治する王家はあったが、彼らは中国朝廷に朝貢し、外交政策は中国に指導を仰いでいた。 ・しかし、日本は一八六九年、中国朝廷を迂回して、韓国に通商のための開港と、日本の鎖国政策で断絶されていた通商・文化関係の復活を働きかけた。 ・日本は、ペリーのように、辛抱強く、丁重で、執拗だった。 ・鹿児島や長州のような事件が起きた。日本は国際法を遵守させるために砲艦を派遣した。一八七六年、日本は韓国を「説得」して数ヵ所の港を開かせた。そして、日本人は治外法権に守られて定住し、交易できるようになった。 ・欧米列強は反対するどころか、むしろこれに乗じ、若い生徒につづいて自分たちも特権を得た。一八八二年までに、アメリカ合衆国、大英帝国、イタリア、ロア、フランスが韓国に代表部を開いた。 ・日本はまだ欧米列強の半植民地だったが、韓国では、遅れた国民を近代化する役割を担う、列強と対等の「進歩的」[注1]勢力として認められていた。 [注1]今日、私たちは天皇を反動的権力、「恐ろしい病根」と非難しているが、十九世紀当時は欧米列強に友好的な新政府の代表であり、日本の近代化に貢献したことから、「進歩」の象徴と考えられていた。韓国では、中国との古い関係に固執し、近代化に反対する韓国国王は「反動」の象徴とされていた。 ・欧米の進出が、日本に革命的状況をもたらしたように、韓国にも革命的状況がつくり出された。 ・韓国の「進歩的」勢力の先頭には日本が立っていた。当時、日本は進歩的勢力を代表し、中国は近代化に反対する保守勢力を代表していた。韓国の最も戦闘的で「進歩的」な若い世代は、親日・反中国勢力になった。欧米列強が日本の親欧派を支援したように、日本は韓国の親日派を支援した。 ・日本の侵略的行動を警戒する中国は、韓国の首都に駐在代表を派遣した。中国のこの動きは、当然、緊張を高めた。 ・イギリスは日本の韓国での行動を、注意深くかつ好意的に見守っていた。 ・ロシアはすでにウラジオストクに根を下ろし、中国から満州横断鉄道の建設権を得ていた。 ・一八八四年、韓国国王はロシアに軍隊の要請を依頼し、その見返りにポート・ラザレフ(永興湾)を海軍基地、石炭補給基地として提供しようとした。これは日本、中国、イギリスを怒らせた。 ・日本と中国の抗議で韓国の申し出は実現しなかったが、イギリスは念を入れて、朝鮮半島の先端に近いポート・ハミルトン(巨文島)を占領し二年間そこにとどまった。 ・こうしたことから、戦略的に重要な韓国は、力が弱いために基地と土地使用の要求を拒否できないことがはっきりした。ロシアの領土的近接と満州への急速な進出は韓国にとって脅威だったが、それはとりもなおさず、イギリスと日本に対するさし迫った脅威として受け止められたのである。 ・韓国は中語の「属国」だから、中国に圧力をかけて譲歩を引き出すことができた国が、韓国での特別待遇を得られる。この状況では、イギリスと日本の「利害」は完全に一致していたといえる。 ・一八九三年七月十六日、日英両国は、イギリスが五年後に治外法権を放棄することを取り決めた青木・キンバリー条約に調印し、七月二十三日、日本は韓国の「独立」を勝ちとるためと称して中国に宣戦布告した。 ・日本からみれば、この戦争は完全な成功だった。西洋列強は喝采し、日本における彼らの「特権」を相次いで放棄した。そして、日本を対等の主権国家として承認した。 ・日本は韓国に自由を贈り、韓国国王は中国皇帝、日本国天皇と肩を並べる皇帝の地位を得た。 ・日本は台湾と澎湖諸島を割譲され、西洋の合弁会社が高利で中国に貸した賠償金で金本位制についた。 ・日本は中国本土の遼東半島で大きな租借地を得ることになったが、ロシアが強く反対した。数年後、フランスとドイツに後押しされたロシアは中国との条約によってこの地域を領有した。 ・日本が最初の教育で学んだことを知りたければ、欧米列強が中国で「割譲合戦」を演じていたこの時期がよく教えてくれる。 ・満州と沿海州にロシア、山東省にドイツ、華北、揚子江流域、香港にイギリス、雲南省にフランスというように、中国はいくつかの「勢力圏」に画然と分割された。日本は韓国を手に入れ、福建省を確保したが、この地域では具体的開発に手をつけていない。 ・外国勢力の進出で、中国は混乱状態に陥った。義和団事件が起き、欧米列強と日本の連合軍に徹底的に鎮圧された。いまや独立国となった日本は、イギリスの完全なるパートナーとして、西洋文明のために非文明の中国と戦って「立派な仕事」をしていた。 ・多くの国が中国割譲に殺到した事実は、極東に介入した超大国がイギリスとロシアだったことを不透明にしているが、両国が超大国であったことに変わりはない。 ・中国本土のイギリスと満州のロシアは、それぞれ鉄道建設、鉱山開発、工場建設などの大事業を着々と進め、経済権益を追求していた。 ・韓国の日本は小さい存在だったが、ライバルとしての力を貯えていた。日本は韓国と中国における彼らの「権益」はイギリスあるいはロシアの権益以上に、当然のものであると考えていた。 ・日本は競争相手の大国のどこかに助けてもらわなければ、自分たちの権益を確保できなかった。日本にとって幸運だったのは、ロシアを押し返すという点では、イギリスと利害が一致していたことである。 ・日清戦争後に締結された日英同盟は、やがて日本とロシアが戦うことを想定して、日本強化のために結ばれたものである。一九〇四年、日本はロシアに宣戦布告し、再び「韓国の独立」のために戦うことになる。 ・日本が西洋に認められるうえで、日露戦争は有益な学習だった。文明世界は奇妙な小男たちの勇気と闘争心に仰天し興奮した。彼らは民族衣装のキモノを着ながら、たちまちにして近代戦の技術を習得していたのだった。 ・日露戦争は日本を「世界国家」に変えた。 ・この戦争で日本は旅順港を含む遼東半島のロシア領有地、ロシアの南満州鉄道、樺太の南半分を獲得し、アジア大陸に橋頭堡を築いた。 ・ロシアが大陸にもっていた諸権利の譲渡に関しては、もちろん条約に基づいて中国の同意を得ていた。 ・若い同盟国に、こういう問題は「法的に」処置しなければならないと教えたのはイギリスである。 ・ロシアと日本が平和交渉を進める過程で、イギリスは日英同盟を更新した。 ・新たな同盟関係では「韓国の独立」は忘れ去られ、その代わり、イギリスは韓国と中国における日本の「政治、軍事、経済」権益を永久に尊重することを約束した。 ・これに対して日本は中国とインドにおけるイギリスの永久権益の尊重を約束した。 ・日本がこの時代をどのようにみていたか、早稲田、法政両大学の国際政治学教授、信夫淳平博士は、次のように要約している。 「日英同盟の主目的は、中国における英国の権益と、中国、韓国における日本の権益を第三国の侵害から守ることであった」 「日清戦争ののち、日英同盟は共通の利益が極東において結びついているとの認識を得た」 「とくに英国は、義和団事件で日本が果たした優れた役割を通じて、日本の実力を認識したのである」 「この同盟によって日本はさし迫った対露戦争の勝利を事前に確実にし、他の勢力がロシアに加担するのを未然に防ぐことができた」 「日本が戦争目的を達成できたのは、英国と同盟していたからである」 ・アメリカも中国、韓国、日本との間で「和親」条約を結んでいた。私たちは表向きは中立だったが、実際行動では日本を支持することになった。 ・一八九四年七月二十九日、韓国駐在のシル米代表は次のように書いている。 「……日本は思いやりの態度で韓国に接していると思う。今度こそ、韓国を中国の束縛から解放しようとしているようだ。韓国国民に平和と繁栄と文明開化をもたらすことによって、力の弱い隣国を安定した独立国にしようと考えている。こうした日本の動機は韓国の知識層である官僚の多くが歓迎している。アメリカにも異論はないと思われる」 ・日清戦争が継続中の一八九四年、アメリカは治外法権をはじめとするすべての特権(特定関税制限を除く)を放棄する新条約に関し、日本と交渉し、日本を完全な主権国家として認めた。 ・日露戦争では、米政府は日本を強力に支持していた。 ・ルーズベルト大統領は、日本が勝っている段階で、しかも日本の不十分な戦備が底をつく前に、戦争を終わらせようとしたのだ。 ・日露戦争後、アメリカは「事実の論理」を認め、韓国から代表を引き揚げた。 ・韓国皇帝はセオドア・ルーズベルト大統領に訴えたが、大統領は韓国は「自主統治にも自衛にもまったく無能力であることがはっきりした」として、介入を拒否した。 ・「その後三年の間に、現地情勢に詳しい外国人たちの称賛をかち得るような改善が数多く実現した」と書いたアメリカの歴史家もいる。 ・一九一七年、ランシング米国務長官と日本の石井(菊次郎)元外相の間で交された協定で、米政府はとくに韓国と中国における日本の特権を認めた。 ・ランシング長官は次のように確認している。 「合衆国政府と日本は、領土的近接が国家間に特別な関係を構成することを認める。したがって、合衆国政府は日本が中国に、とくに日本の租借地が近接する地域に権益を有することを認める」 ・こうした公式記録を見るかぎり、なぜ日本が韓国国民を「奴隷にした」として非難されるのか理解できない。 ・日本の韓国での行動はすべて、イギリスの同盟国として「合法的に」行なわれたことだ。国際関係の原則にのっとり、当時の最善の行動基準に従って行なわれたことである。しかも、その原則は日本がつくったものではない。欧米列強、主にイギリスがつくった原則なのだ。 ・日本は韓国の「独立」という実にもっともな動機から、中国、そしてロシアと戦った。 ・第二次世界大戦後の日本は、自分たちは何のために戦ったか忘れてしまったかもしれないが、日本はとにかく当時の国際慣行を律儀に守り、それなうながされて行動したのだ。 ・日本外務省が韓国の「対外関係と対外問題」を「管理統括」し、日本人の租特が韓国の首都で行政権限を与えられていたのはすべて、韓国政府と締結した条約にもとづくのである。 ・一九〇七年、韓国皇帝はハーグの第二回万国平和会議(当時の平和愛好国の会議)に抗議しようとしたが、皇帝の特使は発言の機会を与えられなかった。そして皇帝は退位に追い込まれた。 ・一九一〇年、日本が韓国を併合したのは、新皇帝が「誓願」したからだった。 ・パ―ルハーバー以前は、日韓関係について語る歴史家は、日本は欧米列強から教わった国際関係の規則を、実に細かいところまで几帳面に守っていた、といってほめるのだ。 ・トリート教授によれば、日本は「……一つひとつの手続きを外交的に『正しく』積み上げていった。そして、……宣言ではなく条約で、最終的な併合を達成したのである」 ・事実、列強の帝国建設はほとんどの場合、日本の韓国併合ほど「合法的」手続きを踏んでいなかった。 ・日本の帝国建設について、フォーチュン誌は「十九世紀の日本はヨーロッパ帝国主義を真似て、帝国主義にふさわしい力を得ようとしていた。そして、日本は西洋帝国主義列強の役をあまりに見事にこなした。だから、中国とロシアに対する日本の勝利は、あたかも西洋の勝利のようにみえた」と論評する。 ・いうまでもなく、これは「西洋の勝利」だったのだ。 ・イギリスとアメリカの直接、間接の支援がなければ、日本は海外に遠征に出ても、一つの基地も固めることができなかったろう。一九三七年の「日華事変」がいい例だ。 ・私たちは日本人を「コピー屋」と呼び、西洋を真似したと批判しながら、日本が国内制度や国際関係で失敗したのは、私たちの原則ではなく実際行動を真似したからだ、とは思っていない。アジアの人々はこの点をよくみている。 ・たとえば、インド国民会議の派の指導者、バンディット・ネルーは当時の日本について「日本は工業大国になった。そして、西洋列強の行動を真似して帝国主義的掠奪国家になった」というのである。 ・アジアやその他の植民地、半植民地の人々の視点から見れば、「凶暴で貪欲」な帝国を建設した日本は、まさしく、新たな「掠奪的西洋列強」だった。しかし、日本を「凶暴で貪欲」な国家と非難する私たちは、それを無視してきたのである。 3 全体主義 ・今日、私たちが日本の韓国「奴隷化」を非難するとき、私たちがいわんとしているのは、私たちは韓国国民の幸福を考えているということなのである。 ・しかし、日本が韓国を奴隷化していたとき、各国が考えていたのは韓国国民の幸せではなく、この地域の資源を開発し、通商上の優位を握るのはどこか、そして韓国という戦略的「橋頭堡」を押さえるのはどこか、ということだけだった。 ・日本がアジアと接触を再開したとき、彼らが接触の基盤にしたのは昔の関係ではない。日本が鎖国している間に、西洋がつくり出した新しいルールを基盤にしたのだが、そのルールは私たちが思うほど現地住民の幸せを考えてはいない。 ・今日、日本人を非難する私たちの論理には、西洋人は伝統的に「後進民族に西洋文明の恩恵をもたらす」こと、すなわち近代科学、医学、公衆衛生、倫理原則を教え、教育制度を改善し、政治的、経済的に自由な社会に導くことだけを考えて行動してきた、という思い込みがある。 ・しかし、西洋は民主主義国でさえ、植民地に民主主義をもたらしはしなかった。 ・私たちが日本の発展をもっとじっくり分析し、日本人は「間違っている」と非難することだけに時間を費やさなかったら、私たちがその壊滅のために戦ったと主張する「ファシスト」社会の源を、もっとはっきり突きとめることができただろう。 ・私たちが「全体主義」社会から思い浮かべるのは、個人と集団に対する残虐行為である。あるいは、人種的偏見、市民的自由に対する警察の暴力、政治的討論と選択の弾圧、生まれつき優れたものが政治、社会、経済を支配するという「指導的人種」観、あるいは「力は正しい社会をつくる」という独善的信仰、などである。 ・私たちはドイツ人、イタリア人、日本人、そして、ときに応じてロシア人を感情的に嫌ってきた。彼らは野蛮と弾圧と侵略の社会をつくり出し、選択した、と私たちは非難するのだ。 ・この非難は、西洋人(アメリカ人もある程度まで)が植民地や半植民地に対してとってきた態度にも当てはまるが、私たちはそれに気づいていないらしい。 ・十九世紀に日本人を教育したとき、西洋人は平和と民主主義を教えなかった。平和と民主主義は自分たちだけのものなのだ。 ・彼らが教えたのは「後れた」地域の住民との関係、そしてパワー・ポリティクスの実践であった。 ・もしこれがヨーロッパで行なわれたら、私たちが「全体主義」として非難することになる行動を教えていたのである。アジアや植民地の人々はそうみている。 4 改革か戦略か ・いまになってみれば、日本が韓国を「奴隷化した」ことは明らかだ。日韓相互防衛のため、自国を併合してほしいと日本に要請した韓国皇帝の「請願」は侵略を糊塗するための法的擬制であることも明らかだ。 ・しかし、その当時のイギリスとアメリカは「奴隷化」も擬制も認めていた。なぜなら、そのころの日本は力の均衡地域で極東の「安定」を維持する「安全な」「同盟国だったからだ。 ・軍事同盟によってイギリスに縛りつけられた小国日本は、イギリスの安全保障体制の「番犬」の役割を演じていた。 ・日本の役割は潜在的「混乱」地域である韓国で「法と秩序」を維持し、より強大な敵がその地域で必要以上に勢力を拡大しないよう牽制することだった。 ・韓国は戦略的に重要だが軍事的に脆弱だから、力のある国が管理する。それが大国の論理だった。 ・イギリスは、もし韓国が「安定化」も「近代化」もされず、他国の「保護」もなく放置されていたなら、必ずロシアが入ってきて華北のイギリス権益をじかに脅かすだろう、と考えた。だから、日本は当然かつ「安全」な同盟国だった。 ・日本は近代的工業・軍事大国に必要な天然資源をほとんどもたない島国だから経済封鎖にもろい資源的に脆弱な日本は、イギリスとの軍事同盟に意のままにされる操り人形だった。 ・一九二一年ワシントン会議で日英同盟が解消されたのちも、海外の物資供給源と市場に大幅依存しなければならない日本は、国家というより、単なるチェスの駒だった。 ・一九三一年の満州事変で初めて日本は、西洋の先生である、イギリスの事前同意を得ないでうって出た。満州事変はアメリカと国際連盟から非難された。 ・第一次世界大戦後、列強は主権国家間の紛争解決の手段としての戦争を原則として否定することを宣言していた。 ・また、中国に権益をもつ九ヵ国(アメリカと日本が含まれているが、ロシアは入っていない)は「中華民国」の「領土保全」を尊重する条約を交わしていた。 ・日本に対する非難は、こうした事実を「法的」根拠にしていたが、「中華民国」は名前だけの主権国家にすぎなかった。 ・九ヵ国条約の締結国自身が中国の「領土保全」を尊重していなかった。すなわち、条約当事国のほとんどが中国の大都市に大租界をもち、軍隊を駐留させ、中国の河川に自国の砲艦を遊弋させていた、彼らは治外法権と特権を主張し、中国の「領土保全」はまったく無視していたのだ。 ・日本と中国の関係は、全条約当事国と中国の関係がそうだったように、主権国家間の関係ではなく、大国と半植民地の関係だった。 ・九ヵ国条約状況変化の「論理」に従って変更し調整できる法的擬制(韓国皇帝の請願と同じ)であると、日本は解釈していた。しかも、国際連盟は満州事変を非難したけれども、植民地体制そのものは何ら非難していない。 ・国際連盟の加盟大国は依然、アジアに覇権をもち、中国での勢力圏を支配している。だから、連盟非難にはそれぞれの国の思惑がからんでいると日本は考えたのだった。 ・日本からみれば、欧米諸国は、中国の「領土保全」(日本を非難している国自身が侵している)を真剣に考えているのではなく、それまで日本の勢力圏として認めていた地域に、西洋の支配権を広げようとしているから、日本を非難しているにすぎない。 ・超大国か遠隔地の「勢力圏」と「特殊権益」を握る現在のような国際関係システムが存続し、超大国が自分たちの「帝国ルート」と様々な「防衛システム」、すなわち「勢力圏内の連帯」や遠隔地の「防衛拠点」の必要性を叫びつづけるかぎり、弱小国家が彼らの例にならうことを許さない超大国の論理は、「民主主義と秩序に向かっての前進」などということはできない。 ・その論理は、植民地の権益と利権領域の現状を固定するための装置にほからないのだ。 5 国際教育なるもの ・今日私たちは「法と秩序」「条約の尊重」「国家の平等」「領土保全」「個々の人間に対する人道的配慮」といった、誰も否定できない原則に立って日本を非難している。しかし、最初の教育で日本は、そうした原則は文字に書かれた教典ではなく、力の強い国が特権を拡大するための国際システムのテクニックであることを、欧米列強の行動から学んだのだ。 ・西洋の原則というものは、国際法のうえであれ、人類の幸せを考える人道主義のうえであれ、現実には強い国々が弱い国を犠牲にして、自分たちの利益の増大を図るための術策にすぎないということだった。 ・領土の併合、あるいは力による経済的優位の獲得も、超大国がつくり出したルールに従って、「合法的にやりさえすれば」正当な行為とみなされる。日本が列強の行動からみてとったのは、そういうことだったろう。 ・日本には合法的術策というものがはっきり見えてきたようだ。つまり、力を行使できる強い国は、「合法的」要求(外交ないしは通商関係の)を通すために「後れた」地域に力をつかう。ひとたび、要求が通れば、条約に書き込む。 ・この手続きによってすべての行為が「合法」化されるだけでなく、弱小国は半永久的に「条約で決められた誓約を尊重」しなければならない。弱小国(あるいは後進地域の住民)が平等の関係を望むなら、強大国のために貢献して新たな地位を得るか、要求を出せるだけの力をもつことだ。 ・日本人が実戦で学んだ国際ルールによれば、力の立場を確立した国は、力の弱い国において特権的地位が得られるのだ。 ・大国は必要とあれば力で「防衛」できる「 ・大国が近接の、あるいは遠隔の地域に「友好的」政府を求めるのは「法的」に正しい。 ・そして、情勢が「国民を守る」あるいは「治安を維持する」ことを必要とした場合には、経済的圧力、または、できれば外交的手段で、「防衛上絶対に必要」なら武力によって、そのような友好的政府の樹立を助けるのは、合法的行為なのだ。 ・ルールは大国の利益に役立つかぎり「合法」とされた。大国は自分たちの利益に必要であると思えば、必ず「事実の論理的帰結として」ルールを変えた。 ・日本が学んだのは、大国として認められたいなら、ルールを適用される側ではなく、ルールをつくる側にまわれ、ということだった。 ・日本はまた、「後れた」国でも運よく本物の大国と同盟できれば、名誉ある大国の地位を得ることができる、ことを学んだ。 ・私たちは、日本人は「凶暴で貪欲であると非難する。しかし、最初の教育で日本は、人道主義、機会均等、人種の平等なるものは、国際法のルール同様、「法的擬制」にすぎないことに気づいたのだ。植民地住民は、日本より前に、ルールの理想論的内容と植民地の現実を比較して、それを知っていた。 ・欧米列強は「平等」を口にする。しかし、実際には人種差別を行ない、人種と力と「条約上の権利」を盾に特権を要求している。 ・彼らは「自由競争」と「自由経済」を口にする。しかし、彼らは後進地域で独占支配を強め、経済的圧力あるいは武力で高価な権益を獲得し、特権として関税(自国だけでなく、支配地域の関税も)も管理している。 ・彼らは「主権上の平等」という言葉をつかう。しかし、彼らは現地政府を経済的圧力と武力で動かし、自国の法律に守られて居住している。 ・国際関係のルールとは、実は、暴力と貪欲を合法化したものだ。基本原則の中で大国がきちんと守っているのは唯一、各国の政策立案グループが設定した「国益」だけではないのか。日本人が学んだのは、そういうことだった。 第五章 鵞鳥のソース 1 満州事変 ・ここで論議しているのは、日本が有罪かどうか、日本国民が受けている懲罰は妥当なものか、そして現在私たちが進めている教育計画の結果が極東での戦争を抑止しうるか、という問題である。 ・私たちの告発には、日本人の「戦争を好む本性」と一九三一年にさかのぼる日本の軍事行動が含まれている。しかし、満州事変までの日本の「暴力と貪欲」は、欧米民主主義国がつくった国際法で許されていたのだ。日本帝国は「合法的」につくられたのである。 ・一般に行なわれている日本非難は道義と人道を基盤にしているが、外国の侵略を押しとどめるのは道義ではなく、国際法である。 ・私たちが日本を罰する権利は、庶民感情や理想によっているのではない。超大国アメリカの工業力と軍事力を後盾にした米国務省の決定によっているのだ。 ・今日行なわれている公式の日本非難には、韓国の「奴隷化」とか「凶暴で貪欲な」という道義的表現がつかわれている。しかし、日韓併合当時は、「奴隷化」という言葉はつかわれていなかった。「法と秩序」と日本の手段の「合法性」という言葉で議論されていたのである。 ・事実をみれば、満州事変も同じであることがわかるだろう。韓国でも、満州でも、国際問題は「道義的」かどうかではなく「合法」かどうかなのだ。 ・欧米列強は韓国問題では日本を無罪とし、満州事変では有罪とした。しかし、侵略行為で有罪としたのではない。国際連盟もアメリカも、日本が満州を侵略したという非難はしていないのだ。 ・日本は国際条約を破り、条約当事国の満州における権利を侵したから有罪なのである。 ・国際関係を正しく議論しようと思ったら、道義と国際法はまったく関係ないという事実を直視すべきだ。 ・日本を有罪とするアメリカの世論は、満州事変を明白な侵略行為と考えている。しかし、事実はまったく違うのである。アジアからみれば、これこそ日本と欧米列強が合法性を装い合う伝統的パワー・ポリティックスなのだ。 ・米国政府と国際連盟は「九ヵ国条約」、「門戸開放」政策、「パリ条約」をもち出し、一方、日本は「合法的自衛権」で対抗した。日本がいうのは「文明国家が……国民と海外の権益を守る」権利、「自決」の原則、弾圧的政府に対する革命の権利である。 ・中国からみれば、欧米列強も日本も、これらすべての「原則」をつかって、極東における「権益」を守り、あるいは拡大しようという本音を覆い隠しているのだ。 2 中国の歴史 ・満州事変は複雑で混沌とした中国情勢の所産である。そして、こうした情勢をつくり出した責任は、すべての欧米列強が分担しなければならない。 ・欧米の進出は日本と韓国に大きな変革をもたらした。同じように中国でも複雑な革命状況を生んだが、ここでは情勢はよくなるより、むしろ悪くなった。 ・日本では、「進歩的」親欧勢力がすみやかに状況を抑え、安定した中央政府のもとに国家統一を成し遂げた。 ・新政府は所有権、通貨の統一と安定、銀行制度、国内法制の改革、貿易の管理など欧米列強が求める改革を実現した。 ・しかし、中国はあまりにも広すぎて、仮に国民がその価値を認めたにしても、近代化計画はそうそう早く達成できるものではなかった。 ・だから、欧米列強は自分たちの「利益」を守るために、主要都市における租借権あるいは割譲地を確保し、治外法権の保護のもとに自主行政権を行使し、これによって取引相手の中国人を規制したのである。 ・居留外国人が享受しうる広範な特権が条約に明記された。中国に半植民地的地位を押しつけたことから、「不平等条約」という名前で呼ばれた条約である。 ・一八四四年以降この条約で保護された外国人社会は、共同して治外法権をより有利な特権的制度へと発展させていく。 ・一九三一年当時、中国の産業資本の四分の三は、中国の低賃金水準を利用する外国人に握られていた。 ・外国人(実際にはイギリス人)が関税と塩税を管理していた。そして、その収入(西洋列強が承認した「中央政府」の主要収入源)のほとんどが対外債務の利子返済に充てられ、政府の行政運営、近代化、福祉にはつかわれなかった。 ・イギリスは、「中央政府」との関係で特権的地位を握っていた。これが日本にとっては大きな不満だった。 ・そのうえ、関税と塩税を担保にするイギリスの借款には利子が支払われているというのに、日本は膨大な額の債権を焦げつかせることになる。 ・外国勢力はまた、中国の政治をかなりのところまで動かしていた。 ・一九一一年の中国(辛亥)革命で満洲王朝(清朝)が倒れ、中華民国の成立が宣言された。 ・しかし、新しい共和国はすぐ、北京の保守政権、南部の革命政権、独自の軍隊と通貨をもち地方権力を握る軍閥小君主などの対立政権に分裂した。 ・西洋列強はそのうちの一つ、一九二八年まで北京を本拠としていた政権だけを「中央政府」として承認したが、それでいながら、競って「地方軍閥」に金を貸し与え弾薬を与え、特権を得ようとしていた。 ・小君主たちは西洋列強の歓心をかおうと競っていた。彼らはいつも「認知」という勲章をつけた北京と、中央政府に入ってくる利益を争っていたのだ。 ・西洋列強は、厳重に守られた租界の中で、自分たちだけは安泰だったが、中国の安定にはほとんど貢献していなかった。中国人はこうした体制には不満を抱いていた。 ・満洲王朝を倒した中国人は、次は弾圧的な地方小君主と西洋列強からの解放を目指した。彼らにとって支配階級と西洋列強の癒着は、もはや耐えられないものになっていた。 ・中国に特権をもつ国は、ヨーロッパのほとんどの国とブラジル、ペルー、メキシコを含め全部で十三にのぼる。 ・しかし、はじめから、巨大な経済権益をもつ最大の外国勢力はイギリスである。 ・日露戦争までは、ロシアがイギリスと並ぶ勢力だった。一九〇四年から五年にかけて、日本はロシアと戦ってその勢力拡大を食い止めてくれた。 ・そして、日本は活動の場を朝鮮半島と満州に限定していたから、イギリスをはじめとする西洋列強は、中国本土でほしいままに振る舞うことができた。 ・しかし、第一次世界大戦で力の均衡が崩れた。敗戦国ドイツがもっていた山東省を獲得しようとする日本の試みはアメリカに妨げられたが、日本は大戦を利用して、強引に中国での権益を求めていった。 ・それ以上に極東の「安定」を揺さぶったのは、共産主義革命という形をとって再び出現したロシアである。 ・中国に権益をもち、アジアとその周辺地域に植民地をもつ大国にとって、共産主義ロシアは帝政ロシアよりずっと危険な対抗勢力だった。 ・ツアーのロシアは「合法的」にゲームをしていたが、ソ連は「帝国主義」を否定し、帝政時代の「不平等条約」を認めず、西洋列強が特権を享受しているシステムの基盤そのものを直撃してきたのである。 ・加えて、ソ連の既存体制否定と革命的スローガンが、中国の革命的大衆の感情に火を点けた。彼らにとって共産主義は、地方の軍閥権力の圧政と西洋列強の支配から自らを開放する理想の象徴だった。 ・一時期、ロシア人顧問が国民革命軍と行動をともにしていた。しかし、革命軍が上海を手に入れる直前になって、革命軍指導者の蒋介石は保守派と欧米列強の説得に応じ、ロシア人を排除した。 ・彼は革命勢力に対抗して南京に保守的な軍事独裁政権を樹立し、欧米列強はこれを中央政府として承認した。 ・満州事変は、その後の日華事変同様、この複雑な状況の論理的帰結だった。 ・大きな問題は中国での「権益」を守り、拡大しようとする西洋列強同士の対立だった。 ・争っているのは、日本と中国ではなく、日本と欧米列強だったが、ロシア革命で状況が複雑になった。 ・これによって中国の共産主義思想が日本の勢力拡大より大きな脅威になろうとしていたのだ。 4 アメリカの役割 ・国際関係の上で「侵略」という言葉が、満足に定義されたことは一度もない。 ・満州事変に対するアメリカの姿勢は、中国人民への人道的懸念、中国の主権と平和を守ろうという意志に発している、というのが米国民の一般的理解である。 ・しかし、そういう理想と愛に貫かれた正しい目的を、国際法の中にフォーミュラ(公式)として明文化するのはむずかしい。満州事変はそのむずかしさを象徴的に見せつけたのである。 ・アメリカが日中非難のよりどころにしたのは、一九二二年にワシントンで調印された九ヵ国条約である。 ・中国に「権益」をもつ八ヵ国の間で取り交わされた条約で、これによって各国は「中華民国」の「領土的・行政的保全」を尊重し、全当事国に対中貿易の機会均等を保障する門戸開放を約束し合った。そして、九番目の当事国である中国は調印国の権利を尊重することに同意したのだ。 ・米国政府は、この条約は中国の分割を阻止すると同時に、戦争を防止しようとする意志の表われであると解釈している。 ・しかし、平和と国家間の安定の土台であるべきこの条約は、二つの相反する目的をもっている。 ・すなわち、不平等条約体制下でアメリカの特権を守り、同時に中国の主権と平和を維持しようというのだが、不幸なことに第一の目的が第二の目的を殺してしまうのだ。 ・中国からみれば、九ヵ国条約は中国の主権を保障するどころか、否定するものだった。 ・何よりもまず、中国における西洋列強の特権的地位を保障する不平等条約体制を「固定化」し「合法化」するための合意である。これらの条約は中国にとって、屈辱的であるばかりでなく、恒常的な不安定要因だった。 ・中国が「国内秩序を確立する」までは、すなわち法制を改め、国際的に認知された強力な中央政府のもとに国家を統一し、「共産主義」革命勢力を抑え、反外国宣伝を止めるまでは、各国はそれぞれの権益と在留市民を守るために「条約上の権利」を保持すべきであると主張していた。 ・中国からみれば、国際条約(アメリカの政策基盤である)は条約締結国の権益を保護するほどには、中国の保護を考えていなかった。 ・一方で各国が牽制し合い、一方で高まる民族主義の流れを押しとどめるためのものだった。だから、中国は反日行動への支援を求めながら、西洋列強をすべて排除しようとしていた。 ・中国にいわせれば、満州事変に対するアメリカの施政は「中国の側に」立っているようだが、フォーミュラが適切ではないのだ。 ・中国の独立のためであるはずの行動が、実際には独立を侵している。 ・中国からみれば、アメリカの態度は中国に対して「公正無私」なのではなく、日本を含む列強との関係で公正無私であるにすぎない。 ・もしアメリカが対中国関係で本当に公正無私なら、アメリカは中国にもっていた特殊権益を放棄していたはずである。 ・だいたい、主権国家たるものはこのような権利を外国に与えはしないのだ。 ・私たちはどこの国の軍艦であろうとミシシッピー川に入るのを許さない。そうであるなら、私たちには揚子江に軍艦を配備する権利はないのである。 ・アメリカが常々、中国の主権を守るためだ、といってきた門戸開放政策も、実際の行動では中国の主権を否定するのだった。 ・ここでの問題は、中国が主権国家として西洋列強と交渉できるかどうか、ではない。西洋列強(日本も含む)が、おたがいにどこまで進んだら、中国を排他的植民地にして貿易と投資を独占することになるのか、その線をおたがいの合意できめることができるか、という問題にすぎない。 ・本当の敵は日本ではなかった。敵は、日本に満州での「合法的」権利を与えている不平等条約体制だった。このような体制がなければ、日本は満州事変を起こせなかったのである。 ・それでも、私たちは満州事変非難のすべての根拠を、中国と日本が条約体制を危機に陥れたことに置いていた。 ・現実政治の国イギリスは、国際連盟を代表する国として、中国と経済的に最も深いかかわりをもつ国として、そして、日本の古い同盟国として、満州事変を現実的にとらえていた。 ・イギリスは、中国における経済上のライバルである日本にあまり先までいってほしくはないのだが、同時に、日本は大国(中国での特権を認められた条約加盟国)であり、中国は半植民地である事実を認識する必要性も感じていた。 ・そして、日本に対して行動を起こすにしても、それが他の条約加盟国の中国に対する立場を弱めるものであってはならない、と考えていた。 ・なによりも、日本は一九二一年までイギリスの同盟国だった。 ・日本とイギリスは革命で揺れる中国の「法と秩序」を守るために協力しあっていた。 ・一九二五年から二七年にかけて、中国革命で情勢が混沌としていたとき(中国人はイギリスを排斥し、イギリスと日本の両方を嫌っていた)、上海と広東のイギリス支配圏で、日本は「警察」力によって一度ならずイギリスを助けた。 ・日本は、列強が必要なときにはとっている行動をとったにすぎない。それを犯罪と決めつけるのは、いかにも下策であった。 ・つい二、三年前、イギリスを始めとする西洋列強は、中国国内あるいは中国へのルートに総勢二万の軍隊を配備していた。 ・よその国が中国で軍隊や軍艦をつかえるのに、なぜ日本はいけないのか、彼らには理解できなかったろう。 ・アメリカと連盟がゆっくり動いている間に、満洲の事態は急展開した。 ・連盟が設置した調査委員会(リットン調査団)が満洲に到着する前の一九三二年二月二十九日、満州人代表が瀋陽に集まり、中国からの独立と独立国家、満州国の樹立を宣言した。 ・そして、リットン調査団が報告書を連盟に提出する前の一九三二年九月十五日、日本は新しい国を独立主権国家として「承認」したのである。 5 リットン報告 ・「文明」国は「古来」海外権益を守って来たのだから、日本が満洲で権益を守ることも「法的」に許されるはずだ。 ・もし関係大国が日本の行動に反対すれば、不平等条約の全構造は弱体化し、極東における力の均衡は崩れてしまう、というのが日本の理解だった。 ・ソ連が満洲に隣接していることから、日本は絶えず共産主義浸透の「脅威」を感じてきた。 ・日本軍が満州を軍閥政権から引き離し、安全を保障すれば、極東の安定に貢献できる。欧米列強はこの「事実の論理」を韓国の時と同じように十分認識しているはずだ、と日本は考えていたのだ。 ・しかし、日本は行きすぎたようである。一九三二年一月、満州事変は抗日運動が盛り上がる上海に飛び火した。 ・上海の租界に権益をもつ各国の軍隊が警備態勢についた。 ・日中両国が衝突し、日本軍は上海の中国側の拠点 ・各国は協同租界の周辺で起きたこの衝突に強い懸念を抱き、アメリカとイギリスは日本政府に抗議文書を送った。何度か交渉が重ねられた結果、戦闘は止んだが、五月まで事態は収拾されず、日本軍は撤退しなかった。 ・上海事変における日本側の狙いは、各国、とくにイギリスに圧力をかけることだった。 ・すなわち、華北で日本の立場が固まらなければ、中国の他の地域でも事態が悪くなることを各国にみせつけ、満州事変に同調させようとしたのである。 ・日本の華北への進出には、いつも華中あるいは華南のイギリス勢力圏をにらむ陽動作戦がともなっていたが、上海事変は拙劣だった。日本は支持を得るどころか、失ってしまったようだ。 ・一九三二年六月、日本はさらに重大な過ちを犯した。新満州政権が税収と塩税収入の全面管理政策を発表し、イギリス人税務管理官を追放した。 ・それまで中国の税収の三分の一は満洲からきていた。そしてイギリス人の借款の大部分はその収入で保証されていた。イギリスは日本の真意を疑い始めた。 ・フォーミュラはリットン調査団の報告で明確にされた。 ・報告は日中双方に責任があるとする。中国側の責任は、国内を混乱させていることである。それが日本を挑発したのである。 ・しかし、日本も秩序維持のためとはいえ、あまりにも行きすぎた。報告は日本の教唆によるものとしか考えられない満州の独立を認めることはできないとし、満州は中国の主権のもとに留まるよう勧告した。 ・同時に、報告は、満洲の情勢は明らかに監視体制が必要であり、何らかの形の「国際」軍によって満州を管理すべきであると勧告した。 ・しかし、「国際管理」には、現実的には、どうみても中国にいる日本のライバルが当たることになる。すべての関係国は、自分たち自身の勢力圏はあくまで自分たちで管理しようとしているのだから、日本にいわせれば、これは差別だった。 ・リットン報告は驚くべき文書である。調査団が集めた事実を証拠としてつかえば、日本は中国を世界平和を乱した罪で告発できる。報告は日本自身では考えつかない中国告発の材料をそろえてくれた。しかも、これで日本の「警察行動」は正当化されてしまう。 ・リットン報告は主要な二つの点で、きわめて中国に厳しい。まず、「共産主義犯罪集団」が混乱要因となっていること。第二に、国民党(欧米列強が合法的中央政府として承認した南京政府の指導者、蒋介石の党)は「反外国」感情に侵されていること。この二つの要素が、欧米諸国がつくった安定構造全体を危うくさせている、と非難する。 ・具体的にいうと、中国には中央政府というべきものが存座手せず、「排外思想」が「建設的改革」を遅らせ、「犯罪集団」が「本物の軍隊」と化して「飢餓地帯」を苦しめている、と次のように指摘する。 「一九一一年の革命以来、中央政府が弱体であるために、政治動乱、内戦、社会・経済不安がつづいているのが中国の特徴である。こうした諸条件が中国と接するすべての国々に悪影響を及ぼしている。これが改まらないかぎり、中国は世界平和を脅かし、世界不況を助長しつづけるだろう」 ・リットン報告は、両勢力を厳しく批判している。報告は共産主義について、次のようにいう。 「これ(共産党)は国民政府の現実の対抗勢力として、独自の法律、軍隊、政府、そして支配領土をもっている。こういう状態は、他のいかなる国にもない」 ・報告は国民党にも平和を乱している罪があるとし、反外国プロパガンダを行なっている蒋介石政権(国民政府)をとがめている。 ・またリットン調査団は、蒋介石は不平等条約と治外法権を否定しようとしているといって非難する。 ・リットン報告は「中華民国」の「中央政府」という考え方は、法的擬制にすぎないことを認めている。 ・「軍閥」政権の多くは、南京政府(蒋介石)を中央政府として認めておらず、単に「たまたま外国勢力から中央政府として認められているにすぎない」と考えているのである。 ・もし、ある「軍閥」政権が外国勢力に認められたというだけで「中央政府」になれるなら、大国である日本が自分の勢力圏内にある望ましい政権を中央政府として認めてならない理由はないのだ。 ・もし、中国の中央政府が報告で明確にされているように法的擬制なら、日本の満州政府も同じである、と日本は考えたのである。 6 日本は合法的に行動している ・日本は満州国の建設についてこう説明する。 満州がかつて中国の一部だったことはない。まったく逆で、中国のほうが満洲帝国の一部だった。 満州人が北京に在って中国を統治しているかぎりは、二つの地域の間に関係はあるだろう。しかし、万里の長城が証明しているように、満洲王朝の統治時代でも、満洲の各省は中国の境外の地と考えられていたのだ。 ・一九一一年の中国革命で満洲王朝は倒れた。これによって中国と満州の法的関係は切れたにもかかわらず、欧米列強は満州は中国の一部であるという ・これに対して、不平等条約は満洲王朝との間で結んだのだから、外国に付与された特権は当然、満州にも及ぶ、だから中国に対して、満洲まで主権を及ぼすよう求める現実的理由があるというのが列強側の主張だった。 ・満州国における日本の役割は、「共産主義の脅威」と軍閥の悪政から国民を守り、近代国家への発展を助けることなのだ……。 ・リットン調査団は、連盟加盟国は満州国を承認すべきではない、と勧告した。 ・報告は日本の誇りを傷つけただけでなく、アジアの大国としての地位を根底から脅かすものだった。 ・心理的衝撃は、日本は西側先進国ではないとされたことである。日本は五大国の高い席から、アジアの後進民族と同じ地位に引きずり下ろされたのである。 ・現実的衝撃は、もし国際連盟とアメリカが経済制裁措置に踏み切れば、日本は満洲から完全に撤退せざるをえなくなる、ということだった。 ・列強は中国の特権を放棄するなどとはいわない。 ・それどころか、彼らは特権の保持を問題提起の土台にしている。 ・非難の根拠は、中国国民にたいする憂慮ではない。欧米列強は中国における自分たちの地位を心配しているのだ。 ・アジアと中国に覇権と勢力圏を維持しつづける連盟加盟大国が、日本を非難するのは自分の利益がからんでいるからだ、と日本は考えた。 ・日本の立場でみると、欧米諸国が日本を非難するのは、中国の領土保全を尊重しているからではない。 ・それは、すでに大国自身が侵害している。彼らはいままで日本の勢力圏と認めていた地域に、自分たちの支配を拡げたいだけなのだ。 ・日本を「侵略者」として非難する民主主義諸国の世論も純粋に人道的とはいえない。つい五年ほど前、米英両国の軍隊と砲艦が自国民の生命財産を守るために中国の「討賊」を攻撃したとき、両国の世論は中国人を野蛮人と呼んで非難した。 ・ところが、日本が同じように中国の「討賊」を攻撃すると、同じ国民が日本人を野蛮人と呼ぶのである。 ・そこで日本人は、こうした非難は日本の行動に対してではなく、人種に向けられたものだという結論に行きつく。 ・国際連盟がリットン報告を受け入れ、連盟とアメリカが満州国を独立国として承認しなかったことから、日本は連盟を脱退した。 第六章 第五の自由 ・ <途中> |