
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2022年04月11日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
7 |
22.03 |
がん患者学Ⅰ 長期生存患者たちに学ぶ 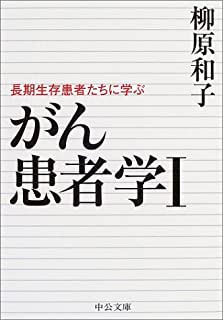 |
柳原和子 |
中公文庫 |
◎ |
第1部 患者は語る 1 身近な仲間たちをたずねる 一つとして同じがんがあるだろうか? 武藤すみ子(70歳)・昂夫妻 (末期卵巣がん・一九八四年発症) 昂 「人間が自分に無用なものを体外に出すには、尿と便と汗しかありません。私は便よりも尿がその機能を果たしているのではないか、少なくとも能力が高いと考えました」 「無用なたん白質もほとんどが腎臓で 「腎臓は身体の掃除に大切な機能を果たしている臓器でしょう。そういう点で考えても、腎臓に副作用が出る制がん剤は理に合わない」 「制がん剤で腎臓機能が破壊されてしまったら、下水の詰まった家みたいなものではないですか。薬でがんを叩けば、腎臓が弱る。がんは小さくなったとしても、人間も死ぬ」 「口に入れたもの、摂取したものを出すこと。飲んだ液体を排泄すること。そのためには水をたくさん飲んで、腎臓を働かせたほうがいい」 明らかながんの所見は認められません 久保修哉(80歳) (末期胃がん・一九九三年発症) 担当した近藤誠医師のコメント 「放射線というのは普通、照射した範囲でしか影響が出ないものだ。ところが理論的には、放射線を照射したところのがん細胞が変性して免疫状態がよくなったりすると照射していないところのがん細胞も消えていくっていうこともありうる」 医師をたよったのが、まちがいでした 匿名希望・女性(51歳) (子宮がん、のち大腸転移・一九九一年発症) ・「臓器を失うってことは、元の、人間にとって自然の身体ではなくなるということです。仮にがんがなくなった、治ったとしても、身体は全然ちがったものになっていると考えるべきでしょう。日常生活の端々にそれは現れます。思い知らされる。動作、所作一つ一つ、普通の人と同じにはできません」 「失った臓器が増えればそれだけ、体内をいじくればいじくるほど、その辛さは増します。肉体的な辛さはもちろんですが、心理的、社会的な問題として、辛いわけです」 ・「がん細胞って、普通の方にもあるそうです。できたり消えたりしていると聞きました」 「身体の全身状態が悪い、衰弱してくると、つまり極度に免疫力が落ち込むと、凄まじい勢いをつけて広がっていってしまう」 「だから患者が心がけなければいけないのは、がんの勢いを抑え込んでおける免疫力、気力、体力をいかに維持してゆくのか、ということではないでしょうか」 [飲尿療法] ・自分の尿は自分の原初的な免疫系に訴えかける大事な要素がある、とする。 ・一方では、効果は疑わしいものの、汚いものまで飲むことによる精神的な刺激が大きい、という説もある。 ・「飲尿療法なんかでも朝一番の尿をコップいっぱいのめ、と強制する先生もいます」 「私の先生は、一滴の尿だけで、脳は体調のデータを感知するからそれで大丈夫と言います」 「飲尿療法は効果があると信じています」 ・「現代医学は、悪いところを切るというところまでしかできない、ということですね。そうした治療の末に副作用や後遺症が出たあとには、もはやお手上げということでしょう」 いろいろな治癒のてだてがある 匿名希望・女性(42歳) (卵巣がん・一九九三年発症) ・自分が生きるためだけに自分のすべての気持ち、時間を使い果たすってすばらしいことです。 ・自分が生き延びるために生きる――この実感は生まれて初めて味わうものでした。 ・生きているのが私、大好きなんです。 玄米で治そうなんて、アホか 濱田隆三(60歳) (肝臓がん、肺転移・一九七九年発症) ・玄米食というのは、玄米と野菜の力もあるでしょうが、食品だけではないさまざまな要素が総合的に噛み合って治癒力、免疫力をアップしていると考えたほうがいい。 ・まずは小食咀嚼。唾液が活発に働く。 ・次に重要なのは一物全体食ということです。 ・食品は丸ごとすべて食べなければ逆に毒になる、と考えてもいい。 ・栄養素というのは無限です。たん白質、脂肪、炭水化物、ビタミン、ミネラルだけで生物ができているのかといったら、そうではありません。それ以外いまだ分析されていない物質が無限にあると考えていい。 ・ビタミン剤やミネラル剤を飲んだとしても、発見されていない微量元素の欠落部分を補給する効果が出ないこととなる。 ・生物の生命が成り立っている状態そのまま、つまり丸ごと食べる、一物全体食がもっとも簡単な補給法と考えたほうがいい。 ・あかなんだ人でも自然療法を徹底した人は死ぬ直前までしっかりとしています。 ・自然に生きるということは自然に死ぬとということとイコールやないかと思っていますね。 死と向きあいつつ、「普通」を生きる 松本 剛(62歳) (睾丸がん・一九八二年発症) ・人間の死に方にはさまざまある。がんによる死に方は、人間のそうした死のなかでもいろいろなことを自覚し、準備し、後始末をして死にゆくことのできる病ではないでしょうか。 ・自分なりに腹のくくり方を試され、闘い方という選択の可能性が残されている病だ。 ・脳梗塞、痴呆、心臓病というのは自分で自分の死に方、闘い方、つまり死までの時間が自らコントロールできぬままに終わっていくという悲劇性がある。 もっとからだにやさしい療法でいきたい 大野聰克(54歳) (直腸がん・一九九一年発症) ・人間が病気になるには心の問題が大きいのではないですか。 ・ストレスなどの要因で血管が収縮し、血流が悪くなる。臓器に通常の七割くらいしか血液が流れなくなったとします。ある程度なら許容範囲で問題ないけど、それ以上少なくなると全体が機能を落としてしまい、人間が生きていけなくなるのではないだろうか。 ・かんじんなのは血液を流すことです。 ・人として自然なことをする。 息をする、歩く(動く)、食べる、匂いをかぐ、音を聞く、見る、肌で感じる……。 すべてのことが身体をととのえていくのに大切なことです。 ・自分で考えず、努力もせず、ただ医者に任せているだけでは駄目です。医者や薬の手助けを借りながら、患者自身が頑張ること、これこそが治すための第一歩ではないでしょうか。 再発させてはいけない 原田一正(62歳) (直腸がん・肝臓転移・一九九一年発症) ・気功は、とにかく体を動かして、それで免疫力を高め、さらにリラックスして気分がよくなる、それは薬効とは別のものです。 頑張ったらだめ、この病気は 田口克己(66歳) (胃がん・一九九二年発症) ・お医者さんは病気をよくするのが限度だ。 ・よくすることはできても、根本から治すことはできません。治すのは自分であって、医者はその手伝いをするだけ。 ・入院患者のなかでも、元気になっていく人は皆、プラス思考ですね。 ・大切なのは友だちを持つことです。それと人の話をよく聞くこと。 ・自慢話はやめよう。これを守っていけば、友だちはきっと増える。 ネバー・ギブアップ! 阿岸明子(61歳) (卵巣がん・一九九二年発症) ・[がんを告知されたときなすべき五〇のポイント]より ◉がんに関する本を資料として集め、知る。 ◉決心! 決意は力だ。 ◉あなたには自分の生き方を選ぶ責任がある。 ◉回復への自分なりのプログラムをたてよう。 ◉運動、そして自分に必要なリハビリを心がける。 ◉自分の症状の進行に合わせて、その都度、がん闘病計画を組み立て直そう。 ◉今を生きる。 ◉治癒力を高めるために、笑おう。 ◉自分自身の規律を作り、守っていこう。 ・人生って短いけれど一生懸命に生きて、ちょっと手をのばしてみれば夢と希望がすぐそばにある感じです。人生ってすばらしい、生きていてよかった。 ・一日一日を大切に生きていきたいですね。 文庫版へのあとがき ・考えてみれば、医療現場では死は敗北として扱われている。勝利は治る、ことにある。そうした価値観はじつは社会全体にある。 ・病むこと、死ぬことを排斥して成立する社会、元気であることだけが勝利と扱われる社会はじつは恐ろしいのだ。 ・がんであることはじつは、もっと深く豊かな経験になりうるのではないか? ・がんや生死の境をさまようような病の経験は私たちをすばらしく成長させ、より重厚な人生にしあげてくれる機会ではないのだろうか? ・健康者よりもはるかになにかを見てしまった人々なのではないか? ・絶望と苦痛に喘ぐ人々にとって当事者としての先輩の経験は強い援助になりうる。 ・死を間近に直視しながら生きるがん患者たちの視線は、社会にとっても大きな力になりうる。 ・病むこと、死ぬことの意味、をがんほど深く教えてくれる病はない。 ・がん患者になった人は誰もが実感する。医療はほんの少しの救いをしか与えられぬ、ということを。逆に、おそろしいまでの恐怖心と不安をもたらしてしまう、ということを。 解説 岸本葉子 ・統合医療という言葉を、新聞等でしばしば目にするようになっている。現代医学と、伝統療法や心理学を組み合わせるものだ。日本の医療機関でも、取り組むところが出てきている。 ・長期生存者たちは、自分なりの統合医療を、「個」のレベルで実践していたとはいえまいか。 ・個別は、自由に似ている。 ・個別とは、「絶対」もない、ということでもある。すべてを自分で判断しなければならない。 ・誰かの力をあてにしない、あてにはできない、奇跡はない……、と腹をくくる。くくれずとも、日々、そう言い聞かす。 ・自分自身の生であり、死なのだ、と自覚したとき、初めて自分が生きてきた時間の集大成としての納得の行く医療がたしかな像として浮かびあがるのではないか? ・自分がいま、何を医療に求めているのか、がはっきりとわかるのではないか? ・そのとき初めて私たちは自分らしい選択が可能となるにちがいない。 ―― 完 ―― |