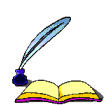
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2022年05月09日 月曜日 】
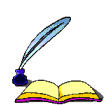
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
10 |
22.04 |
一下級将校の見た帝国陸軍  |
山本七平 |
文春文庫 |
◎ |
"大に ・昭和十年代の当時の世界では、兵役のない国はむしろ例外であったから、平凡な平均的人間は、内心で兵役を嫌っても、それを一種、逃れ得ない。「人類の宿命」乃至は「男に生まれた宿命」のように受取るのが、むしろ普通であった。 ・その感じは、私と同世代の女性が時々ふと漏らす「兄が召集されて、日曜日などに帰ってきて話すことを聞いてくると、つくづく "女に生まれてよかった" と思ったものですよ」といった言葉にも現れている。 すべて欠、欠、欠……。 ・第二次大戦の "謎" 「ナチス・ドイツが最後まで婦人を動員しなかったこと」 「陸軍が最後の最後まで学生を信頼せず、それを戦力として活用しようとはしなかったこと」 がある。 ・ナチスの場合は「婦人は家庭に」が一つの思想だったのであろう。 現地を知らぬ帝国陸軍 ・陸軍は、比島派遣軍を自活させるという方針を取りながら、現地の実情には全く盲目であった。 ・そしてその無知はまず基本的な問題「食糧問題」で露呈し、ついにその露呈は、宗教問題・社会問題・男女の問題からあらゆる問題へと及んでいった。 ・アメリカの戦史曰く、「尚武集団(比島派遣第十四方面軍)の殆どすべては餓死である」と。 私物命令・気魄という名の演技 ・「私物命令」とは、官給品の支給のように系統的に上から末端まで下がって来る命令ではない "命令" 、いわば上官個人が命令権を私有化し、その私有化に基づいて恣意的下す命令の意味だが、内容的に分ければ二種類あった。 ・一つは次のような場合である。 原隊の第二大隊長であった士官学校出の若いH大尉は贅沢で、隊内で支給される煙草『ほまれ』で満足せず、市販の『光』を毎朝三個買ってこいと経理少尉に命令した。 ところが、戦局が悪化するとともに、いかに奔走しても、「ヤミ」でもなかなか『光』は手に入らなくなった。彼はこの大隊長の私用に疲れ果て、『光』の買い出しをやめてしまった。 H大尉は怒った。「『光』を買え、と命令したはずだ、なぜ命令に従わないか」。さすがの彼もむっとして言った。 「命令とは思いませんでした」 「何だと、命令と思わなかった、と」 「ハイ」 「よし、ではこれから大隊命令を出す!」 H大尉は堂々と、『光』を毎朝三個ずつ「購入スベシ」という正規の大隊命令を出したという。 ・これが通常いわれる「私物命令」で、部下の "私的使用人化" である。 ・これは若いエリート将校ほどひどく、まじめ一点張りの老将校が眉をひそめるような例は、決してすくなくなかった。 ・第二の型とは正規の発令者が全然知らないのに、堂々たる命令として、時には口達で、時には正規の文書で来る命令である。 ・戦後の戦犯問題で、形式的には堂々と発令しておきながら、「そういう命令は出していない」と証言したため、「部下に責任を転嫁して助かった卑怯な指揮官」ときめつけられている人は決して少なくない。 ・バターン戦終了時に、どこからともなく発せられた捕虜殺害の "軍命令" 実は「私物命令」だった。 ・現在では、この私物命令の発令者が、大本営派遣参謀辻正信中佐であったことが明らかである。 ・このことの大要は戦後の収容所の中では、すでに周知の事実だった。 ・従って私などは、戦後のはなばなしい辻正信復活に、何ともいえない異様さと絶望を感じたことは否定できない。 ・この奥には何か、日本軍も戦後人もともにもつ弱点があるはずである。 ・確かに人生には、そして特に戦闘には「何ものにも屈せず立ち向かっていく強い精神力」が要請される。だがこういう意味の精神力と "強がり演技" にすぎないヒステリカルな「気魄誇示」とは、本来、無関係なはずであった。 ・真のそれはむしろ、静かなる強靭な勇気と一種の自省力のはずであり、この本物と偽物との差は、最後の最後まで事を投げず、絶対に絶望せず、絶えず執拗に方法論を探求し、目的に到達しうるまで試行と模索を重ねていけるねばり強い精神力と、芝居がかった大言壮語とジェスチュア、無謀かつ無意味な "私物命令" とそれへの反論を封ずる ・精神力とは、これらの気魄誇示屋の圧迫を平然と無視して、罵詈讒謗には目もくれず、何度でもやりなおしを演じて完璧を期し、ついに完全成功を克ち得たキスカ島撤退作戦の指揮官がもっていたような精神の力であろう。 ・そしてこの精神が最も欠如していたのが、「気魄誇示屋」なのだが、あらゆる方面で主導権を握っているのが、この「気魄誇示屋」というガンであった。 ・辻正信の「言いまくり」がそのまま "命令" となる「私物命令」の世界では、当然の危惧なのだが、「帝国陸軍の統帥権絶対神話」が今も生きている日本、そのため真の元凶、真の責任者が平然と復活し、活躍し、権威と名声をほしいままになし得た戦後の日本では、今も人が信じない一つの事実なのである。 「オンリー・ペッペル・ナット・マネー」 ・軍人は二言目には「日清・日露の……」と言った。日露戦争時までは、戦艦、イギリス炭、下瀬火薬、小銃があれば戦争はできた。 ・また砲兵では、測地という技術がなく、第一次大戦のような統一仕様による猛威は発揮できず、せいぜい中隊単位でポツン、ポツンと射撃しているにすぎなかった。まことにのんびりしたものであった。 ・だが第一次大戦ですべての様相が一変し、まず石油と補給力が決定的要素、これがなければ、前線の機能は一切停止することが証明された。だが日本には石油もないし、加速度的にまして行く消耗戦に耐えうる資源も国力もない。 ・日露戦争的前提は、すでに完全になくなったていた。 ・そして前提がなくなっているのに、それに目をつぶって前提は変わっていないとしたとき、帝国陸軍はすでに虚構の存在になっていた。 ・その結果、あらゆる組織は無意味・無目的の "自転" をはじめ、その "自転" が無意味でないことを自己に納得させるため、虚構の世界に入ってしまう。 ・そしてそれが虚構でないように見せる演技が「気魄誇示」であり、そのため「事実」を口にした者には、「気魄」を持ち出して徹底的な罵詈讒謗を加えて、その口を封ずる以外に方法がなくなる。 ・それが "組織の自転" "辻正信型言いまくり " "兵隊の要領" を生み出した根本的な原因であった。そしてこの三つはとめどもなき悪循環を重ねて行く。 最後の戦闘に残る悔い ・戦闘集団としての軍隊は、だれかが、衣食住、武器弾薬を支給しない限り成り立たない。そしてそれが断たれた瞬間に、この集団は、武器を生活用具とする生活者集団に変化せざるを得ない。 敗戦の瞬間、戦争責任から出家遁世した閣下たち ・一体、日本の将官、指導者に欠けていたのは何なのか。一言でいえば自己評価の能力と独創性・創造性の欠如ではないか。またその前提であるべき事実認識の能力ではないか。 ・日本軍のすべてが、新しい発想もなければ、想像力もなく、変転する情勢への主体的な対処もできず、対象を正確に直視して、その弱点を見抜くことさえできなかった盲目無能の集団だったではないか。 ・日本という枠内での、軍部という井の中の蛙が、仲間ぼめという相互評価で、土地ころがしのように軍部の評価を高めて無敵無敵と自称したところで、それは単なる自画自賛で国際的評価としては通用しない。 ・だが戦争はまさに国際的事件であり、国際的評価に耐え得ないものは、はじめからこれに対処できるわけはない。それすら理解していない、一人よがりの思い込み集団。 統帥権・戦費・実力者 ・戦前の日本は、司法・立法・行政・統帥の四権分立国家とも言える状態であり、統帥権の独立は明治憲法第一一条にも規定されていた。 ・従って政府(行政権)は軍を統制できず、それが軍の暴走を招いた。 ・「執拗に統帥権の独立を主張して横暴をきわめた軍」は、私にとってあまりに身近な存在であったため、軍部以外に統帥権の独立を主張した人間がいようなどとは、夢想だにできなかった。 ・ある機会に、明治の先覚者、民権派、人権派といわれた人びと、たとえば福沢諭吉や、植木枝盛が、表現は違うが、「統帥権の独立」を主張していることを知った。 ・なぜこの民権派・人権派が「統帥権の確立」――いわば兵権と政権を分離し、政府に兵権をもたせず、これを天皇の直轄とせよ――と主張したのか。 ・それを主張した前提は、明治の新政府が、軍事政権とはいえないまでも、軍事力で反対勢力を圧服して全国を統一した新政府、いわば軍事的政権であったという事実に基づく。 ・この先覚者たちにとっては、民選議院の設立、憲政へと進むにあたり、まずこの藩閥・軍事的政権の軍事力を “封じ込める” 必要があった。 ・軍隊を使って政治運動を弾圧する能力を政府から奪うこと。これは当然の前提である。彼らがそう考えたのも無理はない。 ・これに対して当時の進歩的主張が、「軍は天皇の軍隊であって、政府の軍隊ではない。政府が軍隊を用いてわれわれを弾圧することは、聖権(天皇の大権)の干犯である」となったことも不思議ではない。 ・また、この先覚者たちの恐れの第二は、政争に軍が介入してくることであった。 ・たとえば板垣自由党を第一師団が支持し、大隈改進党を第二師団が支持するというようなことになれば、選挙のたびに内戦になってしまう。 ・ここに、「軍は天皇の直轄とし、天皇と軍は政争に局外中立たるべし」という発想がでてくる。 ・南米の国々や第二次大戦後独立した多くの国々を最も苦しめ、今も苦しめているのが、政争に軍が介入してくる内戦であることを思えば、人権派・民権派のこの主張は当時の主張としては不思議ではない。 ・そしてこの点で、政権と兵権の分離、兵権の独立、天皇と天皇の軍隊の政争への局外中立化は、確かに、当時の進歩的な考え方であったであろう。と同時に日本が範とした当時の西欧諸国にも、同趣旨の規定があったという。 ・帝国陸軍とは、日本国行政府の支配下になかったという意味で、天皇の軍隊であっても、日本国「政府軍」ではないという形態へといつしか進んでいった。 ・この点、諸外国の国民軍とは非常に性格が違っており、従って国民軍とも国防軍とも言いがたい。 ・だが皇軍という呼称は軍隊内にはなく、大日本帝国陸軍の略称は「国軍」であった。そしてその内容は「日本軍人国軍」の趣があった。 ・「統帥権」の独立は、「ある時代の最も進歩的な考え方行き方は次の時代の始末に負えぬ手枷足枷となる」というケースの典型的なものであろう。 ・そして、統帥権により日本国の三権から独立していた軍は、逆に、まず日本国をその支配下におこうとした。 ・そして満州事変から太平洋戦争に進む道程を仔細に調べていくと、帝国陸軍が必死になって占領しようとしている国は実は日本国であったという、奇妙な事実に気づくのである。 ・S中尉という、士官学校出の若い中隊長は、政局や戦局がこのようになったのは、「 ・彼は議員を罵倒し、軍需太りの利権屋を国賊とののしり、戦死者の屍肉を食う人非人どもと言った。まじめな下級将校のこの憤慨には一理ある。 ・「軍人が戦時利得者でなかったことは事実」、戦時利得者は大小無数の “小佐野賢治型” 人物であり、将校、特に下級将校の実体はそれとは全く別で、インフレに最も弱いサラリーマンのそれにすぎなかった。 ・戦費を打ち切れば、戦争を終らすことができた。 組織の名誉と信義 ・名誉は組織のものなのか個人のものなのか? 帝国陸軍には、そういう問題意識すらなく「組織の名誉」以外に名誉はなかった。 ・生きて虜囚の辱めをうけた者を、その個人の名誉を救うため自決させて “名誉の戦死” として扱うことは一見 “個人の名誉” のためと見えるが、実は、「捕虜なし」という組織の名誉の絶対化が個人を抹殺しているにすぎない。 ・「これが帝国陸軍だったのだ。そして自転する “組織の名誉” という考え方が日本を破滅させたのだ」。 ・師団の名誉のため、軍旗(連隊)の名誉のため、大隊の名誉のため、それにさしさわりのある事実は死んでも口にしない、それを口にするぐらいなら黙って死ぬ、それが帝国陸軍の一貫した倫理観であった。 ・これはおそらく徳川時代の “一家一門の誉れ” “一家の恥は外に出さない” に由来する考え方であろう。 ・この倫理観は、戦後三十年、今なお続いているほど強い。 ―― 完 ―― |