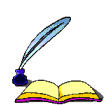
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2024年05月29日 水曜日 】
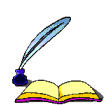
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № |
了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 |
評価 | コメント&抜き書き |
11 |
22.05 |
歴史教育を考える 日本人は歴史を取り戻せるか  |
坂本多加雄 |
P H P 新書 |
☆☆ |
序章――歴史教育問題の核心 戦後という時代を見直すことが必要 ・私たちの多くは、戦後社会をよいものであったと、最初から決めてかかってきた。 ・しかし、そこから進んで、戦後日本のあり方をすべて絶対化して、敗戦に至るまでの日本の歴史の歩みを、もっぱら、そうした戦後のなかで培われた価値基準によって観察したり、裁いたりするということになると、私たちは、反省とは正反対の夜郎自大的な自己満足に陥ることになるのである。 ・実際、これまで、私たちは、そうした戦後的な価値観から、日本の過去を眺めて、総じて否定的な日本近代のイメージを形作ってきたようである。 ・戦後がもっぱらプラスの価値を負荷されてきたことに対応して、そこに至るまでの日本の姿には、むしろ、過剰にマイナスのイメージが投射されてきたように思われる。 ・しかし、戦後半世紀という時代に改めて客観的に臨もうとするとき、そうした、戦前と戦後のいずれかに立つということより、むしろ、それを超えた公平な見地から、今日に至るまでの日本の歴史を客観的に眺めることが必要ではないだろうか。 ・すなわち、この半世紀の日本を、近代日本全体と、それを取り囲んだ世界史の大きな動きのなかに改めて位置づけてみることが必要ではないだろうか。 ・ここで改めて問題となってくるのが、歴史教育の問題、とりわけ、中等・初等の学校での歴史教育の問題である。 ・というのも、これまでの学校での歴史教育こそが、上に述べた戦後の日本人の歴史へのアプローチの仕方を大きく規定し、その平均的な日本史像を形作ってきたからである。 ・そうした戦後に一般的に見られる歴史へのアプローチから独立して日本の過去に臨み、様々な知見を身につけてきた人々がいたし、学校の歴史教育のあり方や、そこで教示されている内容へのそこはかとない違和感を抱いていた人々も少なくはなかったのである。 ・しかし、一般的にはそれに代わる歴史教育のあり方に本格的に接することのないまま、受験への配慮や、タテマエとホンネという二分法的な見地から、学校の歴史教育の内容には一応の尊重の態度を示しつつ、実際は、どうでもよいものと見なしたり、そこから進んで、総じて歴史への関心そのものを喪失するといった態度が生まれてきたのである。 ・そうしたなかで、当の歴史教育の内容そのものは、もともと内在していた日本の過去を否定的に眺めるという傾向を、近年ますます著しいものとしながら進められてきた。 ・ところが、最近になってそうした傾向がある臨界点を越えたことを象徴するかのような事態が生じた。そして、そのことを契機に、一般の人々においても、現状の歴史教育のあり方が、にわかに関心の対象となって浮かび上がってきたのである。 ・そうした事態とは、いわゆる「従軍」慰安婦についての記述が、平成九年度からの中学校歴史教科書のすべてに登場したことにほかならない。 ・そこから、そうした教科書を生み出してくる歴史教育の現状が、それについての一般的な常識に鑑みてあまりに異様なものとなっているということが、改めて世論の強い関心を引くに至ったのである。 ・すなわち、これまで漠然と考えていた歴史教育および歴史教科書のイメージと、現実とのギャップがあまりに大きいということが、改めて再認識されたということなのである。 ・ただ、このような教科書記述をめぐって、世上しばしば「自尊史観」と「自虐史観」との歴史観の対立だということが言われ、いずれの史観が正しいか、いずれの史観によって歴史教育がなされるべきか、などという議論がもっぱら先行しているようである。 ・しかし、ただちにそうした問題の設定を行うことが、かえって問題の本質を見失わせるように思われる。 ・この問題に関して、最初に考えねばならないのは、むしろ、「歴史教育とはそもそも何か」ということではないだろうか。 ・にもかかわらず、一般の歴史教育についての議論が必ずしも明瞭な方向性を持てないのは、そうした日本人が抱いてる歴史教育の本来のあり方についてのイメージや常識を、明確に提示することができていないためであろう。 ・漠然とした違和感はあるものの、それを理路整然と解明することができず、そこから、ただちに歴史観そのものの可否に議論が及んだりする傾向が見られるのである。 第一章 歴史教育とは何か 「教育」とは何かの視点の欠落 ・「従軍」慰安婦の事項を中学校の歴史教科書に載せるのが適切か否かという問題については、さしあたり、この事項の記述が、現行教科書検定基準のなかの、「図書の内容に、児童・生徒がその意味を理解するのに困難であったり、誤解したりするおそれのある表現はないこと」、「未確定な時事的事項について断定的に記述しているところはないこと」、さらに「図書の内容に、特定の事項を強調し過ぎていたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところはないこと」といった基準を本来クリアしないということを指摘すれば十分だと考えている。 ・にもかかわらず、実際にはクリアしてしまった。「従軍」慰安婦問題は、現代の中学生にとって理解困難であり誤解もしやすく、まだ歴史研究においても未確定な部分を含む事柄である。しかも、現行教科書は、全体としてきわめて限られたスペースしか持たない。 ・そうした中で、こうした事項が歴史教科書に是非とも記載しなければならないものとは思えないのである。 教育的配慮を押し退けた議論 ・このように見てくると、「従軍」慰安婦についての記述が中学教科書に載ることは、きわめ異様うであるという印象がある。 ・従って、こうした記述が不可欠だと主張するには、それなりに特別な理由がなければならない。 ・そこで、この事項を記載すべきだという場合に唱えられるのが、第一に、「そもそも戦地の慰安婦制度を単なる売春制度と捉えるのは誤りで、何よりも戦争で犯された悪として見なければならない」という議論である。 ・さらに、第二に、「そもそも歴史教育は、加害者としての日本の責任を自覚させることに力を注ぐべきだ」という主張である。 ・加害者の責任について言えば、検定基準はもとより、他のあらゆる教育的配慮を押し退けてでも、加害者としての自覚を教えるのが歴史教育の目的なのかという疑問が、当然のことながら生じてくる。まさしく、歴史教育とは何か、という問題が関わってくるわけである。 ・私は、歴史教育の本来の課題から見て、加害者の自覚ということは、他の歴史教育の課題を退けてまで、特別に優先して重視すべき目標ではないと考える。 ・前者については、慰安婦制度が論じられる際に、戦場で起こった性に関する戦争犯罪や個別的な暴行のケースと混同している場合が多いことに注意しなければならない。 ・戦場での非戦闘員への暴行は、日本軍自体が軍刑法で禁じた戦争犯罪なのであって、そうした個々の事件と戦場においての慰安婦の制度そのものとは別の問題なのである。 ・「従軍」慰安婦制度が教科書に載るに至った経緯を見ると、慰安婦となる人びとを大規模な人狩りのごとき拉致によって連行したという説が、与かって大きな力を持っていた。 ・しかし、すでに周知のように、この説の唯一の論拠となっていた吉田清治の『私の戦争犯罪――朝鮮人強制連行』は、虚構であることが明らかとなっている。 ・そこで、強制連行を非難していた人たちは、強制連行の存在を証明できないとなると、慰安婦制度自体がいかに苛酷で、慰安婦たちがいかに人権侵害の危機に曝されていたかを強調するようになった。 ・しかし、この場合には、現在の倫理的観点で見て慰安婦の生活状況が非人道的であったとしても、少なくとも、当時の日本の制度が他国のそれに比べてことさら悲惨できわめて特殊であり、そのことを抜きにしては当時の日本の姿が明らかにならない、それゆえ、他のいかなる教育的配慮に優先して特記されなければならないということが確認されなければ、教科書に記述して中学生に教えるべきものとは言えないのではなかろうか。 ・こうした比較は、すさまじい管理売春を行ったドイツや、始めから通常の女性を強姦や暴行の対象としていた旧ソ連軍といった事例を考慮しなければならないが、他の参戦国と比べても、日本が並外れた残酷な制度を作りあげたということは証明されていない。 ・つまり、この点でも研究自体が十分に進んでいないのであり、そうした事項は載せるべきでないという基準はクリアできないわけである。 「歴史教育とはどうあるべきか」 ・歴史的事実の確認という観点から見ても、教育という観点から見ても、「従軍」慰安婦問題は、中学校教科書に記載するような事項でないことが明らかであろう。 ・ところが問題なのは、確信的に慰安婦記述を主張してやまない人とは別に、言論人のなかに、「最近の中学生は性的成熟が早いから、従軍慰安婦問題についても理解できるはずだ」と論じたり、「この問題について、意見が分かれているならば、併記すればいい」とあっさり述べる人がいることである。 ・ここでは、そもそも、「教育とは何か」という問いが完全に抜け落ちており、冒頭に、問題が単に歴史観の相違といったことに還元できないと述べたのも、こうした事態を念頭に置いているからである。 ・そもそも、性に関する事項が「分かる、分からない」とか、単に意見が分かれているから、両論を「併記すべきか否か」ということではない。 ・「従軍」慰安婦の記述の可否に真剣に関わることの鬱陶しさや、単なる、無責任な興味本位の見地から、そうしたことを口にしているのではないか。 ・そして、そうした態度の背景にあるのが、まさしく「教育とは何か」という思想の欠落なのである。 ・そもそも、教育においては、「何を教えるべきか否か」ということがまず問題であり、「理解できるか」とか、異なる解釈のある事項をどのように記述するかは、その後にくる問題に過ぎない。 ・教科書協会の会長が自民党に呼ばれて、なぜ従軍慰安婦の記述が記載されているのか質問されたことがあった。このとき教科書協会の会長は、「いま世論で問題になっているからで、思想的な背景はない」と答えている。 ・おそらく会長は、「左翼思想や、特定のイデオロギーにもとづいて載せたのではない」という意味で述べたものだと思われるが、「思想」ではなくいわゆる「世論」で話題になっているからと答えるところに、大きな問題を感じさせる。 ・すなわち、こうした発言が出てくること自体、歴史教育や歴史教科書に直接関わる人々においてさえ、歴史教育とは何か、あるいは、教育とは何かといった問題についての「思想」そのものが欠落していることをうかがわせるのである。 ・ここからも、やはり、こうした基本的な論点について改めて、真摯に議論を深め、その「思想」を確かなものにしていくことが、喫緊の課題であることが痛感させられるのである。 政治・研究・教育の違い ・歴史教育について論じる際、政治の世界、歴史研究の世界、さらに歴史教育の世界は、それぞれあくまで別の原理に立つべきだということである。 ・もちろん、この三つの世界は微妙に関係を持ち、影響しあっているのだが、しか原則的には別のものだという前提から出発しなければならない。 ・政治の世界というのは、そのときどきの内外の問題を解決することが優先されるから、過去に生じたとされる事態をめぐって外国との間で紛糾が生じた場合、事実の真相の探求ということとは別に、政府が現在の立場から、たとえば遺憾の意を表明するといった政治的判断が必要な場合があるかもしれない。 ・歴史研究はどうかと言えば、基本的には様々な具体的な政策的関心から独立していなければならないし、それが、どんな観点からなされようと、どのような対象を取り上げようと、まったく自由でなければならない。 ・むろん、世界には様々な国があり、つねに歴史研究がそのときの政治権力の意向に従属しているような例もあるが、それは決して文明国の姿とは言えない。 ・歴史教育の場合には、国民意識の形成という高度に政治的な領域に関わっているので、政治とまったく無関係というわけではないが、そのことは、歴史教育の内容が、その時々の政策判断と連動し、それを側面から合理化するようなものでなければならないということを意味しない。 ・たとえば、「従軍」慰安婦についての記述が歴史教科書に記載されるに至ったのは、平成五年八月の河野洋平官房長官談話によるところが大きい。 ・この談話のなかで河野官房長官は、「従軍」慰安婦の強制連行を認める発言を行い、それがあたかも確定した事実であるかのようにマスコミが流布した。 ・そこで文部省も、官房長官談話によって述べられたことである以上。記載削除を申し渡す根拠がないと判断したという。 ・しかし、強制連行を証明する書類等はないのにもかかわらず、官房長官談話は韓国に対するきわめて政治的な発言として行われたことが明らかになっている。 ・「相手がそのように言っているのだから、当面のトラブルを避けるために、とりあえず、その言い分を認めて謝罪しておけばよい」というような、きわめて近視眼的な見地からの判断が、政治的判断として賢明であったかがそもそも問題であるが、そうした政策的見地からなされた判断に基づいて、歴史教育の内容を決するようなことは好ましくないだけでなく、国家の長期的な見地からも問題を孕むものといわねばならない。 ・むしろ歴史教育に求められるのは、諸外国との関係には様々なものがあり、場合によっては、敵対する場合もありうるという事実をも学べるようにすることだろう。いわゆる「相互理解」の真の意味はそういうことでなければならない。 歴史研究と歴史教育の関係 ・歴史研究と歴史教育が共通する部分もある。 ・そのひとつが、現在という時点を絶対視することなく、より広い時間的な視野をもって様々な時代、多くの民族、社会、人々の暮らしを学ぶということである。このことにより、われわれは現在を相対化して見ることができるようになる。 ・もうひとつが、歴史教育にはその時代の歴史研究の水準が反映していなくてはならないという点である。 ・ある歴史研究の分野でAという学説が有力となっているのに、歴史教育の分野ではそれ以前のBという学説で教科書が書かれているという事態は、やはり好ましいとは言えない。 ・ましてや、イデオロギー的な偏差による誤りが明らかとなっているのに、相変わらず記述が々イデオロギーによるという現実は改めねばならない。 ・現在の歴史教科書は、戦後的価値を絶対視するという観点から記述されているため、日本の他の時代および他の国の歴史への理解を著しく阻害している。 ・すなわち、戦後に獲得されたとされる民主主義と平和主義によって、現在という時代がもっとも良い時代であるといった印象を与えるような記述になっている。その結果、過去の人びとの生活やそれを支えた信条というものに踏み込んで理解するといった態度が養われないのである。 ・これは歴史を学ぶことで得られるはずの自己を相対化する視点をむしろ潰してしまっている。 ・また、現在の教科書に反映されている学問的水準は、ひとことで言って昭和二十年代から三十年代の、講座派マルクス主義のものと言ってよいだろう。 ・つまり、戦前のソビエト連邦が世界戦略のために、コミンテルンを通じて各国の革命を位置づけるテーゼを発したが、そのテーゼに合わせて日本の歴史が研究された時期があり、それが戦後に遅咲きの花を咲かせたわけである。 ・そのため、歴史を社会主義実現への過程と考え、階級闘争史観により抑圧者と被抑圧者の闘争として描くことが多く、たとえば江戸時代の記述において、農民は重税に苦しめられ収奪されているといった面が過度に強調されている。 ・また、総じて権力者はつねに悪人で、民衆はつねに抑圧されているという図式が見られ、なかには漫画まで動員してこの図式を強調している教科書があるが、そうした図式は、著者のあまりにも狭い歴史観や人生観をうかがわせるもので、歴史に臨む精神の貧困さを示すものに他ならない。 ・さらに、現在の歴史教科書は、往々にして国内の状況に視野を集中させるために、歴史上の出来事の全体像を十分に描ききれないものになっている。 ・たとえば古代の律令制についても、唐帝国という大国の誕生という当時の東アジアの国際政治の状況の大きな変化と関連づけて説明して初めて十分に理解できるのに、単に唐を模倣して制度を移入したという、狭義の文化的影響の範囲にとどまるような記述がしてあるのは、あまりに視野が狭い。 第三章 歴史における正義と正常 戦後の現実と日本人の平和主義 ・この半世紀、現実に戦争を経験することもなく、あるいは、そのリアルな脅威を感じることのなかった国は、世界のなかで、日本くらいなものだった。 ・そうした戦争の当事者である国家が、どちらが侵略したかを、倫理的基準で、しかもすべての基準に優先させて議論しているかは疑問であり、また、そういうことをしている余裕もないのである。 ・少なくとも、戦後世界の現実は、戦後日本の世論が考えたほどには、倫理的に高い水準に向かったわけではなかった。 ・そうであれば、戦後の日本が受け入れてきた戦前日本の軍事行動の「違法性」も、考え直す必要があるのではなかろうか。 ・国際世論の変わり目でなされた日本の軍事行動は、確かに突出して見えたかもしれないが、それをより長期のタイム・スパンのなかで、各国との行動との比較で観察したときに、日本の戦争に対する関わり方が、他国に比べて異常なまでに逸脱していたとはいえないのではなかろうか。 ・むしろ、日本は一六〇〇年から一八九四年まで、つまり関ヶ原の戦いから日清戦争まで、実に三百年間近くまったく対外戦争を行わず、その後の五十年間の戦争期をへて、ふたたび五十年間まったく戦争をしていない。これが、この四百年間の日本の歴史なのである。 ・ことに一九四五年以後、一度も戦争をしていないというのは、いま見たように、おそらく世界で日本だけではないかと思われる。 ・むしろ、五十年間戦争をするどころか、ほとんど戦争の脅威すら感じなかったということが異様なことといえよう。 ・平和教育の必要性が叫ばれるが、実際は、われわれは戦争というものがまったく分かっていないに等しい。 ・日本人ほど戦争についてのリアリティのない国民はいないのである。平和について云々する前に、この事実を自覚することのほうが先であろう。 ・いずれにせよ、このようにタイム・スパンを広げて眺めてみれば、少なくとも日本人が戦争を好む国民だとはいえないし、また日本という国が、とくに好戦的な国であるとも主張できないのではないだろうか。 歴史教科書と戦争の記述 ・日本の歴史を考える際に、戦争の多かった近現代をもって日本史全体の性格を規定するものとしたり、ましてや特定の倫理的観点によって他の時代をも判断するといった方法は、あまりにも偏ったものだということになる。 ・現行教科書の近代史の部分は、明治維新以来の日本があたかもアジア侵略の準備をしてきたかのような書きぶりをしているものが多い。 ・このような視点で書かれた教科書からは、自国の歴史に対する誇りどころか、正確に知ろうと�する意欲も生まれない。それどころか、世界における日本の位置づけについても歪んだ像しか得られないだろう。 ・確かに日本の過去を眺める場合に反省すべき点はあるだろう。先の戦争が、まれに見る惨禍をもたらしたという点で、政治・外交上の大きな失敗であり、避けるべき事態であったことは否定できない。その意味での反省は欠かすことはできない。 ・また、実際の戦争遂行の過程で、その直接の当事者である陸海軍の首脳部が、「軍事のプロ」と呼ばれるのにふさわしい適切な作戦計画を立案したかというと、これもあやしい。 ・しかし、そうした政治的・外交的な成功・失敗、また、軍事的観点からの巧拙を評価する視点と、戦争そのものを悪とする倫理的観点は同じものではない。 ・もし倫理的な観点を含めるにしても、そのときの日本の過去だけを取り出してあげつらうだけでなく、その当時の世界の実際の倫理的水準がどの程度のものであったのかを充分に考慮することが必要となるだろう。 ・国際世論の変化にもかかわらず、世界では戦争が絶えたことがないという事実を念頭に置けば、日本が戦争をしたというだけで、直ちに、日本が他国にまして倫理的に劣った行いをしたと論じ、さらには子供たちにそのように教えるは誤っていると言わざるをえない。 正義と正常との区別 ・こうした問題を考える際に大事なのは、正義と正常ということを分けてものを考えるということではないかと思われる。 ・たとえば、通常、ひとつの国のなかでは、勝手に人を殴ったり人の物を盗んだりする者は権力によって拘束され、そして裁かれるだろう。すなわち、正義が実現されるわけで、誰しも当然のことだと思うであろう。 ・そして、そもそも、そうした犯罪は、普通に暮らしている人々の間で、日常茶飯事のごとく起きているわけではない。 ・もちろん、国によっては犯罪が多すぎたり権力が弱いために正義が充分に実現されない場合もあるが、通常の文明国では、正義が保たれているとが、そのまま正常な状態だとされているわけである。 ・いっぽう、国際社会の場合は、ひとつの国が他の国に攻め込んだり、そこを占領したりすることは、これまで無数に行われてきた。 ・しかも、そうした国が、他の国々や国際機関によって処罰されたという例は、ニュールンベルク裁判と東京裁判を除いて、その前後に一例もない。 ・すなわち、国際社会では、各国が戦争を行い、かつ、そのことが、法的に処罰されたりすることのない状態がむしろ正常なのである。 ・要するに、国際社会ては、国内社会におけると同じレベルで正義が実現されてはいないが、遺憾ながら、それが正常なのである。 ・私はここで、だから戦争を好ましい良いものであるなどと言うつもりはない。戦争は多くの悲惨をもたらすが、決して例外的な異常なものではなく、ありふれているという意味で「正常」だと言っているに過ぎない。 ・ただ、ここから、戦争についても、国内の犯罪に対するのと同レベルの正義の基準で臨むのが果たして妥当なのかということが問題となってくる。 ・すなわち、国際社会の法については、天下り的に高いレベルの正義の基準を設定するのではなく、むしろ、そのように「正常」とされている状態のなかで、各国を実際に拘束している判断基準やルールのレベルはどのようなものかを考慮しなければならないのではないかということである。 ・この点に関して興味深いのは、かつての軍国日本とナチス・ドイツの比較である。 ・ナチスが行ったことへの非難は、戦争を引き起こしたということよりも、ユダヤ人を虐殺したことに向けられているのである。 ・ナチスが行ったホロコーストは、たまたま偶発的に起こった事件ではなく、国家の中枢が計画を立てて組織的に遂行し、六〇〇万人ともいわれる他民族を抹殺したものである。これはいくら国際社会の基準に照らしても「正常」とは言いがたいであろう。 アンネ・フランクは「戦争の犠牲者」ではない ・ナチスと比較したとき、日本はナチスと同様の意味で異常と言えるのだろうか。 ・国家の中枢が他民族の抹殺を計画し、それを組織的に大規模に遂行したような行為が果たしてあっただろうか。 ・そもそも、日本人の多くは、ナチスの行なった悪の巨大さとその深刻さへの認識が足りないように思われる。 ・『アンネの日記』を取上げた中学教科書が、アンネがあたかも戦争の被害者であるかのように記載しているのは、その一例である。 ・アンネは戦争の被害者ではない。彼女はナチスのユダヤ人抹殺という計画的犯罪の被害者なのであって、戦争の犠牲者ではない。 ・ユダヤ人抹殺は、戦争行為の一環としてではなく、戦争遂行に勝るナチス本来の政治目的だった。 ・アンネの死を、戦争の悲惨さを述べるために引き合いに出すというやり方自体に、すでに日本人の認識の甘さがあらわれている。 ・同様に、現代の日本人の多くには、日本の関わった戦争の犠牲についての把握にも混乱がある。 ・硫黄島で戦死した兵士も、東京空襲や広島・長崎の原爆で死んだ人々も、ひとしなみに「戦争の犠牲者」であると思い込んでいるむきが多い。 ・正規の戦闘における犠牲と戦争犯罪の犠牲と、さらには、アンネのような、人類史上、異常な犯罪の犠牲とは、是非とも明確に仕分けをして見ていかなくてはならない。 戦争犯罪と戦闘行為は違う ・ナチスのユダヤ人抹殺も、ポルポト政権の虐殺も、戦争犯罪も、また戦闘の犠牲者もすべてひっくるめて戦争の名で受けとめているのは思考の貧困というものである。 ・戦争犯罪がいかなるものかを教育するのも、戦争の現実を理解させるには不可欠であろう。だが、この場合も戦闘行為と戦争犯罪の違いや、時代ごとの法的、倫理的レベルの相違も説明しなければ、ひどく歪曲した内容となるだろう。 戦争における個々の人々の美質 ・戦争そのものへの政治的・倫理的評価とは別に、そのなかで発揮された個々の人々の美質そのものを評価する視点を持たねばならない。 ・戦争で発揮された勇気や決断力、そして愛国心や尊い犠牲の精神などを、われわれは国民の物語として後世に伝えねばならないのである。 日本の戦争は異常とは言えない ・ナチスのユダヤ人虐殺に巻き込まれた人々は、ナチスの戦争行為ではなく民族抹殺という犯罪によって殺された。 ・交戦中の兵士の死でもなく、また占領地での敵軍の戦争犯罪によって死んだのでもない。むしろ戦闘状態にないナチス・ドイツの支配領域の日常のなかで、殺害されていったのである。 ・しかも、それは国家の命令として行われていたのだから、ドイツ国内法によっては裁くことが出来ないし、また国際法においても、こうした犯罪に対する規定は存在しない。要するに裁く法律というものがないのである。 ・仕方なくニュールンベルク裁判は、そのために「人道に対する罪」という概念を新たにつくり、ナチスの犯罪を裁いた。 ・日本の場合は、ナチスのケースとは大きく違っている。日本人将校や日本人兵士が戦後になって裁かれたのは、多くの場合が個別の兵士の戦争犯罪か、せいぜい現地部隊のレベルの戦争犯罪であり、国家自体が戦場での犯罪を容認していたわけではなかった。 ・従って、ナチス・ドイツの現実を踏まえて、なおかつ日本を同質であり同罪であると考えることは、日本をユダヤ人虐殺と同等のおぞましい犯罪を犯したと宣伝するようなものである。 ・しばしばこうした不用意な認識が、あたかも罪を認めることが人間的で誠実なことだという浅薄な思い込みで行われていることは憂慮すべきである。 第四章 倫理的視点と戦争犯罪 自国の戦争犯罪に対する態度 ・世界を見回した場合、自国が犯した戦争犯罪に対しては、どの国もそれほど敏感ではないようである。 ・比較的最近の(平成六年)ことだが、オランダ人作家によって、インドネシアの独立戦争の際オランダ軍が、インドネシア人を大量虐殺していた事実が暴かれた。 ・オランダは長年にわたり、戦地における自国の軍隊のおぞましさに対して正面からの直視を回避してきた。 ・戦争に従事した元オランダ兵の証言として、インドネシア人は誰が兵士か民間人か、まったく見分けがつかないために、やむをえずまとめて殺害するしかなかったという話が出ていることである。 ・こうした事態は、たとえば南京事件の際に南京に入った日本軍が立たされた現実と酷似しており、証言は、戦争ではしばしば起りうる状況であることを示唆している点でも注目される。 東京大空襲と広島・長崎の原爆こそが戦争犯罪 ・私は、とくにオランダを非難しようとは思わない。他の国も大同小異であって、国際社会の「正義」の感覚は、いまだにせいぜいこのレベルにあるということなのである。 ・東京大空襲や広島・長崎の原爆投下といった、まことに大規模なものとなると、アメリカは依然としてその犯罪性は認めようとはしていない。 ・日本人はこの問題に対して、大きな勘違いをしていると言わざるをえない。というのは、アメリカが核兵器を用いたということについて、世界中の人が間違った行為だと認めていると信じているからである。しかし、これは必ずしも世界的なコンセンサスに達したわけではないのだ。 ・ことにアメリカの場合は、そもそも、核兵器を国際法が禁じるところの残虐な兵器であると認めてしまえば、自国の核戦略そのものが成り立たなくなるということもあると思われる。 ・日本人は、原爆投下について自分たちなりに様々な意味づけをして、自分たち自身の戦争の罪と関わらせて深刻な反省をしているから他の国も当然シリアスに考えていると思い込んだ。 ・しかし、アメリカは原爆投下は正当な戦闘行為であると合理化し、また、それを理論づけるような国際法理論も存在するのである。 ・軍事上とられたある措置や行動が、すなわち国際法上合法な戦闘行為か、それとも違法な戦争犯罪であるかという判定には、実際にはまだまだ難しい問題が控えている。 ・イギリスの倫理学者ヘンリー・シジウィックは、その行為を行うことで生じた被害と、その行為によって避けられた被害を考慮して、もし避けられた被害の方が大きい場合は戦争犯罪でなくて正規の戦闘行為であるとの説を唱えた。 ・アメリカ大統領の主張は、このシジウィックの見解に近いものに基づいているのではなかろうか。 ・日本本土決戦が行なわれたとした場合の予想犠牲者数、五〇万人から一〇〇万人と、実際の原爆犠牲者の数とが較べられて、原爆投下を正当化するという論理がとられているからである。 ・日本は、戦後、自国が世界で唯一の被爆国であるということを強調し、あたかもそのことで原爆の問題に対して特別に発言する資格があるかのように考えてきたが、まず、考えるべきだったのは、原爆投下が正規の戦闘行為であったのか否かという一点であった。 ・日本の立場からすれば、糾弾を受ける南京事件のおそらく何十倍にも匹敵するような犠牲を招来したのが広島・長崎の原爆投下に他ならない。 ・アメリカがあくまで原爆投下を戦闘行為だとして正当化するなら、日本はそれを覆すだけの論理を持たなくてはならないはずであろう。 ・これまで国際社会において、戦争や戦争犯罪が引き起こした惨禍については、国家相互のいわゆる講和条約によって決着を図ってきた。 ・個人の心情のレベルで考えれば、国家間の条約が交わされたからといって、必ずしもその傷は癒されるわけではない。にもかかわらず、国家間の取り決めによって決着をつけるというのは、問題が際限なく継続しないための国際法上の約束ごとである。 相手を尊重することにならない加害者意識 ・「従軍」慰安婦問題にせよ南京事件にせよ、日本人の多くは戦争に関わる問題を持ち出されると心が痛む。それは、事実である。 ・いずれの問題も、多くの場合、現在のわれわれとは無関係の他人が他人に対して加えた危害の問題である。それを、日本人は自分自身がそうした加害を行ったかのように感じるのである。 ・それはなぜかといえば、このとき、危害を加えた者と自分とが同じ日本国民であるという意識が関与しているからに他ならない。 ・もし日本という国も日本人という意識もまったく介在せず、ひとえに個人の立場に立つなら、過去の日本が行った戦争に関する問題を持ち出されても、心が痛むことはないはずであろう。 ・そうした個人中心の立場に立ちながら、「日本人の戦争犯罪」を糾弾している人びともいる。しかし、このような人々は、日本を糾弾しながら、日本人である同胞の犯罪ということで自らの心を痛めている様子も見えないのである。 ・彼らの頭のなかには、かつての左翼の階級闘争の考えに由来する、国家権力と一般民衆という図式がまずあって、一般民衆を虐げるのはつねに国家権力であり、そして被害者である一般民衆は日本の民衆であろうと中国の民衆であろうと、同じだと考えているのだろう。 ・そのうえで、同じ被害者の側に身を置くものとして、アジアの民衆と連帯して、ことさら悪質な国家として日本を糾弾するということのようである。 ・そこまでいかなくても、まず、こうした被害者対加害者という図式を先行させたうえで、日本を、なによりもこの加害者として捉えるという点から出発する人々も多い。 ・その一つの例として、駒込武氏は藤岡信勝氏の「私たちは日本人ですから、日本のことをまず考えることは自然の出発点である」という言葉に反論して、次のように述べる。 「私ならば、『日本人』としての意識的・無意識的に身につけてきた『他者』へのイメージがあります。そのイメージの中には、植民地支配と侵略戦争の歴史を通じて形成された中国人や朝鮮人への先入観、偏見、あるいは身勝手な思いいれなどが色濃く沈殿していることでしょう。そうした制約から自分自身ができるかぎり『自由』であるためにも、出発点としては『日本人』としての自己を引き受けざるをえない、と私は考えています」 ・同様の傾向は、いわゆる「歴史主体論争」といわれた議論にも表れている。 ・「三〇〇万の自国の死者」への哀悼を通じて「われわれ日本人」を確立すると述べた加藤典洋氏に対して、高橋哲哉氏は、まずアジアの死者に向き合うことが先で、そうしなければ、自らのアイデンティティは確立できないと述べている。 ・自国のそして自国民の欠陥を鋭く認識し、過去の悪を反省することは必要である。 ・にもかかわらず、こうした人々のように、日本はまず何よりも加害者であり、その日本に自分が属している事実を恥と捉え、その気持ちから出発することが良心的だと考えるのは、果して妥当であろうか。 ・このように、自国を加害者と見なし、それに対応して、相手方を被害者として眺めることから始めるのは、両国についての理解を非常に歪んだ一面的なものにしてしまい、それこそ、真の相互理解を困難にしてしまうであろう。 ・さらに言えば、こうした見方は、ともすれば、相手のアイデンティティそのものを単なる同情すべき無力な被害者のイメージで理解することになりかねない。そして、それは、相手方の尊厳を真に尊重することにはならないのである。 良心派が主張する被害の弁償の非現実性 ・良心の立場に立つ主張も、果たして、その良心的態度を実際にどこまで貫けるのかを考えていけば、その非現実性が明らかになってくるように思われる。 ・たとえば、こうした人々の主張のように、「従軍」慰安婦の人たちに国家賠償をすることになったとしよう。 ・いったん「従軍」慰安婦の補償をすると決めれば、論理のうえでは、必ずや戦争中に死んだ人にも当然、補償が必要だということになる。 ・とりわけ、合法的な戦闘行為による被害者も、また戦争犯罪による被害者も、等しく加害による犠牲だという、先の仕分けのない議論に立って論を進めていくと、日中戦争での被害者は三〇〇〇万人と中国は主張しているから、こうした人々すべて、あるいはその遺族に、少なくとも慰安婦であった人々と同程度もしくは、それ以上の割合で、補償しなければならなくなる。 ・しかも、日本政府に対して賠償を請求している元慰安婦は、実際には、一人当たり二〇〇〇万円から一億円を主張しているから、この額をそのまますべての個人補償に適用すると、日本の一所帯当たりの負担は、これよの一けケタないし二ケタはね上がることになるであろう。 ・戦争の被害をすべて個人に保証するということは、究極的には、こうした問題に行きつかざるをえないのである。 ・そのとき、日本の国民はこの補償案を受け入れるだろうか。また、良心派の人々は、ここまで考えて発言しているのだろうか。 ・確かにわれわれは、戦争の被害を受けた人々を思えば胸が痛くなるのを覚える。そこに私たちの良心の証があるように思うであろう。 ・個人として胸を痛めること自体は、私はきわめて大切なことだと考える。苦しみに共感を持てない人間は、他者と付き合ってゆくことはできない。 ・しかし、戦争の賠償の場合は、それをどのように表現し、どのように行動するかということになると、このようにきわめて複雑な問題を孕んでいる。 ・というのも、個々での「痛み」というものが、一個人としての当人自身の行為でもなく、まったく無関係な他人の行為でもないような、まさしく「国民」としての行為に関わるからである。 ・ここから、その賠償ということも、単に個人間の関係とは異なった解決のやり方を考えなければならない。 ・この意味で、戦争時の互いの被害をめぐるトラブルは、国家間の講和条約で解決するという方法は、国際社会が、その長い経験のなかで生みだしたきた、ひとつの知恵なのである。 ・さらにもう一つ問題がある。戦後五十年たってなお補償せねばならないとすれば、単にそれに留まらず、戦争犯罪を犯した人々に対しては、時効を停止しても訴追されねばならないことになる。 ・ドイツ政府はナチスの犯罪に限っては時効を停止しているが、それと同じ扱いが必要だということなのである。ただし、これは日本の戦争犯罪が、ナチス並みの異常なものとすればの話である。 ・日本の戦争犯罪はナチスと同等のものではない。 ・胸の痛みを表明して、個人補償の主張をする人々は、それが、実際には、どこまでの範囲の行動を含むのか、提示しなくてはならない。 ・国家が保証せよということは、国民の一人一人が補償するということであることを忘れるわけにはいかないのである。 韓国や中国についての政治的配慮 ・韓国や中国にしてみれば、日本が当時の国際社会の通常の道徳基準に照らして、ことさら異常な行動をとったわけではなかったと主張されても、納得できないだろう。 ・韓国や中国にとって真に問題なのは、日本がある基準で見て正常だったか否かということではなくて、まさに自分たちが被害を被ったこと、あるいは民族的自尊心が毀損されたことが問題だからである。 ・従って、日本は先の戦争で被害を与えた国々に対して、良好な関係を維持しようとすれば、細かな政治的配慮を行うことは当然である。 ・政府首脳が折に触れて遺憾の意を表明したり、国として友好的に援助を行ったりするのは、そうした政治的配慮の一環である。 ・そのことと歴史教育の原則ははきり区別しなくてはならない。すなわち、そうした政治的配慮からなされた決定と、歴史教育がいかになされるべきかは、ひとまず区別して考えねばならないのである。 倫理的な視点だけでは他国の歴史も理解不可能 ・日本の歴史、ことに近現代の歴史を考える場合に必要なのは、日本が良きにつけ悪しきにつけ、世界的に見た場合に決して特殊で逸脱した存在ではないということである。 ・その他の国々と同様に、日本もまた様々な問題に直面し、それを克服しあるいは危機に陥りながら現在の日本を形成してきた。 ・それは、高次の倫理的な水準を設定して、過去を裁くような視点からは明らかにならないのである。 ・もしこのことが理解しがたいというのであれば、他国の例を考えればいい。 ・十九世紀半ばから二十世紀前半にかけてのアメリカは、西部の開拓を終えフロンティアが消滅し、キューバやフィリピンをめぐって戦争を繰り返し、ハワイに進出してゆく。 ・もともと、西部開拓の過程も、その実態は原住民のインディアンを駆逐し追い詰め、居留区に閉じ込める政策であったといえないこともない。そして、その後の対外政策も、侵略の歴史であったことは否定できないのである。 ・当時フィリピンはスペインの植民地であったが、スペインとの戦争によってフィリピンを領有するにいたるが、フィリピン側の抵抗を鎮圧する過程で、アメリカは六〇万人のフィリピン人犠牲者を出したとされている。 ・しかしながら、こうした側面を持つアメリカの歴史を、ひとえに侵略の歴史と理解するのはやはり、あまりにも一面的であろう。 ・アメリカ国内では、西部の開拓は未開な地域を切り拓いた偉業として語られるのが一般的であるし、その後の対外発展も、アメリカのデモクラシーと文明を普及させる使命を遂行したと捉える傾向が強い。 ・アメリカ国内の解釈が客観的に見てどうかは別として、アメリカの歴史が様々な側面から成り立っているのは間違いない。略奪と侵略の歴史がアメリカの歴史だというのは、明らかに偏った見方であろう。 ・西洋世界に視野を広げれば、大航海時代以来の彼らの歴史をどのように見るべきかという問題がある。 ・西洋人の目的は、キリスト教を世界に布教するという意図があったことはもちろんだが、同時にアジアの富を西洋に持ち帰るという目的も大きかった。それどころか、前者より後者のほうが比重としては重かったかもしれない。 ・そこで、西洋の近現代の歴史を、アジアに対する侵略と略奪としてのみ記述したとすればどうだろうか。この場合には、西洋文明の世界への拡大ということの意義を見逃してしまう結果になるだろう。 ・各国間の関係を加害者対被害者の図式から出発して築いていくということは、往々にして、両者の相互理解を、一面的で歪んだものにしてしまうのである。 第五章 愛国心と歴史の連続性 『ポーツマスの旗』を読ませる ・歴史に興味を持たないといわれる現在の学生も、過去の事実について共感をもって書かれた書物を読めば、ひとしく共感をいだき、内面的な理解を示すということは確かなのである。 武士が幕末に活躍したのは教育の効果 ・歴史や道徳のような教育の効果は目に見えないし、その効果が現れるのは何十年もしてからという場合が多いために、さして意味がないと考えがちである。 ・しかし、このような教育は潜在的に非常に大きな力を持っているし、それを通して人間や社会の理解を広げ深めることは不可欠である。 ・たとえば、幕末に武士たちが日本の運命を担っているとの自覚をもって行動したのは、まさに教育の効果であったと考えられるのである。 ・徳川時代に武士たちは、統治階級と位置づけられたが、本来の彼らの役割であった本格的な戦闘は、大坂の陣が終わった十七世紀の始め以来、約二百数十年の間、まったくなかった。 ・ところが、幕末になって武士本来の役割を発揮すべきチャンスが到来したとき、彼らの多くは、まさしく戦闘者としての、統治階級としての任務を遺憾なく遂行した。ことに、下級武士においてそれは顕著で、明治維新への推進力となっていった。 ・考えられるのは、武士の支配階級としての責任感と戦闘者としての自覚が伝統として継承されていたことである。 ・本来、戦闘者である武士は普段どのような心構えでいなくてはならないか、また支配者としてどう振る舞うべきか、などの教育が継続されていたのである。 ・『葉隠』や『武道初心集』といった武士道を論じた書物は、武士という存在が、極限的には死に直面しなければならないような非常事態においてこそ、その価値を発揮すべきものであることがつねに強調されている。 ・どのような時代においても教育は、今日明日の利害関心から論じるべきではないし、また短期的な政治的要請から判断すべきものではない。 ・人間の精神や資質を時代の情勢や変化に流されずに維持しようとする強い意思が数百年もの後までも影響を与える。 ・教育はそうした伝統の保存という大きな課題と関わっているのである。 ・現在の教育も、目下の現実がどのようなものかということとは別に、わが国は本来どうあるべきか、そして国民はどのような構えで生きていくべきかという問題と深く関わる面を持たなければならない。すなわち、数百年単位で、その意義を考えなければならないのである。 日本国家の連続性はどこから生じてきたか ・これまでの歴史教育で大きく欠落しているのが、日本の国家制度がどのように継続してきたのかという視点である。 ・個々の時代の特色を学ぶと同時に、時代を越えて連続性を持っていたものは何かということを知ることが大事であろう。 ・われわれは、歴史を見ていく際に、どうしても現実の支配者が誰かという面にのみ注目しがちである。 ・たとば平安時代から武士が台頭してきて、やがて幕府を作り武家政権がつづき、さらに明治維新で近代的な政府になったと理解するのだが、では、その武家政権の正統性の理論的根拠は何だったのだろうか。 ・確かに徳川幕府は関ヶ原の戦いで勝利することで、権力を名実ともに獲得した。実力によって政権を盤石なものにしたのは事実であろう。だが、徳川政権は武力だけを根拠にして自己の政権を正当化したわけではなかった。 ・徳川幕府は征夷大将軍という名で日本の支配を行うが、この役職は基本的には律令国家のものであって、日本古代以来の法・政治的な制度が念頭におかれている。 ・征夷大将軍は、征夷使などとも呼ばれ、もとは朝廷が臨時に定めた役職であったが、後に源氏のような武家の棟梁によって世襲され、様々な属性を身につけていく。 ・そうしたなかで、この役職の者が日本全国の統治権限を預かっているというかたちをとったのが、幕府にほかならない。 ・言ってみれば時代の状況から防衛庁長官もしくは国防大臣が全国統治の任を帯びるになったわけである。幕府とは文字通り「陣」を意味し、軍事動員体制なのである。この軍事動員体制がそのまま国家統治の体制となったのが幕府政治なのである。 ・この動員体制は、律令体制というはるか古代から継続してきた政治システムに究極の根拠をおいていた。 日本の「憲法」は律令制であった ・憲法とは本来の意味からすれば、文章にされて制定されているか否かといった体裁の問題を問わず、国家の根本制度であり、国のあり方として人々に思い浮かべられている内容を指す。 ・この意味での憲法は、近代国家でなくとも必ず存在し、国家の歴史を規定している。 ・日本の歴史を眺めて、武家政治までの根本制度が何であったかを考えれば、やはり基本的には律令制であったと言わざるをえない。 ・日本の根本的な制度として、天皇を頂点とするシステムが、きわめて長い間にわたって継続してきたことを否定することはできない。 ・こうした議論を始めると、すぐにそれは皇国史観であるという批判がなされることになる。天皇を頂点とする政治システムが継続してきたなどという説は、戦前戦中の狂信的なイデオロギーにすぎないというわけだ。 ・しかしながら、率直に日本の歴史を見ていけば、天皇がどの程度に実効支配をしていたかはともかくとして、その時々の権力者が政治的権威の源泉を天皇に求めてきたことは明かなのである。 ・日本の歴史を見ていく場合に、様々な権力者が登場するが、天皇と無関係に形成された権力は正統ならざるものであるという共通了解が、日本にはずっと存在していたことを見過ごしてはならない。 ・たとえば幕末の尊皇攘夷論にしても、この一事が欠落していては、その理解が不可能になるのである。 「五箇条の御誓文」が近代日本を支えた ・幕末に関することで非常に興味深いのは、鎖国開国の議論のなかで、全国統合の象徴としての天皇という認識と、公議輿論を尊ぶという民主化への傾向が、ひとつに統合されたことである。 ・浦賀に黒船が来航して開国を迫った際、鎖国体制を敷いてきた幕府はこの問題を処理できない状況に直面し、そこで窮余の策として採用したのが、外様大名に意見を聞くという方法だった。 ・この意見の聴取が何を意味したかといえば、権力底辺の拡大と深化であり、言い換えれば民主化の進展であった。 ・つまり、幕府が専制的に決めていた事項について諸大名に意見を求めたという意味で拡大であり、また諸大名も藩内の武士たちに意見を求めるに至るので、深化という面を持った。 ・そうしてなかで、日本国中の中級および下級武士たちの政治参加の欲求が高まり、激しい政治闘争を引き起こしていくのである。 ・そこから、政治決定は、多数の人々の意見を集約した「公議輿論」に基づかねばならないという理想が生み出されていく。 ・さらに、幕府は、通商条約の調印をめぐって、国内の反対を押し切るために、朝廷の勅許を求める動きに出たので、そこから、朝廷の意向が、まさしく現実政治のうえでも重要性を帯びるに至った。 ・そこで当然のことながら起こったのが政治的な危機である。 ・すなわち、朝廷の意思決定をめぐる政治的駆け引きで、一方では幕府が工作し、他方ではこれに長州藩や薩摩藩といった雄藩が対抗するという形となっていった。さらには、そこに、一般の武士たち、とりわけ草莽の志士と呼ばれる人々が様々な形で関わってくる。 ・こうして朝廷の意思決定は、様々な政治勢力に影響を受け、きわめて不安定にならざるをえなくなっていった。 ・その結果、問題となったのは、急速に権威を上昇させた朝廷が出す勅令と、様々な勢力が持ち込む政治的意志との関係である。 ・もし、朝廷が一つの政治勢力の意志にのみ依存して勅令を発すると、それは、公議輿論に矛盾する勅令だとされ、朝廷の権威自体が失墜する恐れがある。 ・そこで、朝廷の権威を維持するためにも、合理的に「公議輿論」を形成するような制度をつくりあげる必要が出てきた。 ・他方、各政治勢力も、互いに自分たちの主張こそ「公議輿論」だと主張しようとしたが、それだけだと混乱が増すばかりである。こうして幕末に様々な立場から様々な形での議会制度の試みが提案されていくのである。 ・そこで重要なのは、ある意見が公議輿論であるというだけでは日本全国の統治が可能かといえば、たぶん困難だったろうということである。 ・というのも、この時期には、朝廷は、日本の本来的な統治者であるということが、かなり広い範囲の人々において、より一層明瞭に意識されるようになっており、日本国の政治意志は、やはり、勅命という形で発せられて最終的な権威を持つという事が当然の前提とされるようになっていたからである。 ・おそらく後に明治のリーダーとなる人々はこの難問に直面し、勅命の権威と公議輿論の二つをなんとか統合する必要があるという共通認識を持ったのである。それが、一八六八年三月の五箇条の御誓文というかたちで現れてくる。 ・五箇条の御誓文の第一条には「万機公論に決すべし」とある。これは他ならぬ天皇自身が自らの意志として、公議輿論に即した統治を行うべきであると宣言したものである。 ・日本の近代憲法は、こうした天皇の権威のあり方についての新しい解釈のもとに発せられた。この五箇条の御誓文に淵源を持つことになるのである。 ・その場合、古い神話の再解釈も動員されることになった。実際、岩倉具視のように、公議輿論に従うことを、神話の ・こうした試みは、屁理屈に思われ、つい軽く見られがちだが、にもかかわらず、日本の国家制度を伝統との連続性のうえに築こうとした努力のあらわれであり、その意義を見落とすべきではない。 ・このような連続性を強調して、憲法の意味を考えることは、もしかすると新奇に聞こえるかもしれない。明治以前にも憲法があり、五箇条の御誓文がその再解釈なのだという説は突飛に過ぎると思う人もいるかもしれない。 ・しかし、それは憲法というものが、帝国憲法やとくに戦後の日本国憲法のような体裁をとったものだけを憲法と呼ぶと思い込んできたからに過ぎない。 ・明治期には、こうした広い意味で憲法を考える例は、今日よりはるかに一般的に見られた。 ・たとえば明治のジャーナリスト福地桜痴は、憲法とはその時点で創設するものではなく、歴史の連続のなかで、従来あったものを編纂するものだと論じている。 象徴天皇制度の継続性に注目すべき ・明治憲法体制では、天皇大権を認めながら、同時に天皇大権の行政権の行使にあたって、各種大臣の輔弼によることになっており、実際に大臣が決定をして天皇の裁可を仰ぐというかたちになっていた。 ・明治維新の「五箇条の御誓文」に発する民主化の動きが、次第に明確な形をとっていったのが、日本の憲法の歴史なのである。 ・すなわち、「万機公論に決すべし」は生きている。戦後の天皇の「人間宣言」と呼ばれるものもその本来の趣旨は、この五箇条の御誓文を確認することにあったのである。 ・日本国憲法は、アメリカに押しつけられたという議論がある。しかし、日本国憲法の条文を作成する段階で、天皇を象徴というかたちで残さざるをえなかったことは重く見るべきであろう。 ・象徴としての天皇は、廃止すれば日本国民が抵抗して、アメリカの占領がうまく行かなくなるので残したとされている。 ・それも一面は正しいが、裏を返せばいかに占領軍でも日本国民が持っている憲法感覚を、全否定するようなことはできなかったということに他ならない。そのため、日本側の憲法感覚が生き延びて、現在の象徴天皇制度として継続しているというべきであろう。 ・われわれは、いずれの憲法典をも絶対化することなく、わが国の憲法の歴史全体を視野のなかに収め、様々な状況の変化を考慮して、日本の国制の望ましいあり方を追及していかねばならないのである。 第六章 近代史を見直す 現在の歴史教育の内容的欠陥 ・日本の歴史を見ていく際、これまでは、あまりに国内的な視点にのみ囚われてきたようである。 ・ことに歴史教科書の場合、国際社会においての位置づけを語らないかぎり、正確な理解には至らないような事実が多数あるにもかかわらず、この点の配慮が十分ではない。 ・日本は古代以来、周辺のアジア諸国と密接な関係を維持してきた。国内の事件も、そうした国際情勢を背景に考え初めて、解釈できるのである。 ・たとえば、大化の改新も基本的には唐が成立した後の国際情勢の変化が影響しており、当時の大陸の大きな政治変動との関連で捉えられねばならない。 ・端的に言えば、大陸で緊張が高まったために、日本国内でも対外的な脅威に備える必要が実感されるようになったのである。 ・しかし、現在の教科書では日本の大化の改新は、単に唐の制度にならって中央集権国家をつくったというような膨らみのない記述がなされており、制度上の模倣のようにしか読めない。 ・明らかに、大陸に対する防衛が意識されていたにもかかわらず、単に大陸文化の移入が試みられただけのような印象しかないのは、この時期の歴史を真に理解したことにはならないであろう。 ・また、江戸時代の鎖国にしても、キリスト教を禁止し徳川体制を維持するために国を閉ざしたように書かれているが、当時豊かだったアジアに物質的なものを依存していた日本が、アジア経済から鎖国を通じて自立していく過程という面があり、それは、ヨーロッパが産業革命によってアジア経済から自立していく過程とパラレルなものだった。 ・日本国内からの視点だけではなく、巨視的に見れば江戸時代の鎖国もまた、当時の世界史の大きな動向に対するひとつの対応であった。 ・それは西洋が「産業革命」を背景にアジアに進出してアジアの豊かさを収奪していくのとは対照的に、日本は国内を「勤勉革命」によって豊かにしていくというコースを辿ったということなのである。 ・現在の歴史教科書では、こうした世界的な視界を持たないために、鎖国に対する否定的な評価のみが旧態依然のままに残されている。 ・また、国内を見る視点も支配する者と抑圧される者の対峙という図式に押し込められ、支配がきつくなると民衆が爆発して一揆を起こすという歴史に矮小化されてしまっている。 ・教科書には必ず百姓一揆の発生件数グラフが掲載されているが、この一揆が実際にはどのようなものであったかの最近の研究は採用されず、階級闘争史観もしくは民衆抵抗史観で書かれている。 ・日本とアジア諸国との関係を、ひとえに、加害者対被害者のそれとしてとらえるということも、こうした学校での歴史教育のあり方が大きく関係していよう。 ・さらに、明治維新を経て近代国家を確立してゆく日本が、国内の事情に重きをおいて記される傾向も強い。 ・ペリーの来航自体が当時の国際社会の激しい動きをしめす事件だというのに、そうした国際的背景は詳しく述べられていない。 ・そしてそのことが、近代化後の日本が味わった国際社会参加のための苦闘の経緯を欠落させ、その後ひたすらに侵略に向うという、一方的で狭隘な記述につながるのである。 世界史における日露戦争の意義 ・日露戦争についてだが、現行の歴史教科書においての扱いは、日本の帝国主義の発露としてしか描かれていない。戦争は悪いことで、戦争を行った日本はアジアの問題児であるかのような記述である。 ・必ずといってよいほど記載されているのが与謝野晶子の「君死にたもうことなかれ」という弟に手向けた詩であるが、教科書の編纂者はこの詩が反戦的なものであると考えて採用するらしい。 ・その一方で日露戦争終結のためのポーツマス条約に不満だった暴徒が日比谷焼き打ち事件を起こすのは、戦時体制の苦しさに耐え切れず暴発したことになっている。 ・与謝野晶子の詩は、商家である実家の後継ぎである弟が無事に帰ってくることを願った詩に過ぎず、自覚的な反戦思想とは無関係である。 ・また日比谷焼き打ち事件を起こした人々が主張していたのは、戦争を継続して賠償金を取れという要求に他ならなかった。 ・民衆はつねに戦争によって苦しんできたという一面的な解釈が、こうした戦争やそれに関する人々の実態を見落とすことになるのである。 ・しかし、これも世界的な視野を導入することで、一面的な理解から抜け出すことが出来る。 ・日本にしてみれば世界最大の陸軍国といわれたロシアが、朝鮮半島に南下してくることはいかにしても食い止めねばならないことであった。それは、日本の存立をかけた戦いであった。 ・そしてその結果の勝利は、初めて白人以外の国家が白人の脅威を撃退したということで、世界中が着目した。 ・ことに西洋諸国の植民地や半植民地となっていた地域の人々は、この日本の勝利に沸き立った。 第七章 世界史への日本の貢献 一九三〇年代はソビエトの脅威を抜きにしては語れない ・一九二〇年代が終わるころには、すでにアジアの情勢はワシントン体制を維持できない状況になにりつつあった。ワシントン体制とはつきつめるところ中国に権益を持っている先進国が共同で中国を管理するということである。 ・ところが、一九二〇年代の終わりには蒋介石の国民党が全国統一を進め、それが華北に及ぶと日本は満洲の権益をめぐって脅威を感じるようになる。 ・さらにもう一点、第一次世界大戦末期に起きたロシア革命によってロシアにボルシェビキ政権が生まれ、北方からの脅威が非常に大きなものとして意識され始めたことである。 ・そのため、日本の軍部、ことに関東軍のなかに、この満州の地域を中国から切り離し、一方では中国の統一推進によるインパクトから満州の権益を守り、もう一方ではその権益を用いて満州を産業化し、ソビエト・ロシアの南下を防ごうとする構想が生まれてくる。 ・その結果、満州事変が引き起こされ、一九三二年三月には満州国の建国が宣言されるわけである。 ・ソ連の成立は資本主義に対する社会主義の挑戦だったともいわれている。しかし同時に、イデオロギーによって形成された体制であったがゆえに、国内外の伝統に対する容赦のない破壊攻撃や国際的規模でのプロパガンダは史上類例を見ないものであった。 ・ことにコミンテルンの結成以後、ソ連は国際的共産主義運動の本部として、世界中の共産党をコントロールするようになった。各国の共産党はそうしたソ連の世界革命プログラムに則して行動することになったのである。 ・戦後日本の歴史学会を長い間拘束した講座派の議論も、実はコミンテルンが戦前に日本の情勢を分析するための理論だったわけで、それ以後も影響を及ぼし、現在の歴史教科書にまで入り込んでいる。 ・ここで確認しておくべきことは、ソビエト連邦というものがどのような国家体制であったかという評価を示すことも、歴史教育の重要な課題だということである。 ・ところが、スターリン体制下での「反対派への弾圧」があったといった記述はあるものの、そもそも、数千万人に及ぶ「収容所群島」体制下での一般人民の犠牲については言及がない。 ・さらにロシア革命が現在の視点から見ていかに多くの災禍を世界にもたらしたかが記載されなければ、その先行モデルとされてきたフランス革命が、人類に人権と平等をもたらした革命であるとの単純なイメージも、訂正されることがないだろう。 ・にもかかわらず、日本の歴史教科書においては、依然として、ロシア革命やフランス革命は無条件で称賛すべきものであるかのように記されているのである。 戦前日本の置かれた立場を多面的に把握することが必要 ・戦前の日本を考える際には、一方では遅れてきた帝国主義国家として獲得した権益を何とか擁護したかったということと同時に、急速に国際社会に影を広げてゆくラディカルな体制ソビエト・ロシアに対抗する必要が生まれていたことも、きちんと押さえてかからねばならない。 ・ソ連にいかに対抗するかは、さしあたり外交課題であったが、それは同時に国内的な課題にもなっていく。 ・というのは、各国の共産党と同様、日本共産党もまたモスクワのコミンテルンの指令によって動いており、「コミンテルン日本支部日本共産党」が正式名称だった。 ・治安維持法は、外国から指示を受けて行動する革命政党に対して、従来の治安法規では不十分であるという認識から、ソ連との国交樹立と併行して一九二五年に制定されることになったことを忘れるわけにはいかない。 ・悪名高いこの治安維持法については様々な批判があるが、日本の特高警察と日本共産党との戦いが、明治期におけるような、単なる国内の権力と反政府団体との抗争とはいえないことを前提とすべきであろう。 ・歴史的な経緯を押さえるならば、この戦いはソビエト・ロシアと大日本帝国との国際的な戦争の一環であったと考えざるをえないのである。 もちろん日本とソ連は、宣戦布告して正式に武力衝突を開始したわけではないから、いわば冷戦に突入していたということができる。一九二〇年代とはこうした日ソ冷戦の時代だったのである。 ・このとき日本側からして問題だったのは、当時としては対抗するための理論もイデオロギーも準備できなかったことであった。 ・そのことが日本警察の、マルクス主義やソ連に対するヒステリー的な症状を生みだしたと考えられる。 ・そもそも、治安維持法は「国体を変革し、私有財産制度を廃す」ることを目的とする政治活動を取り締まると述べている。 ・この「国体を変革」するとは、天皇制度を廃止するということを意味する。 ・当時の情勢を考えてみれば、この条文の背景には、ソビエトの共産主義というものが、単に資本主義を否定するにとどまらず、伝統的なものをすべて否定・破壊する敵だとみなすという認識が込められていたのではないだろうか。 ・ソ連が当時どのような勢力として考えられていたか。ボルシェビキは三百年以上も継続したロマノフ朝の皇帝を無残な方法で処刑したが、そのすさまじさは日本の庶民の間でも感じ取られていたようである。 ・理屈では対抗できないが、形容しがたい恐ろしさ。この感覚が「国体を変革」するものを取り締まるという表現になったものと考えられるのである。 ・言い換えれば、ソビエト・ロシアの持っていたラディカルな原理主義に、危機感を持ったというのが実態だったろう。 原理主義に対する原理主義的な反応 ・日本の脅威となってきたソ連のイデオロギーは別の意味で「危険な純粋さ」を有していた。 ・イデオロギー的な一貫性の追求ではあったが、それだけに強力な破壊性を持っていた。 ・それは階級闘争の貫徹を信じ、「階級の敵」「人民の敵」という一切の「不純なもの」を殲滅したのちに、新しい社会をつくるという原理主義に他ならなかった。 ・日本でも、明治維新において克服されたかに見えた原理主義が、一九三三年代になって、息を吹き返してきた。 ・この時期の日本の原理主義は、国体明徴運動につながっていく。 ・「国体明徴」という言葉自体も「純粋さ」への願望を語るものであろう。 ・明治時代に地下水脈にもぐった原理主義が、ボルシェビズムの台頭に刺激を受けて地表に現れてきたものであった。 ・つまりソビエト共産主義という原理主義に対して、原理主義的に解釈された「国体」の観念で対抗するというかたちをとったのである。 ・明治立憲制は、こうした原理主義の噴出に耐えることができなかった。 ・明治立憲主義はあたかも戦前の軍閥政治の前に必然的に崩壊していったかのように考えられがちだが、当時の厳しい国際環境を考慮に入れたうえで、戦前と戦後の国家制度のあり方をもう少し連続的に眺める視点が必要だと思われるのである。 満州事変と日中戦争との違い ・現在、中国大陸に関する日本の行動はかべてが侵略行為であり、世界中から一貫して非難され続けたかのように言う人がいるが、これは必ずしも正確ではない。 ・客観的に眺めると、一九三一年の満州事変では、関東軍の行動は明らかに計画的であり、侵略的と言われても仕方のないものだった。 ・それに比べて一九三七年の北支事変は、初めは偶発的なものだったと言える。 ・にもかかわず、諸外国は、満州国の建国宣言以降はそのまま黙認するという対応をとる。 ・というのも、日本の行動を武力まで用いて制裁するという意志も能力も持たなかったからであり、そもそも、日本の侵略を過度に批判すると、中国本土に対して持っている自己の権益の正当性もあやうくしかねなかったからである。 ・また、満洲という地域はもともと歴史的には、中国本土とは見なされておらず、その周辺部分に位置していたということも大きかった。 ・それに対して、支那事変には強い関心を払い、激しい非難を行った。支那事変における日本軍による侵攻は明らかに中国本土に対してなされたからである。 ・しかも、戦闘が、上海に飛び火し、揚子江流域が戦火に晒されるようになると、各国は、日本の行動に激しい懸念と警戒心を抱くようになった。 ・というのも、その地域には、西欧列強の権益が集中していたからである。こうして、日本に対する国際世論は硬化の一途をたどることとなった。 ・蒋介石の中国政府は、軍事的には弱体だったが、こうした国際世論を背景にして、日中の戦争を世界の問題として諸外国を巻き込む戦略に出た。なるたけ問題を国際化して、日本を孤立させる方法をとったのである。 ・その結果、日本国内にはどのような考え方が生まれてきたかといえば、明治時代に突きつけられた三つの選択肢の見直しだった。 ・日本が国際社会のなかでつねに批判を受け、不利益を被るのならば、ヨーロッパ国際法秩序に参画している意味はない。日本は東アジアで独自の秩序を形成し、その盟主になるべきだという第三の道がリアリティ持ち始めたのである。 ・日本はアジアに独自の秩序をつくり、欧米列強を排除するというこの思想は、アジア・モンロー主義などとも呼ばれたが、日本政府の声明としては「東亜新秩序」とか、さらには「大東亜共栄圏」として主張されるようになる。結局、日本はこの路線に沿って、大東亜戦争に至る。 ・歴史教育では、こうした日本の辿った経緯を、理解可能なものとして提示することが必要であろう。 ・そこには、日本が行った選択への批判があってもよい。しかし、それは当時日本が置かれた立場への内面からの理解を前提とするものでなければならないのである。 戦後のアジア世界から見た日本の近代史 ・第二次世界大戦に日本は敗北し、そして日本の領土は日清戦争以前に戻ることになった。 ・この時点での敗戦と世界政治からの後退を見れば、日本が明治維新以来重ねてきた営為は、水泡に帰したかのように思われる。 ・しかし、このことから、日本近代の営みが無意味であったと考えるのは間違っている。 ・そしてさらに戦争についても、日本は野蛮な侵略を行っただけで、アジアに何の利益ももたらさなかったということは正しくない。 ・第二次世界大戦が終わったとき、アジアにおいては、日本の侵攻による大きな衝撃の結果、イギリス、オランダ、フランスの植民地体制が崩壊した。 ・それは同時にアメリカのアジアにおけるプレゼンスが高まったことも意味したが、アジアを植民地にしていた国々が再び戻って支配者になることはなかった。 ・確かに、日本が、もっぱらアジアの植民地支配を開放するために先の戦争を始めたという言い方は正確ではないであろう。 ・だが、アジア諸国の独立の経緯を詳しくたどっていけば、アジア独立のために行動した日本人が少なからず存在することも事実であり、植民地支配からの解放という意図を全否定することはできない。 ・ちょうどそれは、たとえばヨーロッパ人がその時々の私利私欲のために世界に植民地を開拓していったことと、同時に、ヨーロッパ文明を広めることにもなったという歴史的認識が矛盾なく成立するのと同様である。 ・あるいは、亜米利加の西部開拓は現実には原住民であるインディアンを駆逐していくことであったにもかかわらず、アメリカの立場からすれば自由の理念が広がり、アメリカ合衆国が成立していったと述べることと、さほどの懸隔があるとは思えない。 日本が世界の歴史に貢献できた理由 ・日本の場合も、その当時の個々の政策遂行者が実際に何を考えていたかとは別に、日本の行った戦争が、ヨーロッパ諸国のアジア植民地支配を覆したという客観的事実は語られるべきだと思う。 ・そして注目すべきは、そのアジアの国々がいまやすべて主権国家となったということである。 ・かつてのヨーロッパ国際法秩序では、三つの層が存在した。 ・同じ国家としての関係でありながら、対等であったのは欧米諸国のみであり、日本などの追随国は第二層にあり、アジアやアフリカの国々は植民地として第三層に位置づけられていた。 ・しかし、いまやすべての国々が主権国家として横並びで対等な関係になった。国際社会は、ここまで民主化されたわけである。 ・大東亜共栄圏という思想のなかには、日本が、必死で同化しようとしたヨーロッパ国際法秩序に対して、その一方で抱き続けてきた釈然たらざる思いが投影されていた。 ・そうした思いを背景に戦われた大東亜戦争は、結果としてはヨーロッパ国際法秩序そのものではなく、従来の三層構造を破壊し、それを民主化して、真に法的に対等な主権国家によって構成される国際社会をもたらしたのである。 ・日本はひとつの国際体制に所属してその根本原理(対等な主権国家)を承認しながら、その体制の現実に対する批判から、その原理を文字通りの形で実現するような国際革命を果たしたのだと言えよう。 ・おそらく、日本近代の国民の物語は、以上のようなかたちでヨーロッパ諸国のアジア進出に対抗し、そのことを通じて国際社会の歴史にしかるべき独自の位置を築いてきたことを忘れてはならない。 ・そして日本がそのような役割を果たすことができたのは、日本の歴史のなかに国際性が培われていたからこそ可能になったのであり、そうした見地から日本の歴史を見つめ直していくべきであろう。 ・現在の歴史教科書は、こうした視点に欠けているだけでなく、そのことを考えるための発想を阻害している。 歴史教育は連続性と蓄積の大切さを教える ・もし日本が、並外れて好戦的な国であったならば、なぜ日本は江戸時代のような世界に類例のない平和な時代を、あれほど長期にわたって現出させることができたのだろうか。 ・江戸時代が閉鎖的でそのため日本人に国際性が欠落しているとしたなら、いかにして日本は近代国際社会をアジアに拡大し、また現在みられるような世界経済との関係を作りだすことができたのだろうか。 ・これまでも「日本人とは何か」あるいは「日本文化の特徴は何か」という議論は盛んに行なわれてきたが、その議論を有効にするためには、何よりも伝統が連続性と蓄積によって形成されているということを認識しなくてはならない。 ・歴史教科書の記述も、この点に配慮がなければ、結局、ばらばらの事実の集積に終わるだろう。 ・もちろん、連続し蓄積されたものがすべて好ましいということにはならない。歴史で蓄積してきた資産のなかに積極的な要素と、また、一貫する要素をつねに反省的に把握していくことが必要である。 ・こうした見地に立ってつねに過去を振り返り、こうした積極的な面と一貫性を活かそうと努めることで伝統が形成されるのである。 ・われわれは近代以降、西洋文明の文物を輸入してきたが、それは、それは、単なる模倣ではなく、まさしく、主体的な選択による摂取と同化であった。 ・われわれは西洋文明の個人主義を受け入れながら西洋流のいわば純粋個人主義は回避して、人間関係の脈絡や役割を重んじるような日本型の個人主義を実現した。西洋文明のある面を受け入れ、それを西洋とは異なった方向に発展させたのである。 ・要するに、西洋文明を受け入れながら、それを日本に特有な形で発展させる。こうした方法は、今日から振り返ってみれば、非西洋地域の近代文明発展の先駆的なモデルであったと言える。 「日本的なるもの」は積み重なりのなかにある ・日本の世界史における位置を述べることは、歴史教育のきわめて重要な部分を占めているし、また、それは同時に日本文化や日本人の特質を語ることでもある。 ・その際重要なことは、われわれの歴史のすべての局面にわたって目を配り、その全体像のなかで考えるということである。 ・これまで人口に膾炙した日本人論の多くは、遠く離れた太古の時期にあらゆる特質の起源が含まれていたかのように論じるか、あるいは特定の時代に示されたものを日本人の美質として、ことさら強調するというものが多かった。 ・日本の特質は、誰の記憶にもとどまらないような考古学的事実にあるのでもなく、また理想として恣意的に想定されるものでもない。 ・日本人の文化は、むしろこうした事実を含む長期の歴史と、そこで様々に織り成された文化的要素の蓄積の過程のなかに見出されるべきものであろう。 ・教科書の歴史もまた、この意味での長期にわたって培われた伝統のなかの「日本的なるもの」を様々な工夫と創意を活かして描き出し、進取と発展の気性に富んだ、次代の日本国民の育成に貢献するものでなければならないのである。 ―― 完 ―― |