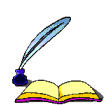
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2022年10月12日 水曜日 】
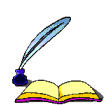
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
15 |
22.06 |
がん患者学Ⅱ 専門家との対話・闘病の記録 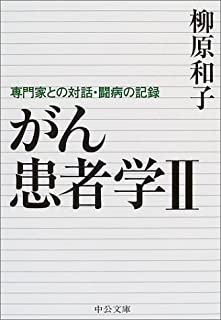 |
柳原和子 |
中公文庫 |
◎ |
第二部 専門家に聞く がん患者はなにを怒り、恨むのか 石川寛俊 弁護士 ■医療はどうあるべきか 石川 ・医療を考える上で重要なのは、はたして西洋医学だけが医療であるといったい誰が決めたのか? という問題です。 柳原 ・ムンテラという言葉があります。ムントテラピー、つまり患者との語り合いもまた医療行為として重要な要素である、という考え方です。 ・がんという病の場合、とくに治療の確率がかなり低い再発以降には、技術以外のムンテラ的要素がかなり重要になってくると思うのです。 ・また、がんとストレス因子との関係、日常の生活習慣とのかかわりが強く懸念されている現代にあっては、治療のための心理分析、日常生活まで含めたムンテラが求められている。 抗がん剤治療、その選択権は誰に? 福島雅典 医師 ■治るということ 福島 ・抗がん剤で殺されるがん細胞の数というのは一定数で決まっているんです。すべての細胞がそれで死んでしまうわけではない。死滅しないわけです。 ・生き残った細胞がまた、動き始める。動き始めるのにかかる時間、増殖速度がそれぞれによってちがう。 ・生き残ったがん細胞が一〇の六乗、百万個くらいならば身体の免疫力でなんとか押え込める。一〇の六乗個というのは大きさで言えば耳かき一杯くらいかな。 ・二ミリ以上の大きさになると、そこに血管が入ってきて一つのの悪性腫瘍として大きく増殖を始める。二ミリ以下だとまだ血管が入り込んでいっていない。 ・がんが治るか治らないかではなく、再発の確率が非常に高いのか、低いのか、というようなものの見方をするようにもっていったほうがいいのではないか。 ・今まではがん細胞を殺さなければいけない、という考え方だったけれど、成長させなくする、という考えかたに変わってきつつある。 ■日本のがん治療のどこがおくれているのか 福島 ・日本では患者さんのパターナリズム、つまり医師への依存度が強い。すべて医師におまかせする、という風土でしょう。個の確立がなかった。 ・自立していません。医師と患者の関係だけでなく、ものごとをはっきりと言う、言葉にするというのをはばかる風土がある。 ・まして死という事実については曖昧にしておきたい、と思うでしょう。 ・アメリカの知人が言ってました。日本人っていうのはほんとのところやさしくない、って。その人は日本が好きなんですけれどもね。 ・多くの日本人は親切なんだけれど、本質的に心と表現が離れている。あるいはそう見える。 ・世の中を変えていこう、とするような運動も決して盛り上がってはいきません。 ・日本の保険制度が問診について、診療費を認めていない。 ・医者は治そうとして無理をしている。それがとても多い。悪意ではないんだ。 ・これをやればもう少しはよくなるのではないか、と思っていきすぎになってしまう、というものですね。 ・医師として、責任感のあり方が後ろを見ない責任感なんです。前ばかり見ている。振り向いて、全体を見渡して、方針を決めようとしない。 ・ちょっと立ち止まって、これはなにもしないほうがいいと考えれば問題がないことが多い。 ・一つには患者を観察していない、というのが原因です。 私が代替療法に与しない理由 近藤 誠 医師 ■代替療法を否定しない 柳原 ・食事療法、運動療法、さらに健康保険で認可された範囲での漢方薬などはお金もいらないし、日常生活にあった原因の一つを取り除こうという意欲につながって、がん告知による心理的動揺から立ち直る支えにはなるように思うんです。 ・しかも、そうした姿勢が、生き方の積極性を生みだしうるし、さらに一日一日を大切にするシンプルな生き方を創りだしうるわけです。 ・一般的には少なくとも食生活と軽い、継続的な有酸素運動はがん発生防止の因子の一つと考えられているわけでしょう。 開業医が進めるサイコオンコロジー 河野博臣 医師 ■病院がなしうる医療とは 河野 ・医師は心身一如ということについて、もう少し深く考えなおす必要がある。 ・心と身体っていうのは潜在的に共通領域にあるということです。 ・まったく無縁に存在しているように見えるけれど、見えないところ、基礎のところで心と身体はつながっているんです。 ・身体と連動している心の領域のほうが全体としては大きい。 ・心と身体は相互に影響し合っている。 ・病気を通して人は自分の心を知る。病気を通してこそ、初めて人間は個性化の道、自己実現を果たしうる。 ・病気をしたり、悩んだりすることで人は小さな死を体験できます。それを体験しないことには、わからない。 ・あなたはがんではありません。がんを持ったあなたなんです。 ・がんっていうもの、がんはあくまで私のなかの一つの要素なんです。要素ではあるけれど、全体ではない。だから、がんについて私という全体はコントロールできるはずなんです。がんも身のうちって考えるべきかな。 ・日本人はがんに私という全体が支配されてしまいがちなんですね。それがやっぱり欧米の人とちがうってところだ。 ・日本人の精神構造にかかわってくる。日本人は相手の顔を見て自分の態度を変えてゆくでしょう。相手の顔を見る、気持ちを察する、というのが問題なんだね。がんになってもそうした傾向が抜けない。 ・がんを持っている人間として、患者として、自分のがんを治すあらゆる可能性、治療を試し、受けていく権利があるということ、自分でそのことをはっきりと意識してほしい。 ■サイコオンコロジーとはなにか? 河野 ・人間は生きてきたようにしか死ねない。 ■がんと心 河野 ・人間は誰もが微小がんを持っている。そういうことでイニシエーションが起こる。 ・正常細胞ががん細胞になって、普通はそれが元に戻るわけだけれども、トラウマが強いとがん細胞にそうした気持ちが移って戻らなくなる。 ・がんがさらに増殖する力になっていってしまう。 ・少なくとも、そういう問題を含めて患者の心理、精神的問題を捉えておかないと、完全な治療はなしえないということになるんです。 ・大事なのはあなたがなんでがんになったのか? がん患者さんにとっては、自分がなぜがんになるのか? ということではないかと思っているんです。そのときの原因という言葉は医者が語る原因とはちがいます。 ・私自身がなぜ? という疑問なんです。医者はこれに答えられない。 柳原 ・がん発症にストレスや心の問題が深くかわっているとしたら、心について対話するのは医療行為の重要な要素になるのてはないでしょうか? 河野 ・医療行為です。しかし、保険が評価していない。 ■告知とインフォームド・コンセント 河野 ・日本の医者は患者がほんうに痛くなるまで我慢させる。欧米の医者はほんの少しの痛みも我慢させない。 ■末期の抗がん剤について 河野 ・アメリカのがん協会でも代替療法は勧めている。大事なのは副作用がないということだ。 ・自分のがんを取り除く、消えてと願うだけでなく、そのがんといかに共に生きるか? ・日本人のがん死が無残であることから抜け出すためにはまず日本の国民性から変わっていかなければいけない。 ・戦後、という時代にも問題がある。物中心になって心がない。 ・がんというのはもっとも心と密接なかかわりがある病です。心がなくて、臓器だけのがんと考えているというのは、これは医者だけでな患者もそうした視点にがんじがらめになっている。 ・化学療法の方法や、新薬を求めるだけでは駄目なんです。 ・人間としての生き方です。臓器のがんとともに心のがんも診ていく。 ・もう一度、がんになったことを契機に自分を見直していくということが重要なんです。 ・そういうプロセスを経ると、たとえ再発を迎えたときにも、自分が「気づき」を与えられたということでよりよい生き方が与えられることとなる。 ・人間は知らない世界に行くことに対しては大変な不安を持つ。死が人間にとって最大の恐怖なのは、体験できないためである。 消化器に学ぶ――食生活とがん 大原純一 医師 大原 ・脂肪に溶ける物質というのは、人間の体に蓄積しやすいのです。 ・ビタミン剤などでも、水溶性のビタミン剤の副作用はあまり恐れなくてもいい。大量に飲んでもどうせ尿や汗に混じって出てしまいます。 ・問題は脂溶性のビタミンE、ビタミンA、ビタミンD、ビタミンK。体内の脂肪に残って蓄積してしまう。そうすると副作用が出やすいし、大量には飲まないほうがいい。 ・結局、体脂肪を減らすということです。免疫細胞を高めておくためにも運動はいいです。 ・私たちの身体には、がん細胞がときどきポコポコできたり消えたりしているわけですから、要するにがん細胞が一個が二個に、二個が四個に増殖しないうちに殺してしまえばいいわけです。そのメカニズムとして人間の身体にはインミューン・サーベイランス、つまり免疫監視機構があります。 ・血液の成分であるリンパ球のなかのT細胞、あるいはキラーT細胞と言われるものがそうした役割を果たしていると考えられている。 ・そうした細胞が活発に機能するような状態をキープするためには全体の免疫をあげる必要があるんです。その意味でも身体を動かすことは大切です。 栄養学はがん治療に無力か? 中村丁次 聖マリアンナ医科大病院栄養部部長 ■がんのための栄養学 中村 ・食べ物というのは生命に必要な栄養素を供給する源であると同時に、健康を害するリスクを持っているということです。 ・人間の身体にとっていいところもあれば、悪いところもあるのです。 ・戦後動物性たん白質を多くとることで確実に平均寿命は延びたと言えます。しかし、食べすぎればがんや生活習慣病の誘因となってゆきます。 ・そうしたメリット、デメリットの関係をもっとうまくかみ合わせるために、食べ物を相互に組み合わせて、一番いい形にするのです。 ・一定のカロリー内で多様な効能をひきだすには、少ない量の食品をできるかぎり多種多様に組み合わせて食べる、というのが基本的な食べ方と言えます。 ・そうした考え方で一日に三〇品目くらいの種類を食べれば、なんとか過不足なく微量な栄養素をも確保できるだろう、ということです。 ・脂肪を多く摂取すると体内の胆汁酸の分泌が多くなり、これが大腸にいって、腸内細菌の作用をうけて、発がん性物質となる、という説が現在のところ有力です。 ・食事の西欧化、つまり外食やグルメ嗜好は高脂肪、低ファイバーになる。穀類の摂取量が減って、脂肪の摂取量が増える傾向を示すわけです。 ・そうすると、便秘になります。便が大腸内に停滞するわけです。 ・食物に発がん性物質があると大腸のなかに停滞することになり、発がん性物質と生体との接触時間が長くなると考えられます。 柳原 ・がんになるほど衰弱しているときにはだいたいが代謝が悪くなっている。 ・身体を形成している基本的な微量元素のバランスもまた崩れていると想像します。 ・玄米にしても、漢方薬にしても、水分接種にしても、それぞれが排泄機能を高める作用を果たしている。 中村 ・水を飲むと体内の老廃物の排泄をよくすると同時に、便通をよくする意味もあります。つまり排泄機能がよくなるのです。 ・穀類が減ると便秘になる。それはなぜかというと、穀類に入っているスターチ、つまり澱粉のなかの一部がファイバーとしての働きをするからです。 ・味噌のなかの大豆が発酵すると、エストロゲンの類似物質ができるということが知られるようになりました。 ・じつはこのエストロゲンというのはがんの予防効果があることで知られています。 柳原 ・ミネラルとビタミン、ミネラル同士、ビタミンとほかのたん白質や脂肪、穀類とのかかわりなど、栄養素には単純に考えられない連関性がある。 ・食事の改善、規則正しい生活や運動は、自分で自分の病に立ち向かう小さいけれどもたしかな武器を得たという気分的な効果はあるだろう。 日本のがん医療現場を解読する 入江健二 医師 ■アメリカの医療とは 入江 ・手術というのは悪いところを取るという治療、放射線療法は悪いところを焼き切る。化学療法というのは薬でもって悪いところを殺す。でも、ついでに正常な部分もかなりダメージを受ける。毒をもって悪いところを抑えるという考えです。それだけでは、がんは完全には克服しきれない。 ・抗がん剤治療については、量をたくさん打てばがん細胞は死ぬ確率は高い。しかし、いい細胞もやっつけてしまうわけですね。免疫抵抗力もやっつけていきます。 ・全身状態、腫瘍マーカー値などを総合的に見て、勢いとして、がん細胞がなくなっていくという方向がはっきりしたら、そこでやめれば自分の抵抗力の問題として、体のほうでやっつけられる可能性は大きくなる。そのやめどき、というのを判定するのがむずかしい。 ■日本の医療の悪口を言うなら…… 入江 ・諦めない、ほがらか、前向きで、仕事や趣味がはっきりある人が、がんに対しても強い人だと思います。 柳原 ・人間の免疫力は心の問題と密接な関係にあると考えてもいいんでしょうか? がんの進行にストレス因子は強く働いて入る考えていいんでしょうか? 入江 ・非常に深い関係があると思います。 ・よく笑う人にはリンパ球のキラー細胞が多い。それからストレスが多くなるとキラー細胞数値が下がる。 宗教なき時代のがん医療 森岡正博 大阪府立大総合化学部教授 ■死生学とは何か 柳原 ・がんの生還者は、がんという不治の病を得て、それまでにはない充実というか、逆に安定と安らぎを得たという感覚を語る人がとても多かった。 ・つまり死を具体的なものとして実感することが、考え方、気分、生き方を非常にさわやかなものにするべく働いた。 ・そして、そういう人たちの多くが、自分なりの闘病方法、きわめて独自で具体的な闘病プログラムを持っていました。 ・逆に医療にすべてを委ねて、という患者さんはなかなかそういう境地になっていけない。 森岡 ・現代文明のシステムというのはすべて、最後に死がある、ということから目をそらしながらつじつまをうまく合わせて快楽だけを供給している。快楽というのはそれを重ねていくときに必ず搾取が起きるわけです。これが大きな問題なんです。 ・自分が自分自身に起きる事実を見ないようにするために、我々人間というのは人を利用するんですね。利用するとによって、力の弱い者が犠牲になっている。 柳原 ・ある種の宗教も、医療も、健康食品も皆、そういう側面がありますね。 ■ホスピスと宗教 柳原 ・ホスピスというのは、死の現場をより安らかに、という思想で誕生したと聞いています。しかし、逆にホスピスの誕生が皮肉にも、病院のがん病棟からなにか大切なものを抜き去る結果にもなってしまった。 ・現実的には、患者は医療に見放されて初めてホスピスに行きます。 ・多くの患者は、本音で言うならばやはりどんなにひどい状態になってもホスピスを選択したくありません。 ・死にゆく自分を容認したようで、もう治る希望がないとみずからギブアップしたようで、患者の家族にしても同じでしょう。 ・ある医師は言いました。現在行われている末期の延命治療は家族の納得のためであって、患者本人のためとは言いがたい、と。 ・国立大学の付属病院などでは、末期患者に対しても信じられないほど病院中心に医療プログラムができあがっている。患者は管理される対象でしかありません。 ・ホスピスという具体的な現場に移ることで、死が敗北ではない世界に移った、ということ……。 ・ホスピスでは、痛みの除去と人間としての対話、最後の時間になるかもしれない日々の過ごし方への自由と尊厳の確保に、ものすごいエネルギーが投入されています。でも、どうしてそうしたエネルギーが一般病院、がん病棟には注がれていないのか。 ・病院もまたホスピスでなければならない、と思うんです。 ・がんを治すための暮らし、免疫値をあげよう、という暮らしは宗教の修行が似ている。 ・チベットでも末期患者に断食をさせるか、巡礼に出ろという。もちろん、亡くなる人も多いわけですが、そうすることで生き返る人もいる。窮極の生は死と隣接していた……。亡くなるにしても、ある種の安息のなかで息をひきとることができる、、という装置になっている。 ・先端医療現場に働く人々は極端に言うならば生しか見ない。 ・死の瞬間を看取るという時間が医療現場から除外されてゆくわけです。 ・ホスピスが完成されてゆくということは、医療現場が死を想定しない、生の幻想だけを背負った苛酷な世界になってゆきかねません。 森岡 ・老いと終末期の医療というものを組み込んだ一つの医療に再編成するしかない。 ・老いと終末期を医療現場から切り離すのではなくして、医療全体を人間の人生全体として再編成する。 ■医学はほんとうに科学か? 森岡 ・現代医療というのは病人を見ずに病気だけを見ている。 ・全体を見ることなく、臓器だけを見ている。がんならばがん細胞を見ているけれども、全体を見ていない。 柳原 ・そもそもトータルに人間の存在を見てゆくという東洋医学や自然療法、原因をさぐるというサイコオンコロジーに、現代医療だけでは治らないと直感したがん患者が寄り添っていくのは、その反動とも言えるかもしれません。 ・薬漬けにすることで医療がもうかる。終末期の医療で莫大な金額が動きますからね。 ・ただ入院させて痛み止めだけを処方するような治療では、人間関係や問診などに保険点数がつかない現在の制度では医療機関が厳しい経営を迫られるんです。 ・終末期の医療をやらなければ採算がとれないようになっています。 ・尊厳死論争を云々するよりも、まずは終末期の医療コストとその有効性について、徹底的に検証してみる必要があるかもしれません。 森岡 ・今でその人がどういう人生を生きてきたのか、ということが死のときに現れるんです。 第三部 再生――私とがん 柳原和子 ・リンパ球療法 ― 若い青少年のリンパ球を体内に入れることで異物に対する抵抗力をあげる、免疫値をあげる、と言われている療法。 ・抗がん剤を受ける、と決めたら、次は抗がん剤に耐える体力作りとほかの臓器の強化、体質改善を同時にやっていかなければいけない。 ・心の薬が大事なのだ。 ◎佐藤博『癌の生態学』 ・腫瘤が大きくなると、からだ(宿主)の栄養が奪われる。からだが弱ると癌を異物として見分けてその増殖をおさえる免疫監視機構の勢力も衰えてくる。 ・この状態の宿主に抗癌剤の投与を行えば(一部に効いたとしても)抗癌剤そのものが宿主にとって毒であるために、免疫監視機構にとり好ましい状態ではなくなる。このためさらに監視の勢いが落ちる。 ・薬の投与量をふやせば、毒性のためからだは衰弱し、監視機構は無にひとしくなる。このような状態では、癌の危険ばかりでなく、外界に無数に存在している細菌までが、宿主体内に侵入する危険性がふえてくる。 ・癌の治療では、根本的には癌細胞に焦点をあわせ、この除去につとめなければならないが、これだけでは癌はなおらない。 ・癌細胞におかされた占拠された部分と、それによって疲弊したからだを補強し、総合的に集約的に癌をからだから追放してからだ側の姿勢(機構)をたださない限り、癌は再発し、あるいはまた別の新しい癌が発生する恐れがある。 ―― 完 ―― |