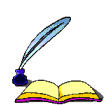
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2023年11月24日 金曜日 】
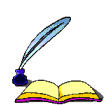
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
16 |
22.06 |
江戸時代を考える 徳川三百年の遺産  |
辻 達也 |
中公新書 |
◎ |
一 「日本的」文化の形成 禅宗文化と日常生活 ・建物の入口を意味する日本語は「玄関」である。玄関とは本来「玄妙の世界に入る関門」、つまり仏教界への入り口、端緒の意味であるが、建築物としては禅宗寺院の入り口を指す語として日本に伝わって来た。 ・中世の貴族・上層武家の異国趣味をそそる場所の入り口が玄関であった。 ・それが今日では住居一般の入り口として、他に置き替えるべき言葉が見出せぬほど、日本人の生活の中に定着してしまっている。 ・玄関にかぎらず、禅宗寺院の建築様式は今日の日本の住宅建築の中に融け込んでいる。 ・日本家屋といえば、床の間・付け書院・違い棚・唐紙障子・明り障子・欄間・縁側などを備えた座敷に代表されるが、これは禅宗建築にともなって入って来た書院造りである。それが近世初期、安土桃山時代に宮殿建築に採り入れられた。 日本の文化的自立 ・朱子学が幕府の官学つまり近世儒学の正統として定着する寛文年間(1661~1673年)とほぼ同じころ、それを批判する古学が勃興したのである。 ・この古学派の学説は、日本儒学史上において、はじめて日本人自身によって樹立された独自の学説である。 ・さらに古学派の勃興は、単に外来思想たる朱子学を批判克服したにとどまらず、はじめて日本の思想家が仏教思想の影響からも離脱したことを意味する。 ・古学派の出現によってはじめて儒仏は分離したのである。 ・日本人が独自に樹立した学説によって、朱子学および仏教という外来思想から離脱したことは、日本文化史上注目すべき事実である。 ・かつて「日本的」思想家の代表的人物として国粋主義者などから崇敬されたのは山崎闇斎(一六一八 ― 八二)である。 ・彼は日本においては自分の国を「中国」とよぶべきだと主張し、また孔子・孟子が軍隊を率いて攻めて来たら、孔孟の道を学ぶ者としてどうするかと弟子に問うたところ、だれも返答に窮したのに対し、断然これと戦って孔孟を捕虜にして国恩に報ずるのが孔孟の道であると教えたという。こういう逸話・言動が後世評価をうけたのである。 ・山鹿素行も『中朝事実』を著し、日本を「中華文明之地」あるいは「中国」とよんでいる。 ・こういうところがやがて万邦無比なと゜という独善的な日本中心主義の歴史観を生育させてゆく芽になるのであるが、この時点では大きな中華文化の傘下から自立しようとする現象の一つと理解すべきであろう。 ・「中国」という表現とともに、あるいはそれ以上にしばしば日本を「神国」と称することが多くなるのも近世に入ってからである。 ・近世においては中華対立の儒、インドの仏に対する日本固有の信教としての神道を奉ずる国という意味で用いられている語であり、日本の自立意識の表徴と考えてよかろう。 ・豊臣秀吉・徳川家康がキリシタン禁制・伴天連追放を命じた文章にいずれも「日本は神国」と表現しているのも、日本が独り神聖不可侵の国であると主張しているのではなく、異教国に対し、信教の相違による日本の自立性を意識した表現である。 ・神道が日本の風土と結びついた固有の信教であるとともに、その道徳精神は他の地域(ただし、唐天竺を併せた三国世界の域内であるが)固有の道徳、とくに儒道と一致するという考え方が儒家神道として成立したのも近世初期である。 ・古代の日本の神祇信仰は素朴な民俗信仰であるが、これが渡来した仏教の影響を受け、とくに平安時代に入って密教と結びついてはじめて宗教的体系をもち、両部神道となった。 ・やがて鎌倉時代のころになると、神道家の中に仏教から独立しようという動きが起り、唯一神道が唱えられたが、もともと神祇信仰は単純なものなので、これを体系化するため仏教に代って儒教に接近していった。 ・こうして儒家神道が起り、江戸時代初期に林羅山・熊沢蕃山など儒者の神道説が輩出し、十七世紀後期の山崎闇斎の垂加神道、吉川惟足(一六一六 ― 九四)の吉川神道にいたって完成した。 ・その教説は日本の神話を儒教道徳的見地から解釈するもので、たとえば伊勢大神宮と春日大明神と八幡大菩薩は、仁・智・勇の三徳を表現するものだというような説である。 ・つまり日本の神話を普遍的な世界に引き入れたというべきである。換言すれば日本には神代の時代から普遍的な道徳がそなわっていたという主張である。 ・「日本的」儒学としては古学派をこれにあてるのが適切で、また思想的にはともかく、折衷考証学も「日本的」儒学に加えるべきであろう。 ・これに対し儒家神道は儒学の「日本化」ではなく、むしろ逆に日本神話を普遍的世界に引き出してしまった。 ・しかしそれは大きな中華文化圏の一隅にある日本を、なんとか文化的に自立させ、唐天竺という巨大文明にあたかも日本文化が対等の立場にあるかのごとく懸命に主張しようとする当時の日本の知識人の意識の表れといえよう。 ・近世中期において、近世以前に成立した日本の古典的文化をあらためてひろい階層に普及定着し、異国趣味としてもたらされた外来文化も「日本的」性格を帯び、そこに近世社会が生み出した新しい文化も加わって、いわゆる「日本的」文化が成立した。 ・これらの動きは単なる文化の復古ではなく、近世における新しい文化の潮流と理解すべきである。 ・そうしてそれは日本が文化的に中華大陸文化の傘下から独立しようという自己主張であった。 鎖国について ・近世の鎖国と相対比して考えるべき事象として、寛平六年(八九四)、菅原道真の献言による遣唐使の廃止があげられる。 ・こののち日本は、奈良・平安初期と盛んに摂取した大陸文化を同化して、いわゆる国風文化を成立させた。 ・近世の鎖国について私なりの見解は、結論からいうと、江戸幕府の鎖国政策、とくにその実施に関して、後世の論評はその意義や功罪の点で、あまりにこれに不当な重荷を負わせすぎていると考える。 ・たとえば現今における日本人の国際性の欠如まで近世の鎖国の後遺症であるかのごとき意見を耳にしたこともあるが、日本人の島国根性は単に鎖国のなせるものとは認められない。 ・寛永の鎖国は寛永十三年(一六三六)の日本人海外渡航禁止と同十六年のポルトガル船来航禁止を大きな二本の柱とするが、幕府はこれらの政策をなにか積極的な意図のもとにあえて行なったとは認められない。むしろ受身の行動であったように思える。 ・鎖国の理由について、江戸時代にもっぱらこれをキリシタン禁圧から説明しているが、近代に入ると経済上の問題から解明しようという動向が主流である。 ・鎖国体制というのは、より進展しようとしている海外交流を幕府があえて無理に遮断した孤立政策ではなかった。鎖国の一面は幕府の手の及ばない外国間の勢力争いの結果である。 ・もう一つの面は日本人の海外渡航禁止であって、これは幕府の責任に帰するが、これとてもその基底には、当然急速に衰えてゆくべき近世初期の海外貿易の状況があり、それゆえにキリシタンの脅威が前面に強く出た結果である。 ・鎖国が文字通りあえて国を鎖すという意味で論ぜられるようになったのは、近世後期、ほぼ十九世紀に入ってからのことである。 ・鎖国下といっても決して文化交流の面で孤立していたわけではない。 ・明末から清にかけての中国文化はかなり日本に影響を及ぼしている。 ・鎖国とはいっても、文化的情報はかなり豊富に入って来ており、また日本の知識人はそれに鋭敏に反応した。 ・つまり「日本的」文化の形成は、そういう刺激をうけつつ行なわれたのであって、世界から隔絶・孤立の中に熟成されたものとはいえないのである。 二 新しい国家の成長と展開 公儀の成立 ・現在では一般に江戸幕府とか徳川将軍などとよんでいるが、当時は幕府は公儀、将軍は公方様とよぶのが普通であった。 ・近世の公儀の力を如実に示すものとしては、たとえば改易転封があげられる。 ・戦争によることなくして封建領主から領地を没収し、あるいは領主を他所に移すことができる力、それは中世の武家政権には考えられないものであり、ヨーロッパの国王と封建諸侯との間にもなかったものである。 ・豊臣秀吉のいわゆる太閤検地に始まる近世初頭の検地によって、公儀は全国の土地の実態を把握し、諸大名をあらためて配置した。 ・全国の土地の最終的領有権は公儀にあり、諸大名の領地との結びつきはそれだけ弱かった。それゆえ江戸幕府が倒れて、明治維新後ほどなく廃藩置県が抵抗なく実施しえたのである。 ・検地の結果は石高、つまりその土地の生産力を米穀生産量として表示した。これは領主が現物納として農民から徴収する年貢の基礎をなした。 ・また俸禄制と軍役制、つまり幕府と大名・旗本の、また大名とその家臣の封建的主従関係の基礎をなした。 ・石高制と深くかかわっているのが軍役制である。制度としては三代将軍家光の寛永十年(一六三三)に完成した。 ・それぞれの俸禄の高に応じて軍備を課せられたのである。 ・江戸時代には、中央政府としての幕府が直接もっている常備軍は比較的少なく、主として諸大名の軍役に期待し、幕府はその統帥権をもっていたのである。 ・軍役は鎌倉時代の御家人役に淵源する。 ・鎌倉将軍家から所領を給与または安堵された武士は、その御恩に対する奉公として一年ずつ交替で大番役(京都の警護役、のちには鎌倉も加わる)を務めなければならなかった。また戦時には動員をうけた。「いざ鎌倉」である。 ・こういう封建的主従関係の表徴が制度化されたのが近世の軍役制である。したがって近世にあっては軍役制と俸禄制、さらにその基礎にある石高制は一体不可分の制度であった。これらの制度は明治五年(一八七二)の地券交付、徴兵令、続いて石高制廃止から秩禄処分にいたる一連の施策まで存続した。 ・軍役は中世に起源をもつとはいっても、近世のそれははるかに強制的である。 ・公儀の統帥権は単に徳川将軍家の家政機関の内にかぎられた権限ではなく、日本全土に徹底した権力であった ・江戸幕府に対し諸大名が負っていた大きな義務として参勤交代がある。 ・これについては俗に、幕府が諸大名の経済力を弱めるため強制した策略だという見方が依然としてある。 ・たしかに諸大名の江戸生活は、かなりそれぞれの藩財政にとって負担になっていたことは事実である。 ・しかしそれは結果であって、幕府の目的がそこにあったというのは曲解である。 ・参勤交代は軍役発動の一形態である。 ・幕府の直接にぎる常備軍は少なかった。そこで、つねに大名を半数ずつ江戸に駐在させて、首都防衛に当らせたのである。 ・同様に幕府が種々の土木工事を諸大名に負担させたのも、大名の経済力削減を目的としたという俗説がある。しかし普請役も軍役の一種である。 ・戦国末期以降の戦争はもはや勇将の一騎討ちではない。城を築き、道を造り、坑を掘るなど、さまざまな普請土木工事も重要な戦争行為であった。それが平時においては都市建設その他に動員されたのである。 ・鎌倉幕府は朝廷の光を背負って自己の足場を固めていった。そうして私的支配の伸長にともなって公権力は退化衰弱していった。 ・江戸幕府は極力朝廷を形式的・装飾的地位に抑え、自己を公儀=公権力として成長させていったのである。 家政から国政へ ・身分というと通例士農工商の四身分というが、これは儒者などが唱え出した区分で、武士・百姓・町人の三身分である。 ・これは近世初頭の検地・刀駆りあるいは城下町の建設などの諸政策で、兵農分離・商農分離が行なわれ、それぞれの身分が成立した。 ・江戸幕府政権がはなはだ長期にわたって存続しえたのも、またみずから脱皮して明治政府へと発展しえなかったのも、この身分制と深くかかわりがある。 タテ社会への抵抗の挫折 ・日本社会の構造の特色は人間関係の縦の結びつきが強いところにあるといわれる。 ・身分制はまさに人間を上下尊卑、縦の系列に位置づける制度であるから、もっとも明瞭に日本社会の特色を表現しているといえよう。 ・しかしその特色が日本の歴史の上につねに貫徹していたものでもない。横の人間関係が社会的に意味をもっていたときもあった。 ・「武士は相見互」という言葉があるが、それは社会の支配階級という立場からではなく、公儀の支配、つまり縦の従属環境に置かれた者同士の、横の連帯意識である。 ・近世初頭に「かぶき者」という連中が横行した。 ・日本の古典的演劇の代表である歌舞伎は、歌と舞と伎、すなわち俳優、換言すれば三味線音楽と舞踊と演技の三要素を巧みに文字で表現しているが、これは当て字である。 ・近世初期に「傾く」という語があり、これから「かぶきたる踊り」、ついで「かぶき踊り」となった。 ・「傾く」とは、意表に出る、常軌をはずれる、自由放縦な行動をとるというような意味である。 ・「かぶき踊り」の創始者出雲の阿国の踊りが人々の常識を破った新しいものだったので、この名がついたという。 ・「かぶき者」も同様、常軌を逸した風俗・行動によって名づけられたもので、現代でも太陽族とかヒッピーなどが流行したのと類似している。 ・彼らは集団を組み、市街を横行し、しばしば他の集団と喧嘩をした。 ・しかし仲間の結合は固く、援助を求めて来る者は、打算を離れて仲間としてこれを庇護した。 ・衆道(男色)は戦国期から近世初頭の流行の習俗であったが、「かぶき者」の間にあっては、男子の同志的結合の盟約でもあったという。 ・「かぶき者」の主たる階層は、若党・中間・小者と呼ばれる下級の武家奉公人と浪人とであった。 ・彼らの出身地は中世末・近世初頭の農村であったと推定されている。 ・兵農分離の進行する中で、武士にもなりえず、百姓としても落ち着くことのできない人たちが、農村をはじき出されて都市に集まり、生活の手段として武家奉公をする。そうして新しい身分制社会の形成の動きに対し、仲間を組んで抵抗しつつ、頽廃の道を歩んでいった姿といえよう。 ・十七世紀も後半に入り、近世社会が確立して来ると、そこに出現したのが旗本奴と町奴である。 ・奴とは武家の下級奉公人のことであるが、その家に代々住みついて子供のときから一生仕える譜代奉公人が禁止されたので、年季奉公人となり、その年季も短くなって、期間が一年とか半年という、いわゆる一季半季の出替わり奉公人に変わっていった。 ・農村から都市へ流れ込んだ人たちは、親戚・知人などの身元保証人のない場合、人宿、あるいは口入と呼ばれる者を頼って奉公先を世話してもらった。 ・彼らは人宿の出居衆・寄子などと称された。この社会に「かぶき者」の風俗が継承された。 ・人宿の主人が親分で、出居衆が子分となり、町奴の組が結成された。 ・町奴の代表というべき幡随院長兵衛は口入の主人だったと推定されている。 ・これに対し旗本奴は、中下級の旗本や御家人、その二、三男などいわゆる部屋住の冷飯食や浪人などであった。 ・これらの無頼の武士や奉公人などが集団を結成し、喧嘩・博奕で市街を騒がせたが、その舞台はもっぱら新吉原の遊郭にかぎられるようになった。 行政官僚の役割 ・近代日本の政治にきわめてその存在の大きい官僚の系譜を遡及すれば、まず寛政改革以降の官学の役割、さらに遡って享保改革に結実した人材登用政策、そうして十七世紀前半に定型を成した近世初頭の官僚群にまで到達するのである。 近世社会の盲点 ・本多正信の著と伝えられている『本佐録』に、「百姓は財の余らぬように、不足なき様に治る事道なり」という言葉がある。 ・また享保改革のとき活躍した勘定奉行 ・ともに幕府の農民収奪がいかに過酷であったかを如実に示す言葉として、しばしば引用されるところであるが、両者をくらべてみて、とくに「胡麻の油」云々の方がいかにも残酷な収税吏の姿を連想させる。 ・ところがこの両者は歴史の発展の異なった段階を示している。 ・『本佐録』は、秋の収穫に対し、まず翌年一年分の種籾その他耕作に必要な経費のための米と食料を取り除いて、その残りを全部年貢として収納せよという。 ・いいかえれば単純再生産に必要な物は農民の手に残しておけと説いているのである。 ・ともすると収奪が再生産に必要な部分にまで食い込むことも戒めている言葉である。それが「財の財の余らぬ様に、不足なき様に」と表現されているのである。 ・これは近世初期の領主に、全余剰部分を収奪しうる力があることが前提となっている。 ・これに対し「胡麻の油」の方は、いくらでも絞れば出るということは、逆にいくら絞ってもなお領主側が余剰部分を取りきれぬ状態になっていることを物語るものである。 ・それだけ領主側の徴租力が相対的に低下してきたことを示している。 ・『本佐録』の著された近世初期と、神尾若狭守の活躍した享保期とでは約一世紀の差がある。この間、生産力の発達も格段の相違をみせている。しかしその生産力の発達は必ずしも領主財政の発展とは結びつかなかった。 ・むしろそれは十七世紀後期から顕著になった幕府・諸藩の窮乏の根本的原因となっている。「胡麻の油」云々の言葉の中にその理由の一端をうかがいうるのである。 ・つまり江戸幕府の権力は社会の末端まで貫徹し、民衆の生活に厳しい干渉と束縛とを加えていたというのが近世史についての一つの通念であろうが、そこに存外大きな盲点があった。生産力の発達は主としてその盲点をついて進展していったのである。 「私」の世界の成長 ・幕藩領主権力が石高制によって把握することができた産業経済界が公的な世界であったのに対し、その盲点から成長していった世界は私的な世界であった。 ・公的世界では商行為を賤視し、利益追求を悪とするのに対し、私的世界ではそれを積極的に肯定する意識が生れた。 ・心学道話をおこした石田梅岩は、商人の利益追求の道を士道と対等においた。 ・海保青陵(一七五五 ― 一八一七)にいたっては、社会関係をすべて商行為で説明した。 ・君臣が売買の関係なら、領主と人民は貸借関係である。 ・犯罪と刑罰も取引関係として考えている。 ・営利行為の正当性を主張する背後には、人間の感情・欲望を承認し肯定する思想の成長がある。 ・近世初期以来、正統派教学の地位を占めている朱子学では、「私」の存在は認められない。 ・個人道徳は家族道徳につながり、やがて政治的規範へとつらなる。 ・格物にはじまり、修身・斉家・治国・平天下にいたる『大学』の八条目がそれである。 ・つまり個人も家庭もまったく公的な規範に律せられている。「私」=「情」=「人欲」は悪であり、抑止・滅法せられるべきものであった。 ・ところが時代が元禄期に入って来ると、朱子学派の中にも、貝原益軒(一六三〇 ― 一七一四)のように、求利という人間の情欲を是認しているのである。 ・古学派においては、いっそう明瞭に「情」=「欲」=「私」に対し寛容な態度を表明している。 ・山鹿素行、伊藤仁斎、荻生徂徠、本居宣長然り。 ・宣長にとっては、人間のまことの心を有のままに表現することにもっとも価値をおいているのである。 ・人間の真情を発露しうるのは、政治や社会とは別の世界、つまり個人の心の中にかぎらけねばならなかったのである。 ・山鹿素行にしても伊藤仁斎にしても、人間の情欲の存在を当然のことと認めつつも、聖人の道はこれを節制することにありと説いている。 ・荻生徂徠はこれを政治の外の世界としつつも、聖人の道は人情をよくわきまえ知り、人情に基づきつつ、しかし人情に流されることなく制度を立てることが重要だと論じている。 ・いずれも支配者側、つまり公的世界の立場から、私の世界をいかに制御するかを説くものである。 ・現実においても近世社会は公的な人間・社会関係によって、人間の真情の発露、つまり私的な世界が強く制約されていた。 ・そこに近松門左衛門の戯曲をはじめ、「義理と人情との葛藤」を主題とするいくたの文芸作品が生れ、観衆の涙を誘ったのである。 ・公私二つの世界がふれ合うときは、必ず公的世界が優先した。しかしそうでなければ二つの世界は互いに関与することなく並行した。 ・たとえば商行為にしても、政治に関係する問題が生ぜぬかぎり、公権力はそこに立ち入らなかった。 ・享保四年(一七一九)、幕府が「金銀相対済令」を発して、今後借金銀の訴訟は受理せず、当事者間で解決せよと令したのも、その根底には商取引は私的行為で、公権の関知するところではないという観念があったからである。 三 「近代化」日本の基盤の形成 農民観の修正 ・近世日本文化の特色が庶民文化にある。 ・近世日本では、規模はそれなりに小さいが、三都の町人の文化や諸国の地主・豪農層の文化史上に演じた役割を重視しなければならない。 民衆の知識欲 ・近代日本の学校教育は前近代の寺子屋教育と質的に相異し、系譜的に断絶しているというのも一つの歴史の観点であるが、他方、十八世紀以来の日本の庶民層には、ひろく底辺から強い知的向上の欲求の力があったことを看過してはならない。 文化の商品化 ・近世日本の庶民文化発展の重要な条件として、文化が民衆の手にとどくところにあったこともまた見逃せぬ問題である。 ・これは貨幣経済の発達、庶民の経済的向上という社会的条件の問題でもあるが、庶民にとって文化が比較的容易に商品として購入しうる存在になったのである。 ・零細な庶民にとっては、書籍の購入は容易ではなかったろうが、貸本屋から借りれば、比較的簡単に書籍に接することができた。 ・貸本屋は庶民にとって図書館の役割を果していたと考えてよかろう。 ・書籍出版を営業として成り立たせたのも、近世文化の一特色である。 ・書籍に関連して印刷文化をみると、十七世紀後半、菱川師宣(一六一八 ― 九四)が浮世絵を民衆芸術として大成し、これを木版の絵本あるいは一枚刷として大量に印刷し、廉価に販売して民衆に大いに普及させた。 ・その後、印刷技術の進歩にともない、錦絵の出現を見、またすぐれた作者を生んだ。 ・上層の庶民の日常生活の中には、美術工芸品が入っていった。陶磁器の生産が発達し、緒方乾山(一六三三 ― 一七四三)の鳴滝窯などをはじめ、日常の食器類にもすぐれた作品が生れた。 ・家具調度類や装飾品の方面でも、漆器や金銀の蒔絵などの生産が諸国にひろがった。尾形光琳(一六五八 ― 一七一六)の作品などはその代表である。 ・彫金では幕府の御用を勤める後藤家の門下から横谷宗珉(一六五一 ― 一七三三)があらわれ、幕府の扶持を辞退し、後藤家から独立して町彫と称せられた。つまり御抱え職人として作品を彫るのではなく、作品を販売して生計を立てる生活に入ったのであるから、文化の商品化を見事に象徴する行動である。 ・文化が権力者や一部の特権的豪商の社会でのみ享受されるものでなく、ひろい底辺をもつ民衆に滲透定着した文化となっって来たところに近世、十七世紀後半以降の文化の特色がある。 ・浮世絵版画にせよ、庶民の日常生活における美術工芸品の進出にせよ、何れも「日本的」文化形成を示す現象である。 ・綿・絹織物の国内生産の発達は、十七世紀末以降の経済界の大きな特色である。その質もだんだん高級化し、幕府の倹約令にもかかわらず、羽二重・繻子・紗綾・天鵞絨・緞子・繻珍などの高級織物の生産技術が発達した。 ・それと並行して、友禅染など染色技術も進歩した。それに歌舞伎の影響もあって、大都市の風俗を形成していった。 ・延宝元年(一六七三)三井高利(一六二二 ― 九四)が江戸に開いた越後屋呉服店で「現銀安売掛値なし」の商法を初め、これが大いに江戸市民の評判となり、この商法をまねる店が相次いだ。 ・商品生産や製造技術の進歩発達にともなって、新しい商人の進出も都市風俗を大きく変えていったのである。 ・浄瑠璃や歌舞伎その他演劇・音楽など芸能関係の発達が、近世とくに十七世紀末期、いわゆる元禄時代以降著しかった。 ・これも劇場に大衆を集めての興業が商業的になりたったことによってもたらされたものである。ここにも「日本的」文化と商行為の深い結びつきを指摘することができる。 知的市民社会 ・渡部崋山(一七九三 ― 一八四一)を中心として結成された「蛮社」とは「蛮学社中」の約語、つまり西洋学研究の意味である。 ・天保八年(一八三七)、漂流民送還のため浦賀へ来たアメリカ船モリソン号を、異国船打払令(文政八年=一八二五発令)に基づいて浦賀奉行が砲撃して追い返したことについて崋山らがこれを批判したため、幕府に弾圧された一件(蛮社の獄、天保一〇年=一八三九)で有名である。 外来文化の受容 ・鎖国下においても、日本は決して文化的に孤立した状態でなかった。 ・とくに中華大陸からは、仏教では黄檗宗の渡来をはじめ、禅宗界の刷新に多大の影響があり、禅の「日本化」をもたらした。 ・儒教では水戸学や考証学派の形成に深く関係し、荻生徂徠も明の著書にふれて古文辞学への眼を開いた。 ・絵画においては写生画・文人画の発生に強く影響している。 ・とくに科学技術については、蘭学に先立って、その方面の学問的基盤を造成していることを看過してはならない。 ・わが国に影響をおよぼしたといえる輸入漢籍は『農政全書』である。編者の徐光啓(一五六二 ― 一六三三)は明末の宰相である。 ・『農政全書』は元禄ごろには日本に渡っていた。宮崎安貞(一六二三 ― 九七)の『農業全書』(元禄十年‹一六九七›刊)はこれから強い影響をうけている。 ・元禄期の経済的発展は農業技術の改良に負うところ多大であり、当時、農業技術書が多数著されたことはそれと深くかかわっている。 ・『農業全書』は元禄期の農学書の代表というべき本である。 ・十七世紀末から十八世紀初めにかけての日本の産業経済に大いに貢献した本といってよかろう。 ・輸入漢籍は横文字の本に先立って、日本人の中に科学技術に関する基礎を築いた。 ・鎖国下の外来文化を考える場合、漢籍の役割を無視することはできない。日本近代化への貢献はおおきかったのである。 新しい格物窮理 ・山片蟠桃はなかなか合理主義的思考の持主である。 ・たとえば『夢の代』巻三では「神代」を論じて「日本紀神代ノ巻ハ取ルベカラズ、願クハ神武巳後トテモ大抵ニ見テ、十四五代ヨリヲ取用ユベシ、然リト雖、神功皇后ノ三韓退治ハ妄説多シ、応神ヨリハ確実トスベシ」と鋭い文献批判を日本の神話・古代史にあびせている。 ・『夢の代』の完成は文政三年(一八二〇)であるが、執筆開始は享和二年(一八〇二)である。 ・すでにこのころ彼がかかる批判を考えていたとすれば、近代日本人が歴史教育においてかかる古代史文献批判に接する自由を得るようになったときより、実に一世紀半も前のことであり、津田左右吉博士の学説発表よりも百年あまり先行していることになる。 ・儒教には一種の合理主義的思考がある。 ・新井白石も、「神は人なり」という命題の下に日本の神話を割り切って、古代史を考えている。 ・その合理主義と西欧近代の合理主義とは、成立の根源や過程を異にしているのであるが、近世の日本知識人の多くは、さして苦しまずに近代的合理主義を儒教的教養の上に受け容れたのである。 むすび ・東洋の道徳、あるいは仁義忠孝つまり儒教思想と欧米の科学技術思想とが、それほど簡単に折衷融合しうるのであろうか。 ・ともかく同じ儒教文化圏といわれながら、日本はいち早く近代化=西欧化の型をもった。 ・儒教の本家である中華大陸と、その影響を大きくうけた朝鮮半島と日本、それぞれの地域における欧米近代文明との接触と、それに対する反応の相違、それをもたらした要因の一つには、それぞれの地域における儒教文化の果した区割り、あるいはその性格の相違が考えられねばならない。 ・戴国煇氏は、日本は「儒家思想の読みかえによる『和魂洋才』で維新を成功させたのに比して、中国は読みかえの条件がなく、したがって読みかえがきかず、『中体西用』論は機能できないまま維新もまた挫折してしまった」と論じている。 ・日本においては儒学が大衆に滲透してゆく過程で、変質というべきか、あるいは日本独自の性格というべきか、とにかく中国のそれとはかなり違った理解をされるようになっていった。 ・そういう日本の独自性をもった背景として、私は第一に、近世という時代が、近代につながる統一国家権力の形成期であったこと、それは同時に中華文明の大きな傘下から独立する時期であったことを指摘したい。 ・そうしてその新しい統一国家の中で、日本の伝統文化も外来の異国文化もひろい民衆層の中に滲透し定着して、あたかもこの風土に土着しているかのような「日本的」文化を形成した。 ・その視覚をかえると、下層のはなはだひろい底辺にいたるまで、智識教養に対する民衆の強い意欲が沸き起り、その上に封建的身分階層をこえた知的市民層が形成されていった。 ・日本近世の文化は決して王侯貴族の主導・保護によるものではなく、また単に都市豪商の文化でもなかった。庶民層における底辺のひろがりを無視しては本当の理解にはいたらぬのである。 ・「和魂洋才」は一朝一夕のものではなく、十七世紀後半、朱子学が正統派の地位を確立するころから、すでに朱子学にあわせて漢唐の訓詁学を採るという折衷主義が現れ、やがてこれが主流を占め、観念的な道徳哲学の論議よりは、経験的・実証的学問の風潮がたかまっていった。 ・ここにおいてはじめて、彼の長を採り我が短を補う、東洋道徳・西洋芸術、表裏兼該も可能だったのである。 ―― 完 ―― |