
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2022年08月29日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
25 |
22.08 |
報道災害【原発編】 事実を伝えないメディアの大罪 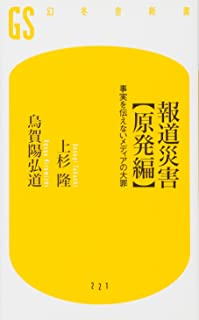 |
上杉 隆 烏賀陽弘道 |
幻冬舎新書 |
◎ |
第二章 日本に民主主義はなかった 第二節 自由報道協会の意味 ぎりぎりだった設立 上杉 ・自由報道協会というのは世界標準の記者会見をやろうとしている非営利団体です。 ・フリーであろうが大手メディアであろうがインターネットメディアであろうが海外メディアであろうが会見に出られる。つまりアクセス権を平等に認めて、権力側と丁々発止できる場を作ろうというものです。 烏賀陽 ・日本では記者クラブが壁になってフリーの記者は記者会見にも入れなかった。 ポイント・オブ・ノーリターン 烏賀陽 ・日本の民主主義は、情報公開ひとつをとってみても、ものすごく遅れている。日本の政府がこんなに非民主主義的な政府だとは思っていなかった。 ・記者クラブ系マスコミってこんなに不能だとは誰も思っていなかった。 ・あいつらただの統治機構の一端でしかないじゃないか、と明らかにしてしまった。 第三節 ソーシャルメディアを可能にするもの、不可能にするもの コンセンサスは必要ない 烏賀陽 ・日本のソーシャルメディアを見ていて感じるのは、何かみんな「最後はコンセンサスをつくらなくてはならない」と思い込んでいるような気がすることです。 ・アメリカ人とフェイスブックをやっていても、誰もコンセンサスなんか考えていない。バラバラのごちゃごちゃ。 上杉 ・むしろコンセンサスをつくろうとすると「オレとお前は違うぞ!」となる。 烏賀陽 ・「違う」ことを認めるということは、「コンセンサスに近づかない」ということです。日本人は他人が自分と違ううとイライラするようだ。 第三章 アメリカジャーナリズム報告2011 第一節 アメリカのジャーナリズムは劣化したか プリントジャーナリズムからネットジャーナリズムへ 上杉 ・日本のメディアや日本人は嘘には寛容だけどミスにはとても厳しい。逆に海外、特に米国は、ミスには意外と寛容ですが、嘘に対してはものすごく厳しいんですよね。嘘をついたら一発で終わりですから。 烏賀陽 ・人間だから間違いはする。最大限努力しても避けることはできない。けれど、意図的な嘘は許さない。 第二節 日米メディアリテラシー比較 ジャーナリストの定義が違う 上杉 ・海外ではメディアが潰れていくけれど、日本ではメディアがひとつも潰れない。 ・テレビも新聞も、戦後、ほとんど新規参入がない。 ・メディアは原子炉の格納容器のように健全性が保たれ続けている。そして、その格納容器の中にはジャーナリストがひとりもいない空っぽな状態だったんです。 ディベート教育が必要 烏賀陽 ・アメリカの高等教育は、先生の言うことにいかに反駁できたかで点数が上がっていく。日本の大学教育は先生の言うことを忠実になぞったかどうかで点数が上がっていく。 多様な価値観を認めるか否か 上杉 ・海外のジャーナリズムには多様な価値観を認めるというのが前提にあります。 ・今の原発報道災害について、海外だとマーティン・ファクラー東京支局長も書いてますが、日本ではメディアが相当の嘘をついていると。 ・「現場には入らずに書いている」と。やっぱり海外から見ると現場に行かない記者、会見にも行かない、現地にも行かない、そういうところに行かないという記者が発言をすること自体に非常に違和感があるわけです。 ・テレビのコメンテーターとか、あるいは記者が専門家のようにコメントすることに対して、日本はタレントがコメントしていますからね。 烏賀陽 ・現場に行かない記者には本来は発言権がないのに。 上杉 ・どこにも行かない、スタジオだけにいる人間が発言して、それが影響力を持っている。 ・アメリカだったら、キャスターっていう椅子に俳優が座るとかタレントがなるなんてことはあり得ないんですよ。もちろん俳優のほうも、もしキャスターをやれと言われたとしても断りますよね。 ・ファクラーは日本の言論界に民主主義がないっていう言い方もしていました。民主主義国家なのに書いてあることに多様性がないと書いていた。民主主義の根幹である多様性がなくなるというのは危険なことです。 メディアは「公共の場所」である 烏賀陽 ・ニューヨーク・タイムズには、「新聞は多様な社会の意見交換の場であるべきだ」という考えがある。 ・「新聞=パブリック・フォーラム」という考え方なんですよ。だから「社論」ではないんです。 ・ニューヨーク・タイムズが人格として何かを考えたり価値を決めて読者に一方的に説いているのではなくて、そこにいる記者や発言者たちがいろんなことを言う。ニューヨーク・タイムズはそのための「言論空間」を提供するという発想です。 上杉 ・それは社会もそうですよね。 烏賀陽 ・カリフォルニア州政府を訪ねて「なるほどな」と思ったんですよ。政府の建物にちゃんとパブリック・フォーラムがある。州政府庁舎の前に会談があって、庭がある。そこはいつでも誰でも演説していいし、記者会見をしてもいい場所なんです。「それって州政府が維持しているの?」と聞いたら、そうだった。「だってここはパブリック・フォーラムだから」と州の広報担当が当たり前のこととして言う。 第四章 死に至る病 記者クラブシンドローム 第二節 王様は裸だ シュピーゲルもアルジャジーラもBBCもびっくり 烏賀陽 ・日本の記者クラブって秘密結社みたいになっている。 ・記者会見のオープン化に反対する理由って、実は言論の自由なんて高尚な問題じゃない。 上杉 ・自分たちの身を守る自己防衛本能ですね。 東電も新聞もコメディになる 烏賀陽 ・日本のマスコミっていうのは統治機構の一部なんです。 上杉 ・本当に「向こう側」なんですよね。完全に権力構造の中に入っている。それがわかると日本の報道が理解しやすいんです。 ・一番ずるいのは、権力構造の中に入って、どっぷり広報活動をしているくせに、自分たちは反権力を気取るわけです。 第五章 報道災害からいかにして身を守るか 第二節 多様性こそすべて 疑いの目を持つことは悪くない 烏賀陽 ・同じ人が発している言葉であっても、賛成することもあれば、反対することもある。疑うこともある。それが健全な言論だと思う。 ・だけど今それが属人的になっている。「言論」と「人間」が混同されている。言論っていうのはあくまでも言論で、「お前の言うことに賛成しない」と言っても、その人を否定しているわけではないんですよ。「論」を否定しているに過ぎない。 ・日本文化は言論の否定と人格の否定を区別できていない。 トップを替えれば組織は劇的に変わる 上杉 ・英国の歴史学者・政治学者シリル・ノースコート・パーキンソンが提唱した「パーキンソンの法則」 (第1法則)「仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する」 (第2法則)「支出の額は、収入の額ま達するまで膨張する」 ・これは記者クラブにぴったり当てはまる。 ・パーキンソンの凡俗法則には「組織はどうでもいい物事に対して、不釣り合いなほど重点を置く」というのもあるんです。 タダの情報には理由がある 烏賀陽 ・民放はスポンサーがいやがるものは放送できない。 上杉 ・つまり、タダの情報だから、上方としては価値がない。 烏賀陽 ・民放がなぜ原発の危険性を警告しなかったかと批判してもムダです。そんなの絶対にありえない。スポンサーを批判できないなんて当たり前だ。そもそも民放にそんなことを期待するのがヘンだ。 上杉 ・日本ではこれまで「テレビ局に期待するなよ」という議論すら起こったことがなかったから、「タダの情報には理由がある」という感覚がわからないんですよね。だから情報弱者なんです。 ―― 完 ―― |