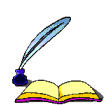
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2023年03月10日 金曜日 】
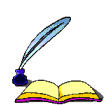
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
30 |
22.10 |
日露戦争 勝利のあとの誤算  |
黒岩比佐子 |
文春新書 |
◎ |
第一章 薄氷の勝利 小村寿太郎 vs. ウィッテ。ポーツマスの攻防 ・最後まで議論が対立したのは、「賠償金と領土割譲」の二つの条件である。 ・ウイッテはロシアのニコライ二世から、「一にぎりの土地も、一ルーブルの金も日本に与えてはいけない」と言明されていた。 ・そのため、ウイッテはポーツマスに着いたときからあたかも戦勝国の代表のように振る舞い、ロシアは講和を望んでいるわけではなく、いつでも戦争を継続する用意がある、という態度を崩さなかった。 ・ウイッテは新聞記者たちに愛想良く応対し、巧みにアメリカの世論を味方につけていく。 ・ウイッテは最初から、日本の条件が賠償金や領土割譲を要求するきびしいものであると予想して、それを強調すればロシアへの同情が集まることを察していた。 ・しかも、彼が新聞記者に流した情報によって、「日本は多額の賠償金を得るためには、戦争を続けることも辞さないらしい」と非難する報道が行われ、日本は金銭のために戦争をしているのか、という好ましくない印象を与えている。 ・新聞記者への対応も、小村とウィッテとはまったく違っていた。外国の新聞記者にコメントを求められた小村は、「われわれはポーツマスへ新聞の種をつくるために来たのではない。談判をするために来たのである」と冷たく答えた。記者は小村に馬鹿にされたように感じ、激怒したという。 ・その後も、小村は秘密主義を貫いたため、新聞にはロシアが提供した情報のみが載ることになる。 ・全権代表として誰を派遣するのかというときに、首相の桂太郎が最初に打診したのは、小村ではなく伊藤博文だった。 ・伊藤は最初、引き受けてもいいという態度を見せたが、伊藤の側近たちは猛反対した。 ・戦争に勝った栄誉は桂が握り、講和によって起こる国民の反感を引き受けるなど馬鹿げているので、止めるべきだ、というのである。 ・結局、伊藤は全権大使への就任を辞退した。 ・伊藤はずっと、ロシアと戦うことには慎重な態度をとり続けていた。まだ日本はその準備が整っていない、と判断していたからである。 ・この四年前の一九〇一年十一月に、伊藤は自らモスクワ入りして日露提携の道を探った。それが逆にイギリスを刺激することになり、翌年一月に日英同盟が結ばれる。 ・この日英同盟が、当時の日本人にとって心理的に大きな支えとなり、ロシアとの開戦を主張する対露強硬派を勢いづける結果になった。 ・世界列強のなかで、イギリスとロシアの二ヵ国を日本はもっとも恐れていた。 ・そのイギリスと対等な立場で手を握ったことを、当時の日本人が「玉の輿」とか「提灯に釣り鐘の縁組」と称して大喜びしたのも無理はなかった。 ・一九〇三年には、新聞もさかんに、ロシアへの敵愾心を煽るような記事を載せはじめる。 ・いまロシアと戦わなければ日本の将来はない、という「主戦論」が、次第に新聞の論調の主流を占めるようになる。 ・開戦には慎重な姿勢をとっていた政府も、対露外交の手段が尽きた形で、戦争の準備を進めていくことになった。 講和条件をめぐる駆け引き ・天皇は平和的解決を望み、最後に直接ニコライ二世に対して電報を送ったが、翌日になっても返事はなかった。 ・日本は開戦の瞬間から、戦争の期間を約一年に想定し、先制攻撃を行って戦況が優勢なうちに、講和に持ち込むことを考えていた。数字の上で、ロシアはすべての戦力において日本を上回っていたからである。 ・開戦以来、日本軍が連戦連勝を続けてきたのは奇跡的ともいえた。 ・一九〇五年三月の奉天会戦後、武器や弾薬の補給も途絶えてしまった日本軍は、ロシア軍に決戦を挑もうとはせず、ひたすら講和の機会をうかがっていた。 ・そして、五月の日本海海戦での圧倒的な勝利が、日本にとって絶好の講話のチャンスとなったのである。 ・すでに、日本はこの戦争に約百八万人の将兵を動員し、約二十億円の戦費を使い、約二十万人の戦死傷者を出していた。 ・満州軍総参謀長の児玉源太郎は、今後一年間戦争を続けるとすると、さらに二十五万人の兵と十五億円の戦費が必要だと予測して、その成算はなしと結論づけていた。 ・一方、ロシア軍には新たに増援部隊が加わって、日本軍を圧倒する兵力を集めつつある。 ・戦闘を継続すれば、ロシアが有利なのは明らかで、日本は勝者である間に戦争をやめて、どうしても講和を成立させねばならなかった。 ・小村寿太郎は、そうした複雑な事情をすべてのみこんだ上で、講和会議に臨んだのである。 ・だが、何も知らない国民は戦勝気分に浮かれていた。 ・新聞も同じで、七博士の代表格として知られる戸水寛人が、講和の最低条件として「樺太・カムチャツカ・沿海州全部の割譲、償金三十億円」などを挙げたことを奉じて、国民の期待感を煽っている。 ・十年前、日清戦争に勝利した日本は、台湾を領有した上に賠償金も得ていた。 ・今度は相手が大国ロシアだけに、それに見合った条件で講和が結ばれると国民の大半は信じ、巷では「三十億円」とか「五十億円」という数字が一人歩きするようになっていた。 ・このように、会議が始まる前から、政府の思惑と国民の期待とは大きく隔たっていたのである。 ・政府が予想したとおり、ウイッテの態度は強硬だった。 ・その後、「日本は賠償金を要求しない、ロシアは樺太の北緯五十度以南を割譲する」という条件で日露双方はついに合意に達した。 ・ホーツマスの街は平和を祝う人々の歓声で包まれた。祝砲が轟き、教会の鐘が鳴り響く。アメリカやヨーロッパの新聞は、日本が人道国家であることをさかんに賞賛し、日本は開戦の目的を達成した、という趣旨の記事を掲げた。 ・実際、日本はこの講和条約で、韓国における日本の優位、満州からのロシア軍の撤退などの問題を有利に解決し、樺太の南半分に加えて、大連・旅順の租借権をロシアから譲り受け、長春から旅順までの東清鉄道南満州支線なども譲渡されている。 ・小村は粘り強い交渉によって、政府が期待していた以上のものを獲得したといえる。 ・こうして九月一日には休戦条約が結ばれ、あとは五日の「講和条約」調印さえ終われば、日本とロシアの間には平和が戻ることになった。 新聞の取材競争と講和反対キャンペーン ・講和会議の形勢が日本に不利になりはじめてから、政府が外電を片端から押さえてしまった。 ・そうした政府の秘密主義への不満があった上に、成立したと伝えられた講和の内容は、とても納得できるものではなかった。 ・九月一日以降、講和条約に対する不満の声が全国で上がり、各紙はいっせいに講和反対と桂内閣批判の一大キャンペーンを始める。 ・講和に賛成したのは、蘇峰の『国民』くらいだった。 第二章 「帝都大騒擾」の二日間 矢野龍渓の証言 ・『経国美談』の著者として知られる矢野龍渓は、焼打ちで、店舗が襲われて商品が略奪されるような事態にならなかったのは、まだしも日本の国民の潔癖さを証明するに足る、と指摘している。 ・これほどの大騒擾の最中でも、市民の間では一定のモラルが維持され、犯罪や乱暴狼藉が横行する無法状態には至らなかった。 第三章 戒厳令下、政府 vs. 新聞 社会主義者、竹久夢二と中里介山 ・日露戦争中に発表された「反戦詩」といえば、与謝野晶子が出征中の弟を歌った「君死にたまふこと勿れ」(『明星』一九〇四年九月号)が有名だが、与謝野晶子は社会主義や非戦論を支持してこの詩を書いたわけではなかった。 ・大町桂月などが晶子の「君死にたまふこと勿れ」を天皇批判と読んで非難したが、「すめらみことは、戦ひに/おほみづからは出てまさね」という部分は、晶子がトルストイの非戦論におけるロシア皇帝批判にモチーフを得て書いたものだった。 『毎日』記者、木下尚江が書いた非戦小説 ・石川半山は、ポーツマス講和会議に『報知』から派遣された徳は記者で、『報知』に入る前は『毎日』の主筆であり、さらにその前は長野の松本市の『長府日報』の主筆を木下尚江から引き継いで務めていた。 ・『毎日』時代の石川半山は、「城北隠士」の筆名で「当世人物評」を書いて人気を博したが、「ハイカラ」という言葉は彼がそのときに造語したものだという。 ・さらに、半山はこの時期に幸徳秋水とも知りあい、生涯にわたって親しく交友している。 第四章 凱旋と歓迎 韓国保護国化の推進 ・そもそも日本がロシアとの戦争を始めた最大の目的は、南満州からロシア軍を撤退させることと、韓国における日本の優越をロシアに承認させることにあった。 ・日韓交渉の場で、日本は統監府を京城(ソウル)に設置してその支部を各開港場に置くことと、韓国の外交機関を日本政府に委託することの二つを要求している。後者は、日本が韓国の外交権を収めることにほかならなかった。 ・この日韓新協約は一九〇五年十一月十七日に調印された。 ・日韓新協約の調印より三ヵ月以上さかのぼる七月二十九日、桂はアメリカの陸軍長官ウィリアム・H・タフトと「桂・タフト覚書」を交わしている。 ・これは、日本がフィリピン群島におけるアメリカの特殊権益を認める代わりに、アメリカは日本が韓国を保護国化することを認める、という密約だった。 ・日本は米、英、露とそれぞれ取り決めをして、韓国を保護国化することへの承認を得た上で、韓国にこの新協約を押しつけたのである。 ・翌一九〇六年二月には統監府が京城に置かれ、伊藤博文が初代統監に就任する。こうして、日本は列強の承認のもとに韓国支配を進めていった。 ロシア兵士俘虜との交流 ・陸軍病院や俘虜収容所を取材した海外メディアの特派記者たちは、ロシア兵負傷者や俘虜に対する日本の寛大な処置を讃える記事や著作を数多く残している。これは三十数年後の太平洋戦争での日本軍の俘虜に対する暴力行為でつくられたイメージとは大きく異なっている。 第五章 エピローグ 大逆事件と徳富蘆花 ・日本の近代史をふり返ると、第二次桂内閣のときに、韓国併合と大逆事件という二つの大きな出来事が起こっている。 ・一九〇九年十月、初代統監の伊藤博文が、朝鮮の独立革命家の安重根にハルビンで狙撃されて死去し、翌一九一〇年八月、桂内閣は強引に韓国併合を行った。 ・一九一〇年五月から、大逆罪に問われて社会主義者が次々に検挙された。 ・このとき、天皇暗殺の計画を実際に進めていたのは幸徳秋水ではなかったにもかかわらず、警察は最初から大逆罪を適用して、秋水の逮捕に踏み切っている。 ・警察はこの機会に秋水をはじめ、社会主義者を根絶やしにしようとして事件を拡大し、最終的には二十六人もが起訴されている。 ・大逆事件は社会に暗い影を落とし、人々は重苦しい不安を感じていた。この年にはのちに「特高」と呼ばれて悪名を轟かせる「特別高等警察」が設置され、以後の社会主義者への弾圧は、ますます苛酷で容赦のないものになっていく。 あとがき ・司馬遼太郎は、『この国のかたち 一』では次のように述べている。 「要するに日露戦争の勝利が、日本国と日本人を調子狂いにさせたとしか思えない。…ここに、大群衆が登場する。 江戸期に、一揆はあったが、しかし政府批判という、いわば観念をかかげて任意にあつまった大群衆としては、講和条約反対の国民大会が日本史上最初の現象ではなかったろうか。調子狂いは、ここからはじまった。大群衆の叫びは、平和の値段が安すぎるというものであった。 講和条約を破棄せよ、戦争を継続させよ、と叫んだ。「国民新聞」をのぞく各新聞はこぞってこの気分を煽りたてた。ついに日比谷公園でひらかれた全国大会は、参集する者三万といわれた。… 私は、この大会と暴動こそ、むこう四十年の魔の季節への出発点ではなかったかと考えている。この大群衆の熱気が多量に――たとえばせ参謀本部に――蓄電されて、以後の国家的妄動のエネルギーになったように思えてならない。 むろん、戦争の実相を明かさなかった政府の秘密主義にも原因はある。また煽るのみで、真実を知ろうとしなかった新聞にも責任はあった。当時の新聞がもし知っていて煽ったとすれば、以後の歴史に対する大きな犯罪だったといっていい。」(「 “雑貨屋” の帝国主義」) ・二十世紀初頭の日露戦争の勝利のあとに起こったこの民衆の大暴動こそ、近代日本の一大転換期だった。 ―― 完 ―― |