
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2023年03月13日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評 価 |
コメント&抜き書き |
32 |
22.10 |
民と神の住まい 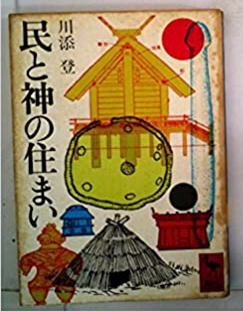 |
川添 登 |
講談社 学術文庫 |
◎ |
まえがき ・建築の地鎮祭とか、棟上式とか、あるいは落成式、その風景はなんとも奇妙なものである。 ・超近代を誇る鉄筋コンクリートの一隅に、シメ縄が張りめぐらされ、衣冠束帯をつけた神主が、うやうやしく祝詞を読みあげる。そして、オーオーオーと、叫ぶとも、吠えるとも、唸るとも、 ・この招かれる神が、アマテラスオオミカミ(天照大神)なのか、オオクニヌシノミコト(大国主命)なのか、知らない。 ・が、こういった神々が、あんがい、私たちの体の血や肉の中に、現に生きのこっているのかもしれない。 ・言葉や文字だけが思想であれば、天照大神を『テンテルダイジン』と読み、大国主命を『ダイコク生命という保険会社か』と聞く、新しい世代が生まれでているような今日、もはや、これらの神々は死んでいると言ってもよい。 ・しかし、文字や言葉は、あくまでも記号である。記号の操作は、やがて人工頭脳が、人間にかわってやってくれる時代がくるであろう。 ・そして、人はやがて、どうしても文字や言葉におきかえられない思想について、考えるようになるのではなかろうか。 ・思想とは、本来的に、肉体そのものから発するものである。 ・日本人の体質の中で、驚嘆すべきものとして、よくあげられるのは、「勤勉さ」である。 ・いわゆる貧乏性というのであろうか、いくら働いても貧乏なのに、じつに、よく働く。未来に夢があるからではなく、いわゆる『 ・あきっぽくあきらめやすいという生理を一方にもちながら、何にかきたてられ、身をすりへらして、これほど働くのか。 ・私たちの血の中、肉の中に、テンテルダイジンか、ダイコク生命かが、巣食っていると言われても、あながち、とっぴではないと思うほどの不思議さがある。 ・『今日様』のために働く日本人は、本質的に現世主義者だと言えよう。にもかかわらず、一方で新興宗教が、これほど勢力をもつ国というのも、めずらしい。 ・今日様的勤勉性や、新興宗教といった日本人の体質の骨格を支えているのは、疑いもなく、農村と中小企業にある。 ・社会学者の説くところにしたがえば、農村と中小企業が日本の社会で占める位置の特殊さは、『天皇制』国家なるがゆえだという。 ・ところが、「天皇」とは、あの、無気味にして気持の悪い神道という原始宗教の大神主のことであった。あの神主のオーオーという、原始の叫びこそ、日本人をいそがしくかりたてているものであろう。 ・原始の日本人が、文字にもならぬ、言葉にもならぬ動物的なもやもやした世界から、もがき、苦しみ、戦いながら、ようやく生みだした最初の思想体系は、神話であった。 ・そして、日本列島に住む人びとが同じ神をイメージするようになって日本人として、たがいに結ばれるようになったのだ。だから、神々が日本人を生んだという神話を、あながち、うそだというわけにはいかない。 第一章 古代は現存する 一 一木一草に天皇制がある 柱は語る ・私たちが住んでいる現代の日本に、興味深い二つの柱が立っている。 ・一つは建物の床下に独立して立ち、もう一つは建物の中央に、それをがっしりと支えている。 ・この二本の柱は、現在「心の御柱」という同じ名前でよばれており、ともに、古代の昔から伝えられてきたものである。この二本の柱こそ、現代日本の異なる二つの側面を、それぞれに、暗示しているように思われる。 ・その一本は、伊勢神宮の正殿床下に、人知れず立てられており、あたかも原始の暗い影をただよわせる天皇制を象徴しているかのようであり、また一本は、出雲大社に、太い柱となって今に伝わり、日本の民衆の健康な姿を表現しているかのようでもある。 ・これまで二本の柱は、その「心の御柱」という同じ呼び名によって、同じ起源のものと考えられてきた。 ・しかし、この二つが、まったく異なる起源のものである。 ・古代の出雲大社は、じつに、約四八・五メートルにもおよぶ高さを、誇っていたという。 ・その中央柱として立つ巨木が、現在の出雲大社に伝わる「心の御柱」の原形である。 ・この柱は、民家を支える「大黒柱」の起源ともなり、今なお「大黒さん」の愛称で、英雄神オオクニヌシノミコト(大国主命)の名を、語り伝えている。 ・一方、伊勢神宮の床下に立っている柱は、人が一人、あるいは多くても二、三人で、持ち運ぶことのできるものであった。 ・古代の人たちは、この柱を地面に立てることによって、そこに、大地に住む神や、空とぶ ・日本の歴史は、この出雲大社に象徴されるたくましい民衆が、伊勢神宮に象徴される原始的なマジナイに屈服し、支配された歴史であった。 ・この二つの建築の原形は、仏教渡来以前のものであり、したがって、いまだ外来文化の影響を受けない、純粋な日本建築と考えられる。 ・「古代」は、この二本の柱とともに、「現代」に存在している。 天皇制と日本人 ・「天皇」という言葉は、すでに、七世紀の初頭には存在していた。少なくともそれに当たる人物が、日本に君臨していた。 ・その系譜をさかのぼれば、三世紀の崇神天皇(第十代)がハツクニシラススメラミコト(所知初国之天皇)だという。 ・神武天皇(第一代)がハツクニシラススメラミコトだという説には、創作の疑いが濃厚である。 ・また、日本最古の文献、『古事記』・『日本書紀』の伝える応神天皇(第十五代)以前の記述は、ほとんど信用できないとされている。 ・が、ともかくも、ほぼ三世紀もの昔から、「天皇」が連綿と、うけつがれてきたことだけは事実であろう。 ・厳格な意味で「万世一系」であったかどうかという詮索は、このさい、あまり問題ではない。あくまでも、天皇の「血筋」が重んじられ、そして、つながってきたことに意味がある。 ・さらには、その「血筋」をさかのぼった果てには、伊勢神宮の祭神で、太陽の神である天皇の祖先神アマテラスオオミカミ(天照大神)がある、と説明され、しかも、日本民族はすべて、アマテラスの子孫であり、天皇家はその本家だ、と言われてきた。 ・天皇制が、神道とよばれる宗教を土台にしていることは、広く知られている。 ・しかし、現在の私たちにとって、天皇制は、一種独特なものである。それは、理性に訴えかけるものでも、また、感情をとらえるものでもないし、まさに、「皮膚感覚」にあるとしか言えないようなものである。言いかえれば、日常経験的なものである。 ・明治以後、私たちは、支配者の側から、日本は天皇を中心とする一つの大家族であるという考え方――「家族国家」観を押しつけられた。しかし、その考え方が、たやすく受けいれられたのは、日本民族の長い歴史の中でつちかわれた、天皇制の素地があったからこそ、と思われる。 ・そのように考えるとき、私の頭上におおいかぶさってくるのが、伊勢神宮とよばれる建築なのだ。 ・これを究明することは、建築評論家という私の職分から出発し、その職分をこえた日本人としての感情である。 「皇大神宮」と小学生 ・「家族国家」観が為政者によって強力に押し出されたのは、明治四十四年(一九一一年)の国定修身書の改訂と、この解説普及運動にあった。 ・この改訂では、それまでの修身書(一九〇四年制定)にあった、「他人の自由」「社会の進歩」「競争」「信用」「金銭」といった近代的な思想を教える課がはずされた。そのかわりに、「皇大神宮」「建国」「国体の精華」「皇運扶翼」「忠孝一致」「皇祖皇宗の御遺訓」といった、天皇制を強固にするふさわしい課が新しく加えられている。 ・新しい課の中で、尋常小学校で教えるのは、「皇大神宮」だけである。 ・昭和の初めごろには、教室で、月々、少しずつの金額を貯金させられた。それによって、全国学童のほとんどが、卒業前に、「参宮旅行」に出かけた。 ・この「家族国家」観的な行事も、古く中世から続いていた「伊勢講」などのように、今なお、全国の農民層に深くくいこんでいる民間組織や行事が、日本人の生活の中にあったからこそ、可能になったのではなかろうか。 ・「皇大神宮」と言えばいかめしいが、「お伊勢さん」と言えば、庶民的な響きを感じる、といった類いのものが、天皇制の基礎にはあった。 ・伊勢神宮は、なにゆえ≪一木一草に天皇制があり、われわれの皮膚感覚に天皇制がある≫かを解きあかすのに、重要な足がかりになる。 二 おどる民衆 伊勢の一大PR ・伊勢神宮は、古代に諸制度を定めた書物『延喜式』(九二七年)に、«およそ王臣以下、たやすく大神宮に幣帛を供するを得ず»と書かれているように、一般民衆はおろか、皇族・貴族ですら、近よりがたい存在であった。 ・伊勢神宮を神秘な ・これは、明治になって、«天皇は神聖にしておかすべからず»と『皇室典範』第三条に記したのと、同じ思想である。 ・十三世紀ごろには、大宝律令の制定以来、打ちたてられていた体制が、崩れはじめていた。 ・それにしたがって、しだいに、伊勢神宮は経済難におちいり、とりわけ天皇家からの援助があまりなかった外宮では、経済難がひどくなっていた。 ・そこで、外宮の神官たちは、蒙古撃退に偶然の立役者となった「神風」に力を得、ここをせんどと、全国民へ向けて、伊勢の一大宣伝戦を開始した。 ・彼らは、「 ・外宮の「御使」たちは、その祭神が、トヨウケオオミカミ(豊受大神)という農業神であることを利用して、農村にくい入った。 ・また、場合によっては、彼らはさらに格づけの高い神アメノミナカヌシノミコト(天御中主命)などの名を詐称した。 ・これによって、伊勢信仰は、民間に深く伝播浸透し、全国にわたって、伊勢神宮の末社を設立していく。そして、信仰集団としての「伊勢講」を組織していった。 大衆ヒステリー ・「伊勢講」は、伊勢参宮を希望する村人が集まって、その旅費を共同出資で積み立て、くじ引きで代表者を選び、順番に、代参者を派遣する積立貯金式の組織である。富くじ的な興味と、旅行への楽しみの二本立てで、この「伊勢講」は、ひじょうな人気を集めた。 ・代参者の出発の日や、帰村にあたっては、村じゅう総出の盛大な催しなどもあり、娯楽にあまり恵まれない農民たちにとっては、たのしい行事のひとつになっていた。こうして、桃山時代になると、目もみはるばかりの人数が、伊勢参宮に、全国から集まってきた。 ・しかも、このころから「伊勢踊り」という奇妙な社会現象が、たびたび現われはじめる。 ・それは、社会の変革期にあたって、あたかも、民衆が解放要求を叫ぶかのように、伊勢からはじまって、京・大和・近江・美濃・加賀などにまでおよぶ道のりを、おどり狂う一種の流行現象であった。 ・宿場から宿場へとおどりついで、じつに短期の間に、そうとう広範囲の民衆を、伊勢信仰に結びついた興奮のるつぼの中に、たたきこんでしまうものであったらしい。 ・これが江戸末期、周期的にあらわれた「お陰参り」や「抜け参り」、そして、薩長軍による討幕のクーデターが、まさに行われようとした明治維新の直前に、日本全土に、突発的にひろがった「ええじゃないか」の端緒をなすものである。 ・「お陰参り」は、一般的には、伊勢神宮へのお礼参りを指す。参詣人が伊勢への途中、道中で施しものを受け、そのお陰をこうむりながら参拝することである。 ・特殊的には、江戸時代(一六〇三~一八六七)を通じて、ほぼ六、七十年に一回ずつ、自然発生的に、全国から人が集まり、ひしめき合いながら、おどり歌って、伊勢神宮に参拝した事件を指している。 ・中にはまったくの箱入娘である良家の子女までが、群集心理に巻きこまれ、突発的な衝動から、こっそり家を抜け出して、路銀も持たずに、人の群れにまぎれこんで、参宮についていくのすらあった。これを「抜け参り」と呼ぶ。 「ええじゃないか」 ・このもっとも激しかったのが、幕末に起こった、有名な「ええじゃないか」である。 «慶応二年(一八六六年)、一揆・打ちこわしにかわって、「ええじゃないか」の大衆混乱が、全国を風靡した。八月下旬、名古屋地方に皇大神宮の御札が降ったとの噂をきっかけに、老若男女が「気違いのごとく」おどり狂ったのが初まりで、この狂風は、たちまちに四方に伝播し、ほとんど全国各地に波及した。 当時、狂乱する民衆の間に歌われたのが、「ええじゃないか」という囃子をもった唄で、卑俗猥雑な言葉をもってつづられ、それは「ええじゃないか」という語によって代表されるような、いっさいの常識規範を無視した、反抗的な、しかし、また希望のない、投げやりな享楽的気分に満ちていたものであった。 この唄をうたいながら、華美な服装で、中には、男装せる婦人、女装せる男子もまじって、太鼓・小鼓・笛・三味線の鳴り物入りで、おどりまわり、つね日ごろ心よく思わぬ地主や、富商の家に土足でおどりこみ、酒肴を出させた。 ときに、その家の衣類・器具・金銭を持ち出して、「これくれても、ええじゃないか」。眠くなれば、誰の家でもかまわず眠り、さめればまたおどり、「当時は神代となり、遊びをしてその日を送られ、まことに、ありがたき世の中なり」と喜ぶ。» ・この大衆乱舞によって、枢要な街道筋は、ことごとく混乱におちいった。それがため、幕府の機能は、かんぜんに麻痺させられる。 ・この間に、薩長軍による討幕の手が、つぎつぎに打たれたのである。 ・これらの現象は、討幕軍によって、しくまれた大衆混乱であり、この混乱に乗じて、徳川幕府を倒すとともに、農民一揆や打ちこわしなどで、これまで抵抗運動を続けてきた民衆の鉾先をかわして、薩長独裁を打ちたてるためであった、と羽仁五郎氏は説いている。 三 わが日本の謎 天才的な手腕 ・民衆の間に深く根をはった伊勢信仰をたくみに利用しつつ、伊藤博文ら明治の元老たちは、その天才的な手腕によって、日本人の理性も感情も、そして皮膚感覚までをも、「家族国家」としての天皇制機構の中に、みごとに組み入れてしまった。 ・現在、地方の氏神として、アマテラスをまつる神社が、おびただしい数で建っている。それを調べてみると、そのほとんどが、明治以後に建てられたものであるか、あるいは、以前は、その地方地方の土地神をまつっていたにすぎなかった。それが、明治以後になって、アマテラスをまつるようになったのである、と言う。 ・一方では、地方の氏神を伊勢の出先機関とし、伊勢信仰の伝統を、国家神道として制度化したわけである。 ・こうして、日本はアマテラスの直系の子孫=天皇=「現人神」を中心とする一大家族であるという観念を、国民の中に浸透させていった。 ・天皇が現人神であるためには、現代を神代そのまま、つまり原始時代をそのままに、もどすより方法はない。 ・そこで一月一日の「四方拝」にはじまり、十二月三十一日の「大祓の儀」にいたる一年十九の祭を、天皇みずから、「古式豊かに」とり行なわせられた、ということになる。 ・現在でも、農村に行けば、日本に農業が伝わったころから続いていると思われる農耕儀礼が、いまも行なわれている。 ・これは元来、その地方の土地神を中心にして行なわれていたものであろう。しかし、この祭神を、多くはアマテラスにされてしまったのだ。 謎をとく鍵 ・伊勢神宮は、遠く古代から、破損をさけ、原形にしたがって、二十年ごとに社殿をつくりかえる。それによって、もっとも古い日本建築の姿を、今に知ることができる。 ・日本国民の皮膚感覚にまで浸透している天皇制の謎は、この幾重にもめぐらされた玉垣の中に建つ伊勢神宮の奥深く、まるでフェニックス(不死鳥)のように生きつづけているのだ。 第二章 秘められた柱 一 伊勢の 八世紀の昔から ・ <途中> |