
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2024年04月21日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
38 |
22.11 |
神と仏の間 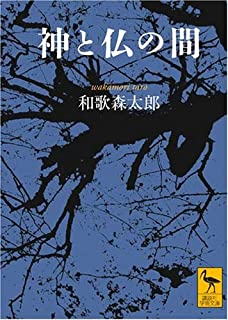 |
和歌森太郎 |
講談社 学術文庫 |
◎ |
総論 日本人における神・仏 一 神代の成立――自然神の祖先化 ・天岩戸神話については、日食神話という説もあるけれども、私は、太陽の光と熱とが最も弱まる季節、およそ冬至のころに行われていた、いわば太陽復活祭を語る話だと理解している。 ・太陽に活霊をいれ直す点で、のちの鎮魂祭の祭儀とも通じるが、天細女命の裸身をもってするはげしい踊りと、日神の使令である常世の長鳴き鳥に鳴かせることの、二つの要件から考えて、日の精に活をいれることを要求した、冬至のころの民俗を語る神話だといえる。 ・ニニギノ尊に関する神話には、皇統のシンボルたる神器を掌握することや、いわゆる天壌無窮の神勅をうけたことなどが、広く伝えられていて、皇祖神の降臨を強く印象づける。 ・ニニギノ尊は、生まれた直後に神器を授けられ、 ・山頂に天から降臨した祖神を戴いて、地域集団の中に里めぐりをすることが、山宮から里宮に迎える祭儀に続いて行われるところは珍しくない。 ・天つ神の群れの中から生まれたての幼童を、現し世に迎えたことから、自分らの社会に支配の中枢を占める権力の源が発するとの信念を降臨渡御の形態で描くことにより、ニニギノ尊の皇祖神たることを明確にしているのである。 ・各祖霊をめぐるさまざまの神話伝承の世界までが、高次の自然神的神の世の一つと連ねられ、自然神を祖先神化してもいった。雷とか土地や山川草木など種々の自然神を祖神化するようにもなったのである。 ・こうして、記紀についていえば、神武天皇以前の神話群も、ほんらいの「神代」と一様に「神代」の物語だととらえられることになり、神代巻として表題が付けられるに至ったのである。「祖神の代」が「神代」に包括されたのである。 ・このようにして「神代」が、一般的自然神、祖神を含めてあらゆる神々の活動した時代として成立し、日本史の前史をなすことになるとともに、そこに物語られたことがすべて、後世の国の歴史の規範であり、原動力だとみさせる神国思想を培うものになったのである。 二 神観念とその社会性 ・日本人にとっての神が、個人を越えたミウチ仲間、近隣の仲間とともにある自分の幸福と安全とを祈祝する対象になってきたことから、生業のさかえを願って神の保障を願う傾向が強かった。 ・生業のさかえは、近代以前のおおかたの日本人としては農耕生産のゆたかに結実することであった。 ・正月の初めにあたって、家々の主たるなりわい――多くは稲作生産であった――を守り、さかえさせるよう、その守護神であるものを、家の祖霊とかさねて迎えるべく、松や、古くは榊などを依り代として立てたのである。門松はもとその意味のものだった。 ・農民は、山の神が春、山から田に降りて田の神となる、秋には、稲作の終わるに伴いまた山に帰ると信じ伝えてきた。この信仰にも、祖霊が山にこもっているものだとする見方があずかっている。 ・旧暦五月は、田植月であったので、サ月といわれ、稲苗もサナエといわれた。これを手にとって植え付ける女たちはサオトメといわれた。 ・日本人がその主とした生業の守護に神を求めたことは、農事を離れたなりわいを事とするに至っても同じであった。 ・もともとは、稲成りの神として、農民生活にとって意義のあった稲荷の神が、町方の商人の業について福を保障する神として、商売繁盛を祈願する対象に転じていった。 ・野鼠などを好んで捕える点で、農地を守る狐は、稲荷の神の使令のように信じられ、農家の守護霊ともなっていた。その狐は稲荷と密接な関係をもって、家の屋敷神に祀られたところが多い。 ・異境の神としてのエビスが、遠くに船出して漁撈にたずさわる漁民にとり豊漁などを守る神とされたのが、町方の商売繁盛を支える神になっていたこともある。 ・出雲美保関の美保神社は、俗にエビスさんとよばれて親しまれてきたが、もとはその地方での漁撈神であった。 ・神信仰は、もとより人生、人の社会生活の要求によって現われたものである。日本人の人生観、社会生活の在り方が、種々に変わってくるのに伴い、神の観念も当然変化してきた。その本質に社会性を帯びるところから、絶対不動の性格をもち、貫くことがなく、変わりやすくもあったし、政治的にも利用されやすいものだったとえよう。 三 民間信仰における神・仏・キリスト ・日本の神信仰は、何らかの集団生活ごとに保たれてきたわけであるが、集団が、これを要求したのは、その社会生活や立場に、安らぎを得ようとしたからである。 ・被支配の一般人民は人民なりに、支配の力をふるったものは支配者なりに、それぞれの不安感がいつもつきまとっていた。 ・古今を通じても、人生は不安と安らぎの交錯の中で展開する。ニギミタマの神でも、アラミタマのアラブル神・御霊神・役鬼の神でも、畢竟は人生の不安から安らぎへの転化を祈求するところに、観念されてきたものである。 ・香川県の金刀比羅に讃岐のいわゆる金毘羅さんがある。金毘羅は、もともとインドの民間信仰での、また仏教信仰では外道の神とされた水の神= ・今はもちろん神仏分離で金刀毘羅宮として神社化しているが、久しく神仏混淆のままでの信仰対策に据えられてきた惰性はなお続いている。 ・宗教の定義 人間は、個人としても、いつどんな環境にあっても、有限なものだとの自覚をもっている。生命について、精神能力について、誰もおのれを無限に保てるものとは思わない。しかし有限であると自覚すればするほど、これを無限絶対のものに結びつけることにより、有限の自覚に伴う不安から逃れたいと思う。 そうした要求に発する無限、絶対そのものを人間はさまざまのイメージで想定してきている。その無限、絶対者を一般には神とか霊として観念してきた。それは無限、絶対であるがゆえに、何ものにも冒されたり、潰されたりしない、またそういうものを排除する聖なるものである。 その意味で、限りある、したがって日常不安にさらされている人間は、聖なるものに帰一することにより、俗の相対的境地から離脱しようとはかる。 この聖なる霊や神、あるいは力の存在を確信し、不死なり、永遠なりにおのれを帰一させることを、人間は原始このかたつとめてきた。そうした活動を、宗教というのである。 ・人びとは、その聖なるものを、まず自然のうちに想念した。人間を取りまく自然には、きわめて説明しがたい、いろいろの現象が発して、人びとを畏怖させてきた。 ・古い時代の人間は、そのような自然の前にいよいよおのれの有限さ、相対性を自覚させられ、おそるべき現象を現実化させる自然そのものに神霊を感じ、その絶対無限の力を観取した。 ・ために自然そのもの、あるいは自然にひそむと信じた霊威・霊力を神とし、これを聖と仰いで、俗生活を、この聖の威力で支えていこうとした。 ・その意味では、自然崇拝も、宗教活動の一つだといえる。けれども、聖なるものを、自然のような外在と見るか、人間に内在すると見るか、二通りあり、原始段階では一般的に外在的にとらえた。 ・やがて人間に内在するとしても特定の三位一体的人格にあるとするか、誰の内心にも在るとするか、前者から後者へと進んできた。 ・人間がその有限さを、無限の絶対なる聖に結びつけることで、安心を得ようとするとき、聖と俗とを結ぶ媒介を要するとした。 ・これには行事と人とがある。行事としては神については祭儀がある。仏教では、それを修行としていた。これが宗教的実践である。この実践を通して、人びとは永遠の安心を獲得する祈りを籠めてきた。 ・歴史の発展に伴い、こうした媒介を、どのように実践するかにより、また何ものの力をとくに助けとして、永遠への回帰を可能にし、なぜ相対から聖への帰一を可能にするのか、根拠と方法とを、人間は求めねば承知できなくなった。 ・そこで、聖と俗とを結ぶ媒介の祭儀にも、仏教者の禅定修行にも、その規範となるものがつくられた。 ・祭儀については、神話である。禅定などの修行その他の仏教行事については、法・理・道など、あるすぐれた人格が創唱した教説である。また、神聖との帰一を求めるものと、神聖との間に立って、より神聖に近づきやすくするようはからう人物が現われた。 ・たとえば、神霊を憑依する巫女、神主・山伏・教祖・僧・使徒たち聖職者である。 ・日本人はこうした人びとへの期待について、神道系と仏教系とを、きびしく分けてはこなかった。 ・これらの人物は、神霊的なものを現わして身につけたと信じる、啓示や悟りを開いたものである。 ・これをつかむためにも、修行が要求されたりする。物忌・斎戒したり禊ぎ祓えをするなどもその類の手段である。 ・これを経て俗を離れ、聖なる境地に浸っていく。中には呪術を介して、そこに至るものもある。 ・いろいろの行事を通じてなり、先輩の伝承的体験と結ぶ祭儀神話を聞いたり、聖職者の導く規範的教説なり、法理に即して思索することで、聖なる無限、絶対への帰一をはかることが、人びとに生きる自信とよろこびとを深めさせ、俗世間での不安・困惑からまぬがれさせる。そうした機能を果たしてきているのが宗教である。 ・このような、聖なる絶対への帰一をもって、相対的不安感から抜けさせるという、人生における機能から見れば、民間信仰も神社神道・教派神道だろうが原始宗教だろうが、ゾロアスター教だろうが、ヒンズー教・仏教・イスラム教・ユダヤ教・キリスト教のいずれにしても、皆相通じている点がある。 ・受験生の神だのみの仕方は民間信仰の一つの型であるが、こういうものが、機能としては宗教の機能はもつにはしても、仏教とかキリスト教のような宗教と、同じ次元において、照らしあわされる類の宗教とはいえないのではないかという疑問がある。 ・少なくとも、キリスト教とか仏教とかのような、キリストや釈迦のような個人が開き、創唱者となっている、あるいはその教説を秩序だって展開している教義・教理をもつものとは、民間信仰はちがうではないかといわれよう。 ・また、これらの創唱宗教には、教会があり、寺院があり、そこには信徒との間をとりもつ専門の聖職者がいる。神社神道の場合は、創唱宗教ではないが、それでも多くの神社には、聖職者としての神主・神職がいる。 ・民間信仰というものは、そうした創唱者もいないし、教義・教理をとくに述べ立てることもなく、特別な宗教的施設もなく、家や村のどこかで、また野の仏なり、辻の祠なりの前で直接に、信仰が表現されるようなものである。特定の聖職者が、その信心の対象とこれを信仰する庶民との間を媒介し世話をするなどということもない。 ・日本人は、神社神道や仏教、近代以降ではキリスト教にそれぞれの人生のよりどころを得てきているが、なお多数のものがそれらとは別に、自然崇拝・祖霊崇拝・精霊崇拝・御霊信仰・呪物崇拝をはじめ、もろもろの生業を守る神への信仰とか、家の ・これらの民間信仰は、古くからの民衆生活のうちに、おのずからに発生し習俗化してきたものであり、誰かが発明し、伝導した結果のものではない。 ・民間信仰というものは、原始宗教・神社神道と同様だが、その信仰者の社会生活構造と深くからみついている。 ・したがって、キリスト教や仏教が、同族や地域を超えて、個々の人間の選択によってよりどころとなるはずのものだったのに、民間信仰では、その属する同族・村落などの社会集団として希求される聖なるものへの帰一となっている。 ・創唱宗教は、そうした社会集団の埒を超える普遍性をもつ点で世界宗教といわれる面をもつ。 ・絵馬奉納の祈願は、個々人の信仰ではあるが、金毘羅信仰者というよりも、そのめぐりの高松市その他の、近くの地域に伝承する習俗にそっているものなのである。 ・一般の生活が、地方差・地域差をもつように、民間信仰の表現の仕方にも、地方差・地域差のあるものが多い。もともとは一つの民族の間で普遍的であったものでも、歴史の進みに従って、そうなったのである。それは、それぞれの地域社会の歴史が、時代とともに一様には進んでこなかったところから、元来、社会生活構造と密接にからんで発展してきたような民間信仰の型も、おのずから地域性を帯びるようになったのである。 ・しかし、キリスト教や仏教には、そのようなことがない。地域・地方はおろか、一民族内にとどまることもなく、普遍的にこれが受容されてきている。 ・このような創唱宗教と民間信仰との違いが、教団や教会の有無とも関連する。 ・教祖が創唱した教義を信奉しつつ、その中核にある聖なるものを絶対視して、救いを得ようとするもの、個々人の意思をもった結果が成り立つ。それが教団である。その教団の中から、格別指導性をもって布教伝導に、専門的にあたる聖職の牧師、司教者としての神父、僧侶が現われたりする。この教団と聖職者とは、ある一つの地域や地方に定着する者ではない。かけ離れた地域や地方にまたがって、一つの教団を成したりする。聖職者も、もとより一定のものが、ある信徒団に常にかかわるということがない。 ・ところが、民間信仰では、族縁社会・地縁社会そのものが、信者の仲間となっている。そこで指導性をもつものは、その仲間のうちで比較的長上・先輩として、その信仰習俗により深く馴染んでいる人物である。彼はよそものであるとか、その指導なり司祭についての専業者とかではない。それは各同族や地域社会という集団での伝承的習俗の継承者であるに過ぎない。 ・原始キリスト教や原始仏教の研究が示しているように、創唱宗教の生まれる母体としては、それぞれのところでの民間信仰があったといえる。 ・たとえば、キリスト教の母体となったユダヤ教では、ヘブライの族長だったアブラハムが、テレビンという、いわば神木のもとで、ヤーヴェと出会ったと伝えている。これはセム民族の中での民間信仰に含まれていた樹木崇拝を根底にしたものである。一般に樹木崇拝は、神霊が依ります樹木にたいする信仰にもとづくものが多い。 ・そうした民間信仰は、セム族の間での習俗としてあったものであろう。キリスト教の教説もそのような伝承習俗にこもった信仰に結びつけることで、これを受容し、支持する者を増加させていくことができたのである。 したがって民間信仰が伝承していた段階がまずあって、その後の段階で、創唱宗教の教説が形成されたということができる。両者は、歴史段階を異にして現われたものなのである。 ・創唱宗教は、民間信仰を基底にしつつも、これをむしろ否定し、変革させる向きにおいて止揚しながら、新たに発明されたものだといってよい。 ・さらにまた民間信仰の内容は、いわゆる多神教である。一般的にいえば自然神を絶対の神霊として認める信仰が著しいけれども、その自然は、天・山・川・水・海・樹・木・石……など個々にそれぞれ絶対の神性を認める点で、機能神化して分かれもする。しかもおのおのが人格的に形象されたりしている。 ・けれども、創唱宗教は、民間信仰を素地としながら、これを否定する向きで成り立ったものだけに、そうした多神を一神のうちに集約している。その一神のさまざまの部面にこれをとりこんでしまう。あるいは全くこれを排除して純然たる一神化を確立している。その一神は非人格的原理として表象され、具象化されない、理念となっている。 ・自然神・機能神が多元的に人格的イメージをもって含まれる民間信仰では、また生存のときにすぐれた人物であったとか、聖職にあったものとか、祖先などの人物をも、聖なる絶対の神と化して包みこんでいる。こうしたものは、仏教の如来にたいする菩薩のように、創唱宗教では、絶対一元の神そのものと峻別されている。 ・宗教の本質を考えれば、キリスト教・仏教と民間信仰との間には、相通ずる面をも否定しがたいし、民間信仰はたしかに宗教の一種と見ることができるにもかかわらず、その間には、またきわだった異質さがある。 ・これまで神社神道や仏教などの創唱宗教が、在地の民間信仰を無視することなしに、これを摂取するなり、否定するなりしながら展開してきた。金毘羅信仰などもその著しい証拠である。 ・神社神道の祭儀において、必ず行われる玉串奉奠という、常盤の葉をもつサカキを神前にささげることがある。これは、祭りが神と人とを一体にすることだという意味を表わす作法である。 ・サカキにしても、松にしても、常盤木は、日本人においては、とりわけ神霊の依り代とされてきている。 ・民間信仰の習俗としての正月の門松――ところによっては、あるいは松以前には門口にサカキを立てていた――にみられるような聖樹崇拝と通ずるものである。 ・神社神道には、民間信仰に根ざした要素がすこぶる含まれている。 ・仏教についても同様である。すでにインド以来、仏教は在地の民間信仰を包摂しつつ、おのれの教理の世界に位置づけていた。 ・金毘羅さんは、明治維新の神仏分離以前は仏寺であったが、この金毘羅は、インドの民間信仰での宮毘羅という神であった。この神は鰐の表象であり、水の守護神であった。これが日本では水難除けの神として、再び民間信仰のうちに定着してきたのである。 ・その間、仏教における薬師十二神将の一つ、あるいは般若守護十六善神の一つとされ、仏の教えを妨げるものを退治し、その化道を扶けるものになってきた。増一阿含経巻三の弟子品には、金毘羅は、独り坐して禅定三昧をこらしている比丘だといわれている。 ・このように仏教界の比丘とか、弁財天のような天部とかにおいて、仏につかえこれを守るものには、古いインドの民間信仰界の神であったものが多い。 ・仏教は、中国に伝わっても、その民間信仰に立脚していた道教との習合を行っている。密教の中には、これがよく認められる。その結果、逆に中国の民間信仰のうちに仏教を浸みこませることにも成功した。 ・日本においても、金毘羅が、仏教界で、仏の教化活動を扶け守るものとして受けとめるよりも、讃岐の地で瀬戸内海交通の舟航を水難から守るものになったのは、やはり、もともとその地方で、古来活発だった瀬戸内海往来の船を守る、民間信仰上の神が海ぎわの山に祀られていたからである。 ・この山を、仏典で金毘羅の在所とされている ・そうしたことは、仏教の含む浄土教信仰にかかわる地蔵信仰が在来の民間信仰にあった、地の神とか、サエノカミ(道祖神)とかに結びつくことで、著しく普及したさまにもうかがえる。 ・キリスト教にしても、クリスマス・ツリーといわれる樹木が民間信仰との交渉をよく物語っている。これは実は、一六〇五年、ドイツのシュトラスブルクでのクリスマスに、初めて用いられたものだという。 ・ゲルマンの民間信仰習俗にあった聖木崇拝、やはり、神霊が樹木に依りますとみる信仰にクリスマスを結びつけることにより、この聖誕節を一般化できるようにしたのである。 ・ゲルマンの習俗としては、樹木信仰は原始以来の古くからの伝承であったことが、タキトゥスの『ゲルマニア』でも知られるけれども、それがキリスト教に含みこまれた時期は、ようやく十七世紀初頭に及んでからである。 ・前にセム族の聖樹信仰をユダヤ教・キリスト教がとりこんできたが、そのように、成立の初期においてのみならず、クリスマス・ツリーで知れるとおり、その後の発達過程の中間においても、民間信仰習俗を随時摂取しながら伝導・伝播していったのである。 ・キリスト教の降誕節としてのクリスマスは、もと一月六日のエピファニー(公現節)と同じときに営まれた。これが十二月二十五日になったのは、ローマ人の間で太陽神ミトラを祀り、ちょうどその勢いの最も衰えるころである冬至の時季を選んで、太陽の活霊の復活祭ともいうべき祭儀が行われていたのに結びつけたのだといわれている。 ・そのときを古代ローマではサトルナリアともよんで、サタンである悪魔はらいのために、無礼講の宴を張っていた。そうした、民間習俗としての信仰行事が、救主キリスト崇拝の一表現としてのクリスマスに結びつけられたことで、その信仰を定着させるのに効果をあげたのであった。 ・歴史的には、原始宗教以来の民間信仰よりも、遅れてすべての創唱宗教は開かれている。したがって仏教もキリスト教も、民間信仰とのいわば対決を迫られたのである。 ・すでに何らかの民間信仰をいだいて生きてきた人びとは、高度の創唱宗教に触れた場合、既存の民間信仰を全く離れて、飛躍的に、その伝導宗教に帰依しがたいものである。 ・従前の信仰との習合、結びつけを、民衆の側からも行うし、伝道者が意識的にこれをはかることは珍しくなかった。 ・キリシタン弾圧を受けた日本の近世封建社会の民間信徒は、為政者の眼をそらすため、マリヤ信仰と仏教の観音信仰とを集合させ、マリヤ観音を造像し、ひそかにキリスト教信仰を護持し続けた。 ・キリスト教が日本に伝導されたとき、耶蘇会の宣教師は、在来の民間信仰ならぬ呪術については、これをきびしく批判し、嘲笑しながらしりぞけた。山伏が行う密教的呪術などは、妖術扱いして民衆の蒙を啓いていった。 ・従来の日本の民衆が、十分な医療術に親しまず、もっぱら俗信の中の悪魔はらい、憑きものはらいを旨とする呪術に依存したり、民間信仰としてあった疫病神送り、禊ぎ祓えに頼っっていたのにたいし、西洋の科学的医療術をもって、救うことに努めたことが、宣教師の活動として著しかった。いわゆる南蛮医術がここで日本に伝わることになったのである。十六世紀に日本に伝道されたキリスト教の布教活動は、救癩・医療伝導と称してもよいほどのものであった。 ・また西欧の言語や文学を教えることによる伝道も活発であった。教育伝導・文化伝道の趣を呈していた。このような伝道方式では、在来民間信仰とキリスト教との間に、多分に矛盾を感じさせたに違いない。いきおい民間信仰との対決、ひいてはこれを排除する動きをとったに相違ない。 ・祖先神信仰にかなり重きをおいた日本の民間信仰、家・一族、また村落社会の安寧と平和とを求める線での民間信仰が著しかった日本人にとり、普遍的世界宗教として、個々人の人間としての内省から発するキリスト教信仰は、なかなか馴染みがたいところをもっていたろう。 ・日本の民間信仰における神々は多様である。それを大きく分けると、人間の社会生活を守護すると信じられてきた神と、社会生活を脅かし祟りをなすと信じられてきた神とがある。 ・前者は、古典神話などでいうとニギミタマに相当し、後者はアラブル神に相当する。 ・前者には甘えよりかかる祭りを行うことで、それとの一体化をはかってきた。後者には鎮め抑えるための呪術的祭儀を行うことで、それが取り憑くことから免れようとしてきた。御霊信仰や怨霊観が、その系統のものである。 ・守護神霊も脅威神霊も、ともに自然崇拝と精霊崇拝とを基調にして想念されたが、とりわけ脅威神霊の中には、人鬼(生きていた人間の魂)崇拝もあずかっている。これにたいし、守護神霊には、祖霊信仰がからんだものがある。 ・守護神霊は、祭祀を怠ると、脅威神霊化し、人生に祟りを及ぼすとされたが、逆に脅威神霊も、これを鄭重に鎮め祀ることにより、 ・これらの神霊が擬人化されたり、またほんらいその霊が使令としていた動物などが、その神霊の化現だとみられたりした。 ・ところで守護神霊が守るもの、脅威神霊が祟るものは、同族・家、地域社会としての村落などの社会生活全般であったが、とりわけ、それぞれが共通にたずさわる生業を守護したり、これに妨げとなったりするものとされた。 ・農耕生活・漁撈生活などの安全と順調な収穫(獲)をゆたかにあげるよう、保障を守護神霊に祈願することとか、これを妨げ荒らすことがないように脅威神霊を鎮め祀ることとかが、民間信仰の主たる内容となって来た。 ・農業生活が支配的であった前近代の日本では、したがって、年の初めの正月から歳末まで、とくにその年の農耕生産の無事、豊饒を期しての祭りが、家ごとに村ごとに営まれてきた。それがくりかえし伝承されてきてのいわゆる年中行事は、ことごとく民間信仰と、これに関連する呪術の表現であったといってよい。 ・生業の守護を祈り願うほかに、人びとは生死の運命にとうぜん敏感であったから、病を避け、怪我あやまちがわが身におこらぬよう守護神霊にたよることもあったけれども、どちらかというと呪術に依存した。病にかかり、死に瀕してくると、これを癒すことを、信仰というよりもやはり呪術にたよった。 ・村内全般にひろがる疫病については、疱瘡神送りとか御霊祭りとかをしたほか、疫神が村内に立ち入らぬよう村境に注連縄を張り、疫神がいやがるような悪臭の強いものをこれに吊るすとかした。 ・日本の民間信仰では、同族や地域社会など、個人を包む共同体的な集団としての信仰が顕著であり、純然たる個々人の生死など運命にかかわるものの守護を乞うことは、古くは呪術にたよることが多かった。個人的に神社に参るとか籠るとかしてこれと一体化し、祈願をすることは比較的にすくなかった。 ・しかし、人びとが家族として、村びととしての不安以外に、まったくの個人としての不安にかられ、苦しむということは、とうぜんあったのである。そうした人間の個人的不安を解消するに、多く呪術にたよっていたのを見て、キリスト教の伝道者は、これを迷信のしからしめるところとして排斥し、キリスト教による救いの道を開き、教えさとすことがあったのである。 ・従前の民間信仰、またこれに結びつく呪術をもってしては、純然たる自分一個の運命を切り開けない、不安におののく。そして人間というもののみじめさをなげく。そのようなものに、さし伸べられた救いの手は神を愛することによって神から認知されつつ、絶対の境地に入るという道であったのではあるまいか。 ・この場合は、キリスト教の伝道時代において、日本人一般に不安感がありながら、これを宗教的に救う考え方、手だてをもたないでいたところを、キリスト教が埋めにかかったということである。 ・神社神道は、もとより集団的信仰の対象であった。仏法はもともと個人の苦悩を客観視しつつ、その煩悩や苦難の運命を相対化して見直す悟りを導くものであったけれども、早くから日本では、家ごとの、家族ぐるみの信仰対象となっていて、やはり純粋個人の不安からの救済には、加持祈祷といったような密教的呪法くらいしか、すべてを教えなかった。 ・キリスト教は、そうした呪法を斥けつつ、個々人の安心をはかる道を示すことにより、帰依者を獲得できたのである。いわば、帰村の民間信仰を補完したのである。 各論 民間信仰の中での神・仏 Ⅰ 山の中の神 一 山岳信仰の起源と修験道 1 山岳宗教と山岳信仰 ・人間がこの世に現れて以来、生きるということは、不安感とともに生きることであった。 ・そこで人間は自分につきまとう不安を少しでもやわらげたり鎮めたりする努力をした。 ・ために人智を練っての工夫がいろいろ行なわれてきたが、そこに限界を感じると、何か無限絶対のものを観念的に要請して、これに帰一することをはかった。 ・あるいは、その不安の根源が、人間の原罪や煩悩にあることを悟る方向で、つまり内省を深める線で、その救済・解脱の道をさぐってきた。 ・ともに、それは一種の観念操作をはかることで、相対性・有限性をもつ人生に、絶対なもの、無限なもの、したがって力あるものを結びつけ、合一を求めるのである。 ・こうした生き方を、私は信仰を持った生き方とする。言いかえれば、安心の境地に浸りうるために、絶対無限の力ありと信ぜられるものへの合一化をはかる。それが信仰だというのである。 ・この絶対無限の力ありと信ぜられるものを神ということにもなるが、日本人における神は、ある集団にとってだけ、あるいは何か個々の特別なことについてだけ、絶対無限のものだとされた趣が濃い。 ・祖霊としての神とか、氏神とか、種々の職能神や地域の鎮守神などとかが、そのことを示している。 ・それぞれ限界を具えた無限絶対のもの、それが日本人の神であり、人間一般にとっての絶対者を想念することは、仏教やキリスト教の導入以前には無かったともいえる。 ・山岳信仰とは、人びとがその社会生活や個々の人生に伴った不安感を、山を絶対者としてこれに帰一することにより、やわらげ解消しようとつとめた態度である。 ・その場合、山そのものを神と観たものと、山を支配しているいわば主を神と観たものとがあったとされる。 ・前者については、たとえば、大和の三輪山は神体山だとされ、三輪神社はとくにその山の神の座を設けないといわれる。信濃の諏訪神社についてもそうした理解がされてきた。 ・しかし論理的には、山そのものを神と観た型と、山の主を神と観た型を分かつことが可能であるにしても、実際の信仰の中では、両者の峻別はなかなか微妙ではっきりさせられるものではない。 ・なるほど古典神話に現われる大山祇神は、山の主としての神というイメージで成立しているが、この神名が意味する「大いなる山の神」とは、山そのものに具現している偉大なる神と理解することも可能である。 ・山川草木・日月、すべての自然体を神と観たという原始信仰はたいていそれぞれの自然の神霊がこもるが故に神と観られたのである。 ・山にしても、その全容に神秘を思い、神聖感をおぼえるのは、そのうちにこもる神性によってであって、その神性を然らしめる神霊の潜在を信じたからである。自然体の各々にこもる神霊によって、それぞれが神体となるのであった。 ・大山祇神も、山の中にこもる偉大な神霊でありつつ、したがって、同時に山を支配する主としての神と想われたのである。 ・山岳信仰は、結局、山にこもり、かつその山の主ともなる神霊を絶対者と仰いで、それへの合一を求める態度であるといえる。 ・ところが一方では、人生や生活を不安にならしめる根源としての有力な神霊も山にいると見られた。 ・ということは、一つの山に、一つの神霊ということではなかったのである。 ・日本人の古い神観念にはニギミタマとしての神霊と、アラミタマとしての神霊と二種類あった。 ・後者のアラブル神に通じるそれは、人生を脅かす不安の種子になるものを蔵しているとしておそれられた。これもその面で異常にすぐれた力を含む霊なるが故に、神ではあった。 ・この類の神にたいしては、これをなごめ鎮めることにより、その人生への災厄となることを防ぎとどめようとした。これは信仰の対象となるものではなく、呪術を誘うものであった。 ・言葉をもってする、あるいは、たとえば性器を形どった石棒のようなものを据えるなど何かの道具をもって、またあるいは何らかの動作を通じて、いわゆるまじないとしての呪術を行うことで、アラミタマを鎮めおさえようとした。 ・山の神としてのアラブル神は、出雲、その他中国・四国地方に伝承してきている ・日本の山岳宗教史、あるいは山伏の修験道の歴史をかえりみると、呪術のことが頻繁に問題になるのだが、その素地は、山の神にたいする古来の古来の基本観念にすでにあったのである。 ・呪術をもって、悪霊的な神をおさえる役割を後世の修験者は負うていたが、その場合、鎮魂調伏者として、呪術を行うものへの信仰があった。念仏を唱えるのも呪術の一つであったが、後世においては、そうした呪術者としてすいぐれたものに帰敬し、これを絶対者として崇めるようになったのである。 ・そのような、特定の呪術者たる人格への信仰も現われていくが、そもそも原始形態での山岳信仰では、神信仰という側面のほかに、呪術を行うこと自体を絶対視して進行する側面もあったのである。 ・したがって、原始信仰というものには、神信仰と呪術信仰があったとしてよい。ともにその信仰により、人生を不安から安心へと転回させたのである。 ・山岳信仰でいうと、ともども山の神を想念して発するものながら、一方は直接に神との合一を求める信仰に、他方は呪術を介入させる行為との合一を求める信仰となっていた。 2 日本の原始山岳信仰 ・日本列島のどこに立っても、必ず山を仰ぎ山を望見できるほどの土地柄であるから、山にたいし何らかの思情が原始住民の間に当初からいだかれていたに違いない。 ・山には怪しげなものがいる。おそろしい形相のものがいるとの想いは、疫病などの流行が、山おろしの風のもたらしたものと見るのとも通じていた。それはアラブル邪神である。 ・いっぽうでは、天界から降臨する神の、里に迎えられる中継ぎの場も山である。 ・貴い神霊は天から山頂に降りて、やがて里人に迎えられ、祀られるとしたが、そうした降臨の神ではない、元来山の中に棲む邪神も考えられていたのである。 ・同様のことは、人の死後の霊についてもあった。 ・死骸とその霊魂とは、死後しばらくして離れるのだが、それは多くは山の方に、狭い離島では海上に赴くと信じられた。 ・山に赴いたものは、さらに時を経て天界に昇るとされた。 ・死骸を、山の裾に葬ったあと、遊離した霊はそのように山から天へと渡っていくとされるのが常だったけれども、普通の寿命を尽くしたものでない、疫病に斃れ、たたかいに中途非業の死を遂げたものの死霊は、そう簡単に山を離れていかない。その中の谷間などに低迷し、邪神に近いものとなって、後の里人の人生に妨げをすると怖れられた。 ・前者の死霊は、中国の言葉でいう人鬼である。人鬼は、唐の祠令で見ると、天神・地祇とあわせて、祭祀の対象となっていた。 ・日本の神祇令では、天神・地祇とは次元を異にするものとされ、神社信仰のうちには含まれずにいた――それで自然神としての天神・地祇を祖霊のように見なすに至り、氏神の祭神を祖先神化する向きのものもあった――が、一般の民間信仰としては山中他界観は著しいものになっていた。 ・山への信仰の一つの契機は、そうした他界観としてであった。 ・その中で後者の、いわゆる浮かばれざる死霊はむしろ仏教でいう「鬼」の概念で、おおわれたおもむきである。 ・仏教の鬼は、古代インドで、死後に供養されないとされたプレータ(梵語Pleta)の訳語で、『餓鬼事経』という教典までできたが、夜叉・羅刹などの凶暴な精霊をも含めて餓鬼道にうごめいているものすべてが鬼であった。そして地獄の獄卒にまでされている。 ・俗にいう浮かばれないでいる人鬼がいると見られた。 ・山中を死霊の赴く他界と観た中で、とくに仏教的に表現すれば成仏しきれないで、山間の谷間に低迷しているような霊もあるとされた。 ・一般の亡霊としての人鬼のうちで、そうした浮かばれない亡霊が、仏典の示す「鬼」にふさわしいとされていくのである。 ・仏教信仰が伝わる以前の時代から、山中に畏怖すべき魔性のもの、いわゆるアラブル神がおるとの見方があったので、仏教に触れてから、これを「鬼」の表象にまで仕立てていったのかと考えられる。 ・そうした鬼を鎮めおさえて、尋常の神と化すことにより、これを人の世、また人生の幸せを保障するものへと転換することが求められた。 ・言いかえると、日本の原始山岳信仰の中には、のちの仏教での言葉を借りれば「鬼」と観念されるにふさわしいような荒ぶる魔ものにたいする畏怖感がこもっていた、ということである。 ・その結果、仏教受容後の山岳信仰にも、また修験道でも、その開祖と伝える役行者が、山中で前鬼後鬼を従属する姿でたびたび表現されてきたように、山と鬼との関連は深まることになるのである。 ・一般に山の神霊を水分の神のように見て、人生にとっての恩恵的存在と見るふうが進んできたのと同様に、山の鬼もまた一般の死霊としての性格をもって観念されてきた。 ・前段には、山上に地獄を想念されたのに、やがて、ここに極楽が措定されるに至ったのは、鬼の見方が変化したからである。 ・死後山界で苦悩する人間の亡霊にたいし、念仏供養や真言の呪法を続けることにより、素直な親しめる亡霊になるとされた。 ・つまり聖や山伏が登場し山籠りの間に活動する時代になってから、中国での本来の鬼の意味でも見られるに至ったのだといえよう。 ・その基底にあったのは、人が死んだあと、その霊が山に赴くとの信念であった。山はそうした死霊のこもる他界なるが故に、霊気の充ちる、聖なる世界として信仰上惹きつけられてきたのである。 3 山の杜と呪術師 ・神社の所在を見ると、山ごとに神社があると言うのも過言でないほどに、山に在るものがすこぶる多い。多くはそれぞれの山の名をもって社名と称されている。 ・そのほとんどのものが、明治維新の廃仏毀釈によって、神社として独立したものであるけれども、山に在った寺院の地主神だったりして、古くからともかくそこに神が祀られていたのである。 ・ということは、仏教に山が占められる以前に、原始信仰をもって、各山々に神の存在が観念されていたことを示すものである。 ・その神を仏如来や菩薩が包みこむようにして、また本地にたいする垂迹の神であるかのように説くことによって、仏教が日本の山岳宗教を形成してきたのだと言ってよい。 ・もともと、神社として社殿が整備されたのは、仏寺建築の刺激をうけてからのことである。 ・ヤシロとは屋形をもってする神の依り代の意味であって、石なり樹木に神の依り代を定めてそこに依りつく神を祀るのが最も古い神祀りの仕方であった。 ・山の神の場合、まず山麓の里方にその祭場としての屋形が祭りの度ごとに仮屋として設けられたのが社殿として常設化し、さらに後に山内にも山宮が設けられることになったのである。 ・山に魔性のものが居るとの原始的観念、つまり仏教的にいう鬼がうごめいているとの観念が前提となって、そこにはこれをおさえ鎮める呪術師ともいうべきものが居た。 ・それは、中国から伝来する方術や、仏教の真言呪法に触れる以前から、固有の呪術を操るものであったろう。それはあるいはシャーマンの類であったかもしれない。 ・こうしたものの存在が、後の修験者、山伏の祖型になるのである。 ・役小角自身は山伏修行者ではなかったけれども、すぐれた山の固有的呪術師であったという点で、後世輪をかけてそのその呪術が喧伝されつつ、山伏の祖師のようになったのである。 5 修験道の展開 ・大峰の女人禁制は、明治以後も、他の山と違い、ここに限って解かれない。現代もだいたいそのとおりに守られていて、「是より女人禁制」の標柱が立っている。 ・仏教の影響以前から血の忌をふくむ女人にたいし、聖地としての山への立ち入りを禁ずる信仰があったかと思われるが、ここではさらに山伏修行をする男たちにとって、煩悩の一つが女色にあるとの考えもあずかっている。 ・こんにちの登山者にたいしても、真の宗教的登山を要求するところから女人の入峯をゆるすまいとするのが、大峰側の態度である。 二 山と鬼 ・鬼という概念を、もともとの日本人は知らなかった。天神・地祇・人鬼、この三つの類の神が中国にあった。 ・人鬼を日本では低次元においた。そして、むしろ、仏教の経典からの影響で、悪しき神、荒ぶる神、そういうものにこの「鬼」という字を借用して当てた。 ・一般の死者の霊を表わすのに、「鬼」という言葉を用いないで、妙な人に迷惑をかける、人生を妨げるようなもの、社会を乱すもの、そういう悪霊を対象にして、「鬼」という字を借りてきて表現しているわけである。 ・仏教伝来の鬼というものに触れて、日本人がこれはこういうものにふさわしいというふう考えたものは、ミサキとかユキアイ神という、ヒューと風のように飛んできて、首っ玉についたかと思うと、気絶させてしまうような、恐ろしい ・一般的に山から発したと考えられて、恐ろしい災害をもたらすとされた雷も、やはり「鬼」という文字を知ったときに当てるにふさわしいと考えたものであったかと思われる。 ・そういう前提というか、根底があるので雷を表現するのには、後々、鬼のイメージをもって、表象するということになったと思われる。 ・日本の山岳信仰の中で一番古い段階を、いろいろ考えてみると、そういった悪霊というか、人生を妨げるような迷惑をかける “spirits” が山に籠っているという考え方は、非常に普遍的なものがあったろうかと思う。 Ⅱ 仏教民俗と神信仰 一 仏教行事の民族的基底 1 仏教の伝来 ・仏教を日本人が受け入れるまでに以前から固有の宗教的習慣ないし信仰などの民俗宗教が存在し、そこへ仏教が伝来し結びついて、だんだんと変遷しつつ今日に伝えられたものと解される。 ・仏教の日本伝来以前にも、とにかく日本人はあらゆる部面で神信仰とか、呪術めいたものを持っていたのである。それとうまくマッチし、結びつきやすく、かつ古代の社会事情にも相応する格好で仏教が採り入れられた。 ・仏教のすべてが入ってきたのではなくて、やはり固有信仰の中にそれと触れやすいものの部分が、いわば抜き出されて日本人の社会生活に意味ある仏教になっていったわけである。 ・それゆえ、インド本来の仏教あるいは、中国・朝鮮での仏教と比較すると、やや異色ある仏教というものが、日本の宗教界に滲透してきたわけである。 ・つまり日本人の観念の根幹といったものがやはり軸になり、その軸を中心に仏教を摂取している。仏教は単に移植されたのでなくて、取り込まれた。 3 彼岸 ・春の彼岸、秋の彼岸、この彼岸に庶民は皆先祖参り・墓参りをする。 ・彼岸という言葉そのものは、パーラミッタという言葉から由来する。これも仏典に現われる言葉であるから、いうまでもなく仏教の概念である。 ・現実に対して、あるいは凡俗に対して悟りの境地である仏の世界としての彼の岸、これに到達する為の特別の精進を要する期間だというのが、春分なり秋分の日を中心にした一週間の彼岸である。 ・このようにいかにも仏教によって支持され、それによって伝えられてきたような彼岸ながら、本来の仏教にはそういうものがなかった。 ・中国では彼岸における特別の行事というものはない。やはり日本の固有の信仰と結びついたためではないかと思う。 ・民族学的に考えれば、日拝みは太陽信仰なのであるが、春の彼岸ならばこれからいよいよ日が長くなり、秋の彼岸ならばこれから日がつまってくる、という境目に立ち太陽にたいする関心が深まってくる。それで太陽を特別に拝むということをしたと思われる。 ・というのは、正確な暦を知るまではだいたい勘で平分になりそうな季節を選んだであろうが、文字で理解されるような暦を知るに至って、春分とか秋分に行うようになった。 ・この春分・秋分の日を仏教の方で利用して、たまたま日拝みを行っていたことから、ヒオガミ→ヒガミ→ヒガンとして、あるいは日の神への願いという日願にこじつけて、彼岸という言葉を選び、彼岸会を設けた。 ・そしてこの日を中心に、僧侶たちは、特別修学期間とし、あるいは一般の習俗からいえば先祖の供養をするのだということを呼びかけたので、民衆の方でも、この機会に寺に積極的に接近するようになったのではないか。 ・とにかく日本の仏教界で発明されたものである、ということは間違いなく言えるのである。 ・その発明は、結局日本人の民間信仰を無視しては仏教が伸びなかった、るいは普及しなかったところから起ったわけである。 4 盂蘭盆会 ・盆踊りというのは、新しい精霊の出たところ、そういう悲しみの深い家に挨拶にいく、念仏にいく、念仏踊りの戸別訪問であった。それを特別な送り膳でもするだけでやめてしまい、踊りそのものを誰々の供養とは考えないで、盆のフィナーレの一つの行事としてきたのである。 ・西川如見という元禄時代の学者は、日本の盆の行事は仏教の行事だけでは説明がつかない。それは仏教以前にすでに祖先祀りとして昔から行っていたことが仏教が入ってきて強化されたのだろうと、説明している。 ・つまり、古来から先祖の霊を祀るということを正月にも行ったし、後半年の始めの七月にも行っていた。そこへ仏教が入ってきた。それが、だんだん民衆に信仰を浸透させる都合で、ほんらい先祖祀りを行ってきたものとうまく結びついた。 ・だからもともと行っていたことを全面的に白紙に戻さないで、それを生かしながら仏教的要素を加味したから、今日の民間伝承に残っている盆棚を中心にした催し方には相当日本固有の習俗がみられるのである。 ・しかし肝心なのは盆に施餓鬼棚設けること、つまり一族以外のどこの何者ともわからないような普遍的な亡者にたいする施しをするための棚をつくることだった。 ・盆の機会に一般の人たちに、どこかに浮かばれないでうろついているような餓鬼・生霊にたいしての施しをすることが仏教としては大事な点とされたのではないかと思う。 ・盆踊りなども年中行事といえばいえるが、豊年踊りのようになっている。 ・豊年による現実の極楽化を願うものに弥勒踊りというのがある。これはこの世が開けてから五十六億七千万年が経てば、弥勒菩薩が 二 民間信仰の中の地蔵 1 日本までの地蔵 ・地蔵信仰そのものが全くインドにはなく、中国における所産ではないかと怪しまれる。 ・けれども「地蔵」という概念自体は、だいたい仏陀出世以前の婆羅門徒の間で、日蔵・月蔵・天蔵(虚空蔵)などと併せて、星宿の神として崇信されていたものではないかとされる。 ・地蔵信仰が中国の家族倫理と結びついて支持されていた。 ・地蔵は、隋唐代、末世破戒の比丘の擁護者として、今世・後世にわたって能き引導者となる。後世においては六道に苦しむものをなかんずくその遺族の修善を俟って救いあげるとされた。 2 平安末期の地蔵信仰 ・日本の知識人の間で地蔵のことが早く知られたことは、その関係の経典が奈良朝に写されていることでも認められる。 4 地蔵信仰の民俗 ・国境・村境に地蔵を祀ることは非常に多く、地名にもそれを思わせる痕跡がある。 ・たとえば、大菩薩峠には種々の古仏があるが、最も古いのは嘉永八年(一六三一)の銘をもつ地蔵尊である。 ・境にあってさえぎり守る ・ひいて村の内なる社会の土地を鎮め安んずる地神的性格をもたされ、密教でいう堅牢地神と融通して地蔵が想念された場合もある。 ・けっきょく、地蔵信仰が民間に受けいれられ普及するについては、日本人の神と子供との特殊の関係についての観念、ならびにかねて伝わってきた道祖神信仰、それと、中世以来とくに地蔵にたいして一切の救済を乞う、ほとんど身勝手なほどに救済の要求を寄せた態度、これらの三要素が大きな前提的契機となっていることを考えさせる。それがこんにちの地蔵信仰に関する民間伝承を複雑・豊潤に、しかも日本的に特色づけている理由となっていると思う。 ―― 完 ―― |