
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2023年02月10日 金曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク |
7 |
23.02 |
英仏百年戦争 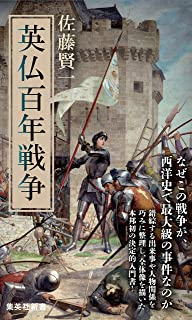 |
佐藤 賢一 |
集英社新書 |
◎ |
前史 一、それはノルマン朝の成立か イギリスか、イングランドか ・サッカーの国際試合など観ていて、イギリスからだけイングランド代表、スコットランド代表、ウェールズ代表と三チームも出ることがある。 ・アイルランド代表とフランス代表を加えて、ラグビーでは五ヶ国対抗戦も行われる。 ・これは遠く中世の時代にイングランド王国、スコットランド王国、ウェールズ侯国に分かれていた地域と、アイルランド王国として独立していた地域の一部が統合されてできた、「グレイト・ブリテンおよび北アイルランド連合王国(イギリスの正式名称)」の独自の歴史を背景とした現象である。 ・イギリスという日本での呼び方は「イングランド」が語源だ。 ・それぞれが独自の代表チームをもつように、連合王国の内実は歴史的にも文化的にも、日本人が気軽に「イギリス」と一括りにするほど、一本調子なものではない。 ・「グレイト・ブリテンおよび北アイルランド連合王国」の意味で受け取られるなら、中世にイギリスという国はないといわなければならない。 ・「英仏百年戦争」という場合の「英」も、ひとまずはグレイト・ブリテン島の南部でしかない「イングランド」のことである。 ノルマン・コンクェスト ・グレイト・ブリテン島は古来ケルト民族の土地だった。 ・四世紀に始まるゲルマン民族の大移動で、その一派であるアングロ・サクソン人が段階的に移住してきた。 ・このとき辺境に追いやられたケルト民族の末裔が、スコットランド人であり、ウェールズ人であり、またアイルランド人であるといわれている。 ・新たに渡来してきたアングロ・サクソン人が建てたから、イングランドというわけである。 後史 結、かくて英仏百年戦争になる 国民国家と歴史 ・国民国家が成立する以前は、当然ながら国民国家を前提にする発想がなかった。 ・中世ヨーロッパ、それも英仏百年戦争が新しい潮流をもたらす以前は、むしろ国の感覚など希薄であり、家や領地の感覚のほうが優先していた。 ・他方で国の感覚が全く欠落していたわけでもなかった。いや、この場合は国というより、ひとつの世界というべきか。 ・中世ヨーロッパの主役は長らく、イングランド王でも、フランス王でもなかった。イタリアのローマ教皇と、ドイツのローマ皇帝(神聖ローマ皇帝)こそは、舞台の中央を占める千両役者だったのだ。 ・人々は小さな家にしがみつき、ちっぽけな領地を必死に守りながら、同時に教皇を頂点とするキリスト教の共和国、皇帝を頂点とする世界帝国、つまりはヨーロッパという、いっそう大きな空間を強く意識していたのである。 ―― 完 ―― |