
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2024年07月01日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク |
10 |
23.03 |
がんばれ仏教! お寺ルネサンスの時代 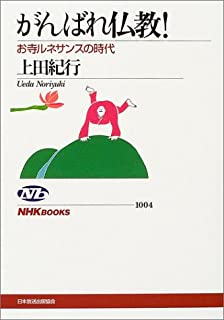 |
上田 紀行 |
NHKブックス |
☆ |
序章 仏教は面白い! 1 仏教ルネッサンス塾 仏教に期待しない人々 ・われわれの心の闇っていうことがこのごろ言われてますが、それを各個人が処理するようになっていて、社会全体でっていうのがないんですよね。みんないろいろとはき出してみようよ、とかいった場が。 仏教再生のために ・東京、愛宕にある青松寺が二〇〇三年五月、「仏教ルネッサンス塾」を開講した。 ・私は開講の辞にこう書いた。 「仏教とは何よりも人間の「苦」に向き合い、その原因を深く探求することで、そこからの解放へと導こうとする教えではなかったのでしょうか」 「ブッダにせよ、宗派の祖師たちにせよ、時代と真摯に向き合い、そこでの苦悩に寄り添い、立ち向かっていったからこそ、その教えは人人に力を与え、時代を切りひらいてきたのではなかったでしょうか」 ・青松寺は若手僧侶向けの集まりも始めた。その名も「ボーズ・ビー・アンビシャス!!」。 ・宗派を超えて、大志を抱いた若き僧侶たちが交流して、新しい動きを作っていこうというものだ。 ・「老師」のありがたいお話を伺う会ではなく、志を持てばこその悩みや葛藤もそのままぶつけ合える会、現在進行形の集まりだ。 がんばれ仏教! ・多くの人は仏教とは口先だけのものだと思っている。ありがたいお言葉だけで、何も行動しない。 ・言っていることがいくら良くても、行動がそれに伴わない人間は、口先だけの人間だと言われる。世の中では軽蔑されるタイプの人間だろう。 ・仏教の多くの僧侶は、言っていることもどこかから借りてきたような「いい話」に過ぎないし、行動も全くともなっていなように、多くの人々は感じている。 2 神宮寺――希望が生れる場 全国ボランティア研修集会 ・スリランカの「生きた仏教」を目の当たりにして、私は驚愕した。 ・スリランカでは仏教が人々の生きる支えになっている。僧侶は尊敬されているし、仏教はスリランカの文化の中核を担うものでもある。 ・僧侶の意識も違う。スリランカの僧侶には誇りがある。自分たちがこの国の宗教の中核を担っている。文化を担っている。歴史を担っている。 ・しかし、日本の僧侶で誇りを感じさせる人は少ない。威張っている僧侶はいても、何かを担っているという意識を感じさせる僧侶が少ないのだ。 第一章 生きているスリランカの宗教 上座部仏教とは ・世界の仏教は現在、スリランカ仏教のような ‹上座部(小乗)仏教› と、日本仏教のような ‹大乗仏教› に分かれている。 ・「小乗」という名称は「大乗」の人々からの蔑称なので、現在では「上座部」仏教と呼ばれている。 ・仏教にその二つの分派が生れたのは、ブッダが亡くなってから一〇〇年後の「根本分裂」と五〇〇年後に始まった仏教改革運動によるものである。 ・ ‹上座部仏教› は、ブッダが生きていた当時の教団の姿を時代を超えても守り続けようという仏教の姿である。 ・現在、スリランカ、タイ、ミャンマー、カンボジア、ラオスなどで行われているのが、上座部仏教である。 ・すぐ分かる見分け方としては、僧侶が黄色の衣を着ている仏教が上座部仏教ということになる。 大乗仏教とは ・当初の仏教とはブッダになることを目指す教えではない。ブッダの教えを厳格に守り、修行によって解脱を目ざそうというのがそれまでの仏教である。 ・解脱者のことを ‹阿羅漢› というが、目指すべき目標はブッダではなく、阿羅漢なのである。 ・ところが大乗仏教はブッダその人を偉大な存在と捉え、自らもブッダになろうと目指すのだ。 ・修行は阿羅漢になるためではなく、ブッダになるためなのだ。これは全く驚くべき発想の大転換であった。 ・新しい大乗仏教では、自らを ‹菩薩› だと自覚せよという。 ・菩薩とはそれまで、悟りを開く前のブッダのことを指す言葉だったが、その意味が拡大解釈されるようになり、ブッダの体験を追体験し、自らがブッダになろうと目指す者を菩薩と呼ぶようになった。 ・われわれもブッダになることを目指しているのであるから、一人ひとりが菩薩なのだ。 ・その菩薩の修行とは何か。それは「自利行」と「利他行」の二つである。 ・自利行とは自らの悟りを目指して行われる修行であり、利他行とは衆生を救済するという修行である。 ・ブッダその人は、瞑想と修行を行うという自利行とともに、悩み苦しむ人々に深く共感し、彼らを救済する利他行によって偉大なブッダとなった。 ・ゆえに、大乗仏教は利他行の重要性を強調する。そして上座部仏教は自利行のみで利他行を欠いていると批判する。 ・自分たちこそが衆生とともに歩む大きな乗り物なのであり、上座部仏教は自分が解脱することのみを目指した、劣った小さな乗り物であるとし、自らを ‹大乗› と呼び、上座部仏教には ‹小乗› という蔑称を与えたのであった。 ・日本仏教は大乗仏教であり、それは、現実の社会で苦悩する人びとにぎりなく共感し、自己犠牲をいとうことなく、衆生に奉仕する菩薩行をその根本としている。 ・すべての生きとし生けるものを救おうとする利他行としての仏教、それが大乗仏教であり、自分だけが僧院で瞑想修行を行い、自分だけが解脱を志す自利行の上座部仏教に対する痛烈な批判の上に大乗仏教は成立したのであった。 サルボダヤ運動の本部 ・サルボダヤ運動とは、仏教の教えに基づいて、農村開発運動を進めている有名な団体。 第三章 魅力ある寺・僧侶とは 1 秋田光彦(大阪市・應典院住職)――寺よ僧侶よアーティストたれ! 若者の集まる超モダンな寺 ・應典院の活動プログラム ◉Play(演劇) ◉Live(ライブ) ◉Talk(トーク・講演) ◉Seminar(講座) 学び・癒し・楽しみ ・葬式仏教と言われるが、寺が庶民の葬式の場となったのは江戸時代に檀家制度が確立してから後のことで、葬式仏教に特化したのは明治に入ってからのことだ。葬式仏教の歴史は実は短い。 ・逆に、仏教伝来以来一五〇〇年もの間、日本の寺は生活文化における拠点としての三つの機能を持っていた。それが「学び・癒し・楽しみ」だった。 ・まず「学び」だが、日本の教育史上最初に庶民に対して開かれた学校は、空海の創立した ・次の「癒し」だが、日本に仏教が渡来し最初に建立された寺である四天王寺は四つの施設からなっていた。「療病院」「施薬院」「悲田院」「敬田院」の四つだが、最初の三つは、順に、病院、薬局、家のない人やハンセン病患者の救済施設であり、最後の敬田院のみが儀式や修行を行う機関だった。 ・四天王寺にして、当時の総合医療センターであり、中世以降も高野聖など、寺に定住しないで行く先々の地域の問題に対応したたくさんの僧たちがいた。 ・最後の「楽しみ」、芸術文化だが、日本文化ではそもそも芸術、芸能は神仏に奉納する芸であって、それ自体が宗教行為だった。 ・お寺が新築したりするときの資金集めのための勧進興行などがお堂や境内で大々的に行われていたわけだ。 ・こう考えてみると、「学び・癒し・楽しみ」は仏教寺院がそもそも日本人の生活文化において担っていた機能だったのだ。 ・しかし、明治に入って、学びは学校へ、癒しは病院へ、楽しみは劇場や放送へと、行政サービスや商業的サービスへと奪われてしまい、寺に残った機能は葬式だけになってしまったのだ。 ・だから、「学び・癒し・楽しみ」をテーマとする寺にするのは、むしろ日本仏教の長い伝統に沿うものなのであり、その伝統の復興に他ならないのだ。 ・それに加えて、秋田は都会にある寺の住職としての「説明責任」(アカウンタビリティ)を強調する。 ・都会にある寺は、それだけの資産としての土地を占有していることに対して、寺がなぜそこになくてはならないのかという「存在理由」を社会に対して説明できなければいけない。都会の寺には自らの存在価値に対する「説明責任」がある。 ・そして単に檀家の葬式や法事をするからというのではなく、「学び・癒し・楽しみ」といった、共同体の中で伝統的に寺が担っていた役割をもう一回取り戻し、周囲のコミュニティーに開かれた寺になることが必要なのではないかと、秋田は考えたのだ。 教化情報センター21の会 ・まず浄土宗の若手の僧侶と一緒に「教化情報センター21の会」を結成した。 ・彼らが発行してきた「現代教化ファイル」という雑誌がすごい。A4版という仏教関係の雑誌としては珍しい大判の中に、ぎっしりと仏教をめぐる「問題群」が詰まっているのだ。 第1号 脳死・臓器移植を考える(生命倫理) 第2号 寺の子コネクション(後継者問題) 第3号 儀礼の経済学(布施と寺院経済) 第4号 出家とボランティア(阪神大震災と仏教者たち) 第5号 新・寺院解体新書(都市寺院の揺らぎ) 第6号 にっぽん葬式ビッグバン(葬儀) 第7号 お墓の未来学(墓のゆくえ) 第8号 出家の家族論(ジェンダー) ・この「現代教化ファイル」の編集長である、佐賀・専称寺住職の川副春海は、一九九四年一二月発行の同誌の編集後記でこんな思いを述べている。 「宗教ブームといわれつつも、学生諸君の ‹若さ› へのなんのアプローチもできないわれわれ伝統宗教の現状。浄土の教えにしても禅の教えにしても、日本仏教の核心は、現代社会に対して、またその中で格闘している ‹若さ› に対して十分にピュアできらきら輝いているメッセージのはずだ。そんな若い感性と伝統仏教との橋渡し、それが本誌の役目の一つだと思っている」 NPОとしての寺 ・タイ、ベトナム、インド……。そうした国でのNGO活動では、僧侶たちが活躍をしていた。社会的な活動から遠いと思っていた上座部の黄色い衣の僧侶たちが、寺が、活動の中心となっている。日本の寺が見失っている仏教の原型は実はアジアの国々にあったのだ。 ・秋田は確信した。そうして、NPOとしての寺、應典院ができた。 ・運営は「應典院寺町倶楽部」というNPOが行う。自分たちの使命を掲げ、その使命に賛同する会員を募り運営していくという、前代未聞のNPOとしての寺の誕生であった。 さらなる飛躍 ・どんな人間も、逃れられない老い、死に直面したとき、平等になる。しかし、それは悲惨なことではなく、そこにこそ慈悲の心が現われる場があるのではないか。 2 高橋卓志――真の葬式仏教とは 志、実力、そして場としての寺 ・ヤル気、実力、それを発揮する場の三つがそろったときに、僧侶は輝き出し、寺は輝き出すのだ。 ターミナル・ケア ・芥川賞作家である重兼芳子は『やまあいの煙』の中で、仏教を痛烈に批判した。 「現代社会の病んだ深層があり、だからこそそこに目を向け、動かなければならない仏教はいったい何をしているのか。仏教がいのちやその延長線上にある死を真正面から捉えず、過去の遺産の上にあぐらをかき、その遺産を食い潰すかのごとき行為をどう考えるのか。いのちの終末を迎える人々の苦悩や、家族の悲嘆を支えることもしないで、営利に走る仏教は宗教といえるのか」 ・彼女の目には、仏教が日常の具体的な問題や、一人ひとりのいのちとの関わりとはかけ離れた、学問のための学問に映っていた。 4 玄侑宗久――気づきの場としての寺 寺小説家の誕生 ・現役僧侶にして芥川賞作家、 仏教相対化の遍歴 ・玄侑の寺は福島県三春町にある、臨済宗妙心寺派 「和」を「積」に変える場 ・一九八九年に行われた催し「鼓舞一管・二つの春」のプログラムに、主宰者であり、仲間たちと作った 「人が出会えばそこに『和』が生れます。『和』とは足し算の答えでもあります。人それぞれのもてる力が、まるごと足し算されるような出会いを、今後も続けていきたいものです」 「聖徳太子の『以和為貴』をまつまでもなく、仏教では『和』を最も大切にいたします。和合第一であります」 5 南直哉――僧侶よ発心を持て 獅子吼林サンガ ・ ・この「サンガ」は、そもそも修行道場であった青松寺が、僧侶の学びの場、修行の場を復活させたものだ。定員は10名。 「問い」を欠いた住職たち ・僧侶と住職は違う。明晰な答えである。 ・発心して仏教者、出家者として生きる覚悟を定めた人間が僧侶だ。だから僧侶とは職業ではない。僧侶とは仏の道を歩むことを発心した者であり、仏弟子の自覚を持った出家者のことなのだ。 ・それに対して、住職とは寺の管理運営者という「職業」である。そして、南は発心のない人間が、家業の相続のために住職なってしまうことに、宗教としての危機を感じているのだ。 ・「発心が欠けてしまったままで住職になってしまい、宗教者としての自覚を欠いていることがいちばん怖いことだと言いました。それは、自分の中での発心が欠けていると、今の社会に生きている人たちが求めているものに対して、全く応えられないからなのです」 「現代社会は、孤独と不安の時代です。八〇年代くらいから、若者の間では生きることの虚しさが言われるようになってきました。それは『精神世界ブーム』といった形で、日常を超えた『精神世界』への期待を生み出しました。しかし、彼らの求める『精神世界』には既成仏教など全く入っていなかった。そのとき既に若者たちは既成仏教には何も期待していなかったわけです」 「そして不幸なことに、そうした『精神世界ブーム』のある部分は明らかにオウムのようなカルトにもつながっていきました」 「九〇年代に入って、八〇年代には先端的な若者に感じられていた不安が、一般的な若者全体に広がっていきます。そして、九〇年代後半に入ると、その不安や孤独感は中高年世代にまで広がっていきました。特に今までの決まりきった社会のしきたりに従って安定を得ていた中高年以上が、年金やリストラの問題にしても、もはや自分たちの住んでいる世界は安心できる社会ではなくなったという意識が、はっきり出てきたわけです」 「私たちがいま生きているこの社会は、不安や孤独が、中学生から高齢者まで広がっている社会です。自己のありさまの完全さ、安心できない状況に対して、世代を超えて、人々は疑問や不安を共有している。自分とは何なのか。どうしてこうなってしまったのか、という『問い』を誰もが抱え込んでいるのです」 「現在の『宗教ブーム』というのも、その時代状況によるものでしょう。しかし、現在の仏教は果たしてそれに応えることができるのか。自分自身が『問い』に向かい合っていない住職たちが、果たして人々の『問い』に応えることができるのか」 「八〇年代以降の社会の有り様や動きを考えたとき、僧侶は自らのあり方を問いかける視点と、その上での『発心』が絶対必要であろうし、それがある人が、仏教の可能性を開くだろうと思うのです」 ・私は現代日本人の根本問題は「孤独と空しさ」、そして「かけがえのなさの喪失」だと論じた。 ・貧困を克服すれば幸せになると走りつづけてきた日本社会、貧困を克服しこれだけ豊かになっているにもかかわらず、その中で私たちは孤独と空しさに苛まれている。それは、結局のところ自分自身の人生が自分のものであるように思えないからだ、 ・私たちが自分自身を「かけがえのない存在」だと思えないのがこの現代社会だ。「かけがえのない」とは何ものとも交換できない、それ固有の価値を持っているということだ。 ・しかし、今や私たちは自分がどこまでも「交換可能」な存在だと思い知らされている。私の価値が偏差値で表されるならば、偏差値の同じ人間なんていくらでもいるから、私はどこまでも交換可能だ。マニュアル通りに動く店員は、別に一人いなくなったところで、次のマニュアル人間が自分に置き換わるだけだ。 ・その「かけがえのなさ」の喪失感覚は、最初若者たちを襲った病だった。右肩上がりの経済状況に自己同一化してきた年長世代は、どうしてこんなに豊かな社会で若者たちが病に陥っているのかが理解できなかった。しかし、その病は時とともに年長者に広がっていく。 ・「私はこの会社で『かけがえのない』存在だ」と思いこんでいた社員が、簡単にリストラされる。「あなたくらいの人間はいくらでも代わりがいますから」と宣告される。リストラされた社員の自殺の問題は、単なる経済的な苦難によるものではない。そこにあるのは、安定していると思われた自分自身の価値が、一瞬にして踏みにじられ、虫けらのように扱われたことの、あまりの「空しさ」である。 ・今や「かけがえのなさの喪失」はすべての世代を襲っている不安であり、孤独感である。 ・自分はいったい何のために生きてきたのか。何のために生きていくのか。そもそも自分とは何ものなのか。世界とはいったい何なのか。 ・自分自身を右肩上がりの経済に同一化し、実存的な問いを発しなくてもやっていけた時代はもう終わった。そして、一人ひとりが自らへの「問い」に直面しているのがこの時代なのである。 ・しかし、そうやって人々が自分に対する「問い」に直面し、自己の生の方向付けのありかを求めているこの時代に、「住職になるために僧侶になった」という、「発心」なき僧侶に出番はあるのだろうか? ・自分の人生に対する「問い」のない者が、この現代社会の中でどうしようもない「生き難さ」を感じ、切実な「問い」を発している人たちに対して、生きた言葉で答えることができるのだろうか。南はそう問いかけているのだ。 第五章 ‹ホトケ› はどこにいる? 1 ‹ホトケ› 探しの旅 葬式の弱体化 ・なぜ伝統仏教は「葬式仏教」と批判されるのだろうか。それは一つには寺が葬式や法事だけをやっていて、他には何もしないということへの批判である。 ・しかし、そこにはもう一つの大問題が隠されている。それは、葬式だけをやっている仏教の、その葬式そのものが形骸化し、人々を納得させるものになっていないということである。 ・日本仏教が「葬式仏教」と批判されるのは、葬式ばかりやっていて人々の苦悩や社会問題に向き合わないという批判であるとともに、その葬式自体が全く人々を納得させるものとなっていないという、二つの要因が重なっていることによるものなのである。 ・その原因として、寺という場の不透明さを挙げた。 ・しかし、葬儀の弱体化にはもう一つ大きな理由がある。それは、 ‹ホトケ› とはいったい何なのか、誰なのか、という葬儀において決定的に重要な核心部が、今、大きく揺らいでいるということなのだ。言い換えれば、 ‹ホトケ› が見失われようとしているということだ。 ・宗教人類学者の佐々木宏幹の著書『‹ほとけ›と力』より ①最近の葬儀は例外なく仰々しいだけで迫力がない。 ②その原因は争議を司る僧に迫力がなく、遺族にも迫力が欠けていることによる。 ③具体的には、僧は凛として葬儀をリードしコントロールすることができていないし、参列者もだらだら並び順銀に焼香して帰るだけである。 ④こうなった理由は、僧だけでなく、教団や教学者も含めて、仏教界全体にはびこるコンプレックスにあると考えられる。 ⑤葬祭仏教は仏教の本流ではなく、仏教が本来やるべきことではないのだが、仕方なしにやているのだという意識を仏教界全体が持っている。 ⑥その背景に明治以降の仏教学がある。近代の仏教学は観念的に仏教の経典や教理を教えるだけで、実際に人が死去したときにどのように対処すべきかを教えなかった。僧の養成機関も教団人も、こうした影響から抜け切れず、結果として僧自身が葬祭コンプレックスをもつにいたったと考えられる。 ・葬式における僧は、死者をして「この世」から「あの世」に引導するという聖なるスペシャリストでありながら、その僧侶自体が特に若い世代になればなるほど葬式の意味づけが不明確になっているというのだ。 「あの世」はどこへ行った ・佐々木はそうなった大きな要因として、「あの世」とは何か、「ほとけ」とは何かと言う、葬式においては極めて重要であるはずの ‹あの世› ・ ‹ホトケ› イメージの弱体化、風化、崩壊が、宗教者においても進行しているのではないかと言う。 ‹ホトケ› の死 ・「仏」をブッダの意味に、「ほとけ」をこれまで日本人が伝統的に抱いてきたホトケのイメージとして捉えるものとすれば、「仏」と「ほとけ」は相容れない概念ではない。 ・日本人が伝統的に担ってきた「ほとけ」とは、「仏」と「タマ」(霊魂)の複合した概念であった。 ・「仏」とは仏教教理の説く「覚者」の意味と、民間信仰における「霊魂」の、両方の意味が含まれている。 ・「ほとけ」とは仏教思想と民俗信仰(アニミズム)との接触・交流の過程で生成してきたものであり、その意味は曖昧かつ弾力的だ。 ・「「ほとけ」と聞いて日本人が思い浮かべるのは「ブッダ、覚者、死者、死霊、祖先、祖霊」といった、幅広いイメージなのである。 ・仏教が日本に伝来したとき、ブッダその人も「ほとけ」と呼び、死者も「ほとけ」と呼ぶという離れ業によって、それまでのアニミズムと仏教が接合され、そこに日本仏教の独自な世界が展開してきた。 ・日本仏教とは、「仏」信仰ではなく、「ほとけ」信仰であったのである。 2 「苦悩」から未来をひらく 苦悩と現代性 ・仏教の実践論の根幹をなす「 ・「苦」があるとき、その苦をすぐに取り除こうというのではなく、「集」、すなわちその原因を深く探求しようというのが仏教の教えであった。 ・例えば、なぜ私たちが、老いることが分かっているにもかかわらず、老いを悲しむのかといえば、それは「若いままでいたい」という願望があるからだ。 ・なぜ若いままでいたいのかと問えば、「若いほうが価値がある」と思っているからだ。しかし本当にそうだろうか? ・若いほうが価値があるというのは単なる一つの味方であって、正しい見方、「 ・そして、一つの見方に固執して、「苦」に陥るのはいかがなものか、必ず老いていくのに「若さ」に執着するのはいかがなものか、と「苦」を転換させていくのが仏教的戦略なのである。 ・自分の実存に深く関わる苦痛に関しては、それを立ち止まって深く探求することで、生の新しい次元を開き、「苦」を転換していこうという態度こそがそこでは求められているのである。 「苦悩」がひらく現代日本の救い ・現代日本人の直面している「苦」とは何だろうか。多くの人たちはそれを「不況」だと言うかもしれない。経済的状況が悪くなったので、人々の元気がない。リストラされて自殺する人も続出している。「不況」こそが「苦」なのだ、と。 ・しかし、そこですべてを不況のせいにできるならば、問題は単純だ。 ・しかし、私たちの多くが既に気づいているのは、私たちを今襲っている問題の本質は、単なる不況に帰せられるものではなく、もっと根深いものだということだ。 ・なぜ不況になっただけで私たちは元気がなくなるのか。なぜリストラされただけで自殺してしまうのか。なぜこの豊かな社会の中で若者は荒れるのか。なぜこんなに豊かになった日本で、昔より年寄りは空しいのか。 ・例えば、私の滞在したスリランカには、失業してもニコニコして暮らしている人たちがたくさんいたし、もっと貧しい経済的状態で幸せそうに暮らしているお年寄りもいた。サルボダヤ運動でも、学校でも、自分の国の将来を目を輝かしながら語っている若者たちがいた。なのに、なぜこんなに豊かな日本で、私たちは今このような状況に陥ってしまっているのだろうか。 ・そう考えてみると、私たち日本人を今襲っている様々な「苦痛」は、単に不況が引き起こしたものではないことが分かる。 ・私たちを苛んでいるのは、「苦痛」の向こう側にある「苦」の構造なのである。その「苦」の構造は、右肩上がりの時代には、そのめざましい経済成長の影に隠れていた。しかし、その右肩上がりが停止し、不況に直面したとき、私たちはそこに隠されていた「苦」に向かい合わなければいけなくなったのだ。 ・それは、現代日本人を襲う不安と孤独感である。 ・それは「私自身が誰であるか分からない」という、自分自身の存在への不安である。 ・そして、背景には私たちが「交換可能」な存在であると強く認識させられる社会状況があり、私たちが自分自身を「かけがえのない存在」だと思えないという、人間にとって根本的な「生き難さ」が存在している。 ・自分の人生が自分のもののように思えない。何で自分がここにいなければならないのかが分からない。 ・不況の克服ならば、政治や経済の施策で解決するかもしれない。しかし、こういった「生き難さ」はいったいどうしたらいいのか? それが私たちの射会が直面している南門なのである。 ・そして、その難問こそが、この日本社会が長く続いた右肩上がりの時代の中で、取り組むことを忘れてきた問いのであった。 ・そして、私はここにこそ、仏教の出番があると思うのだ。 ・もちろんそれはこれまでの「時代の苦悩に向き合わない」仏教ではない。この時代の苦悩に向き合い、そこに現代の ‹ホトケ› を現れ出でさせる仏教、真の「現代仏教」の出現こそが今求められているように思えるのである。 ‹信頼› の喪失 ・私たちはこれまで、自分の学校の成績に応じて、なるたけ「いい」学校に進学、「いい」企業に就職するのが、「いい」生き方なのだとでもいうような教育を長い間受けてきた。 ・しかし、その「いい」「悪い」を判断するのは誰なのかといえば、それは社会であり世間であった。 ・社会の大多数が、世間的な「いい」の基準を受け入れてきたのが、この社会だといえるだろう。 ・この社会の経済的なパフォーマンスが極めて優秀で、世間が「これがいい」と命ずるままに動いていれば、しっかりと経済的な利得は得られてきたからだ。 ・別に自分の頭で考えなくても、世間的に「いい」とされる生き方をしていれば、儲かっていたし、幸せだったのだ。 ・しかし、そんな右肩上がりの経済成長は停止した。そして、これまで機能してきた「いい」生き方に利得が伴わなくなってしまう。 ・「いい」生き方をしていたのに、ある日突然会社からリストラされる。「いい」生き方をしろと教えられて、その通り走り続けてきたのに、就職できない。「いい」奥さんをやっていれば一生幸せだと言われてきたのに、何でこんな苦労をするのか……等々。 ・現在の日本を襲っている悲劇は「いい子」の悲劇だ。皆から期待される通りに歩んできた「いい子」たちが期待通りに歩んできたにもかかわらず、切り捨てられ、失意に沈んでいるのである。 ・ならば、景気を回復させて、失業率も低下させ、「いい子」の利得を回復させればいいではないか、それで問題は解決するだろうと経済人は思うだろう。確かにそれで表面上の問題は軽減するに違いない。しかし、それは決して問題解決にはならない。 ・というのは、私たちがこの時代で失ってしまったものは、単なる経済的利得なのではなく、真に失われたものは、社会への、そして自己への ‹信頼› だからである。 ・右肩上がりの時代、私たちは会社を信じていた。会社はもちろん利益を生みだす組織だが、そこには人々のつながりがあり一体感があり、互いが互いを幸せにする共同体なのだと信じてきた。 ・その時代、私たちは地域共同体や行政を信じていた。しかし、景気が後退し長期不況に陥る中で私たちが気づかされたのは、そうやって「皆が皆の幸せを祈りながら助け合う場」だと思われていた会社や共同体や行政の姿が「幻影」でしかなかったということである。 ・金がなければ、弱い者から切り捨てられる、そうなれば誰もかばってくれない。老後の面倒は自分で見なさい。ただ孤独に置き去りにされるだけだ。 ・あの「共同体」は「幻影」だったのだ。それが私たちの実感だ。 ・「この世の中は単なる約束事でできているのではないか。こんな約束事なんてやーめた! となったら崩壊してしまうのではないか」。そう、世の中は「約束事」でできていたのだ。 ・お金があるのでその約束事を皆が守っていたのだが、金がなくなったとたんに「それって単なるお約束だったでしょ」と言われてしまったのだ。 ・私たちは「世間」を信頼していた。しかし、「世間」は単なる「お約束」だったのだ。会社も地域共同体も「お約束」だったのだ。皆が「お約束」を守っていたから、それは信頼できる「実体」だと見えていたけれど、それは「幻影」なのだった……。私たちが失ってしまったのは、そうした「信頼」なのである。 ・そして私たちはいま叫んでいる。「お約束」を信じて、期待通りに「いい子」をやってきたぼくをどうしてくれるんだ。あんなに確かだと思われていたものが、今さら幻影だなんて、そんなこと言われても……。 ・諸行無常、諸法無我。ある関係性の中で生じた、一つの形、一つの意味、それが実態だと思い込んでしまうことから生じる「苦」。私たちはそんな「苦」に直面しているのだ。 「処世術」から「処生術」へ ・私たちの幸せを保証していた「世間」、言われる通りに行動していればまあまあ幸せな人生が送れた「世間」が崩壊してしまった。 ・私たちの孤独と不安は、私たちが生まれ育った地であり、信じきってきた「世間」から放り出されてしまったという、「故郷の喪失」から生じている。 ・しかし、このような苛酷な状況に置かれた人たちに対して、これまでの仏教は何も救いの手を差しのべることができなかった。 ・なぜならば、その仏教もまたそうした「世間」を基盤にしており、そんな「世間」が幻影であることにも気づかず、「世間」の中での安定した役割に満足してきたからである。 ・南直哉はこんなふうに語っていた。 「もう田舎でも、ありがたいとかおかげさまの話を歓び、当たり前のように聞いていた世代は、明らかに消えつつあるわけです」 ・しかし、今までの「ありがたい話」とはいったい何だったんでしょうね、と私は聞いた。 ・「要するに、高望みしないで地道に生きなさいというのが多いと思いますよ」 「諦めなさいが、ありがたいんだ」 「禅宗あたりだと今の自己に徹しろという言い方になりますね。しかし、それが悪く解釈されてしまうと、人間が目的を持ったり、反省したり、決断することを繰り返して生きていくものだという視点はなくなってしまう。自分の人生において決断する主体は自分なのだという視点がすっぽり抜けてしまうわけです。今ここでの自己の有り様は誰が決めるんだと言ったとき、それは会社だとか、地域共同体だとかになってしまうわけです」 「なるほど、ありがたいありがたいと言いながら、世間のいいなりになってしまう。うなると、仏教は自分に対する根本の問いを発しない、単なる処世術になってしまう」 「そうです。その処世術というのも、『生きること』に処するという、『処 ・「処世術」と「処生術」の違いの指摘は鋭い。 ・これまでの仏教は、ありがたいありがたいと言いながら、世間の流れに逆らわずに自分の人生を処していこうという、「処世術」になってしまうことが多かった。それは、「世間」の調子が良かったときは一見機能しているように見えた。 ・しかし、今やその安定していた「世間」が崩壊してしまったときに、「処世術」を志向していた仏教もまた瀕死の状態に陥ってしまったのである。 ・「処世術」の無効化といえば、この本に取り上げた僧侶たちの共通点の一つに、「オウム真理教事件」への関心の高さがある。 ・彼らの誰もが何であの若者たちはオウムに行き、そしてあのような忌まわしい事件を引き起こしてしまったのか、ということを我がことのように考えていた。 ・それは、彼ら僧侶たちが、若者たちをオウムに走らせたのが、まさに「世間は虚構だ」という思いであったことを知っているからだ。 ・それに対して仏教は、「世間」が元気なときにそれにおもねり、それ故「世間」が崩壊したあとも何も発言できないでいる。 ・そもそも仏教とは「世間」を超える知慧への希求であった。「世間」にいては見えない知慧を獲得するために、「世間」を出ること、それが「出家」だった。 ・だからこそ、「世間」で傷つき、絶望した人々の苦しみに、それを超える知慧を示すことができたのだ。 ・とすれば、「世間は虚構だ」とメッセージを発し、「出家」主義を取ったオウム真理教に対して、そこで問われているのはひるがえって現代の仏教のあり方自身なのだ。 ・世間に処する「処世術」ではこの時代の「苦」を救うことはできない、私たちの「生」そのものに処する「「処世術」でなければならない。それは仏教のそもそもの基本認識であるとともに、現代における「目覚めた僧侶」が共有して持つ基本認識なのである。 「苦悩」が真の「個性」を生む ・となれば、この時代の「処生術」はいかにして可能になるのだろうか、と考えるとき、そこでは人生の「苦悩」が、そして人生への「問い」こそがその中核となるのである。 ・これまで私たちは、なるたけ苦悩が少ない人生が良いものだと思ってきた。世間から求められる「いい」人生をそのまま受け入れ、葛藤することなく歩んでいけば、そこに苦悩はない。 ・しかし、そうした生き方は、より大きな「苦」に私たちを直面させることとなった。 ・例えば、学校でいい成績を目ざし、その成績に応じていい大学に入り、いい企業に入る、などという人生は、別に私でなくても誰でも歩むルートだろう。この成績だからこの大学に入る。今世間で人気があるからこの会社に入る。というのでは、その選択は自動的であり、ロボットでもできる選択だ。 ・フリースクールで話をしたとき、そこには不登校で学年が遅れてしまった悩める子どもたち、そして心配そうな顔をしたなやめる親たちが集まっていた。 ・そこは決して明るい場ではなかった。しかし、私は誰もが生きることに真剣なその場に、むしろエネルギーを感じた。 ・皆さんは、学校に行けなくなって何年か学年も遅れてしまって、たいへんなことになったと思っているかもしれません。 ・でも、一六と一八というのは大きな違いに思えるけれど、四六と四八なんていうのは全然関係のない年の差です。 ・だから、今ちょっと寄り道をしたなどということは、人生の中ではあまり気にすることのないことです。 ・それよりも、皆さんは今きっと苦しい思いをしていると思うのだけど、その苦しみの中で出会ったことが、きっと人生の宝になるのです。 ・もし皆さんがお父さんやお母さんの期待通り、学校の先生の期待通り、いい成績を取っていい大学に行ってというコースを歩んでいたら、それは一見幸せで、何の問題もないように見えるかもしれない。でも、皆の期待通り歩むだけで、これが本当の自分なのかと悩むかもしれません。 ・皆さんはそのことに疑問を感じて、ちょっと一休みしてしまった。でもそうすることで、いろいろなことが見えてきたはずです。 ・学校からちょっと離れることで、いい成績を取るということを離れて、むしろ何かに興味が出てきたかもしれない。 ・自分は獣医になりたいなとか、花屋さんがいいや、とか何かが見えてきた人もいることでしょう。 ・ぼくもノイローゼになって、カウンセラーに通い、学校も一年遅れたけど、そのときに人生についてたくさん考えました。 ・人生で何が大切なのか。何は捨てても良くて、何にこだわるべきなのか。もちろんその一年間だけではなかなか見えてこなかったけど、それはぼくの将来を考える大きなきっかけになりました。 ・そして、その苦しい時代にぼくは親友と呼べる友人たちに出会いました。 ・すいすいと抵抗なく歩いていく人生もいいでしょう。でも、何か疑問を感じてしまって立ち止まってしまう人生、それもいいものです。 ・皆さんはきっとぼくの年齢くらいになって思い返すことでしょう。皆の期待通りに進んでいたら、それは他の人と変わらない人生だけど、壁にぶち当たって悩んで苦闘したあの何年間は誰とも交換できない自分の人生そのものだったって、 ・そして、そんな「かけがえのない」自分に出会うことができた人は、その分ちょっと自信がついたり、自分の人生にこだわりを持つことができるのです。そして、それもまたぼくたちが生きていく大きな宝物となるのです。 ・いかに「苦悩」しないで歩んでいくか、「処世術」にはそれが大切かもしれない。しかし、「処生術」は違う。私たちはむしろ「苦悩」に直面し、その意味を深く探り出すときに、他者と交換不可能な「かけがえのなさ」を見出すのだ。 ・若者の苦悩が「生」の問いだとすれば、「老・病・死」もまた「処生術」をもたらす大きなきっかけだ。 ・大病を患って生き方が定まったという人は多い。入院中に、人生で捨てられる部分は何で、大切なものは何かが分かったというのだ。 ・病はもちろん「苦痛」である。しかしその苦痛の中で「苦」を見つめ、人生を転換し、より意味深い人生を始める人は少なくないのだ。 ・「苦悩」の中での「問い」、それが私たちの「かけがえのなさ」を回復させる。 ・現代に生きる私たちを襲う「生き難さ」は、「違和感や葛藤、苦悩はないほうがいい、それらが出てきたらすぐにたたきつぶそう」といった、「苦悩」に対するネガティブな意味づけによるものなのだ。 ・私たちは苦悩によって人生の意味を深める。そして、苦しみの中から「かけがえのなさ」を回復する。「苦」に向かい合う仏教の「現代性」はまさにその点にあるのである。 ‹正しいが無意味› を超えて ・仏教が現代的であり得るためには、一つの転換を成し遂げなければいけない。それは、「説く仏教」から「聴く仏教」への転換である。 ・これまでの仏教は、「真理を説く」仏教だった。正しい教えを説けば、人びとは救わるだろう。だからブッダの教えをできるだけ正確に説く。宗祖の教えを間違いなく説く。宗祖の示した修行法を間違いなく伝える。これが「教化」であった。 ・しかし、「説く仏教」は限界にぶち当たっている。それは現代の苦悩に届かないのだ。言ってることが正しそうなのは分かる。しかしそれが私の苦悩とどう結びつくのかが分からない。 ・私の苦悩という「個別」の苦悩に向かい合い、その「苦」の構造をあぶり出すことから私は「かけがえのなさ」を回復していくのだとすれば、その「私の苦悩」との関連が分からない「正しい教え」をいくら聞かされても、全く何の役にも立たないのだ。 ・これまでの仏教の抱えている大きな問題は、 ‹正しいが無意味› だということだろう。正しいことを言っていそうなのだが、私にとって無意味であるような説き方が多いのだ。 ・ふつうの坊さんは説教をしてしまう。それはあなたの心が生み出しているものだ、とか、執着が生み出しているものだ、とか。 ・そして、その発言は目の前の人よりもちょっと上の方から投げかけられる。対等な参加者としてではなく、「自分は知っている」という立場から「知らない」あなたに対して、教えを諭す口調で降ってくるのである。 ・あなたの心が葛藤を生み出している、執着が戦いを生み出している、煩悩のもたらすものだというのは、きっと結論としては正しいのかもしれない。しかし、多くの僧侶の場合、その到達点に達するための手段もアドバイスも持っていない。 ・「自分をよく見つめて」とか、「足ることを知れ」とか、「まずは坐ってみなさい」とか言うのだが、だいたいが結論の言いっぱなしだ。 ・結論は正しそうだから、そう言っていれば間違いはないだろう。そして、言われていることが正しそうなので、いわれたほうはそれに反論はできないから、「その通りです」と答えるしかない。しかし、そこで何か判然としないものが残るのだ。 ・正しそうだが役に立たない言葉。正しそうだが無意味な言葉。それに、この人は誰に対しても同じことを言っているのではないか。別に私でなくても、誰ら対しても同じ答えなのではないか、と疑念を持ってしまう。 ・しかし私が何かを言う前に既に答えは出ているならば、彼は私の悩みを、苦しみを聴いたと言えるのだろうか。 ・「縁起を生きない言葉」、状況から孤立した「教え」を繰り返されても、私はむしろ私自身が「交換可能」な人間として扱われたという空しさを感じてしまうのだ。 ・多くの僧侶の物言いに感じられるのは、「私の人生」と「正しい教え」の間をつなぐものの欠如だ。 ・彼らのまなざしは現実に生きている人間のほうではなく、「正しい教え」の方を向いている。その「正しい教え」は最終兵器だから、それを用いればみんな納得するだろうと思っているのだ。 ・しかし、私たちが納得するのは、「私の苦しみ」が私の個別の問題として聴かれ、そこから次のステップに踏み出すときである。聴く前から用意されている解答を示されても、私たちは納得できないどころか、何かバカにされた気分になってしまう。 ・誰にでも々「正しい教え」を説教していることからは、永遠に説教しつづけるという行動しか生まれない。しかし相手の苦悩を聴き。受けとめるときそこには新たな行動が生まれる。 苦悩の表出と悪の相対化 ・スリランカの農村では、悪魔が憑けば村人総出の楽しい悪魔祓いで祓ってくれる。とすれば、悪魔は来るべきときには来てもらったほうがいいということになる。 ・悪魔は決して歓迎される存在ではないが、しかし実は悪魔のいる社会のほうが、人間にとって優しい社会なのではないか。 ・どんなに「苦悩」を抱えていても、それが「自己責任」のもとに切り捨てられてしまう社会は冷たい。悪魔が来ているのに、誰も悪魔祓いをやってくれない社会は冷たい。そして、自分に悪魔が来ていることさえ、誰にも言えない社会はもっと冷たい。 ・じつは、誰でも心の底では、傷ついている人を助けたいと思っている。苦悩している人の力になりたいと思っている。しかし、毎日の生活は忙しいし、そんな善人面して生活するのも嫌だから、私たちはそんな気持ちを押し隠している。 ・しかし、悪魔祓いの場が設定されたらどうだろうか。私たちはその場に足を運ぶことで、隣人を励ましてあげることができる。苦悩を受けとめてあげることができる。そこでは、私たちは普段隠されている「慈悲」の心を顕わにすることができ、それは私たちの「慈悲行」となる。 ・しかし、悪魔憑きになった人は「慈悲」を受けるばかりかというとそうではない。自分が苦悩し、悪魔憑きになったおかげで、人々の「助けてあげたい」という「慈悲」の心を呼び起こし、人々を「慈悲行」へと導いたという意味で、彼/彼女も「善行」を積んだといえるのだ。 ・「苦悩」を表出すること、それは私たちの共同体を回復する、大きなきっかけになる。 ・私の苦悩なんて、誰にとっても迷惑だから、自分の中にしまい込もう、しまいこまなければいけないという社会は、苦悩する人間にとって冷たいだけではなく、その周囲の人間にとっても冷たい社会なのだ。 ・悪魔はいたほうがいい、悪魔のいる社会のほうが実は温かい社会なのである。 ・そしてもう一つ、この悪魔祓いは悪魔を抹殺する儀式ではないことに注目してほしい。人々は最後に悪魔と腹の底から笑い合う。そして、悪魔も供え物を取ってハッピーに去っていく。 ・これには神話的な裏付けがある。ブッダと悪魔が出会ったとき、悪魔はブッダを何とか倒そうとして、様々な超能力を使ったのだという。だが、何をやっても、ブッダの「徳」の力には勝てなかった。悪魔は敗北を認める。 ・しかしブッダは悪魔に言ったという。「ではあなたには、人間に一度だけ憑いて病気にすることを認めよう。しかし供え物をもらったら、気持よく去ると、私に約束しなさい」。 ・何と慈悲深くエレガントな結論だろうか。この民族的な儀礼の中には仏教の「悪」に対する深い洞察が生きている。 ・「悪は相対的なものだ。そして「悪」もまた縁起の中で生じるものだ。悪魔は悪魔の国ではいいお父さんなのかもしれない。しかし、人間の国に来ると悪さをして人を苦しめる「悪」となる。しかし、その苦しみに直面することで、人はむしろ大切なものに気づかされる。そして、最後には悪魔も人間もともに幸せになって、悪魔祓いは終わるのである。 ・仏教における「悪」は相対的なものだ。「悪」も縁起で生じる。誰だって善と悪の両面を持っている。調子のいいときは善でも、悪い関係性・縁起の元では悪事をはたらいてしまう。 ・だから「悪」が起こったときには、何が「悪」をもたらしたのかという原因を考えなければいけない。悪事を起こす人を見たら、なぜ彼が悪事を起こすに至ったのかという縁起を見なければいけない。 ・この「悪」の相対性は、西洋のキリスト教的な「悪」とは全く違う。 ・キリスト教においては、悪は絶対的な悪だ。世界には「悪」があるのであって、その存在自体を抹殺しなければいけない。だから西洋の「魔女狩り」などは陰惨なものになる。悪魔は殺さなければいけない。悪は根絶やしにしなければいけないのだ。 ・こう見てくれば、現在の世界情勢が、キリスト教的な「悪」の概念から生じていることは明らかだろう。 ・自分を攻撃するものは「悪」であり、それはこの世から抹殺しなければならない。その論理が世界を覆っている。そしてその論理によって、世界の平和はますます脅かされ、罪もない命が日々失われている。 ・キリスト教は「愛」の宗教でもあるが、「悪」に対する硬直した解釈のみが強調され、政治的に利用されることで、世界は「愛」から遠く離れた状態に陥っているのだ。 ・自分を攻撃する「悪」はなぜ「悪」になってしまったのだろうか、という縁起を考えることがなければ、この問題は決して解決することはないだろう。 ・また、自分の側も自らの中の「悪」を見つめることなしには、和解はありえないだろう。 ・世界には圧倒的な富と機会の不平等がある。貧しいものは努力しないから貧しいのではなく、最初からその機会を奪われているから貧しいのだ。 ・その構造を放置したまま、現れてくる「悪」を抹殺しつづけても、次から次へと「悪」は現れるはずだ。 ・それはその「悪」の背景には「苦悩」があり、その苦悩に向かい合うことなしに問題の解決はないからだ。 ・世界の平和は八正道を連呼するだけではもたらされない。世界に現れている「悪」の向こう側の「苦悩」を見ること。そしてその「苦悩」に向かい合うことこそが問われているのである。 ―― 完 ―― |