
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2023年04月30日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク |
13 |
23.04 |
原発事故を問う ―チェルノブイリからもんじゅへ― 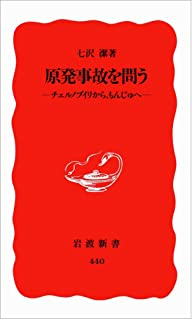 |
七沢 潔 |
岩波新書 |
◎ |
第一章 「パニックを回避せよ」 チェルノブイリ・事故と政治① 一 はがされた秘密のベール 情報公開とソ連邦崩壊 ・ペレストロイカ、グラスノスチの浸透とともに、いったん情報公開が始まると、それまで何も知らされず、沈黙させられてきた人々の憤りは燎原の火の如く燃え広がり、汚染地帯のウクライナや白ロシア、事故処理作業者を多く送り込んだバルト三国では、やがてその炎が民族独立の動きの重要な発火源の一つとなっていったのである。 第二章 隠された事故原因 チェルノブイリ・事故と政治② 一 運転員たちの汚名 制御棒の構造的欠陥 ・当時の国家原子力安全監視委員会の副委員長、ニコライ・シュテインベルク 「実は原子炉の欠陥が真の事故原因だったことは、八六年五月の段階で、政府の事故調査委員会、そしてソ連政府の上層部にまでも、十分よく知らされていたのです。その証拠に、事故後すぐにRBMK型原子炉の制御棒の改良をしています。それにもかかわらずソ連政府はあの当時、意識的に偽の情報を世界の前に、そしてソビエト国民の前に出していたのです」 二 ‹原子炉の欠陥›は、こうして隠された ・ソ連政府は事故発生直後から「原子炉の欠陥」を知っていた、というシュテインベルクの証言、それならばどうして、原因と責任が運転員に負わされることになったのか――。 ・調査の結果、この事故原因の扱いをめぐってソビエトの科学者、官僚、政治家のあいだで激しい闘いが繰り広げられたこと、そしてその向こうに、社会主義国家ソビエトを半世紀以上にわたって支えてきた、軍事・産業・政治が一体化した巨大な体制が抱える、矛盾と葛藤が横たわっていることを知った。 二人の巨人 ・事故から三日後の四月二十九日、ゴルバチョフが設けた、ルイシコフ首相を議長とするチェルノブイリ事故処理問題緊急対策会議の第一回目の会合だった。 ・政治局員と多くの官僚が居並ぶこの会議には、齢八十歳を超えながらも威風堂々とした二人の老人が参加していた。 ・一人は、チェルノブイリ型原子炉の開発、設計、製造をはじめソビエトの原子力行政のすべてを牛耳ってきた、中規模機械製作省の大臣エフィム・スラフスキー。 ・スターリンの時代から従事した核兵器開発などの国防と、国の基幹をなすエネルギー開発への貢献から、ソビエト国家賞、レーニン賞をはじめ、数え切れないほどどの栄誉を手にしてきたソビエトの「国家英雄」であり、実力者だった。 ・そしてもう一人、禿頭の眼光鋭い大男は、ソ連科学アカデミー総裁アナトリー・アレクサンドロフ。 ・核物理学者のアレクサンドロフはソビエトの「核開発の父」イーゴリ・クルチャトフの創設したクルチャトフ原子力研究所の所長でもあった。原子力潜水艦、砕氷船、核兵器生産のための軍事用原子炉、最初の発電用原子炉からチェルノブイリ型原子炉まで、半世紀にもわたるソビエトの原子力開発を学術指導者としてリードしてきた大御所である。 ・ゴルバチョフは語った。 「アレクサンドロフとスラフスキーはこう言いました。『みなさん、いったい何をそんなに思い悩んでいるのですか。特にどうってことないじゃありませんか。原子炉の開発にはこうしたことはつきものなんですよ。何も怖れることはありませんよ』。いいですか、あんなに偉大な人たちがこう言ったんですよ。科学アカデミー総裁自身がこう言うんですから。クルチャトフ原子力研究所を指導してきた物理学者がね。スラフスキーは、ソビエトの原子力エネルギーの確立に一生を捧げてきた人物ですよ」 ・ゴルバチョフはこの日の二人の「巨人」との顔合わせについて、 「私は油断できないと思いました。書記長としての独自のルート、つまりKGBの組織を使って、情報の収集とくわしい調査を始めました。ほかの人たちよりも多くの情報を得ることで、私は厳格な立場をとるようになったのです」 ・改革と情報公開政策を押し進めるゴルバチョフと、二人の「巨人」を象徴とするスターリン以来のソビエトの体制との戦いが、この時始まったのである。 電力電化省の境遇 ・もともと原爆開発のための秘密組織を母体として発展した中規模機械製作省は、発電という民生用の事業を展開する時代になっても、依然として情報の機密化が支配する軍事産業の性格を色濃く残していたのである。 内部告発 ・組織の考え方 「偉大なソ連の党と政治局が承認した科学が過ちを犯すことなどありえない。間違えるとしたら労働者しかいない」 三 国際検討会議の舞台裏 レガソフの名演説 ・ウィーン国際検討会議に派遣されるソ連代表団の専門家二十三人が選ばれた。そして団長には政府事故調査委員会のメンバーとしてチェルノブイリ現地で活躍した、レガソフ科学アカデミー会員が選ばれた。 ジャトロフの怒り ・もらった勲章の多寡で処罰も変わるソビエトの権力社会。 「英雄」たちの死 ・一九八八年四月の末、チェルノブイリ原発事故からちょうど二年目に当たる四月二十六日の深夜、レガソフは自宅の階段の手すりで首をつり、自殺した。レガソフはその一年前にも睡眠薬を大量に飲み、自殺未遂をおかしていた。 ・レガソフが「原発の安全性を確保するためには体制の改革が必要である」と説いている。 ・「チェルノブイリの事故は、同じ型の原子炉を持つ発電所ならいつでもどこでも起こりうる」と警告し、行き詰まったソビエト科学の大改革と意識改革が必要なことを語っている。 ・レガソフはその後、グラスノスチとペレストロイカの進展に勇気づけられて急進的な考えを持つようになっていったのである。 ・レガソフが提案する改革案はことごとく受け入れられなかった。 ・ワレリー・アレクセービッチ・レガソフ、享年五十二。レガソフはその最晩年に、チェルノブイリ原発事故を招いた真の原因は長年国を支配した官僚体制がその内部に宿した病巣、「体制を維持するためには秘密を守り通し、民をかえりみない」という倒錯的な矛盾にあったことを見抜いていたに違いない。 ・ソ連が崩壊するのは、レガソフの「早すぎる死」から三年半ののちであった。 第三章 世界は事故をどう受け止めたか 四 「もんじゅ」の国――日本 政治の不在 ・国家が進める原子力政策を、国の政治家たちが真面目に議論もせず、原子力施設を押しつけられた地方の人たちに、その選択を委ねている現状こそ、本末転倒もはなはだしく、官僚主導国家日本の姿が剥き出しになっていると言わざるをえない。 ・もちろん、事故が起こった時だけ大騒ぎして、あとは知らないという「一過性」のマスメディアの責任も、自戒の念を込めて反省すべきである。 ・日本はプルトニウム利用もふくめて、このまま二十一世紀以降のエネルギー供給を原子力に賭けるのか(もしそうならば増え続ける核廃棄物の処理をどうするのか)、それとも方向を転じて、ヨーロッパやアメリカで進む再生可能エネルギーや省エネ技術の開発に、より重きを置き、環境とエネルギーが調和した社会を目指すのか――国家百年の計が今こそ必要とされているのである。 第四章 ‹チェルノブイリ›は終わっていない 二 「グレーゾーン」の憂鬱――事故処理作業者六十万人のその後 人海戦術の果てに ・「石棺」づくりと合わせ、原発を復旧させるための事故処理作業に参加した人数は、六十万人といわれる。 ・ロシア国防省の機関誌『赤い星』が事故から八年目の九四年四月に封じた記事によれば、ロシア人の事故処理作業者三十万人のうち、三万人が身体障害者となり、すでに五千人以上が死亡したという。 三 原子炉の骸のなかから あえて核原発と呼ぶ心 ・事故を起こした大背景となった‹科学の政治化›が、事故から十年たった今も、原子力を取り巻く世界を覆っているのである。 ―― 完 ―― |