
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2023年05月24日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク |
15 |
23.05 |
元禄時代 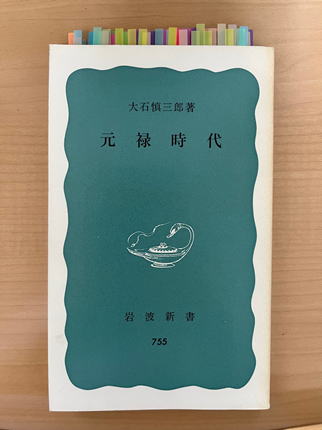 |
大石 慎三郎 |
岩波新書 |
◎ |
はじめに 倹約の経済論と浪費の経済論 ・将軍をはじめ、武士階級の質素倹約と緊縮財政こそ最大の美徳だと吉宗が考えていたのにたいし、お金というものは、上の者が使うから下々までそれがまわって万民がうるおうものである。それを上の者が倹約倹約というものだから、世の中の金銀がすくんでしまって、下々の者が難儀をするのだ、というのが尾州藩主徳川宗春のとった立場だった。 ・当時は、将軍吉宗の政治にみられるように、倹約と緊縮を領主財政の王道とする “倹約の経済論” が圧倒的な力を占めていたが、一方には、 “浪費の経済論” とでも名づくべき考えかたも一部には存在していたのである。 ・この “浪費の経済論” は、封建社会においては重要な意味をもっている。 江戸時代の領主経済のしくみ ・江戸時代の財政のしくみは、今日の国家財政のしくみとは決定的に違っている。 ・今日では国家は国民から吸い上げた租税を一度国庫に収め、しかるのちに財政計画にもとづいて、それを政策的に再分配するしくみになっている。 ・しかし江戸時代の領主経済は再分配の機能をもっていなかった。 ・すなわち年貢徴収のときとり残された剰余部分のほかには、年貢をとりたてた領主層が、浪費によってそれを吐きだしてくれなければ、富は庶民の手元に還元されないしくみになっていたのである。 ・こんなわけで封建領主が浪費するということのなかには、個人的浪費にあたる部分のほかに、税金の社会への還元も含まれていたのである。つまり庶民にとっては、封建領主の浪費政策がかえってその経済をうるおすという側面があったのである。 ・将軍綱吉は護国寺・護持院・上野寛永寺根本中堂の再建、日光東照宮の造替など、多くの寺社建立などをして、幕府財政を湯水のごとく浪費してしまったと非難されているが、このような視覚からみると、それは必ずしも非難されることではないといえよう。 ・たとえば元禄一一年の上野寛永寺根本中堂の建立は、綱吉の寺社建立事業のなかでも最大のものであるが、元禄時代第一の俄分限者といわれた紀国屋文左衛門は、この根本中堂の建立で五〇万両もの巨利を得たといわれている。しかし彼は吉原を一人で買いきって他の客をいれぬとか、そのほか豪遊の限りをつくして一代でそれを使いつくしてしまった。 ・また奈良屋茂左衛門も日光東照宮の造替で巨万の富をつかむなど、将軍綱吉の浪費政策に寄生して俄分限者となるが、紀文に張りあって豪奢な消費生活を送っている。 ・その行為には道徳的評価はあろうが、彼らが幕府からかすめ取った富を、そのような形で庶民の段階にまで還元する結果となったことは確かである。 ・将軍吉宗のように、農民がやっとのことで手にした剰余部分まで年貢増徴で吸い上げたうえ、緊縮緊縮で本来庶民に還元されていくはずの浪費部分を引き締め、そのうえ倹約倹約で富裕者の消費にまで制限を加えたのでは、景気が沈滞して庶民生活が火の消えたように委縮してしまうのは当然のことである。 ・ “享保” とか “寛政” とか “天保” といった、江戸時代でも模範的にりっぱな時代といわれているときに、じつは庶民生活が停滞し、為政者が無能・放埓で、もっとも政治が乱れたといわれている “元禄時代” “田沼時代” “大御所時代” という時代が、逆に庶民にとって、生活に余裕のある豊かな時代になっているのは、以上のようなことからも説明できるのである。 「元禄=文治主義の時代」説 ・綱吉は将軍就任当初より賞罰厳命主義を旗印にしており、その根底には将軍綱吉個人の ・将軍個人の ・むしろ綱吉・白石時代の文治主義からふたたび武断主義に返ったと考えられている吉宗時代の政治のほうが、実際ははるかに文治政治というにふさわしい内容をもっている。 ・というのは将軍吉宗の政治はまず行政機構を整備し、各部局の政治を従来のように担当者個人の裁量にもとづく政治ではなく、機構の一員としての政治に切りかえると同時に、『御定書百箇条』、『御触書集成』など法典の編纂をして、政治を個人の恣意によってではなく、客観的な法によったものに切りかえているのである。 ・また経済政策などでも、各種の実態調査を行ない、その結果にもとづいて決めていくなど、将軍吉宗によって行なわれた享保期の政治は、文治政治といわれるどの時代のものよりも、はるかに “文治的” である。 ・このようなことを考えると、元禄時代を文治主義の時代とする政治史でのとらえかたは、元禄時代の性格規定としては必ずしも十分とはいいがたいのである。 Ⅰ 元禄時代の前提 2 幕藩制社会のしくみ 農と商工の分離政策 ・幕藩制社会を語るとき、その社会構成上の特徴として兵農分離ということがあげられる。 ・支配者である武士と被支配者である農民とが身分的にはっきりと区別され、それまで農村に住んでいた武士が城下町に集められてしまうのである。 ・それによって政治と軍事の機能が農村を離れて都市に集中する。しかしこれだけであれば、幕藩制社会の支配の機構はまだそれほど完備しているとはいえない。 ・それをほぼ完全なものにしたのは、そのうえに農と商工の分離政策が加わったからである。 ・戦国時代までは兵農未分離のままで戦いをつづけていた武士たちは、戦闘上の必要から要害堅固な山城などをつくって戦いの本拠とし、平時は生活に便利な平地につくった館に住んでいた。 ・しかし戦国時代が終りに近づき、戦闘より政治のほうが大事になるにつれて、領主たちは城を、戦闘に主眼をおいた山地から、政治経済に都合のよい平坦地に移していった。 ・幕府を中心とする諸般の連合組織=幕藩制は、それができあがる徳川の初期には、それまでは隙あらば隣接する他領に攻め入って領地を拡げようとしてきた領主たち相互の闘争行為を防ぎ、戦いに向けていた彼らの勢力を領内経営に向かわせる役目をした。 身分制度と城下町の構成 ・その中心になったのが ・この町づくりは、城の周囲には十分な平地があるので周到に準備された稀有壮大な地割(都市計画)にもとづいて、整然とおしすすめられた。 ・これほど都市が周到な都市計画によって大規模に建設された国は世界史上でも珍しく、その意味では江戸時代は “都市の時代” といえるほどである。 ・このようにしてできた城下町は、ふつうは武家屋敷地・町人地・社寺地の三区域よりなっていた。 ・武家屋敷地は城にもっとも近いところに、城を取り巻くようにつくられ、多くの場合他の二地域と木戸または溝で区別され、万一戦いになったときは、城の外郭として役立つように工夫されていた。 ・そして兵農分離によって領内各地から集められた武士たちが、身分の高い者ほど代の近くに屋敷を割り当てられて秩序よく住んでいた。 ・城下町のもっとも外側に用意されたのが社寺地である。ここは万一他国から敵が攻め入ってきたときに城防衛の第一線の人知として役立つようにと、あらかじめ用意された地域でもあった。 ・しかし平和がつづくにつれて社寺地は、城下町の防衛第一線の陣地から、しだいに庶民のリクリエーションの地域へと転化してゆき、比較的制約の多かった江戸時代にあって、庶民がもっとも人間的な楽しみを享受できる地域となった。 ・武家屋敷と社寺地のあいだには町人地が用意されていた。ここには領内村々から集められたもののほかに、領外からも呼び集められた町人たちが住んでいた。 ・戦国期までの武士は、平時には農村に在ってみずからも耕作に従事する生産階級であったが、一度城下町に集められると今度は逆に完全な消費階級になった。 ・このような消費階級が存続するためには、その生活物資をまかなう商工業者が必要である。城下町の町人地に商工業者たちが集められたのはこのような理由からである。 自給経済にとじこめられた農民 ・封建社会は、全人口のなかで大多数を占める庶民を、少数者である武士が支配する社会である。 ・この被支配者たる庶民大衆は、そのほとんどが農業生産者であり、彼らは自分の田畑を自分の家族の労働力で耕作し、しかも生活物資は、万やむをえないもののほかは自分の手でつくるという、自給自足の生活をしていた。 ・したがって、封建社会を長く維持させるためには、できるだけ農民たちを交換経済から切り離して、自給経済の枠のなかにとじこめておくのが有効な手段であった。 ・たいていの藩が、江戸時代のはじめ、領国経営に着手した段階で、領内の全商工人を城下町に集め、商行為は原則としてここで行なわせ、とくに許された商品のみをもって、農村に商いにゆくことを許すといったような、きびしい統制を加えているのはこのためである。 ・幕藩制社会には、その社会を維持するのに役立つよう用意された一群の商人たちがいた。 ・彼らは封建支配の重要な一翼をになうものとして、領主からいろいろの特権と保護をあたえられていたので、これを初期特権商人と総括して呼んでよいであろう。 ・元禄時代に登場する新興商人とは、このような初期特権商人とはまったく系譜を異にする、また利害関係を異にする商人である。 3 農民経済の変化 収奪体制の後退と農業の体質変化 ・近世初頭に六割六分強であった年貢率が、一〇〇年余ほどのちの正徳二年(一七一二)には二割八分九厘にまで下がっている。 ・綱吉が五代将軍に就任する少しまえ、四代将軍家綱の初政ころに、それまで全剰余労働分にまでおよんでいた年貢収奪体制が後退し、農民の手元にも必要労働分をうわまわる剰余が残るようになったのである。これは全江戸時代を通してみても注目すべき変化で、その影響はあらゆる方面におよんでいる。 ・まずその影響の第一は、農民の体質変化である。 ・農民がその生産物のうちから、全余剰労働部分にあたるものを年貢として領主に取られている段階、これは幕藩体制の原型と考えるのだが、この時代は豊臣政権から徳川四代将軍家綱の初政ころまで、約一〇〇年近くつづいたと考えられている。 ・この時代の農民生活は鋤・鎌とか塩といったごく一部の品を除いて、ほかはすべて自分たちの手でつくりだすという自給経済、すなわちみずから使うためにのみ物を生産するという使用価値生産の状態にあった。 ・そこでの農民は、年貢納入をすまし、あとはみずからの生産物がその生活を満たしさえすれば、それで十分だという考え方・生活態度をもっていた。つまり非経済人的体質とでもいうべき農民の体質が一般であったのである。 ・ところが農民の手元に剰余労働部分の一部が残るようになると、この状態はかわってくる。 ・ひとたび剰余が交換にだされ、いままでにない豊かさを農民生活に加えるとそれはとめどなく広がるもので、より多くの品を交換にだそうという意欲を農民たちにかきたてる。 ・そのため自給時代にもっていた明日への生活を満たせば足るという自足的意識はしだいにうすれ、少しでも多くのものを生産し、それを交換にだして、より生活を豊かにしようという、飽くことを知らない労働人間へと農民の体質はかわってゆく。 ・この変化は、農民の意識をかえるのみでなく、具体的な生活の仕様をもかえてゆく。 ・江戸時代初頭の農業は米麦中心であって、それ以外の作物は作付制限令などによって強く規制されていた。幕藩制という社会体制が、米を経済の軸にして組み立てられていたからである。 ・ここでは「朝早くから夜遅くまで働き、質素倹約を旨とし、自分が作った米でもむざむざと食べず、大豆・小豆の葉、芋の茎や葉などをぷかぷか浮かせた雑穀の雑炊などを食べ、農業にひたすら精を出す」のが理想的な農民として期待されていた。 ・しかし、元禄を前後する時代は、地方書と呼ばれる一連の農書がでることで特徴づけられている。 ・これらの地方書というのは、地方役人とか豪農とか農学者などが書いた農業手引書で、そのなかでは、どの地方ではどんな作物をどのようにつくれば有利であるとか、これくらいの規模の農家では年貢がこれくらいであれば、その家計収支はバランスを保てて、農民がくたびれることがないなどというように、頭を使って農業経営をする農民が期待されていたのである。 米の商品化と稲の品種改良 ・ <途中> |