
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2025年01月29日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク |
19 |
23.05 |
物語日本史(上) 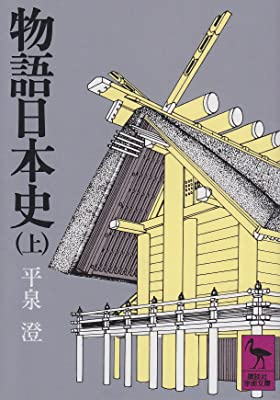 |
平泉 澄 |
講談社 学術文庫 |
☆ |
序 ・人生は短く、芸術は長し。豹は死して皮を留め、人は死して名を残すといいます。 ・しかるにその芸術功業の長く伝わり、名声栄誉の万世に不朽なるは、その精神功業の、子孫後世に理解せられ継承せられるがためであって、もし子孫にしてこれを理解せず、後世にしてこれを継承することがないならば、すべてはその人と共に消滅してしまい、人生はすべて一瞬の泡沫、死と共に雲散霧消するでありましょう。 ・古来、家に定訓を厳しくし、国に教育を重んずるのは、そのためであって、教育の要諦は実にここに存するのであります。 ・しかるに明治以来、西洋文明の輸入追随を急務としたために、本義はしばらくこれを不問に附するもやむを得ずとしたうえに、昭和二十年以降は、占領政策のために抑圧せられて、父祖の精神を継承し、その功業を顕彰することは不可能となりました。 一 国家建設 志を立てる ・普通は十五歳前後で元服すなわち成人の式をあげ、それより後は、大人としての待遇を受け、同時に自分は言葉にも、行為にも、完全に責任を負うたのでありました。 ・それまでは、 ・形の上での元服は、心の上では立志ということになります。いよいよ一人前の大人となれば、心が定まり、目標がハッキリしなければなりません。それを「志を立てる」と言うのです。 ・個人においては立志であり、元服である、民族においてはその立志に当り、元服に当るもの、それは国家建設にほかならない。 三 皇紀(上) 六国史 ・第四十代天武天皇は、昔からの ・しかしこの人の寿命にも限りがあるので、第四十三代元明天皇は、漢字漢文の教養の深い太安万侶に命じて、稗田阿礼の暗唱するところを、文字に記録させられました。 ・和銅五年(西暦七一二年)正月、それが完成して献上せられました。これが有名な古事記で、上中下の三巻に分れています。 ・古事記は古い口伝を元にしたものですが、これとは別に、聖徳太子以来の歴史家の努力があって、外国の歴史を参考にし、諸家の記録を整理し、これによって口伝に欠けていた年月を補い、我が国の歴史を大成する計画が進められていました。 ・それが第四十四代元正天皇の養老四年(西暦七二〇年)五月にでき上がって、総裁舎人親王より献上せられました。日本書紀がそれであります。 ・その後、その続編がつぎつぎに作られ、続日本紀、日本後記、続日本後記、文徳実録、三代実録とつづき、日本書紀氏合せて、六国史と呼ばれるようになりました。 四 皇紀(下) ・我が国の歴史、古い時代の年立てに、無理なところがあるのは、その原因を探ってみるに、外国から、間違った歴史の法則を採用したからです。 ・秦が亡びて後、天下を統一して、大帝国を建設したものは、漢ですが、その漢が二百年ばかり続いた後、一応滅亡したのを、再び建て直したのが、後漢の光武帝です。 ・その光武帝がまだ民間人であった時に、ある人が予言して、あなたによって漢の王朝は再興せらるる運命にあるといい、光武帝の奮起を促しました。 ・この予言が的中したものですから、運命を予言する学問が盛んになりました。これを讖緯の学といいます。 ・それは人生の出来事、必ず一定の法則によって支配せられているもので、決して偶然に変化が起るわけではない、その法則を理解し、変化の徴候をつかみ、前兆を判断すれば、前もって将来のことを予測し、正しく予言することができる、とするのです。 ・この学問は、後漢が亡びた後には、次第に衰えましたが、その衰える前に、すでに朝鮮に伝わり、それがさらに海を超えて我が国に入って来ました。 ・推古天皇の勅命により、聖徳太子が古代史を研究して整理して、天皇紀・国記などを作られた時、この事業に参加して働いた人々には、朝鮮から帰化した学者が多かったに違いありません。 ・漢の高祖の子孫が、漢亡びて後、百済へ移り、 ・そして我が国に残っている ・讖緯の学から、どのようなことが出てくるかといいますと、 (一) (二)千二百六十年を単位として、歴史の時代は転換すること。 ・(一)の辛酉の年というのは、六十年に一度あります。従って六十一年目に、大きな変化がくるはずです。(二)の千二百六十年単位で、歴史の時代がうつりかわるのも、その変化する時は、(一)の辛酉の年でなければならないでしょう。 紀元元年 ・推古天皇の御代を見ると、聡明なる聖徳太子によって、盛んに外国の文化がとり入れられ、政治、外交、学問、文物、すべて一新することになったので、人々はこれを新しい時代の始まりと考えたであろう。 ・そしてその新しい時代が始まるのは、辛酉の年でなければならないから、推古天皇の九年辛酉の年、これが、新時代の発端と思われたであろう。 ・そうすれば、我が国の歴史は、ここに第一の時代を終って、第二の時代に入るのである。 ・そこで過去をふりかえってみるに、第一時代の始まる時は、神武天皇の建国の時でなければならぬ。それは必ず辛酉の年であり、かつ推古天皇の九年より、千二百六十年前でなければならぬ。かように推理したであろう。 ・この推理に基づいて、日本書紀の年立てが行なわれ、そして、 (一)神武天皇の御即位は、皇紀元年辛酉の年。 (二)推古天皇の八年 (三)翌九年辛酉は、新しい時代の出発点となった。 として、整理せられたでありましょう。 ・当時、漢学者の間に信用せられた讖緯の学説から推理すれば、かように判断せられたものの、実際の事実はこれとは違っていたでしょう。 ・どう違っていたかといえば、神武天皇の御代と、推古天皇の御代との間隔が、それほど長くなかったのです。 ・長くないものを、長いとしたために、御歴代天皇の御寿命も、その御代に活躍した人物の命も、引き延ばして長くして、ともかくも話が合うように、まとめねばならなくなったのです。 ・それでは我が国の歴史、古いところは、いっこうデタラメで、信用できないものか、というに、そうではありません。 ・年の立て方は誤り、年代は延びすぎているものの、事実そのものには、讖緯の説も介入せず、手をふれていません。 ・もし手を入れたとすれば、たとえば、神武天皇より推古天皇まで、三十三代であるものを、十数代ふやして、四十五、六代とすれば、御寿命にも無理がなく、万事辻褄が合ったでしょう。それをしなかったものだから、年立てに無理が生じたのですから、口伝にはほとんど手を入れず、わずかに御寿命に影響が出た程度と思われます。 ・それではいったいどれほど年代が延びすぎたのか、といいますと、宋書の中に、我が国との交渉の記事があって、宋の武帝の永初二年(西暦四二一年)には、我が国では仁徳天皇の御代であったことが分ります。・仁徳天皇は、第十六代の天皇ですから、その前を十五代、遡れば、神武天皇の御代になります。一代は平均三十年というのが常識ですから、三十年を十五倍にして四百五十年、西暦四二一年から四百五十年ばかり遡ったあたりが、我が国の建国の時と考えられます。 ・つまり皇紀は、事実より五、六百年延びているわけです。 ・皇紀だけではありません。世界各国各民族、あるいは各宗教に、いろいろの紀元が立てられていますが、そのどれを見ても、正確に事実を実証し得るものは、ほとんどありますまい。今年昭和四十五年は、それらの紀元では、次のようになります。 インド経歴紀元 二〇二六年 回教歴紀元 一三四九年 フリーメーソン紀元 五九七〇年 ユダヤ紀元 五七三〇年 コンスタンチノーブル紀元 七四七八年 アレクサンドリア紀元 七四六二年 マケドニア紀元 二二八一年 スペイン紀元 二〇〇八年 ペルシャ紀元 一三三九年 キリスト紀元(西暦) 一九七〇年 ・最後のキリスト紀元のほかは、歴史的事実としては、まず信用がむさかしいと思われるでしょう。 ・ところがそのキリスト紀元すら、事実とは違うのです。すなわちそれはキリストの誕生を、紀元元年とする建前ですが、実はその計算に誤りがあって、キリストの生れたのは、紀元元年ではないのです。 ・キリストの生れたのは何年かといえば、困ったことには、学者によって説がまちまで、これっを一定することはできないのです。 ・二千年、三千年も前となれば、どの国にしても正確に年月を押えることはむつかしい。 ・わが国の古代史に、年の延びすぎがあっても、それは珍しいことではなく、かつまたそれは讖緯の説の責任であって、我が国の歴史自体の責任ではないのです。 ・我が国の紀元、つまり今年を皇紀二千六百三十年というのに、あとからしらべてみると、五百年ばかりの間違いが出ましたけれども、そのような間違いが出るほど、我が国の歴史は古いので、それはむしろ楽しいことで、少しも心配する必要はないのです。 五 神 代(上) 神話 ・神代の口伝、これを世に神話と呼んで、とうてい信用することのできない不思議な物語とし、これを軽く見る考えがありますが、もしそのように批判するとならば、外国の古い伝承も、皆同様でしょう。 ・神話を、そのままの姿で、今日の知識から批判すれば、どれもどれも荒唐無稽、つまりデタラメで、信用もできず、価値もないように思われるでしょうが、実はその中に、古代の宗教、哲学、歴史、道徳、風俗、習慣が、その影をうつしているのであって、その民族の世界観と人生観、その知性と感性とを、これによってうかがうことができる、貴重な資料なのです。 ・我が国の 古事記では、 日本書紀では、 一書(甲)に、 同 一書(乙)に、 一書(丙)に、 同 一書(丁)に、 国常立尊 一書(戊)に、 同 一書(己)に、 とあります。 ・御名前が違ったり、または出現の順序が違ったりはしているものの、神であることは、すべての伝に、共通しています。これはすこぶる重要な点です。 ・なぜかといえば、我々が動物から進化したとするか、または野蛮な人間から発達したとするか、いや発達ではなくて、堕落してきたものとするか、それとも神から出たものとするか、その出発点の相違は、その民族の宗教に、道徳に、政治に、重大な影響があるからです。 ・簡単に進化論をうけとる人は、人は猿から発達したようにいいやすいのですが、猿はいつまで経っても猿です。 ・猿は猿、人は人、別のものです。それを誤解して、猿こそ我々の先祖であるとすれば、祖先崇拝は出てきますまい。先祖の恩徳を感謝する厳粛な祭は行なわれますまい。 ・われわれ日本民族は、その祖先は神であったと信じ、敬い、そして祭ってきたのです。 ・すなわちその生活は、奉仕の態度であって、「つつしみ」「うやまい」を正しいとし、「おごり」「たかぶり」を善くないとしてきたのです。これが、神代巻において、第一に考えられるのです。 六 神 代(下) 天孫降臨 ・高天原では、たびたびの使者、皆失敗に終った。 ・手間取っているうちに、年月もたちましたので、いよいよ御降臨になるのは、 ・天照大神には、御孫に当られるので、 ・その御降臨に際して、大神は、 海の幸山の幸 ・瓊瓊杵尊の御子、御兄は ・この 日本の神話の特色 ・神話の特色として注意すべきことの一つは日本の島々が、人と同じく、神の生み給うたものとされている点です。 ・つまり我々の先祖は、この国土山河を、我々とは別のものと見ず、等しく神によって作られたものであって、いわば血が続いているように考え、極めて親しい気持ちで対していたのです。 ・かように山河自然に対し、動植物に対して、あたたかい感情をいだいたことは、日本人の国民性を、美しくやさしく育ててゆくうえに、大きな関係があったと思われます。 ・今一つの特色は、悲惨とか、冷酷とか、凶悪とか、いうような暗い話が少なくて、だいたいほがらかな、愉快な物語が多いことです。 ・余所の神話では、人間の発生が怪獣から出たとしたり、また罪悪から人が生れたとしたり、あるいは残殺、姦淫など、猥りがましい話が多いのに、我が国には、そのような暗い話は少なく、まことにおもしろく、楽しい話が多いのです。 ・そして皇孫瓊瓊杵尊御降臨の際に、天照大神より下し給うた天壌無窮の神勅と三種の神器、さらにその御降臨の御様子を伝えた神話に至っては、まことに荘厳であって、光に充ちているものでしょう。 ・「 ・神武天皇が国家を建設し、国民統合、上下和楽の基礎を築かれたことは、非常な辛苦艱難を伴ったに違いありません。 ・しかもついにそれをなしとげられたところを見れば、何ものにも挫けない強い意志と、人々を心服させる徳望とが、、豊かにお有りになったに違いありません。 ・そういう意志や徳望の基づくところは、天皇の御先祖、すなわち天照大神を初めとする神代の神々にあったでありましょう。 ・神話をそのまま歴史的事実とは思われませんが、このように考えてくる時、深い意味があると思われます。 七 日本武尊 御歴代天皇 ・民族の統一といい、国家の建設という、言えば簡単であり、容易であるようであって、実際は非常に困難な大事業でありますから、普通平凡の人にできることではありません。 ・それをやりとげられたのでありますから、神武天皇始め御歴代天皇の御苦労は、非常なことであったでしょう。 ・すべて人は、困難に出会い、努力してその困難に打ち克ってゆくところに、おのれの ・神話によれば素戔嗚尊は、初めはまことに粗暴で無作法な性格でありました。それが高天原から追放せられて、根国へ下られた時、ひどい雨風に遭って、さんざん苦労をせられたことを、日本書紀に「 ・その「たしなみ」つまり「苦労」によって素戔嗚尊の性格は一変して、今度は貴い神におなりになり、後世厚い信仰をお受けになるようになったのです。 ・さればこそ、その御子孫、皇統長く栄え、その国家、二千年を経て隆盛であって、はるかに天壌無窮の神勅にお答えしているのであります。 ・その皇統連綿として今につづき、百二十四代に至っていますことは、世界の歴史を見渡すに、全く ・第十代崇神天皇の御代には、初め疫病が流行して死亡する者が多く、国内騒然として落ち着かず、中には反乱を企てる者もありました。 ・天皇は御信仰の非常に深い御方で、これは神徳をけがすところがあったためではないかとお考えになり、それまでは宮殿の中に三種の神器を奉安して天照大神をお祭りになっておられましたのを、もったいないとして、 ・また国内の神社を整えて、お祭りが粗末にならないようにされました。 ・そこで人々の心も落ち着き、流行病も治まりましたので、今度は建国の大業をさらに広めようとして、将軍四人を任命し、 つかわされました。四道将軍として名高いのは、この方々であります。 ・かようにして政令の及ぶ範囲も広まり、皇威大いにあがりましたので、国民は御偉業を讃えて、 ・次の垂仁天皇は、父帝の御精神をお承けになって、神を尊ばれ、皇女 ・倭姫命は、神鏡を奉じて諸所御巡歴になった結果、伊勢の五十鈴川の川上こそ、大神をお祭りするに最もふさわしい聖地であるとして、ここに神宮をお建てになりました。これがすなわち今の伊勢大神宮であります。 ・そのころまでは、殉死という風習がありました。これは主人が亡くなると、親しくその人に仕えていた人々が、死後も仕えるように要求せられて、いっしょに生き埋めにさせられるのであります。 ・シナにも、西洋にも、ひろく行なわれていたことは、記録にも残れば、遺跡からも分るところです。 ・そのような残酷なことはしてはならぬとお考えになった垂仁天皇は、野見宿禰に命じて、土器で人や馬の形を造り、これをお墓の周囲に建てて殉死に代用させられました。野見宿禰の子孫、代々これを ・次の景行天皇の御代には、九州に反乱があって、天皇の親征によって、一応は鎮まったものの、また ・ ・そこへ皇子は変装して少女の姿になり、女どもの中にまじって給仕をされました。 ・梟師は、これがたいそう気に入って、そばに引き寄せて、盃を与えたりしていましたが、そのうちに夜もふけて人も散じ、川上梟師も深く酔って動けないほどでした。 ・この時、皇子はかくし持ったる刀をもって、これを刺し殺されましたが、梟師は息の絶える前に、深く皇子の勇敢に感心し、「今後は 日本武尊 ・日本武尊は九州を平定して、お帰りの途中でも、方々の反乱を平らげて、大和へ凱旋せられました。 ・そのうちに、今度は東国が乱れましたので、 ・その際、まず伊勢神宮へ参拝せられましたところ、使命すこぶる重大であるとして、 ・ ・この神剣は、 ・さて尊は、相模から上総へ渡ろうとして、暴風雨にあい、船は危険に陥りました。その時、弟橘姫は、身代りになって海の中へ跳び込み、危難を救われました。 ・尊は東国を平らげて、お帰りの途中、 吾妻はや! と詠嘆せられたので、それより関東のことを「あづまの国」と呼ぶようになりました。 ・以上が、日本武尊に関する、古事記や日本書紀の記載の ・恐らく長い口伝のうちに、誇張は誇張を生み、こじつけはこじつけを加えたところがあるでしょう。 ・しかし話の大筋は、事実であったでしょう。それは、こういうことです。 ・建国の大理想は、神武天皇によって掲げられ、かつ、その第一歩を踏み出されたでしょう。 ・そして第十代崇神天皇は、さらにそれを推し進めて、四道将軍を ・しかし ・景行天皇御自身も、また皇子日本武尊も、すなわち皇室が先頭に立って、辺地の開拓、紛乱の平定に、力を尽されたに違いありません。 ・その証拠の一つは、シナの旧い歴史の書物である宋書、これは西暦四八七年、つまり今から数えて一千四百八十余年前に作られたものですが、その中に雄略天皇の外交文書が載っています。 ・それには、「我が父祖は、身に甲冑を装い、山河の険を冒して四方に出兵し、東の方五十五国を征し、西の方六十六国を服して、ついに全土を統一した」とあります。 ・すなわち雄略天皇より数代前の皇室は、みずから武装し、みずから武器を執って、東西辺境の平定に力を尽くされたこと、明らかでしょう。 ・御血統の上からいいますと、 景行天皇――日本武尊――仲哀天皇――応神天皇――仁徳天皇――允恭天皇――雄略天皇 となり、日本武尊は、雄略天皇の祖父様の曽祖父様に当られます。 ・その故におの外交文書には、日本武尊のめざましい西征東伐が、その影をうつしているのだと思われます。 ・今一つの証拠といいますのは、およそ日本国の重大なる危機に臨んでは、皇室みずから先頭に立ってこれに当られ、御自身の苦難は少しもお厭いにならないのが、前後一貫した御態度であって、そのめざましい例をあげますと、たとえば聖徳太子、中大兄皇子、後鳥羽天皇、順徳天皇、後醍醐天皇、皆そうでしょう。 ・ことに後醍醐天皇の皇子が、大塔宮 ・御子孫の勇ましく雄々しくましましたことによって、その御先祖の潔くすぐれておわしましたことを推察してよろしいのは、御血統がまっすぐに続いているからです。 八 神功皇后 広開土王の碑 ・ <途中> |