
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2023年07月02日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク |
21 |
23.06 |
アジア・太平洋戦争 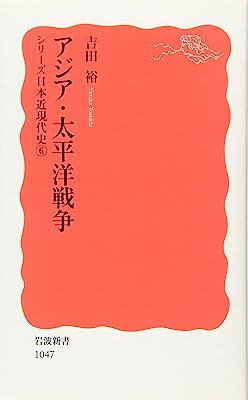 |
吉田 裕 |
岩波新書 |
◎ |
第1章 開戦への道 2 戦争の性格 日英戦から日米戦へ ・一九四一(昭和一六)年一二月八日午前二時一五分(日本時間)、日本陸軍の ・日本軍の攻撃が真珠湾ではなく、英領マレー半島に対する攻撃から始まっている事実が端的に示すように、この戦争は何よりも対英戦争として生起した。 ・すでに、日中戦争の開始以降、日本は中国におけるイギリスの権益を次々に侵害し、日英関係は急速に悪化していた。 ・さらに決定的だったのは、四〇年九月の日独伊三国同盟の締結と日本の南進政策の開始である。 ・四〇年春のドイツ軍の大攻勢によって大陸からの撤退を余儀なくされたイギリスは、引き続きドイツの攻勢に直面していた。八月には、英本土上陸作戦の前哨戦として、ドイツ空軍は英本土への空襲を開始する。 ・日本政府はこうした国際情勢の変化を好機としてとらえ、三国同盟の圧力の下でアメリカを牽制しながら武力南進する路線を選択したのである。 ・日本の武力南進政策が日英戦争を不可避なものとしたとはいえ、日米間には決定的な利害対立が必ずしも存在しなかったという事実である。 ・したがって、日本の軍部内にも、対英戦に主力をそそぎアメリカとの戦争は極力回避しようとする「英米可分論」と、対英戦は対米戦を必ず誘発する以上、対英戦決意は対米戦決意を伴うものでなけれ゛ならないとする「英米不可分論」の対立が生じた。 ・実際の戦争は、対英戦とともに対米戦を開始するという形をとったが、結局、日本の武力南進政策が対英戦を不可避なものとし、さらに日英戦争が日米戦争を不可避なものとしたととらえることができる。 ・ナチス・ドイツの膨張政策への対決姿勢を強めていたアメリカは、アジアにおいても「大英帝国」の崩壊を傍観することはできず、最終的にはイギリスを強く支援する立場を明確にしたのである。 日米戦争の性格 ・アジア・太平洋戦争には、植民地を保有する帝国主義大国である欧米列強と、同じくアジア最大の帝国主義国である日本との間の植民地再分割戦争という側面があり、帝国主義国家相互の戦争という側面に限っていえば、日本はアメリカやイギリス、オランダに対して戦争責任を負ういわれはないという主張がある。 ・このような戦争観の背景にあるのは、なぜ日本だけが断罪されなければならないのか、アメリカに日本を裁く資格があるのか、という不公正感であり、不平等感である。 ・戦後の東京裁判(極東国際軍事裁判)においては、原爆投下や日本の都市への無差別絨毯爆撃など、アメリカの戦争犯罪はまったく裁かれなかったし、アメリカ自身がその後、軍事覇権国家としての歴史を刻んできたことも否定できない。だとするならば、こうした歴史認識がある種の健全なバランス感覚に支えられている面があるのも確かだろう。 ・しかし、歴史の現実の展開のなかで戦争責任という問題を考えてみた時、「日米同罪論」、さらには、アジア・太平洋戦争は日本の自衛戦争であり、アメリカの側にこそ戦争責任があるという主張には、過度の単純化があるといわざるをえない。 開戦にともなう違法行為 ・ <途中> |