
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2023年10月20日 金曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク |
26 |
23.09 |
日本史から見た日本人『古代編』 「日本らしさ」の源流 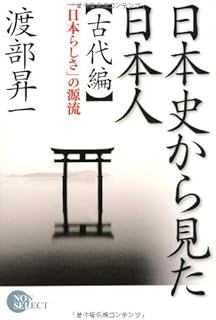 |
渡部 昇一 |
祥伝社 黄金文庫 |
◎ |
まえがき ・日本史の本質は――他の国々と根本的に違うところは――神話以来、王朝が一つであることである。 1章 神話に見る「日本らしさ」の原点 (3)「日本の神」と「ゲルマンの神」の同質性 欧米人が天皇を理解できない理由 ・二〇〇〇年前には、近代の欧州で発生したような合理主義や唯物論はなかった。したがって、近代的な政治学論理で断ずれば、天皇の存在は当然ながら論理に合わないところが出てくる。 (5)日本的アイデンティティの出発点 パリ祭は平和的記念日か ・神武天皇がご即位なされたとき、「 (6)「伝統への敬意」こそ民主主義の精神 「全能の神」あってこその個人主義 ・キリスト教になると北の海が天国になり、先祖の霊に会見するよりも、神とかキリストに対面するということが、強調された。死後に自分が対面するのは、全能の神と一対一であることを原則とするという信仰は、家族中心であったゲルマン人を、心の底から個人主義者に変えてゆく作用があった。 ・西洋人の個人主義の根源は、この辺にあるのであって、その信仰を前提としないで「日本人はもっと個人主義的にならなければならない」とか「個性を確立しないといけない」と言うのは、相当にビンボケである。 ・死んでから、「生前の決算は自分一人で全能の神の前でやるんだ」という信仰のない個人主義などは、「我儘のすすめ」以外の何物でもない。 ・だいたい、自然的に見れば、個人主義というのはあまり根拠のないものである。肉体的には、われわれは父母より生じ、特に母親とは長い間、文字どおり同体であったこともあるのだから、精神だって、(そんなものがあるとすれば)どっかで連なっていないという保証はないのであるから。 死者の権利と時間的民主主義 ・「地鎮祭」の問題。公立の建物を建てるときに特定の宗教の儀式を使うのは憲法違反だという。そういう理屈は成り立ちそうに見える。しかし、日本人は有史以前から建物を建てるときはそういうことをしてきた。 ・そういう習慣は、積極的に有害であるということが歴然としていない限り、一握りの人が作った法で圧殺すべきではない、というのが正統のセンスである。 ・それに公共建造物の地鎮祭をキリスト教の一派や仏教の一派でやるならば、憲法違反にもなろうが、神社の神主さんがやるのならばかまわないだろうというのが、日本の庶民のセンスである。 ・これが憲法違反なら、天皇の存在自体が憲法違反ということになる。何しろ神の子孫となっているのだから、 なぜ、民主主義はイギリスから誕生したか ・民俗として、また土俗としての神社は、西洋の意味での「宗教」でない、という解釈である。というのは、民俗としての神道には「教義」がない。教義のないのは、西洋人の概念では、宗教ではなくて民俗である。 ・天皇は神道の大司祭ということになるが、神道の神はつまり天皇の先祖であり、何となく日本人全員と血の繋がったものであると伝承されている。 ・そしてこれらの神々は十戒を与えたわけでもなし、「われ以外の神を崇めるな」と言ったけでもない。 ・歴代の天皇でも退位後は仏門に入られた方も多いし、皇子皇女で仏門に入られた方は数えきれない。 ・つまり神社はなにを祀ろうと、つきつめていけば現在の日本人の先祖を祀っているわけなので、先祖に敬意を表することに反対の宗教や倫理はあるわけがないのであるから、地鎮祭を憲法違反というのは、事実誤認にもとづく法律遊戯なのである。 ・健全な保守主義は死者への配慮が無意識的にせよ働いてゐるという意味で、つまり ・これに反し、急進的な革命勢力は、デモクラシーを志向するように見えながら、かえって反対のほうに、つまり独裁に流れやすいというのが歴史の現実である。 ・ロベスピエール、ヒットラー、スターリン、毛沢東、森恒夫(元赤軍派幹部。浅間山荘事件の主謀者の一人)というふうに並べただけでも、革新と称する者は、最悪の独裁君主よりも、もっと独裁的であったことをわれわれはよく知っているのである。 日本の独自性は、神話の独自性に由来する ・昔の日本人が先祖を意識したことは、たいへんなものであった。 ・その人達にとっては、自分たちの先祖の話はこの上なく重要なことであった。特に先祖が神であった時代の伝承は重要であった。 ・藤原氏の例を挙げると、彼らの先祖はアメノコヤネノミコトである。 ・皇孫ニニギノミコトが高千穂の峯に降下し給うたとき、それに付き従って降りてきたと伝承されている。 ・さらにその子孫は、また神武天皇に従って日本の建国に参加したことになっている。 ・春日神社というのはこの神を祭っている神社であり、藤原氏の氏神である。自分の先祖がカミであった神代に、すでに皇室に仕えていたのである。 ・したがって、平安時代に藤原氏がいかに権勢を得たとしても、自分が皇位に即いては神代以来の先祖の行為を引っ繰り返すことになるので、昔の人には絶対にできることではなかった。 ・せめてできることは、自分の娘を天皇や皇太子に嫁がせること、あるいは自分の息子に皇女を嫁にもらうことであった。 ・したがって、血液的には自分が天皇の祖父にはなれるが、自分の ・時代が下って頼朝は鎌倉に幕府を開いた。もちろん皇位を武力で取れる立場にあった。しかし頼朝は、んなことは夢にも考えない。 ・頼朝は、祖先の霊を考えた人であった。 ・頼朝にとって、皇位に即くことは、すべての先祖の意志を無にすることなのであった。つまり頼朝は源氏の嫡流である。そしてその先祖は清和天皇の皇子貞純親王にさかのぼる。そういう系図を持つ頼朝が、宗家の位を奪って亡ぼすことなどは、絶対に念頭に浮かべないのである。 ・同じことは徳川家康の場合にも起こる。家康も征夷大将軍になり、源氏の流れをくむと言い出した。そして幕府を作ったのは頼朝の真似である。 ・家康は啓蒙された考えを持ってはいたが、頼朝さえなかったことをやろうとは考えない。それをやったら、ほかの大名からの忠誠を保持できなくなることは、考えるまでもなく、明らかであった。 ・実力がいくらあっても自ら天皇にはならない、という日本の歴史上の実力者たちの奇妙なビヘビアの型は、西洋史や東洋史だけをやった人には説明できないように思われるのであろう。これが「日本人はわからない」と言われる理由の一つになっているのかもしれない。 ・しかしこのパタンの根が、日本の神話、つまり史前史にあることがわかれば、その謎は解ける。『古事記』や『日本書紀』は、つねに日本人の心にとっては、厳たる 2章 上代――「日本らしさ」現出の時代 ―― “異質の文化” を排除はない伝統は、この時代に確立した (1)「和歌」の前に平等な日本人 カーストを超越して成立した「万葉集」 ・ <途中> |