
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2023年11月08日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | 抜き書き&コメント |
30 |
23.10 |
くらしのなかの仏教 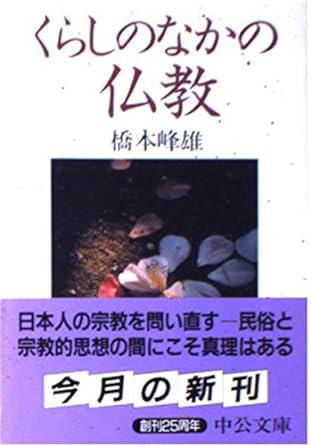 |
橋本峰雄 |
中公文庫 |
◎ |
Ⅰ くらしのなかの仏教 くらしのなかの習俗 中陰について ・中陰とは、人の死後七七・四十九日の期間のことです。 ・人の死後七日ごとに経を読んだり御詠歌を唱えたりし、七回目を満中陰として追善法要を営むという習俗は、わが国で今日でも広く行なわれています。 ・死者の魂はこの期間その家の軒を離れない、などとよくいわれます。俗にこの期間は亡魂が迷っているといわれる。 ・ヨーロッパでも、人の死なんとするとき、ドアや窓をあける習俗があります。フランス、ドイツ、スイスでは、屋根のタイルまで一枚はがすそうです。時計を止めたり鏡を壁に向けたりします。すべて、死者の霊魂が出口を迷わないためです。水を入れた容器を全部からにとたりするのは、死者が溺れないためです。 お墓について ・彼岸を彼岸会という習俗としてみれば、それは単純明快、お盆(盂蘭盆会=うらぼんえ)とともに、お墓参りをする時節です。 ・これは仏教行事であるといっても、もともとインドにも中国にもなく、日本独特のものです。しかも、早くも聖徳太子ころから始まったといわれています。 ・日本人はお墓参りを好む民族だということです。 ・日本人の宗教的習俗と欧米人のそれとのさまざまな違いを象徴的に明示するものが、墓参の慣習の有無ではなかろうか。 焼香について ・私たち日本人は死者とのコミュニケーションを持つことができると信じ、この世とあの世とは交通可能であると信じている、というのが間違っていなければ、焼香こそはそのコミュニケーションのメディアなわけです。虚空にひろがり消えてゆく焼香の煙にたくした、この焼香のシンボル的な意味は、あらためて考えてみなければならないと思うのです。 ・仏教は仏を供養する方法として焼香を採用した。 ・つまり焼香は、仏と私たち、そしてさらに死者と私たちとがさまざまなコミュニケーションを持つ、おそらくは唯一のてだてなのです。 神について ・拍手を打つのはどういう意味があるのでしょうか。 ・要するに、音によって「神」の注意をひくのではないでしょうか。 ・日本の神々のきわめつきの特徴は、人間神、つまり人間が祀られれば神になるという信仰ではないでしょうか。 ・これは仏教で人間が成仏する、つまり仏になるという信仰とパラレルな考えですが、神の場合にはあくまでも人びとによって「祀られる」ということが必要条件です。 ・いわゆるアニミズム(物活論あるいは精霊崇拝)が普遍的なものとしてあって、その上に「人を神に祀る風習」が乗っかったのだと思われます。 ・そして日本人のアニミズム的心情は、今日においても強固に生き続けています。日本人は祭りが大好きです。 ・日本の神々は現代でも生きているのです。「祭如在」(祭ればいますがごとし)です。 神仏習合について ・鈴の音をたてたりするのは、起源的には、参拝者自身が一種の神憑りの状態――つまり神とのコミュニケーションを持ちうる心身の状態――に入るためであったでしょう。 ・ちょうど神楽を舞う巫女(=かんなぎ)が手に持つ鈴と同じ意味だったでしょう。 ・しかし、今日、神社詣でをしている人の意識は、おそらく神の注意を呼びさますということではないでしょうか。 ・行動形態(習俗の形)は同じでも、それに伴う意識、つまりそれの意味づけは歴史的に変化します。それと同様に、日本の神々の性格も歴史的に変化しました。 ・およそ古代の神々は、御霊神社というようなあり方をしたように、恐ろしい神、たたりをする神、ユダヤ教の神と同じ性格といってよい畏怖神でした。その神々がいわゆる「衆生擁護の神」、恩恵をたれる神へと変貌したのは、やはり仏教の影響といわなければならないでしょう。 ・仏教はキリスト教や回教のような征服の宗教ではなくて統合の宗教でした。 ・本地垂迹の説 中国では、儒教の聖人や道教の神などは、本地としての仏がこの世に迹を垂れたものと説かれ、日本でも神道の神々について同じように説かれたわけです。 ・この本地垂迹の説が、わが国の宗教のいわゆる神仏習合というあり方を理論づけるもっとも代表的な形です。なんとか神と仏とが共存しうる形を考えたわけです。 ・奈良時代には神社に付属した寺、神宮寺が建設されるという形でしたが、平安時代中期に仏との地位が逆転していわゆる本地垂迹説が成立しました。 ・天台宗から山王一実神道、真言宗から両部習合神道と呼ばれるものが作られました。 ・鎌倉時代になると、代表的な神々にそれぞれの本地である仏が選定される(たとえば八幡神にたいして阿弥陀仏)一方、法然さん、親鸞さんのように弥陀一仏、神祇不拝といういわば一神教にちかい態度決定が初めて出てきました。 ・南北朝ごろから、従来の従来の仏本神迹をふたたび逆転して神本仏迹を主張する神道主義者(たとえば北畠親房)が現われ、室町時代の吉田兼倶の唯一神道、江戸時代の国学へとつながります。 ・そして最終的には、近代明治国家によって政治制度的に神仏の分離が果たされたわけです。 愛について ・平安時代に保元の乱まで約四百年近くも死刑が行われなかったという、世界に例のない事実があります。 ・敵も味方も仏の慈悲のもとにすべて救われるという仏教の「怨親平等」の思想は日本人の心に浸透しました。 ・わが国では戦争の勝利者は敵味方の亡霊を平等に弔ってきたのでした。 論理について ・あの世とこの世とはコミュニケーションが可能であるとする日本人の「墓参」の習俗がある。 ・私たちには「袖ふれあうも他生の縁」とか「縁は異なもの味なもの」という言い方を好むように「縁」というもので生活の葛藤を少なくしようという一種の知恵があります。 死について ・日本語の “死ぬ” の語源は「シイヌ」(息去)だとされている。つまり「息がなくなる」ことである。 いかに死ぬか ・人間のみが自殺できる。人間は生きる基本的人権(要求)をもつとともに、 “死ぬ権利” “自殺する基本的人権” をももっている。 何のために死ぬか ・古代ギリシャのエピクロスは「死はわれわれにとって無である。われわれが生きているかぎり死は存在しない。死が存在するかぎりわれわれはもはやない」といった。 ・仏教は、もともと生病老死を超越する道をもとめるところから出発し、釈迦自身は死を無視すること(解脱)によってそれを超越した。 ・しかし、仏教のうちの浄土教は、極楽をたてることによって、キリスト教とはちがう形の「死への挑戦」をめざしたといえる。 葬送のかたち ・民俗学者の柳田国男は、日本の常民の「死」のとらえ方の特色をつぎのようにまとめた。 (1)人間の霊魂は死後もこの国にとどまって遠くに行かないと考える。 (2)この世とあの世、顕幽二界の交通が頻繁であって、いずれか一方がそう思えば、コミュニケーションができると思う。 (3)子孫のために死にぎわにねがったことはかならず死後に達成されると思う。 (4)二度でも三度でもこの世に生まれかわってきて、おなじ自分の事業を継続できると思う。 ・これはキリスト教とはよほどことなる「死への挑戦」の仕方である。 ・(2)の死者と生者とのコミュニケーションだけは、今日も日本人の習俗として持続されているといえる。そしてこれこそ西欧人などとの決定的な相違点であろう。 ・すなわち、日本人はキリスト教文化圏の人びととちがって、死者の墓参を好む、少なくとも忌避しない民族であるということである。 ・日本人にとっては、両者のコミュニケーションが可能と信じられていればこそ、命日や彼岸やお盆の展墓の習俗が維持されているのである。 仏教と日本人の美意識 ・ファとシぬきの日本の伝統的ないわゆる五声音階の歌謡。 ―― 完 ―― |