
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2023年11月26日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | 抜き書き&コメント |
31 |
23.11 |
生き方のコツ 死に方の選択 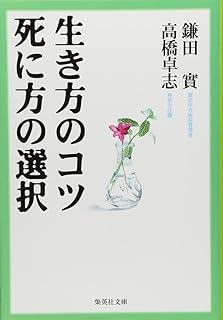 |
鎌田 實 高橋卓志 |
集英社文庫 |
◎ |
死を受け入れる 「家で死ぬ」ということ 鎌田先生(へのメッセージ) ・チューブに取り巻かれて迎える死が、いまの時代では普遍化されてしまい。そのことにだれも疑問をもたなくなってしまったのです。 ・手厚い治療機器と最新の医薬品に守られた病院という堅固な城の中で、ルーティーンの流れに沿った医療行為を施されることが家族にとってみれば、「最善の手は尽くした」という印象を強くするはずです。 ・「何もしないで、いのちの流れにまかせてほしい」などという要求を家族がしようものなら、かえって批判されてしまいます。 ・逝く人にとってどんな状態や環境が最も快適なのかを、その人の立場に立って考えるという基本的な思考を、現代人は忘れてしまったのかもしれません。 「いのち」の受け渡し ・自宅の畳の上で死にたいという願いは、実は畳が問題ではなく、親戚や家族のあたたかい関係のなかで、それらの人々に見守られ、子どもたちや孫たちに「いのちの受け渡し」の認識をさせていくという大切な場所の設定のことをいうのです。 「死をはげます」ということ いのちの終末にできること 鎌田先生 ・古来、寺というものは病院としての機能を備えていました。 ・聖徳太子が日本に初めて建てた寺、四天王寺は悲田院、施薬院、療病院、 ・そこに仏教の修行道場としての敬田院を加えたものが「寺」というものであったわけです。 ・だからここには、すべて死後にかかわり、葬式、法事だけを行なう現代の寺の姿は見えません。 ・寺は生きている人のためにあるもの、もっと言えば生きながら苦しみを抱え、病を得、行き暮れている人々のためにあったのです。 病院とお寺が仲よくするなんて 卓志和尚 ・なぜ今まで医療と宗教は仲良くなれなかったのでしょうか。 ・ホスピタルやホスピスの語源はラテン語でホスト(客をもてなす主人)という意味をもち、本来は旅人が憩いのために短期滞在したり、病気や傷ついた人や貧困者をケアする場所として、中世のヨーロッパに宗教団体の手で建設されたものだったようです。 ・日本でも寺院は江戸時代までは教育の場であったり、病を癒す場であったりしました。 ・四天王寺や薬師寺などはまさに癒しの空間だったのではないでしょうか。 ・欧米では、キリスト教系の宗教は現代においても病院の中に入りこみ、大きな役割を担っています。 ・しかし、日本人の多くが信仰している仏教は、病院の中になかなか入りこめていません。いつ頃からか仏教が葬式仏教になってしまい、「死んでからお世話になる所」と、多くの人に思われるようになってしまいました。 ・僧衣を着てぼくの病院を歩けば、半分くらいの方は「縁起でもない」と思われるのではないでしょうか。 ・教会で行なっている日曜礼拝などのような日常活動がないと、ターミナルステージに突然僧衣を着て登場するのは無理なことだと思います。 ・Length(長さ)にこだわる医療にとって、宗教は不必要なものになってしまいました。 (LOL=命の長さ) ・しかしQOL(いのちの質)の重要性に、医療は気づきはじめました。 ・いのちの質を考えるとき、宗教の役割はこれから大きなものになると思います。 ・タナトロジー(死学)のなかで、人間の痛みには、肉体的痛み、精神的痛み、社会的痛み、宗教的痛みの四つがあるといわれています。 ・LOLを目標にし続けてきた現代医学は、アンバランスなほど肉体的痛みだけにこだわってきたようです。 いのちを支えるネットワーキング ・今、「いのち」が見えなくなりはじめています。 ・病院の最大限の努力で生きのびた生命は、自然の環境から切り離され、入院中のほとんどの時間を一人ぼっちで過ごし、最後の大切な限られた時間を死の恐怖に襲われて、不安なときを送っていないでしょうか。 世界はお前の誕生を待っている 鎌田先生 ・本来「枕経」というものは、臨終の際に枕もとで読まれたものだ。 ・かつて仏教は死の訪れる以前からその人と共にあり、最後の瞬間をお坊さんが家族といっしょに、仏教のもつ臨終作法によって見送っていた時代があった。 闘った、生きた、そして輝いた 卓志和尚 ・いのちは長さではなく、輝きなのだ。 ターミナルケアと宗教 鎌田先生 「がんばって死んでほしい」という思い ・肉親の、あるいは愛する人の死に臨み、「死んではだめだ、死なないでくれ」とは、ほとんどの人が願うことです。でも「よしよし、よくがんばった。よく生きてくれた、もういい、もういい」と死を受け入れ、死をはげます人もいるのです。 ・病気は悪であり、死は忌み嫌われるものであるという考えが「死ぬな」という言葉をうみ、そして医療の中の延命治療もその線上に乗っているのです。 ・ひとつのいのちには、必ずひとつの死があります。それをどう死ぬか、あるいはどう見送るかは、その人が対象とするいのちと、それまでどうかかわったかにかかっていると思うのです。 死が語りかけるもの インフォームドチョイス 卓志和尚 人は人として生まれて人間として死んでいく ・「死が近づいていることを知っていながら、父(義父)は毎日の朝の散歩をやめませんでした。動けなくなって人に迷惑をかけてはいけないと考えていたようです。同時にわずかな可能性かも知れませんが、体力をつけておけば癌と少しは闘えると思っていたのだと思います。どんなときも前を見て生きていた父でした」 【私見 : 自分の父親を思いだす。同様の行動パターン、思考パターンであった】 一日一日を全力で生きる ・死の前日まで、できるだけ子どもたちの介護を受けないようにがんばり続けました。 死に逝くいのちは誰のものか どうしてそんなに急ぐのか? 鎌田先生 ヒューマンスケールの復活 ・医療の分野では、ターミナルケアやPCUという人間本来の「生」の最終コーナーをどう回るか、ということが真剣に語られるようになってきました。 ・いのちの長さに焦点を絞った医療から、いのちの質をどう考えるかという焦点が生まれてきたのです。 さらばスパゲッテイ症候群 卓志和尚 ・日本では、診る側と診られる側の上下関係がつくられ、その上下関係のなかで行なわれる医療は、医師の「全力を注ぐ」医療が優先されてきました。 ・死は、医師にとっては敗北を意味していました。スパゲッテイ症候群という悲しい言葉が生まれました。 ・死に逝く患者が、たくさんの管につながれ、ダイイングメッセージ(お別れの言葉や最後の言葉)を述べるチャンスも与えられないまま、無念の死を遂げていきました。 ・医師たちは治療に夢中になりすぎて、患者のいのちを自分の持ち物のように錯覚してしまいました。悲しい歴史です。 レイテとチェルノブイリ ぼくたちが生きている時代 鎌田先生 ひとりひとりのいのち ・彼の国は政治や経済が大混乱しています。本来いのちの最前線にいなければならない医療は、財源がないという理由で放り出されています。 ・世界の二大国といわれ、七〇年に及びわれわれに内実を知らせることのなかった旧ソ連邦は、その間累積された矛盾が爆発し、まさに破産宣告した国家のような印象を与えます。 ・その矛盾の矛先が、小さな子どもたちのいのちの喉元に突き付けられているかのようです。 ・医薬品は底をついています。プライマリな医療を展開するための機材・器具がまったくありません。 ―― 完 ―― |