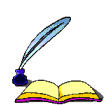
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2024年03月03日 日曜日 】
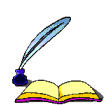
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | 抜き書き&コメント |
32 |
23.12 |
日米戦争観の相克 【摩擦の深層心理】  |
油井 大三郎 |
岩波書店 |
◎ |
第一章 パールハーバーとヒロシマ・ナガサキの間 2 ポスト・パールハーバーの歴史心理 「よい戦争」と「文明化の使命感」 ・敗戦を経験した大多数の日本人にとって、あの戦争は、目的においても、手段においても、とうてい「よい戦争」とはいえず、むしろどんな戦争でも、「戦争はもうこりごり」というのが戦後の共通した国民感情になった。 ・それに対して、米国の場合、何といっても、戦勝国である上、第二次大戦は、反ファシズムの「聖戦」と意識されたこと。それに加えて、直接本土が戦場となることを免れた上、延べ動員数、一六四〇万人弱の中、戦死者数は四〇万人強で、他の交戦国に比べれば、相対的に犠牲が少なかったこと。さらに、戦時経済の急速な拡大によってそれまでの長期不況から離脱することが可能となったことなどが、目的においても、手段においても、「よい戦争」と意識させる根拠が数多く存在した。 ・しかも、米国の伝統的な政治風土の中では、戦争を政治目的を実現する正当な手段視する傾向が根強く存在する。 ・それは、独立自体がイギリスとの戦争によって獲得されたことに始まり、「西漸運動」と呼ばれた西部への領土拡大も、多くが、インディアン諸部族やメキシコとの戦争によって実現したことによっている。 ・古くは、ワシントン、ジャクソン、グラント、戦後ではアイゼンハワーに示される通り、戦時の英雄が大統領に選ばれたケースが多々見られるのもそれ故である。 ・その上、戦争の目的が、単なる即物的な利益の追求だけでなく、道徳的な使命感に彩られて語られることが多いのも、米国外交の伝統的な特徴であろう。 ・それは、そもそも、ヨーロッパを「旧世界」として批判し、それに反発して移住した初期の植民者自身が、北アメリカの荒野を「文明化」し、「神の国」を建設しようという強い使命感を抱いていたこと、そしてそのような使命感が米国の「建国神話」の中核となったことに由来しているのである。 ・しかも、この「文明化」の使命感は、皮肉なことに、インディアンを掃討し、黒人を奴隷化することを、当初は、当然視するような両義的性格をもっていたのであり、一九世紀末以降になると、それは、アジアへの進出を当然視するようにもなった。 ・米西戦争の直後にフィリピンを訪問したアルバート・ベヴァリッジ上院議員は、「全人類の中でも、神はアメリカ人を選ばれ、この世界の救済において先立ちをする選民とされた」と語って、米国によるフィリピン併合を正当化したという。 ・もちろん、第二次大戦の場合は、「反ファシズム」という連合国に共通した独自の政治目標があったが、米国がその戦争に国民の意識を動員してゆくうえで、このような「文明化」の使命感を強調する伝統が無視できない影響力をもったことも忘れてはならない。 ・たとえば、パールハーバーへの奇襲の直後、ローズヴェルト大統領がこの奇襲を「法の支配」にたいする「野蛮な挑戦」であり、「非文明的行為」とみなした論法にも、自らは「文明」の担い手であるという自負心が読みとれるであろう。 ・そして、戦後は、ソ連との「冷戦」が激化するにつれて、「自由主義」陣営の盟主としての自負が付加され、米国の外交は過剰なイデオロギーに拘束されてゆくことになる。 「聖戦」下の日系人差別 ・他方、第二次大戦中に高揚した「使命感」もまた両義的な性格を免れなかった。それは、「反ファシズムの民主主義擁護」を標榜した米国自体が、その国内においては、約一二万人もの日系人を内陸の山岳地帯に「転住」という名の下に強制隔離したという矛盾に象徴される。 ・当時の米国西海岸における日系社会の三分の二は、米国生まれの二世、つまり、米国市民権をもつ人々で占められていた。一世の場合は、米国の人種差別的な帰化法のために、帰化が認められず、日本国籍のままであったが、多くは何年も米国に住みついていた永住者であった。 ・しかし、フランク・ノックス海軍長官が記者会見で、確たる根拠もなしに、日本軍の奇襲成功の背後にはハワイ在住日本人の「第五列的な協力」があったと示唆したこと。 ・また、パールハーバー攻撃後の日本軍が破竹の勢いで東南アジア方面に進撃していたことなどの条件が重なって、日本軍が米国の西海岸を攻撃する危険や日系人がそれに協力する恐れが、新聞報道や伝聞の形とで、まことしやかに流布されていった。 ・その結果、アジア系移民の排斥団体や西海岸選出議員の間から日系人の強制送還や集団隔離を求める声があがり、陸軍省の内部でも強制隔離が検討された結果、一九四二年、ローズヴェルト大統領によって、日系人の強制隔離が命令された。 ・その際、米国市民である日系二世の扱いが問題になったが、西部防衛司令部の司令官に任命されていたジョン・ドゥウィット中将は、「ジャップはジャップだ。アメリカ市民であろうがなかろうが、ジャップにかわりはない。彼らは不必要であり、……危険分子だ」という有名な文句を吐いて、一括して強制隔離するように主張した。 ・結局、西海岸に居住していた日系人は、二世も含めて、一括して立ち退きを強制され、短時日の間に全財産を売却し、主としてロッキー山脈などの荒涼とした山岳地帯に建てられた十カ所の収容所に分散させられていった。 ・パールハーバー奇襲に始まる日米戦争は、在米日系人に想像を絶する苦難を与えたのであり、「パールハーバー」五〇年を振り返る時、彼らの苦悶の歴史に言及しないわけにはいかない。 ・しかも、彼らの歴史は、単に、米国社会における人種問題を考える上だけでなく、米国における国家と個人の関係や愛国心のあり方を検討する上でも、貴重な経験を提供してくれるのである。 ・たとえば、強制収容所から志願して、欧州戦線に派遣された日系人部隊の第四四二部隊が、多大の犠牲をだしながら、輝かしい戦績をあげ、そのおかげで、戦後、日系人に対する差別が大幅に改善されていったことはよく知られた事実である。 ・戦争中には、みずから従軍して「血」で忠誠を示した日系人たちの方が米国社会では高く評価された。 ・国家と対決する市民よりも、国家と一体化する「市民」の方が米国社会でも評価される時代であった。 人種差別撤廃への外圧 ・戦時中の米国社会で高揚した愛国主義は極めて人種差別的な側面ももっていたが、同時に、それが「反ファシズムの民主主義擁護」という戦争目的と矛盾することも明らかであった。 ・米国側は、戦後にアジアや太平洋地域で影響力を拡大するためにも、米国国内におけるアジア系移民差別の是正が不可欠であることを自覚させられていった。 ・その結果、まず、一九四三年に米国議会で、中国系移民の入国と一世の帰化権を否認していた一八八二年以来の差別法が廃止された。ついで、戦後になって、一九四六年にはインド系とフィリピン系に対する法的差別が撤廃され、日系移民に対する差別条項は一九五二年のウォルター・マッカラン法によって廃止された。 ・このような一連のアジア系移民差別法の撤廃過程は、アジア系移民自身の運動の産物というより、戦後のアジアへの影響力の拡大を重視していた米国政府の外交的配慮の賜物という性格の方が強かった。 ・また、ナチズムによるユダヤ人虐殺の実態などがニュールンベルグ裁判などで暴露されるにつれて、人種差別の否定を求める国際世論が一層高まりをみせ、一九四八年の国連総会は満場一致で「世界人権宣言」を採択したが、その二条では「皮膚の色」による差別を明確に禁止していた。 ・他方、米国の南部社会では、依然として「ジム・クロー制」とよばれた人種隔離制度が維持されていたから、国際世論と南部社会の溝は開く一方であった。 ・そうした中で、一九五四年、米国の最高裁判所は、ウォーレン長官の下で、人種隔離政策を違憲とする画期的な判決を下すのであり、それ以降、黒人の公民権運動が、司法に助けられながら、進展してゆくことになる。 ・そして、一九六四年の公民権法と翌六五年の投票権法の制定によって、南部の人種隔離制度はほぼ一掃されることになった。 ・しかし、法的な差別が廃止されても、経済的格差が変わらず存続している現実に苛立った若い国人たちを中心として、一九六〇年代半ば以降、「ブラック・パワー」運動が盛んになっていった。 ・それは、日系人の場合でも例外でなく、特に、当時、学生であった三世たちが中心となって、一九七〇年代に入ってから、米国政府に日系人の強制収容を誤りと認め、保障を支払うように要求するリドレス運動が始まった。 ・当初、一世や二世はこの運動に消極的であった。それは、収容体験が彼らを委縮させ、戦後はひたすら黙々と働き、米国の主流社会に同化することによって地位上昇を遂げようと努力してきたからである。 ・まさに「サイレント・アメリカン」という特徴を一身に帯びて努力してきた一世や二世にとっては、政府に謝罪を要求することなどとても考えられなかったのである。 しかし、六〇年代の激動を通じて米国社会にあっては、さまざまなエスニック集団の個性を相互に尊重する ・しかも、戦時中に敗れた裁判の再審請求をおこす過程で、再審に決定的に有利な政府資料が発見された。 ・それは、陸軍省側が、日系人の強制収容の軍事的必要性を否認する文書を作成していたのに、裁判所にはそれを改竄して提出していたことを示す証拠であった。 ・そうした結果、一九七六年には、フォード大統領が、強制収容を命じた行政命令第九〇六六号の無効を宣言、一九八〇年には、連邦議会に強制収容問題の調査委員会が発足し、三年間にわたって、全米各地で公聴会を開催した末、強制収容を人種偏見に基づく誤った措置であったとする報告書が提出された。 ・再審裁判の方も、八四年から八七年にかけて勝訴し、八八年には、連邦議会が強制収容者一人あたり二万ドルの補償金の支払いを可決したことにより、リドレス運動はその目的を達成したのである。 日系人補償の投げかけるもの ・日系アメリカ人のリドレス運動が勝利したというニュースは、日本人に複雑な感慨を抱かせる。 ・もちろん、日系人に対する偏見の是正は、共通の文化的ルーツをもつ日本人としても歓迎すべきことであろう。 ・しかし、他方で、戦勝国の米国でさえ、戦時中の不正行為を謝罪し、被害者への補償を決定したというのに、敗戦国の日本は、戦争被害を与えた外国の人々にこれまで何をしてきたのか、という自責の念を禁じ得ないのである。 ・事実、日系人への補償決定のニュースは、アジア各地の戦争被害者や日本軍に虐待された連合国側の元捕虜の人々に大きな刺激をあたえた。 ・旧西ドイツの場合、日本と同じ敗戦国でありながら、一九八五年のヴァイツゼッカー演説に象徴されるように、繰り返し「過去」の反省に言及し、戦争被害者への補償に努力してきた。その努力なしには、西ドイツがECに加盟したり、一九九〇年のドイツ統一が近隣諸国によって受け入れられることはなかったであろう。 ・ドイツの場合、明らかに、「過去」の ・日本政府の場合には、最近、国連の安全保障理事会の常任理事国化や国連憲章の「敵国」条項の削除を求めたり、国際社会への「人的貢献」を推進する動きが目立っているが、「過去」をひきずったままで、果たして近隣諸国に信頼される「貢献」などできるのであろうか。 ・日本人に対する偏見に限らず、ステレオタイプ化した過去のイメージの底には、しばしばドロドロした非合理的な感情が渦巻いている。それを氷解させるには、カタルシス(浄化)効果を生みうる明確な行動、具体的には、戦争責任の清算につながるような、外国人の戦争被害者に対する謝罪と補償が必要である。 【私見 : アメリカの人種差別、ドイツのユダヤ人排斥など、明確に区別して認識できるものは良いが、日本の場合、何をもって戦争責任とするかが問題。 日本のやったことが全て悪かったと全否定されると、国として反省も補償もできないだろう。東京裁判でも、日本の戦争行為自体をすべて悪として裁定した。 日本の戦争責任を明確にするためには、戦争そのものの本質は自衛のための戦争だったと日本国が主張し、その上で、具体的な事例(例えば、食糧の現地調達時の犯罪、捕虜の虐待、外国人収容所での人権問題等々)を取り上げて責任を明確にし補償すべきものは補償するべきである。】 3 アメリカ社会とヒロシマ・ナガサキの影 原爆投下研究のミッシング・リンク ・どのような目的のためにせよ、原爆という手段の採用が連合国の戦争目的や当時の戦時国際法に照らしてどう認識されていたのか、また、実際に投下された後に、民間人が大量に犠牲になったという実態が知らされるにつれ、政策決定者や一般のアメリカ人はどう反応したのか、という点については十分な検討が行われてこなかったように思われる。 ・原爆が戦闘員と非戦闘員の区別なく、大量で無差別な殺戮を伴う平気である点を当時のトルーマン政権や一般のアメリカ人が事前に、また、事後にどのように考えたのか。 ・たとえば、一九三七年七月に始まる日中戦争の過程で日本の戦闘機が中国の民間人居住地域を空爆した時に、アメリカ政府は次のような見解を表明していた。 「平和的な仕事に従事する多くの人々が居住する広範囲な地域を全般的に爆撃することはどのようなものであれ、法律と人道の諸原則に反し、許されないものである」と。 ・しかも、このような多数の民間人の犠牲を伴う都市に対する無差別爆撃は、日本軍が最初ではなく、一九三五年におこったエチオピア侵略の際のイタリア軍機によって、また、スペイン内戦の折りには有名なゲルニカ爆撃が強行され、その都度、米国は非難の姿勢を明確にしてきた。 ・また、ジュネーヴ条約でその使用が禁止されていた生物化学兵器の場合には、日本軍が中国戦線で使用したことを厳しく非難しつつも、一九四三年六月にはローズヴェルト大統領は米国が枢軸国に対して生物化学兵器を先制使用する意思のないことを確認した。 このように米国側は、少なくとも戦前期や戦争初期には使用する武器や戦闘形態などの点で枢軸諸国に対する道義的優位を保つように努力とていた。 ・しかし、その姿勢が徐々に変化してゆくのは、米国も「戦略爆撃」という攻撃形態を採用し始めてからであった。 ・一九四一年六月には陸軍航空隊が発足した。 ・この航空隊の任務には、陸海軍の戦闘を上空から支援する補助的な任務の他に、独自に軍需工場など枢軸国側の戦争遂行能力そのものの破壊をめざす戦略爆撃とがあった。 ・大戦末期となり、枢軸軍が占領地から押し戻され、自国領土内に抗戦拠点を移し始めると、後者の役割が大きくなって行った。 ・その際に問題となったのは、相手側の軍事関連施設と民間施設をどう区別して爆撃しうるか、であった。 ・当初、米国においては「照準爆撃」という形で軍事目標に限定した爆撃を実行すると説明されたが、制空権が完全には確立していない段階では、敵機の反撃や対空砲火を避けるため、かなりの上空から爆撃したり、夜間に爆撃することも多く、特定の目標に集中して爆撃することは事実上不可能であった。 ・その上、徐々に戦略爆撃の目的の中に相手国の戦意の減少や喪失が加わって来ると、むしろ意図的に民間人の居住地域が爆撃目標となっていった。 ・とくにそれは広範囲に火災を発生させる焼夷弾を特定地域にじゅうたん爆撃する戦術の採用に象徴される。 ・一九四三年七月末から八月初にかけて英米両空軍機によって行われたハンブルグ空襲はその最初の事例となった。 第二章 朝鮮戦争と「寛大な講和」の代償 1 占領期の対日イメージ 間接占領方式の陥穽 ・ <途中> |