
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2025年03月19日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | 抜き書き&コメント |
33 |
23.12 |
新 脱亜論 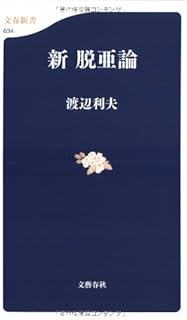 |
渡辺利夫 |
文春新書 |
☆☆☆ |
第1章 先祖返りする極東アジア地政学 「先祖返り」する極東地政学 ・現実の歴史は福澤の予告通りであった。 ・日本を悩ませたのは清国と朝鮮ばかりではない。その背後には、日本海に不凍港を求めて南下を覗うロシアが位置していた。 ・要するに、近現代の日本にとっての最大のテーマは、巨大なユーラシア大陸の中国、ロシアに発し、朝鮮半島を伝わって迫り出す「等圧線」からいかにして身を守り生存を図るかにあった。 ・福澤は日本の生存のための唯一の方途は隣国と「謝絶」し、自らのアイデンティティを東洋にではなく西洋に求め、そうして初めて日本の自立が可能になると主張したのである。 ・福澤をしてそう主張せしめたほどに大陸の状況は日本の生存にとっての「厄事」であった。 ・事態はアジアとの謝絶にとどまらず、日清・日露の両戦争にまで発展し、これに勝利することによって日本はようやく自立の危機を脱することができた。 ・現在の極東アジアはあの時代の日本を深く悩ませた地政学的構図が再現したかのごとくである。 反米、反日、親北の制度化――韓国 ・二〇〇四年三月、日帝下の「親日・反民族行為真相糾明特別法」が超党派議員の共同提案によって成立した。日本統治時代の対日協力者を糾弾するための特別法である。 ・はるか以前の歴史の事実を現在の時点から遡及して犯罪とする事後法であり、罪科を問われる人間が当事者ではなくその子孫であり、彼らの財産の没収であり、私有権の完全な否定である。近代法の精神はここでは完全に無視されている。 「侮日政策」の ・中国の反日は、「五・四運動」に淵源をもつ「侮日政策」の再現である。 ・五・四運動とは、第一次世界大戦後、この戦争に参戦した日本がパリ講和会議において山東省のドイツ権益の委譲を受けたことに端を発した排日運動である。 ・親日官僚の罷免、日貨排斥などを要求し日本と日本人への徹底的な侮蔑をもってその特徴とした。 ・共産党のアイデンティティの淵源は抗日戦争の勝利にある。 ・反日は求心力を求める政権中枢部にとって、今なお中国人の観念操作の重要な武器なのである。それゆえ現在の侮日運動の内実は日本人の「歴史認識」への糾弾をもってその特徴としている。 ・昭和四七(一九七二)年の日中共同声明にいたる外交交渉においても「歴史認識」など問題にはなっていなかった。 ・外交交渉の主題は台湾帰属問題と戦時賠償問題に限られていた。 ・靖国参拝などは元来が日本の内政問題であり、これを外交問題に仕立てたのは中国政府の「狡知」以外の何ものでもない。 ・この問題での日本側の後退は、日本人の深層部に眠るナショナリズムの情念を搔き立て、日中関係を修復不能な事態に立ちいたらせてしまいかねない。中国の狡知に負けぬ強靭な外交力を日本は練磨しなければならない。 ・その意味でも私どもは、清国の存在に強烈な危機感を抱いて日清戦争に挑んだ明治期の政治指導者の言説に、いま一度耳を傾けてみる必要がある。 「ペトロステート」――ロシア ・カーネギー・モスクワセンターの一研究員は近年のロシアを「ペトロステート」と呼び、次のように述べている。 「権力と企業の癒着、天然資源の販売による利益で生活する不労所得者層の登場、汚職、巨大独占企業の支配、富者と貧者の格差の拡大など、ペトロステートの主な特徴がますます目立つようになっている。『核ペトロステート』、すなわち核超大国の野望を持つ一次産品依存国という新しい現象が、いつの日かその強引さで世界をあっと驚かせるかもしれない」 ・石油や天然ガスの今後の開発地域はロシア東部、シベリア・極東である。 ・北方四島返還に対するますます頑ななロシアの対応を合わせ眺めれば、この巨大なペトロステートが資源不足日本への「圧迫」わ加えてくる可能性を否定することはできない。 ・南下政策に悩まされつづけたあの時代の構図が再現しないとはいえない。 第2章 陸奥宗光の日清戦争――機略と豪気 外交とは友好や善隣ではない。国益の確保そのものである。 激怒する福澤諭吉 ・福澤諭吉がみずから創刊した日刊紙『時事新報』に社説として「脱亜論」を掲載したのは明治一八(一八八五)年三月一六日である。 ・福澤は朝鮮の近代化を願い、ともに「西力東漸」に立ち向かわざれば亡国の危機に陥ることを懸念していた。 ・日本の明治維新に衝撃を受けて福澤に接近し、その教えを乞うて国内改革を図ろうとした朝鮮開化党の金玉均や朴泳孝らに福澤は厚誼をもって接した。 ・金玉均らが派遣した多くの留学生を受け入れ別邸に住まわせ、近代国家建設のための諸制度についての知識を彼らに懸命に授けた。近代化された日本と朝鮮の二つを福澤は運命共同体とさえみなしていた。 ・その福澤が「脱亜論」をもって朝鮮への対応を豹変させたのである。 ・福澤を豹変させたのは、国の将来を顧慮することなく、いたずらに繰り返される朝鮮内の政争と内乱であり、しかもみずからに少しでもことを有利に運ばんとして国内問題に時に清国を、時にロシアを巻き込んで ・実際、内乱や政争の度ごとに清国に援軍を依頼するような朝鮮は日本にとって危険きわまりない存在だとみなして、日本が清国に挑んだ戦争が日清戦争であった。 華夷秩序への挑戦、日本の自衛 ・日清戦争とは、一言で言えば朝鮮半島をめぐる日清間の帝国主義的な覇権争奪の戦いであった。 ・なぜ朝鮮半島が日清覇権争奪の場になったかといえば、その地政学的な位置が考慮されねばならない。 ・朝鮮半島がユーラシア大陸から日本の脇腹に向けて突きつけられた一本のナタのような形状をもって位置していることが分かる。 ・中華帝国、ロシア帝国、モンゴル帝国などのユーラシア大陸の強大国が日本への勢力伸長を図ろうという場合、朝鮮半島を通過せずしてそれは不可能であった。・それゆえ朝鮮半島が日本の敵大国となったり滴定的勢力の影響下におかれることは、日本としては絶対にこれを避けねばならなかった。地政学上の宿命である。 ・しかも李朝時代の朝鮮は清国と君臣関係にあって、清国に服属していた。服属の証として朝貢の礼式に服し、その見返りに王号や爵位を与えられて民の統治を委ねられるという国際秩序の下におかれていた。 ・中華帝国を中心としたこのような階層的な国際秩序が「冊封体制」である。 ・冊封とは、君主が臣下に冊書と呼ばれる命書を授け、任命を受けた臣下が君主から土地(封土)を与えられる行為のことである。 ・冊封体制をもたらした中華帝国と周辺諸国との価値の関係がすなわち「華夷秩序」である。夷とは東方の異民族であり、野蛮人のことである。蛮夷ともいう。 ・華夷秩序においては礼にもとづく道義性の序列において最も高位にあるのが中華であり、この中華から外縁に向かって同心円的に広がり、中華から遠くに位置する民族ほど価値において低いという上下関係が想定された。 ・黄河中下流域の「 ・朝鮮はこの華夷秩序に組み込まれて中華に強く服属をせざるをえない位置におかれていた。一方、日本は華夷秩序の埒外にあった。 ・そうなったのは、中華帝国との地理的な近接の度合いねすなわち中華帝国の圧力を直接的に受けざるをえない朝鮮と、対馬海峡の荒い潮流によって半島から隔てられ中華帝国の影響を排除できる位置にあった日本という地政学的なポジションの違いであった。 ・朝鮮が華夷秩序の中に「構造化」され、日本がその埒外にあったというこの事実が、開国維新後の日本と朝鮮との関係の順調な進展を妨げ、ついには日清戦争にいたらしめた背景要因である。 ・明治新政府樹立の旨を伝達し、新たな修好を求める国書をもって釜山港に入った日本使節が対馬藩家老であったが、李朝は国書の受け取りを拒否した。 ・拒否の理由は、国書に「皇上」「奉勅」の二字が記されていたからだったという。 ・「皇」は中華帝国の皇帝、「勅」は中華帝国の詔勅を意味し、この文字を記した国書を、日本の臣下ならざる朝鮮が受け取ることは原理的に不可能だというのである。再三、再四の日本側の要求はこの理由によってすべて朝鮮政府によって拒絶された。 ・当時の日本の朝鮮外交は対馬藩を通じてなされていたが、後にこれが外務省に移され、釜山に所在していた「 ・この公館に対して李朝は食糧や燃料の供給を絶つという挙に出た。この非礼に対して日本は軍艦「春日」と歩兵二個大隊を釜山に送り国書の受け取りを要求したものの、朝鮮はなお頑なにこれを拒んだ。 ・日本側で湧き起こったのが「征韓論」である。筆頭参議、陸軍大将西郷隆盛が、征韓派の副島種臣、板垣退助等の支持を受け、至誠をもって朝鮮への説得に当たれば道は開かれるとして行動に出ようとした。 ・しかし遣欧使節団の旅行を通じて欧米列強の国力を心底知らしめられた大久保利通、岩倉具視等による、列強介入の口実を与えるような征韓はならじとの強硬な反対を受けて、西郷の遣韓は頓挫。西郷はその後下野を余儀なくされ、これが西南戦争の遠因となった。広く知られる征韓論の顛末である。 ・征韓論とは朝鮮を華夷秩序から引き剥がさんとする日本の最初の外交攻勢であった。しかし、李朝はこの日本の攻勢を排除してますます固く華夷秩序の中にみずからを封じ込めてしまった。 ・欧米帝国主義の「西力東漸」が日に日に勢いを増す中にあって日本はこれに抗するには「富国強兵」をもってするしかないと臍を固める一方、李朝は「夷族」日本の富国強兵を西洋の猿真似を演じる「仮洋夷」と見立てて蔑視し、近代化に背を向けつづけた。 ・開国と近代化を拒んで独立への気概なき朝鮮がこのままの状態であっては列強による支配はまぬかれず、開国維新を経てまだ幼い日本の安全をも危殆におとしめると往時の日本の指導者は考えたのである。 ・征韓論が西郷等によって日本の「自衛策」として認識されたことは不合理ではない。征韓論は日本が中華主義的な華夷秩序に挑戦した初めての ・陸奥宗光は次のようにいう。 「朝鮮半島は常に ・日本が朝鮮の「安寧静謐」を求めて行動するのは「自衛の道」だと陸奥は明言したのである。 ・明治二三(一八九〇)年、山県有朋はその意見書「外交政略論」において「主権線」と「利益線」という対比を用いて、「我邦利益線ノ焦点ハ実ニ朝鮮ニ在リ」といい、更に「朝鮮多事ナルノ時ハ即チ東洋ニ一大変動ヲ生ズルノ機ナルコトヲ忘ル可ラズ。而シテ朝鮮ノ独立ハ、之ヲ維持スルニ何等ノ保障アルカ、此レ豈我ガ利益線に向テ最モ急劇ナル刺衝ヲ感ズル者ニアラズヤ」と主張した。 尊皇攘夷と衛正斥邪 ・帝国主義列強の「西力東漸」に抗するに日本が「尊皇攘夷」を、朝鮮が「衛正斥邪」と称する排外主義をもって応えたという意味では両者は共通している。 ・衛正斥邪とは、「正」を朝鮮の儒学とし「邪」を夷狄として、「正を ・しかし日本の尊皇攘夷は、朝鮮のそれと比べて外国勢力の侵入に敏感で柔軟(日和見主義的)であった。アヘン戦争における清国敗北の報に接するや、幕府は「異国船打払令」をただちに撤回したのであった。 ・二度にわたるペリー来航を経て日本は日米和親条約を結んで開国した。安政五(一八五八)年六月にはアメリカ駐日大使ハリスとの間で日米修好通商条約を締結、日本は五港を開港するという変わり身の早さをみせた。 ・開国に対する批判が尊王攘夷運動であった。しかし、この運動は一時の花火のごときものであった。 ・長州藩が英米蘭仏四ヵ国連合軍の火力に圧倒され、薩摩藩が薩英戦争で脆くも敗北して以来、尊皇攘夷は消え失せ、転じて瞬く間に攘夷論は開国論へと傾き、同時に富国強兵の緊急性を薩長に悟らせ、これが明治維新へとつながっていった。 ・加えて日本の王政復古は、朝鮮のそれのように固陋なアンシャンレジーム(旧体制)への復帰ではなく、逆に開かれた体系をもってその特徴としていた。 ・慶応四(一八六八)年三月、西郷隆盛と勝海舟の合議によって江戸開城。それと同時に新国家建設の大方針が五箇条の御誓文として発布され、これが後の近代的立憲国家創造の礎となった。 一 広ク会議ヲ興シ 万機公論ニ決スベシ 一 上下心ヲ一ニシテ 盛ニ経綸ヲ行フベシ 一 官武一途庶民ニ至ル迄 各其志ヲ遂ゲ 人心ヲシテ倦マザラシメン事ヲ要ス 一 旧来ノ陋習ヲ破リ 天地ノ公道ニ基クベシ 一 智識ヲ世界ニ求メ 大ニ皇基ヲ振起スベシ ・対照的に朝鮮における衛正斥邪の思想は対外的危機にあってますます「純化」の度を深め、専制君主制の一段の強化へとつながった。 ・第二五代の国王哲宗が死去し、一一歳の高宗が国王となり、国王の父である大院君が実権を握ったのが文久三(一八六三)年であった。日本へのペリー来航の一〇年後のことである。 ・「西力東漸」に対して大院君の採用した政策は鎖国政策と専制君主制の徹底であった。 ・大院君は対外的には帝国主義列強の開国要求をことごとく退け、内政においては専制主義の強化に成功したのであり、これをもって衛正斥邪の旧思想が朝鮮の追求すべき道だとの思いを深め、中華帝国の属邦たるの誤りなきを確信し、政治と軍事における近代化への道をみずから閉してしまった。 ・王政復古が、片や日本においては富国強兵を促し、片や朝鮮においてはアンシャンレジームの強化を促すという対照性を生みだした。 ・ここに日韓の近代化の分岐点があり、最終的には後者が前者に併合される(韓国併合)という事態にいたる。 清韓宗属関係の破壊を狙う陸奥 ・陸奥の記述、「今日彼の国における如き惨状を ・したがって朝鮮の開国ならびに近代化は日本の「自衛の道」であるとし、自衛の方策としては李朝の立国の礎たる清韓宗属関係の破壊以外にはなく、もって日清戦争は不可避だという思考に陸奥は傾いていった。 ・清韓宗属関係強化に対する日本の対応は、朝鮮に対する砲艦外交になってあらわれた。起点は「江華島事件」であった。 ・当時の朝鮮は清国の属領であった。明治八(一八七五)年、飲料水を得んと江華島に近づいた日本の軍艦が同島の砲台から砲撃を受け、これに迎撃した日本軍艦が同砲台を破壊するという「江華島事件」が発生した。 ・この事件を契機に結ばれたのが明治九(一八七六)年の日朝修好条規であった。 ・しかし修好条規の締結以降の日朝清の三者関係は複雑をきわめた。 ・まずは、日本の明治維新に衝撃を受け朝鮮の近代化を図らんとする ・失地回復を求める大院君派の反乱に清国が乗じ五〇〇〇人の大兵力を朝鮮に派遣し、大院君を清国に連れ去った。 ・この事件は壬午事変と呼ばれ、これにより朝鮮は清国の属領たるを超えて植民地支配下におかれた。 ・閔氏一族も清国の軍勢の圧倒的な力に驚嘆し、清国に事える事大主義勢力に転じ、事大党を名乗った。清韓宗属関係の復活である。 ・これに反旗を翻したのが、福澤と親交を結んだ金玉均や朴泳幸らによる開化党であった。 ・開化党にとっての千載一遇の時が明治一七(一八八四)年六月に勃発した清仏戦争によりやってきた。清仏戦争は、フランスによるベトナムの植民地化に抗して、ベトナムに対する伝統的宗主権を主張する清国との間で勃発した戦である。これに兵力を割いて清国の朝鮮に対する圧力が減じるや、開化党は混乱を煽動し政権を奪取した。 ・しかし敗北した事大党が直ちに清国に援軍を要請し、袁世凱率いる清国軍が再度挑戦に兵力を派遣して、開化党は壊滅。「三日天下」であった。金玉均や朴泳幸らは日本に逃れ三田の福澤邸にかくまわれた。「甲申事変」である。 ・福澤の悲嘆はいかばかりであったか。福澤に「脱亜論」を執筆せしめたものが甲申事変における開化党の壊滅であった。 ・陸奥の最大の努力は朝鮮を清国の属邦としてではなく、まぎれもない自主独立の国とし、もって清韓宗属関係を断ち切ることにあった。 ・清韓が別個の独立した国家関係として構築されなければ、極東アジアの「外交」そのものが成り立たない。陸奥はそうみなして、朝鮮の清国からの独立に満身の力をもって臨んだのである。 ・転機となったのが、日朝修好条規であった。全権弁理大臣黒田清隆を江華島に派して強引に朝鮮の同意を引き出したものがこの修好条規である。 ・華夷秩序の中でおよそ「外交」というものを経験したことのない朝鮮が外国と取り結んだ最初の条約であったという点で、同修好条規は大きな意味を持つ。 ・全一二款にわたるこの条規においてとりわけ重要なのは第一款であり、朝鮮は条約により初めて「朝鮮国ハ自主ノ邦ニシテ日本国ト平等ノ権ヲ保有セリ」と明文化された。 ・しかしこの条規の存在にもかかわらず清国の態度はなお不透明であった。 ・清国と交渉すれば、朝鮮は内政、外交ともその自主に任せており、清国は朝鮮内で起こる個々のできごとに責めを負う立場にはないと言い、しかしそうはいっても朝鮮は属邦であるから、一個の独立した王国として認めるわけにはいかないという実に曖昧な態度に終始していた。 ・朝鮮を属邦と称しながら、内政、外交に責任をもたないというのであれば宗主国の責任を果たしているとはいえない。 ・そのような非論理的態度を清国が捨てないのであれば、日本としては朝鮮を一独立国家と認識し、一切の責任は朝鮮にありという方針を貫かねばならない。陸奥はそう主張した。 天津条約――「李鴻章対日政策の一大錯誤」 ・そこで新たに日本は清国に「天津条約」の締結を要求するにいたった。 ・朝鮮と並んでもう一つ宗属関係にあったのがベトナムである。このベトナムがフランスによる侵略を受け、これに抗して清軍がベトナムに出兵し清仏戦争が勃発した。 ・これを奇貨として日本は天津条約の締結を清国に迫り、譲歩を勝ち取った。参議伊藤博文が天津に出向き李鴻章と会談してようやく両軍撤兵のための条約が相成った。これが明治十八(一八八五)年に調印された天津条約である。 ・この条約のポイントは第三条にある。 「将来、朝鮮国若シ変乱重大事件ありて、日中両国或ハ一国派兵ヲ要スルトキハ、 ・文中の「行文知照」とは外交文書を公文で称号確認するという意味の外交用語である。 ・この第三条こそ、その後の日清関係を左右する最も重要な項目となった。東学党の乱が起こって両国軍が朝鮮へ出兵する際の論拠となった条項がこれであった。 ・陸奥はこういう。 「清国政府が常に己の属邦なりと称する朝鮮に駐在せる軍隊を、条約上より撤回せざるを得ざるに至りたるのみならず、将来如何なる場合においても同国へ軍隊を派出せんとするときは、先ず日本政府に行文知照せざるべからずとの条欵を具する条約を訂結したるは、彼にありては殆ど一大打撃を加えられたるものにして、従来清国が唱え居たる属邦論の論理はこれがために大いにその力を減殺せしことは一点の疑いを存せず」 ・往時の極東アジアの国際関係について克明な記録を残した天津の『大公報』の記者、王芸生が上梓した『日支外交六十年史』でこういう。 「李鴻章と伊藤とは三月四日条約三ヶ条を締結調印したが、其の内容は全く『相互原則』に拠り、清国は朝鮮に対する宗主権を放棄し、而も第三条には明白に日清両国は朝鮮に対し同等の派兵権を有し、且つ派兵の前に互ひに行文知照すべき事を規定した。甲午の東学党の乱起るに ・個々の交渉や公的文書においては、清国はなお「保護属邦」の語を執拗に用いるものの、日本はいまだかつて朝鮮を清国の属邦とは認めたことはないとし、陸奥はこれを無視した。 ・しかし、それがゆえにこそ日清はいずれ開戦を余儀なくされることを陸奥は深く認識し、戦争の準備に怠りなかった。 陸奥、開戦への決意 ・陸奥の心したのは、仮に日清が開戦せざるをえなくなったとしても、この戦争を二国のみに限定し、第三国に干渉の余地を与えてはならないということにあった。 ・日清戦争に勝利したとしても、いや勝利すればなお欧米列強の干渉は日本をより深く悩ませるはずだと陸奥は考えていた。 ・日清講和条約によって日本が清国から割譲を受けることになった遼東半島、台湾、澎湖諸島のうち最大の「戦利品」である遼東半島が、ロシアに仏独を巻き込んだ三国干渉によって返還を余儀なくされたことは広く知られている。 ・清国に負ければ地獄、勝利してますます強い外圧を想定して、独力で戦わねばならなかったところに日清戦争の苦しさがあった。しかも戦力においては、李鴻章率いる北洋艦隊は「定遠」「鎮遠」を擁して、日本の海軍力より優勢であった。 ・陸奥はこれにどう対処しようとしたのか。 「我はなるたけ被道者たるの位置を執り、 ・日本に対する第三国の干渉を排除するためには、清国をこの戦争の「主動者」とし、日本はやむをえず交戦せざるをえなかった「被動者」であるかのように装うという戦略である。 ・日清戦争は東学党の乱を契機として勃発した。明治二七(一八九四)年二月、全羅道郡主の苛斂誅求に耐えかねて起こった、秘密結社東学教団に率いられた農民反乱である。道都全州が彼らによって制圧された。 ・李氏朝鮮の本貫である全州の制圧は、事大党政府をして再々の清軍出動を要請せしめた。本貫とは一族の発祥の地のことである。清国出兵の動機はいうまでもなく属領保護である。清韓宗属関係を認めてはならじと日本が出兵し、日清戦争が勃発した。 ・軍備拡張も明治一九(一八八六)年より加速度を増していった。同年には建艦公債が発行され、明治二六(一八九三)年には建艦を促すべく明治天皇が宮廷費削減を公にし、これに応じて官僚は給料の一定率の政府返還を決め、さらに議会も政府の建艦計画案を与野党一致で支持した。 ・華夷秩序から朝鮮を引き剥がして朝鮮の自立を図らなければ、極東における日本の安寧はありえず、それゆえ第三国の干渉を排して朝鮮自立の方策を立案し、さらには日清共同内政改革提案を練り上げ、これが清国に拒否されるや、全力を清国との戦いに注ぎ込もうという外交官としての陸奥の深い熟慮と迅速な判断、加えてその豪気には眼を見張らされるものがある。 帝国主義にめざめる清国の「東征論」 ・陸奥は清韓宗属関係を破壊し、もって朝鮮を自主独立の国となし、独立した朝鮮の内政安寧を図らざれば日本は危ういと考え、そうして日清戦争をわが国「自衛の道」にとって不可避のものとして捉えた。 ・同じく山県有朋も「朝鮮多事ナルノ時ハ即チ東洋ニ一大変動ヲ生ズルノ機ナルコト」とし、朝鮮は日本にとっての「利益線」だとの認識を明らかにした。 ・朝鮮が日本の自衛の道であり利益線だというのは、いかにも「帝国主義的」な発想である。さもありなんである。陸奥の外交指導はまさしく帝国主義そのものである。 ・列強がアフリカはもとより、中近東のすべてを植民地支配下に置き、南アジア、東南アジアを経て、アヘン戦争以降は中国の沿海地域を次々と租界地とするにいたった。最後に残されたのが日本であり、日本の後方に隠れるように存在していた「隠者の王国」が朝鮮であった。 ・「西力東漸」の圧力に抗し富国強兵をもって自立した日本が、自国の防衛を図るには朝鮮の自立を促し、そのためには朝鮮を臣下とする清国との対決は不可避であった。 ・実は、こうした国際環境に囲まれて、清国もまたみずからを帝国主義化させなければ自国の存立が不可能であることを悟るようになっていた。 ・列強に沿海部の中枢都市の開放を強要され、租界地とされ、半植民地的支配を受ける一方で、清国は朝鮮への権力政治的な介入に乗りだし、朝鮮をうかがう日本と干戈を交えんとする志向性を次第に強めていった。 ・日清戦争は朝鮮半島を舞台にした日清の覇権争奪の戦いであった。 ・朝鮮の独立は日本の自衛の道であり、その意味で朝鮮半島が日本の利益線であるという帝国主義的発想は、この日本に抗せざれば日本がほどなくして「清国ノ巨患ト為」り、朝鮮半島の将来が危ういと発想する点において清国もまた帝国主義的発想の影響を強く受けていたのである。 ・自国が朝鮮半島を先に獲らなければ、他国がこれを獲ってしまう、されば半島において両軍相まみえるべきだと考えて始まった戦争が日清戦争に他ならない。 ・善悪や道義の問題ではない。もしこの帝国主義戦争において日本が敗北したとすれば、おそらく清露いずれかによる日本の植民地化を帰結したであろうことは高い蓋然性をもってこれを想像できる。 ・日本の海軍力は講和条約の締結にいたるまで清国のそれを上まわることはついになかったが、それにもかかわらず日本が勝利したのはその優れた機略と豪気にあった。陸奥宗光を象徴するものがこの機略と豪気である。 ・わが愛する朝鮮半島の民の歴史をそう表現するのはいかにも切ないが、そうしなければ「西力東漸」の帝国主義的な国際社会の中で日本が生き延びていく術がなかったのである。 ・生存のためのわずかな可能性に賭けた陸奥の判断は、日本の「生存空間」を確保するための不可避のものであったといわざるをえない。 ・外交とは友好や善隣ではない。国益の確保そのものである。 ・陸奥の思想と行動はこのこと、つまりは外交の「原型」を示して余すところがない。 第3章 朝鮮近代化の挑戦――金玉均と福澤諭吉 福澤は自分の過去を朝鮮人留学生の中に見出し、頼ってくる彼らに救いの手を差しのべるのは己の責だと感じた 「独立自尊」 ・ <途中> |