
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2024年10月16日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
18 |
24.10 |
20世紀特派員 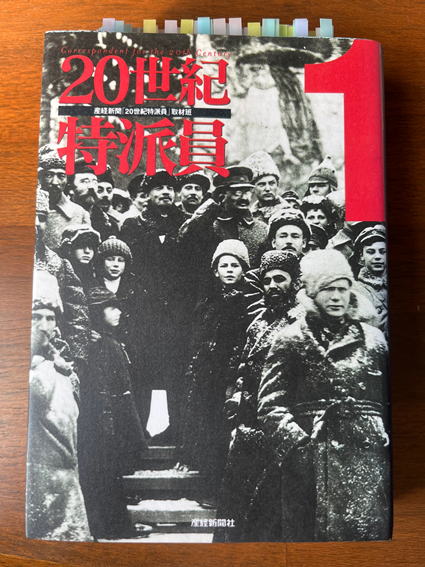 |
名雪雅夫 高山正之 黒田勝弘 古森義久 |
産経新聞社 |
◎ |
第一章 ロシア革命とソ連 1 帝国の崩壊 クーデターに軍は決起せず 二度目の抗命 ・ソ連の多くの共和国指導部が日和見の態度を取る中で、ソ連大統領ゴルバチョフを排除した「連邦政権」対「ロシア政権」の壮絶な権力闘争の色合いがいっそう鮮明になる。 「幽霊国家」が連邦倒す ・大統領権力の奪取を図ったクーデター指導部が、真剣に「祖国ソ連」の秩序ある改革を目ざしたにせよ、ソ連という体制の中で築いてきた自己の地位を守ろうとしただけだったにせよ、その背景には連邦解体への焦燥感があった。 ・だが、一九九一年八月二十一日、彼らが拠点とした「連邦政権」はクーデターに抗戦した「ロシア政権」の前に敗れ去る。 ・クーデター派が降伏し、黒海沿岸の保養地フォロスでの三日間におよぶ軟禁を解かれたソ連大統領ゴルバチョフは二十二日未明、モスクワに帰還し、「私はフォロスから別の国に戻ってきた」語った。 ・彼が帰ってきたところは、すでに「ゴルバチョフのソ連」ではなく、「エリツィンのロシア」であった。まさに「別の国」になっていたのである。 酷薄な場面 ・モスクワに戻った翌二十三日、ゴルバチョフはロシア最高会議に出席した。 ・エリツィンはその場で、ソ連共産党のロシア共和国内での活動禁止を命じる大統領令に署名した。 ・ゴルバチョフは「性急すぎる」と抗議の声を上げたが、むなしかった。党中央委員会の建物群は前日、ロシア政府とモスクワ市によって接収されており、党の機能は事実上、停止していた。 ・クーデター指導部はすべてソ連共産党幹部であり、党中央委の大半がクーデター支持に回っていたことは隠しようもない。 ・ゴルバチョフは二十五日、最後まで兼任に固執していた党書記長をついに辞任し、中央委の解散勧告を出す。事実上の解党宣言である。 ・レーニンが生み、スターリンが三十年間にわたって君臨し、国家を支配してきた党は皮肉にも、その改革と再生を目指したゴルバチョフのもとで最期を迎えることになった。 ・ゴルバチョフには「連邦政権」が残っていたが、それも巨大な国家として立ち現れつつあった「ロシア」の挑戦にさらされていた。 被害者意識 ・エリツィンはなぜ、ロシアの独立を考えたのか。 ・ソ連邦がいずれ立ち行かなくなることを鋭い政治的嗅覚で察知したからに違いなかった。 ・それが確信に変わるのは八〇年代後半からのバルト三国の独立の動きがきっかけだった。 スターリンの不安は的中した 自然の流れ ・ゴルバチョフ政権内のソ連「帝国」維持派が起こした八月クーデターは、ソ連領土の四分の三を占めるロシアの資源と資産を「連邦政権」と「ロシア」が奪い合う熾烈な経済闘争でもあった。民主派と保守派の衝突という思想的次元の争いではなく、ましてマルクス・レーニン主義の救済などとは無縁のものだった。 ・ソ連大統領のゴルバチョフには、いまや座るべき椅子がなかった。ソ連は消滅した。 改革の見通し ・ソ連共産党の書記長になったゴルバチョフは一九八六年、硬直化した社会主義体制を再生しようとしてペレストロイカ〈再編〉改革に踏み出した。目的は経済不振から脱却して国力を強化することにあった。 ・基本的な柱となったのはグラスノースチ(公開性)、経済的自主性の増大、ソビエト(議会)の強化、立候補制限の緩和などであった。 ・これらは、レーニンの時代からソ連を支え、スターリンが強化し、ブレジネフが維持してきた「一党独裁」体制の基盤を揺るがすものばかりである。 ・ソ連は厳しい統制と中央政権によって保たれてきた。そのソ連政治体制の基本を掘り崩しながら、一方でソ連体制を維持しようしたペレストロイカ路線に、ゴルバチョフはどんな見通しを持っていたのか。あるいは、展望も見えないまま追い詰められるように始めただけだったのか。 3 スターリン体制 冷酷で壮大な実験が始まった ・ <途中> |