
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2025年01月26日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
23 |
24.12 |
夜明け前(第二部)上 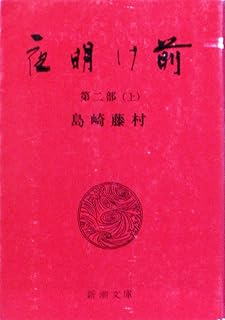 |
島崎 藤村 |
新潮文庫 |
◎ |
第一章 ・ケンペル(十七世紀の末の昔にこの国に渡って来て、医学と自然科学との知識をもっていて、当時に於ける日本の自然と社会とを観察した和蘭人)の眼に映った日本人は義烈で勇猛な性質がある。多くの人に知られないような神仏の如きをも尚かつ軽んずることをしない。しかも一度それを信奉した上は、頑としてその誓いを変えないほどの高慢さだ。もしそれこの高慢と闘争を好むの性癖を除いたら、則ち温和怜悧で、好奇心に富んでいることもその比を見ない。 ・ハリスは米国提督のペリイとも違い、力に訴えてもこの国を開かせようとした人ではなかった。 ・相応に日本を知り、日本の国情というものをも認め、異国人ながらに信頼すべき人物と思われるのもハリスであった。 ・国を開くか開かないかの早い頃に来てこのハリスの教えて置いたことは、先入主となって日本人の胸の底に潜むようになったのである。あだかも、心の柔く感じ易い年頃に受け入れた感化の人の一生に深い影響を及ぼすように。 ・日本に高い運命の潜んでいることを言わない欧羅巴人はない。もし彼等日本人にして応用化学の知識に欠くることなく、機械工業に進歩することもあらば、彼等は欧羅巴諸国民と優に競争し得るものである、日本は文学上にも哲学上にも未知の国であるが、ここにある家屋は清潔に、衣服も実用に耐え、武器の精鋭は驚くばかりである、独創の美に富んだ美術工芸の類に就いては人によって見方も分れているが、とにもかくにも過ぐる三百年の間、殆ど外国と交通することもなしに、これほど独自の文化を築き上げた民族は他にその比をみない。そう言わないものもいない。 ・和蘭代理公使ブロックに言わせると、当時のこの国の急務は内乱をおさめるにある。日本国がいつまでも日本人の手にありたいと願うなら、早くこんな内乱をおさめるがいい。そして国内衰弊の風を諸外国に示さないがいい。これまで強大な諸大名が外国から 第四章 ・すでに大政を奉還し、将軍職を辞し、広大な領地までそこへ投げ出してかかった徳川慶喜が江戸城に未練のあろう筈もない。 ・いかに徳川家を疑い憎む反対者でも、当時局外中立の位置にある外国公使等まで認めないもののないこの江戸の主人の恭順に対して、それを攻めるという手はなかった。 ・慶喜は捨て得るかぎりのものを捨てることによって、江戸の市民を救った。 ・もとより、その直接交渉の任に当り、あるいは ・しかし、幕府内でも最も強硬な主戦派の頭目として聞えた ・慶喜の心事を知らない兵士等の多くは、その恭順をもって専ら京都に降るの意であるとなし、怒気 ・もしその殺気に満ちた空気の中で、幾多の誤解と反対と悲憤との声を押し切ってまでも断乎として公武一和の素志を示すことが慶喜になかったとしたら、おそらく、慶喜がもっと内外の事情に暗い貴公子で、開港条約の履行を外国公使等から迫られた経験もなく、多額の金を ・ ・不幸にも、徳川の家の子郎党の中にすら、この主人をよろこばないものがある。 ・その不平は、多年慶喜を排斥しようとする旧い幕臣の中からも起り、かくの如き未曽有の大変革は ・将軍家の居城を中心に、大きな市街の六分通りを武家で占領していたような江戸は、最早終りを告げつつあった。この際、徳川の親藩なぞで至急に江戸を引き払わないものは、違勅の罪に問われるであろう。兵威をも示されるであろう。その御沙汰があるほど、総督府参謀の威厳は犯しがたくもあったという。 ・噂によると、上屋敷、中屋敷、下屋敷から、小屋敷その他まで、江戸の市中に散在する紀州屋敷だけでも大小およそ六百戸の余もある。奥向きの女中を加えると、上下の男女四千余人を数える。この大人数が、三百年住み慣れた墳墓の地を捨て、百五十里もある南の国へ引き揚げよと命ぜられても、僅か四五日の間でそんな大移住が行い得るものか、どうかと。 ・徳川氏と運命を共にする屋敷方の離散して行く光景を語らないものはない。 第六章 ・過ぐる長州征伐の一大失敗が徳川方を覚醒させ、封建諸制度の革新を促した。 ・旧い伝馬制度の改革が企てられたのもあの時からで、諸街道の人民を苦しめた諸公役等の無賃伝馬も許されなくなり、諸大名の道中に使用する人馬の数も減ぜられ、問屋場 ・今度の東北戦争の結果は一層この勢を助けもし拡げもして、軍制武器兵服の改革は言うまでもなく、身分の打破、世襲の打破、主従関係の打破、その他根深く澱み果てた一切の封建的なものの打破から、最早廃藩ということを考えるのもあるほどの驚くべき新陳代謝を促すようになった。 ・何事も土台から、旧時代からの藩の存在や寺院の権利が問題とされる前に現実社会の動脈ともいうべき交通組織は先ず変りかけて行きつつあった。 ・江戸の方にあった道中奉行所の代りに京都駅逓司の設置、定助郷その他種々な助郷名目の廃止なぞは皆この消息を語っていた。 ・従来、諸公役の通行と普通旅人の通行には荷物の貫目にまで非常な差別のあったものであるが、それらの弊習も改められ、勅使以下の通行に特別の扱いをすることも一切廃止され、公領私領の差別なくすべて助郷に編成されることになった。 ・諸藩の旅行者たりとも皆相対賃銭を払って人馬を使用すべきこと、助郷村民の苦痛とする刎銭なるものも廃されて、賃銭はすべて一様に割り渡すべきこと、それには宿駅常備の御伝馬とそれを補助する助郷人馬との間に何等の差別を設けないこと――これらの駅逓司の方針は、いずれも沿道付近に住む百姓と宿場の町人乃至伝馬役との課役を平等にするためでないものはなかった。 ・多年の問題なる助郷農民の解放は、すくなくもその時に第一歩を踏み出したのである。 ・かくも諸国の人民が新帝を愛し奉り、競ってその御一行を迎えるというは理由のないことでもない。 ・従来、主上と申し奉るは深い玉簾の内に籠らせられ、人間に替らせ給うように僅かに限りある公卿達の外には拝し奉ることも出来ないありさまであった。それでは民の御父たる天賦の御職掌にも ・これまでのように主上の ・今や更始一新、王政復古の日に当り、眼前の急務は何より先ずこの弊習を打ち破るにある。 ・よろしく本朝の聖時に ・そればかりではない。もっと大きな事が、この行幸の後に待っていた。皇居を京都から東京に遷し、そこに新しい都を打ち建てよとの声が、それだ。 ・もし朝廷に於いて一時の利得を計り、永久治安の策をなさない時には、則ち北条の後に足利を生じ、前姦去って後姦来るの ・今や、内には崩れ行く中世的の封建制度があり、外には東漸する ・この際、深くこの国を注目し、世界の大勢を洞察し、国内のものが同心合体して、太陽はこれからかがやこうとの新しい希望を万民に抱かせるほどの御実行を挙げさせられるようにしたい。それには、非常な決心を要する。 ・眼前にある些少の故障を懸念して、この遷都の機会をうしなったら、この国の大事も終に去るであろう――実際、こんな風に言わるるほどの高い潮がやって来ていた。 第七章 ・新時代を迎えるに急な新政府がこれまでの旧い暦をも廃し、万国共通の太陽暦に改めた頃は、やがて明治六年の四月を迎えた。 ・今は四民が平等と見做され、権威の高いものに対して土下座する旧習も破られ、平民たりとも乗馬、苗字までを指し許される世の中になって来た。 ・これまで、実に非人として扱われていたものまで、大手を振って歩かれる時節が到来した。新たに平民と呼ばれて雀躍りするものもある。 ・武家の時が過ぎて、一切の封建的なものが総崩れに崩れて行くような時がそれに替って来た。 ・いよいよ廃藩が断行され、旧諸藩はいずれも士族の救済に心を砕き、これまで蝦夷地と称えられて来た北海道への開拓方諸有志の大移住が開始されたのも、これまた過ぐる三年の間のことである。 ・武家の地盤は全く覆され、前年の十二月には全国募兵の法さえ設けられて、所謂壮兵のみが兵馬の事にたずさわるのを誇れなくなった。 ―― 完 ―― |