
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2025年04月27日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
10 |
25.04 |
毛沢東の朝鮮戦争 中国が鴨緑江を渡るまで 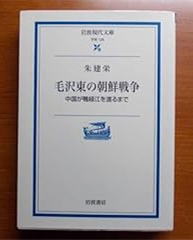 |
朱建栄 |
岩波現代文庫 |
◎ |
序 論 朝鮮戦争研究の流れ ・この戦争は朝鮮半島の分断を固定化し、朝鮮民族に限りない苦痛を与えた反面、米国を、対日早期講和と日米安保体制の樹立に踏み切らせ、日本に再軍備と経済復興をもたらしたのである。 本書の研究対象――中国の政策決定 ・数十万から百万人以上の中国軍の参戦、という政策決定が毛沢東の強い意志により、紆余曲折を経て中国最高指導部内で最終的に行われた。 ・当時、新中国は建国後わずか一年足らずで、国民党残留軍の討伐、破綻した経済の再建、新政権の安定化など、解決を急ぐべき国内問題が山積していた。 ・また、新たな大規模戦争を支える財政能力もなかった。武器装備の後進性もあり、長期にわたった国内戦争後の厭戦気分が普遍的になっていた。なによりも、交戦相手米国は、世界最強の経済・軍事大国であった。 第一章 中国と朝鮮戦争の開戦 第一節 一九四九年からの中国の関与 北京指導者が長年沈黙を保った理由 ・一九五〇年六月二十五日に始まった戦争は当初、朝鮮側にとっての「祖国解放戦争」であって、金日成が発動した。 「革命は自らの努力に立脚すべき」という毛沢東の認識の形成 ・中国革命は、ある意味においてレーニンが指導したソビエト革命への軌道修正、およびスターリンから来た教条主義的な内政干渉に対する抵抗で発展したものである。 ・レーニン、スターリンは、無産階級の産業労働者(「プロレタリア」)が都市部での武装闘争を起こして、政権奪取後も彼らを主な支持基盤にする、というのを、社会主義革命を成功させる金科玉条とした。 ・これが中国に持ち込まれ、二〇年代から三〇年代にかけて中国共産党の指導する革命の指導原則とされたが、それに従って起こした「革命」はことごとく失敗した。 ・後に、毛沢東を中心とする中国共産党の指導者が、革命を成功させ、ついに政権を奪取したが、彼らが実践したのはスターリン理論ではなく、むしろちょうどそのアンチテーゼであった。 ・すなわち、それは農民を主体とし、「土地改革」を主要なスローガンとし、農村で革命根拠地を作り、農村から都市部を包囲する戦略であった。 ・このような中国革命の路線は三〇年代末に延安でほぼ確立されたが、第二次世界大戦中の一九四三年、ソ連がコミンテルン(世界各国の共産党を同一組織とし、モスクワの指揮下に置くための機関)を解散した後、ようやく日の目を見るようになり、一九四五年の第七回党大会で「毛沢東思想」として確立されるようになった。 ・「抗日戦争」が終わった後、延安にあった中国共産党指導部は直ちに、圧倒的な軍事力を有する蒋介石政権との対決に備えを急いだ。 ・毛は、自分自身の情勢判断と長期戦略をずっともっていた。その独自戦略の柱の一つは東北(旧満州)進出の方針だった。 朝鮮の革命闘争に対する中国共産党基本的立場 ・四八年九月九日、朝鮮民主主義人民共和国が建国し、人民軍も正式に発足した。 中国はなぜ朝鮮人兵士の帰還に同意したか ・間もなく中国全土の制覇を実現しようとする毛沢東ら指導者は、マルクス・レーニン主義というイデオロギーに対する信仰や、革命家的な理想主義もあって、同じ共産主義革命家の挑戦に対して「国際主義的な義務」を尽くすべきだ、という考え方をもっていたため、当面は朝鮮半島での全面戦争と早急な統一に賛同していなかったが、革命勢力の強化そして最終的に朝鮮の共産主義者によって半島を統一することを支持しようとしたことも容易に考えられる。ただ、これと直接の戦争企画参加とは別である。 毛沢東・スターリン会談では「南進」は協議されなかった ・筆者は、中ソ首脳会談では金日成の南進計画について具体的な討論が行われず、毛沢東は五〇年五月の金日成訪中まで計画の詳細を知らされなかった、との説に賛成である。 ・毛沢東はその後の対外的実際の行動ではかなり慎重だった。 ・そして朝鮮半島に限っていえば、それは中国共産党の対外的支持・支援を行う対象外だった。 ・朝鮮半島がソ連の管轄地域だということを、中国側は良く「納得」していた。 ・その北半分は赤軍が自ら出兵して占領した戦略的要衝であり、米軍と対峙し、米軍事戦略の橋頭堡日本を牽制する最前線であり、ソ連が極東で太平洋に進出するための海洋戦略にとって不可欠な側翼であるためと理解された。 第二節 開戦の再定義 ― 「六・二五」が唯一の分岐点だったのか 再び柴成文証言 ・中国軍の研究機関が新しく出版した朝鮮戦争史 「一九五〇年六月二十五日早朝、三十八度線で長く続いた小規模な武装衝突と摩擦が、ついに質的な変化を起こし、朝鮮における大規模な内鮮が全国的に爆発した」 ・初代朝鮮駐在臨時代理大使柴成文の証言 「朝鮮戦争を見るとき、国内戦争の段階と、国際戦争の段階とを区別して考えなければならない」 「戦争勃発後、国連軍側の十六ヵ国が参戦し、中国が介入し、ソ連もまったく手を染めていなかったわけではない。この国際戦争の責任は誰にあったのか。それはトルーマンが引き起こしたものだ。中国は、この考えを百年後も変えることはないだろう」 「他人の家で喧嘩が起こったとき、なだめにいくのではなく、その喧嘩に加わる。それも、自分が手を出すだけでなく、他の大勢の仲間を引き連れて、喧嘩に加わる。内戦が勃発するや、米国は直ちに出兵を決定した。その決定後、初めて国連に提起され、討議された。」 「まず朝鮮の南北双方に談判を勧告するよう提案したが、米国に拒否された。だから、国際戦争の責任は完全に米国にあると言える」 「一歩譲って、仮に朝鮮が側が先に発砲してとしても、それは朝鮮半島における内戦においてのことである。その後の国際戦争に関しては何ら責任を持つものではあるまい」 ・朝鮮内部は混乱していた。革命がいつ起こっても不思議でない情勢があるように思われた。同じ民族として、その革命を促進するために、「祖国解放戦争」を発動するのは当然非難されるべきではない。 ・朝鮮戦争当時、世界は東西冷戦の最中であり、米ソ間、特に米国側は、相手に対し極度の猜疑心を持っていた。そのような状況下において、片方が「国内戦争」として、「祖国解放戦争」を起こした場合、相手側の目にどう映るかを考えるべきであろう。 ・特に当時の北側の軍隊はソ連製武器で装備され、ソ連軍事顧問がその軍事作戦の指導にあたっており、それが米国に、「共産主義が侵略、拡張を開始した」ように判断させる可能性は実際存在していた。 ・結局、朝鮮側は、国内戦争としての一面を重視しすぎ、それに対し、米国は当時の国際環境の影響を過大評価したところに、朝鮮内戦が国際戦争へ拡大した悲劇的一要因があるように思われる。 統一戦争は四九年から始まった? ・「六・二五」のみを戦争の起点と見なすこと自体、それは米国が主導した冷戦時代に於ける朝鮮戦争に関する一面的な分析枠組みのせいではなかったのだろうか。 ・仮に国際紛争という角度から見れば、五〇年六月二十七日にトルーマン米大統領が介入の声明を発表し、七月に入って国連軍が半島に上陸し、そして十月に中国軍が参戦したことで、初めて本格的に国際戦争に突入したことになる。 ・だが、南北双方に分かれた同じ朝鮮民族同士の、再統一を目指した国内戦争という角度から見ると、その起源は「六・二五」よりはるか前に、再統一を目指した国内戦争は四九年にすでに始まっていたといっても大げさではない。 ・四八年八月から九月にかけて、それぞれソウルとピョンヤンを首都とする大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国が誕生した。 ・この二つの国は奇妙にも同じ統一の方針、目標を掲げ、同じ統一の手段(平和統一を目指すが、武力も辞さず)をとっていた。 ・それまで半島の未来に関しては完全に米ソなどの外来勢力に牛耳られていたが、それぞれの建国によって、自主的に統一を推進する可能性が現れた。 ・四八年末、一部の軍事顧問を残したものの、ソ連軍は北朝鮮から引き上げた。米軍が南朝鮮から撤退することも早晩のこととなった。 ・そこで三十八度線を挟んで南北朝鮮の軍隊による摩擦が急増し、自分の側が主導する統一路線の実現を目指して政治的・外交的駆け引きおよび探りを入れる攻撃をくり返した。 第七章 大論争 第一節 出兵の緊急決定 矛盾する二つの電報(十月二日) ・一九五〇年十月二日付で毛沢東がスターリン宛に送った電報(A電報) 「義勇軍の名義で一部軍隊を朝鮮国内に派遣し、朝鮮の同志を援助し、米国とその手先である李承晩の軍隊と戦うことを決定した」 「朝鮮全域がアメリカ人に占領されれば、朝鮮の革命勢力が徹底的な敗北をこうむるだけでなく、米国侵略者が一段と気炎を伸ばし、東側全体にとって不利である」 第二の部分は、中国が出兵する意図および覚悟を述べ、参戦すれば朝鮮領内で米軍などを殲滅するか駆逐するのが目的だとし、朝鮮半島で米国の中国本土侵略の「野心」に打撃を与えようとする毛の戦略思想は十分に反映されている。それによって米中戦争になること、米海空軍が中国の沿海都市を爆撃することへの心構えもできている、と毛は言う。 第三部分は参戦による国際情勢へのインパクトを分析し、朝鮮戦場で米軍を殲滅できれば世界の革命勢力側にとって有利な情勢が生まれ、米国が戦争を中国本土に拡大する可能性も低下するとし、「一番不利なのは、国連軍との戦争が膠着状態になり、米国が戦局打開のために中国大陸に戦争を拡大し、中国沿海都市に攻撃を仕掛ける」シナリオだと指摘する。 「早期参戦を見送る」 ・「十月二日」の日付で毛沢東がスターリン宛に送ったB電報について、ローシチン大使はモスクワに伝えた。 「毛沢東の返事は、朝鮮問題における中国指導部の当初の立場が変化したことを示している」 「若干の対戦車兵器や火砲の補充は必要だが、中国政府は朝鮮に戦闘力ある五、六個師団ないしそれ以上の部隊を送りこむことはできるはずだ」 「中国側が豹変した原因は明らかではないが、当面の国際情勢と朝鮮情勢の悪化、災難に巻き込まれないよう中国人に抑制的対応を呼びかけたネールを通じての英米集団の陰謀、などが考えられる」 と分析している。 ・ソ連は内心、毛沢東の共産主義を信用していなかった。 ・中国の軍事力を使って朝鮮半島におけるソ連の戦略的失敗をカバーしようと考えるスターリンはそこで、毛沢東の「動揺」を封じ込める必要があると感じて、毛沢東に返電を送った。 ・スターリンはソ連自身の利益のために、あらゆる手段も辞さずに中国を戦場に誘い込もうとする。 ・電報の中で、 「敵が三十八度線を越えた場合、朝鮮の同志たちを支援するために軍隊を送る用意があるという中国側指導者の度重なる表明」に触れ、中国の置かれた立場を一切考慮せず、「約束を忘れるな」と暗に迫る。 ・次に、朝鮮が占領されれば、「米国、あるいは将来の軍国主義日本が中国を侵略する橋頭堡になる危険性がある」として、中国を脅かす。 ・そして現時点で中国が出兵しても、「米国は大規模戦争への準備ができていない」「まだ軍国主義勢力が復活していない日本は米国に軍事援助を与えることができない」、逆に「米国は朝鮮問題でソ連の同盟国として存在する中国にやむなく譲歩するだろう」「同じ理由から、米国は台湾だけでなく、日本反動派との単独講和、日本帝国主義の復活、日本を米国の極東における前線基地とすることも断念せざるをえないだろう」とメリットを並べるが、これは彼自身も信じていない嘘であろう。 ・本当に「いいことずくめ」なら、ソ連はなぜ自分が出兵しなかったのだろうか。 ・仮に米国が大規模な戦争に踏み切っても、「怖れるべきだろうか。私は怖れるべきではないと考える。われわれは米国、イギリスよりも強いのだ」と虚勢を張りながら、毛沢東に「臆病者」になるなと挑発しようとした。 第二節 激論をへて参戦が決まる 金日成親書を携えた朴一禹の訪中(十月三日) ・十月二日会議の結論は当面、参戦を見合わせることだった。早期参戦に反対した中心人物の一人が周恩来首相だった。彼は、国連軍が北上すれば中国国内での参戦主張が再び台頭することをよく知っていた。 ・十月一日と二日、金日成は立て続けに、倪志亮・中国大使と会って、どうしようもない極端に厳しい情勢を紹介し、「朝鮮労働党中央と政府はもはや中国に支援を求める以外に道が残っていない」と懇願した。 ・三日、労働党中央常務委員、内務相の朴一禹が、金日成首相、朴権永外相が共同署名した支援要請文書を携えて北京に到着し、早速毛沢東に面会し、親書を渡し、出兵を直に申し入れた。 ・金日成親書は、「敬愛する毛沢東同志」の宛名で始まり、次のように中国への支援懇願を申し入れた。 「敵がわれわれの重大な危急状況につけ込み、われわれに時間的余裕を与えずに、引続き三十八度線以北の地域を侵攻する目下の情勢の下で、われわれ自身の力だけではこの危急状態を克服することはできない。したがって、われわれは貴下が特別な援助を下さるよう申し入れなければならない。すなわち、敵が三十八度線以北地域に攻撃する状況下、中国人民解放軍が直接に出動してわが軍を支援して先頭に当う請願するばかりである」 韓国軍のみの北上でも中国参戦 ・十月四日と五日の時点で、国連軍は北上しておらず、韓国軍の一部だけが三十八度線を越えたことである。韓国軍だけの北上に対しても、北側は対抗する兵力がないだろう、というのが中国指導部の共通した読みであった。 ・韓国軍だけの北上でも、毛は出兵を主張し、実際そのように対策を考えていた。 ・そもそも韓国軍が息を吹き返すことができたのは米国の力によるものであって、韓国軍だけの北上といっても、その背後に米国を始めとする国連軍が構えていて初めてできるものである。 ・米国の対中侵略の意図に対する深い疑念を抱いている毛は、朝鮮全域が制圧された後に、韓国軍の「要請」を受ける形で国連軍が鴨緑江南岸まで前進しない保証はないと見て、そのときになっては中国は出兵の契機を失ってしまう、と主張したと言われる。 ・しかし、北京の研究者は、韓国軍だけの北上に対して毛沢東が考えた対応は、国連軍北上の場合の対応とは違うと、強調した。 一、韓国軍だけの場合、その戦闘力はかなり限定されたものと見ているので、中国は数十万のような大規模な参戦をする必要はなく、数万程度の出兵で事足りる、と構想し、 二、その場合、中国は公式の場では参戦の事実を絶対認めずに、人民軍の軍服を着用し、人民軍として参戦する、という。 ・中国は八月ごろから人民軍の軍服を大量に調達するなど、その準備を着々と推進していた。 ・十月十九日に鴨緑江を渡河した義勇軍主力部隊は、朝鮮人民軍の軍服を着用していた。 ・周恩来がインドのパニッカー大使に話した内容は、「韓国軍だけが北上するなら、中国は公式の参戦はしない」と解釈すべきであろう。 ・国連軍の北上と韓国軍だけの北上、両者に対する対応の方法に違いがあるものの、基本戦略の見地から、西側帝国主義敵対勢力が鴨緑江の向かい側まで制圧することは容認するわけにはいかない、という認識では、毛沢東は一貫していた。 第八章 出兵と中止の狭間で 第一節 出動命令に至るまで 軍事委拡大会議(十月六日) ・彭徳懐は、義勇軍出動前後のマスコミの報道に関し次のような要望を出した。 ・報道機関の陽動作戦で、敵軍の注意力を分散させ、その判断を攪乱し、わが軍各部隊が迅速に秘密裡に鴨緑江を渡河するのを援護射撃すること、有利な戦機をつかみ、緒戦の勝利を収めるため、戦闘を開始するまで、参戦問題を一切報道しないこと、戦闘に突入後も、報道を慎重に取り扱うことなどである。 ―― 完 ―― |