
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2025年8月11日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
12 |
25.05 |
イギリスと日本 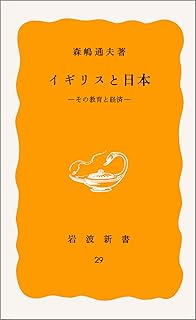 |
森嶋通夫 |
岩波新書 |
◎ |
Ⅰ 英国病私見 ―大帝国からの転進― 四 ・資本主義国では、分配の仕方に変更を加えることを好みませんから、国民の物質的幸福を増すには、純生産物の総額を増加せねばなりません。 ・これに反し福祉国家では、国民の幸福を大きくするには、純生産物をどう分配すべきかを考えますから、純生産物が増加しなくても、分配の仕方を改良して幸福を増進させることができます。 ・福祉国家にとって経済成長率が低いことは、苦しいことでありますが、致命的でありません。福祉国家の成績は、それ自身の尺度で評価すべきであり、古典的資本主義を見る目で採点してはなりません。 十二 ・イギリス人は他人に対して干渉がましいことを滅多にいたしません。 ・アメリカ人の場合は非常にちがっており、彼らは他人の効用関数に敏感であります。 ・効用理論の修正版であるデモンストレーション理論はアメリカから起ったのでありまして、この理論は、各人は他人――身近な人々やライバルや有名人――の行動に影響されつつ行動すると仮定しております。 ・日本はアメリカ以上にアメリカ的で、お互いに注意、干渉、世話、排斥のしあいであります。 Ⅱ イギリスの中等教育 ―階級との闘い― 一 ・戦前の日本の中・高等教育体系は、小学校高等科・青年学校・中学校・実業中学校・実業専門学校・高等学校・大学等種々様々な学校が並立した複線体系をなしていました。 ・ですから、初級程度の教育でもよい人は小学校の高等科から青年学校へ行けばよく、中程度の教育のほしい人は実業中学校へ、高等教育を受けたい人は中学校・実業専門学校のコースを歩むか、中学校・高等学校・大学のコースを歩むことが出来ました。 ・このように複線体制では、長短いろいろのコースを進むことができ、どのコースを出ても、程度の差はありますが、いずれも一人前の人として社会に出ることができたのです。 ・けれども戦後の日本の教育体系は、単線式すなわち、中学・高校・大学という一本のコースしかない簡単なものになってしまいました。 ・もちろん実業高校や工業専門学校など基本コースからはみ出た学校もありますが、これはあくまで補助的、付随的なものに他なりません。 ・「教育の機会均等」「すべての人に同じ教育を」ということを旗印にしますと、こういうことにならざるをえません。 ・複線式と単線式はどんな長所、短所をもっているでしょうか。 ・まず複線式の長所を申しますと、教育期間の長さを選べるという長所をもっています。しかし、このことは同時にその体系の短所となっております。 ・もし個人が何らの強制をともなうこともなく、完全に自発的に、自由に教育コースを選んでいる場合には、問題はありませんが、実際問題としてそういうことは不可能であり、貧富の差、家庭環境その他による目にみえない強制があって、そういう強制下に教育コースが選ばれております。 ・単線式には教育期間の選択の自由はありません。もちろん中学きりで学校を止めたり、高校きりでやめたりすることができますが、それではなま煮えの芋を皿に盛るようなものです。 ・単線体系で短い完成教育が不可能なら、無理矢理にも全員が、長い一本道を歩まねばなりません。その結果、気狂いじみた受験競争が生じ、勉強嫌いの子どもは、長途の旅を強要されるばかりか、その期間中、お前は出来の悪い人間だという判定を、何度もくり返し聞かされます。このことは深刻です。 ・人生の三分の一を学校生活にとじこめて、主として知的な側面だけで評価し、格付けしているのは、知的にすぐれていないものにとっては、耐え難い苦痛であります。もともとちがっているものを無理矢理に無差別に取り扱って、新しい差別をつくり出しているのです。 二 ・差別の撤廃を標榜する単線教育の背後には、新しい差別意識がかくされております。 ・差別意識一掃の戦いに私たちが勝利をおさめ、大学出であるというだけの理由で事務員が工員よりも高い給料をとるという事態が消滅すれば、子どもたちは無意味な教育競争に参加することを拒否するようになるでしょう。 ・勉強に不向きな子どもたちを、彼らの灰色の前三分の一の人生から解放してやるのが、私たちが子どもたちにできる最大の贈物ではないでしようか。 四 ・「教育の機会均等」は決して全員に同じ教育をほどこすことではありません。人間に同じ教育をほどこすことは、人間性の冒瀆であります。 ・各人はそれぞれ、異なった持味や資質をもっており、教育を受けることによって、自分がどんな資質をもっているかがわかり、それらがさらに育てられ、伸されるのです。 ・それのみではなく、各人には能力の差があります。資質のちがうものに一様な教育をすれば、人間を型にはめることになるだけで、それぞれの人の長所を伸すことはできなくなります。 ・また能力の差のあるものに一様な教育をすれば、能力のある生徒は授業がやさしすぎていやになり、能力のない生徒はむつかしすぎていやになります。 ・生徒をいやにさせないためには、能力に応じて組分けして、使う教科書もかえる必要があります。 九 ・不平等をどうしてなくするかは、すべての近代国家で大問題でありますが、果して子どもに教育の機会を均等に与えることは可能でしょうか。 ・一番単純な方法は、国家が学校差をなくし、機会の不均等が起りえないような状態にしてしまうことであります。 ・このことは一見すれば理想的なようにみえますが、二つの難点をもっています。 ・第一は、闇学校である塾や予備校をつくり出し、結局、統制を無効にするか、逆に統制がなかった時よりも著しい機会の不均等をつくり出します。 ・第二は、等しい教育の機会が各人に与えられますと、誰もが同じ程度の教育を受け、従って一人だけ教育を受けないでいることが、非常に難しくなります。 ・教育の程度はますます高くなり、教育の期間はますます長くなります。こうして勉強がきらいな人にも勉強が強制され、人生の三分の一を「劣等生」という意識にさいなまれて空費してしまうことになります。 十 ・イギリスにおいて学歴は重要ですが、学歴の高低は日本のように、どの学校を卒業したかによって決るのではなく、どんな国家試験に、どんな点で合格したかによって決ります。 Ⅲ イギリスの大学 ―産業か教養か― 三 ・イギリスで少数の科目について深く学ばせるのは、「学問とは方法を学ぶことであって、知識を集めることではない」との考え方に基づいております。 ・いろいろの科目を浅く学ぶよりも、一つの学問について深く学んだ方が、学問の仕方ないし方法がよくわかることは確かです。そしてひとたび学問の仕方を会得したならば、あとは一生かかって知識を増やし深めて行くことができます。 ・イギリスでは、個人授業(チュートリアル)が大切です。イギリスの大学の先生は講義の外に、チュートリアルをしなければなりません。 ・チュートリアルでは、先生は学生に問題を提出し、必要な文献を指示して、次の時間に学生に報告させます。また一年間に何回かエッセイを書かせて、その添削をいたします。 ・チュートリアルは大変労力と時間を要する授業法ですが、その代り在学生の全員が常に少なくとも一人の先生と緊密な接触を保つことになりますから、学生が進路を見失ったり、自身を喪失したりして、自暴自棄になるという事態の発生を最小限に止めることができます。 七 ・第一に、日本では大学を卒業するまで親がかりで、したがって同年層のイギリス人と比べると子どもっぽく、同時に無責任です。 ・第二に、二十二歳で大学を卒業して、はじめて本当の人生が始まりますから、二十歳台は日本ではまだ駆け出し時代であります。しかし人生七〇年のうちで、体力的にも頭脳的にも、最も精力的に働ける時代は二十歳台であり、この二十歳台を(社会的に体験が乏しいという理由で)社会の下積みとして過すことは、個人的にも、社会的にも大きい損失であります。 ・イギリスでは、現在(一九七四年十二月)でも、二十五歳以下の教授が二人おりますし、大学講師の二〇%は二十歳台であり、五〇%は三十四歳以下であります。 ・社会が二十歳台の人々に活躍のチャンスを与えるならば、ティーンエイジャーはうずうずし出して、のらくらと大学生活を続けることに堪えがたくなってきます。 ・大学には、本当に勉強したい人だけが残り、大学は本来の機能を取りもどします。 ・一方、社会に出た人たちは若いものの発想法で社会を動かして行くことができます。社会は活動的になり、動脈硬化現象は消えて行きます。 ・長い平均教育期間は直截に言って、悪であります。 Ⅳ 新日本列島改造案 ―経済大国からの転進― 二 ・第二次大戦の責任を右翼や軍部だけに押しつけてしまう見方がありますが、こういう見方は問題の核心をぼやかしてしまいます。 ・第二次大戦の主たる原因が、日本の中国市場支配にあったことを忘れてはなりません。中国市場をめぐって、日本もはじめは米、英、ソ連などといっしょに山分けをしていたのですが、そのうちに日本のとり分がどんどんふえてきたために、日本と他の国々との関係は極端に冷却してしまいました。 ・このような経済進出が武力を背景にして、あるいは武力に呼応して行われたために、ついには戦争にまでなりましたが、たとえ満州事変や日支事変がなくても、日本が中国市場を一人占めするような事態になれば、日本は交戦国同様の総スカンの状態になったと思います。 四 ・英国の大学では、はじめから画一教育はできない仕組みになっています。 ・それに反して日本では、国立大学一期校、二期校の同時入試案がでて、入試まで画一的に…。 ・オックスフォード、ケンブリッジ大学などでは講義はそれほど重要視せず、個人指導に重きをおいています。チューター(個人指導教官)がいて、学生を一人ずつ指導します。だからA学生とB学生で学ぶことが非常にちがってきて、卒業するときには、学生は一人一人が非常に個性をもった人間になっています。 六 ・国家は国際的に活躍できるような次の世代の要請に責任をもたなければなりません。 ・独立心のある人間をつくること、ひとりぼっちになっても絶えていける人間をつくることを目標にしなければなりません。 ―― 完 ―― |