
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2025年07月23日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
14 |
25.06 |
続 イギリスと日本 ―その国民性と社会― 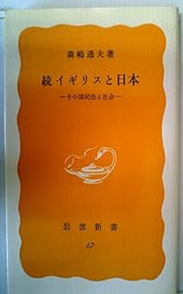 |
森嶋通夫 |
岩波新書 |
◎ |
Ⅰ 英国と日本 ―国民性の比較― 四 ・明治以後、日本が発展したのは、徳川時代にすでに発展のための基礎条件が整備されていたからだ。 ・鎖国と参勤交代と学問(とくに儒学)の振興は、徳川政府が二〇〇年以上にわたってとり続けた三大政策でありました。 ・まず鎖国は、保護貿易をしたのと同じで、その結果、日本の手工業が西欧の進んだ工業によって壊滅させられることが未然に防がれ、日本は完全な農業国になってしまうことをまぬがれました。もし徳川時代に手工業が滅亡させられていたならば、明治になって日本を工業化することは非常な難事であったと思います。 ・次に参勤交代は、全国的な交通網を整備させ、言語の統一、地方文化の向上をもたらし、その結果、地方都市が発達しましたが、このような全国的な発展がすでに徳川時代にあったからこそ、明治になって全国が発展することができたのです。 ・さらに儒教の国民各界層への浸透は、国民を勤勉、節倹にさせると同時に、忠君愛国を原動力とする明治的発展の下地をつくりました。 五 ・イギリス人と日本人についていいますと、両者は共に島国の住民ですから、恥ずかしがり屋で内気です。これに反し、大陸の人は、陸続きに異民族と交渉する機会が多いので、ものおじせず、出しゃばりです。 七 ・日本人は、自分より年若い人の下で働くのをいやがります。彼がどんなに優秀な人であっても、自分よりも若ければたまらないのです。愚物であっても、年長者でさえあれば、その下で働くことにそれほど抵抗はありません。 ・これに反して、イギリス人は無能の人の下で働くことを非常にいやがります。自分の人生が、その期間だけ無に帰してしまっているような気になるのだと思います。 九 ・イギリスが階級社会でありながら、労働者が決して卑屈でなく、むしろ労働者であることを誇りにしているのは、彼らは労働者も資本家も神の前には平等であると信じており、この深いレベルでの平等性の要求の結果、転職の自由が彼らに保証されているからです。 十 ・イギリスの会社や役所や大学は、職員の強制的な定期的健康検査をいたしません。人間の身体は、各個人のものであり、会社のものでありませんから、各個人がそれぞれ自分の身体に気をつけるべきであって、会社は社員の身体上の欠陥にまで節介すべきではありません。 十一 ・第一次世界大戦のあと、日本は世界の五大強国に仲間入りして、国際連盟の常任理事国になりました。 ・国際連盟はご承知のように、アメリカが提案したのですが、アメリカの議会は、アメリカの加盟を批准しませんでした。 ・ソビエトもまた、革命のために国際連盟に加入できるような状態ではなく、実質的には国際連盟はヨーロッパ連盟以外の何ものでもありませんでした。 ・ところでヨーロッパの利害対立を処理する場合には、審判官になれる実力をそなえたヨーロッパ以外の国が必要になりますが、国際連盟加入国でその資格をもっていた国は日本しかありません。 ・それ故、連盟の中での日本の地位は極めて高く、どの国も日本を味方に持ちたがっていたのです。日本は連盟の中で、ちやほやされ、引く手あまたの非常に有利な立場にあったのです。 ・ところが他方において、日本が五大強国に躍進したことによって、アメリカやイギリスとの間に軍縮問題が起ってきました。 ・明治維新の時、尊皇派は、攘夷と開国ののあいだをゆれ動いた後に、賢明にも最後は開国に踏み切りましたが、昭和維新をとなえる昭和の尊皇派は、愚かにも攘夷を実行して、国際連盟という日本にとってもっとも有利な活躍の場を、みずから捨ててしまったのです。 ・あの時にこそ日本が国連外交に徹しておれば、日本は世界に確固たる地位を築けていたはずです。にもかかわらず、間抜けの日本代表は啖呵を切って連盟の議場から退場してしまいました。 ・しかも国民はその知らせを聞いて、歓喜の声をあげたのです。何と愚かなことではありませんか。 Ⅱ 家庭と教育 ―階級はかわれる― 四 ・マルクスの予言にもかかわらず、イギリスに暴力革命が発生しなかったのは、イギリスの階級が開かれた階級であり、階級間を人が頻繁に移動するので、階級対立感情が極端化することが避けられたからだと思います。 Ⅲ イギリス病再論 ―反通説の諸説の検討― 三 ・イギリスの家賃統制は一九一五年に遡りますが、時代とともに統制は強化拡大され、それに平行して住宅投資が増大すると同時に、住宅投資の中で国家投資の占める割合が大きくなりました。このことは国家が住宅供給に責任をもつようになったことを意味します。そしてその結果、国民には住居がほぼ保障され、イギリスには緑が保たれました。イギリスの住宅供給を市場のからくりにまかせていたら、イギリスは緑のない住みづらい国になっていたでしょう。 ・イギリスの南部地方が今なおふんだんに緑にめぐまれているのも、北部地方が再開発に懸命の努力をしているのも、国全体を均斉を保って発展させようという政治的意志の反映です。 ・南部開発を抑制したために、ロンドンが幅広い緑地の帯にいまなおとり囲まれ、ロンドンの都市問題がそれだけ緩和されているのです。 六 ・経済は国民の総力に依存しますから、ちょっとやそっとでつぶれません。しかし文化は一握りの天才に大いに依存しますから、その動きは非常に微妙で、政策のよろしきを得ますと大いに興り、政策をあやまれば壊滅してしまいます。文化政策は不断に、注意深く行なわねばなりません。文化は国のように滅びやすく、経済はむしろ山河のように壊しがたいものです。ですから「文化はほろびて経済あり」という状態は充分ありうることです。 Ⅳ 明治維新を思う ―技術差克服の革命― 一 ・明治維新の主題は、日本的な習慣、日本的な社会生活、上下関係、家族構造を保ちながら、西欧諸国に負けないような九力をそなえた近代国家をつくることが、日本人の念願であったのです。 ・このことは明治維新の前夜でも、ロシアと戦った明治時代の後半でも、大正デモクラシーの時代や昭和初期のファシズム勃興期でも、ナチス・ドイツを理想と考えた軍国時代でも、敗戦後の廃墟のなかにあったときも、経済大国になった現在でも、変ることなく日本人の念願であったのです。 ・西欧精神を否定して空洞化した場所に、狂信的な神州意識以外の何ものでもない日本精神を充填した場合の「西欧なみの強国」は非常に危険なものになってきます。 ・徳川時代末期に鎖国をつづけるか、開国をするかをめぐって国論がわかれますが、進歩的・現実主義的な開国論者の多くも、決して正しい意味での国際主義思想の持主ではなく、たんに方便としての開国論をとなえていたに過ぎません。 ・彼らにとって西欧は「夷狄禽獣」の国であり、したがっていまは屈して開国するけれども、やがては日本が世界万国の大盟主となって逆に世界を統一すべきであるとすら、開国主義者でも考えていたのです。 六 ・日本人は徳川時代以前に、すでに西欧の科学・技術の実力を知っており、それを幕府以外の誰かが輸入すれば、途端に幕府の支配体制は転覆の危機にひんするであろうことを、戦国時代の経験で熟知していました。 ・それ故、西欧技術の輸入を徹底的に管理することが、政権の維持のために必要不可欠でありました。鎖国は消極的でありますが、二〇〇年にわたって有効でありえた輸入管理法でありました。 八 ・明治維新という革命は、日本の政治体制を西欧技術にふさわしいような態勢に変革しようとする革命であって、いわゆるマルクス主義的革命、すなわち国内に新経済階級が勃興して既成支配勢力を打破り、新階級の経済的利益に適した支配体制を築く式の革命ではありません。 ・革命の最後の二年間のあいだに、新政府は新体制を模索しました。 ・将軍に政権を奉還させて、徳川氏も一大名となり、幕府の代りに諸侯会議を常設し、天皇を中心とする公武合体政府をつくるか(大政奉還案)、あるいは幕藩制を一掃した天皇親政の近代的体制に一転させるのか(版籍奉還・廃藩置県案)、更に天皇制を敷くにしても、天皇にどのような政治的地位を与えるのか(絶対的天皇制か、立憲天皇制か)、これらに関しては、彼らは自信をもってこれらの政策を行ったのではなく、いつ新政府が瓦解するかもしれないという危機意識をもっていました。 ・結局は太政官に国家権力を集中させて、太政官が天皇を輔弼するという形の近代的天皇制国家として明治体制が発足しえたことは、当時としては非常に上出来であったというべきです。 ・またイギリスが討幕派が後押ししたのに対抗し、フランスが幕府を助けましたが、討幕派も幕府側も幕末および明治初期の内戦を英仏両大国の代理戦争に発展させることなく、長年にわたる朝廷対幕府という二元政治体制を短期間に解消することに成功したことは、当事者の大きな功績とみなければなりません。 Ⅴ 「維新」百年後 ―なお残る体制的おくれ― ・徳川時代の末期に私たちの先輩は一つの歴史的使命を設定しました。 ・彼らは「何とかして日本を西欧諸国のような強国にしなければならぬが、この目的の実現のために日本人は魂まで売り渡してはならない」と考え、このいわゆる和魂洋才の近代国家を建設する第一歩として明治維新という大革命を実行しました。 ・ヨーロッパ精神とは全く異質の精神的基礎の上に西欧技術の成果を実らせるという接ぎ木を、日本人がはじめて見事に成功させたのです。 ―― 完 ―― |