
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2025年08月13日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
17 |
25.08 |
日本人の法意識 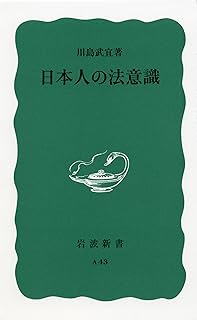 |
川島武宜 |
岩波新書 |
◎ |
第一章 問題 ・明治憲法下の法典編纂事業は、まず第一次には、安政の開国条約において日本が列強に対して承認した屈辱的な治外法権の制度を撤廃することを、列強に承認させるための政治上の手段であった。 第二章 権利および法律についての意識 一 「権利」の意識 ・明治期の近代諸法典、特に民法は、権利を単位として構成され、法律家は権利を照準点として法律問題を処理した。 ・だが、人が自分の権利を擁護することは、西洋では、正しいこととして是認されるのに、日本では、自己中心主義的な・平和をみだす・不当に政治権力の救済を求める・行為として非難されるのである。 ・谷崎潤一郎は『源氏物語』の一節とアーサー・ウェーレー氏の翻訳とを対照し、こう述べている。 「原文で六行のものが、英文では十三行に伸びてゐます。それもその筈、英文には原文にない言葉が沢山補ってあるのであります。……つまり、英文の方が原文よりも精密であって、意味の不鮮明なところがない。原文の方は、云はないでも分かつてゐることは成るべく云はないで済ませるやうにし、英文の方は、分り切ってゐることでも尚一層分らせるやうにしています」 「……英文のように云ってしまつては、はつきりはしますけれどもそれだけ意味が限られて、浅いものになります。……ですからわれわれの国の文学者は、さう云ふ無駄な努力をしないで、わざとおほまかに、いろいろの意味が含まれるやうなユトリのある言葉を使ひ、あとは感覚的要素、即ち調子や字面やリズムを以て補ひます」 「僅かな言葉が暗示となって読者の想像力が働き出し、足りないところを読者自らが補ふようにさせる。作者の筆は、唯その読者の想像を誘ひ出すやうにするだけである」 「……西洋の書き方は、出来るだけ意味を狭く細かく限つて行き、少しでも蔭のあることを許さず、読者に想像の余地を剰さない」 ・谷崎は言う。 「国語と云ふものは国民性と切つても切れない関係にあるのでありまして、……我等の国民性がおしゃべりでない証拠であります」 「……古来支那や西洋には雄弁を以て聞えた偉人がありますが、日本の歴史には先づ見当らない。その反対に、我等は昔から雄弁の人を軽蔑する風があった。……ですから、我等は、支那人や西洋人ほど言語の力を頼みとしない」 「われわれの間には支那にもない『腹芸』と云ふ言葉があって、沈黙を芸術の上にまで持って来てゐる。又『以心伝心』とか『肝胆相照らす』とか云ふ言葉もあつて、心に誠さえあれば、黙って向かひ合つてゐても自らそれが先方の胸に通じる、千万言を費すよりもさう云ふ暗黙の諒解の方が貴いのである、と云ふ信念を持ってをります」 「上に述べたやうな日本人の国民性を考へますと、われわれの国語がえしゃべりに適しないやうに発達したのも偶然でないことが知れるのであります」 第四章 契約についての法意識 二 わが国における契約の法意識 ・契約上の権利義務を確定的のものと見る西洋人の立場からは、誠意協議条項はナンセンスなものに見える。 ・西洋では、「仲裁」という方法によって ・日本的な法意識からすれば、問題が起こったときに「誠意をもって協議し」、 ・この意味において、誠意協議条項は、わが国の契約のもっとも重要な核心であり、それゆえ、わが国では仲裁は行なわれず、いわんや裁判もこれに適せず、 第五章 民事訴訟の法意識 一 裁判 (2)問題 ・わが国では一般に、私人間の紛争を訴訟によって解決することを、ためらい或いはきらうという傾向がある。 二 調停 (6)戦後の変化 ・昭和二九年に発行された『調停読本』には、日本調停協会連合会会長溝口喜方氏が序文を書き、 「云うまでもなく調停の基本理念は和であって、聖徳太子が今から千三百五十年前制定された十七条憲法の第一条に『以レ和為レ貴』と示されているとおり、和を尊ぶのがわが国民性であるから、わが国において調停制度が発達するのも当然であろう」 というふうに、調停の基本精神を述べており、また同書のなかにある、調停の際心がけるべき要点を示す「調停いろはかるた」には、 「論よりは ―― 完 ―― |