
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2025年09月21日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
21 |
25.09 |
街場の中国論 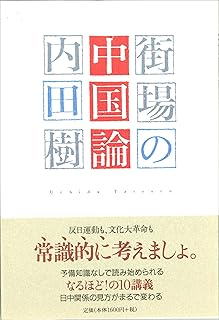 |
内田 樹 |
ミシマ社 |
◎ |
第1講 チャイナ・リスク――誰が十三億人を統治できるのか? 経済の失速と未成熟なインビジブル・アセット ・非常にハイレベルで経済成長が進んでいるせいで、ほんらいであれば政体の危機を招きかねないさまざまな社会矛盾が隠蔽されているということです。 ・パイの分配の仕方に非常に問題がある場合でも、パイそのものが増量しているときには分配方法の不公平についての異論は表面化しない。 ・経済成長の九パーセントが六パーセントに下がるくらいのことは、ふつうの国なら許容範囲ですが、中国の場合は、「い゛すれ私ももっと豊かな生活ができる」という期待がさまざまな社会的な不合理や制度の機能不全が前景化することを防いでいるから、この高度経済成長が停滞すると、いきなり危機的な状況が到来するのではないか。そう言われています。 ・パイの分配方法がフェアであれば、パイの増量スピードが停滞しても、それによってシステムそのものが瓦解するような危機は到来しません。リスクがあるということは、パイの分配方法が(僕たち外国人から見てだけでなく)中国人自身の目から見ても、あらわにアンフェアであるということです。 ・そして、経済成長率が七パーセントまで下がったら危険だということを中国政府自身が自覚しているというのは、言い換えると、中国政府は分配方法のアンフェアを修正する手だてを今後しばらく講ずる用意がないということです。 ・内陸部と沿海部の経済格差や、都市住民と農村住民の待遇格差や、党官僚や特権階層の腐敗に対しては、当分打つ手がない。 ・人間は、まわりがみんな同じように貧乏なときには、それほど政治に対して不満を感じないものです。 ・中国にはいくつか経済成長をしてゆく上での不安材料があります。 ・ひとつはインフラがまだ不十分であるということです。 ・もうひとつ、「インビジブル・アセット」(見えざる資産)と言われるところの組織原理、職業倫理といったものが中国では未成熟、あるいはもともと存在しないことが挙げられます。 ・日本の明治維新以降の急速な経済成長を支えたのは、産業革命以降のテクノロジーだけではありません。江戸時代の「大店」の組織原理がそのまま新時代の株式会社に切り替わるということができたからです。 ・一番番頭さんが専務になり、手代が係長になり、丁稚が平社員になるというかたちで、伝統的な「老舗の信用」や、「終身雇用・年功序列」の雇用ルールや、クラフトマンシップや職業倫理がそのまま近代の産業社会に移植された。 ・江戸時代以来の伝統的な日本の商業資本には固有の組織原理があり、何百年にもわたって「企業家のエートス」とでもいうべきものが練り上げられてきた。 ・しかし、中国の場合は、そういう企業のエートスに相当するものが非常に弱い。 ・ほとんどの企業がまだ歴史を持っていない。 ・「老舗の看板」とか、職人が育つのを気長に待ってくれる年来の「お得意さま」とか、終身雇用であるために企業に家族的一体感や帰属感を持つ労働者とか、そういう日本の場合なら江戸時代三百年をかけて構築されたものには根づいていない。 第2講 中国の「脱亜入欧」――どうしてホワイトハウスは首相の靖国参拝を止めないのか? 歴史から消された中国人 ・日本に対しては中国の側に、日本を批判することには心理的な抑圧が働いていない。 易姓革命の国と、革命のない国 ・ <途中> |