
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2025年02月12日 水曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
3 |
25.02 |
「論語」を読む 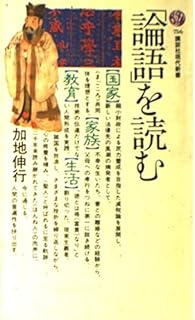 |
加地 伸行 |
講談社 現代新書 |
◎ |
はじめに ・‹古典を読む›ことは、語釈を読み、物知りになるということではなく、あくまでも、自分との関わりにおいて読むことである。 ・自分との関わりとは、いま自分がかかえている問題、自分が行き当っていることがら、それをどのように解決すればよいのかと悩み考えていることとの関わりである。しかもそのほとんどは、簡単に技術的に解決できないようなものであろう。 ・そのようなとき、人は、さまざまな解決方法を求める。あるときは、人生経験豊かな知人と相談するであろう。あるときは、信仰する宗教にそれを求めるであろう。それぞれその人の立場に寄って異なり、一定のルールなどありはしない。 ・しかしそのようなとき、個人それぞれの事情を越えて、だれにでも公平に開かれており、だれもがいつでも ・古典のなかには、人間やその生きている社会のさまざまな問題とその解決への道の類型がある。もちろん、時代が異なる以上、事情はまったく同じではないが、その類型が確実に存在している。 ・数冊の古典を読めば、人間の考えること、感じること、行なうことは、古今東西を通じて、本質的に変っていないことを知るに至るであろう。 ・その古典の一冊として『論語』がある。中国人が、どのように人間や社会や世界のことを考えていたのか、それを『論語』はありありと示している。 第一章――孔子と『論語』について エネルギッシュな孔子 ・いわゆる聖人孔子として祭りあげられるようになったのは実は後世の話なのである。 ・かつて生きていた孔子自身は、われわれ凡人と同じく、欲望を圧えきれず、人に認められたい、自己を顕示したい、地位も金銭も欲しい……といった、ごくふつうの願望を持つ人間であった。 ・『論語』中、孔子が自分の一生をふりかえって述べた有名なことばがある。「吾、十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑はず。五十にして天命を知る。六十にして 五十にして流浪 ・孔子の生涯において述べられたことばが語り継がれ、やがて整理され、今日の『論語』となって残ってきたのである。 ・孔子が思想家であると言えるのは、自分の人生経験を、ただ単なる個人的経験としないで、それを一般化し、人間一人一人に強く訴える普遍的なことばとした点にある。だからこそ、『論語』のことばには多くの人の心を打つ永遠性があるのである。 第三章――家族について 2 日本人の孝・中国人の孝 孝行は葬祭にあり ・生きて在る親に対してのみならず、死後の親に対して招魂儀礼を行ない、またその招魂儀礼を永く行なうためには、子孫を生み家系を絶えないようにすること、そのような三つの行為すべてを含むものを、中国人は孝としたのである。 ・この、生死を貫くものとして理解されている中国人の孝は、宗教的と言えよう。 ・これに反して、生きて在る親に対する子のつくしかたというふうに限られている日本人の孝は、道徳的と言えよう。 ・この中国人の宗教的孝と日本人の道徳的孝との相違、これは決定的な相違である。 ・その相違の根本原因は、実は、死の問題がそこに関わっているか、いないのか、というところにある。 ・中国人の宗教的孝と中国人の死の問題とが欠く関わっているのに反して、日本人の道徳的孝は、日本人の死と関わっていないのである。 第四章――人間について 3 死・霊魂――宗教 悲しみの等級 ・父母の死に対して、喪に服する期間が三年(実際には二十五個月。仏教はそれを取り入れて命日から満二年目を三回忌とする)であるのは、子が生まれて三年間は、おむつをし、両親にたいへんお世話になるそのおかえしとする。 ・そして、この最も親しい者を、一般論的に父母とし、その父母に対する愛をこそ最高とするのである。最高の愛であればこそ、その愛する者の死は、最も悲しいのである。 ・父母と子とのこのような関係を底にして、子の父母に対する愛の行為(生前・死後を問わず)全体を ‹孝› とするのである。 儒教と葬礼と ・三世紀にインドからはいってきた仏教は、この世への再生を説くものではない。因果応報、輪廻転生を説くのみである。 ・現世での行為によっては、来世は、人間に生れることができず、動物として生れ出ると説く仏教は、一時期はともかくとして、ついには中国人のこころをとらええなかった。 ・この世を仮の世と説く仏教は、この世を最高のものと考える中国人の心をとらええない。再生を信じて遺体をそのまま土葬する儒教のほうが、遺体を火葬する仏教よりも、はるかに強く中国人の心をとらえていたのである。 現代中国にも脈々と ・生命の永遠を願って子孫を増やし、その子孫に自分の招魂を願って死の不安を解消しようとする中国人民衆の宗教心が、人口増加と大いに関わっていることが、民衆の抵抗の根本理由であることを、現代中国の為政者はもっと知るべきであろう。 第五章――精神について 1 ことば――論理学と詩と ‹ラング› と ‹バロール› との関係 ・内実のない口先きだけの本当らしい話、それを孔子は「巧言」と言った。 ・巧言を発するとき、相手に対して、顔つきはもっともらしく、そして愛想がいい。それを「令色」と言う。そういう演技を伴っての巧みなもっともらしい話を聞けば、だれでも本当かと思ってしまう。 ・そこで孔子はこう言っている。 ―― 「巧言令色、 第六章――生活について 1 金銭・地位 率直な中国人の金銭感覚 ・中国人は、そのほとんどが、人前であっても金銭や地位の話に対して、はっきりと関心を示す。金銭を稼ぐことは、中国人にとって善なのである。社会的により高い地位につくことは、善なのである。それを率直に示すのが中国人の平均的感覚である。というよりも、人間一般の平均的感覚であると言うべきであろう。 ・日本人は、だいたいにおいて、たてまえ主義である。ほんねは隠す。ほんねを言うことをはばかるところがある。 ・それと言うのも、個人として性格的に弱いところがあり、他者がどういう考えであれ、自分一人ほんねを言いきる勇気にとぼしい。独り立つという気概にとぼしい。 ―― 完 ―― |