| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年11月15日 水曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 (下線を引いている本は「抜き書き」にリンクしています) |
著 者 | 出 版 社 | 評価 | 一 言 コ メ ン ト | |
17 |
11/12 |
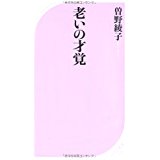 |
老いの才覚 |
曾野綾子 |
ベスト新書 |
☆ |
第1章 なぜ老人は才覚を失ってしまったのか 昔の老人には、老いる「才覚」があった ・戦争を体験している世代は、戦時下では頭が真っ白になるような人は生き延びられなかったはずです。被災したときにこそ、高齢者だという甘えを捨て、過去の経験を活かし、率先して行動すればいいのです。 ・私など、子供の頃から「才覚を持ちなさい」と訓練されたものです。何事に関してもいちいち人に聞かないで、どうしたらうまくできるかを考えろ、と。できなければ、親からも社会からも「あなたは機転の利かない子ね」と叱られました。つまり年をとれば、それだけ才覚にあふれた老人がたくさんいたのです。 基本的な苦悩がなくなった時代が、老いる力を弱くした ・貧しさを知らないから豊かさがわからないのです。 戦後の教育思想が貧困な精神を作った ・戦後、日教組が、何かにつけて「人権」「権利」「平等」を主張するようになりました。その教育を受けた人たちが老人世代になってきて、ツケが回ってきたのだと思います。 ・昔の老人には「遠慮」という美しい言葉がありました。 ・本能をコントロールすることが「遠慮」なんですね。 ・動物的平等化を人間的に慣らす方法が「遠慮」だと思います。 ・かつては、損のできる人間に育てるのが、教育の一つの目標でした。 老人の使う言葉が極度に貧困になった ・原因の一つは、読書をしなくなったからです。 ・読書をすれば、それよりさらに広く自分が経験できないことを学ぶわけです。 ・しかも読書には、非常な自由が与えられています。同じものを読んでも、人によって全く別の受け取り方ができるでしょう。 ・読書の習慣があれば、表現も自然と豊かになりますし、基礎的な知識だけではなく教養も身につきます。何より人間関係を恐れなくなります。 外国人の会話は実にしゃれている ・私は、自分の財産というのは、深く関わった体験の量だと思っています。 ・若い時から困難にぶつかっても逃げ出したりせず、真っ当に苦しんだり、泣いたり、悲しんだりした人は、いい年寄りになっているんです。 第2章 老いの基本は「自立」と「自律」 他人に依存しないで自分の才覚で生きる ・老人であろうと、若者であろうと、原則はあくまで自立すること。 ・自立とは、ともかく他人に依存しないで生きること。自分の才覚で生きることです。少なくとも生きようと ・生活をするのは自分自身だということを肝に銘じておかなくてはいけません。 ・どんな手を使ってもいい。自分で生活を成り立たせる義務があるのです。 ・人からどう見えるか、なんて問題ではない。大事なのは、自分をどうやったら生かして行けるか、ということなんです。 ・老人といえども、強く生きなくてはならない。歯を食いしばってでも、自分のことは自分でする。 ・それはだれにも与えられた人間共通の運命なのですから。 人に何かをやってもらうときは、対価を払う ・誰でも人は何かをしようとしたら、対価を払わなければならないんです。年寄りといえども、この原則を忘れてはいけないと思います。 ・社会が(して)くれるものなら、何でももらっておこうというのは、乞食根性になっている証拠です。払える年寄りは、何歳になっても、自らの尊厳のために払うべきだと思います。 ・対価を払うのが社会にいる「壮年」の務めだ。 ・そんな自立の気構えが、精神の若さを保つうえで非常に大切な要素になっている。そうするのは何より自分のためになるんですね。 高齢者に与えられた権利は、放棄したほうがいい ・老人は、もう少し自ら遠慮すべきだと思います。 ・国の制度や医師の論理では、どんな人も平等です。だからこそ、高齢者が自ら辞退したほうがきれいですね。国が高齢者を切り捨てるのではなく、若者が要求するわけでもなく、高齢者が自由意志で、自らの美学として、自ら遠慮したほうがいいのです。昔の日本では、それが当たり前のこととしてできていました。言葉にしなくても、だれもがわかっていました。年を重ねて当然備えているはずの賢さを、社会の中で充分に発揮していたから、老人は尊敬を払われていたわけです。 第3章 人間は死ぬまで働かなくてはいけない 老人が健康に暮らす秘訣は、目的・目標を持つこと 「何をしてもらうか」ではなく「何ができるか」を考える 受けるより、与える側に立つと幸せになる ・与える側でいれば、死ぬまで壮年だと思います。 ・介護してくれる人に「ありがとう」と言えたら、喜びを与えられる。 ・最終的に与えることができる最も美しいものは「死に様」だと私は思っています。 ・死後、臓器の提供や献体を希望する人もいるでしょう。どんなによぼよぼになっても、与えることのできる人間は、最後まで現役なんです。 第4章 晩年になったら夫婦や親子との付き合い方も変える 「折衷」を許し合える夫婦になる ・半分好きなことをして、半分はお互いに妥協して暮らすんです。それを、いい加減にやれるのが大人だと思います。 ・半分の欲望を叶えて、それをさせていただいたことに感謝する。そうすれば、なんとなく折り合いがつきますし、お互いに楽です。だから老年になったら、折衷を許せる夫婦になったほうがいい、というより便利です。折衷というのは、もしかすると偉大な賢さなのかもしれません。 親しき仲にも礼儀あり ・私は、親が子にしてやれる大きな事業の一つは、別れることを上手にやってのけることだ、と考えていました。子どもを教育しながら、しかも最終目的は独立を完成したその相手の前からさりげなく姿を消す。これは、常に感謝され、自分の与えたものを相手に確認してもらいたい普通の人間関係においてはなかなかできにくいことですが、親の愛情というものは、本来、無私の愛であるはずです。 第6章 孤独と付き合い、人生をおもしろがるコツ 老年の仕事は孤独に耐えること、その中で自分を発見すること ・他人に相手をしてもらったり、どこかへ連れて行ってもらったりすることで、孤独を解決しようとする人がいます。しかしそれは、根本的な解決にならない。根本は、あくまでも自分で自分を救済するしかないと思います。 孤独は決して人によって、本質的に慰められるものではありません。 ・一口で言えば、老年の仕事は孤独に耐えること。そして、孤独だけがもたらす時間の中で自分を発見する。自分はどういう人間で、どういうふうに生きて、それにどういう意味があったのか。それを発見して死ぬのが、人生の目的のような気もします。 一人で遊ぶ習慣をつける ・とくに一人旅は、知恵を働かさないといけないし、緊張していなくてはならないから、惚け防止にも役立ちます。 どんなことにも意味を見出し、人生をおもしろがる ・してもらうことを期待していると不満が募って、つい愚痴が出る。老人の愚痴は、他人も自分もみじめにするだけで、いいことは一つもありません。それどころか、愚痴ばかり言う老人のそばには、人間が集まらなくなります。愚痴は日陰の感じを与えるからです。反対に、何でもおもしろがっている老人には陽の匂いがして、人が寄って来ます。 第7章 老い、病期、死と馴れ親しむ 他者への気配りと、忍耐力を養う 老齢になって身につける二つの力 ・若くても、他者への配慮がなくなったら、それが老人なんですよ。電車の中で足を投げ出して座ったり、眠りこけている人は二十歳でも老年です。言葉を換えて言えば、他者への気配りがあれば七十代でも壮年なのです。 七十五歳くらいから肉体の衰えを感じ始める ・医療サービスの利用状況は、「ほぼ毎日」から「月に一回くらい」までの割合の合計が日本は五六・八%と、他の国と比較して医療サービスの利用頻度がいちばん高いらしいです。 この背景には、全員が全員でないにせよ、「保険料を払っているのだから、元を取らなくては」「健康保険はいくらでも使ったが勝ちよ」という考えがあるからではないでしょうか。元を取るという発想は、商人の行為なんです。元を取ろうとしないのが、人間の上等な生き方だと思います。 死に馴れ親しむ ・死は願わしいことではありませんが、必ずやって来ます。願わしくないことを超えるには、それから目を逸らしていては解決できません。死は確固としてその人の未来ですから、死を考えるということは前向きな姿勢なのです。 ―― 完 ―― |