| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2020年07月15日 水曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 |
著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き |
17 |
13.05 |
島津斉彬公伝 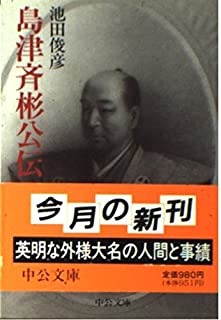 |
池田俊彦 |
中公文庫 |
☆ |
第八章 民政、勧業、経済 治世の要訣 ・斉彬の常に家臣に教えて治世の要とした格言 一、人心の一和は政治の要目なり。 一、民富めば国富むの言は君主たるもの一日も忘れるべからざる格言なり。 一、人君たるものは公平無私、愛憎の念なきを要す。 一、凡そ人は一能一芸なきものなし。其長短を採択するは人君の任なり。 一、既往の事を鑑みて前途の事を計画せよ。 一、勇断なき人は事をなすこと能はず。 一、一癖あるものにあらざれば人は用に立たず。 一、天下の政一変せざれば外国と交通をなすこと能はず。 一、国政の成就は衣食に窮する人なきにあり。 一、下情上達は政事の要なり。 一、彼を知り己を知るものは百戦 一、古への道をきいても唱へてもわが行にせずはかひなし。 一、とがありて人を斬るとも軽くすな活かすも刀もただ一つなり。 第十章 外交上の諸問題 米使ペリーの再渡来、神奈川条約締結 ・自由平和を主義とし新思想の急先鋒をもって自任する米人は太平洋を渡って、先ず日本の門戸を開くの名誉を担うに至りしものなるが、この間ペリーは一方示威虚喝をもって我国に臨みながら、衷心日本に同情し、万国交際は人類自然の法則にして、世界の大勢は 斉彬は純然たる開国論者 ・斉彬は語った。 「清国の事情かくなるべしとは思はなかった。先年阿片戦争起りて未だ数年ならざるに、未だ内政整はず内は長髪賊蜂起し之を鎮定するの威力なく、既に病膏盲に入れるものか、かくしてますます外国の侮りを受け英仏等諸国の侵略を受くるに至らん。彼国既にかくの如しとすれば、日本は隣邦故心を用ゐなければならぬ。英仏等の諸国清国に志を得たる以上は我邦も晏如たるを得ない。何とかして我より先づ福州に手を入るること肝要ならん。畢竟諸国の滅亡せんことを望むには非ず、一日も早く速に政事を改革し軍備を整へ日本と聯合する時は英仏と雖もまた深く恐るるに足らぬが、清国その版図の広大なるを誇り、日本を視ること属国の如くならば到底聯合は困難である。今日の急務は何とかして一日も早くその覚醒を促し両国の協調を見たきものなり」 ・かく考え来れば日支親善を企図し東洋諸国の安定を念願せしかを察するに足る。後に西郷南洲の熱心唱導せし東亜経綸策は斉彬の遺鉢を継がんとしたものである。 ・しかしその理想を達成するには日本の国情もそれを許さなかったが、彼が平素いかに平和を愛好し真の平和国家を企図せしかは次の歌が最も雄弁に説明している。 四海波静 異国の船のたよりも跡たえてなみしづかなる四方の海はら ・彼が平素熱心に軍備を整えしも、産業を奨励せしも、教育を盛んにして、学問を奨励し科学を振興せしも終局の目的は畢竟ここにあったのである。 第十一章 薩摩士風の改善と教育 第十五代貴久の時鉄砲、耶蘇教の伝来 ・ザビエルは日本人の義侠的な性格と真理に忠実なる態度を推奨して本国に贈った書簡に「予が知る限りでは不信徒の国民中未だ日本人に優る者はない、彼等は其類に於て最善の者である、温良にして毫も意地悪からず……酒は随分吞むが、食物は節制す、一切賭博をせぬ、人民の大部分は読み書きを能くす」と書いている。ある意味において真実なる日本国民の知己というべきだ。 郷中制度の改革 ・ ・初の頃は「 ・即ち一定地域内の武家子弟をもって統制ある自治団体を組織し、その名称に地名を冠し、規約を設けて相互に文武を励み 斉彬の文武奨励 ・「学問の目標は身を修め家を斉え国を治め天下を平にするにある」と説いた。 「学ぶところを世に行わざれば、無学無職にひとしい」 「由来正学は人倫に基づきその学び得たるところを実行せざれば何をかなさん」 外国人に対する非礼訓戒 ・当時国内至るところ攘夷思想拡がり、薩藩の壮士またこの風に染みかかる暴挙に及んだものである。ここにおいて斉彬諄々として事理を尽してその非行を ・それからして約束に基づき、五月二度目に日本丸が鹿児島に参りし時は、もちろん御自分船に赴かれ、そうして騎馬で真先に磯の方に案内をして行かれた。 ・前もって御叱責の書附も出ているので、今度は至って静粛で、一点の粗暴も無かったので、斉彬は直ぐ書附を出しこの度の振舞まことに神妙であったとということを一統に達するようにと云う御褒めの語があった位であった。 ・叱るにも褒めるにもまことに当を得ていると思うのである。 ・当時国老等はこの暴挙煽動者の姓名を取糺し至当の処分あらんことを進言したところ、斉彬はこれらの所為咎むべきも、もともと心中悪意あるに非ずして、全く時事に通ぜず血気の勇に逸ったもの故訓戒をして後日を誡めればそれでよろし、とて右のごとく親書を出したのである。 ・それを見て壮士輩は斉彬の激怒されたのを知り恐懼悔悟して罪をまちしに、それを不問に付せられ訓戒にとどめられたので、一堂深く感銘しますますその盛徳を欽慕するに至ったということである。 第十二章 洋式造船ならびに科学的事業 蒸気船の建造 ・驚くべきことには斉彬は汽船の製造と同時に汽車の製作をも命じたことである。 ・安政元年蒸気船雛形の建造に着手したと同時に蒸気車機械並に鉄道の図を示しその雛形の製作を命じた。 ・汽船の製作と同時に汽車の試作を命じたことは力の分散ではない。 ・斉彬の語にある通り「海陸の差別あるのみで蒸気機関の活動に於てはその理は同じき訳なれば蒸気船製造の参考にも相成るべし」との命令は正にその通りである。 ・すでにして蒸気車の模型もでき上り江戸に送り斉彬の観覧に備えた時は安政二年のことであった。 日章旗制定 ・商船軍艦建造の上は旗章制定の要あること当然にて、嘉永六年斉彬は幕府に対し帆船十二艘汽船三艘の申請をなした。 ・後日国旗の制定はこの時の建議に基づくというべきである。 ・この日の丸の発案たる斉彬は、他をして研究考案せしめたものでなく、彼自家の創意によれるもの。 ・或時御風呂上りの折斉彬公の御話 「段々自分は考へて日本は『日の本』の国と異国にても申し居り、又は『日の出る国』とも唱ふる由国名に於ても相当し、また天照大神宮の天の磐戸を御出になりてより、此日本は開けて今日に至りし難レ有国なれば、夫等の事をも考へて見立てたり」 ・日章旗は斉彬がわが国号に因みて親しく建議したるを、水戸斉昭が熱心に支持したるため遂に決定したものといえるのである。 ・そもそも我が国にて日章旗の国旗として制定せられしは明治五年なるも、日像をもってわが国の理想的標章となせるはすこぶる古きことに属す。即ち太陽を崇拝して神とするは我が国古来の習慣である。天照皇大神は日の神にましましその御嗣を天津日嗣と呼び、歴代の天皇は日神の御裔なりと思い来った我が祖先が、太陽を尊べる例は記紀万葉集等に多く散見するより見れば日章の縁は由緒遠しというべきである。 ・しかしこれは皆対内的なものであって、外国に対して国旗を定めたのは安政元年に始まれりというて然るべきであろう。 ・およそ国旗は国家の表章たるが故に、その国体を象徴し、歴史を表現し、国民的精神と合致するものでなければならぬ。これ世界各国にいずれもその国独特の国旗を制定する所以である。 ・されどわが国の国旗ほど純一雄大端正にして荘厳なるは多く他に見られぬところであり、檣頭高く翻々たる日章旗を見ては、斉しく中外人の歎賞措かざるところである。 ・そもそもわが国は東亜に位しいわゆる日の出の国である。赫々たる光輝はわが建国の大理想を表わし、真紅の色は熱烈至誠、白色は清浄、潔白、無垢、平和なる国民性を示す。 ・斉彬の深意まことに万古に輝くものあるを痛感せずにはおれないのである。 集成館と命名 ・集成館及び精煉所においては、反射炉、溶鉱炉、鑚開台、硝子製作所、瓦斯灯、電気、地雷、撮影所、農具製作場、洋式製塩所、陶磁器製作所、綿火薬、硫酸、硝酸、塩酸、氷白砂糖、櫨蠟、樟脳、硝子製作、甘藷酒、鋳銭所等の諸設備あり。 ・またその外金銀 ・安政四年八月磯邸内諸製作工場に集成館の総称を附す。 ・集成館の命名ありしのち従来の後花園精煉所を今後開物館と名づけられた。 ・斉彬は安政四年八月二十日集成館に臨みて当時財政の局に当りし趣法掛用人三原藤五郎、福崎助八及び集成館の係役員等を呼び、当時における日本の形勢を説き、軍備を整えまた理財の道を講ずるは今日の急務にして、集成館創立の主意は実に軍備と理財の二点にあることを諄々として諭したれば、三原等ははじめて斉彬の時局に対する深意を諒知し、大いに感銘せしという。 驚嘆すべき科学者 ・公はその藩庁及び首府の総ての法規及び設備を吾等に見せしめ、吾人が観覧したる諸件につきその意見を徴し、いかにこれを改造し、もしくは変更をなすべきやを希望されたものであった。しこうして諸事の計画は我らの忠告に従い、機敏に実施された。 ・しこうしてその費用と労力は実に莫大なるものにして、これらの改造の中には巨大なる工事ありしも、もしそれが科学的方法によるものであり、それにより成就するならば、また文明の進歩に対しなんらかの貢献をなすものならば、その費用を出すに毫も躊躇せず、かつ工事の遂行を逡巡せずとの意を示された。 中谷博士著『科学の芽生え』 ・北海道大学教授中谷宇吉郎博士 坊之津海岸に金鉱が発見され、金質極めて良好の為公は直に、実地検査を命じた。試掘の結果「鉱脈海中に向ひ厚く陸地の方に薄く着手するに術なし」云々、その時の公の語は大に味うべきものがある。 西洋各国では海底河底にも鉱道を穿って発掘してゐる処がある、「此鉱はたとひ発掘することを得ずともメキシコ鉱山の掘法を習はゞ良法あらん、図面をつくり蘭人にきゝ研究さして見よ」との命令であった。此時の「此鉱はたとへ発掘することを得ず共」の語はまさに科学の真髄に触れたる言葉と私には思はるる。かかる時によくある例は家臣から外国の例を引いて海底発掘の研究を進言する、それに対して主君から「それをやつたら必ず此金山は発掘出来るか」といふ言葉が出る。然るに全く逆の言葉が百年前の公の語に出るのを私は驚嘆するのである。 ・科学は不可能を可能とするものでなく、可能を可能ならしむるものである。明かな事を明かに認める精神が科学の精神である。斉彬公が少しも迷信にとらはれなかったのはその公明なる精神の齎した当然の帰趣である。 ・権力と科学とは普通には両立し得ないものである。権力を与へられた人が科学の心を持つことは、富者が天国の門に入るよりも更に困難なことである。 ・極めて稀な場合にその両者が一致することがある。その時には新星のやうな光芒を発するのである。私には斉彬公の場合がその極めて稀れな一つの例のやうに思はれる。 第十四章 流風余韻 薩英戦争と戦後の大なる悟り ・この戦の教訓により薩摩は今更のごとく斉彬の偉大と先見の明ありしことに感歎措く能わざるものがあったのである。 ・従来斉彬は海岸に砲台を造り市の美しき眺めなくなるとし、また「蘭癖」ありとして彼を非難せし人々もここに至りはじめてその神のごとき識見にそぞろ崇敬讃歎の声を放たないわけにはゆかなかった、 ・されば斉彬の遺志を継紹する久光、忠義はこれら時代の趨勢に鑑み、この戦闘の実験に徴し、直接藩士を外国に派遣し、彼の長所を探り、我の短を補うを急務とし、それがためには戦後薩英両国の握手、交驩を必要とし、同年十月償金七万両を横浜において交附し、留学生の派遣、軍艦武器購入の斡旋を諾せしめ、慶応元年我より留学生を派遣せしむることとなった。 ・要するに皆これ斉彬精神への復帰に外ならぬのであった。 留学生派遣は斉彬の遺志 ・この軍艦武器購入、留学生派遣ということは斉彬の生前に計画せしめしことであった。 ・斉彬は逝去の前年安政四年に藩士市来四郎を琉球に遣わし、在番奉行、琉球官吏とともに在琉仏人に談判を開始し、蒸気船一艘、大砲小銃等武器購入、英仏米の三国に薩摩より五六人、琉球人より三人留学生派遣のこと決定したのであるが、斉彬の逝去により多年の計画水泡に帰したのである。 ・それが今かかる形勢となり慶応元年留学生派遣というに立至ったものである。 第十五章 逸事逸話 寛仁大度の識量 ・戦は敵気を挫きて相手を降伏せしむるこそ本意なれ、さすれば今日敵と思ふも、明日降りし折は即味方にて、国家の用に立べきものを、ねらひ打に射すくむるとは真の御本意にはあらせられぬとの御沙汰。 米価を日々聞かる ・常平倉創建以来は勿論、その以前より市中物価を時々聞食された。 ・凡そ物価平均せざれば末々の小輩困窮の基なり、常平倉取建の趣意は飽まで承知の通り国民衣食の為に苦しむは政治の大闕典なり、たゞに恥なるのみならず国の乱れの基なり、国民苦むは国主の恥なり、和漢共に其例多し、常平倉は仁政の本なり、四海困窮すれば天禄全く終らんとは素より承知の事なるべし、また民富めば国富むとは政治の眼目なり、これは余の明け暮れ心配することなり。 人は一芸一能なきものなしとの話 ・集成館に硝子工人として召仕はれたる、四本亀次郎といふ者、予て酒癖悪く、酒を吞みし上市中に出で買物をなす時、常に店先のものと口論に及び、乱暴をなす癖あり、或時その形行を江夏十郎より御内聴に達したるに、斉彬公晒て御沙汰には軽輩の細工人などにはその癖あるべし、身柄の人にも酒癖はあるものなり、然れ共人は一能一芸なきものなし、右の四本も硝子製作の手腕優れ居るを以て、酒癖の欠点を補ふ所以なり、その癖あるを以てその勝れたる芸は捨て難し、よくよくこのことを本人に申聞えたらば、その癖直ることもあるべし、一体人の上に立って政治に預るものはこの心掛け忘れてはならぬ、また人間誰にも癖があり、十人が十人百人が百人総ての人に好まるゝ人物といふものは絶てなきものなるのみならず、非常な人物は必ず一癖あるものなり、今の世幕府の老中を始め諸役人みなみな姑息の人物にて、非常の世に処する人は一人もなし、困ったることなり、馬も乗り癖のあるものでなければ、実際の用には堪えず、その癖のある馬によく乗る人は少ない、人仕ひもまた同様なり。 ―― 完 ―― |