| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2020年04月15日 水曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 |
著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き |
31 |
13.08 |
徳川慶喜〔2〕 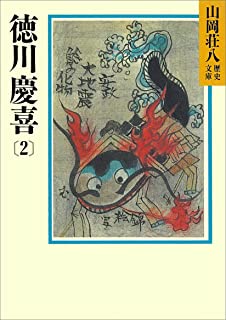 |
山岡荘八 |
講談社文庫 |
◎ |
純真大名 ・橋本佐内曰く、 「退縮追随の開国ではいけない。清国のアヘン戦争の惨敗を戒めとして貿易によって経済を豊かにし、すすんで軍艦を建造し、アジア小国の力を結集してヨーロッパの列強に併呑されないようにすべきだ」 「従来のように役人は譜代大名や旗本の中から採るという方針を打破して、天下からひろく人材を発掘してゆくこと。兵制を改革して国防を充実させること。諸侯の疲弊を救うため、参勤交替や江戸詰めなどの陋習を改めること。蝦夷地(北海道)開拓は、国防富国の両面から急務であること、民業の開発を積極的に奨励すること。学術の振興を期するため学校を興すこと……」 ・それらのどれ一つを取っても、昭和の今日の政策と変っていない。 ・信頼という感情の育ちは恋愛のそれと似ている。相手の愛情に応えようとする心が、いよいよ清冽な愛と愛とを呼び重ねる。 百年の悔い ・慶喜曰く、 「ここでこのまま相手の武力に屈して開国すると、数十年の後、いや百年の後に・・・・・・必ず子孫が、たまり兼ねて堪忍袋の緒を切る時が来るであろう。対等ならざる交際にはそうした怨恨の根が残るものじゃ」 「ここで一戦して、対等の友情の上に立つ交わりならばとにかく、脅迫したものと、されたものとでは仲々一つになりかねる」 「手を握る前に一戦しておかなければ、遠い将来、必ずより大きく激突しなければならなくなる」 怒濤前夜 ・この天皇の御譲位のご決意を、一般世上の不平や責任廻避からする辞表の類と混同してはならない。ここにわが国柄の特異な個性と伝統がきびしく秘められてあるからだ。 「――日本においては、 ・関東へ無理難題を云いかけたつもりはない。どこまでも衆議を尽せということは、国民すべてを吾が子と視る天皇の、国を割らないための当然の心得であり伝統なのだ。それが幕府には通じない。あっさりと無視された。皇位を継がせられる帝にとって、それはまさに絶体絶命の嘆きであった。 ・そこで帝は祖宗の御霊の前に不徳の責めを負うて皇位を退くよりほかにない。その反省がそのまま天皇の怒りであった。 ・天皇の対させ給う良心は、人と人とのそれではない。つねに祖霊の宿り給う宇宙生命の御鏡なのだ。 ・自分の不徳によって、その御鏡に曇りがかかった。幕府が伝統を理解し得なかったということは、どこまでも皇位の汚点に通ずるのだ。 「――この一大事の折柄、愚昧統仁なまじ帝位におり、治世候こと、しょせん微力に及ばざること……このまま帝位におり、聖跡をけがし候も実に恐懼に候間、英明の人に帝位を譲り度く候。さしあたり、裕宮(後の明治天皇)これあり候得ども、天下の安危にかかわる重大の時節、幼年の者に譲り候は本意なきこと、これによって伏見、有栖川の三親王のうちへ譲り度く存じ候」 湧くもの降るもの ・当時鹿児島にあった斉彬は、六月七日に薩摩に戻った西郷の口から、一橋慶喜の擁立運動が、井伊直弼の強引さに押し切られて失敗に終ったことを知らされた。 ・斉彬にとって、それは、決してそのまま聞き流してすむことではない。開国を前にして日本の思想統一と、政治権力の結集は絶対かくべからざる必要準備なのだ。 ・各個各藩が、バラバラのままで開国していったら、日本全国に無数の租借地やら植民地やらが生れてゆく。 ・武力の劣勢から開国は止むないと結論された以上、日本の総力を結集できる政治体制の確立は、理論を超えた必要事なのだ。 ・現今の言葉で云えば、列強の強引な圧力を前にして、政党政派を超越した非常時内閣の成立を期してゆこうというのだ。 ―― 完 ―― |