| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2020年04月17日 金曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 |
著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き |
31 |
13.09 |
徳川慶喜〔3〕 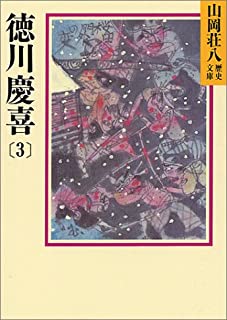 |
山岡荘八 |
講談社文庫 |
◎ |
真光る霜 ・「問題は幕政の改革でごわす。こうしておいて将軍家は一橋卿、大老は越前候、幕府の要路は外様譜代の垣根を払った人材第一と決めてゆきます。それではじめて叡慮にもかない、水戸の大義も立つ道理かと」 ・叡慮の第一は、日本の総力の結集にあるはず。それこそが故主斉彬や水戸の老公の悲願ではなかったのかという、西郷の推論であった。 憎悪の戦場 ・当時の人々はまだ政治と軍事の区別をよく知らないところがあった。戦はいかなる場合にも奇道なのだ。機先を制す必要もあれば、殊さらに敵意を煽って、士気を鼓舞する必要もある。時には奇襲も、 ・しかし政治は決して「奇道――」であってはならない。政治に戦争同様の勝敗感を持ち込むのは一種の冒瀆であり、自殺行為にすぎない。勝つか敗れるかの二途しかない成功率五十パーセントの冒険に、民衆の生活すべてを賭けることなど許していいはずがないからだ。 ・したがって「政戦」という言葉は、現代の労使間の「闘争」という言葉とおなじく、言葉としての体をなさぬ不遜きわまる無智の造語といってよい。 ・殊にわが国では、政治をはっきりと、「まつりごと」と呼んでいる。 ・その根本的な慎しみを忘れてゆくと、それはそのまま ・男一匹、国事に生命を捧げるからは、妻子は持たぬ、というのが常識だった。 ・ところが水戸の志士は、それでは祖先にすまぬゆえ、なるべく藩の騒動に巻き込まれないようにし、自分が死んでも助かるような子ども作りをしておくという・・・・・・ 啓蟄 ・何よりも梅を愛し偕楽園を梅で埋めた父の斉昭だった。士分以上の者は、必ず前栽に三株以上の梅を植え、それを漬けて軍用に備えよと、梅を通じて梅里先生(光圀)の志を行じようとして来た父であった。 ・「天はの、人間一人一人の生死などには冷たいものよ」 ・法華経の中には、未熟な人間と達人の間の段階を明瞭に区別していた。 ・人間として可もなく不可もない平均線上の者を大衆もしくは凡夫とすればそれより少し天道を悟ったもの、つまり釈尊の考えに近づいて、慈悲の布施を行じつつある者は羅漢であり、さらに慈悲行を楽しんで、楽しいままに生きている者を菩薩と云った。 ・代りに平均線上にあって自我を負う者は修羅に堕すると書かれている。修羅は、人間が弱点として持って生れている自我の赴くままに考え、赴くままに行動して、行く先々で修羅場を現出する。 ・(わが身は果して、羅漢であろうか?) 修羅の設問は、つねに自分の利益のために輪廻するゆえ、人もわが身も絶対幸福にはなし得ない。 ・そうした人々が集まって、政治権力をふり回すと、そこに描き出される「修羅場――」はやがて「地獄――」の相をおびてくる。 ・菩薩行は成し得なくも、われを忘れてすることが、天道にかのうた庶民への善行になるのでなければ、世は平静に治まるはずはないのだ。 ・同じ人間の中の未熟な者と達人の間に、こうしたきびしい段階が厳存し、その価値を無視した登用の錯雑が、政治を混乱させ世を騒がしているのだ。 空の軌道 ・何しろ烈公(徳川斉昭)の側妾の数は多く、それだけま子供の数も多い。子供の数は男女合わせると五十人近くになっている。 くちなしの宮 ・烈公は、決して頑固一徹の攘夷論者などではなかった。嘉永年間、はじめて浦賀に黒船のやって来る前から、今日の国難を予想して、そのイギリス研究などは至れり尽くせりのもので、とうてい日本が鎖国のままですむものとはおもっていなかった。 ・烈公が恐れたのは、日本が列強の手で分断されて、植民地化されてゆくことであった。 蓮華品 ・人間の考え方には、全部間違いということもなければ、全部が正しいということもないものだ。正しい理論も時には行き過ぎがあり、間違いの中にも捨て難い至情もある。 ・「いま討幕を押しすすめると、支那で申す革命という乱世になっての、収拾できないことになる。攘夷どころか、列強を喜ばせ、列強に漁夫の利を占められる」 ・「まず開国して、彼の長を採り、わが短を捨てて実力を蓄える。公武合体の、ほんとうの目的はそこにあるはず……」 故国の道 ・慶喜曰く、 「開国と攘夷を対立させて考えるのはな、刀を帯しているゆえ、これを抜いて人を斬らねばならぬと、思い詰める類の生兵法じゃ。刀を帯すは隣人の危難を救わんため……と悟ったら、開国もまた攘夷の手段と気づくであろう」 ―― 完 ―― |