| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2020年04月22日 水曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 |
著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き |
36 |
13.10 |
徳川慶喜〔6〕 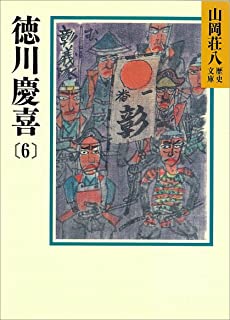 |
山岡荘八 |
講談社文庫 |
◎ |
歴史の表裏 ・昨日までの摂政以下、重臣すべてを追放して、万古不易の国是を定めたい……こんな形ですすめる小御所会議が、どうして万古不易たり得ようや? 先帝の、全大名に意見を徴せよという叡心とは ・それなればこそ、このおり決った体制はわずか八十年間で、昭和二十年には瓦解した。 ・徳川時代の二百六十余年と、初めて外戦を経験した明治二十七、八年戦役までを加えて、約三百年間外国と干戈を交えなかった自粛とは、雲泥の差であった。しかもどの戦にも反対なされた明治大帝という、不世出の聖天子をいただきながらである。 ・この点が日本人としてはもう一度じっくり考えてみなければならない国体上の大問題であると思う。 ・容堂の質問は、きわめて当然な良識であり、忠能の答えは、誰が聞いても公平無私とは思われない。にもかかわらず、この不公平を押し通した理論に昭和二十年(一九四五)までの日本人の多くは追随していった。 ・学者などにも、これでいかにも維新の大業は成ったかのごとく曲言し、一般もそれに巻き込まれて現に、明治百年を、日本の文明の夜明けであったとして盛大に祝ったのは昨日のことだ。 ・まさにヨーロッパ文明の日本における夜明けであったには違いない。しかし、日本においてはこれは大きな瑕瑾になった。 ・この装われた勤皇によって、幼い明治大帝は、九天から地上に引きおろされて武装させられることになった。 ・武装されて大元帥とならせられ、そのお名を異国出兵に利用されることになった事実は、何という痛ましい輔弼の錯誤であったと云うべきか…… ・容堂はまた言葉を続けた。 「――慶喜はすでに政権を返上し、将軍職を辞し、その忠誠はまことに のみならず、慶喜また英明の資を抱くことは天下周知の事実である。彼を召して大政に参与せしめるのは当然のことではないか。 もしそれを拒むとならば、それこそ公議を望ませられる王政復古の本旨にもとるものと思うがいか!?」 ・中山忠能はあわてて参与席の岩倉を見やった。透徹した容堂の反論に応えることができなかったのだ。 ・そこで越前の春嶽も口を開いた。 「――王政復古のはじめにあたり、人の罪を責めることを先とし、徳義を後にして出発するのは、誤りであろう。徳川氏二百六十余年の隆治を致した功は、今日の罪を償うてあまりあるもの、容堂の言を容れ、内府(慶喜)を召されて議をすすめられたい」 明治元年 ・勝海舟の論点 「もし官軍と抗戦すれば、徳川家の勢威を盛り返すことは可能であろう。しかしこれによって国内はハッキリと分裂し、とうてい短日月の間に収受はつかなくなり、勢い列強の援助を乞う者が現われ、これが端緒となって彼らの介入を誘い、日本は印度や支那の二の舞いを演ずるに至るであろう」 ・勝の所論によれば、日本人は日本の家来と、薩摩や長州といった藩の家来の二つにわかれた。 ・それを一つにまとめてゆくのでなければ、列強に比肩することも、対抗することもできない。 ・列強はすでに強烈な国家意識で団結し、どちらが多く植民地を分捕るかという、露骨な侵略主義の鎧をまとって競争しだしている。 ・二分したままの日本では、とうていこれに対抗できない。したがって戦うにしても和するにしても、その方策は、一つになるためのものでなければならない。 ・これは絶対唯一の要求なのだから、説き方しだいで相手にわからないはずはない……というのであった。 ・もしこの意見と、慶喜の信念の差を求めれば、慶喜がもっとも高く自然な民族的な精神面(国体)の美を、大義という名で追及しているのに対して、勝は、これを近代国家として「――生き残る」ための現実的な必要面から、ギリギリの条件を ・「――三種の神器は、四海万民撫育のため!」 この国ぶりを貫く大義のためには、目前の勝敗を離れて幕府の去就を正さなければならない。 ・正月二十一日、慶喜はついに「――恭順」を決定して、新政府撫育の方向へ断を下した。 ・この決断を、政治面での敗退などと解してはならない。 ・戦えば勝つ手段も方法も幾らもあった。しかし、そのつど慶喜はそれをしりぞけ、すすんで、新日本の育つ太陽の道をめざした。 龍虎の会見 ・まるきり無力になってしまっての嘆願では、相手の暴論暴挙を誘うだけだ。相当な実力のあるうちに、言辞を尽して話合うのが交渉なのだ。 ・駿府における龍虎の握手は、これこそ実に明治の入口に射しかけた一条の朝の光であった。 ・これで、勝の心も西郷に通じた。西郷を通じて徳川家の日本人としての忠節心も天皇に通じてゆく端緒になった。 ・勝は決して、幕軍の無力を想うて西郷に屈服したのでもなければ、嘆願したのでもない。 ・戦術面ではきちんとした対抗策を持って臨み、西郷もまたこれを認めて握手した。 ・その人間的な一面と胆略面との相互の認め合いが、不思議な明治の活力と政治力を産みだす根元になったと思う。 ・この場合の、西郷と山岡と勝の出あいは、決して人智による配剤ではなく、ここにこそ「――神風」とも呼ぶべき、微妙な大自然の調和力の配合があったと思う。 ・世間ではこれらの人々(西郷、勝、山岡)の功績を、江戸城明け渡しに限定するきらいがある。 ・しかし、実際にはそれに数倍する功績は、この時に知り合った彼らの奇縁によって、各藩の間の壁に大きな通風口をうがたれたということだ。 ・これによって大帝の許には天下の人材が小さな怨みを捨ててことごとく馳せ集まることになり、さらにこの三人の人格が、堅実真摯な明治の気風を育てあげる大切な基調になった。 ・いや、それよりもさらに大きな収穫は、いったんはマキャベリズム式の奪権闘争に堕しかけた政治の風潮が、どこかに勤皇という得意で清冽な太陽の光を射し残した点を挙げなければなるまい。 民族の良心 ・(――どんな場合にも、朝廷を利用して利己の心を動かしてはならない) その筋をきびしく通すことを忘れては、政治は無限に堕落の道を辿るという、尊皇絶対の哲学で貫かれている。 ・その意味では、大政奉還から王政復古の大号令、恭順、退隠、江戸城明け渡しと、慶喜の態度はむしろ超人的な信念で貫かれている。 ・これが慶喜でなかったら、ここまで来る道程で、日本の国内は収拾できない大混乱に陥ってしまっていたに違いない。 夜明け前 ・人間は人間自身が時流を作るものであることに気がつかない。 ・時流という大きな流れが別にあり、それに抗う者は滅び、それに従う者は栄えてゆくと錯覚する。その錯覚に気づいた時に、時を超え、時を貫く真理の存在が見えて来る。 ・五ヵ条の御誓文 一、広く会議を興し、万機公論に決すべし。 一、上下心を一にして、盛に経綸を行うべし。 一、官武一途、庶民に至るまで、おのおのその志を遂げ、人心をして倦まざらしめん事を要す。 一、旧来の陋習を破り、天地の皇道に基くべし。 一、智識を世界に求め、大いに皇基を振起すべし。 わが国未曾有の変革を為さんとし、朕 御名(御璽) ・ここで特に注意を要することは、この「――五ヵ条の御誓文」が、天皇から民衆に向って下賜されたものとしてではなく、天皇御みずからの、天地神明への誓いとして公表された点である。 ・これが今日まで天皇の政治に対する不変のご信念であらせられ、議会主義、世界主義の日本人すべての聖典とも云うべきものであることもまた言を 江戸から東京へ ・九月八日に改元があって、慶応四年(一八六六)は明治元年となり、ここに国家としての日本の封建政治は面目を一新してゆくことになった。 ・慶喜の恭順は、感情を超えた「――大義」の実践にあった。一君万民の中の、万民の為にある政治……それがわが国体であり、その国体を護持してゆくのが為政者の守るべき義(道理)の中の最大なるもの「――大義」なのだと信じて、これが生き方の基準になっている。 ・したがって「――新しい世代の邪魔になってはならない」という愛情は、いわば王者の愛でもあり、思いやりでもあり、きびしい武人の自戒でもあった。 ・とにかく慶喜は謹慎、隠居と決った日から、徳川家の内部のことにも天下のことにも、いっさい口出しはしなくなった。この事は、側近の人々が、眼を ・それにしても、日本というのは、何という不思議な国であろうか……? ・武力対武力で見てゆくと、とうてい、このまま治まりそうにもない、いわゆる革命戦争の様相が、慶喜の「――恭順」という一つの行為が中心となり、そこからすべてが解決してゆくのだ…… ・これを、新政府の功臣たちの手腕とする見方もあろう。が、手腕ならば、どう考えても慶喜の方がすぐれていた。 ・にもかかわらず慶喜は恭順の意を表し、それがやがて反政府側の人々をも納得させて、一糸みだれぬ天皇の世紀(明治時代)を作りあげていくのである…… ・ヨーロッパ人が「――不可解」とするところは、実にその一点であり、慶喜はそれを見抜いて行動していたといってよい。 ・日本中が、ほんとうに平定して、新しい秩序を取り戻したのは慶喜の弟の徳川昭武(水戸)に箱館の討伐を命じ、新帝が、勅して、明治二年(一八六九)再行幸して、宮殿を東京城に経営する旨布告した十二月七日と見てよいであろう。 ・これで、江戸は完全に東京になった。 鷹は市中に ・沈黙と政治不介入の功績を高く評価された人物は、慶喜のほかになく、慶喜こそは、まことに大切な明治人の亀鑑であった。 ・日本は危機一髪のところで、生命感を異にする異国流の「――革命」を避け得たのだ。 ・この日本の知恵は、世界のいずれの国にもなかったもので、家康の「――九天の上に皇居し給いて、万民のために存在する」と明記した公家法度の理想が、天下の副将軍である水戸頼房から、光圀、斉昭を経て、日本中の志士たちの勤皇運動に流れ、さらに慶喜の大政奉還から恭順へと受け継がれて明治の御代をなした。 ・「――敵のない者に敗れは無いのだよ」 ―― 完 ―― |