| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2017年12月20日 水曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 |
著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
9 |
13/03 |
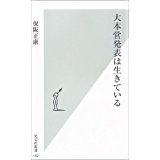 |
大本営発表は生きている |
保阪正康 |
光文社新書 |
◎ |
はじめに ・「大本営発表」 ― 実はこの語や音は、ある時代には権力そのものであり、国民ひとりひとりがこれに踊らされ、そのあげくにこの国が解体寸前にまで追いこまれたという史実を理解しておかなければならない。国民が情報のまったく途絶された空間に押しこまれて、そこに一方的に意図的な情報のみが流されたらどのようになるのか、という教訓も学ばなければならない。特定の情報のみを信じなければ罰せられるという歪んだ時代、この語やこの音にはその無気味さがひそんでいることもまた知っておかなければならない。 大本営発表をあえて定義づけるなら、「太平洋戦争の期間、陸軍・海軍の統帥機関である大本営が国民に向けて発表した戦況報告」といっていいであろう。太平洋戦争は国家総力戦といわれるが、国民をこの戦争に駆りたてるための煽動報告といういい方もできるかもしれない。 第一章 内容とその特徴 ・参謀次長に直結する戦争指導班の幕僚たちの部内日誌(『機密戦争日誌』)には、次のような一節が書かれている。 「戦争ノ終末ヲ如何ニ求ムヘキヤ是本戦争最大ノ難事」 ・戦争をどこで終わらせるかということこそが重要なかぎになっているというものであった。この自省や自戒そのものは重要な意味をもっていたが、しかし戦況が進むにつれ自省も自戒も大本営の幕僚は失っていったのである。 錯誤の連鎖 ・アメリカ側はひとつの戦闘が終わるとその戦果を確認するための部隊があって、自分たちの側の損害や犠牲者を客観的に調査し、それをなるべく国民に正直に伝えていることがわかる。国民が戦争に協力する前提として、事実を伝えることと、納税者である国民に戦費がどのように使われているか、その説明責任を果たすとの姿勢があるからだ。 ・日本では、軍事指導者たちが、国民に都合のいい情報を伝えて自らの意のままに操ろうとしただけでなく、天皇の大権を付与されている身でありながら、昭和天皇に正確な情報を伝えていない節があったことだ。加えて天皇の権威だけは利用しているのである。 主観主義の罠 ・大本営陸軍報道部員 平櫛孝は、台湾沖航空戦の誤報について語っている。 「日本の首脳部は、これまでたびたび国民をだまし続けてきたが、ここに至って、遂に最高権力者の天皇までだましたということになる。こういった欺瞞や糊塗はそのとき始まったものではなかった。これこそ、軍が完全に官僚主義に毒されきっていたことを示す好例である。軍は書類上の上の功名のみをきそい、現場の現実を直視する真の勇気をもたぬ者どもの集団であり、しかもそれを恥とも思わず、国民の上に君臨していたのである。破廉恥そのものといわれてもしかたがない」 ・台湾沖航空戦の誤報や虚報の原因は、主観的な願望を客観的事実にすりかえてしまうという心理構造である。いやあるいは思いこみを事実と信じて、自己陶酔に耽る真理だといってもいいであろう。 ・本来なら、軍事行動は政治の延長線上で捉えられなければならなかった。それが二十世紀の戦争のルールである。しかし、日本の政治・軍事指導者はそういうルールにまったく関心を示さない。ひたすら軍事のみが戦争の全てと思っていたのである。だから戦場の至るところで敗北が重なっていくにつれ、軍事行動そのものを自己の思いや願望で見つめつづけた。そのあげくに主観主義の罠に落ち込んでしまったというべきであった。 ・もともと大本営陸海軍部の作戦参謀は、情報を軽視して作戦を立案していた。たてえば、大本営陸軍部には第二部(情報部)があつたが、そこで情報参謀が集めたり分析した情報も、作戦の立案にはほとんどといっていいほど生かされなかった。作戦参謀にとって、そういう情報に動かされることはすなわち信念のない行為と見なされていたのである。 情報、戦略軽視の体質 ・情報について無頓着だからこそ、大本営発表という名称で国民に伝える戦果は、「戦意昂揚」と「継戦意識の持続」という視点でのみ取捨選択していたことにもなる。自らが情報を軽視するのだから、国民に正確な情報を与えようなどという発想はなかったのである。正確な情報を与えると、国民の戦意は低下し、厭戦気分が蔓延するとの不安にとりつかれていたのだろう。それは国民をまったく信用していないという意味になる。 ・虚構の大本営発表が、実は十万、二十万という単位で日本軍の将兵を死に至らしめたという現実、それは大本営発表そのものの罪悪であるといってもいい。 第二章 組織とその責任 自己陶酔から自己崩壊へ ・大本営の指導者は戦況が悪化していくにつれて、戦争を軍事の側から切りはなして、自己陶酔に堕した美学そのものの枠内で捉えていった。 客観的事実から眼をそらし、主観的判断のみで軍事指導を行った結果(だからこそ三年九カ月も太平洋戦争を続けていたわけだが)、ある病理現象をかかえこんでしまったというのが私の見解である。この病理現象は "妄想" の 第三章 思想とその総括 チャーチルは日本語をどう捉えたか ・イギリスの首相チャーチルが、その著『第二次大戦回顧録』で明かしている一節。 「日本軍の計画は、非常に厳格だったが、計画が予定どおりに進行しないと、目的を捨ててしまうことが多かった」 「アメリカの情報の取りかたは非常に発達していて、敵が最も厳重に守る秘密を、はるか前に見破ることに成功していた」 「戦争は意志と意志の戦い」 ・仮にAとBがいて、ふたりは殴り合いの喧嘩をしていると仮定してみることにしよう。 Aは圧倒的に腕力があり、知恵もある。Bは腕力こそそれほどでもないが、ひたすら精神力だけがある。当然、AがBを殴りとばし押さえつける。Bが「まいった」と一言いえば、Aは殴るのをやめて喧嘩は終わる。ところがBは決していわない。いってしまえば負けたことになるからだ。そのため喧嘩は果てしなく続く。Bは自らの生命の危機にまで及んでも「まいった」とはいわない。AはBが死ぬまで殴ることになるだろう。 その結果、Bは客観的には「死ぬまで殴られた」ということになるが、Bは主観的には決して負けてはいない。「まいった」とはいわなかったからだ。だが、Bはすでにこの世には存在しない。 日本はつまりBだったのである。Bは愚かである。Bは思考力を持たない。理性も知性もない。あるのは、まさに自己陶酔している哀れな姿である。この姿にまで落ちていくプロセスを担った指導者層の軍人や官僚、その提灯役を買い、装飾役を担った言論人の責任は重い。 終章 大本営発表の最期 マスコミ、そして国民が問われるべき責任 ・高見順の『敗戦日記』の昭和二十年八月十九日には、 「新聞は、今までの新聞の態度に対して、国民にいささかも謝罪するところがない。詫びる一片の記事も掲げない。手のひらを反すような記事をのせながら、態度は依然として訓戒的である。等しく、布告的である。政府の御用をつとめている」 と強い筆調で批判している。 ―― 完 ―― |