| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2020年05月29日 金曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 (下線を引いている本は「抜き書き」にリンクしています) |
著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜 き 書 き |
15 |
14.06 |
フォーラム 堺学 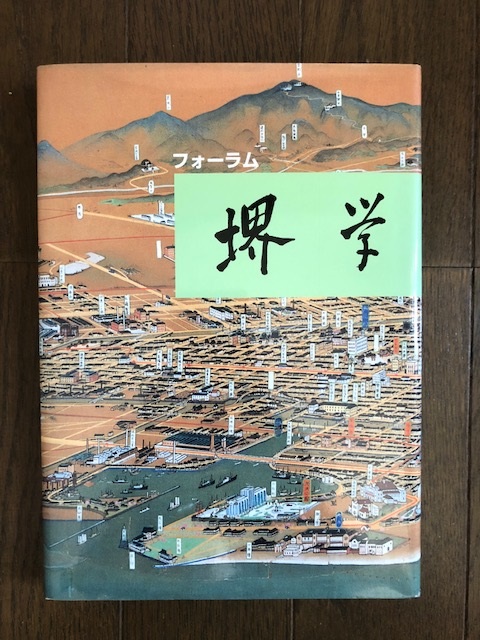 |
堺都市政策研究所 |
〇 |
第一回 仁徳天皇陵はいかにつくられたか (株)大林組広報室次長 林 章 情報発信拠点「仁徳天皇陵」 ・仁徳天皇が、自分が日本を一国に統一したということをどうやって知らせるか。 ・恒常的に「日本という名のもとに私、仁徳天皇が統一したのだ」ということをどうやって知らせるのか。すなわち、税金の一つとして、村の人口に合わせて労働力を出させます。 ・文明の初期になぜピラミッドがつくられたのか。あらゆる巨大構造物は、それぞれの文明の初期において作られているという傾向が著しいのです。 ・我が日本でも例外ではないのです。同じシステムが働いているわけです。 ・今日、戦争が終わったということは、昨日まで戦争をしていた人間が余ってしまうわけです。田んぼで働くべき人間を止めさせて、御陵の労働に従事させるほど無駄はしないわけです。田んぼで働かせた方が効率がいいのならば、こんな墓を作るより稲を植えたり、畑を作らせる方をとっているはずです。 ・昨日まで戦争をしていた。しかし、平和というのは突然にやってきます。すると、人間がいっぱい余ります。 ・さらに戦争をやっていたという事はそれだけ余剰経済力があるわけです。生産物が余っているから戦争ができるわけです。生産に追われていたら、そちらが先で戦争はできません。自分たちの食べ物を探す、生産するのに精一杯です。 ・すなわち、時代が進むに従って米の生産量が増えてきます。その余剰を持って戦争が始まるわけです。 ・経済力が余る中で、今日急に平和になったら男は困るわけです。もう戦争をする必要がないのだから。 ・したがって労働力を集中する政策が必要になります。いわゆるニューディール政策のようなものです。 ・ニューディール方式というものを仁徳天皇が知っていたとは思えませんが、全地球的にかつてそういう傾向があったということは、なんらかのことを知っていた、ないしは当時の人間でも優秀な方はそこに帰結したということができるかと思います。 第二回 お茶の来た道 (株)つぼ市製茶本舗代表取締役社長 谷本陽蔵 栄西禅師のお茶 ・日本に来たお茶は主として栄西の伝えたお茶なのです。 庶民のお茶としての茶道の歴史 ・栄西から約三〇〇年余り後ですが、堺の存在の意義があるわけでして、千利休およびその先生の竹野紹鴎は堺と非常につながりがあります。 ・また一五世紀前後には、「茶の湯」で賭け事をしたのです。その代表的な人は「ばさら大名」と呼ばれた佐々木道誉という方なのです。 ・奈良の称名寺の住職をされていました村田珠光さんが、佐々木道誉らの室町の派手なお茶を「これではいかん」ということで「侘び茶」、草庵の茶として初めて取り上げたのです。今日の茶道の始祖ではないかと言われる方です。 竹野紹鴎 ・紹鴎さんは奈良生まれですが、ほとんど堺で育っています。そしてこの紹鴎さんはどこにお住まいだったかというと、宿院の南東寄りの割と近いところで、現在は屋敷跡の碑があります。 ・紹鴎さんがお住まいの所は昔、あの付近を舳松といったのです。その舳松の中にある氏神さんを合祀して大寺・開口神社ができたので、現在でも大寺さんの中に舳松神社というのがあるわけです。 第三回 博覧会と大浜 京都精華大学助教授 橋爪紳也 ・第五回内国勧業博あたりから、それまで真面目にやっていた博覧会に急に遊びの要素がどんどん増えてきました。もちろんその前の博覧会にも遊びの要素はありました。 ・たとえば、京都で行われた場合ですと、アトラクションで芸者衆の踊りが始まりました。これが「都をどり」で、今に伝わっています。 ・あるいは、平安時代から幕末までのいろんな装束を着た人がパレードをする「時代まつり」というのがありますが、あれも博覧会の余興で始まった催し物です。しかし、遊びの要素が増えたのは、大阪博からです。 ―― 完 ―― |