| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2020年03月23日 月曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書籍名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き |
49 |
14.11 |
高杉晋作 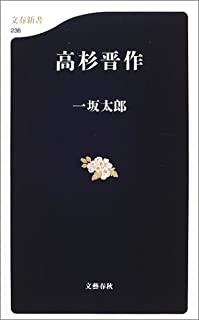 |
一坂太郎 |
文春新書 |
◎ |
第一章 晋作の出自 晋作誕生 ・藩主の側近中の側近である奥番頭は、八組士のうち、七百五十石以下の者の中から抜擢される。 ・その基準は、あくまでも本人の能力だ。登用の時点では家禄が五十石であろうが、七百石であろうが関係ない。 ・たとえば幕末の革新派官僚として知られた周布政之助の家禄は六十八石に過ぎない。 ・六十八石の家に生まれても、本人の能力次第で抜擢され、藩政の舵取を任される。 第二章 松陰との出会い 負けず嫌いな晋作 ・桂小五郎が、高杉晋作が他人の言を容れない「頑質」だから、一言注意して欲しいと吉田松陰に頼んだことがある。 ・だが松陰は、晋作の頑質は良く解釈すれば、妥協を許さないという、ひとつの個性であると見ていた。 ・みだりに矯正しては、ひとかどの人物にならないと考えていたのだ。 ・それに松陰が観るところ、晋作はたとえ他人の言を容れなくても、決してその言を棄てることはない。 ・十年後、自分が何か行う時は、必ず晋作に相談するだろうとまで、松陰は言った。 ・これを聞いた桂小五郎は、納得したという。 吉田松陰と松下村塾 ・松陰は、門下生たちに「志」を立てること、学問を行動に移すことを繰り返し説いた。 ・驚くべきは、全国から優秀な若者たちを集めて指導したならともかく、門下生たちは皆、近隣に住んでいた若者に過ぎないという点であろう。「人材」は探し回るものではなく、育てるものだということを、松陰と松下村塾の歴史は如実に教えてくれる。 江戸へ ・安政五年一月、藩より久坂玄瑞に三年間の江戸遊学の許可が下りた。そして玄瑞は一月十九日、萩を発ち遊学の途につく。 ・これに前後して吉田栄太郎・松浦亀太郎など他の塾生たちも次々と萩を出、上方や江戸で政治運動に身を投じていった。 ・彼らは塾から動けない松陰の手足となり、各地の情報を集め、書き送る。松陰はこうした情報収集を「 ・松下村塾には、各地から送られて来た情報を集めた帳面も置かれていたという。 ・新聞もテレビ・ラジオも無い時代、松下村塾は萩の若者たちにとって情報ステーションの役割を担っていたのだ。 暴走する師 ・松陰は攘夷論者ではあるが、鎖国論者ではない。開国、貿易によって日本が富国強兵して諸外国を制することは、大いに賛成であった。 ・しかし幕府のような弱腰の外交では、いずれ日本は欧米列強の属国になると、強い危機感を抱く。 ・朝廷を政治の中心に押し出し、優秀な人材を登用して新体制を築いて日本を立て直し、欧米列強に対抗するというのが、松陰が唱える「尊皇攘夷」だ。 松陰処刑 ・晋作に影響を与えたと思われる松陰書簡がある。そこには、晋作がかつて発した、「丈夫(男子)、死すべきところ如何」という問いに対する回答が記されていた。松陰は昨年冬以来、答えを探し続け、その結果、「死の一字、大いに発明あり」という。 「死は好むべきにもあらず、また悪むべきにもあらず……世に身、生きて心死す者あり。身、亡びて魂存する者あり。心、死すれば生くるも益なきなり。魂、存すれば亡ぶも損なきなり……死して不朽の見込みがあらば、いつでも死ぬべし。生きて大業の見込みアラバ、いつまでも生くべし。僕の所見にては生死は度外におきて、ただ、言うべきを言うのみ」 第三章 マサとの結婚 象山・小楠との出会い ・政治の目的は民を富ませることにある、そのためには君主以下為政者たちは無限の努力をする必要がある、もし出来ねば藩主であっても辞職せねばならないというのが、横井の説だ。 ・これは、為政者である武士を富ませるために民を隷属させていた、当時の封建制度を否定しかねない考えだった。 第四章 晋作、海外へ アメリカ人と話す ・幕末当時の知識人たちは欧米列強はまずキリスト教を広めることで民心を奪い、やがて国をも奪ってしまうと恐れていた。 ・晋作もキリスト教について神経質になっていた様子がうかがえる。自分は「魔の手」には乗らぬと、宣教師がそれらしい話を始めるや早々に退散した。 上海到着 ・アヘン戦争後、腐敗する清朝政府の打倒を掲げ、洪秀全を首謀者とする「太平天国の乱」が起こったのは、一八五一年から六四年にかけてである。 ・すでに力のない清朝は、英仏の軍隊に協力を要請して太平天国軍を鎮圧していた。清朝は列強に、すすんで内政干渉の糸口を提供したようなものだ。 蒸気船購入の契約 ・晋作は上海が欧米列強の支配下に置かれてしまった原因は「空しく歳月を送り、断然太平の心を改め、軍艦・大砲を制造し、敵を敵地に防ぐ対策が無かったためだ」と見ていた。さらに、それは単なる上海だけの問題ではなく「我が日本もすでに ・理解されないのは、時代の一歩先を歩く人間の宿命のようなものだ。 第五章 内憂外患 晋作登場 ・周布政之助は、「攘夷」は「攘夷」のためではなく、「開国」のためのものだ、というのが持論だった。 ・彼の考える攘夷は、不平等条約を押し付けた列強に抵抗の意を示すための、政治的な手段に過ぎない。 ・長州藩は次に必ず到来する開国の時代を見据え、長期ビジョンをもって密かに人材育成を進めていたのである。 ―― 完 ―― |