| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2020年03月02日 月曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 |
著 者 | 出 版 社 | 評価 | 一 言 コ メ ン ト |
52 |
14.12 |
仏教ってなんですか 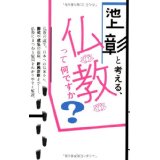 |
池上 彰 |
飛鳥新社 |
◎ |
第一章 仏教って何ですか? 煩悩があるかぎり苦しむ「一切皆苦」という考え方 ・「四苦八苦」とは ◉ ◉老苦 ……老いにともなう苦 ◉病苦 ……病にともなう苦 ◉死苦 ……死にともなう苦 ◉ ◉ ◉ ◉ ・「煩悩」 仏教では、すべての「苦」の原因は欲や執着、怒り、ねたみなどにあると考える。こういった感情すべてを「煩悩」と呼ぶ。 もっと多くの人を救いたい! 大乗仏教の誕生 ・大乗仏教(※)がもっとも大切にするのは利他です。利他とは、自分のことはさておいて、他の人が、あるいは他の生き物が幸せになれるように行動する姿勢です。 (※)大乗仏教 … 利他の行ないによってすべての人を救うと説く。お釈迦様の教えを広く大衆に広めることを目指す。 ・この利他という行ないを積み重ねることで、人は悟りに徐々に近付けると考えます。 ・自分はさておき他人の幸せのために思いやりを発揮し、利他の行ないをしている人を菩薩と呼びます。 ブッダの教えを求めてインドに渡った三蔵法師 ・玄奘がお経を求めて命がけでインドに向かった。この事実に、他の宗教にはない仏教の一面が表われています。つまり、ブッダの教えは向こうからはやってこない。こちらから求めるものだということです。 ・キリスト教には宣教師がいます。私たちは使命や任務の意味でミッションという言葉を使いますが、もともとは伝道を意味しています。敬虔なキリスト教徒にとっては、神の言葉を世界中に送り届けることは大切な使命なのです。 ・一神教ではない仏教には、多彩な価値観を認める懐の広さが備わっています。この仏教のもつ大らかさこそ、八百万の神とともに生きてきた日本人にとって、仏教が親しみやすい理由のひとつではないでしょうか? 日本人はどのように仏教を受け入れたのか? ・日本人が受け入れた仏教は、中国という強力なフィルターをいったん通して、招き入れられたものなのです。 ・当時の日本の朝廷では、物部氏と蘇我氏が二大勢力として競っていました。この対立がそのまま仏教をめぐる対立となりました。 ・蘇我氏は仏教を積極的に受けいれたのに対し、物部氏は外来の仏教を崇拝することに反対しました。疫病が流行ったときには、日本古来の国神の怒りをかったからだと仏教崇拝を非難しました。 ・結局、六世紀後半には、仏教に反対した物部氏が滅び、蘇我氏が実権を握りました。 国家の基盤を作るために仏教を導入した聖徳太子 ・仏教は日本に根付いていきましたが、古来からの日本の神々への信仰(神道)も排除されたわけではありません。 ・神々は仏法を守るという役割を与えられ、仏教と神道は共存の道を歩みました。神道の神様たちは、仏や菩薩の化身(権現)として別の姿で現れて、私たちを救ってくれるという考え方です。平安時代にはこうした考え方が定着しました。 戦乱・大地震の世を救った「南無阿弥陀仏」の教え ・最澄が天台宗を開いた当時、戒律を授ける国家公認の戒壇院は奈良東大寺など日本に三カ所しかなく、仏教の僧侶はいわば国家資格でした。 ・最澄はこうした奈良時代以来の体制に改革を唱え続け、死後七日目にして、比叡山に公認の戒壇院が設けられることになりました。 ・奈良仏教とは独立した組織で、僧侶を養成することができるようになったのです。 ・平安時代から鎌倉時代にかけて、比叡山は多くの名僧を輩出しました。浄土宗の開祖・法然、浄土真宗の開祖・親鸞、臨済宗の開祖・栄西、曹洞宗の開祖・道元、日蓮宗の開祖・日蓮などは、いずれも比叡山に学び、それぞれの独自の仏教のスタイルを見出して、比叡山を飛び出して活躍しました。 ・現在の日本仏教の主な宗派は、この鎌倉仏教に端を発します。 ・法然は浄土宗を開きました。その教えは、「南無阿弥陀仏」と念仏を称えるだけで誰もが極楽浄土へ行けるというものです。南無はサンスクリット語の「ナモー」の音を写したもの「心から信じます」という意味です。つまり、「南無阿弥陀仏」は「阿弥陀仏様を心から信じています」「阿弥陀様にすべてをお任せします」という、阿弥陀様へのラブコールですね。 ・親鸞は法然の弟子として教えを発展させて浄土真宗を開きました。よい行いをせよとか、お経を勉強しろとも言いません。そのままでいい。ただ阿弥陀如来を信じるだけでいい。それだけで極楽浄土に行けるのだと説きました。 ・浄土宗と浄土真宗はどちらも、念仏を称えることで極楽浄土へ行けるという中国から伝わった浄土信仰をもとにしています。極楽浄土とは阿弥陀如来が住む世界。この世の一切の苦しみから解放される世界です。厳しい修行を経て悟りを開くという既存の仏教の教えとは異なったものです。 それぞれの宗派によって違うこと、同じこと ・ブッダの教えを振り返ってみると、「死んでからどうなるのか」ということは、いっさい説いていないことがわかります。ブッダは死後の世界をあえて語りませんでした。死後の世界があるともないとも言っていません。あくまで生きている間に修業をして、悟りを開くことが目的ですから、「いかに生きるか」が仏教の教えの根幹だったのです。 ・仏教がもっぱら「死」担当となったのは、日本独自の仏教の発展の結果です。 輪廻転生がベースの仏教がどこでお葬式と出合ったのか? ・仏教はどこでお葬式とであったのか? それは中国だとされています。 ・中国には仏教が伝わるはるか以前から儒教がありました。 ・儒教に由来する先祖供養に、仏教の僧侶が関わるようになったのです。 ・たとえば、仏壇に供える位牌も、もともとは儒教の習慣に由来します。 ・今でも奈良の東大寺の僧侶は、葬儀を行ないませんし、墓地もありません。 ・東大寺の僧侶が亡くなると、別の寺の僧侶が葬儀を行ない、別の寺の墓地で供養します。 ・奈良仏教の源流を伝える由緒あるお寺だけあって、葬儀が僧侶の仕事になる以前の姿を貫いているのです。 お葬式を望む人々の願いに応えた鎌倉仏教 ・日本仏教の歴史の中で、鎌倉仏教が革新的だったのは、それまで国家や貴族のものだった仏教を、庶民のものにしたことです。 ・死者を浄土へ送り出す葬儀を進んで引き受けるようになったのも、救いを求める庶民の気持ちに応えようという仏教側からのアプローチの一環でした。 「葬式仏教」と呼ばれる理由 ・檀家制度は、キリスト教徒ではないことを証明するための仕組みで、日本特有のものです。どの家庭もお寺に属し、仏教徒であるという社会にすれば、少なくとも表立ってはキリスト教徒は存在できなくなります。檀家制度によって、家とお寺の関係が固定されました。この関係は代々続き、途中でほかのお寺に鞍替えすることは困難です。 僧侶の妻帯・世襲は日本だけ ・仏教派タブーの少ない宗教です。 ・浄土真宗の開祖・親鸞は「南無阿弥陀仏」の念仏を広めたのに加えて、僧侶の妻帯を認めたという点で、日本の仏教を大きく変えました。 「四十九日」の意味を知っていますか? ・人は亡くなると七日目には、三途の川に到達し、その後七日ごとに裁判を受けるとされています。だから七日ごとに法事を営み、よい裁きが得られるように供養するのです。 ・ちなみに、嘘つきの舌を抜くとされる閻魔大王は、五回目の裁判を担当する裁判官です。 ・七回目の四十九日は最後の裁判です。浄土に行けるのか、あるいは次にどんな肉体を得るのか、この日の裁判で決まります。ですから四十九日の法要は盛大に執り行い、傍聴席からお経を読んで声援を送るのです。 今、人を救う力を持つ仏教に出会うには ・もともとチベット仏教は、中国仏教のフィルターを経ていないこともあって、インド仏教の源流に近いといわれています。チベット仏教から仏教を学ぶというのは、アプローチとしては間違っていないでしょう。 第二章 仏教発祥の地インドへ。 心に満足感があれば死は安らかなものになる ・死に直面したとき、私たち自身の心の中に満足感があれば、他の生きとし生けるものに対するやさしさと思いやりがあれば、あるいは、他の人たちの役に立ちたいという利他の心があれば、私たちの死は確実に安らかなものとなります。 仏教の教えを個人のみではなく、社会全体に広げていけるのか? ・できるだけ人の役に立てる存在になろうと考えてみましょう。仮に人の役に立つことができないとしても、少なくとも害を与えることだけは決してしないと心に誓い、非暴力の姿勢を貫きましょう。そうした姿勢が自身の心に平和をもたらし、ひいては世界平和をもたらす唯一の道である。 Part2 ダライ・ラマ14世との対談 被災地の様子を見て悲しい気持に 法王 ・普段から物質的な発展だけを追い求め、外面的な幸せを得ることだけを考えていたとしたら、内面的なことをあまり考えずに過ごしていたとしたら、このような惨事が起きたとき、すべての望みを失ってしまいます。 ・しかし、日頃からどのようなものの考え方をするべきかについて考え、心を訓練していれば、逆境に立たされた場合でも、心の中では希望や勇気を失わずにいることができるのです。「とても悲しいけれど、起きてしまったことは仕方のないことなのだ。まだ大丈夫だ」と考えることもできるのです。 責任感、協調性、共同体の精神を発揮した日本人 ・日本は自由な国であり、まだできることはたくさんあるのです。不満があるのなら、自分たちで政府を動かしなさい。 原発、エネルギー問題にどう立ち向かったらよいか? 法王 ・経済発展のためにはエネルギーや工場が必要だと思います。日本だけの利益のためではなく、全世界において日本の製品は非常に役に立っているからです。 ・すべての原子力発電所を撤去していくことを考えるだけではなく、もっと革新的で新しいやり方を見出していくことが必要ではないかと思うのです。 ・私達人間は、持っているもので満足するという実践をしなければならないと思います。 ・日本の科学技術の専門家たちは、十分な知識と経験があるのですから、他の開発途上国に行ってもっと貢献するべきだと思います。そこで、日本人はもっと英語を勉強するべきだと私はいつも言っています。 ・特に、日本の若者たちは、英語の能力を身につければ、開発途上国で本当に素晴らしい貢献ができますし、それによってもっと自分に自信を持つことができるからです。 ・自分は人の役に立つ人間なのだと思うことで、自身が持てるようになりますし、満足感も得られます。これは人間にとってとても大切なことだと思います。 ・小さな島国の中で縮こまって暮らしていては、人生に意義を見出すことはできません。 焼け野原から再建した日本人は立ち直れる力を持っている 法王 ・日本人は第二次世界大戦で原爆を体験し、それによって悲惨な苦しみを味わったにもかかわらず、焼け野原の灰の中から必死に努力をして立派に国家を再建しました。その事実を私は知っています。 ・日本人は、本当にすばらしい能力のある人たちなのです。今抱えている経済危機も一時的なものに過ぎず、立て直すことのできる力を日本人は持っているのです。その力を発揮するためには、堅い決意と強い意志、そして自信を持たなければなりません。 ・私たちの戦いの本質は、真実の力と銃との戦いなのです。私たちチベット人には真実の力があり、もう一方(中国)は、銃による戦いを挑んでいます。 仏教が発展させた心理学を生きるための教養に役立てる 法王 ・最終的には、仏教の心理学に基づく知識を、学校の普通教育のシステムの中に取り入れていくことができればよいと考えています。宗教としてではなく、自分たちの心や感情について学ぶ心理学という学問として、アカデミックな教養の一科目として、世界的に取り入れることができればよいのではないでしょうか。 ・そうすれば、宗教を信じている人たちにも、そうでない人たちにも、仏教の心理学に基づく情報が役に立つからです。 始まりも終わりもない 死とは衣服を着がえるようなもの 法王 ・心についてもっと学び、知ることができれば、死への恐怖を軽減することができるでしょう。 ・死の恐怖を軽減するために何よりも大切なことは、私たちが生きているこの人生を意義深いものにするということです。 ・意義ある人生とは、他の人たちを助けるということであり、たとえそれができなくても、少なくとも他の人たちに害を与えるようなことはしないもという実践をすることです。そのように生きることができれば、あなたの人生はより意義のあるものとなります。 ・意義ある人生を過ごすことができれば、死に直面したとき、たとえ死への恐怖があったとしても、後悔すべきことはほとんどありません。後悔することがなければ、死を恐れる気持ちもずっと少なくなります。」 十年、二十年前と比べると中国は変化している ・「中道のアプローチ」とはチベット人の自治が実現できれば、中国からの独立は求めないというダライ・ラマ法王の妥協案です。しかし、中国はダライ・ラマは本当は独立を求めていると主張して対話を拒んだまま、チベット問題は一向に進展しません。 第三章 仏教で人は救われるのか? すべての物事には原因がある 実に科学的な態度の仏教 ・歴史的には、キリスト教圏で科学が発展したのは、世界を創造した神の偉大さを証明するためです。 ・しかし、発展の先に行き着いたのが、聖書と相容れない進化論であり、ホーキング博士の宇宙論でした。 ・宇宙や世界のことがわかればわかるほど、キリスト教にとって不都合が生じてしまうのです。 仏教の僧侶は心のはたらきに向き合い続けてきたプロ ・ダライ・ラマ法王は煩悩というネガティブな感情を抑えつけるのではなく、誰にでも本来備わっている愛や慈悲といったポジティブな感情を高めていくことで、克服できると教えてくださいました。 ・感情のコントロール法 腹が立ったら、相手の立場になって考え直してみる。悲しいときは、もっと大きな悲しみを抱えている人が大勢いることを思い出してみる。 ・愛や慈悲というと堅苦しいですが、やさしさと思いやりということです。自分の利益のためではなく、他人の幸せにつながるような言葉や行ないを普段から心がけることで、どんな局面でも、ポジティブな感情が先に生じるような癖がつけられるのです。 死者を弔うことに特化して教えがかすんでいる日本の仏教 ・ダライ・ラマ法王はこうおっしゃいました。 「意義ある人生を過ごすことができれば、死に直面したとき、たとえ死への恐怖があったとしても、後悔すべきことはほとんどありません。後悔することがなければ、死を恐れる気持ちもずっと少なくなります) ―― 完 ―― |