| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年05月02日 月曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
5 |
15.01 |
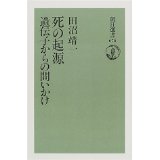 |
死の起源 遺伝子からの問いかけ |
田沼靖一 |
朝日選書 |
☆ |
はしがき ・健康な状態でも身体のなかでは、細胞はきちんとした死の過程に沿って整然と死んでゆく。しかも細胞はたえずいろいろな細胞シグナルを互いに交信し合うなかで、「死ぬべきか」「生きるべきか」と自分自身の運命を自ら判断して決めているのである。 ・細胞は、自分自身に内蔵されている「死の装置」を発動させて、死を完結している。たとえば、身体のなかで老化して不要になった細胞、ウイルスに感染して異常をきたした細胞、発癌性物質が入り込んで癌化するおそれのある細胞は、自分自身で自死装置のスイッチを入れて、積極的に死んでゆく。つまり、生命は細胞死によって守られているのである。そしてまた、個体は最終的に死ぬことができるように、保証されているのである。 ・「細胞に宿る死」は、生命の本体であるDNAのなかに、(塩基配列として)生まれつき書き込まれている。つまり、「死の遺伝子」なるものが存在するのである。 ・死は生の前提として、ただ私たちの内に存在する。 第1章 死の遺伝子からの問いかけ ・DNAの塩基配列のなかに、体を形づくり、生きていくための情報がすべて書き込まれている。しかし、それだけではない。死ぬためのプログラムも遺伝子として組み込まれていることが、最近の研究でわかってきた。 死の遺伝子 ・私たちの手足の指が形づくられるときも、はじめミットのような細胞の ・細胞の死がなければ、細胞は増殖して殖えるだけで、ただの塊にしかならない。生物特有の形は生まれてこないのである。 ・生命体が生まれてくるときに、細胞の死がなくてはならないものであることがわかる。死がなかったら、単なる細胞の集合で終わってしまう。細胞それ自体に死ぬ能力がそなわっていることによって、はじめて複雑な生命体が形づくられ、生命として成り立つのである。 ・細胞死は発生過程ばかりでなく、成体(大人の身体)のなかでも毎日起こっている。 ・「再生系細胞」 = 新しい細胞に置き換わることのできる細胞(皮膚の細胞、赤血球、肝臓の細胞など) ・「非再生系細胞」 = 生まれてから何十年もの間、同じ細胞が高度な機能を果している細胞(脳の神経細胞、心臓の心筋細胞など) ・置き換えのきかない非再生系細胞の死がある 往還としての死 ・「死の起源」を思索する道筋は、私たちの細胞のなかだけではなく、思想のなかにもある。「死によって生命は守られている」という逆説は、すでに『新約聖書』ノ「ヨハネによる福音書」のなかにもみられる。 ・死とは終わりではなく、新たな生の始まりであり、死生は往還の過程なのである。 ・生あるものはすべて死によって無の状態に戻ることになる。とくに、私たちのような有性生殖をする生物は、必ず死ぬ。そして「死/性による生の有限性」を通して、新たに遺伝情報(遺伝子)を未来の時間と空間へと伝えている。遺伝子の連続性は、死による不連続性によって保証されているのである。生命とは、「遺伝情報である遺伝子=DNAと、その表現である生命体とを往還する、回帰し得ない鎖として時空を伝わるシステム」と考えることもできる。 千年紀を生きる ・生あるものに死が普遍的に訪れるのは事実であり、死ぬまでのことは、科学の対象なのである。 ・現在、人間の築きあげた文明は、この自然を排除したり、思いのままに操作しようとしている。それはとりもなおさず、死を排除しようとしていることと同じである。自然を遠ざけることによって己を忘れてしまい、遠ざけた死の重圧がやわらぐことによって、生も空虚になってきている。人間は、意のままにならない自然から逃れられないように、死からも逃れられないことを深く認識する必要がある。 ・死がどのようにして現われ、死はどのように決まるのかを知ることによって、はじめて「生きるとは何か」を問うことができるようになるだろう。この内省によってのみ、善い精神の発動が期待されるのである。 第2章 生命の原理 死による生命原理 ・DNAの損傷や複製エラーによる変異が、とても修理機構だけでは修繕できないほど蓄積されてきた場合、そのDNAをきちんと除去することが、生命を維持していくために、必要不可欠になってくる。ここでの消去システムこそが、「死」なのである。それがないと、個体の維持どころか、そのDNAを共有する種の保持も不可能になってしまうからだ。 生命の特性 ・生命の特性として基本的に重要なことは二つある。その一つは、ある条件のもとで、秩序ある構造体を自律的に創り出す「自己組織能」である。もう一つは、自己を忠実に複製する能力をもち、世代をくり返すことのできる「自己増殖能」である。この二つが揃えば、「生命」が成立する。そして、生命の進化のなかでいつからか、さらに、自己を自ら消滅させることのできる「自己消去能」が加わってきた。つまり、生命に「死」が組み込まれたのである。 ・個々の神経細胞を取り出して調べてみても、思考、記憶、精神活動など脳の高次の機能を説明することは難しい。神経細胞が脳のなかで自律的に組織化を行なうことによって神経ネットワークが形成され、それによって、想像もできないほどの機能が現れてくるのだ。 ・有性生殖では、減数分裂の過程で遺伝子がシャッフルされて新たに配り直されるため、その良し悪しを選別する方策が必要となる。さもないと、個体の生存ばかりか種の保存も成り立たなくなってしまう。その確実な選別方法は何であろうか。それは、個体をつくりあげてゆけない受精卵や、種を成り立たせないような受精卵、また、細胞の癌化を引き起こしてしまうような変異がDNAに生じてしまった細胞などを、きちんと消去できる「死」であろう。こうした必要性が推進力となって、死は進化の過程で、細胞に遺伝子としてプログラムされてきたと考えられる。 ・細胞死という自己消去能が加わることによって、さまざまな環境の変化にもかかわらず、種としての固有な遺伝子(ゲノム)を存続することができるようになったと考えられる。 生命の階層性 ・個体という生命体は、それを構成している細胞の単なる総和といった単純なものではない。細胞社会によって、統一性をもった「自己」という新たな存在が創成されているのだ。 ・一つの個体でみられる個別性は、さまざまな遺伝子の発現パターンによって創出される。そのパターンは、個体が存在する社会という環境によって大きく影響を受ける。すなわち、ゲノムから引き出される遺伝情報のパターンは、まわりの環境により、時々刻々と変化しているのである。しかし、長い目でみれば、変わりゆく環境に対して新しいゲノムを用意しなければならなくなってくる。そのためには、個体のなかで変化してゆく個別性とは別の次元で、それをすべて消去する仕組みが必要となる。その必然性から、私たちの身体のなかには、自分自身のゲノムを確実に消去するために、死が遺伝子として細胞にプログラムされるようになったと考えられる。新たな生命体を介して遺伝子を存続させる死の遺伝子は、利他的な存在であるといえるだろう。 ・このように生命の階層性をみてくると、遺伝子から個体、その上位の種の社会、そして共生するすべての生物を包んで、死があることがみえてくる。そこにはまた、初めもなければ終わりもない生と死の環がある。これが自然の摂理なのである。 第4章 死はどう進化したのか 二倍体細胞への進化 ・生命は長い時間をかけて、この地球上に多種多様な生物を創り出してきた。その過程では、多様化した生物をもう一度組み合わせる高次の共生もあった。事実、私たちの身体のなかにも多くの腸内細菌が宿っている。アブラムシの身体のなかにはブフネラという細菌が共生して、互いに生命を支え合って生きている。こうした多様な共生による種の成立には、死による積極的な選択が不可欠であったと考えられる。 第5章 どのように死ぬのか ・「死」は二倍体細胞生物が、「性」と引き換えに獲得した「生」のストラテジー(戦略)である。二倍体細胞生物を構成している細胞には、自ら死ぬことができる機構がそなわっている。つまり、死は遺伝子として細胞に内蔵されているのである。これによって細胞は、刻々と変わる自分の内部の状態と身のまわりの状況を自ら判断して、自ら死を決定し、死の遺伝子を発動させて死を実行に移すことができるようになった。 細胞死の分類 ・細胞が死ぬというと、一般的には、何らかの損傷を受けた細胞が衰退して単に崩れていくことを思い浮かべるだろう。これは古くから ・ネクローシスでみられる細胞死は、 ・オタマジャクシがカエルになるときには尻尾がなくなる。イモムシが美しいチョウに変身するときには、イモムシ型の筋肉とそれを支配する神経細胞は ・このような、個体の発生過程で、身体や器官の形をつくりあげる(形態形成)際にみられる細胞死は、ある特定の時期に、特定の部域で決まった数の細胞に起こる現象である。この細胞死は、発生スケジュールのなかで秩序正しく進行することから、「プログラム細胞死」と名づけられている。 ・細胞死の分類 (1) 遺伝子に支配された細胞死 ・アポトーシス(自死) 再生系細胞・・・・・・・・統制 ・アポピオーシス(寿死) 非再生系細胞・・・・・・寿命 (2) 遺伝子に支配されない細胞死 ・ネクローシス(壊死) すべての細胞・・・・・・崩壊 アポトーシス ・細胞は細胞社会の一員として、たえず互いに、いろいろな情報を交換し合っている。そのなかには、生きてゆくための情報だけではなく、死ぬための情報もある。 ・ヒトの場合、細胞社会は六〇兆個の細胞からできあがっている。細胞の種類は二〇〇種類ほどあり、互いに連絡を取り合って、一つの生命体としてま統一性を保っている。つまり、「個」である細胞が「全」である個体を認識して、調和のとれた生理機能を果たすことによって、一つの生命体が成り立っているのである。 ・(悪くて生きているよりも死んだ方がましだ)という言葉があるが、細胞自身がそれをアポトーシスによって実行しているのである。この意味で、アポトーシスは細胞レベルでの修復機構といえるだろう。 ・このように異常をきたして有害となるような細胞を自死させることによって除去することで生体を守っている。つまり、アポトーシスは生体を防御する役割も果たしているのである。 細胞死の機構 ・アポトーシスの決定過程を制御する遺伝子が、最近つぎつぎに報告されている。興味深いことにその多くは、癌の発症に密接に関与しているがん関連遺伝子である。癌はアポトーシスの機構がどこかで抑制されて死ななくなった細胞の集団として捉えることができる。 細胞死と疾患 ・癌の発生と成長には、細胞が異常に増殖するだけではなく、アポトーシスの異常(抑制)が重要な役割を果していることがわかってきた。癌細胞は、なんらかの理由でアポトーシスが抑制されるため、細胞が死ににくくなっているところに、さらに増殖に関与する遺伝子の変異が起こって、異常に細胞が増殖できるようになることによって発生してくるのではないかと考えられている。 第6章 死はいかに決まるのか ・アポトーシスは個体のなかで不要になった細胞を取り除くための役割を果たすようになり、これによって、個体の生命活動が円滑に維持されるようになった。この細胞死は、血液細胞や肝細胞のような再生系の細胞に、主にみられる。 ・一方、成体の神経細胞や心筋細胞などのような非再生系の細胞にみられる自然発生的な細胞死が、アポビオーシスである。このような非再生系細胞には、ある時期がくるとアポビオーシスの発動によって自ら死滅する「分化寿命」がセットされている。これによって、個体は必ず死ねるようになっている。 細胞寿命と個体の死 ・細胞の集合体である一つの臓器が、そのなかにある細胞の死によって故障を起こしてしまっただけでも、個体には死がもたらされる。だがその一方で、個体は死んでもその時点ではまだ生きている細胞はたくさんある。つまり、個体の死は細胞からみれば “未完の死” ということになる。 このように細胞の死と個体の死との間には、埋め難いギャップがあり、とりわけ人間の場合はその幅が広い。それは心や意識といった人間を人間たらしめているものを考慮しなければならないからである。また、そういったものを司る身体の部位が死滅すれば、それを個体の死といえるのだろうか。脳死判定の難しさもここにある。ここではとくに、科学の面から死が遺伝子として決まるという基本事項に立って個体の死を捉え直すことが大切であろう。そして、それを前提として、一人ひとりの固有の人間としての根源的な存在を問わなければならない。 第7章 なぜ死ぬのか 二重の細胞死 ・遺伝子が、新しい遺伝子の組み合わせからなるゲノムとして このように、細胞および個体レベルで確実に古い遺伝子を無に帰することによって、新たの遺伝子として生を更新することが可能となったのである。また、当然ここには、有性生殖という新たな遺伝子の組み合わせを構築する「性」が、なくなてはならないものになってきたのである。 第8章 有限による無限 不死の不可能性 ・生命の連続を保証するために、個体にとっての不連続となる死が細胞に組み込まれることは、一見矛盾しているようにも思えるが、これが生命を時空を超えて遺し伝えるためにもっとも有効な手段なのである。変わりゆく環境のなかで、個体という表現体を通さなければ存続できない遺伝子にとって、遺伝子の組み換え(“性”)と消去(“死”)を伴う機構以上に良い方策は、これまでに考えられていない。 ・有性生殖とともに死がなくなてはならない主な理由は、新たにできた受精卵が不良であった場合、それを消去する必要があるからである。生命の誕生という大事件は、死によって成立すると言っても過言ではない。生の始まりに、死が必要なのである。そればかりか、受精卵が良好である場合も、新たな遺伝子の組み合わせをもった個体が存続し、さらに後世に子孫を残してゆくためには、古い(親)個体の遺伝子を消去する必要がある。 |