| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年02月02日 火曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
96 |
15.09 |
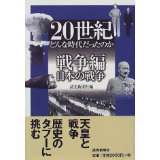 |
20世紀 どんな時代だったか 戦争編 日本の戦争 |
読売新聞社編 |
読売新聞社 |
◎ |
まえがき ・「日本の戦争」を振り返る時、われわれが第一に考えなければならないのは、何が日本を戦争に導いたのかという問いかけであり、その回答の一部は、確たる安全保障観の欠如に由来する無原則な利益の拡大と、リーダーを失い官僚化した組織の政治への介入に求められるであろう。そしてこれは、まさに現在の日本が直面している課題である。 第1章 日米対決 日米衝突 中国めぐり覇権争い ・戦争は、米国と日本の間でほぼ半世紀にわたって生成された問題が爆発したものだった。最も重大な対立点は、日米どちらが中国で主要な役割を果たすかだった。 軍縮会議「対米7割」海軍の執念 ・軍縮を巡る、加藤寛治中将主席随員と、加藤友三郎首席全権(大将)の衝突は、「国防は軍人の専有物にあらず」と、国力を判断して「対米不戦」の立場をとる友三郎と、「持たざる国は平時から強大な兵力が必要」とする寛治の戦争観の相違から生まれたものだった。 このギャップが、海軍内部に「条約派」と「艦隊派」の対立を生んでいく。 海軍と開戦 中堅将校強硬な主戦論 ・四〇年当時、日本は、中国大陸からの撤退か、南方進出かの選択を迫られていた。石川信吾(海軍省軍務局第二課長、終戦時海軍少将)は、中国大陸からの撤退は英米への屈従として断固反対の立場をとっていた。 この時の米内、近衛両内閣は、軍撤退も南方進出もせず国際情勢の変化を待つ姿勢だった。「現在からみれば、この方針が最善だったかもしれない。しかし、石川らには、これは主体性のない無為無策にしか見えなかった」と秦郁彦・日大教授は指摘する。 ・石油禁輸をきっかけに「座して死を待つより打って出るべし」との意見が強まる。これが「じり貧論」だ。 だが、海軍省首脳は、それでも開戦に関してはまだ消極的だった。 米国との国力の差を考えると、消耗戦、総力戦になれば、国力に劣る日本に勝ち目はないと冷静に判断していた。 ・回避派が主流だった海軍省にしても、最後は開戦に同意した。その要因の一つが、「省益」擁護だった。 開戦決定 軍の官僚化 迷走に拍車 ・開戦という国家の重要意思決定に至る道は、開戦か平和かをめぐる攻防を軸に、近衛首相ら政府、陸海軍、外務省などの各機関の思惑や利害が交錯し、迷走を続けた。 そもそも、こうした意思決定のあいまいさは、明治憲法そのものに内在し、現在にも通じる官僚的な縦割り組織の硬直性も反映していた。 ・陸軍も海軍も結局は官僚だった。陸軍士官学校、陸大と昇っていった学校秀才らがエリートとなるようなシステムができ上がり、新しい状況への即応力が欠如していたのではないか。 ・両論併記、玉虫色の字句修正、先送り――戦争をめぐる意思決定過程にみられたこうした特徴は、政治のリーダーシップの不在、官僚の独走など、現代日本の政策決定と相通じるものといえる。 第2章 アジアの戦争 勤勉と融合 南洋を開花 ・「冒険ダン吉」のモデルともなった南洋のトラック諸島では、島を変えたのは日本人の勤勉さだと言う。 スペイン、ドイツは、少数の白人が島民を使役した。しかし日本人は働いた。 裁判制度などが進んだのも日本時代だ。 満州事変 軍独走 国際協調を破壊 ・日本政府は軍が次々と作りだす既成事実を追認していった、 ・さらに、一連の軍事行動を国民が圧倒的に支持したことも軍に自信をつけさせた。 事変拡大とともに、「鬼畜に劣る徒輩を排撃」(読売新聞三一年十月五日)など、新聞は中国への 国民も、軍部が引きずったのではなくして、 第3章 帝国統治 戦争報道 強制と迎合で“宣伝役”に ・戦前から戦中にかけての新聞は、数々の規制により報道の自由を奪われていた。だが一方で、新聞社側から積極的に権力に迎合していったことも明らかになっている。 第4章 戦争の世紀を生きる 斎藤隆夫と反軍演説 ・四〇年二月二日、第七十五議会の再開二日目に、斎藤は立憲民政党を代表し、「支那事変(日中戦争)の処理方針に関する質問演説」を行なった。 「ただいたずらに聖戦の美名に隠れて、国民的犠牲を閑却し、 ・斎藤は一貫して、軍部の政治介入に警鐘を鳴らしてきた。二・二六事件(三六年)後の第六十九議会で行った「粛軍演説」では、軍部によるクーデーター計画である三月事件と十月事件(いずれも三一年)を ・斎藤は反戦主義者ではなかったが、国民の軍部に対する批判や疑問を代弁し、政治家としての責任を見事に果たした。ところが議会は国民の声を封殺し、軍部と手を結ぶことによって戦争指導体制に食い込んでいったのである。その点で、政党の戦争責任も小さくない。 日米開戦 あの時何があったのか ・元国連大使、加瀬俊一氏は、日本の外交目標として「道義国家日本の旗を高く掲げたい。平和への奉仕に不退転の決意を持ち、安易な対米従属心理から離れ、アジアに信頼されるリーダーとしての責務を果たすべきだ」と訴えている。 ・東郷茂徳外相は「ハル・ノートは交渉経過からして疑問の余地のない最後通牒であり、開戦条約の『最後通牒』規定より強いものであった」との認識の上に、「こうしたものが来た以上、日本は自衛のために立ち上がるのであり、自衛のためならば(国際法上、理論的には)無通告で攻撃をしてもよい」とすら考えていたようだ。 第5章 昭和天皇と戦争 「昭和天皇と戦争」京都座談会 ・猪瀬直樹 ずっと大きな流れでいえば日清戦争と日露戦争は日本の独立戦争だった。 つまり弱肉強食の世界で、食うか食われるか、つまり植民地になるか、独立するかという、そういう瀬戸際で選んだ。それは戦争がいい悪いの問題じゃなくて、独立戦争だからしょうがない。 日露戦争は、ロシアが、韓国から下りてきたら、もうやられちゃいますから、そういう生存の危機意識というものが、日本人の国民の根底にしみついています。どくりつせんそうとして戦わざるを得なかった。 ・梅原 猛 藤原不比等という人が日本の天皇制を作った。 日本の律令では、天皇の権力の及ぶところを全部、剥奪している。それは当時の天皇は知らなかったと思うけれども、ちゃんと要点を全部、剥奪して、そし太政官が、つまり太政官のの中心にいて藤原不比等が自分で一切の権力を握れるようにできたんです。 だから現在に近いんです。が、明治維新で別の天皇制を作ったわけです。 一応天皇親政の形で、しかも憲法を作って立憲君主制にした。これは二重三重に、妥協の産物です。だから矛盾が今の天皇制の中にもあったと思うんです。 明治の天皇制が、ちょっと日本の伝統からいえば変則なんです。 もともと日本の天皇は武官でも文官でもない。それが武官になった。それは天皇の権威の失墜です。 ・阿川弘之 「皇位継承」はともかく百二十五代続いてきているのです。これは世界でも珍しい存在で、大事にしたらいいと思います。天皇制という言葉が時々、出ているけど、これには僕は抵抗がある。大正十二年に共産党が作った用語で、要するに否定する含みを持たせてある。 ・猪瀬 東条が(戦争を)やらないような方向で、なんとなく総理大臣になって、非常に消極的になっているのにもかかわらず、議会で「東条、お前、日和ったか」なんて決議を出したりしちゃう。国民の間にそういう空気とか流れというのがあったんですね。メディアの責任は大きいでしょう。 戦争の負け方で、どこで撤退するのかということを決める意志の強さが、天皇個人だけでなく、その時の政治家や軍人たちも含めてなかった。教訓としてこの問題は残ります。 ・梅原 「独白録」には、もう一回、敵に打撃を与えて、それで終戦にしないと結局、無条件降伏せざるをえない。戦果を挙げてと、こういう思想が終戦を遅らせたと思う。 ・猪瀬 当時の国家の中枢にいた人たちがずるずると戦争の深みに入っていったことについては、最近の日本の経済状況と同じ。引き際の決断ができず、『中国で犠牲になった十万の日本兵を見捨てることは出来ない』と言いながら、結果は三百万人もの戦死者を出した。この負け方の不得手さを、日本人は戦後の経済戦争でも引きずっている。 |