| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
【最新更新日 : 2016年02月02日 火曜日 】
| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
| NO | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |
97 |
15.09 |
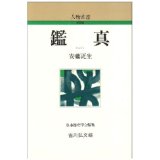 |
鑑真 |
安藤更生 |
吉川弘文館 |
◎ |
第一 在唐時代(一) ・鑑真が日本のために身命を ・揚州は日本人が都へ行くにも帰るにも必ず立ち寄る中継基地であった。だから揚州の人々は日本人に親しみを持ち、日本の事情も割合によく知られていた筈である。 ・鑑真は、およそ戒律の講座を開くこと、前後百三十回、寺を建てたり仏像を造ることは数えきれないほどで、袈裟を二千枚も作って山西省の五臺山に寄附したことがあるし、貴賤貧富平等の大集会を開き、貧民や病人の救済事業をおこすなど社会事業方面でも活躍した。一切経を写本すること三部、三万三千巻、 ・なぜ日本が鑑真を招聘したかという理由 七三〇年代において特に行われたというのには、その蔭に、特にそうしなければならなかった日本の政治的原因があったと見なければにならないし、事実その要因があったと認められる。 ①僧侶の堕落 ②律令政治の矛盾 庶民の窮乏化がひどくなり、ついに本籍の地を離れて他国に流亡したり、各所にある寺院に身を投じて頭髪を剃り、僧侶となる者が続出した。 当時、僧や尼は政府の 仏教を信じホトケの慈悲にすがろうというのではない。名を僧侶にかりて ③民衆の流亡 ・元興寺の華厳学者 第三 来日以後 一 第六回渡日の成功 ・天平勝宝二年(七五〇)、日本政府は十七年ぶりに、また遣唐使を派遣することになり、九月二十四日、光明皇太后の甥で孝謙天皇の従兄に当る藤原清河が大使となり、大伴古麻呂が副使となった。 ・翌年十一月にはさきの留学生で、在唐の経験豊かな吉備真備も副使に任ぜられた。このたびの遣唐使は、当時完成に近づいていた東大寺の ・玄宗皇帝の謁見は、七五三年正月元旦に拝賀の儀があり、この日、天子は蓬莱宮の含元殿に出御し、百官参朝し、海外万国の使臣もまた参列した。 ・拝賀の日、外交団の席次は東西の二班に分け、東班の第一席が新羅、次はサラセン、西班の第一席はチベット、次が日本になっているのを見て、大伴副使は位置に着くことを肯ぜず、色をなして接伴官にいった。 「昔から今にいたるまで、新羅は大日本国に朝貢している国である。然るにこれを東の第一席にして、我れは却ってその下に坐らせるとははなはだ不当である。席次を変更して貰いたい」と。 ・日本副使の頑として承知しない色を見て、新羅の使をチベットの下に就かせ、日本使を東班の第一席、サラセンの上に坐らせた。 ・鑑真は天宝元年(七四二)第一回の渡日計画以来、実に十二年、五度の挫折・大難を乗り越えて、第六度目になって、やっと日本の土を踏んだのである。 ・その間に三十六人の同志が ・終始一貫して変わらずに到着した者は、鑑真と、弟子の思託と、日本僧普照の三人だけだった。 ・和上らは、天平勝宝五年(七五三)一二月二六日、唐から同行した僧延慶の案内で大宰府に着いた。 ・翌天平勝宝六年(七五四)二月一日、和上らは難波駅の国師郷についた。 ・天平宝字三年八月一日をもって「 ・時の人は「唐律招堤」を略して「唐寺」と呼んだ。後に官立となって「唐招提寺」と名づけられた。 ・天平宝字三年(七五九)六月二日、ちょうど唐招提寺の創立準備が進められているころ、普照は平城京の京外の道路ばたに街路樹として果樹を植え、夏は行人をして樹陰に暑熱を避けさせ、飢えれば果実を摘んでこれを食べることが出来るようにしたいと上奏して採用されている。これが日本の街路樹の最も古い例である。 ・藤原・鎌倉を通じて明治に至るまで、日本の仏教彫刻といえば、ほとんど木彫に限られてしまう伝統は、実はその源を鑑真一派の木彫に発しているのである。 |